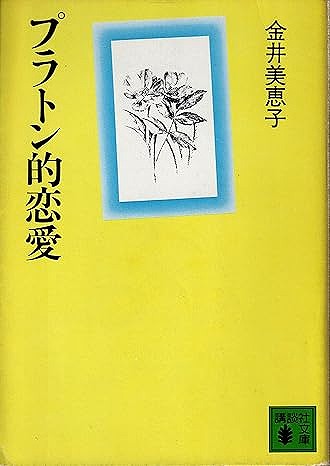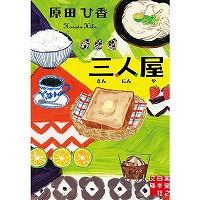Since 2008/ 5/23 . To the deceased wife
Since 2008/ 5/23 . To the deceased wife
�킯������܂��āu�njォ�����v�������������߂Ă����܂��B
�Ȃ̐��O�A�W����̊ӏ܂ⓩ�|�̒������w������Ƌ��ɂ����y���������b��͑�������܂����B
�Ǐ��Ƃ������ȂƂ����łȂ����͏������ƁA�X�g�[���[�ɂ��āA�b������L����荇�������Ƃ͂���܂���B
�߂������Ȏ��͊w������ȗ��E�E�����I�߂��������╶�w��i��ǂ��Ƃ����������̂ł��B
�Ȃ���i�߂��Ă����{���p���p���Ƃ߂���n�߂��̂����������ɁE�E�E
��ɂ���h�����Ɖi���l���E�E�E�h���̒n��K���Ƃ��A���ʂ̘b�����y�Y�ɂƎv���āB

<<�Q�O�Q�R�N�x�E�nj㊴�z������>>
[No. 599] �P�Q���@�Q�X��

�@�@�@�W�p�Ёu���u�J�͐Â��ɋ|�����v���d����
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�Q�Q�N��E�@�R�R�T�@�y�[�W�@
�E�E�E�u���́A���u�J���ĉ��ł����H�v���ɂȂ����q�Ō��t���Ղ����k���A��t�͏����������������Ɍ��Ԃ����B���F�̃`�F���͂��̋��ɕ�����āA�t�ł���u�Ԃ�҂��Ă����B�u�X�����̖��O����B���u�J���Ă����[�C���v
�f�����U���ĕ����Ȏs�������ɐ��荞��ł���G�����̃X�p�C�̂��Ƃ��A�쒆�ł����Ă�ł�����āA�Ɖ����m��Ȃ���t�������B�u���Ȃ݂ɉf��̌���́w���u�J�x�B����Ɋւ��Ă͖M��̂ق����]�����������Č����Ă���B��ɂ��A���Č��t�ɂ́A�|���Đk������ĈӖ��̂ق��ɁA�����U��������ĈӖ������邾��B��ۓI�ȃs�A�m�C���g���ƁA���ꂪ���Ƀ}�b�`�������Ă킯���v
�����CD�̃u�b�N���b�g�œ����m���ˁA�Ə��N�̂悤�ȏ݂����ڂ��B���b�X���̎��Ԃ̓^�C�g������A�����G�k�͂����ɐ�グ����B�Ȃ̂ɂǂ����Ă������Ɍ����āA��t�͂₯���`�ゾ�����B
�u������ȁA�X�p�C�B���Ƌ@���Ƀh�h��ȃA�N�V�����B�O�O�V�Ƃ��D���H�v�u������ς����Ƃ��Ȃ���ł���ˁv�u���Ⴀ���x�ςĂ݂Ă�B���z���ʂ�̉f�悾�Ǝv�����ǁB������ȁA���̃h���p�`���v�N�ɂł��W�F�[���Y�E�{���h�ɂȂ肽���������邾��A�ƌ����āA����Ȋi�D�����X�p�C�Ȃ�ĉf��̒������ł���A�Ƌk�͐Â��ɖڂ���炵���B�E�E�E�E
�S���{���y���쌠�A���̒n���������ō�Ƃ��Ă����k���͂ЂƂ�ŃR�c�R�c�ƍ�Ƃ���̂��D���������B����Ȃ������i�̉��؉ے�����d�b�ŌĂяo���ꂽ�B�ˑR�ɂ��������ɂł��Ȃ����ł��낤���Ў��̖ʐڂ̂������@��Ԃ��ꂽ�B
�@
�u�N�͊m���q���̂���Ƀ`�F���̊y����K���ɍs���Ă���ȁH�v�ˑR�̎���Ɉ��R�Ƃ����B���͉䂪�A���͍J�̉��y���������쌠�Ɉᔽ���Ă��邩�ǂ������ׂ����B�N���Q�N�قǂ����̃`�F�������ɒʂ��Ď��ԂׂĂ��Ăق����B
�k�͂���̂��߂̊w��ƃ{�[���y���^�̘^���@��n���ꂽ�B�������ʂ������Ƀ`�F���̖��͂Ɏ�����Đ̂̐h���������Ƃ͈���ĐS�̖����ɂȂ鉹�y���y���ސS���ɂȂ��Ă��܂����B�`�F���̐搶���I�y�Ȃ́u���u�J�v�������B
�k�͎����̂��Ă���s���͉ʂ����ăX�p�C���̂��̂��B���t�̏�B�ɂ͎q��Ƃ̐e���ȊW����ے�ł��Ȃ��A���������̂��Ƃ��^�������܂ł��ď�i�ɕ��Ă��鎩���̐l�ԂƂ��Ă̙�ӂ�z���B
���̍�Ƃ̍�i�ɏ��߂ďo������B�܂��R�O��̔�r�I�Ⴂ��ƁA���ꂩ����f���炭�ǂ݉����̂����i�ɏo�����邱�Ƃ��y���݂ɂ������B�{����܂ɋP������i�ł����B
[No. 598] �P�Q���@�Q�Q��

�@�@�@���|�t�H�u����͐��v���Y��
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�Q�R�N��E�@�P�X�U�@�y�[�W�@
�E�E�E�u�p���b�v�@��オ���̑��������Ȃ���s�X�g���Ɍ����Ă���ˏグ��ƁA���앖������������Ɋ��̏�ɕ������Ėڂ�����B�u��[���悵�悵�A�܂��ł��������A�����������v�E�E�E�E
�E�E�E���Ƃ͖l���������ƍς܂��邾�����B�u�p���v���앖�͂ӂ��ɂ����ۂ������ƁA�S�Ȃ����������Ɠ|��āA�N�����Ȃ����֊��|���Ċ��ɕ������B�u�ł����I�v���������{�C�Ɋ�сA�����ŏ���������܂ł��Ă݂����B�u�������v�u����ς������������v
������̗₽���������������悤�ɁA���́u�����������������A���������ˁ[�v�Ƃӂ������Â������o���āA���앖�ɕ����킳��悤�ɐg����ƁA���������������B�u���Ȃ���I���Ȃ�����ˁ[�v�u�����������ƌ����Ă��Ȃ�v������͖l�����Ȃ��Ō������B
���앖�͓����������܂܊��𗣂�āA�ׂ̈��̔w���ɘr���A�����̂�����ɂ���������B������ăA�[�`�������F�f�̔����ׂ������A������߂ɍ����ߌ�̌������Ă���B�l�͂�������ڂ𗣂��Ȃ��ł����B�E�E�E�E
�l�E�E���c���͒n���́i���炭��҂̏o�g�n�A�k�C�����ق�����̐i�w�Z�E�E�ł��傤�j�ł͖��N�P��̏C�w���s�̑O�ɃN���X���ŔǕ���������B���c�͂��̔Ǖ����������w�Z�ɂ͋x�ɓ͂��o���Ăǂ̔ǂł��\��Ȃ��|�`���Ă���B
���含���d���w�Z�A���c�͕s�o�Z�ł͂Ȃ����g�̓s���œo�Z�ł��Ȃ��|�̘A���B�����ēo�Z���Ĕǂ̃����o�[�����n���ƂR���̏����A�S���̒j���E�E�s���V���̔ǂ��Ƃ������Ƃ����������B���̔ǂɂ͏����̃��[�_�[�i�ɋ߂����ޏ��₿����Ɖ����ڂȏ��앖�����Ă݂�Ȃɓ�������Ǝv�����B�����ւ̏C�w���s�̂�������͔ǂ��ƂɎ��R�s������A���̑ł����킹�̂��ߔǂ��ƂɌv��𗧂Ă�Œ��������B
���͂̒�����_�Ԍ����i���{���ɐV�N�B�����Ďv�t���̍��Z�Q�N���̒j���̂����ɐ��X����������ł����Ƃ������炢�ɕ\�����Ă���B���̍�҂͍��Z�����ȁE�E�Ƃ����v�킹�Ă����B
���Z�����͐獷���ʁB�w�����r�����E�E���狳�t�ɂ�茵�i�ɒ��ߕt�����Ă��イ���イ�Ƃ��ĉ߂����Ƃ�������邩������Ȃ��B���������c�̊w�Z�͐i�w�Z�Ƃ������Ƃ������Ĕ�r�I���݂��d���������y�̍Z�����낤�B
���������H��܂̌��ɂ͓o�������̂̐�ɓǂ�܍�ɔ�ׂ킽���͂��̑f���ȕ\���͂̕����^�������B
[No. 597] �P�Q���@�P�T��

�@�@�@�V���Ёu�ؔҒ��̂��������v�i�䍹��q
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�Q�R�N��E�@�R�P�O�@�y�[�W�@
�E�E�E�܂���o�����͈̂ꔪ�������B�u�w���b���x�����Ă����ł��傤�B�킴�킴���������̂���H�D�𒅂āA���o�ōs��g�͉̂��ׂ̈����āA�ڗ��ׂł��傤�B����Ă���������Č����т炩���Ȃ��ᓢ�����b�オ�Ȃ��v
�ꔪ����炵���������������B���������Ƃ��Ă͍앺�q������ɁA����Ȃӂ��Ɍւ炵���C�����ɂȂ��Ƃ͎v���Ȃ������B�u�E����Ƃ������Ȃ��Ǝv���̂͂悭������v���������Ă��ꂽ�̂́A���p�������Ă���Ă����^�O�Y�������B
�^�O�Y����͂ǂ������Ǝ��Ă���B�u�����ŗZ�ʂ������Ȃ��v�Ə����̐l�X����͎U�X��������Ă��邪�A����ł������邱�Ƃ��Ȃ��B���̐l�������S�O���Ă��邱�Ƃ�F�߂Ă����B���ꂾ���ł���炩�~����C�������B
�u�܂��A��H�y�܂łɂ͕Ђ�t���˂��ƂȁB���������邵�ȁv�ƁA�����������B�앺�q�����k�̂ӂ�����邽�߂̌�����������o���Ă��邵�A�������݂��o�����ɂ���B�E�E�E�E
���炭�����̐������������Ă����]�ˎ���A���͂₠�������Ȃǂ̋C�T�͉����̐̂̌�葐�ƂȂ��Ă��܂����B�܂��n���̕��m�̒��ɂ͋C�����ӂ���N�����̕��m�����Ĕ˂̍�����a����y�͘V���̕��s�����Ă��܂����B
�����ԍۂ̏��N�͂���ȕs����\�����Ƃ�������̋w�����߂č]�˂܂ŏo�Ă��Ďŋ������ɂ��ǂ�����B���������̂����������̂��̂ɂ��s�����������āE�E���͂Ƃ����ƕ��e�̏�i�A�V���̕s�������j���Ă��܂������̋��̌�n���Ƃ������ƂɂȂ�B
���̍�i�A�����̒��؏܂ɑI�ꂽ�B���\�̍]�ˎ���ɔɉh������]�ˎs���̈ӎ��ƒn���̕��Ƃ̂�������E�E���̉A�ɂ���c���N���i���˂̑䏊����ɂ܂��s���̉��s�̉e���s���E�E�������I�݂ȏ��������ł���ŋ��Ɍ����Ăĉ��������B
�ނ���NHK�Łu�R���f�B�[���]�˂ł�����v�Ȃ�ԑg�������ĉ����S�������́A���Y�����q���̖ʔ�������������ɋ����������ꂽ���Ƃ��v���o���B
�����ƕ��Ƃ̐����ɑ���ӎ��̍��͌��\�ɂȂ��Ē������������Ă������B�l�\�����̓������肪�����Ɍ�y�Ƃ��Ă��Ă͂₳���悤�Ȃ��̌�ɂ��n���̕��Ƃɂ͍X�ɕ��Ƃ̋��̕����͍����������B
[No. 596] �P�Q���@�P�P��

�@�@�@�W�p�Ёu�䂪�F�A�X�~�X�v�Γc�ĕ�
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�Q�Q�N��E�@�P�U�T�@�y�[�W�@
�E�E�E���̎�ڂ����ߐU��Ԃ�ƁA�^���̂悤�ɃX�~�X�E�}�V�����Ă����B���������Ƌ삯���A�����ɐw���B�g���[�j���O�E�x���`�̈ʒu������ƁA���O�Ɍ��ƕI�̏����^���������B�x���`�E�v���X��������肾�����B
��̕��ɁA�S�L����C���`���B�܂��́A�v���[�g��t�����ɃE�H�[���A�b�v����B��r�ɔM�������ʂ��A�߂��߂��Ɩڊo�߂�̂�������B�X�~�X�́A�V���[�A�Ƃ������[���̎艞���́A���̂܂��̐l���ɑ���艞���ł���A���̐���������ɑ���X�萺�������B
�ӂƁAG�W���̃X�~�X�̃��[���ɂ͊����̉e�����傫���AN�W���̃X�~�X�Ƃ͕ʕ��ł��邱�ƂɋC�Â��B�o�[�x���𐨂��悭�����グ�����A���[���̗]�͂ɂ��A�o�[�x�����肩�痣����u��������̂��B���傤�ǐԂ��������������������̂悤�Ȋ|���ւ��̂Ȃ����̂��A�ꎞ��̕����痣��銴�o���B
����AN�W���̃X�~�X�ł́A���������]�͂ɘf�킳��邱�Ƃ͖��������B���̃X�~�X�̃o�[�x���́A�g�̂̈ꕔ���Ȃ���ɁA�s�^���Ǝ��Ɋ��Y�����B����Ȃ��Ƃ��A���X���������B�E�E�E�E
���̍�i�͐̓ǂ��Ƃ̂���E�E�E�u�����߂̃W���i�T���v�E�E�Ă��ȋ����������ēǂB�����ɏo�Ă���X�~�X�Ƃ̓{�f�B�r���Ɍ������Ȃ��o�[�x���̑��u�̂��Ƃ��낤���B���i�X�|�[�c�Ō���o�[�x���̎����グ�͂������s������Ƃ�ł��Ȃ����ƂɂȂ肻���ł��B
�����ł͋ؗ͂����邽�߂Ƀo�[�x�������グ��Ƃ����E�Ƀ��[�������Ă��ăo�����X�ɋC���g�����ƂȂ����S�Ɉ�����@��炵���B
�R�O��ڂ̑O�ɂ����ߐl�̔ޏ����ˑR�ɑ̂̂��Ƃ��C�ɂ��n�߂ăX�|�[�c�W���ɒʂ��n�߂��B���錩�邤���ɏ�B���Ă��đf�l�ɂ��Ă͌��Ⴆ�����Ȃقǂɋؓ����ɂȂ����B�R�[�`�ɖJ�߂��ă{�f�B�[�r�����ɏo�Ă݂Ȃ����d�ƗU����B
�R�[�`�̎w���̌���S�Ƀg���[�j���O�ɗ��ő��ɏo���B���ʂ͎U�X�Ȗڂɑ����Ă��܂��������ꂩ������ł������ƐS�Ɍ��߂�B
�����߂́E�E�H�A������ăI���̂��ƁE�E�H�g���܂����ȁ`�B����ȊȒP�ɑ��ŏ�ʂ��_����قǐ��̒��Â��Ȃ��B�����ăW���i�T�����`�������W���邱�Ƃ̒��ɐl�������o�������������B���Ȃ݂ɂ��̍�i���H��܌��ɂȂ�������ǎ�܂ɂ͎���Ȃ������B
[No. 595] �P�Q���@�@�V��
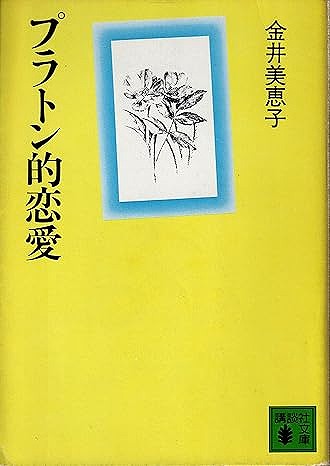
�@�@�@�u�k�Ёu�v���g���I�����v������b�q
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�P�X�W�Q�N��E�@�Q�U�V�@�y�[�W�@
�E�E�E�����̏����������ɂ��Č��Ƃ������ƁA���邢�͏������Ƃ��Ă����i�ɂ��Č��A�Ƃ������Ƃ��A�Ȃ��N�ł���������悤�Ƃ��Ȃ���A���Ɍ�肾���Ă��܂��̂��낤�B
���ق��������Ă���̂ɂ�������炸�A���͂��߂��錾�t�B�^������낤�Ƃ���~�]�ɂ���Č��͂��߂��Ȃ���A���͐^�����������t���A�Ȃ����͂��߂�̂��낤�B�i��������j�Ƃ��������Ƃ̒��ŗv��������҂���Ă�����̂����Ȃ̂��A����͂����̍����Ƃ������̂Ȃ̂�������Ȃ��B
�����ƌ������������̂̒��ɁA�I���Ɍ��z���̂ƂȂ����s�����t���Ђ���ł���Ƃ����`�����킽���͖��z����B�悤����ɍ������邱�ƂȂǂ͉����Ȃ������B�����A���͎����̏�����ǂނ��ƂɁA��ȏ�M�������Ă����̂������B�E�E�E�E
�����܂������H�ł���������e���r�̃R�}�[�V�����Ŗ�⏺�@����̏��������������̃E�B�X�L�[�̃R�}�[�V���������Ƀ^�R�̂ł���قǕ������ꂽ�L��������܂��B
�u�E�E��A�\�N���e�X���v���g�����E�E�j�[�`�F���T���g�����E�E�v�E�E�E�v���g�����ĂȂH�A�����Ď����������Ă��ꂼ���m�肻�̍l���������������L�����܂��V�����B���䂳��̍�i��ǂ�ł݂܂������I�C�I�C�Ђ���Ƃ��ĉ��Ɠ��N�ォ�E�E�H
�܂��A�ޏ��Ƃ�5�قǎ��̕����N��ł��������_�N��ł͂��Ȃ�̂��o����ł��B�̎��̒��Ő����������ꂭ�悤�ɂ܂�݂�ȔY��ŔY�݂Ȃ���傫���Ȃ����B
������R���i�А^���Œ��Ɏ����{���㈲�����B���炭��Ƃ���ł����瑽���̎������܂Ƃߏグ��i�ɂ����B����16�N�ɘj���ď������߂Ă����������ꉞ�̍��q�ɂ܂Ƃ߂Ă݂��B��Ƃ͈ꗬ��ƂƉ����ς��܂���B
�������A���̌�̊���܂œ������������ƂɈ��g�Ƃ�������Ƃ̎コ�Ƃ������c�v�����A�}�`���A���ς��Ȃ��Ǝv�����B
���{�����{�͂��łɎ茳����U�킵�܂����w�@�@�t�@�@���@�x�l�b�g�œǂނ��Ƃ͂ł��܂��̂łǂ����B
[No. 594] �P�P���@�P�V��

�@�@�@�p�앶�Ɂu�_���̎R�v����^�m�Y
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�O�W�N��E�@�Q�P�S�@�y�[�W�@
�E�E�E�u����A���������猩�o���̂���j���A���̑O���s�����藈���肵�Ă���ˁB�N�Ȃ̂��v���o���Ȃ���v�u�ǂ�ǂ�v�Ėɑ����āA�����T�O�Y�����������u���́A��i�����Ȓj���H�v�u�����v
�����ɂ��������Ȓ��̒����ɂ������̉H�D�𒅂����l���A���H�����̂������ނ悤�ɒʂ�߂���Ƃ��낾�����B����˂��J�������������A���ɂ͒N�����Ȃ��B�u�ׂ̔ԉ��ɗp�ł������˂��̂��H�v�ƁA�����������ƁA�u����A�����͂����Ə��H���������ȁv
�ڂ̂����Ė��������B���炭���ǂ��ė��Ȃ��̂ŁA��͂肿���������ȂƎv������A�u���A�Ð哰�̕�݂������Ă����B��y�Y����v�ƁA�m���q�傪�����Ō������B�Ð哰�͉i�㋴�̂����Ƃɂ�����݉��ŁA�l������̂ł��������ɂ���邱�Ƃ������B
�u�Â��炾�Ȃ��B�ʓ|�ȑ��k���Ƃ�������Ȃ���v�u�ǂ����A���邱�Ƃ������˂�����v�ƁA�����͏����B�Ă̒�A�K���̐����������̂ŁA�O�l�͉��ɍ~�肽�B�����ɂ����̂́A�\�N�y�̒j�ŁA���T�Ȋ�����Ă���B
�ǂݎn�߂āE�E����H�A�ȑO�ǂ��Ƃ̂��镶���B�������Ă݂�Ƃ���܂����Q�N�O�̂P�Q���ɓǂ�i�B���̕���́u��]�˒�N�g�v�B���ƕ�s�A���Ƒ�X�̎�A���Ɗ��{�E�E���ꂼ�ꒇ�̂����c����̉B�����Ԃ̘b�ł����B
�g�����炿�����ꂼ��ł͂���܂������c��������Ő��j������y��ő��o��������肵���c��������ł���������������ꂼ��̓ɑ����ĉB�����܂������R�l�ŋƂ������Ă�����V�т̋��_�ɂ��悤�Ƃ܂��W�܂����̂ł����B
��肠�����͒����ߏ��̉ł���T���̎�`���A���育�Ƃ̑��k��Əo�����L�̒T���A�ʂĂ͐̎�����n���ő����̂��߂��Ƃ܂Œm�b���o�������ĉ������悤���E�E�E�Ƃ����V�є����̏W�܂�B
������N�ސE�������͂܂����C�[���B���ԂŃX�L�[�̃N���u��������肵�܂������܂��ɂ��̍�i�̎�l���E�E�^������Ŋy���������B�P�O�N����Ǝ��ʂ�̗͌��ςȂǂ̗��R�ŗ��E���U�E�E�B��N����̂Ƃ��̊�т͍��ł��Y����Ȃ��������ł����B�ł�������͓��������v�E�E�H�A�����Ɠ��������Ȃ����E�E�H�A����ɊÂē����l�������ł������b�g�����̂��������Ƃ�O�ʂɉ����o���l���̊y���݂𖡂���Ăق����B
�����̊ԗc����Ɛz�K�̂�����������ŃR���i�Ђ̌�R�N�Ԃ�̍ĉ�����܂����B�W�O�߂��̂R�N�ԁE�E�E�A���������͎��߂����Ԃ����ĕς��܂��ˁB
[No. 593] �P�P���@�P�V��

�@�@�@���|�t�H�u�n���`�o�b�N�v�s�썹��
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�Q�R�N��E�@�@�W�O�@�y�[�W�@
�E�E�E���݂��R�C�S�Z���`�͂���{�𗼎�ʼn������Ėv������Ǐ��́A�ق��̂ǂ�ȍs�ׂ����w���ɕ��S��������B���͎��̖{��ł����B�ڂ������邱�ƁA�{�����Ă邱�ƁA�y�[�W���߂���邱�ƁA�Ǐ��p�����ۂĂ邱�ƁA���X�֎��R�ɔ����ɍs���邱�ƁA�[�[�[�[�T�̌��퐫�������Ƃ�v������Ǐ������̃}�`�Y����ł����B
���̓������ɋC�t���Ȃ��u�{�D���v�����̖��m�Ș�������ł����B�Ȃ�������ł��낤���Ďx����d���������ɂ��a�܂��A�����������ׂ��Ȃ�����Ȃ��������O�X�p���̂����Œn���Ƃ̍j�����ɕ����Ă����B
���̖{��ǂނ��тɎ��̔w���͏������Ȃ����Ă����悤�ȋC������B���̔w�����Ȃ���n�߂��̂͏��R�̂��낾�B���͋����̊��Ɍ������Ă����^�������w��L���č����Ă����B�N���X�̂R���̂P�قǂ̎����̓m�[�g�ɖڂ������t���A�w�����ۂ߂��ٗl�Ȏp���Ŕ����ʂ��̂������B
����Ȃ̂ɑ�w�a�@�̃��n�r���e�[�V�����Ȃł��������Ɉ͂܂�Ȃ��症�ɔ����ꂽ�g�̂ɐp��т���������ꂽ�͎̂��������B�p���̈������펙�̔w���̓s�N���Ƃ��Ȃ���͂��Ȃ������B���̎q�����͐������v�}��������Ă������炾�B
���̖{�����N�̊H��܂ɑI�ꂽ�Ƃ����͔邩�Ȋy���݂������Ă����B���̍�Ƃ���̃v���t�B�[���Ȃǂ��łɑ����̕��̏^�ĕs���Ȑ������ɂ�������炸�m�~�l�[�g������Ɏ�܂����E�E�E�ƁB
�������A���Ȃ��͎��̐l���̔��������܂������Ă��Ȃ��B�����̑̂̐v�}���s���S�Ȍ`�Ő��܂�Ă��Ă��܂����c���Ƃ�O�ʂɑł��o���Ă̂��̍�i�Ɏ��͐^�������������B����Ȋ����Ő_�l����̐v�}�ʂ�̐l�Ȃ�ĊF���A�݂ȂT�O���P�O�O���ł���B���������Ȃ��́u�E�E���̑̂͐����邽�߂ɉ��Ă����E�E�v�Ƃ܂Ō����Ă��܂���������F�X�X���P�O�O���ł��B
�܂��Ă�v�}�ɂ͑ϋv�N���܂ł͑z�肵�Ă��Ȃ��ł��傤�A���̍���Љ�܂ŁB�����݂�Ȍ��t�ɔ����Ȃ������ł��A�����������������R�������Ȃ��Ȃ�ꂵ�݂Ȃ�����l���̑����͂܂��Ƃ����悤�Ɠw�͂��Ă��܂��B
�悸���̍�i�͂���Ȑv�}�̕s���Ȃ�Ă��������C���~�낵�Ă�����x�������Ƃ����{���͂��������Ăق����B���͂��̍�i�̓�����ɘȂ܂܋������������Ă͂��܂����B
[No. 592] �P�P���@�P�O��

�@�@�@�u�k�Ёu�I���[�u�̎��邱��v�������q
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�Q�Q�N��E�@�Q�P�P�@�y�[�W�@
�c�v�̐����͂قƂ�Ǖς�炸�A���N���āA�K���b�v�ɉa�����A�H����H�ׂďo���A�[���ɃK���b�v���Ԃɏ悹�ċA����B�y���͔��d�������ăK���b�v�ƒ����т�H�ׁA���܂ɂ킽�������͐z�K�Ƀs�N�j�b�N�ɏo�������B�~�ɂ̓��J�T�M��ނ�ɍs�����B
�������������܂�ƁA�v�w�ŗ��s������B��x�������[���b�p�ɍs���Ă݂�����ǁA��l�Ƃ��p�ꂪ�ł��Ȃ��̂ŋْ����Ċy���߂��A���͍����������Ƃ������ƂɂȂ����B�s���Ă��O�����炢�̉��s�Ȃ̂ŁA���̊ԁA�K���b�v�͂ЂƂ�ʼn߂����Ă���炵���B
�������v�w�̗��s�́A������H����~�Ɍ�����B���̎������Ɛz�K�ɔ������������āA�K���b�v�����݂����Ȃ����낤�Ǝv�����炾�B�v�͂������D��������A���y�Y�͗��s��Ŕ����n���������A���̂ق��ɂ��y�n�̂����������̂Ȃ��Ė߂��āA�ӎނ�����Ƃ��ɃK���b�v���������?�B
�ۂނƗz�C�ɂȂ��ăK���b�v�͉̂��̂����B�m���̔����Ƃ����킯�ł͂Ȃ�����A�Ƃ��ɔ������킯�ł͂Ȃ��B�K���b�v�͉̂��̂����A�悭�b�������Ă���B�Ȃ�Ƃ����Ă���̂���������炸�s��������ǁA������������ɂ���ƕ�����悤�ȋC�����邱�Ƃ������B
���̖{�ɂ͂U�҂̍�i�������Ă������u�I���[�u�́E�E�v����̍�i�ł��傤���ЂƂO�́u�K���b�v�v���ʔ��������B���̎q�ǂ��̂���ɐz�K�͓~�G�S�ʌ��X�����̂Ŕ����̔͂Ȃ������B�ߔN�̉��g���Ō��X���Ȃ��Ȃ蔒�������~���z���B
�킽���͉��J�ɐ��ސ��c���珼�{�̋ߐ�Őz�K�ɒނ�����ɗ��Ȃ����ƗU��ꂽ�B���߂Ẵh���C�u�f�[�g�͐z�K�������B���c�͗��e�̏Z��ł����傫�ȉƂɂЂƂ�ƈ�H�ƂŏZ��ł����B���̈�H�Ƃ����̂������̃K���b�v�������B
���c���ԂŋA���r���ł��̔����͉�������ē��[�ɂ������܂��Ă����̂��Ԃɏ悹�ĉƂɘA��A�蔒���ْ̋����ق������߂ɂ܂������̂�����ۂ܂����B����Ȏ��ÂŐH�����Ƃ��Ă���Č��C�ɉ��Ĕ�ׂ�悤�ɂȂ��Ă��Ƃɋ������B
���̖{�̑�����E�E�E�ɔ��������c�Ƃ̌������ł��낤���Ǝv�킹��G���`���Ă������B�{��ǂݐi�ނ����ɂ��ꂪ�Ȃ�ł����������炩�ɂȂ����B
[No. 591] �@�X���@�Q�S��

�@�@�@�u�k�Ёu�܂̎�v��F
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�P�X�W�S�N��E�@�R�O�W�@�y�[�W�@
��l�̎Ⴂ���m�����̉�������Ă���B���ɐ����A�S�̒��ɂ͌������{�肪�Q�܂��Ă���B�Ƃ����Ȃ��A���̒j�͕����o�����Ƃ��錃����������悤�Ƃ��Ă��邩�̂悤���B���Ƃ����Ă��A�����̎��ł͂Ȃ��B
�����̔g�����Ĉٍ�����^�ꂽ����̍�����i�ł���B���̒��ɂ́A�ٍ��̐l�Ԃ�����B��ؐl�̑D���A���l�̒ʎ��[�[�[�����ł͒N���݂��̑��݂��C�ɂ��Ƃ߂Ȃ��B
��B�̍�A���ꂪ���̒��̖��ł���B�j�͂ӂƎ��E�𒈂Ɏ~�߁A�������������B�u�����̔����A����̔t�A���܂�Ɨ~����Δ��i�n��ɍÂ��[�[�[�v�ˑR�A�w�ォ�犣�����������a�����B
�u�|�|�|�����č���ɉ炷�A�N�����Ɣ���B�×�������l�����v�j�́A���̂悤�ɂǂ���Ƒ�������ŁA����U��Ԃ����B�V�哪�̔w�̒Ⴂ�j�������ɂ����B�u���҂��H�v
�j�̖₢�ɑ��āA���̏��j�͊���킸���ɘc�܂����B���ꂪ���̏��j�������̎d�����Ƃ͂��Ƃł킩�����B�E�E�E�E
�P�R�㏫�R�E�`�P�̎����p�҂̂��߂��Ƃ̍Œ����̂����Ƃ����R�̗L�͂Ȍ��҂Ƃ��Ă̋`���͓����z��ɓ��S���Ă����̂��S���e�n�̎��喼�ɏ㗌�̎菕�����˗����Ă����B
�Ƃ��ɐD�c�M���͔��Z�肵���Ă̓c�Ɏ��ł������B����Ȑ܁A�`���㗌�̎菕�����˗�����L���V�ɂȂ�A���̐�D�̋@��������Ď�������悵�ď㗌�𐬌������悤�Ɗ�Ă��B����A�����Z�̍���E�֓������͂Ȃ��̐��L�V��~�C�h�r���Ƒg��ŐM���̎��_�����Ɖ�����藧�����������B
�퍑����̗��j�̉A�ɂ͌@��N�����Ί����̃h���}���W�J���ꂽ�ł��傤�B�������j���̂̌�y��i�Ƃ��ďH�̖���y���݂܂����B
[No. 590] �@�X���@�Q�P��

�@�@�@�u�k�Ёu���j�������v�g�c�C��
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�O�R�N��E�@�P�X�R�@�y�[�W�@
�E�E�E�u�҂��āA�ǁA�ǂ��s���́H���肢�A�҂��āI�v�K���ɐ����ӂ�i�����B�������N�������Ɗ����Ă��������A����Əo�Ă���悤�Ȋ����������B�u���������āA�܂��߂܂����Ⴄ��B�ӂ���œ��������āA�܂��߂܂����Ⴄ�B�q���ӂ��肶��A�����Ă����Ȃ���v
�r�̒��Ŗ\���j�̎q���A�T���q�͕K���ŕ������߂��B�j�̎q���������������قǁA�K���̗͂ŕ������߂��B���ő������Ă���̂��A�����Ȃ̂��A�j�̎q�Ȃ̂�������Ȃ������B�u�����I������I�v
�قƂ�ǔߖɋ߂��j�̎q�̐��ɁA�܂��������Ă���̂ɋC�������B���������Ă���̂��A�u�����I�����I�v�Ɗ����Ȃ���A�u���u���Ƒ̂�k�킹�Ă���B�u���v�I���v������B��ɁA���v������v�j�̎q��������߂��܂܁A�T���q�͖����ʼn��x�������J��Ԃ����B
�u�c�{�݂ɓ����ꂽ��A�c���E�����A���E�����A�ǂ����ɘA��Ă���Ă��܂��B���肢�A�����Ă��������B�E�c���肢�v�B�T���q�̘r�̒��ŁA�u���u���Ɛk���Ă���j�̎q���A�����������B�K���ɐ����ӂ�i���Ă����������B�����Ƌߊ���Ă����킪�A�����Ă���Z�̌��Ɏ��u���āA�������ڂŔT���q�����߂�B�j�̎q�����x�������ꂢ�ċ����B�Z�̌���͂킪�A�ꏏ�ɂȂ��ē���������B
�u�E�E�E�E����Ȃ��Ƃ����Ȃ�����B���o����A��ɂ���Ȃ��Ƃ����Ȃ�����I�v�����ł��M�����Ȃ��قNj������������B�E�E�E�E
�T���q�͎��g�̐����ɋ�肪�����u�����x���Z���^�[�v�Ɋ��x���d�b�ő��k�����B�u��x�A������ɗ��Ă��b���܂��H�v�ƗU���ďo�������������ɑ��k���ɗ���l�����̒��ɂ͎������͂邩�ɓr���ɕ�ꂽ�l���������邱�Ƃ�m��B
���x���K��Ă��钆�Ŏ����ł����k�̓d�b���Ă������邱�Ƃ�m��A����`��������悤�ɂȂ����B���̖{�ɂ͓s��Ő������Ă���Q�O�`�R�O��̂T�g�̎�҂����̊�����`���Ă��Ă��̂����ɂ��T���q�������B
�T�g�̎�҂̒��ɂ�������ł���c���Z�킽�����o�ꂵ�Ă��Ă��ĔT���q�����̍s���������͂��邱�ƂɂȂ�B
[No. 589] �@�X���@�P�T��

�@�@�@�u�k�Ёu�C�ɍ~���v���R�@��
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�P�X�V�U�N��E�@�Q�X�U�@�y�[�W�@
�E�E�E�u�˂��A����Ȃ��Ƃ��āA���̂��Ƃ�v�u�N��?���ς����Ȃ����Ă������Ƃ��v�ޏ��́A�O���ӂ�킹�ėT������Ԃ����B���ꂩ�炻�̖ڂ��������Ɖ�������̂ӂ��܂̕��Ɍ�����ꂽ�B�u���̂��ƁB���̂��Ƃ�B�ڋ��Ȑl�ˁv
�u�ڋ��Ȑl�́A�N�̕����낤�v�v�킸�ނ͉�����̕��֊{�����Ⴍ���Ă��܂��Ă����B���q�͗��\�ɃX���b�p��E���A��������̕��֕����o�����B������x��������̂ӂ��܂���A�ނ̕���U��Ԃ����Ƃ��A���q�̖ڂ͊����Ă����B�����ď������Ȃ����ڂ��A�������]���̂Ȃ��֒��ݍ���ł����B
�����ƌ��߂Ă���ƂƂ߂ǂȂ����������Ă䂫�����Ȗڂ��������B�u���̂��݂���B���̎莆�����L��ǂ̂ˁv�u�����A�ǂv�u�ڗv�u�ڗ�͌N�̕����v�������̂̒m��Ȃ��z���͂̂��߂ɒ��ݍ���ł䂫�Ȃ���A�K���ɍR���Ă���ڂ������B
�Ƃ��q�͏��o�����B�Ђイ���Ƒ����z�����݂Ȃ��炷��A���̂����̏����ł͂Ȃ������B�u�R�����́B�R�����́B����Ȃ��́v�u�R����Ȃ��v�䉪�S��́A���߂��݂��ӂ�킹�Ȃ����ɂ�ł����B�u���Ȃ��Ȃɂ͕�����Ȃ��̂�v���q�͋��B
�u���Ȃ��Ȃc����������Ȃ��̂�B�Ƃ̒��͂������܂ŁA�킠���Ƌ삯�����݂����ɂ��ē����֏o�Ă��āB�ł��A���A�o�̂Ƃ��̉w�̖������邾���ł��������ς��ŁA�X�ł͂�����l�ڂ����ŁA�������Ȃ��āB��Ђ��Ђ���ƁA������l�ő�ʂ�̃V���[�E�C���h�`���Ȃ���A���������Ă��邾�����������̎q�̋C�����Ȃ�āA���Ȃ��ɂȂA������Ȃ��̂�v
�ޏ��̐��́A����Ⴍ���남�됺�ɂȂ��Ă��܂����B�u�����Ԃ����炢���ł��傤�B�����A�Ԃ��Ă�B�����ɋA���āB�����ċA���āB�A���āB�A���āv�E�E�E�E
�䉪�S��͎R�`�o�g�A�����W�̉�������Ɍg����Ă����B�������q�͏H�c���o�g�ŗ��s�Ǝ҂̃A���o�C�g�����Ă����B�ԑg���쒆�ɂ��܂��܃Q�X�g�o�����Ă��������ƈ䉪�͉��C�Ȃ����t�����킵��������������ɍ����R�Ƀn�C�L���O�ɍs���B�C�S���m���悤�ɂȂ茋�Ǔ��������B
�����̃X�g�[���[�Ƃ��Ă͎Ⴂ�j�����m�荇���ē�����������݂��̌��_���ڂɂ��n�߂ĕʂ�Ă��܂����E�E�E�E�B�P���ȍ�i���A�ł��Ȃ����ꂾ���̕��͂��₵�Ă���ȃo�J�������e��[���@�艺�����̂��E�E�E
���̍�i�̍�҂����߂Ėڂɂ����B�V�l���Ǝv�����玄���7�ゾ�Ƃ����B��i�̐���N���炷��ƍ�Җ{�l�̂Ƃ����������̐�[�I�Ȏ�҂����̕��������g�̑̌���ʂ��ē`�����������̂�������Ȃ��B
[No. 588] �@�X���@�P�O��

�@�@�@���w�فu���݂����� �v�R�{�b�m
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�S�N��E�@�R�W�X�@�y�[�W�@
���i�p�̃X�`�[�����b�J�[�̔����J���Ē���`������ł�����V�������W������ł������B���̏�Ŏx�o���ߕ���t�@�C���ɕ����Ƃ����Ă����{�썹�I�́A�������˓I�Ɏ���~�߂āA�����g���ł������B
�������̊��Ńm�[�g�p�\�R���Ɍ������Ă����y�̒r�������ƁA��u�ڂ��������B�������r�������͂����Ɏ������m�[�g�p�\�R���ɖ߂��A�������Ȃ��������̂悤�ɃL�[��ł������Ă���B���̒m�������Ƃł͂Ȃ��A�ǂ��������������̂͂��Ȃ��[�[���₩�Ȏ����͂��������Ă����B
�Ă̒�A��V���W���́u�{�삳��v�Ƒ傫�Ȑ��ŌĂсA�菵�������B���I�́u�͂��v�Ɠ����ĐȂ𗧂����B�܂��A��X�����Ԏ������Ă��܂����B���̒i�K�ł��������Ă���B���I�͎��Ȍ����ɂ����Ȃ���A��V���W���̕��ɕ��݊��B�uA4�̕����A���ꂾ�������Ȃ��̂��H�v
��V���W���̓��b�J�[�̒��ɐς܂�Ă��邻����w�������B���i���炠�܂�Ί���������A�����߂��ʂ����Ă���j���A����Ɍ������������Ă���B�u���́E�E�E�v���I�́A�����̐��������ジ��̂������Ȃ���A��x�������ݍ��B
�u��S���͂���Ǝv����ł����ǁv�u���ꂶ�ᑫ���v�E�E�E�E
����ȋC�̎ア���I�ł͂��������C���炵�ɔ��`��ς��悤�Ɨ��e�@�ɍs�����B�b���D���̏��������������C�����ǂ��}�b�T�[�W�����Ȃ��獹�I�͋C�����悳���疰���Ă��܂����B���ӎ��̎��Ԃ̌�A�u�N�����܂���v�̐��Ŗڂ��o�܂��ċ������ċ������B
�N�A����B���I�͖ڂ��^�����B�u�܁A�����c�v�u�ǂ��A�����ł���B���^�ɂ��҂�����v�����e�t�͂����ɂ��������ɏ��Ă���B
���Ǎ��I�͋ߐ�ɍs���Ă��W���Ή������ɂ��Ȃ������������Ĕ[��������B���͂��������I�̐S���̕ω���ϋɐ��̒��Ɋ����Ĉ�ڒu���Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B
�R�{����̂��̖{�ɂ͂U�҂̍�i�������Ă��ꂼ�ꂪ������̂�ς��邱�Ƃő�ϐg�A�Ƃ��������������ɒu�����ƂŎ㍘�̐l�������C���������悤�ɂȂ����b�B�܂��A�l�Ԃ̈ӎ�������ȊȒP�ɕς�����ΐ��b�͂Ȃ��ł������������I��i�ł��B
[No. 587] �@�X���@�@�S��

�@�@�@�V���Ёu�E�Ԑ� �v�O�Y�N�Y
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�P�X�U�O�N��E�@�R�V�T�@�y�[�W�@
�E�E�E���͓�K�ւ̂ڂ낤�Ƃ��āA�ӂƑ䏊���̂����ƁA�o�������ŁA���Ԃ��ԂƊ�����Ă����B��A�Q��O�ɁA���Ő�炷�邱�Ƃ͎o�̖���̏K���ŁA�����O����m���Ă͂������A���̎��A���͂Ƃ����ɁA�o�����܂ŁA�����ŋ����Ă����̂ł͂Ȃ����낤���Ƃ����������B
�u�T���悢�ɂ��A��邢�ɂ��A�q���Ȏo�̐S�͗h��Ă���͂��������B���́A���������������傤���������̂����̂��ꂩ��������A���̂܂܁A�����Ɠ�K�ւ����������낤�Ǝv���Ȃ���A�ǂ��ǂ��Ƒ����r�������ɂ��邫�A�o�̔w���ցA�u�����B�v�Ƃ������B
�o�́A�G�ꂽ�Ԃ���łӂ�ނ����B���́A���̊�ɂӂ�����ɋߊ���āA�킴�Ɨ��\�ɂ������B�u���̉ł���A�ǂ����ˁv�o�́A���H�̂��ꂱ�ޖڂ�����ڂ���ڂ����āA�������B�u�����ЂƁB�v�u���̖������B���܂�����Ă������������B�v
�o�͖����ł�炢�Ȃ���A�����ӂ肠���A�e�L���q�L���Ԃ悤�ȁA���e�����̐e���������߂Ď��̋����ǂ���ƂԂ����B�u���肪�Ƃ��B�v���́A�u�T�Ƃ̌��������������Ǝv�����B�E�E�E�E
�킽���͐[��ɂ���w�����̂��ɂ��闿���u�E�ԑ��v�ʼn����������Ă����u�T�ƍ��ӂɂȂ��ċx�݂̓��ɂ��̐�̖؏ꂠ������U�����悤���E�E�Ƒ��k�����B���݂��̐g�̓��Ȃǂ�b���Ȃ��玄�͂��̐l������Ă�肽���Ǝv���悤�ɂȂ�B
����A�u�T�����̕s�^�ȉƑ��̌���𗝉����Ă���Ă܂���w�Q�N���̍݊w���ł͂��������u�T��X�̎��ƂɘA��Ă����ĉƑ��ɂ���������ꂽ�B
���̍�i���O�Y�N�Y���g�̎������Ƃ����Ă悢��i�ł��B��r�I�L���������ƒ됶���E�E�A��������l�̎o�����E�Ƃ����`�Ŏ��������Ă���ɓ�l�̌Z���o�z�Ƃ����`�ŖS�����B�c���ꂽ��l�̎o�͖ڂ������s���R�łU�Ԗڂ̖����q�������ނ̐������h�_���݂�B
�ꋫ�����z���ĎႢ��l�̏������т������̎���̊H��܂ɋP�����B
[No. 586] �@�W���@�R�O��

�@�@�@�V���Ёu������ �v�R�����l
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�V�N��E�@�P�T�R�@�y�[�W�@
�E�E�E�N���������������B�u���̘b���ĉ��ЂƂ܂Ƃ��ɕ�����ւ��v�@�@�V���B�V�������������̂��B�V�͍��Z�̓����ŋ��N�̏t���Z�𑲋Ƃ��Ă��炽�܂ɂ������肵�Ă������ŁA���炭�����֍s���Ƃ������Ƃ�������Ɠ`���悤�ƍ��������B
���������O�ɉ����֍s���Ɠ`�����C�ł����̂����ǑO�̓��u������s���v�Ɠd�b�����Ƃ��V���͂��߂ĕ������悤�ɋ������̂ł��̂��Ƃɋ����ĉ���ƂɂȂ����B�u�������ĉ��Ȃ�v�V���������B
�u�������ĉ���B�����������Ƃ��Ă����Ƒ��������ɂ���ւ�H���ʁv�u�������v�u�����Ăւ�v�����Ȃ̂��B�������C�����邯�ǂ����ĂȂ������̂��B�Ȃ̂Ȃ�ӂ����B�u�S�����v���̂Ƃ����u����������������ȁv
�u���v�u���̘b���ĉ��ЂƂ܂Ƃ��ɕ�����ւ��v�Ƃ������̂́B�E�E�E�E
�R�����l�P�X�A���܂��܌�z�����ꂽ�V���E�E�E�A���܂��܂����ɍڂ��Ă������c�W�̍L���ɖڂ��s���Ė^��d�҂̏m����W�ɉ��債����^�悭���i�̎莆����������B�������̖ʐڏ�œ����ɍ��i���Ėk�C���x�ǖ�ɂ���m�ɓ������B
���̍�i�͍�Җ{�l�̎������B�e���|���ǂ����ނ��Ƃ̂Ȃ����͂̉^�т͓ǂ�ł��ċC�����������B�r���ŘA���D�ɏ��i�K�œ��������ԂƑ҂����킹�Ĉ��A���������A�u����A����������������Ƃ�����̂Ńu���[�X�E���[�Ƃ����q���݂����ɂȂ�Ă��v�B
�u�ց[�A����ŏm�̐搶�̍�i�ł͂ǂ�Ȃ̂Ɋ��������́E�E�H�v�u���I�H�A����Ȑ搶�������́E�E�H�v�B�����ɂقƂ�ǖ��S�������R�����l�͂Ȃ�Ƃ��̗L���ȉ����E�r�{�ƂŗL���ȑq�{���̎��m�E�x�ǖ쎩�R�m�̓�����Ƃ��ē��m�����B
���̍�i�A�Q�O�P�V�N�̊H��܂���܁B���̓�N�O�ɂ͂����|�l�̖��g�������u�ԉv�œ���܂��Ă��������̌�͂��܂��i�̔��\�͂���܂���B�������R������͋r�{�ƂƂ��āA���c��Î҂Ƃ��āA�܂���ƂƂ��Ă������̎��т��グ�Ă���B���ꂩ����y���݂ł���B
[No. 585] �@�W���@�Q�U��

�@�@�@�u�k�Ёu�Ă̖� �v������
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�O�O�N��E�@�P�X�R�@�y�[�W�@
�E�E�E���炭�ꏏ�ɏZ�ނƂ����q�J���́u���炭�v�́A�͂��߂���l���Ԃ̊������������B�d�����ۂ�������̂ŁA��ؘA�������Ȃ��悤�ɂ��ă}���I�̕����ɗ����̂��ƌ����B
����Ǝg�����Ⴄ����A�ƌg�ѓd�b���玝���Ă��Ȃ���������������A����ł��ꉞ�͖{�C�̓����s���B�������B���p�̃q�J���́A����ԑ�̏�ӗ����ł����ς��ɂ��đ҂��\���Ă����B��Еt�����S������������Ǝ咣����B
�u���܂ł�����Ȑ������Ƀn�}���ĂĂ����̂��ˁv�����ɉ^�ڂ��Ƃ����M�𐨂��ǂ����グ��ꂽ�}���I������Ďw�E����ƁA�u�����́B�|���V�[�ƃt�@���^�W�[�͕ʕ��Ȃ́v
�q�J���͕��R�Ɠ����āA�킩���Ă邩�猾��Ȃ��́A�ƊÂ��������o�����B�E�E�E�E
�Ђ̑����ۂɋΖ����鏼��}���I�ƃt���[�ҏW�҂̎O�؋��q�J���͂������ł�27�Γ��m�A���ꂼ��̎d�������肵�Ă������m�荇���Ĉȗ����݂����Ɏv���قǐ[�����ɂȂ��Ă����B
������20�N�ȏ���O�̊H��܍�i�ł��B���ł����W�F���_�[�E�E��肾�Ƃ����̑��l���E�E���Ƃ�����҂�ɒ��ڔᔻ���邱�Ƃ��݂�錻��Љ�ł����܂�����Ȃ�ɔF�߂���Љ�\���ɂ͂Ȃ��Ă���B
�ł���������������Љ�ɊS�͎��ĂȂ����͌Â��I�W�T���Ȃ̂ł��傤�B���̎��̐R�����搶�̂��ӌ�������ƐΌ��T���Y�ЂƂ�u�����܂�Ȃ��E�E�ދ��ȁE�E�v�B�O��̋g�s�~�V���̒j�Ə��̃h���h���E�E��ǂ�ł̓I�����u�������ȁE�E�v
[No. 584] �@�W���@�P�W��

�@�@�@�V���Ёu���F�̊X�E酉J �v�g�s�~�V��
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�P�X�T�S�N��E�@�R�P�R�@�y�[�W�@
�E�E�E�s�ӂɁA�j�Ə��̉�b�̐����A�傫���L���ɔ��������B�����̌˂��J���ċq�𑗂�o�����Ƃ��������~�߂āA�ˌ��Řb�������Ă���炵���B���̐��̓��~�̐�������A�L���̓˂�����̕������B���~�͖�ꂩ���ȑO�ɗ������ł���B
�@���̗ǂ��A�͂��Ⴂ�������o���āA���k�a����܂�o���ɂ��Ē����Ă���B���~�͕��f�͕W������Ęb�����Ƃɂ��Ă���̂�����A�ǂ������킯���낤���A�Ƃ����݂͕������𗧂Ă��B����ƁA�j�����k�ق��g���Ă��邱�Ƃ����������B
�u��Ȃ��A�X���W���Ă����ǂ���m���Ă�ׁv�u�ق��Ȃǂ��A�I���m��ˁB�ǂ�����Ȃ�v�u�ق���A�V����B�̂̕���ɂ�����ׁB�킽����V���̔~�̉ԁA���Ȃ��i���g�J�����A�āA�ق�A����ׂ�v�u�}�����쉹�����ׁB���b�g���߂̂��ƉS���ׂȂ��v�u�B�v
���~�͕��i���������Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ���a���݂�Ƃ���Ȃ��g����̂��������炵���A���Ƃ��狭���a����Ђт����Ęb���Ă���悤�ɕ��������B�E�E�E�E
���̖{�ɂ͐̂̐Ԑ�����̍�i���ڂ��Ă���B�O���1951�N�̊H��܌��ɂȂ莟��͊H��܂���܂��Ă���B�Ԑ��E�E�E���@���ɂ���ċւ���ꂽ�͎̂������Z���̂���A�������͏�z�K�w�O�̃S�~�S�~�����ɉ؊X�̂��邱�̕ӂ��Ԑ��n�т��ȁd�H�Ɗ����Ă��Ȃ���ʊw�̋ߓ��Ƃ��Ė����ʂ��Ă����L��������B���͓����܂����ɂ��m��Ȃ�����̒�����ӂ܂ŃX�|�[�c���N����������ł���B
���F�̊X�E�E�E�ł͂����ɕ�炷�������̂���Ȑ������甲���o�������C������ԗ��X�ɕ\�����Ă���B
�����̐��̒��ł͂��ꂪ������O�ƍl���鎞��w�i����������̂̍����̏�����ǂނƎ��ɂЂǂ��A�����Ă��ꂪ������O������������o�č������邱�Ƃɐl�ނƂ��Ă̂�����߂�����������B
[No. 583] �@�W���@�P�T��

�@�@�@�p�앶�Ɂu�c���ꂽ�Ԃ₫ �v�R�{����
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�Q�Q�N��E�@�Q�P�X�@�y�[�W�@
�E�E�E���ł����X�A�������x�Ȏ��Â��Ă�����A��������������ꂽ��������Ȃ��Ǝv�����Ƃ�����܂��B���܂�ɕa�@�����Ȃ̂ŁA���̊Ԃɂ��N�Ɉ�x�̌��f�ɂ����܂�A��Ă����Ȃ��Ȃ��Ă��āA��������X������Ă��܂��܂��B
�ł���͂�d���Ȃ������̂��A�Ō�̓��A������ɂȂ�ׂ��ꂵ���v�����������A���₩�ɉ߂������Ă悩�����Ƃ����C�������傫���ł��B���̃x�b�h�ɏオ�艺��ł��Ȃ��Ȃ����Ō�̂P�O���Ԃ́A���r���O�ɕz�c��~���Ă�����Ƃ�������ɐQ�܂����B
������͂����̎O�єL�Ȃ̂ł����A���ɂƂ��āA�e�F�Ŏo�Ŗ��Ŗ��ŁA��e�݂����ȁA���l�݂����ȑ��݂ł����B���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��ė҂����ł��B�ł�������Ɖ߂������y�������Ԃ�A�ق�ق�ł����������̂̏d�݂́A���̐��U�ł��̂������M�d�ȕɂȂ�܂����B
�����炪���Ă���Ă悩�����B�����炪�K�����������ǂ����́A����͔L������킩��܂��A���Ȃ��Ƃ����̂��Ƃ��D���Ă͂��Ă��ꂽ�Ǝv���܂��B�E�E�E�E
���߂Ĉ��L��S�������߂��݂��Ђ��Ђ��Ɠ`����Ă��܂��B���̑O�ɂ͎������S���Ȃ��Ă��܂����B�����Ĕޏ����g���T�a�̋^���������ē��މ@���J��Ԃ��Ă����B����Ȃ��Ƃ����߂Ēm��܂����B
�Q�O�Q�P�N�̏��߁A�{����܂Ƀm�~�l�[�g���ꂽ�Ƃ����̖{�͓ǂ����Ǝ��̖{�̍w�����X�g�Ƀm�~�l�[�g����Ă��܂����B���̉Ăɂ��̍�i�͒������_���w�܂���܂����̂��@��ɍw�����Ď��̓d�q���Ђɂ͊��Ƀ_�E�����[�h���ēǏ����ԑ҂��ł����B
�������͂��́u���]���Ȃ�����]����v��ǂޔԂ����d�Ǝv���Ă������ɂP�O���P�R���A�R�{��������̎����܂��T�W�Ƃ����Ⴓ���������Ƃ��m��܂����B����قǂɍ�i�ƍ�Ƃ���ɑ��ẴC���p�N�g���������L���͂Ȃ������B
���̖{�͔ޏ��̂Ԃ₫�E�E�A���ۂɔޏ����g��SNS����g���Ĕ��M�������t�����Z�ߍ��q�Ɏd�オ���Ă��܂��B�c���ꂽ��i�̐��X������͂킽�����ǂ�ł������Ƃł��傤�B
[No. 582] �@�W���@�P�Q��

�@�@�@����o�Łu���t�̂ǂ� �v�x���@�r
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�Q�O�N��E�@�Q�O�@�y�[�W�@
�E�E�E���������āA�����̔����ɑΉ����鑼�҂̔������Ȃ�����ƌ����đS���C�ɂȂ�Ȃ����A�ނ�̊Ԃɐ��_�I�Ȃ킾���܂肪��������悤�Ȃ��Ƃ́A�܂��l�����Ȃ��B����̍����Ɨ�{�́A���̎�̘b�ɗ������낤�Ƃ͂��Ȃ����̂́A���̐��E������������ł͂Ȃ��B�ނ�ɂƂ��āA�����䂤���Ȑ��E�͖ʓ|�ł��邵�A��������������B���������āA�ނ�ɂ́u���������������ɖڎw�����H���Ă��鐶���ɁA�Ȃ�ׂ��]�v�ȉ������������݂����Ȃ��v�Ƃ����v�������邩�炾�B
�ނ�́A�O�ҎO�l�ɂ��݂��̖ڎw�������𗝉��������Ă���B�Ƃ����ƁA���Q�����邩������Ȃ��B�ނ�͐��������A�l�������A�܂������قȂ��Ă���B�݂��ɗ����������ɂ́A���܂�ɂ����Ⴊ�傫������B
�ł́A�ނ���݂��Ɍ��ѕt���Ă�����͈̂�̉����H�ꌾ�ŕ\������A���R�Ɠ��S�ɋ����������̂������āA�C�t���Ă݂�C�S�������Ă����A�Ƃ������Ƃ�������Ȃ��B
��������l�����͈���Ă��Ă��A����d�˂邲�Ƃɏ�ʂ��āA�݂��d����C�����A���R�̂Ő��܂�Ă����̂ł���B�E�E�E�E
�V�V�̑��c�ƂV�T�̍��������ĂU�X�̗�{�̎O�l�͂��݂��̎U���R�[�X������Ă��Ēm�荇���ĉ�b����悤�ɂȂ��đ��P�O�N������B�����Ă��炭��@��Ȃ������̂����̏t�̒g�����ɗU���ĎU���ɏo�āA�܂����R�ɑ������Ƃ��ł����B
���c�͂��̒��Ԃł͔N���҂Ƃ������Ƃ����邪���͎Љ�S�ʂɑ��Ĉꌩ�������̂��������Ɨ�{�̓�l�Ƃ�����Ȃ��Ƃɂ͖��ڒ��A�����Ď������̐����������H�����̐�����搉̂��Ă���B
���̍��Z�̃N���X���[�g�̍�i�ł��B�ȑONo.329 �u�R�Ƌ��v��ǂ܂��Ă�������ȗ��A�ŋߍ�����]�����Ƃ��낱�̍�i�𑗂��Ă����B���������̂Â��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����E�E�E�Ƃ����B�s�f�̍E�E�Ƃ����ɂ͂Ƃ����ɉ߂��������l���ł���B
�l�ނɂƂ��Ă��݂����łɂW�O���Ă������ɐ����鉿�l�����o�����Ƃ͍���������Ȃ��B�܂�ɂ킩�d���Ẳ��l�ςɂ͖�����������E�E�E�E�A�P�O�N�O�̏����ȋC�����̍�i��҂������B
-1-�@-2-�@-3-�@-4-�@-5-�@-6-�@-7-�@-8-�@-9-�@
-10-�@-11-�@-12-�@-13-�@-14-�@-15-�@-16-�@-17-�@-18-�@-19-�@-20-�@
[No. 581] �@�W���@�@�R��
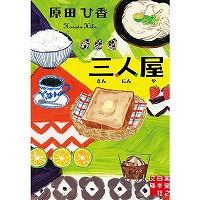
�@�@�@���ƔV���{�Ёu�O�l�� �v���c�Ѝ�
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�W�N��E�@�Q�T�W�@�y�[�W�@
�E�E�E�����͎v���B�l�ƌ����̂́A���Ɩ�Ƃł���Ȃɕς����̂��ƁB����A��l��l�̐l�Ԃ͂����ς���Ă��Ȃ��̂��B�F�A�悭�m���������ł���B�Ȃ̂ɉ������Ⴄ�B�����ɉc�Ƃ��Ă������ŁA����́u�����v�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă����B
��̒j�����́A�ق�̏����������߂��B���ڐG���Ă���A�Ƃ��ł͂Ȃ��B�����A����܂Ŕ��a�ꃁ�[�g���ȓ��ɂ͓����Ă��Ȃ������l���A���a���\�܃Z���`���[�g�����炢�܂œ����Ă���B�������̓�\�܃Z���`���ǂ����Ⴄ�B
����Ɏ����Ƃ܂Ђ�͂܂�����Ă��Ȃ��B����Ă��Ȃ��ǂ��납�A�܂��������̋�����������ł��Ȃ��B���͂܂��A�ނ�͌������Ă��Ă����B���������������Ă���ƌ�������O�A�h�����邵���Ȃ����낤�A�Ǝv���Ă���̂�������Ȃ��B
�ł��A���ꂪ���܂ő����̂��B���܂ʼn䖝���Ă����̂��B�����ɂ͕�����Ȃ��B�E�E�E�E
�V�h���琼��15���قǂ̎��S�w�̏��X�X�Ɏb���X���Ă����i���X���ǂ����܂��ĊJ�����l�q�������B�ӂ����������X�����j���[�A���Ɍ����Y��Ɋ��荞�܂�ĊŔ��������B�u���E�W���[���v�A���͖����̒������o�c���鑁���i���A���͎����܂Ђ�̌o�c���邤�ǂA�����ė[���ɂȂ�ƒ����錎�̌o�c����X�i�b�N�ɂȂ�B�ޏ������͕��ꂪ�c���Ă��ꂽ��Y�Ƃ������ׂ��i���X�����ꂼ�ꂪ�����p�������Ǝ咣���āE�E�E�������A���݂����Ȃ�s���̎o���ł������B
�������ʂ��Ă������Ƃ͍��͖S�����e�����y����o�ăs�b�R���̑t�҂Ƃ��Ċy�c�ɓ����ĉ��t���Ă����Ƃ��d�̕����`�Ăł����Ȃ��������ւ�Ɋ����Ă����B
���͒j�O�Z��̖����q�ň炿�܂����B���������̐��i�͎O�ҎO�l�A�������_��������������ł͂Ȃ��������Ǝv���܂��B�����������ɓo�ꂷ��O�o���̂����܂���w���̎O���ȊO�݂͂Ȓj�Ƃ̉��ɕs�K���t���܂Ƃ��Ă��܂������ł��B�ł����h���Ă������e�����ẴN���X���[�g�ƌ����j���X�Ɍ���Ęb�������e���ɋ^���������B�����ŕs���ȎO�o�������������������Ă����E�E�B�ʂɕs���ł͂Ȃ������ł������̎O�Z����e���̎������������ɂ�����J�𑝂����L�����V�����B
[No. 580] �@�V���@�Q�W��

�@�@�@�V���Ёu�I�̏Z�� �v��茛��Y
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�Q�N��E�@�P�R�P�@�y�[�W�@
�E�E�E�h�A���J���Ȃ�A�ނ͍ȂƖ��Ɍ������ċ��B�u���߂����I�Ƃ����Ă邼�I�v�B�Ȃ͗��������Ă����A�ނ̑S�g��^���ʂ��猩�����A�ڂƌ����ł������Ɣ��݂Ȃ��牞�����B�u�����ˁA�������낻��A�������������ˁv
����͂܂�ʼnƑ��ŗV���n�֍s�����̂�������ł��邩�̂悤�ȁA�\��N�Ԃ����Ƃ��̉����̒��ɗ��܂葱���Ă������̂悤�ȁA���炩�Ŏ��R�Șb�����������B�������̂̍�����A�����܂������Ȕ��͂ЂƂɂ�������A�����Z�[�^�[�ƃx�[�W���F�̃X�J�[�g�͍אg�̑̂ɔ畆�̂悤�ɓ\����Ă����B
���ς��܂��������Ă��Ȃ��A�f��̂��̂����ς�Ƃ����������͉����������i�����Ă���悤�Ȉ�ۂ�^�������A�����ɖ����߂������낵���������������B���̖��͂ɋ��������Ō�A�Ȃ������𑗂鉓���ٍ��ւƘA�ꋎ���A��x�Ƃ͖߂��Ă���Ȃ���������Ȃ������B
�������ނ̌��S�͂����ς��Ȃ������A�ǂ����Ă��Ƃ͌��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�E�E�E�E
�ނ͂������̑O�̓��{�l�̃T�����[�}���̓T�^���ƍl���Ă݂܂��B���̒�ӂ͒j�����ڂƈӎ������ɂӂ�܂��Ă����ƒ�d���邱�Ƃɑ��閳�\�����@���ɐF�Z�������܂��B
�������ɑ傫�Ȏd������萋���ďd��ȉ�Ђ̏d�ӂ��ʂ����ĉ䂪�Ƃɖ߂��������߂Ė������Ȃ��Ȃ��Ă��邱�ƂɋC���t�����B�u���͍��A�A�����J�ŕ�炵�Ă�̂�E�E�v�ƍȂɌ����Ĝ��R�Ƃ���B
�Ⴂ���ɂ͌����Ă���Ȃ��Ƃ͂Ȃ������̂ɍ��ł͊K�i�̑�����[�z������̂��D���ɂȂ��Ă��܂����B�����Ė����Ȃ邱�Ƃ��N�Ƌ��ɋ��܂��Ă���B�͂邩����������������Ƌ߂Â��Ă��鎀�Ƃ����W�ł͂Ȃ��悤�Ɏv��ꂽ�B
[No. 579] �@�V���@�Q�S��

�@�@�@�V�����Ɂu�Ƃ�̒� �v����@��
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�Q�R�N��E�@�Q�T�P�@�y�[�W�@
�E�E�E�ӂƁA���̃��{������Ɋ����t���ēV�䂩��Ԃ牺��������ǂ��Ȃ�̂��낤�A�Ƒz�������B���̒��ɂ́A���炪����̈ӎu�Ŗ����I��点���i�����邱�Ƃ������Ă��ꂽ�̂����ꂾ�B
�ł��A�킽���ɂ͂ł��Ȃ������B���A���������̂ɁA���̃��{���ł͗���Ȃ�������B���̃��{���͍��A���̐l���ɉ��̖��ɂ������Ă���Ȃ��B�ŁA���̏�ɓ|�ꍞ�ށB���������Ȃ��B�߂�������ǁA�����̓S�~���~�Ȃ̂��B�킽�����g���A���̂��݂̈ꕔ�Ȃ̂��B�����v���ƁA�����Ȃ���ɂ��āA�̂̒[���畅���Ă����悤�Ɋ������B
���s�͏������L�����āA���������̂��ׂĂ��s�����Ă��܂��B����ł��킽���́A�ꂳ��Ɏ̂Ă�ꂽ�Ƃ͔F�߂����Ȃ������B�킽���͂܂��A�ꂳ�A���Ă��邱�Ƃ�M���Ă����B�����āA�킽���̕ꂳ����B�킽���ƕꂳ��́A�i�Ƃ�̂����j�Ō���Ă���̂�����B
�ӎ��������낤�Ƃ���B�ŁA�����āA�̂������������ɂȂ�B�����ǁA�ꂳ��Ɖ�܂ł͎��˂Ȃ��B���ꂾ���́A�킽���̐S�̒��ł͂����肵�Ă���B�E�E�E�E
�Ƃ�E�E�́A���l�Ɉ�Ă��Ă����B�Ƃ�E�E�͐��܂���ڂ������Ȃ������B�����ĕꂪ�����ɍs���Ă��鎞�͌����ĉƂ���o�邱�Ƃ����Ȃ���������K�̑����犴������납�畷�����鏬���̂���������y���݂ɕ�炵�Ă����B
�������Y���ĕ���̖{��ǂ�ł��ꂽ��A������ˑR�ꂪ�A���Ă��Ȃ��Ȃ�B�Ƃ�͐H�ׂꂻ���Ȃ��̂������Ȃ���T��ŕK���ɂ������ĒT���Ă������A�P�O�̂Ƃ��̂��j���ɂ�������i�̃��{������ɐG�����B�������A�Ƃ�͏��߂Ĉ�l�Ō��ւ��J���ď��������߂��B
�Ƃ�͎{�݂Ɉ�������c���\�a�q�Ɩ��������ēƂ藧������P���ɗ�ށB�����Ď��͂̏��������\���߂��Ă��邱�Ƃ��m��B������{�݂���ӓ����̃W���C��������B�����Đ������т���w�[�߂Ă����B
���̏��ł͂Ȃ���e����������E�E�ƌ����悤�Ȕƍ߂߂������ƂɂȂ������͖��炩�ɂ���Ă��Ȃ��B�Ӗڂ̏����ł����Ă������悤�Ƃ���ӎu�ɂ���Ė��邢�������J���Ă�����]�̖��J�������������Ă����̂��~���Ɋ������B
[No. 578] �@�V���@�Q�S��

�@�@�@�֓��}���u�a�@�� �v����ӌO
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�P�X�S�R�N��E�@�V�W�@�y�[�W�@
�E�E�E�u���������ād�d���݂����Ȏ҂ɂ������o����d���������ł��傤���v�ނ炪��z�O�������悤�ƁA�Ƃ����͓���U���Ċ���グ���B
�łȂƁA�F���͂�����ƍl����悤�ɂ����B�݂�Ȑ��d���ł��Ԃ̑f�l�ɂ͎�������̂��肾���A�e��Ƃ肭�炢�Ȃ���Ȃ����Ƃ͂Ȃ����낤�B���̎�Ԓ����Ȃ��Ȃ��n���ɂ͏o���Ȃ��̂ŁA���Ƃ͈�і�œ�K���x�ł����������݂ł͏\��A�O�K�ɂ܂œ����Ă���Ƃ����F���ɁA�Ƃ����͂��낢��Ɛu���͂��߂��B
�����y�g����������Ă��āA���������y�Ȏd���Ƃ͎v��Ȃ��������A�܂��d���̐h�������낵���̂ł��Ȃ������B���ʂ̔_�Ƃ������猩�������̂����A�F�ڏ���̒m��Ȃ����Ƃ̂Ȃ��ɂƂэ���ŁA�܂�Ŏ�o���̂Ȃ�Ȃ��g�̂�����ɂ����鎩���ɂȂ肻���ȋC������̂������B
�����ƂƂ����Ώ��葺�Ɍ����Ă��āA�����ł͐�Ɏ���o���Ȃ��Ƃ������Ƃ�����Ƃ����͉�������ݓ����Ȑ�����z��������ꂽ�B�E�E�E�E
�������A���݂̓�{���s�x�O�A���k�{�����B�w���瓌�ɂS�q�قǂ̎R�Ԃɂ�����葺�͏��a�����ɂ͘a���̐��Y�����Ȃ萷��ŕi�����ǂ������B�c���̎d���̍��Ԃɗ{�\������ł͂��������������̕��Ƃ͂����ς�a���̐��Y�ɏ[�Ă��Ă����B
���ӂǂ��ł��a���̐��Y�͏o�������Ȃ��̂ł��邪�A���Ƃ��炱�����葺�łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��������R�������ċ�����Ό������A�g�������ނ悤�ȗ₽�����Ɏ��Z����������E�ϗ͂��������Ƃ������Ƃł��傤�B
����E���̍Œ��A����ȎR���ɂ����̐�ЂƂ������ׂ������ɑ����̐l�o�����ꎟ�j�̑y�g������A�����ĕ��@���Y���v���A���ɓ�����ł��������j�F���܂Œ��W���߂����ĉƂɂ͏������c��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
�ӂƌ��������펞�����̐��܂ꂽ���a�P�V�N����̊H��܍�i�ɏ��荇�����B�Z�҂̊��ɂ͑吨�̓o��l�������Ă��̊W�}�����Ȃ���ǂݐi�B�n���������̂Ȃ��ɂ��L���Ȑl�Ԃ̉c�݂�����������G��ł����B
[No. 977] �@�V���@�P�V��

�@�@�@���w�فu���@�� �v�R�{�b�m
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�O�V�N��E�@�S�W�T�@�y�[�W�@
�E�E�E���Ƃ����āA�J�Ђ�\����������Ƃ����ĕ����Ƃ��v���Ȃ��B�ٔ��ɂȂ��Ē���������̂͌����Ă邵�A�g���S���{���{���ɂȂ邱�Ƃ��o�債�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����܂ł̏��f�͊Ԉ���Ă��Ȃ��ƁA�F��]�͎v�����B
����܂ŗL���Ȏ�i���l�������Ƃ��ł����A�ǂ��߂�ꂽ�C��������Ă��Ă����̂����A���e�Ƃ������@�Ɏv������A�}�Ɏ��E���J�����悤�ȋC������B��A�̏o�������������߂ĐV���ɓ��e����̂��B�v���]�[�ǂœ|�ꂽ�B
��i�́A�����̎d���ʂ⌒�N�ɗ��ӂ��闧��ɂ������̂ɂ����ӂ����B�v���������ł��邱�Ƃ�s�����ł��鎖���m���Ă����ɂ�������炸�A��i�͐ӔC����̂��߂ɘJ�Ђ̐\��������Ȃƈ��͂������A���̈���ŕv��������悤�Ɖ��u�n�̔��Ⴂ�̐E��ɔ�����Ƃ��Ă���B
���Ƃ̐^�ӂ�q�˂Ă��A�̂�肭���Ƃ��킳��āA�ٓ���ɂ��Ă����Ƃ��������Ă���Ȃ��B�������A���T�J�ɂ��Ă��Ƃǂ�Ȗڂɑ���������Ȃ����ƁA���ɋ������ꂽ��������B���T�J�̌����ȉ����߂����[�[�[�B�E�E�E�E
������Ѓ��T�J�͑n�Ǝҏo�g�̔���s�ɂ����Ă��̔ɉh���炵�Ă����������̉�Ђ̏鉺���Ƃ����l���ł���B���������̌o�c�p���͑n�Ǝ҈ꑰ�Ɉ����Ă��Ċ�Ƒ̎��Ƃ��Ă͓�������s�����o�n�߂Ă����B
�ɍ蕶���͂��̎Ђ̌�������̉ے��E�Ƃ��Đ��i�̊������P�̂��ߓ��镔���̐擪�ɗ����Ċ�����ڎw���Ă����B�������c���ɔ]�[�ǂ��N�������@�����B�����Ă��̌o�߂��炵�Č��̐E�ɕ��A�͓�����E�E�ƂȂ������A��Њ������炻��ƂȂ��Ȃ̗F��]�ɂ͊֘A��Ђւ̓]�����ɂ��킹�Ȃ��������̕a�C�ɑ��ĘJ�Ђ̐\���͂��Ȃ��悤�Ɂd�Ƒ����ꂽ�B���ėF��]���g�A�����ƌ�����������Ђ��狭���Ɏ��ގЂ���悤�Ɍ����Ă��ė��s�s���������Ă����B
�F��]�͓��e�Ȃǂɂ��n���V���ЂȂǂɑi���������Ƃ��ƃ��T�J�����Ă̒n�������Ƃ������Ƃ��v���m��B�����Ď��X�Ə�w���A�o�c�w�ɑŌ���^���悤�Ɣƍ߂ɂ�����肻���Ȏ���ŕ��K���Ă����B
���̍�i�͂Q�O�O�V�N��Ƃ����܂��B���ł����e�n�ɖh�ƃJ�����������đ����ȕ��y�Ŕƍ߂̌����ɍv�����Ă���B������Ƃ���Ȏ���ł͌��݂ɂ͒ʗp���Ȃ���ȁE�E�Ǝv���B���������̎��O�̕������̈�[��`�����C������B
[No. 576] �@�V���@�P�O��

�@�@�@�u�k�Ёu���A���̂��Ƃ� �v��ǂ䂤
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�Q�Q�N��E�@�S�S�P�@�y�[�W�@
�E�E�E�\���̂킽���ɁA���q����͂����������B�[�[�[�����Ŏ�����{����A����͐l�������čs����ł̍Œ���̕���ł��B������o�Y�Ƃ������̕ω��ɔ����Ĉꎞ�I�ɂ��܂��Ă������B�ł����ł����o����悤�A�����e�͂��Ă����ׂ��ł��傤�ˁB
�����ƂȂ�Γ�����B�ǂ��ɂł���ї��Ă�B�Ɛg���낤���������Ă��悤���A���̏����������Ȃ����Ől��������Ă��܂��B�O�\��̂킽���ɁA�k���搶�͂����������B�p�[�g�i�[�����Ă����Ȃ��Ă��A�q�ǂ������Ă����Ȃ��Ă��A�����̑��ŗ��Ă邱�ƁB
����͎�������邽�߂ł�����A�����̎コ��N���Ɍ����肳���Ȃ��Ƃ������Ƃł�����B�l�͌Q��Ő����铮��������ǁA���������ƈˑ��͈Ⴄ����[�[�[�B
�u������A�m���Ɏ��ɂ͎q�������Ȃ��B�ł��e�͂���B������q���Ƃ��Ă��肢���܂��B���ʋ����Ȃ��Ă�������A���߂Ďq���ɗ]�v�ȉו���w���킹�Ȃ��ŁB�����ł���������ו��������Ă�������A���ꂭ�炢�̑�l�ł��Ă�v�E�E�E�E
�{�B�Ǝl�������ԘA�����̂����L�����ƈ��Q�������ԓ��X�͎��Ӎ��킹���2�`30���̓��X���_�݂��钆��6�̓�������ʼn����ł���B���������̓��ɂ��Ă��̂���̕��K�͖����Ȃ�Ȃ��B�u����A�N���ꂳ��ƒN���ꂳ��͂ł����悤���E�E�v�Əu���Ԃɓ����ɒm��n���Ă��܂��B
���Z��N���̈��ŊC�͓ޗǂ���]�Z���Ă�����W�D�Ɨ��l���m�ɂȂ������u���Ԃ̓����̎����Ƃ��ĔF������Ă��܂����B�������D�̕�͂��Ƃ��Ƃ��̓��Ɏd���ňڂ�Z�j��ǂ��ė��������A������͌��̂Ă��Ă��܂��^���B
����D�̓l�b�g�Ŏ����̐��삵���\�����G�ɂ��Ă���钇�Ԃ������Ă��łɑ��Ƃ��邱��ɂ͂����ς��̗L���Ȗ��搻��҂ɂȂ��Ă����B�D�͑��Ƃ��ē����Ɉ����z���A�ŊC�͕�����̓��Ō��Ȃ��Ắd�Ǝb�����������������Ă������E�E���݂����ł�32�E�E�B
�������������V�C���������̂ň��S���ēǂݎn�߂����ҏ����A�ǂݏI����Ē�ɖڂ����Ƃ����~�J�����̐�B�E�E�����I�H�A�܂��~�J�����錾�͂��Ă��Ȃ������́B
[No. 575] �@�V���@�@�R����

�@�@�@�u�k�Ёu���̐��̊�т� �v��ː�ˎq
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�Q�Q�N��E�@�P�R�W�@�y�[�W�@
�E�E�E���Ȃ��͔w���ŁA����s�����X�[�p�[�K���Ŏ��}�b�T�[�W���v���o���Ă���B����l���s�������Ƃ����̂ŁA�^�I����召�ꖇ���e�X�����Č��������B
���Ȃ��͖{���͗��𖺂����Ɍ�����̂́A�p�����������猙�Ȃ̂��B�C�͂������Ȃ��̕����������B���̖��̕��������傫���A��̖��͂ȂŌ����A���ɂ͎o���Ȃǂ��Ȃ�����ǂ������A���Ԃ��̂��Ȃ����S���Ƃ��Ȃ��͎v�����B
�I�V���C�̓��C�͖��邢���ւƐi�݁A���ƏƂ�z�����ʂɕz�̂悤�ȃV��������āA���̕����̂ɉf�����B�u���̐l�݂����ɂ��킢��������A���Ďv�����Ƃ��āA�܂����ꂳ��ł�����H�v
���ʂɂ������̎q�����D����o�Ă����ƁA���̖������������A���ꂪ����́A�Ƃ��Ȃ��͌����ď����E�E�E�E
��ꂳ��͂���50���炢�ł��傤���A�p�[�g�ŋߏ��̃V���b�s���O�Z���^�[�̑r�������œ����Ă����B���̌������ɂ̓Q�[���Z���^�[�������āA�ߍ����̏o������ɋ߂��Ȃɂ����̏����������Ă����B���������Ă݂��15�̒��w���ƌ����B
�ǂ����Ă�������ȂƂ���Ɂd�Ɛq�˂�ƍŋߒ킪���܂�Ă��̎q�̖ʓ|������悤����������̂ł��������邽�߂ɂ����Ŏ��Ԃ��Ԃ��Ă���E�E�B
��ꂳ��͂�����������q��Ă̂���̋��►�����̒��w������������̋�Y�͂�������Y��Ă��܂����B�������Q�[���Z���^�[�̏o������ɂ��������ɐ��������邱�ƂŖ���������Ă���т������яオ���Ă���C�������B
���̍�i�̕��͂��Ă���������I�B���̏����������Ă���l�͒N�Ȃ́E�E�H�B�ǂݏI����Ă���n�b�Ƃ����A���̖{�̃^�C�g���E�E�͕�ꂳ��͋C���t���Ă��Ȃ��B��ː삳��͂����v���Ă����ē�l�̗̂��ꂩ�珬���ɂ����B�Y���C�I�B
[No. 574] �@�U���@�Q�U��

�@�@�@�V���Ёu�r��n�̉Ƒ� �v�������u
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�Q�Q�N��E�@�P�V�Q�@�y�[�W�@
�E�E�E���C���������̂͌[�������S���Ă����A��ԊÂ������O�Ƃ����N�̍��������B�Ӕт�H������ȂǁA�[���͕�̓�����k����낤�Ƃ���悤�ɍ��z�c��~�����̈֎q�ł��炤��ƋC�����悳�����ɂ܂ǂ��ł����B
�ŋ߁A�[���ɋ��������ꂽ�B�\��炵���S�̕ω��Ȃ̂��A�č�����̒m���q���Ƃ��o�������Ŗ����ɓ��h�������Ă���̂��A�C���͒m��悤���Ȃ������B�����̊Ԃ܂Ō[���͏�����{�����肵�Ȃ���w�Z�̗l�q��b���Ă��ꂽ���A�ŋ߂́A�b�������Ă��B���ɕԎ������邾���Ŗق��Ă��܂��B
����܂ōD�����������̂��������Ƃ����A���Âɉ�������A�ނ���ƍǂ����肢�������C����Y�܂����B�N�����̐V�����S�̑��ʂ̕\��ɁA�C���͗]�v�Ȃ��Ƃƒm��Ȃ��玩���ɋN��������̂�T�����Ă悤�Ƃ���B
�����Ď����̂������Ɛi��Ŏv���Ⴂ�����āA�������Ă��Ƃ肪�M�N�V���N���Č[���Ƃ̋������L����B�E�E�E�E
���C���̉Ƒ��͂��̓����{�̍ЊQ�����z���Q�N�قǂ��ĐV���ɑ����Ƃ̎d���𗧂��グ����悾�����B�C���͉Ƒ��̂��߂ɂƐg�ɂ��ē����Ă�������Ȑ܁A�Ȃ̐��C�̓C���t���G���U��X�点�č��M���o���A��ʐl�ƂȂ����B
�������̍ЊQ���Ȃ�����������Ƃǂ��ɂ��Ȃ��Ă����̂Ɂd�Ƃ����z���͗C���̎��͂̓������Ɍ��炸�ǂ������ɂ����݂��Ă��Ăʂ�������Ȃ�����̎v���͊��N�����Ă������邱�Ƃ͂Ȃ��B
�V������̍�����`���[�n����H���Ă����[���͗C���̋A���Ă���������ėC���̓����w�����ăQ���Q���Ə��o�����B���ʏ��ɍs���ċ�������ƁE�E�E���̖сA���сA���݂����E�E�����Ђ��܂ł��^�����������B
�Ō�̐��s�̌��t�̒��ɖ�X�Ƃ��ĉ߂����Ă����C���̋�Y�Ə����͐S���J���Ă��ꂽ���q�A�[���Ƃ̊ԂɃt�b�ƐS��ʂ킹�Ă������̂����������Ƃł��傤�B
[No. 573] �@�U���@�P�O��

�@�@�@�p�앶�Ɂu�̂̂͂ȒʐM �v�O�Y������
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�W�N��E�@�T�O�S�@�y�[�W�@
�E�E�E�ł��ˁA�̂́B���̖{�S�������A�������Ƃ������̂��Ȃ��́B�������͂��ׂāA���Ȃ��Ƃ̗��Ŏg�������Ă��܂����B������A�v�ƃZ�b�N�X�������Ă��A�u�܂��������v�ł��܂�����B
�����q�ǂ�����Ȃ��̂ŁA�R����悤�Ȍ���������������ł͂Ȃ���A�����ƒm���Ă��܂��B�v�Ǝ��̂������ɂ́A�������₩�ŐÂ��Ȉ����������ɂ���B���ꂱ�������Ƃ����̂�������Ȃ��Ƃ��v���B�����ǁA���̐S�̉���ɂ͍��ɖ����ꂽ��Ղ������āA�����₽���������������Ă���B
���܂��͂��܁A�������e���ȉƂŁA�g�F�̉ɓ������Ă���B���̂����������A���䂳�ꂽ���������Ǝv���������Ƃ��Ă���B�����A�{�����H���܂��͖{���́A�킩���Ă���͂����B���܂����S�̉���ɒ��߂����A���܂��ՂƂȂ������̋L���������A���܂��̐��ɂ����Đ^���́A�����ЂƂ̂��̂������̂��ƁB���܂��͂��܁A�K���Œg�F�ɐd�����ׁA���Ƃ������₳�ʂ悤�w�߂Ă��邪�A�{���Ɏ���������ׂ����̂��������̂́A��Ղɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��������̂́A���܂��̂Ȃ��Ŗ���ɂ����A���܂⍻�܂݂�̈�
�܂莄�Ȃ̂��ƁA���܂��͖{���ɂ킩���Ă���B����Ȑ����������Ă���̂�B�̂̂̐��H����Ƃ����̐��H���Ă̎������̐��H�킩��Ȃ��B�킩��Ȃ������ǁA�Ƃ����̐̂ɏI����Ă��܂������Ă��Ƃ����͕�����B�E�E�E�E
�����̏@���n���q���̓�N���ɂȂ������듯�����̖�X�����Ɩq�c�͂Ȃ͋��������������ƂɂȂ肨�݂��̐S����莆�Ŋm���ߍ����Ă����B���̂����Ɍ��������߂����悤�ɂȂ肤���������̓�l�E�E�E�H�Ƃ����\�܂ŗ��Ă���قǂ܂łɂȂ��Ă��܂����B
����������Ȏ��������������̂̂������ӂ���̊Ԃɕs�M�����萶����w�����ꂼ��̓���I��Ő��l���Ă������B���łɂQ�O�N�ȏ�o�߂��ċ��R�ɂ��A�t���J�̖^����g�v�l�ƂȂ��Ă����h�͂ȁh�ƎG���L�҂Ƃ��ĉ߂����Ă����h�̂́h�̓��[���ŋߋ�����������ɂȂ����B
�O�Y������̍�i�͂���܂łT�`�U��i�͓ǂ�ł��Ċm���ȓy�䂵�����肵����i�\���A�Ŏ��ɂƂ��ĐM���ł����Ƃ���ł����B�����č���͒����҂̖{��i�ɂ�����ْ����ēǂݎn�߂��B�ӂ���̎������q���̓��������m�����Ɋׂ����̂��Ăѐl���̐ܕς��n�_�ō��x�̓��[���ł��݂��̐S���f�I�������B�������藊��ꂽ�肵�Ă����P�O��̗��������S�O��ɂȂ肻��Ȃ�̐c�̂���l������ޏ��̂܂�������������Ɏ��߂Ă���B
�c������̎莆�̂���������d�q���[���Ő��E�̉ʂĂł��ӎv�̑a�ʂ��ł��鎞��ɂȂ��Ă����B����Ȓ��łӂ���̏�������l�ɂȂ��Ċ��������z�͂܂����݂��c�������ˁB�����Ƃ��ł��B
[No. 572] �@�U���@�@�U��

�@�@�@�V���Ёu �����̂悤�ɂ���₩�Ɂv���c�@��
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�O�V�N��E�@�R�P�T�@�y�[�W�@
�E�E�E�����Q�Ă����̂́A����K�̉��̋��������������B���X�͔[�˂������炵���A���낢��Ȃ��̂��u���Ă����āA���ɗ^����ꂽ�X�y�[�X�͂����킸���������B�q���̕z�c���ꖇ�~���̂��������ς��̃X�y�[�X�����Ȃ������B
�K�R�I�ɁA�ǂɂ������ĕz�c��~���A�����Ŗ��邱�ƂɂȂ�B�q�ǂ��͋����ꏊ���D�ނ��̂Ȃ̂ŁA�����͋�ɂł͂Ȃ������B�ނ���A�z�c�ꖇ�̃X�y�[�X�����C�ɓ��肾�����B�������A���ӂ��̕����Ŗ��邤���ɁA��Ȃ��ƂɋC�t�����B
�s�v�c�Ȑ����悤�ɂȂ����̂ł���B�ǂɂ͑傫�ȃJ�����_�[���\���Ă������B�����ǂ��B�����߂������̂��낤�B������v�����Ă߂����Ă݂���A�����^���̕ǂ̈ꕔ���͂���Ă��āA������ǂ̂悤�Ȃ��̂������ނ��o���ɂȂ��Ă���A�������琺���������Ă���̂��ƋC�t�����B
�b���Ă�����e�܂ł͕������Ȃ��������A���ꂪ�j���̐��ł��邱�Ƃ͕��������B���̒��q����A�ǂ����閧�߂����A�Ђ��Ђ��Ɨ}�������ł���B�m���Ă��鐺�ł͂Ȃ��B�����ƁA�悻�̉Ƃ���ǂ�`����ĕ������Ă���̂��낤�B���͂ǂ��ǂ������B�E�E�E�E
�l�Ԃɂ́u�ǁv�Ƃ������̂ɋ��������������Ă���̂ł͂Ȃ��낤���E�E�E�����튯�E�E�E���ǁE�E�E���̏����ł��u�ǁv�Ɋւ���lj������X�ƘA�z�����B�g�����y�b�g�t�҂Łu�������v�������ɉ��t����V�˓I�t�҂������B
�c�����̒lj��̒��ɕǂ̒��ɔ����o���ɂȂ��Ă����ǂ����l�̔�ߎ��̂悤�Ȑ����`����Ă��邱�Ƃɑ��ċ��������B���̐��͉������畷�����Ă����̂��d�����ĒN�̐��Ȃ̂��܂ł͕�����Ȃ����������ɑ�����̃A���\���W�[�����L����B
���܂ʼn��c������̍�i�͂���������ҏ����łR��ǂ�ł����B����͂P�S�ҒZ�ҁA���������̂ǂ�����~�X�e���[�A�I�J���g�A�h�L�������^���[�^�b�`�̊�Șb����ł����B�ނ̍�i�Ȃ̂ň��S���ēǂݎn�߂ēx�̂����ꂽ�B
���߂Ă��̒Z�҂�ǂݏI����ĈȑO�ɓǂ��ҍ�Ɣ�r���āu�A�b�I�I�E�E�v���Ƃ��������B���V��Ȗʔ�����i���I�u���[�g�����ăG�L�X�������ׂ�Ƃ���ȍ��g�݂������̂��E�E�E�B����`�Ǐ����ĉ����[������ł��ˁB
[No. 571] �@�U���@�@�Q��

�@�@�@���~�Ɂu ���̂��̒�ԏ�v��@�ǎq
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�Q�O�N��E�@�R�U�U�@�y�[�W�@
�E�E�E�u�ݑ�Ŏ���O��Ɏ���ň�Â��s���Ȃ�A�Ƒ��ƈ�Î҂��I������Âׂ̍������j�𗧂ĂĂ����B���̕v�w�Ƃ́A���x�������b�������̂����c�v�u���Ⴀ�Ȃ��H�v��C���������Ԃ��������Ɍ���B
�u�������Ȃ����ƂɁA�ς����Ȃ��Ȃ�̂��������v���̍�a�q�ɂ͕�����B������S�x�h����l�H�ċz��g�p�̉ۂȂǂ̍זڂ�b�������āA�ݑ�̕��j���v�����j���O���Ă������Ƃ��Ă��A���ۂɉƑ������Ɍ������ĕω�����p��ڂ̓�����ɂ����Ƃ��A���O�v�����̒��g�ȂǂƂ������͎̂��͂̐l�X�̓����琁�����ł��܂��B
�����̏ꍇ�A����Ăӂ��߂��ċ~�}�Ԃ��ĂсA�~���~�}�̃v���Z�X�ɏ�邱�ƂɂȂ�B�u������l�̎����܂��F�߂����Ȃ��[�[�[�����������ƂȂ�ł��傤�ˁv
��a�q�̌��ɁA���͑傫�����Ȃ������B�u���̌��ʁA�h�����Â≄�����Â��{���ꂽ����A�]�܂Ȃ������ꏊ�Ŏ����}���邱�Ƃ�����B�����䂤���Ƃ͂ˁA�ݑ�ł͂Ƃ��ɋN���Ă��܂���ȁB�ŁA��a�����A�a�@�ł̗l�q�͂ǂ��������H�v�E�E�E�E
�����̋~���~�}�Z���^�[�ŕ������߂Ă�������̔���a�q�U�Q�B�Ƃ��邱�Ƃ�����ӎ��C�����Č̋��̋���ɋA�Ȃ����B������t���������͂��łɈ��ނ��Ă��������̊��߂������Ĕޏ��̐�y����t�̍ݑ��ÃZ���^�[����`�����ƂɂȂ����B
���܂ŋ~�}��ÂŐ����̋��̊��҂�@���ɐ����������Ă����v���ƍݑ�I����Â̈�Ís�ׂ̃M���b�v�ɒ��ʂ��傫���Y�ށB�����������̖������ɂ݂̊ɘa�P�A�[����Ɍ��������y����]�܂�邱�Ƃɂ��Ă��傫�ȔY�݂����B
�Ƒ��̍Ŋ���ڂ̑O�ɂ��āu������̂ł���ł��邾���̂��Ƃ����Ăق����E�E�v�ƁE�E�B����͎��Â����Ď���ړr������̘b�ł��B���̈�ËZ�p�������Ă��������������Ί��ł��������Â��{�����Ƃ͕s�\�ł͖����炵���B��������͂���ێ����u�ɂ�����߂ɂȂ��Đl�ԂƂ��Ă̑����������Ȃ��B����̂͐�������Ă��鑸�������B
����ԈႢ�Ȃ���Â̑傫�ȉۑ�ƂȂ�u�ݑ�ł̏I����Áv�B�Ȃ̍Ŋ��ɒ��ʂ������Ƃ̂��鎄�͍Ȃƈ�t�Ǝ��ōݑ�̃v�����j���O�����{�����B����͎���ŐÂ��ɍŊ����}����E�E�����čȂ͍Ō�܂ő������������̎�𗣂�Ă������B
[No. 570] �@�T���@�R�O��

�@�@�@�u�k�Ёu �t�Ƃ͂Ȃv�Ό��T���Y
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�P�X�U�T�N��E�@�T�U�P�@�y�[�W�@
�E�E�E�u�m���ɌN��̗�����Ă���e�����ɏ��F������͓̂���B�������悸���ꂪ�o���Ȃ��Ăǂ����ė����̊���������B�e�͑��l�ł����Ă�͂�e���Ƃ������Ƃ�Y�ꂿ��Ȃ���B�N�炪���K�v�Ƃ���E�C�́A����ȏɑς��A�����������������Ă������Ƃւ̗E�C���v
�u�͂��A�ł��A�ǂ�����Ă�����������炢���̂��v�u����A���ꂾ�ȁB����ɂ��Ă͉����ł������͂ɂȂ낤�B�m�b���݂�������Ȃ����B�Ƃɂ����A������̗����Ɋւ��āA��łȐe��������ĕς��邱�Ƃ��ł����ɁA���̒��̑��̂��Ƃ�V�����ǂ��ς�����Ƃ����B�E�E�E
�ʂ������ăA�����J�łP�O�N�߂�������X������͉���������S���̍����w�Z�̉p�ꋳ�t�ɂȂ����B���������̊X�͎�҂��N��肽�����܂����̊w�Z�̐搶�������Â��l���ɔ���ꂽ�NJ���t�̊w�Z�������B����͂܂��p��̎��Ƃ��炵�ċ��ȏ����炸�ꂽ���p�I�Ȃ��̂ɂ��悤�Ƃ��������t�����甽����H�����B
���������Ԃ������Ă܂����k�̐S���J�����A���t�̒��ԓ�������x���҂�悤�ɂ��A���ɂ�PTA��ʂ��Ē��̌Â��l�Ԃ����ɊJ���ꂽ�𗬂𑣂����������o���Ă����B�����ɐt�Ƃ͂ȂE�E�ƌ����Ӌ`�����o�����Ƃ���B
�܂���i�������Â��Ό�����̑��z�̋G�߂Ɏ�����i�\���ɏ�����������������B���������̒��ɂ͂̂��ɐ����ƂƂ��Ă̐M�O�������ɐ��荞�܂�Ό��T���Y�̂��̌�̓���������������B
[No. 569] �@�T���@�Q�R��

�@�@�@�V���Ёu ���������́v�p�c����
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�U�N��E�@�Q�P�S�@�y�[�W�@
�E�E�E�{�I�̖{�����Ă������ė��͏I���B������܂��̂��Ƃ�����ǁA�D���Ȑl���ł����Ƃ���������ꂽ�Ƃ��A���͂Ђǂ������낢���B����ꂽ�C�������B�n�i�P���ɁA�ł͂Ȃ��āA���ʂ̖{�ɁA���B
�D���Ȑl���ł������炱���ł��݂Ƃ�������ɕ�炵�Ă������Ƃ͂ł��Ȃ��ƁA�܂�Ŏ�����������ꂽ�悤�Ƀn�i�P���͌������B�~�J���̂��Ƃ��B���N�̔~�J�́A�J������܂�~��Ȃ������B���̐l�A�{��ǂނ́H
�v���o���Ə��Ă��܂��B���Ƃ����낤�ɁA�D���Ȑl���ł����ƍ�������āA�����܂����ɂ������₪���ꂾ�����̂�����B���A�Ə����������悤�Ȋ�����āA�ǂ܂Ȃ��A�ƃn�i�P���͓������B�ǂ܂Ȃ��Ǝv���A�Ə��������肩�������B�E�E�E
���̖{��9�҂̒Z�ҁA���̒��̈�Ղ��u���������́v�ł������́u�ނƎ��̖{�I�v�̂ق��������[�������B�l���ɂƂ��ėF�l�ł���v�w�ł��ꋤ�ʂ����b��͑��������܂�����Ȃ��Ƃ͑債�����Ƃł͂Ȃ��B����͂����̒m�荇���ɂȂ邫�������ɉ߂��Ȃ��Ǝv���B
����ł͗F�B�E�E�����v�w�Ƃ����ǂ����݂���ɖ��͂���s���͂Ɣ��M�͂d��������ԕ��ł��邩�ɐs����Ǝv���܂��B�����j���̒[����ł�����ꌩ���͓I�Ɍ�����ِ��ł����Ă������ɖO���Ă��܂��Ă͈Ԃ߂ɂ����Ȃ�Ȃ��̂ł��B
������9�҂͋��炭�p�c����́u���Ƃ����G�b�Z�C�@���ۗ����v�������������C�̌��ۗ����ɐs����Ǝv���B�Ⴂ���琫�I�𗬂���̂ƂȂ������ۂ͐l���[�߂��������ۂƂ͖{���I�ɈႤ���Ƃ�z���B
[No. 568] �@�T���@�P�W��

�@�@�@���~�Ɂu �ڂ������̉Ƒ��v�����a�^
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�P�N��E�@�R�P�O�@�y�[�W�@
�E�E�E�������l������蒼����Ƃ�����A�ǂ̎��_�ɖ߂邾�낤�[�[�B�������̏�����ɂ��閞�����C�ʂ��Ƃ炵�A�����̂��R�̉��܂Łh���[�����[�h�h�����тĂ���B�����Ɛ������ʌ��i�߂Ȃ���A��؍����͍l�����B��ɂ͂��̍��Ȃ������g�ѓd�b������B���������́A���s���R�Ȃ������������Ă�������B
�k������z�c�≮�̒��t�Ƃ��Ċɏo�������̕��E���O�Y�́A�����̖��E���q�Ɨ����ɂȂ�A���Ί��������悤�Ȍ`�œƗ��B��\��ňꍑ���̎�ƂȂ������A�R�ɕz�c�������Ƃ������b�ɂ���������A�����ɉ�Ђ�傫�������B���ƋK�͂Ɣ�Ⴗ��悤�ɓ�l�͎q�������X�Ǝ��������B�����̏�ɂ͎l�l�̌Z�Ǝo����l����B���̑S������N�Ԋu�Ő��܂�Ă���A��������������̌Z�Ɣ���������Ă����B���O�Y���l�\�Z�A���q���l�\�̂Ƃ��̎q���B
�u�x�\�����͖]�܂�Ă��킯����Ȃ�����ȁv�Z�����͂��Ƃ��邲�Ƃɂ����������B���e���v��I�Ɏq�Â��肵�Ă��������Ƃ��v���A�������z��O�̎q�ǂ��������̂͊ԈႢ�Ȃ��B�E�E�E
�E�E�E�Ȃɂ���̍��m�A�������]�����������Ȃ��ƒm�������A�����͊��ɉƂ��痣��Ă����Z����܂߂����ň�Ԃ������肵�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂͏\���킩���Ă����B��Ђɂ��Ă�����Ȃ�̎��т������͂̒���������ɂ��Ȃ��Ă����l���������B
���܂�}�Ȃ��Ƃɉʂ����Ă��̎������Ȃɓ`����ׂ����A�����đ��q�����ɂǂ��Ώ����Ă����̂��E�E�E�B���e�Ƃ��Ă̌��ЂȂǔ��o���Ȃ��قǂɒ@���̂߂��ꂽ�B���j�E�_��́u���₶�A������Ɠ����₵�ė�����E�E�v�ɉ�ɕԂ�B
�v�������Ȃ����j�E�r���̋@�]�ŗL�\�ȃZ�J���h�I�s�j�I���ɏ��荇���A�Ȃ̗]���͑啝�ɉ��P���ꂽ�B�����Ă���Ȃ��Ƃɂ���ĉƑ��̂����Ȃ͂�������ƃ^�K�����ߕt�����邱�ƂɂȂ�B
[No. 567] �@�T���@�@�X��

�@�@�@���|�t�H�u �R���L�v�t����
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�S�N��E�@�Q�V�R�@�y�[�W�@
�E�E�E�u�v�����Ƃ����ގv�����т����Ƃł��v�Ƃ���������܂����B�{�\���̕ς̌�A�����l�Ƃ͐S���ʂ�ʕv�w�ƂȂ����K���V���l�́A���̂Ђ�₩�ȕ�炵�������������A�L���V�^���ƂȂ��ăf�E�X�l���Ɏv�����Ƃł悤�₭�����铹��������ꂽ�̂ł��B
����ǁA���Ȃ����ƂȂ�Εv�w�Ƃ��Č݂��ɂ��Ƃ����ޓ������ł݂��������A�Ƃ̎v�����K���V���l�ɂ͂�����ł����B���y��ɗH����Ă����ԁA�c�������l�������ނ��Ƃ����܂܂Ȃ�Ȃ������̂��S�c�肾�Ƃ����ł����B�킽�������v�����т��A�K���V���l�ɑ����Ē����l�̂��K�������͂��Ă����A���ꂪ�����Ƃ����������Ƃł��A�Ƃ������Ⴂ�܂����B
�������钆�A�K���V���l�͎����̘a�̂��킽�����ɂ������ɂȂ�A�u����ʂׂ�����m��Ƃ́A�U��ׂ����͎��炪���߂˂Ȃ�ʁA����ł����A�Ԃł���A�ЂƂȂ̂��Ƃ����v�������߂Ă��܂��B�琢�a���U��̂͂��܂ł͂Ȃ��A�����a�Ǝv����ʂ킹�A�Ԃ��炩������̂��Ƃł��v�ƌ���ꂽ�̂ł��B���̂����t�����ɟ��݁A�킽�����͔R�����鉊����ɉ��~���o���̂ł������܂��B�E�E�E
�����̕�ł������K���V���͂Ȃ����~���瓦�����ɉ��̒��ɂƂǂ܂�A�����ĂȂ��ł̐琢�݂̂����u���ē������̂��E�E�E�B�琢�͂���ΓG���̎��Ƃɐg�������Ƃ̂ق��ɖ������̂��낤���E�E�B
�̎�ɂƂ��ēV�������ڂ̊փP���̐킢�͓����ǂ���ɒ������ɂ���Ă��̌�̓������܂�B���������̗��ɂ͕��G�ɗ����������������ď��l�̉ł���ɂ���Ă͓��e�ł����Ă��G�����ɕ��f����Ă��܂��B
�퍑���ォ��]�ˏ����ɂ����Ă̏��̐��E�����G����Ȑl�Ԍn���������Ă��̗��܂����l�Ԗ͗l�J�ɕR�����Ă����E�E�E�t������̐^�����������v���ł��B
[No. 566] �@�T���@�@�U��

�@�@�@�V���Ёu ���炴��v���O��
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�Q�O�N��E�@�Q�P�U�@�y�[�W�@
�E�E�E�u�ł������A�������āA�����Ƃ����ɏI������������Ȃ��́v���������ƁA�o�������͂����Ƃ��炵�����U��A�u�C�͐S�v�Ɠ������B���傤���Ȃ��̂ŁA�������́u�������v�����邱�Ƃɂ����B�O�l�̂���������A�Ȃ��Ȃ������̂ŁA�O�l�ɂƂ��Ă��ꂪ���^�������N�͂��߂Ắu�������v�Ȃ̂ł͂������B
�u�o������A��������ɂȂ�Ȃ�����v�P�����������B�ցH�ƃo����������Ԃ��B�u���Ƃ����ŏ��Ɂw�����܂��Ă��߂łƂ��������܂����N���ǂ�����낵���x���Č����Ă��B���ꂩ��݂�Ȃł����V�������āA���N�ʔz���v�q���̂悤�ȕ\��ōP���������̂ŁA���ƃo�������͂Ղ��Ɛ����o�����B
�u�����Ƃ����āA�������p���Ƃ��H���Ă��v�o����������B�킽����Ƃ��́A����̒����G�ϐH�ׂ邾���ŁA���Ƃ͂����Ɠ����������B�����������X�Ɍ����ƁA�P���́A���[���A�ƌ����Ĕ߂������Ȋ�ɂȂ����B�E�E�E
���̎O�N�Ԃ͖{���ɃR���i�ɔY�܂���Đh�������ł����B�s��ɏo����҂����͂Ђ�����炢�d���ɂ��ς��Ė{���Ȃ点�߂Ă������ɂ͉��������c�ɂɋA���ăM�X�M�X�ɂȂ����S��������邱�Ƃ̑�������䖝���ċA�Ȃ����߂�����B
�����̎O�l���{���Ȃ�c�ɂɋA���ė��e��������u�E�E�������O�����낻�댋���ȂǍl���Đg���ł߂Ȃ����E�E�v�Ƃ��̏����ɑς��Ȃ�����߂����ł��낤�����ł͂������͂��ł����B
����ȋC���Œ��ԎO�l���W�܂��Ă̂������k�`�E�E�E��コ��͂���Ȕޏ���̋C���́u���炴��E�E�v�Ɗ������̂ł��傤�B
[No. 565] �@�S���@�@�T��

�@�@�@�o�t���Ɂu �C�F�̚ށv�c�ۉ�q
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�S�N��E�@�Q�U�S�@�y�[�W�@
�E�E�E����̓O���X���f���A���ɂ������Ă݂��B�G�������h�O���[���̒�ɔ������n�̂悤�Ȃ��̂������A���܁A�g�Ɋ����ꂽ�悤�ɂ����ƕ����オ��B�ォ��̂������ނƁA�����O���X�̒�ɔ��͗l������Ă���B
�T�d�Ɍ��Ɋ܂�ł݂��B���̓r�[�A����₩�Ȓ������@�o�𐁂������Ă������B����͎v�킸�ڂ�����B�����̊C�͍L�������B�u�O�ÁA�Ƃ����ꏊ�̊C���͂���܂��v����́A�v�킸�����������Ă����B
�����������A���ꂽ���̌̋��̖��O����B���̊C�ւ̎v�����ꂪ�A����͂Ƃ��ׂ������āB����������A�S���Ȃ����������Ɏ��������āA�悭�ʂ����B�C�ݐ��ɂ����āA�ЂƉw�̂��������ꗼ�d�Ԃɂ��Ƃ��Ɨh���ĂˁB�E�E�E
�u�C�F�̚ށv��20�҂̂�����V���[�g�V���[�g�̍�i�W�ł��B���ꂼ��̍�i��400���l�ߌ��e�p���Ō�����10���قǂ̍�i�ł��B���炭���҂����ǂ�ł��Ȃ��������ɂƂ��Ă͒Z�����͂̒��ɓW�J���铪�̐�ւ��ɍQ�ĂĂ��܂����B
���炼��̍�i�ɂ͋��ʂ����b��͂Ȃ��킯�łނ���ʓǂ��������ғǂ炻�����������܂Ŏ��Ԃ������Ȃ��Ƃ��ꂼ��̍�i�����̍�i�̓��������������Ă��܂��B
������Ǝc�O�ȃV���[�g�V���[�g�ł����B
[No. 564] �@�R���@�P�T��

�@�@�@�n���L���Ɂu �����������܁v�Q�@�悤��
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�Q�Q�N��E�@�P�T�Q�@�y�[�W�@
�u�E�E�E������Ђ����߂����Ƃ������������Ƃ��A���l���̐l�ɑ��k���ꂽ���ǁA���̌�A��Ђ�������������߂��l�͈�l�����Ȃ�������ˁv
�N�}�K�C�������ɂ́A�����͈Ӓn����������A����A�ǂ����đގЂ◣�������Ȃ������̂��Ɣޏ������ɕ�������A�u�ł��d�d�v�u����ς�d�d�v�ƁA���������ƌ��������āA�͂����肵�����R�͕����Ȃ������Ƃ����B
�u���������{�C�őގЂ◣���������l�́A���k�Ȃ��Ȃ��ŁA���ς��Ǝv������ˁB���k������Ă������Ǝ��́A���������̂�B���͂��������ӂ��ɂ������̂����ǁA�ǂ������i���ɂ��Ă������킩��Ȃ��A���Ă����̂Ȃ�O�����ȑ��k�����ǁA�E�E�E�E�v
�T�T�K���L���E�R�͑���Ƃɋ߂Ă��ăL�������[�Ƃ��čŐ�[�̍����т��Ă���Ǝ��g�͎v���Ă����B���������鎞�A���̐����͎����I�ł͂Ȃ��c�Ɗ����đ����ސE�̓���I�B
�����Ă��|��邩�S�z�Ȃ��炢�Â��A�p�[�g�ɏZ�ނ��Ƃɂ������d���ꂪ�܂��v���������Ȃ��قNjC�ɓ������B�����������ɏZ�ޏZ�l�B�Ƃ��C�S�m��ČZ�v�w�������瓯����i�߂�����f�葱���Ă����B
�������L���E�R�͂܂������͎Ⴂ�Ǝv���Ă��Ă��T���猩��Ƃ�������N���҂ɂȂ��Ă���B�Ⴂ�l�̐����ԓx�ɂ������̋ꌾ�������Ȃ���������̐������т��Ă����B
�Ђ邪�����ăL���E�R�������g�ɓ��Ă͂߂Ă݂�B�ǂ��ɍs���Ă����͂�ŔN�����B�Ⴂ�l�̐����ԓx�ɋꌾ�������邱�Ƃ��Ȃ������̂��ƂŐ������ς����B�l���ꂼ��ł����̂��B
[No. 563] �@�R���@�P�P��

�@�@�@�u�k�Ёu �����v���c�і덁
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�O�T�N��E�@�Q�O�T�@�y�[�W�@
�E�E�E�搶�͕K�v�Ȃ��ƈȊO�܂���������Ȃ��������͂������C�ɓ������B�搶�͖ق��ĎQ�l�����J���A���₩��{���ʂȎ��Ńm�[�g�ɏ����ʂ��B���ꂪ�I���ƃm�[�g�����̕��ւ��炷�B
���͂��̖����A�����������B���ꂾ���œԋ߂����߂����B�������搶�Ɩق����܂܍����Ă��Ă��A�s�v�c�ƋC�܂����͊����Ȃ������B�ق����܂ܐ������\�₭�炢��������A�搶�͏��߂Ċ��������ɂ����B
���v��T���Ă���悤�������B�搶�������̕ǂ����߂Ȃ��猾�����B�u�������ł����H�v�u�����l�\�ܕ��v�u���̖��ŏI���܂��v�E�E�E�E
���q�͍��Z��O�ɂ��Ă����B��͂��̑O�̖͎��̌��ʂ�����2�����N���̏��q���ɂ��Ȃ����ƌ�����̗F�l�̉����q����w�@���Ȃ̂ʼnƒ닳�t�Ɍ}����ƌ����o�����B
���̊w���͐��^�ʖڂőS���]�v�Ȃ��ƂȂǒ��炸�M�S�ɒ��q�Ɋw�Ȃ����̋����ɓw�߂��B���x�����߂�ꂽ���Ԃɂ�����Ɨ��Ď��ԂɂȂ�ƋA���Ă����B���q�͂���Ȕނ������̗V�ё���ɂ��n�߂��B
���c����̍�i�ɏ��߂ďo������̂�6�`7�N�O�̊H��܍�i�u�R���r�j�l�ԁv�ł����B�����Ă��́u�����v�͂�����10�N�O�ɏ����ꂽ��i���ƒm��܂����B
�ߌ��Ȋ���̒��w���̐��̖ڊo�߁E�E�E10�N���ēs��ɐÂ��ɕ�炷������D�������߂�E�E�E�B��i��ʂ��č�Ƃ̐l�����̂��̂������Ă���B
[No. 562] �@�Q���@�P�W��

�@�@�@�u�k�Ёu ���������v��c���Y
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�V�N��E�@�R�X�U�@�y�[�W�@
�E�E�E��N�ސE�Ƃ����l���̋��ɂ́A���������d�v�ȈӖ�������̂�������Ȃ��B�ʐ��E�ɂȂ��Ă��܂�����Ђł̏o�����ȂǁA�ǂ�قǎ��Ԃ��悤�̂Ȃ��G���[�ł������ɂ��Ă��A���͂��ׂĂ����b�ɂł���B
�ڂ݂��Ƃ���ŁA���Ẳ�Ђ͖l�̂����₩�Ȗ����Ƃ͂܂�Ŗ����̓V�̂ɉ߂��Ȃ��B�����v���A�V��Ƃ����D��ȉF���D�̒��ŁA�ڂ��Ɛߎq���Ђ����ɉB�������Ă����t�Ƃ̎v���o�����肰�Ȃ����������Ă��A����͂܂���������������邱�Ƃ̂Ȃ��A���������Ȃ̂ł͂���܂����B
�������ɁA�����v���o���Ă������̂��낤�B�����Ƃ��݂��������݂�������A�߂��݂��Ȃ��A���݂����Ȃ��B�E�E�E�E
�|�e����U�T�ł߂ł�����N���}������ȑ��ʉ�̌�ԑ������ɂ����̒n���S�ɏ���ċA�r�ɏA�����B�������A���E������Ŏ���w�߂��܂ŗ������]�쌌�Ŏԓ��œ|��Ă��̂܂W�����Î��ňӎ��̂Ȃ��܂��u�𑱂���B
�ӎ��̖߂�Ȃ����U�T�N�Ԃ̐l�ԊW�A�Ƒ��W�c�l�X�ȏ������ɔ]�����삯�����Ďv���o�����B
���ׂƂ����ӎ��̒��ŋ͂��S�ł��̐������������q�̏t�Ƃ���}������̌��ɏo��B�u���ꂳ�����l�ɂ��Ȃ��ŁE�E�v�t�Ƃ͂��������c���čX�ɒn���S�ŋ����Ă������B����́u�������ȁE�E�v�Ƃ��Ȃ����ĊK�i��������B
���Ԃ̒��ɂ���N���l���̏I���w�d�Ǝv�������������B���͈Ⴄ�Ǝv���A���i�K�̔��ɗ������Ƃ��������ӎu�ł��̔����J���Ă������Ƃ�����B
[No. 561] �@�Q���@�@�W��

�@�@�@�u�k�Ёu �Ί݂̉Ǝ��v���A�q
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�W�N��E�@�R�X�P�@�y�[�W�@
�E�E�E���z�Ԃ͂��̊X�ɂ��炢�Ă���B���̉Ԃ��炭�̂́A��N�̂����ŁA�����Ƃ��_���d�����ꂱ�߂Ă��邱�̋G�߂��B�X������F�������A�݂�Ȃ��P�������A���������ĕ����Ă��鎞�A���z�Ԃ͂Ђ�������A�ō炭�B
�����Ă��̐l�́A���̉Ԃ̐���ɋC�Â����Ƃ͂Ȃ��B�����ɒʂ�߂��A�d�Ԃɏ���āA�߂܂��邵���Љ�ւƏo�Ă����B���̉Ԃ̑��݂ɋC�Â��̂́A�傫�Ȍ��ɗ�������ł��܂��������B
�N�����ɂ��Ă���Ȃ��Ȃ��ď��߂āA���̐F�̑N�₩���ɋC�Â��B���̎莆�̍��o�l�ɂ���������������������̂ł͂Ȃ����낤���B�E�E�E�E
���㎍��27����l���B14�̎����a�C�ŖS�������Z�𑲋Ƃ���܂łЂƂ�ŕ��e�̂��߂ɉƎ������ɔw���킳��Ă����B����Ȕޏ��̂��߂ɕ��e�͈�̎菕�������Ȃ������B
�������ɂƂ߂�v�̌N�Ƃ̊Ԃ�2�̖��A䕂ƎO�l��炵�A��Ǝ�w�Ƃ��ĉƎ��ɂ������ށB���͂̉ƒ�͂ǂ������҂��Œ��̌����ɍs���Ă�䕂Ɠ�l�����̎��Ԃ����������B
�܂荡�̂��̎����̒��Łu��Ǝ�w�v�ł��邱�Ƃւ̋^��̖ڂ����̊Ԃɂ�������Ă����B�������A����Ȕᔻ�I�Ȓ��ɂ��Ă�����̑��ς�炸�̐����ԓx�݂͂�Ȃ��猩������鎞�������B
����̂��̎����E�E�͂܂����̐��̐�������v�w�Ԃ̈ӎ����v�ȂǑ傫�Ȗ��_�������Ă���B�����ĎЉ�S�̂��Ƒ����^���Ɏx������̐������Ȃ��Ƃ�Ƃ�̂��鋤�҂��̎q��Ă͎����������ɂȂ��B
[No. 560] �@�Q���@�@�Q��

�@�@�@ �p�앶�Ɂu �X���[�����[���Y�v���~�`
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�Q�P�N��E�@�R�P�T�@�y�[�W�@
�E�E�E�������A�q�����̈ӂɏ�����悤�Ȏ����͂����Ă͂Ȃ�Ȃ����ƂŁA���Q�҂̐ӔC�͒Njy�����ׂ��ł����A���Q�҂��������Ȃ��ׂ��ȖԂ̖ڂ͕K�v�ł��B
�ł��A���̒��Ŗ����̐l�Ԃ����܂�A�ꂵ��ł���Ƃ�����\�\�ނ�͕ېg�ɒ������R���ł��傤���B����Ƃ��A���ӔC�ȕs�͂����̂ł��傤���B�q������ĂĂ������ŁA�u���̎��������Ă���悩�����v�ƌ����������u���Ȃ��e�͂���̂ł��傤���B
�q���̂�����Ƃ����s���ł����A�Ƒ����ɂȂ����o���̂Ȃ��e�́H�q���̐����ƌ����̂́u���܂��ܖ����ł��Ă��ꂽ�v���X�̐ςݏd�˂��Ɗ��������Ƃ̖����e�́H�B
�����̑��q���������Ƃ��͂��ς��ŁA�ƃx�e�����ٌ̕�m�����݂��݂ƌ��܂����B�[�[�Ȃ����x�̂��₵�����B�ƒ���āA����Ӗ��u���b�N�{�b�N�X�ł�����ˁB�O����͌����Ȃ����O�ɕ������Ă��炤���Ƃ�����B�E�E�E�E
�v�ɐ旧����Ă���̊�a�q�ɂƂ��ċ߂��ɋ����\���Ă��ꂽ���̉l���q�Ƃ��̘A��Y���̕v�T�V�̊Ԃɒa�����������̖���͊�]�̐��������B�u�����a���邩���x�v�w�ʼn���ɂł��s���Ă��낢�ł����ŁE�E�v�Ɨa�������������]�����ŖS���Ȃ��Ă��܂����B
��a�q�͓ˑR�̗��J�ɐ�����荞��Ŗ߂��ĈٕςɋC���t�����E�E�E�B���R�Y�������Ƃ��Ď�蒲�ׂ��S�u���ꂽ�B
�x�e�����ٌ�m����Ɍ��炸�u�悭������ȐV�ĂȐe�̌��ŁE�E�v�Ǝv������ł��B
[No. 559] �@�P���@�Q�R��

�@�@�@ �p�앶�Ɂu ����ł���͐��v�����@�_
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�W�N��E�@�R�P�X�@�y�[�W�@
�E�E�E�퓬�@�͖{���Ɍ����Ă����B�E���@�݂����ȉ����w��ɔ����Ă����B���͂���ɍ���Ⴍ�����B�����𗚂������������p�C�i�b�v���̃M�U�M�U�̗t���ł������Đ荏�B�����ƁA�������������ł���l�Ԃւ̎d�Ԃ����낤�B
�p�C�i�b�v���̏n�ꂽ�����X�Ɍ�����āA��ʂɊÎ_���ς��������Y�����B����ł���͐������B�l�Ԃ����Ă�݂����ɐ������B�X�܂ł��Ə����̎��A�C�Â����B�����x��ăp�C�i�b�v���̉A�ɉB��Ă��������l�ɁB
���͂��̑̂̏�ɕ������Ԃ������B�����N���Ɍ����鏗�̎q���������炾�B������̂��j���Ă���B���ɐԂ��z�����������������B���͌��b�̃p�C�i�b�v���̐��ł͂Ȃ����Ƌ^�����B�����A������B
�����Ă������Ɏ��U����������̂́A�����݂����ɑf���炵���傫�Ȗڂ��������������B�u���ꂪ�A�������H�v�ʐ^�̒��̂������̖ڂ́A�������Ƃ�����菬�������ǁB���������͗����オ���āA���d�̔���߂��B�u�Ⴄ�v�E�E�E�E
�{���ɂ͂V�҂̍�i�����܂��Ă��܂��B�����Ă��̏��̕\��ɂȂ��Ă����i�͂���܂���B�Ō�̍�i�́u�l���̓p�C�i�b�v���v�Ƃ�����i�ł�����������̑t���ɘb���ĕ���������p�ł̎v���o�̒��Ɂu����ł���́E�E�v�Ƃ������t���łĂ��܂����B
���̒��̂V�҂͎��ɑ��ʂŖ��킢���L���ł����Ƃ�킯�싅���ނɂ�����i���R�҂���܂��B��������싅�Ƃ����X�|�[�c������Ɍg��邱�Ƃɂ��l���̌��݂�[�������������i�ɂȂ��Ă��܂��B
[No. 558] �@�P���@�P�S��

�@�@�@ ���~�Ɂu �߂����A�����m�������v�d���@��
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�S�N��E�@�S�U�X�@�y�[�W�@
�E�E�E�L�O���ׂ����^�C�A�̓��̗[�H�́A���i�ʂ�̈�`�O�������B�T�����̉��Ă��Ɏ�|�ρA����Q���������g�������ƁA�R�̖��X�`�B���т͂������������炱�ꂭ�炢�́A�Ƃ������Ƃŏo�������̐Ԕтɂ����B
���������ł͂Ȃ��B�Z�\��ɂ��ẮA���������N��肶�݂�������������Ȃ��B�����A����͐̂���̗��V�������B���w�Z�̋��t�̒��H�́A���������̏ꍇ�A�q�ǂ������Ɠ������H���Ƃ�B�ŋ߂͋��H�ɂ������ԁu�a�v���̂�������悤�ɂȂ��Ă������A��͂��{�͎q�ǂ��̖��o�ɍ��킹�����j���[�Ȃ̂ŁA���߂ė[�H�ł͑�l�D�݂̗����𖡂킢�����B
�ӎނɂ́A���{���ɂ��邳���ߏ��̎����������߂̏��đ����̕�������B���d�̃_���i�Ɗ��t���āA�e���r��BS�����̗��ԑg���ςȂ���؎q�̃O���X�ɒ��������������т��ш����Ă�����A���̂܂ɂ��l���r���������B�E�E�E�E
���w�Z�̋��t�����Ă����������Îq�͂R�W�N�̋����������N�ސE�����A�v�ł������G�j�������ł͂��������U�R�ł���������ɂ�����旧����Ă����B��l�̎q�����l�����ꂼ��̓������ł���B
�܂��A���ꂩ��͂��߂Ď��R���Ԃ��g���Ďv�������莩���̎v�����ɂԂ��Ă��������B����Ȏ����܂ł̋����q�����S���ɋ��ʂ��đ������u�߂����A�����m�������v���������Ɏ莆���������߂��B
�d������̍�i�͂������ǂ�ł��邪�L���Ɏc���i�͂���������̍�i�̃^�C�g���̂悤�Ɏ��ɕ�����₷���ǂޑO����搶�Ǝq�������̘b�d�Ɨe�Ղ��z���ł���B
�S�N�ȏ�̊ԂɐV���ɘA�ڂ�����i���܂Ƃ߂����������Ă��Ȃ�d���ň����搶�̒�N������ׂȉB�������Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ����G�ȊW�������ɕ`����Ă���B