|
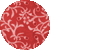
【四章】
オー・タンは取り合えず国家としての体裁を採ってはいるが、実際にはイルクーツクによる民族統一を果たしたに過ぎない。法も、制度も持たずただイルクーツクとその配下による合議による支配と庇護を大多数の民が受け入れそうでないものが除外された。
イルクーツクが倒れればそれだけで瓦解する危うさだが、国家組織としての骨組みがないからこそ行える行為がある。オー・タンの外征とは征服戦争ではなく略奪戦争であった。それこそ民族ぐるみの盗人家業とでも言ったところである。
オー・タンの侵略が国家戦略に基づく行動ではなかったために、南西諸国の混乱は大きなものとなり被害は年々拡大していった。領土の拡大ではなく物品の略奪にこそ主眼があったが故、南西諸国の統治者達にしてもその意を諮り迎え撃つと言う戦の定石が通用しないオー・タンに翻弄された。
元々草原は大陸の東西に花開いた文化文明圏から取り残された辺境地、経済も産業も興りようが無く、たまに馬商人との取引が物々交換で行われていた位である。当然そこで暮らす民の生活や習慣が文明圏へともたらされることもなく、また草原の民が文化の恩恵に与ることもなかった。
草原では決して手に入れることなど叶わないものを手にする機会を、イルクーツクによって与えられ、草原の民は欲しいままの暴虐と殺戮を行った。慎ましい生活を続けてきた草原の民にとってそれは甘美な毒であり麻薬と言っても過言ではない。イルクーツクの支配とは、日々の暮らしが天候に左右され、贅沢という言葉さえ知らずにいた草原の民に、労せず手に入るものがあるとまやかしの豊かさを教えた事にある。瞬く間に広がり浸透した毒は本来の生活基盤する揺るがす程となる。
それは年を重ねる毎に男達が草原を離れる時間が増え、残された者達への過剰労働となって現れた。イルクーツクのもたらす富の分配という輝きの裏で、民族の変質変容を誰よりも良く理解し恐れていたのは、外の誰でもないデイ・アナであった。
しかし、そのデイ・アナにしても諸国の事情を逐一知っていると言う訳でもなく、叉遺恨を残さず事態を収束させる術など、思いつきようもなかった。
デイ・アナに解っていることは、此程までに被害を拡大させた草原の民をひいてはイルクーツクを、南西諸国が何の報復措置も取らず済ませる筈がないという事である。
事実、昨年南西諸国同盟に北国の雄邦ロジーナ帝国最南領カザリエフ公国軍、大陸最古の歴史を持つラフリエル王国軍の参加によって状況は変化した。南西諸国同盟は声明一つ発すること無い侵略者に対し、手痛い反撃を食らわせることに成功している。
ついにオー・タンの侵略は五年目にして頓挫させられることとなったが、冬の到来は双方共に戦力の維持を不可能へと追いやった。
南西諸国では人命被害の甚大さと疫病の発生、並びに食糧不足、オー・タンでは初めて受けた兵力的被害とイルクーツクの指導力に対する不審がそれである。今年に入ってからの負け戦続きは草原の民に里心を抱かせるのには充分すぎた。
そして草原においては、水面下で深刻な生活基盤の破綻が待ち受けていた。
夜も更けた城塞の広間では、息詰まる雰囲気の中で誰もが固唾ののみ、見守っていた。
イルクーツクは微動だにすることなく娘を睨み据え、幼い娘は怯むことなくその視線を受け止めていた。
獣脂の灯りを受け煌めく黄金の瞳のデイ・アナは瞬きを一つすると
「話せと言うなら、お話しします。ですが、決して父上にとって良い話とも思えません。場所を改めた方がよろしいかと」
毅然とした声で話し出した。
媚びも、怯えもしない、こずら憎い娘の言いぐさに、鼻を一つ鳴らしイルクーツクは
「良いか悪いかは、儂が判断することだ。誰がお前にしろと言った、さっさと話せ」
デイ・アナは微かに眉をひそめたが、それが父親のかんに障ったと知ると努めて平坦に口を開いた。
「ロリ・アナ姉上は今日嘘を付いた。姉上にはそんなつもりが無かったと言うかもしれないが、結果として姉上の身勝手な嘘でクリグ兄上達を振り回し、幼い弟妹達を飢えさせた。体の具合が悪いから家畜を集めてきて欲しいと言い、代わりに私の仕事をすると言った。集めに行った家畜は数が合わないし、言われた場所にもいなかった。漸く集めて戻ってみれば、姉上は私の仕事を何一つせず放り出したままで自分だけが食事にありついている」
自分の所行を暴露されたロリ・アナは居心地悪げに体を動かし、回りを見回して顔を赤くした。広間にいた男達が一様に呆れた顔をしたために。
幼い弟妹の面倒を見るのは惣領娘の仕事であるが、イルクーツクの長女、二女、三女は既に鬼籍の人となっている。当然それはデイ・アナではなくロリ・アナの仕事だが、ロリ・アナが弟妹達の面倒を見ていないことは、氏族中とうに知れ渡っていた。勿論そのしわ寄せをデイ・アナが一手に引き受けていることも。
オー・タンでは働けないものは、乳飲み子と足腰の立たない老人だけという習慣からすれば、ロリ・アナはひどく怠惰で不道徳な娘である。イルクーツクの可愛がりようがあからさまなだけに誰もその事を指摘せずにいたが、デイ・アナの思い切りの良さに一同は感心するより不安が先立つ。実の父親に生まれた時から疎まれている娘と皆が知っているだけに。
「何よ、デイ!ここでそんな事言わなくたって良いじゃない。ひどっ」
流石に口を閉じていられなくなったロリ・アナがデイ・アナを詰るが、ちらりと目をくれ
「姉上」
と一言で黙らせた。金色の視線は針のようにロリ・アナの口を縫い止める。イルクーツクは考えつきもしない事だが、その眼光の鋭さこそデイ・アナが父親から受け継いだものである。改めて父親に視線を戻し
「父上、私は姉上が嘘を付いたことが悪いとは言わない。ただ自分のしでかしたことがどういう事なのか考えようとしない事が、悪いと思う。大体姉上は、嘘を付いてるわけじゃなくその場の思いつきを口にして、それを忘れるから嘘になる。すぐばれるような嘘を付くより始末が悪い」
「ほう、それだけか」
「まだあります。姉上のした事が、家族の中だけなら問題はありません。冬の城塞に集まった全ての氏族に迷惑の掛かることを、姉上はやってくれました」
「どんな、迷惑だ」
イルクーツクは両目を眇めた。
「姉上は、自分の家畜のために冬越しの支度をしていない。この砦の中には余分な干し草の蓄えはありません。それどころか、足りないのです」
「何故、足りぬ」
唸るような声が低くなった。
「女子供だけでは手が足りず、刈りきれなかったからです。母上達も兄上達もめいっぱい働きましたが間に合いません。姉上は一度も作業には出ていなかったから知らないだろうけど、今年は種付けも控えたくらいです。なのに400頭の羊、到底賄い切れません」
デイ・アナの話は広間の男達を驚愕させるものであり、それはイルクーツクとて例外ではなかった。
「そんな話は聞いとらんぞ、どいうことだ」
イルクーツクはデイ・アナに向かって怒声を浴びせる。珍しくも狼狽えた様子を見せる父親の顔をしげしげとデイ・アナは見つめて、
「やはり気が付いていなかったんですね。母上達が砦の中にいないことを。まだ戻ってきていません、たぶん真夜中を過ぎるはずです。この十日程、毎日そうですから」
大きな溜め息を付いた。イルクーツクの神経を逆なですると解っていても付かずに入られなかった、それ程までに留守を預かっていた自分達は疲れていると言いたかった。動ける女と少年達は総動員で草刈りをしている、竈と水屋は老女達が切り盛りしている。集めた家畜の世話は老爺と少女達の仕事となった。
「父上、姉上はそんな事すら知らない。何もしていないから、知りようがない。でも、人に聞くぐらいのことはしても罰は当たらないと思う。それすらしないのだから、姉上のしたことは立派に迷惑です」
怒りに身体を震わせるイルクーツクの前で、デイ・アナの瞳は揺らぐことなく父親を避難していた。イルクーツクの苛立ちは募る一方である。
自分に何一つ似たところのない、痩せていて器量の悪いちっぽけな小娘の物言いに返す言葉が出てこない事も、留守の間の困窮に気付かなかったことにも怒りが湧く。己の落ち度が避難されてしかるべきものだと解るが故に、怒りの矛先を何処に向けるべきか迷いの生じるイルクーツクであった。
デイ・アナが父親にとって良い話ではないと警告したにもかかわらず話せと命じた分、広間に集まった男達の手前これ以上の醜態を晒すべきではないと理性が囁く。
デイ・アナにしても自分の言ったことが充分差し出口だと解ってはいたが、ロリ・アナに対する不満はもう自分一人で処理しきれる事では無くなっていた為、何としても父親から姉へ罰なり注意なりの言葉を引きだしておきたかった。
そのさなか、イルクーツクの反対側から事態を眺め楽しんでいる剛の者達がいた。イルクーツクの同母弟に当たるバルクーツクとイルクーツクの年かさの息子達ザイナイルとダルクイルである。
バルクーツクは、イルクーツクとよく似た風貌の持ち主ではあるがその中身は、全く似たところを持ち合わせない男であった。
兄イルクーツクに従いながらもその異常な執念に引きずられることなく、代わりに草原との連絡を絶やさずに引き際を考えていた位である。どの様な事を起こすのであれやりすぎるのは良くないとの考えからであった。
草原の男にしては珍しく、理性と知性を併せ持つ男はデイ・アナの言に尤もだという感想を抱き、イルクーツクがこの事態をどう処理するのか見物であると思ってもいた。
ザイナイルとダルクイルは、バルクーツクよりも更に中身がかけ離れた息子達は、2人とも草原での暮らしに充分満足していたので、他国への略奪行為には反対であった。
それでも家長に従うのが草原の習いであるために父親に付き従っていたが、自分達が草原を離れている間に家族に不測の事態が起きる方が、よほど嫌なことであり事実帰ってみればとんでもないことが起きていた。にもかかわらず一同を集め酒盛りをし、ラフリエルとオルバリスに対する恨み辛みの繰り言には些かどころでなく呆れ、そんな事をしてる暇など無いと言ったところで聞く耳を持たないイルクーツクに少なからず苛立ちを感じていた。
そこへデイ・アナの非難とも言える発言は、流石の父親でも我に立ち返るかと期待が持てた。
常日頃気に入らないと公言しても憚らないと言え、デイ・アナの言ったことは全て真実である。如何にイルクーツクといえどこの場でデイ・アナを打ち据えたりすれば面目を失う事になる。
イルクーツクはどうにか怒りを納めると座り直し、デイ・アナに向かって声を掛けた。
「足りぬのは、どれ程だ」
「おそらく雪解け前60日分は不足になります」
広間中で、息が詰まった。しかしイルクーツクはもう動じることなく
「解った。明日から全員で草を刈る」
決定事項を口にした。しかし、デイ・アナは追及の手を弛めたりはせずに
「姉上はどうなりますか?」
イルクーツクに食い下がった。忌々しげにロリ・アナとデイ・アナを見比べて
「全員と言った」
「無駄なことは止めてください、鎌など持たせては余計に仕事が増えます。姉上には出来ないことが多すぎます。誰に注意をされても父上を引き合いに出し、責任逃れをしないように父上から言い聞かせてください」
男達を更に唖然とさせる要求をデイ・アナは口にした。
「儂に指図をするのか」
「いいえ、お願いです。今日姉上は弟妹達を昼、夜と飢えさせました。そして自分だけが食べ物を口にした。二度とそんな事があってはいけないと思うからです」
デイ・アナの必死さが、バルクーツクに口を開かせた。
「兄者、デイ・アナの言うことは尤もだ。これではどっちが年上なんだか解らんぞ。第一、ロリ・アナが何も出来んというのは周知の事実だ、明日連れて行ったところで足手まといだ」
広間にある顔という顔を眺めながら
「俺も、ロリ・アナについては困ったことがあって、兄者に言っておきたい事がある。うちの娘達に禄でもないことを吹き込むのは止めて貰いたい。手を汚すような下賤な仕事は相応しくないときたもんだ」
「バルク、何が言いたい」
じろりと睨み付けるイルクーツクに答えるでもなくバルクーツクは
「うちの馬鹿娘どもはロリ・アナの真似ばかりをする。どうせ真似るならデイ・アナの真似をして貰いたいと思うのが親心と、このままでは嫁の貰い手が見つかりそうもない。怠け者の嫁など誰も欲しがらんからな」
痛烈な皮肉であった。器量の善し悪しは問題にもならない、働き者の娘の方が喜ばれるもの。ロリ・アナへの侮蔑でありデイ・アナへの賛辞は、その兄達の大笑いで迎えられた。
「確かですね、伯父上。怠け者の嫁では困る、赤子のおしめも自分で洗うか?」
ザイナイルが笑いを堪えながら同意を示せば
「デイはこれから器量好しになるかもしれないが、ロリは食べるだけで動かなければ太るだけだ。怠け者で不器量じゃそれこそ嫁の貰い手が見つからない」
ダルクイルはもっと強烈にロリ・アナをこき下ろし男達の笑いを誘った。イルクーツクとデイ・アナの間に張られた緊張もゆるむ。しかし、笑い者にされたロリ・アナは余りの悔しさに広間から飛び出したかったが、そんな真似をすれば余計に笑われる。反論も出来ずにただデイ・アナを恨めしげに睨み付けるしかない。デイ・アナにしてもこんな誉められ方はごめん被りたかったし、自慢のロリ・アナを笑い者にされながら反応しないイルクーツクの方が心配になる。
そっと気付かれぬように伺えば、イルクーツクの口元が歪んでいる。
笑い声がさざめき、和やかな雰囲気の中でイルクーツクだけが不適な笑顔を浮かべていた。デイ・アナは広間に入る前に感じた悪寒を寄り一層強く感じ、恐怖が喉元を駆け上がり口から飛び出していくのではないかと思った。
「バルクよ、良いことを言ってくれた。確かに働き者の嫁は何処へ行っても喜ばれるだろう。デイ・アナは何処に出しても恥ずかしくない娘だ。ラフリエルの国王もさぞかし喜んでくれるであろうな」
「兄者・・・」
バルクーツクは一瞬答えに詰まった。弟を無視してイルクーツクは続けた。
「デイ・アナ、お前は良くできた賢い娘だ。レジナルドはつい先だって后を亡くしたばかりで、娘が一人あるそうな。お前ほどの働き者の嫁ならば喜んで迎えるだろう」
イルクーツクの猫なで声には、悪意が滴っていた。
「さて、誰を使者にした者か・・」
息子達がたまげたように
「父上!!」
イルクーツクは更に和約の条件は外に何があろうかと韜晦を続ける。まるでこれ以上に楽しいことはないと言うばかりに。広間に集った男達は困惑気味に囁き交わす。何時の間に話が、デイ・アナの輿入れに話に変わってしまったのか、訳が分からず呆然と。
イルクーツクの意を正確に読みとったのは、やはりデイ・アナだけであった。父の後ろに巨大な空洞が重なり見える。その中に蠢く物までがデイ・アナを見つめ続けている。悪寒と服の下を流れる汗だけが、デイ・アナに感じられる現実になった。
イルクーツクの後ろで蠢く物がのたうちながら触手を伸ばす。憎悪の炎、恩讐の呻き、今にも父親の身体を食い破ろうとざわつく。
デイ・アナの耳に遠く音が聞こえた。それは広間のざわめきなどではなく、昔風の精霊王が教えてくれた天の歯車が回り始めた音なのだと、風の巫女は悟った。 |
