| 第3章 江戸上屋敷
女中奉公
宮ヶ谷塔を出たトクが、中山道を通り日本橋に着いたのは、万延元(1860)年春先の夕暮れ時だった。長さ28間(約50㍍)の日本橋は、東海道や中山道など日本の主要幹線の基点になるところ。
清吉は、欄干にもたれてトクを待っていた。
「どうしたんだ、赤ん坊は?」
清吉は、彼女が栄三郎を背負っていないことに首を傾げた。トクは、発つ間際に祖父に取り上げられたことを告げた。
「それでも、あたしは宮ヶ谷塔を離れたかったの。あんな家には1日たりともいたくなかったから」
頼りにする男を前にして、息子と別れた事情を話していると、知らず知らずに涙が溢れ出た。
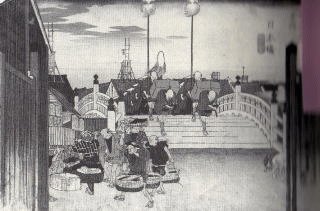
広重画「日本橋の朝」
「仲間に紹介してもらった口入屋(くちいれや)(奉公人を斡旋する店)には、赤ん坊と一緒の住み込みでって頼んであるんだが」
清吉は困惑気味だったが、すぐに気を取り直した。
「考えたってどうしようもねえや。あした一緒に行って理由(わけ)を話そう。何とかなるだろうよ」
清吉はあらかじめ頼んであった近くの旅籠に案内した後、翌日の仕事があるからと言って帰っていった。道中はそんなに気にならなかったことだが、宿に一人取り残されると、そばに赤ん坊がいないことが無性に切なくて涙があふれ出た。
翌日の昼過ぎに迎えにきた清吉は、トクの手を引いて八丁堀の口入屋の暖簾(のれん)を潜った。応対に出た番頭の与助は、トクが独り身であることを聞いてむしろホッとした様子である。
「実はね、赤ん坊と一緒でいいと言っていたお店(たな)が、急に断ってきてさ。清吉さんからの頼まれごとだし、何とかしなきゃと探していたら、さる大名屋敷のお武家さんから、一人身の女を探しているって話があってさ。行ってみるかい?」
大名屋敷での女中奉公と聞いて、一瞬腰が引けた。でも、仕事を選ぶ余裕など自分にはないことくらい分かっている。
翌日、トクが1人で口入屋を訪ねると番頭の与助が待っていて、さっさと前を歩き出した。
八丁堀の店から西に向かい、芝増上寺の門前に出た。途中目に入るものすべてが珍しくて、首を左右に振っているトクを与助がたしなめた。
.gif)
芝増上寺
「これから長いこと江戸で暮らすんだ。珍しいものは後の楽しみにとっておきな」
生まれて初めて武家屋敷に入るわけで、歩いていくうちに体中が強張(こわば)ってくる。
「お武家さんだって、同じ人間だ。怖がることもないし、珍しいこともないさ」
「お屋敷では、お殿さまにも会えるの?」
「馬鹿だな。お前が働く屋敷のお武家さんと殿さまじゃ身分が違い過ぎるわ。だから殿さまとは住む場所も違うのさ。生涯お顔を拝むこともなかろうよ」
トクを案内しながら、与助は江戸での暮らし方や武家屋敷での作法などを伝授した。連れて行かれたところは、三田赤羽にある久留米藩の上屋敷であった。
上屋敷は、新堀川(現古川)に架かる赤羽橋を渡ったところにあった。屋敷の面積が2万4000坪もあると聞いて見渡すと、遥か彼方まで高塀が続いている。久留米藩と隣り合わせに、薩摩藩など名だたる大名屋敷が連なっていると言う。現在の三田国際ビルや三田病院・済生会病院・赤羽小学校などがすっぽり納まる広さなのである。
屋敷内には、藩主とその正室が住む御殿があり、御殿の周りに家来たちの住居や諸役所・倉庫・武道場などが建てられているとも、与助が教えた。
当時の久留米藩主は11代目の有馬(ありま)頼咸(よりしげ)で、正室は精姫(あきひめ)であった。精姫は徳川将軍家の養女で、元は天皇家縁続きの有栖川家(ありすがわけ)の姫君だという。
広い通りを歩いていて、ひときわ目に付くのが火見櫓(ひのみやぐら)。
「あれは、久留米藩が増上寺を見張るための櫓だよ」
屋敷を囲む塀の西方に、何十本もの幟(のぼり)がひるがえっている。「あれは水天宮」と、与助が一つ一つ説明した。

広重が描いた、久留米藩上屋敷を囲む高塀と新堀川
(幟の見えるところが水天宮。上方櫓から増上寺を見張る)
久留米(有馬)藩の石高は21万1000石で、江戸屋敷は上・中・下からなる。上屋敷には、大名夫妻が住む御殿が建っている。中屋敷と下屋敷は、上屋敷の避難用として位置づけられているとか。
江戸市中を護衛するのは地方大名の重要な仕事である。いったん急ある時の備えを怠ろうものなら、当該藩の存亡すら危機に陥ることになる。万一増上寺で不始末が起きれば、久留米藩取り潰しも覚悟しなければならない。
勝手を知っている与助が、水天宮御門脇の引き戸を開けて中に入っていった。門番に用向きを伝えると、しばらく待たされて、身分の低そうな中年男が現れた。与助はトクを男に引き渡すと、振り向きもせずに立ち去った。
不安この上ないトクは、神妙に男のあとをついていくしかない。案内する男は、江戸詰めの久留米藩士戸田覚左衛門の中間(ちゅうげん)で源助と名乗った。中間とは武家の奉公人で、足軽のもう一つ下に位する身分のことをいう。
トクもその時初めて自分が戸田家の女中になることを知った。
屋敷の中の水天宮
雇い主の戸田覚左衛門は、久留米藩の大小姓(おおこしょう)で15人扶持の身分である。大小姓の主な役目は、藩主の身近にいて気を配ることであった。
覚左衛門の家族は、妻美智と母親摂子の三人暮らし。中間(ちゅうげん)の源助は離れの小部屋に住んでいる。最近までいた女中が暇を貰って田舎に帰ったため、その後釜としてトクが雇われたというわけである。
上屋敷内に見える御殿が藩主夫妻の住居で、次に大きな建物は江戸詰め中の家老や御用人など上級武士が住むところ。そのそばに、久留米藩の役所が設けられていた。上屋敷には千人以上の藩士とその家族が住んでいると聞かされた。
上屋敷内での住居の位置はそのまま身分の上下を表し、上級武士と覚左衛門のような中級武士の家族が屋敷間を行き来することは原則禁じられていた。トクは、源助の先導で道路脇に建てられた戸田家の勝手口を入った。勝手口そばの小部屋で待っていると、主人の覚左衛門とその妻美智が姿を現したが、主人はすぐに消えた。残った美智が屋敷内を案内し、これからの仕事を言いつけた。
その日女中部屋に落ち着いたのは、夜も遅い時刻だった。翌日からはひと息つく暇もないくらいに働いた。家の内外の掃除、主人夫婦と母摂子の身の回りの世話、出入り商人への応対、朝昼晩の食事の準備と後片付けなど、あっと言う間に1日が過ぎてしまう。
「私の部屋においで」
3日たって、覚左衛門の母摂子に声をかけられた。還暦を迎えたばかりの摂子は、武家の女らしく、背筋をピンと伸ばして上座で待っていた。
「トクと言いましたね。嫁は何かと口うるさいところがあるゆえ、我慢して奉公に励むように」
かしこまっているトクに、摂子は家族のことや武家屋敷での年中行事など女中としての心得を伝えた。摂子も嫁の美智も江戸生まれの江戸育ちで、国元のことなど何も知らないと言って苦笑した。
戸田家と並んで建つ50戸は同じような身分で、住民同士は自由に行き来していると摂子が説明した。隣家の今井市九郎の妻静江からは、わからないことは女中のウメに教わるようにと言ってくれた。
.gif)
水天宮の跡地(中之橋側の三田病院角地)
摂子から「水天宮さまにお参りしましょう」と誘われた。現在東京蛎殻町(かきがらちょう)に祭られている水天宮は、当時ここ久留米藩の上屋敷内から移されたもの。
「こちらの水天宮さまは、お国元の筑後川岸にあるお宮さまから分祀されたものだそうですよ。 そんなこともあって水難除けにご利益のある神さまです。また、安産のお手本みたいなお犬さまがご縁で、懐妊された女の人が大勢お参りにいらっしゃいます」
水天宮は上屋敷の塀の内にあるが、毎月5日だけは、江戸市民がお参りできるよう開放されるとも聞かされた。
忙しい昼間と違って、夜の女中部屋は一人だけの世界となる。夜が更けてくると、宮ヶ谷塔に残してきた赤ん坊が、母の乳房を探していないかと胸を締め付けられる。
国元の町人
トクが戸田覚左衛門の屋敷に奉公に上がってすぐの万延元(1860)年3月、屋敷内が騒がしくなった。使いから帰る途中に、隣屋敷のウメに呼び止められた。雪が散らつく午後であった。
「お城(江戸城)で、ご大老さまの身に、大変なことが起こったみたい」
ウメが言う大事とは、江戸城の桜田門外で大老の井伊直弼(いいなおすけ)が水戸浪士らに暗殺された事件のことである。この事件を機に、260年続いた徳川幕府の時代が一挙に崩れていくことになる。トクが奉公に上がる前後は、日本政治が激動する時代であった。
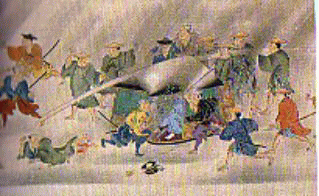
桜田門外の変図
江戸に来て、1年2年と時が過ぎていく。トクは、摂子や美智の使いで町中に出て行くことが多かった。日本橋あたりを歩いていると、どうしても道行く人の衣服に目がいってしまう。絹を素材にした縮緬(ちりめん)や紬(つむぎ)を身につけた町娘の華やかなこと。つい見とれて立ち止まることも。
自身が宮ヶ谷塔で織っていた木綿の縞織物を改めて眺めると、絹織物に劣らず見栄えが良い。子持ち縞の半纏(はんてん)をまとった女の艶姿(あですがた)は、宮ヶ谷塔時代には想像もできなかったことであった。
江戸には、関東平野全域から種々の織物が運び込まれてくる。溢れるばかりの人で賑わう江戸庶民には、江戸城内でのすさまじい権力闘争など、関わりのないことのようにさえ見えてしまう。

江戸で流行の子持ち縞半纏
「待たせたな」
トクは町に使いに出るとき、幼馴染の清吉に会うことを楽しみにしていた。摂子が、美智には内緒で寄り道を許してくれている。二人は、めし屋の二階に座り込んだ。トクが江戸に出て来て3年が経過した頃である。
「久し振りに宮ヶ谷塔に帰って、お前の家の話も聞いてきたぜ」
清吉の冴えない声に、悪い予感が走った。
「去年の暮れにおばあちゃんが亡くなったって」
背筋に何か冷たいものが突っ走ったような衝撃を覚えた。
「それで、栄三郎はどうなったの。誰か面倒みてくれているかしら」
「小深作の親戚に引き取られたんだと。とてもじいちゃんだけでは幼子(おさなご)の面倒はみきれねえだろうし」
今にも立ち上がって、実家に戻りたい衝動に駆られる。
「大丈夫だって、おふくろが言っていたぜ。叔父さんのところは、みんな喜んで栄三郎の面倒を見てくれてるって」
「それで、清吉さんところのおばさんは元気にしているの」
揺れ動く気持ちを抑えるために、話題を替えた。
「今のところはな。だが、年齢(とし)も年齢(とし)だし、いつまではたを織っておれるやら」
「清吉さんの帰りを待ってるんじゃないの」
「そうだけどさ。今の仕事も投げだせないし、それに・・・」
「なに?」
清吉の次の言葉が気になった。
「お前のこともさ。女が一人、この大江戸でやっていけるのか心配でな」
「心配しなくていいよ、あたしのことなら」
そんなことを言うつもりはないのに、言葉が勝手に飛んで行ってしまう。
「そうだ。トクに渡してくれって、おふくろからの預かりもんだ」
清吉が懐から取り出したのは、縞織の端切(はぎ)れだった。
「トクが田舎を出た頃に江戸で流行り出した『二タ子縞(ふたこしま)』だって」
手にとった端切れは、自分が織っていた頃にはなかった、糸入り(絹使用)が一目でわかる華やかさを備えていた。
「織りだして、まだ10年くらいしか経っていないらしいぜ。なんでも、川越あたりから始まったらしいと、おふくろは言っていた」
清吉が差し出した二タ子織は、絹の産地でも知られる川越地方で編みだされ、その後岩槻や蕨でも織られるようになった。ヨーロッパ方面からの輸入糸使用が可能になったのが、二タ子織が世に出る最大の要因である。
「織物も、どんどん進んでいるんだね。でも、はた織りを止めたあたしには関係ないか」
「おふくろがトクにって、持たせてくれたもんだ。お守(まもり)代わりに持っておきな」
清吉は、二タ子縞の端切れをトクに手渡すとすぐに立ち上がった。
江戸の上屋敷で働くようになって、6年が経過した慶応2(1866)年の夏である。
トクは屋敷内の水天宮に出向いた。江戸の庶民に開放される毎月5日以外は、境内も閑散としている。拝殿で最初に願うことは、やはり息子の無事であった。栄三郎もやがて7歳になり、遊び盛りであるはずだが・・・。
「えらい熱心だね」
背後から声をかけたのは、紺の半纏(はんてん)をまとった若い男であった。トクより3歳か4歳は年下に見える。
「ごめんよ。びっくりさせるつもりはなかったとばってん」
屋敷内でも聞き慣れない言葉であった。
「あんた、誰?」
「俺の名は末吉。筑後ん久留米で大工の棟梁(とうりょう)ばしとる宗野家の4代目たい」
この男が話している言葉が、国元の訛(なま)りなのか。そのうちに、若者が悪い人間ではないように思えてきた。

宗野末吉(宗野吉博氏提供)
「お武家さんでもないお国元のあんたが、どうして江戸の屋敷にいるのさ」
二人は、境内に設けられた板台に、並んで腰をかけた。末吉と名乗った男は、屋敷内の普請や小間物を揃えるなどして、お武家さん方から結構重宝がられているのだと自慢した。
「俺が江戸に来る建前は、江戸屋敷の中で壊れたところば修繕することたい。ばってん・・・、本当のところはお殿さまからついて来いち言われただけ」
若者は、こちらから聞きもしないことを勝手にしゃべる。
「嘘でしょう、あんたなんかが、お殿さまから直接言葉をかけられたなんて、信じられないわ」
この男、女の前では背伸びをして見せる癖があるのかなとも思った。
「あれ、俺のことば信用しとらんごとあるね。これはほんなこつ(本当のこと)たい。俺は町民のくせに、お侍と同じごと苗字ば使うてよかちも言われとるとばい。じゃけん、俺の名前は、宗野末吉」
初めて会う男だが、まんざらのほら吹きでもなさそうだ。
「殿さまは、機械のごたるもんがほんにお好きじゃけん。・・・例えば時計なんぞ」
「時計?」
「そう、時を知らせる機械のこと。殿さまは、国元のお城でも西洋時計ば大そう重宝がられておった。崩れ(故障し)たりすると、大工なら直せるじゃろうと、俺に。何とか修繕ができたら、今度は江戸に着いて来いち」
「それで、江戸に出てきたというわけ? その西洋時計とはどんなもの?」
「お前が知っとるのは、古くから日本で使われてきた時計たい。夏と冬じゃ昼と晩の長さが違うけん、季節ごとに針ば調節せにゃならんじゃろ。ばってん、殿さまがお好きな西洋時計は、夏も冬も、昼も晩も同じだけ時ば刻むけん、そげな面倒なこつはせんでもよかと。1日ば24で割って、それば1時間とするとたい。1時間が12回で半日が過ぎたことになり、それが2周すると、1日が終わるという仕掛けたい。機械はゼンマイで動かすとばってん、やっぱり崩れたり(故障したり)するもんじゃけん・・・」
目の前の男は、時計のことを話し始めると止まりそうにない。新しいものに興味を持つ殿さまなら、末吉のような若者をそばに置きたがるのも頷(うなず)ける。
.gif)
東京港区三田赤羽橋(旧久留米藩江戸屋敷あたり)
「詳しいのね」
「ちょっとな。商売が大工じゃけん、生まれつき手先の仕事が得意なだけたい」
「それであんた、いつまで江戸にいるの」
「それは殿さまのご都合次第。来年の国元ご帰還の折かな、久留米に帰れるとは」
もっと会話を楽しみたかったが、仕事のことを考えるとそうもしておれない。
「また聞かせてね、時計の話」
「おいおい、時計のこつばかりでよかとね。江戸屋敷の修繕の話は・・・」
「それもまたの機会に。それより、お国元の久留米ってどんなところ?」
「結構賑(にぎ)やかな町ばい。10年前までは飴屋(あめや)かおこし屋くらいしかなかったとばってん。このところ、生姜糖(しょうがとう)とか窓の雪とかいうしゃれたお菓子屋もあるし。蕎麦屋(そばや)では、蒲鉾(かまぼこ)や鯉(こい)の吸い物、鳥の吸い物まで食わせてくれる。やっとることは江戸とそう違いはせん。ところで、あんたの名前ばまだ聞いとらんが」
末吉も久しぶりに同年代の女と話をして気が昂(たか)ぶっているのか、用事があるからと話し半ばで去っていくトクを未練がましく言葉で追いかけた。
恋人との別離
「国元の久留米では、毎年のように筑後川が氾濫して、大きな被害が出ているそうですよ」
摂子は、知っていることを何でも話してくれる。覚左衛門の妻の美智はというと、妊娠の兆候もあってか不機嫌な日が多かった。
間もなく美智が女の子を出産した。慶応3(1867)年の正月である。赤ん坊にはモトと名づけられた。トクは出産の前後からまた忙しくなった。なにしろ子供を産んだ経験者であり、覚左衛門や摂子は何かと彼女を頼りにする。
「大変ね、トクさんも」
たまたま近所で赤ん坊の誕生があり、乳を貰いに出かけるうちに女中仲間が声をかけてくれる。
「お嬢さまのお顔を見ていると、自分の子の顔と重なってしまって。それが辛いのよ」
そうこうしているうちにも、世の中の動きはますます早まっていった。元土佐藩士坂本竜馬の働きで、薩摩と長州の連合が成立したのが慶応2(1866)年の1月である。翌慶応3年10月には、徳川家茂(いえもち)の跡を継いだ徳川慶喜(よしのぶ)が、朝廷に大政奉還の上奏文を提出する。
そんな幕末のある日、トクは覚左衛門に呼ばれた。座敷に赴くと、摂子が先に来ていて、中間の源助とともに覚左衛門の入室を待っていた。そこにいるはずの美智がいないのを不審に思いながら、トクは1歳の誕生日を迎えたおモトを膝に乗せて源助の隣に座った。
「屋敷内の動きで、おおよそのことは感じておろうが・・・。徳川さまは新しく出来た政府にお城を明け渡されることになった。本日殿からお言葉があり、屋敷に住む者はなるべく早く家族を伴って国元に帰るようにとのことだ」
来るべき時が来た、トクは主人の話を聞きながらそう思った。
「お名残り惜しゅうはございますが、大変お世話になりました」
トクは覚左衛門と摂子に深々と頭を下げた。その時、何故だかわからないが、清吉の顔が脳裏をさまよった。
幕府から諸大名への締め付けも大幅に緩められた。莫大な費用を要した各藩の江戸屋敷は縮小され、「御国勝手」という名目で、江戸詰めの武士たちを国元に帰すことが許されたのである。
「違うのだ。トクには母上とモトを久留米まで送り届けて欲しいのだ。察しておろうが、妻は久留米など田舎には行きとうないと言って、既に実家に帰ってしもうた。道中においてモトの面倒を見れる者はトクしかいない。娘が不憫(ふびん)と思って同行してはくれまいか」
「それはなりません。私にだって一人息子が・・・」と言いかけて言葉を飲み込んだ。
「トクの気持ちもよくわかる。母上とおモトを送り届けてくれれば、久留米におられるお住居(すまい)さま(藩主夫人)が江戸に戻られる折に、同行を許してもらうようお願いする」
「ご主人さまはどうなさいますので?」
「長年続いた徳川さまの世が終ったばかりで、これから先、殿の身に何が起こるかわからない。それゆえ、今しばらくは江戸に残らなければならん。落ち着いたら急ぎ久留米に向かうつもりだ。それまで母上とおモトには辛抱してもらうしかない」
その時覚左衛門の顔は、トクや源助の主人というより、母から見捨てられた哀れな娘の父親にしか見えなかった。
トクは摂子に頼んで1日だけ暇を貰った。清吉にこれからのことを相談するためだった。屋敷の門を出ると清吉が待っていて、二人は高輪の海に突き出た料理茶屋に上がった。遥か彼方に房総半島が眺望できる部屋である。
座敷の向こう側では、上役らしい中年の男が、若衆5人と永の別れを惜しんでいた。ここは江戸市中から東海道に出る境目であり、別れの場所でもあった。木戸のあたりにはそのための茶店が軒を連ねている。
「あたしはこれ以上栄三郎のいるところから遠くへ行きたくない。主人の頼みは断るしかないのかな」と、トクがきりだした。
「江戸のお屋敷がなくなれば、お前の居る場所もないな」
「・・・・・・」
二人の間に沈黙が続いた。その間トクはうつむいたままだった。
「でも、母上に見放されたお嬢さまを放ってもいられないし・・・」
そんなことを言いながら、清吉から「俺の嫁さんになれ」と言われるのを期待している自分が恥ずかしかった。

旧久留米藩上屋敷近くの史跡
「トクちゃんの相談に乗ってやれるのも、このへんまでかもしれないな」
考えてもいなかった清吉の言葉に、こちらで用意していた言い分を逸してしまった。
「前にも言ったろう。田舎のおふくろがてっきり弱ってな。おいらの江戸での暮らしもここらが潮時かなと思っているのさ。宮ヶ谷塔に帰って、遅まきながら嫁を貰い、母ちゃんを安心させなければ・・・」
自分の今後を述べる清吉の口元を覗きこみながら、永遠の別れを告げられているのだと悟った。
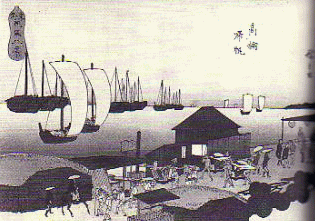
高輪の大木戸
「そうだよね、あたしのことばかりにかまっていたら、年をとってしまうもんね。それにお世話になったおばさんがあんたの帰るのを待っていると聞けば、これ以上そばに居て欲しいとは、いくらずうずうしいあたしだって言えやしない」
この人の嫁さんになると心に決めた娘時代からの夢も、これですべておしまいだと実感した。
「じゃあな、体だけは大事にしろよ。遠くにいても、トクちゃんの無事を祈っているからさ。それに、落ち着いたら、おふくろからの端切れのお守りを出して見るのもいいさ。また好きなはた織りが始められるといいな」
藩邸の水天宮御門まで送ってきた清吉は、大きく手を振って別れを告げると、そのまま増上寺方向に走り出した。
「おーい、そこにおるのはこの前の姉(あね)さんじゃなかか」
高塀の窓から聞き覚えのある声がした。いつか水天宮で語りあった大工の末吉だった。
「ああ、あの時の・・・。この間はご免なさい。私の・・・」
「いいからそこにおらんね。すぐ下りていくけん」
末吉とは、江戸に出てきてすぐ水天宮境内で会って以来であった。その後国元に帰ったのだが、最近再び江戸にやってきたのだと言う。二人は以前と同じように水天宮境内の板台に腰を下ろした。
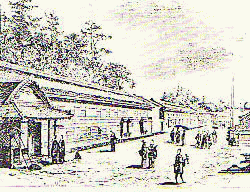
幕末の有馬藩江戸屋敷
「殿さまの遊びが増えたもんで、また呼ばれたとたい。ところで、何?」
末吉は、先ほど呼んだとき言いかけたトクの言葉の続きを促した。
「ご免なさい。前に会った時自分のことを名乗りもしなかったわ。私は戸田さまのお屋敷で女中奉公をしているトクと言うの」
トクは、生まれ故郷から江戸に出て来たいきさつを、かいつまんで話した。
「私ね、田舎にいるときは、はた織りばかりしていた」
「そうかい、はた織りが好きたいね。久留米にも、井上伝さんというお人がおって、大勢の娘にかすり織りば教えとらすけん。ほんに盛んばい」
末吉も、トクの苦労に同情しているようだ。「自分も近日中に久留米に行くかもしれない」と言いかけたが、やめた。まだ、覚左衛門の要請にどう答えたらいいか迷っていたからである。
「ところで、末吉さんは、いつ久留米に帰るの?」
「きのう殿さまに呼ばれてな。こちらにおるうちに、時計修理の修業ばしておけち言われた。そこで、横浜あたりの時計屋に弟子入りばしようち思うとる」
目の前の青年は、ずっと先の世の中を見て生きている。だが、彼が見る彼方に何があるのか、トクにはわかりようもなかった。
「もう二度と会うこともなかろうばってん。元気でな。それに、息子さんば大事に育てろよ」
末吉は、話し足りないトクの気持ちを無視したまま、水天宮御門の外に出ていった。
江戸を発つ
トクは、清吉と別れた夜、おモトに付き添って久留米まで行くことを覚左衛門に返事した。そばで聞いていた摂子は、目頭を拭きながらトクに頭を下げた。
主人の要請を受けたものの、気持ちが完全に吹っ切れているわけではない。女中部屋に戻ると涙が止まらなかった。どうしてこんなに悲しいのか、自分でも説明ができない。息子のいる宮ヶ谷塔から遠く離れる辛さなのか、江戸に未練が残るのか、また初恋の清吉に、今生(こんじょう)の別れを告げられた悲しさか。そのいずれでもないような気がする。
摂子と誕生日を過ぎたばかりのおモトが、トクに率いられて江戸の上屋敷を出立しのは慶応4(1868)年の5月5日であった。国元帰還の3家族と連れの旅である。
久留米までの経路は、藩主の参勤交代に倣って、東海道から山陽道を経る陸路となった。
年老いた摂子に気を使い、未だ乳飲み子同然のおモトを抱いて、通し駕籠に乗っての長旅であった。その頃駕籠は庶民にとって高嶺の花だったが、藩が世話をしてくれたから安心である。
江戸を発って3日目には小田原から箱根の山を越えた。富士の山がよく見えたが、絶景を楽しむ余裕などトクにはなかった。最初は機嫌がよかったおモトだが、駕籠に退屈するとぐずりだす。摂子は腰が痛いと言っては駕籠を止めさせた。大雨による川止めなど予想外に時間を食い、大坂を経由する頃には既に1ヵ月も経っていた。
その間に立ち寄る茶店や宿で、国内での不穏な動きを聞かされた。一行は山陽道に別れを告げて、赤間関(現山口県下関市)から渡し船に乗り小倉に上陸した。いよいよ国元と陸続きの九州路である。小倉から長崎街道を更に筑後へ。
この頃には、それぞれの事情で、他の同行家族とも別々の道行きになっていた。江戸を発って48日をかけて、松崎宿(現小郡市)に着いたことになる。宿場には、大名の参勤交代に使用される本陣や脇本陣のほかに、一般の客が泊まる旅籠(はたご)が2軒あった。トクはあらかじめ聞かされていた屋号を見つけると、ためらわずに暖簾を潜った。
「戸田さまでっしょ、久留米からお迎えの人が来とらすですよ」
小倉を発つとき、飛脚に頼んで、覚左衛門の伯父宛に松崎宿での宿泊とその後の久留米到着の予定を知らせてあった。だが、手紙を受け取った伯父が迎えを寄こすことまでは考えていなかった。
「お待ちしとりました」
部屋に入るなり、女がきつい地訛(じなま)りで挨拶した。どこの誰かも聞かされていない摂子やトクが不思議な気持ちで顔を見合わせた。
「覚左衛門さまの伯父上にあたる柴田時右衛門さまの使いのもんです。みなさんは久留米が初めてということですけん、私がお世話ばするごと言いつかったとです」
シゲと名乗る女の年恰好は、トクとそう違わない。亭主が時右衛門の屋敷に出入りしている大工という縁で、戸田家の世話を頼まれたのだと告げた。
.gif)
面影が残る松崎宿
見知らぬ土地で不安ばかりが先走っているトクにとって、シゲの登場は地獄で仏に巡り会ったような心境だった。長旅の最後の宿場ということもあって、その夜は江戸での出来事や久留米の話を出しあって賑わった。おモトだけは早々に深い眠りについた。迎えにきたシゲという女が、これから先トクの暮らしに大きく関わっていくことなど、そのときは考えようもなかった。
「もうすぐ筑後川ですけん」
翌朝松崎宿を出立した一行は、シゲの案内で久留米を目指した。宝満川に沿って2里(8㌔)ほど進むと、大きな川が行く手を遮った。
「これが、お話に聞いていた筑後川ですね」
摂子が感慨深そうに、川の流れに見入った。渡し場は、現在の国道3号線のすぐ下流にあたる。
「渡し船に乗れば、落ち着く先の新廓(しんくるわ)はすぐそこですけん」
シゲが説明した。
「息子からは、行く先が新廓(しんくるわ)だとは聞いていませんが」
摂子が困惑顔でシゲに問い直した。
「お城では、江戸からお戻りのお武家さまのために、上妻街道(こうづまがいどう)(現国道209号)沿いに120軒もの屋敷を造られました。ばってん、これからも毎日お城に上がられるお方には、新廓の屋敷も設けられたとです」
.gif)
現在の筑後川
訛りがきついシゲの説明を、トクは上の空で聞いていた。目の前の大川を渡ってしまえば、二度と引き返せない怖ろしい川に見えたからである。川幅いっぱいにゆったりと流れる大河は、ちっぽけな人間の我がままなど絶対に許してくれそうにない。できることなら、川を渡る前に江戸に引き返したい。
「舟が出ますよ」
シゲに背中を押されて我に返ったトクは、おモトを抱いて渡し舟に乗り込んだ。振り返らないよう自身に言い聞かせながら、じっと川面を見詰めていた。
|

