| ��Q�́@�����A�{���J��
���]�˂ɑ���������
�@�g�N�́A�������̎q�͊�(�����̂�����)�̉חg����ɍ��荞��ŁA�l�v�����̓�������Ă����B�̎q�݂͊Ƃ́A�ޏ����Z�ދ{���J���߂��𗬂�鈻����ɑ���ꂽ��`�̂��ƁB�g�N�́A���N�W�i�����N�j�ɂȂ�������̏��̎q�ł���B
.gif)
���Ă��̎q�͊�
�u�܂����Ă�ˁv
�@�݂͊ʼnׂ̗g�����낵���d�鐭�O���A�d���̎���x�߂ăg�N�ׂ̗ɍ������낵���B
�u���̑D�ɂ͉����ς�ł���́H�v
�@�m�肽���Ǝv�����킯�ł͂Ȃ��̂ɁA�����Ă��܂����B
�u�����A�ωׂ̂��Ƃ��B�����炪���낵�Ă���̂́A�݂�ȍ]�˂���^��ł������̂��v
�u�]�˂��āH�@���̐�͂��]�˂ɑ����Ă���́H�v
�u�������B�����Ɖ����Ă����r��ɏo�āA��������]�˂̐^�ɍs�����̂��v
�u�ւ��A���]�˂Ɍq(��)�����Ă���B����ŁA�ו��̒��g�́H�v
�u�c��ڂ┨�ɎT(��)����₵����B����ɁA���Ƃ����Ƃ��A���Ȃ��ȁv
�u�ǂ����āA���]�˂���H�v
�u��₵�Ƃ����́A���̕ӂł͑����Ă��Ȃ�����ˁv
�@�����Ȃ�����A�g�N�̎���͎~�܂�Ȃ��B
�u���̑D�́A�܂����]�˂ɖ߂�́H�v
�u�D�����������x��ł�ɂȂ�����B�ωׂ����낵����A���x�͂�����ׂ̉��ڂ��č]�˂܂ʼn^�Ԃ̂��v
�u������̉ו����āH�v
�u�ق�A���s��(�͂炢���ǂ�)��ʂ��Ĕn�Ԃ������������Ă��邾�낤�B���̎Ԃɏ���Ă���Ă┞�����]�˂ɉ^�Ԃ̂��v
�@�ڂ̑O�̉ו����A����܂ł͂��]�˂̂ǂ����ɂ������Ǝv�������ŁA�g�N�ɂ͕s�v�c�ȋC�������N(��)���B���̐�`�A�]�ˊ����疾���`�吳�܂ŁA�����i�]�ˁj�Ɗ��(�����)�E��{�n������ԉݕ��A����i�Ƃ��āA�d�v�Ȗ�����S���Ă����B������ɂ́A�̎q�݂͊̂ق��ɂ��A�㗬�E�����ɂ������̐�`���A�Ȃ��Ă����B
�u���ꂶ��A�����������̑D�ɏ���Ă���A�����ɂ͂��]�˂ɍs����ˁv
�u���������A�����Ȃ��Ƃ��l�����Ȃ���B���̑D�͐l���܂��悹�����Ȃ�����ˁv
�@���Ȃ��琭�O�������オ�����B
�u���܂���A���܂ʼn��낵�Ɏ�Ԏ���Ă�B���낵����A�������Ƃ����̕U��ςݍ��߁v
�@���O�ɓ{���āA�Ⴂ�O�̍�Ƃ��Z�����Ȃ����B�݂͊ɂ���ׂ��y�X�ƒS���A���X�ɍb�ɐςݏグ�Ă����B
�u�����A�o�`���v
�@���O�̍��}�ŁA����܂ʼnׂ̗g�����낵�����Ă����A�����A���x�͗��݂ɕ�����āA�D���w��(�ւ���)�Ɋ�����Ă���j�������������B
�@�������̎�̉^���D�ɂ͔����@�͂��Ă��炸�A�l�Ԃ����݂��烍�[�v�ň��������Ă����B�����ɏo��ΐ앝���L���Ȃ�A�����ő傫�Ȕ��|���D�ɐςݑւ����đ��ɏo��B�̎q�݂͊̒j�����̎d���͂����܂łŁA�D���̎q�݂͊��疭���͊݁i���葺�j�A�V�͊݁i�V�a���j�A�����͊݁i�������j�A�J�ÉF�͊݁i�k�����S�������j�ʼnׂ�ςݑ����Ȃ���A���c����o�č]�˂̍`�ɒ������ƂɂȂ��Ă����B�j�őD����������j�����ɂƂ��āA����͊y�����A����ɋt�炤���͂S�`�T�l���͔C���őD�������d�J���ł������B
�@�g�N�͗������������̎q�݂͊ɗ��āA����Ɠ����ꏊ�œ����悤�ɒj�����̗͎d���߂Ă����B�V�ђ��Ԃ��A����(�ނ�Ȃ�)�̊o���@(������������)�ɐ݂���ꂽ���q���ɏo������Ԃ̉ɂԂ��ł���B

�o���@�i�{���J�����j����ē��j
�g�N���Z�ދ{���J�����́A���݂̓��k�����ԓ���C���^�[�ɋ߂��A������c���̎���(�ȂȂ���)�w�Ɗ�Ήw(���������)�̒��Ԃɂ�����B�n���̑�{���炾�ƁA15��������Ă���Ύ����w�ɓ������鋗���ł���B
�@�g�N�́A�����ېV����k�邱��30�N�قLjȑO�̓V��10�i1839�j�N12���P���ɁA�_�Ƃ��c�ޏ���Ƃ̑P�ܘY�E�`�G�v�w�̊Ԃɐ��܂ꂽ�B�ޏ����U�ɂȂ������ɁA���e�Ƃ��͂��a�ɏP���Ă��̐����������B���e�̈�̂́A�Ƃ̗��ɂ��鏬��Ƃ̕�ɖ������ꂽ�B
�@����̖@�v�̓��A�g�N�͗��e�������̑O�ɂ����B��ł���o���@�̏Z�E�́A�����𗧂Ă�Ƃ����ɓnjo���n�߂��B�g�N�ɂ͏Z�E��������o�̗}�g���A���ƕ��ӂߗ��ĂĂ���悤�ɕ��������B
�u���₾�A�������A�ꂿ���������߂����͍D����v
�@�ˑR�Z�E�ɐH���Ă�����ƁA���̂܂܋삯�o�����B���s�����班���������Ƃ���̕X��_��(�Ђ��킶��)�ɒ����ƁA�q�a�̊K�i�Ɋz���������ċ������Ⴍ�����B�����߂����̂��A�����ł��킩��Ȃ��B
�@�c���Ƒc��́A�����ɋ�������X(��)�˂��肷�鑷���ɁA�قƂقƎ���Ă��Ă����B����ł��A����Ƃ𑶑������邽�߂ɂ́A���̈�l����e���ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
.gif)
�{���J���̕X��_��
�u���悤�傫�イ�Ȃ��āA���{�q��Ⴄ�āA��v�Ȓj�̎q���Y��ł���v
�@�c���́A�������鑷�Ɍ������āA���̂��Ƃ�����J��Ԃ����B�������ƕꂿ�������A����Ȃ��Ƃ͌���Ȃ������낤�Ǝv���A���e�̕�̑O�ŋ����Ă��܂��B�ڂ̑O�̕�́A�B��Â����鑊��Ȃ̂ł���B
�@�g�N��10�ɂȂ����B���̓����A�����̎q�݂͊Ɍ����Ă����B�D���o����ŁA�݂͊ɒj�����̎p�͂Ȃ������B�d���Ȃ������Ԃ������ɁA�Q�ΔN��̐��g�̉Ƃ̑O�ŗ����~�܂����B���g�͕��S����������A�ؓo���Ɗy(����)�܂킵�������Ă��ꂽ��D���Ȃ��Z�����ł���B
�͂��D��n��
�u���ƂˁA���̎q�́A���[��(���ӂ�����)�̏f������Ƃ��Ɏg���ɍs������v
�@���g�̕�e�̈�}�́A�͂��D��𑱂��Ȃ���g�N�Ɏӂ����B���̂܂܉ƂɋA���Ă��܂�Ȃ����A���炭��}�̎d�������Ă��邱�Ƃɂ����B��}�͈ꎞ���x�ނ��ƂȂ��A���݂ɓ���(�ӂ݂�)�����Ă���B���̓����ɘA�������āA�E���獶�ւƞ`(��)�𓊂���B�`���^�e���̊Ԃ����ƁA���x�̓��R�����(����)�ŗ͋������ߕt����B�������삪�J��Ԃ���邽�тɁA�D���̖ʐς��L�����Ă����B�g�N�ɂ͈�}�̓��삪���@�g���̂���Ɍ������B
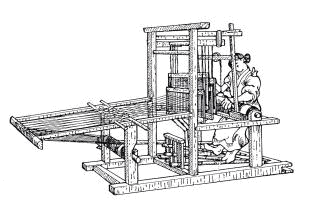
��ʒn���̍��@�i�n�s���j���������فj
�u����A���g�N�����A�܂������ɂ����́v
�@���t���ꂽ�悤�Ɍ������Ă���g�N�ɋC�����āA��}���Z��������x�߂��B
�u����ȂɁA�͂��D�肪�ʔ��������H�v
�@�g�N���ق����܂���(���Ȃ�)���ƁA��}�͑��q�̐��g�ɑ����āA���炭����߂邱�Ƃɂ����B
�u�͂��D��̂ǂ�������Ȃɖʔ����́H�v
�u������A���Ǝ�����ƁA�z(����)���ǂ�ǂ�o���オ��Ƃ���v
�u���g�N�������A����Ă݂邩���v
�@��}�ɑ������ƁA�g�N�͊��������ɂ͂��̑O�ɍ������B�w�}�����܂܂ɞ`�𓊂��A�^�e���̊Ԃɒʂ������R�����(����)�Œ��ߕt����B���@�܂œ͂��Ȃ����́A���̓s�x���݂ɕБ���L���ē��������B���Ǝ�̓����ɍ��킹�āA�u�J�^�����R�A�g���g���v�Ɖ��������Ԃ��Ă���B
�@�g�N�́A�A���Ȃ�c��̃��c���ɁA���g�̉Ƃł̂��Ƃ�����B�c��͑������͂��D��ɋ��������������Ƃ���B�����[������Â��D�@�����o���Ă��ĉ����ɐ������B�g�N�͎��Ԃ��o�̂��Y��Ğ`�𓊂��������B����Ă��Ă킩��Ȃ����Ƃ�����Ɛ��g�̉Ƃɔ��ōs���A��}�ɋ����𐿂��B���ꂪ�܂��y���������B
�@���c���́A���̂��߂ɖȂ̎���T�����B��ʒn���ł��������z�Ȃǔ�r�I���n�ł́A�K���͔|���Đ����Y�������A���(�����)�Ȃǒ�n�ł͖ȉԍ͔|������ł������B��ɋ߂��{���J���̔_�Ƃ��A���̗���Ƃ��Đ���ɖȂ��͔|���Ă����B
�u����Ȃɂ��ꂢ�ȕz(����)��D�邱�Ƃ��A�N���l���������́H�v
�@�g�N�́A�ؖȐD��̂��Ƃ������ƒm�肽���āA��}�Ɏ������B
�u���g�N������܂�邸���ƑO�̂��Ƃ����ǂˁB�ˉz���ɍ����V�ܘY����Ƃ����l�����ĂˁB���̂��l���H�v���āA�����ɂ���悤�Ȃ͂��D��@�B�����Ȃ�������������v
�@��}����鍂���V�ܘY�́A�{���J���������ɂR���i12�`�j�̒ˉz���i���n�s�j�ɏZ�ޕS���ł������B�_�Ƃ����ł͕�炵���������āA���ƂŖa�����Ȏ����A15���i60���j�����ꂽ�����܂Ŕ���ɏo�����Ă����B
�@�V�ܘY�̑��q�i���P�j�́A������̑����ōw���������@(������)�Ő�(��������)��D��n�߂��B�ȂƂ́A���Z(�͂�Ă�)�ȂǂɎg�������߂̖ؖȐD��̂��Ƃł���B�����n�ł���]�˂ɋ߂����Ƃ������āA�����͑听�������B���ꂪ�A�����Ƃł̖{�i�I�ȐD���ҋƂ̎n�܂�ł���B
�@�����V�ܘY�́A�Ȃ�o������A���x�͍]�˂̒������D�ތ��D��⌦�Ɏ������Ȃ�D�����B���ꂪ�܂��]�˂̏����ɑ傢�Ɏ��B�����ō����͎��Ɛ��Y��ł���A���ׂďo�@(������)���ɐ�ւ��A����͐e�@(�����)�ɓO���邱�ƂɂȂ����B�u�o�@(������)�v�Ƃ́A�e�@�������ĉ������炦�����āA�_�ƂȂǂɒ��D�肳���邱�Ƃł���B
�@�����̏o�@(������)�����́A�����܂��ނ��ĂсA�ߗׂɉ������̂͂������a������B�_�Ƃ̏������͌��������̎�i�Ƃ��āA�͂�������^�e���ƃ��R����a�����ĕz��D��A��Ԓ����҂��B�D�@�������Ȃ��_�Ƃɂ́A���̓s�x�͂������݂��o�����B�������̕��ƂƂ��Ă̂͂��D��́A���̌�����䐬�X��(�ɂ��������Ȃ肩���ǂ�)��`���悤�ɂ��āA�]�˂Ƃ̋��𗬂��r��߂��܂ōL�������Ƃ����B
�@�X�ɂ��̑��q�̍����V�ܘY�i���P�j�̎���ɂȂ��āA���D��⌦�Ɏ������ȐD���i�߂Ĕɐ����邱�ƂɂȂ�B���̓��ɁA��z�������Ă������l���A�A��������g������^�q�D��`���������ƂŁA�n�n���̎ȐD�͂܂��܂��i�����邱�ƂɂȂ�B���ꂪ��ɏ���g�N���v���Ēn���ŋ����o�q�D�̂����悻�̑O�g�ł���B�V�ܘY�̓�^�q�D�́A�c��42�ԁA����30�ԂȂǔ�r�I���ڂ̎��ŐD������v��_����̕z�n�Ȃ̂ŁA�_���⏤�X�̕���l�Ȃǂ̒��߂Ƃ��ďd��ꂽ�B��^�q�D�����s��o�����̂́A�g�N���{���J������ɂ��āA�]�˂Ɍ��������x���̍��ł������B
���������ďo�Y
�@�͂��D��ɋ������������g�N�́A������D��@�̑O���痣��Ȃ��Ȃ����B�`�𓊂��邾���̍�Ƃł͕�����Ȃ��Ȃ�ƁA�^�e���̊ԂɃ��R�����`�̊����A�^�e���̒������H�v����悤�ɂ��Ȃ����B15�̍��ł���B
�u�����x�݂܂��傤���v
�@�����Ă����Ύ����玟�ɋ����𐿂��g�N�ɁA��}�������������B���~�ɐ�������������ׂ������o���ƁA���ɂ��鐴�g���ĂB
�u��������Ȃɖʔ����̂��ˁA�ؖȂ�D�邭�炢�̂��Ƃ��v
�u�j�ɂ͂킩��Ȃ��̂�v
�@�g�N�������Ԃ��ƁA��}���ޏ��ɖ����������B
�u����Ȃ��Ƃ��肵�Ă���ƁA�ł���ɂ��Ă��Ȃ�����ȁv
�u���Ȃ̉ł���ɂȂ邭�炢�Ȃ�A���ق����܂������v
�@��l�̌����܂��A��}�͂���ׂ���j����Ȃ�����������ɕ����Ă����B
�@18�ɂȂ�ƁA�g�N�̂͂��D��̘r�́A�ߏ��̒N�ɂ������Ȃ����炢�ɏ�B�����B�ꂵ���_�ƌo�c���������鎞��ł���A�ޏ����͂����������Ԓ��́A�ƌv��傢�ɏ����邱�ƂɂȂ�B
�@���g��20���߂��āA�̎q�݂͊̐��O�̂��Ƃœ����悤�ɂȂ����B�唪�Ԃ��݂͊ɒ������тɁA�]�˂Ɍ������D�ɉׂ�ςݍ��ޏd�J���ł���B���̍��̃g�N�́A�������g�̉ł���ɂȂ邱�Ƃ�S�Ɍ��߂Ă����B�Q�l�́A���g�̎d�����I���ƁA�X��_�Ћ����ł̌�炢���y���B
�@����Ȑ܁A�c���̈ב��Y���g�N�ɐ^��Řb���������B
�u���O�̖������߂�����v
�@�ˑR�̘b�ŁA�ǂ������Ă悢���������܂܁A�g�N�͎�����ɐU�����B
�u���O�Ɛ��g�̂��Ƃ͑��ł��]�����B�����A�����͒��j�����A�����Ƃ͉ƕ����Ⴄ�B���O�̖��{�q�ɂ͂ł��˂��v
�@�ב��Y�̕\��ɂ́A���������Ȃ������ӎv���ɂ���ł���B�c����܂��c���̌������ɂ����������������B�c����ƃg�N�̐^�������͂��ꂩ����ӂ��������B
�@����Ȃ��Ƃ������Ă��炭���āA���g��������������B��}�ɍs�����q�˂邪�A�u�]�˂ɍs�����v�Ɠ����邾���ŁA�ڂ������Ƃ͉��������Ă���Ȃ��B
.gif)
�{���J���̋���
�@���ǁA�g�N�͑c�����p�ӂ������k���邵���Ȃ������B����͗ב��̌Ց��Ƃ����A�傫�Ȕ_�Ƃ̎��j�V�������B���ɗ����������̘b���ƁA��ς܂��߂Ȓj�œ����҂��Ƃ����B����ŏ���Ƃ����X���ƁA�c����͗L���V�ł������B
�u�܂��߂œ����ҁv�Ƃ́A������c�����g�N��������邽�߂ɍ��グ���G�ꍞ�݂ł����Ȃ������B�j�����ς�ʼn��������Ă��A�Ց��ɓ����C�z�͌����Ȃ��B��������~�ʼn��ɂȂ�������ŁA���ɏo�悤�Ƃ����Ȃ��B�[���ɂȂ�ƁA���c���ɂ˂����ċ��������o���A��x���܂ň��ݕ������B
�@����ȃO�E�^���j�Ƃ͂P���������ʂ�Ȃ���Ǝv���̂����A�c���������Ă���Ȃ��B�u�h���A�h���v���J��Ԃ�����ł���B�g�N�́A�������D�P���Ă��邱�ƂɋC�������B����ɖc���ł������������Ȃ���A����Ȓj�̎q���ȂY�݂����Ȃ��ƔY�B������܂܂Ȃ炸�A��Y�̖��ɒj�̎q�ݗ��Ƃ����B�c���͂��̎q�Ɂu�h�O�Y�v�Ɩ��t�����B����ȂɌ��������o�Y�ł��������A����ɐH�炢���q���̖ڂ����Ă���ƁA���̎q�����͉䂪�g���]���ɂ��Ăł����h�Ɉ�ďグ�Ȃ���ƐS�ꂩ��v���̂������B
�@�q�����ł��Ă��v�̗V�ѕȂ͂��������ɉ��܂�Ȃ������B����ǂ��납�A�ŋ߂ł͉Ƃ��o���܂܂R�����S�����A��Ȃ����Ƃ������Ȃ����B���܂ɋA���Ă��A���c���ɋ��̖��S�����邽�߂ŁA�䂪�q��������Ƃ����Ȃ��B
�@������ł��x���Ȃ��A�ʂꂽ���Ɖ��x���ב��Y�Ɋ肢�o���B�����A�c���͐��ԑ̂��C�ɂ��邠�܂�ɂ܂Ƃ��ɉ����Ă���Ȃ��B���̂����ɁA���c�����g�N�ɋ��������B
�u�ŋߌՑ�����́A�X�ɏo�Ĉ������Ԃƕt�������Ă�����ĉ\����B�Ƃ̋����Ȃ��Ȃ������A�����Ȃ�Γc��ڂ邵���Ȃ��B�Ց�����ɉ��Ƃ������Ă�����łȂ����v
�@�����猾��������Ȃ��A�ƌ����Ԃ��������Ȃ邪�A�c��ɐH���Ă��������Ƃ���ʼn��̉�����ɂ��Ȃ�Ȃ����Ƃ��炢�킩���Ă���B
�@�����Ƃɐ�������h�O�Y�̂��߂ɂ��A�����Ă������҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�g�N�́A�͂��D��̎�Ԓ������ł͊Ԃɍ��킸�A�͂����i�e�@�j�ƐD���̌q�����܂ň������B������o�@(������)���̎g������ł���B�͂�������^�e���ƃ��R����a����A�����D���ł���_�@�Ƃ̎�w�ɓ͂���B�D��I��鍠�����v����ďo�����A���������z�n��������Ă͂����ɓn���d���ł������B
�@�_�Ƃł͉���ɍ��荞��ŁA�͂���D���w�Ɛ��Ԙb�����킵���B�g�N����D���̈ӌ������͂����́A�܂��V��������Z�p���J�������B���߂�ꂽ�d�������Ȃ������ł͖O�����炸�A�@�B�̍\������z�n�̖͗l�܂ōl���o��������������̂͂��̍��ł���B
�ӂ邳�ƌ��
�@������d���������ɂ����Ă��A�����őc����ƕv�E�q����H�ׂ����Ă����̂͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B�ב��Y�́A���������c�������ɖ��A���Ď����̑����ɂ����B����ł��Ց��̗V�ѕȂ͂��������ɉ��܂�Ȃ��B���̂����Ƀ��c����g�N�̒�����̂܂Ŏ����o���ċ��Ɋ�����n���B���̂܂܂ł́A�����͂����̓����I�ɏI���Ă��܂��B���Ƃ���D���Ȃ͂��D�肪�ł��Ȃ��Ă��A���������b������Ă铹�������Ȃ���Υ���B�v�̂��炵�Ȃ�������ɂ��A�g�N�͍l�����B
�@����Ȏ��A�ˑR���g����Ăяo���ꂽ�B�g�N�́A���܂�C������}���ĕX��_�Ђ̋����ɏo�������B�ނ͂Q�N�O�Ɏp�����������R(�킯)��b�����B���}�ɁA�g�N�̍K�����v���Ȃ�A�{���J�������炭�����悤�����ꂽ�̂��ƌ����B���̊Ԃ̎���̓g�N�ɂ����X�킩���Ă������Ƃł͂��������A�����͂������ƌ������Ă��܂�����O�A���g�ɍ��݂��������Ƃ͂ł��Ȃ������B
�u���]�˂��A�����Ȃ��B���������s�������ȁv
�@�g�N�̌�����A���{�����R�ꂽ�B
�u���O�A�q�����ł������Ă�������Ȃ����B��������Ȃɖʔ����˂��v
�@��x�͌����̑���ɂƎv�����j��O�ɂ��ċC���ɂ̂��A����܂ł̐h�����X�̂��Ƃ��������B
�u�����𗣂�āA�q���͂ǂ�����H�v
�u�������ꏏ���B�ł��A�����c��(����)�����ɒm�ꂽ�炽���ł͍ς܂Ȃ����낤�ȁB������A�����ť���B�]�˂ŕ�q(���₱)����炵�Ă����铭������T���Ă���Ȃ����ȁv
�u����͂����Ƃ��āA���O�ɂƂ��Ĕт��D���Ȃ͂��D��͂ǂ�����H�v
�u�h�O�Y���傫���Ȃ�܂ŁA���̋��ɂł��d�����Ă�����v
�@�Ђƌ��������āA�̎q�݂͊œ����j�����g�̓`���������Ă����B�����x�̌�����(���������)�ɗ���ł��������������������ƌ����B���̋@����āA���̐������甲���o�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�g�N�͖��������ݎq�̉h�O�Y�ƈꏏ�ɉƏo�����錈�S���ł߂��B����͂������̂��ƁA�e����Ɉ�ĂĂ��ꂽ�c������A�ӂ邳�Ƃ܂ł������ς�̂Ă�o��ł������B
�@�]�˂ɏo��̂ɂ���قǕs���͂Ȃ������B�������{���J���Ă��̓��̂����ɒ����鋗�������A������ɂ͗���ɂ��鐴�g���҂��Ă��Ă����B�]�˂̎���ɂ��Ă��A���g���̎q�݂͊̐l�v�Ȃǂ��畷���Ă��āA����Ȃɉ������ɂ͎v���Ȃ������B
�@�閾���O�A�����Ă���h�O�Y��w�����ė������o���Ƃ���ɁA�ב��Y��������(�ӂ�)�������B
�u�o�čs���Ȃ��l�ōs���B�h�O�Y�͏���Ƃ̑厖�ȐՎ�肾�B����Ȃ��Ƃ����낤���Ə�������̋��q(����)��p�ӂ��Ă������B��J�����������O�ւ́A���߂Ă����S�ʂ��B�Ց��Ƃ̗����̎�͂��͂�����łƂ��Ă������祥��B�a�C����Ȃ�v
�@�ב��Y�́A����݂��g�N�̉��ɂ˂����ނƁA�������ԉh�O�Y��w�����甍��������B�q���ƕʂꂽ���Ȃ��ƈ��肵�Ă��ב��Y�̈ӎv�͌ł��A�g�N�͒P�g�]�˂Ɍ����������Ȃ������B�������g��h����{���J���̊������������B
1.gif)
���R���n�h
|

