|
転職の勧め
.gif)
赤レンガの国武倉庫(現通町五丁目)
明治時代、日本列島を駆け巡りながら久留米絣と久留米縞を売りまくった男がいた。明治維新までは典型的な城下町だった久留米を、日本有数の商業都市に塗り替えた商人の代表格・国武喜次郎である。
久留米市の中心部(通町)に、歴史を感じさせる赤レンガ造りの倉庫が残っている。この建造物こそ、国武喜次郎が久留米のかすりを世に広める重要な前線基地であった。
喜次郎は、久留米城下の魚屋の長男として産声を上げた。明治維新から遡(さかのぼ)ること21年前の弘化4(1847)年である。
父親源策は、朝暗いうちに起きだし、仕入れのために店を出る。一緒に起き出す母のヒサは、独特の生臭さも厭(いと)わず、売り場の準備に忙しい。喜次郎の後には、妹の美代とツルが生まれ、兄妹は祖母のトリに子守りをしてもらいながら成長した。その祖母も、喜次郎が10歳になった頃に他界している。
喜次郎が13歳に成長した頃、父の源策が視力を失った。現代でいう、生活習慣による糖尿病が原因の病気だった。一家の大黒柱が働けなくなれば、たちまち家族は路頭に迷うことに。
「よか、俺が稼ぐけん」
数え年13歳になったばかりの喜次郎が、母と妹の前で胸を張った。現在でいえば、小学校から中学校に上がる年齢である。
父に言われるままに仲買の親方を尋ねると、前後の籠に幾種類もの魚が載せられた。いかに体が大人なみといっても、腰に力が入らない。やっとのことで店にたどり着くと、休む間もなく武家街へ。これまた父から聞いたとおりに屋敷の勝手口を潜(くぐ)った。
喜次郎が扱う海魚は、鯛(たい)・伊勢えび・あわび・たこ・鯨・ぶり・かつお・まぐろなど。博多湾や有明海、唐津方面から運ばれてくるものが中心である。一方川魚は、筑後川でとれるものが主であった。
1年が過ぎ2年が経って、喜次郎の行商も少しずつ板についてきた。そんな折、通町三丁目で木綿織物業を営む庄兵衛に声をかけられた。
「喜次郎ちいうたない、お前ん名は」
「はい、毎度うちの魚ば買うてくれてありがとうさんです。ところで、松屋の旦那さんが俺に何か?」
5年も同じ商売をしていると、挨拶も決まってくる。「松屋」とは、声をかけた庄兵衛が経営する本村織物店の屋号である。
「ちょっと、付き合え」
通町から西側の細工町にかけて、狭い通りの両側には、蕎麦屋(そばや)に蒲鉾屋(かまぼこや)、子供向けの駄菓子屋などが連なっている。庄兵衛は、喜次郎を従えてさっさと食べ物屋の暖簾(のれん)を潜った。
喜次郎の意見も訊かずに鯉(こい)の吸い物2人前を注文した。
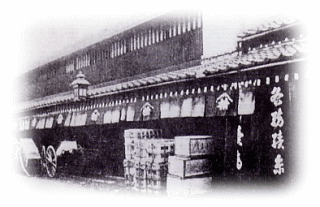
明治期の本村商店
「親父(おやじ)さんの具合はどげんね。目が見えんごつなったげなが」
「目は見えんばってん、口は達者です」
「それは何よりばい。ところで・・・」
庄兵衛が喜次郎を誘ったわけは、どうやら源策の体の心配ではなさそうだ。
「わしは、ずっと前からお前の働きぶりば見ておった」
「・・・・・・」
「そろそろ大人になる年齢(とし)じゃけん、自分のこれからのこつも考えておかんとない」
喜次郎には、庄兵衛の言っている意味が理解できなかった。
「お前のごたる働きもんば、このまんま魚屋にしとくのはもったいなかちいうことたい。それに、近ごろの子供にしちゃ珍しゅう頭もよさそうじゃけん」
「ばってん、俺は父ちゃんに代わって、家のもんに飯ば食わせにゃならんとです」
「それはわかっとる。じゃけん、もうちょっとよか商売ばしたらどげんか」
「魚屋じゃいかんとですか。魚屋のどこがいかんとですか?」
父親から引き継いだ商売を馬鹿にされたような気分になって、喜次郎が反発した。
「魚屋はどげん転んでも魚屋たい。死ぬまで久留米の城下から出るこつもでけん。ばってん、わしのごたる木綿屋なら、やりようによっては、いくらでも広か世界で商いがでくる」
その時、庄兵衛が発した「木綿屋なら、いくらでも広か世界で・・・」のひと言が、喜次郎の脳裏に焼きついてしまった。そして秘かに、魚屋からの転業を考えるようになった。
近江商人心得三ヵ条
喜次郎が16歳になった。武士の世界であれば、元服の儀式を執り行う年齢である。だが貧乏魚屋の息子では、そんな大それたことは考えも及ばない。商売ものの鯛を前にして、母親に前髪を剃ってもらうのが関の山だった。日を追って源策の容体が悪くなり、ついに帰らぬ人になってしまった。父親を亡くした喜次郎は、失意を隠すために、それまで以上に体を動かした。
行商の帰り道、筑後川の渡し場付近で、天秤棒(てんびんぼう)を担いだ四十前後の旅姿の男に声をかけられた。男は近江国(おうみのくに)のあきんどで、鍋屋の増吉と名乗った。独特の上方言葉である。
「すぐわかりましたで。松屋はんが言うとりはった若もんが、おまんだちゅうこと。ちっとばかり、話しをしていかんか」
男は、相手の都合も聞かずに、川面が一望できる土手に座り込んだ。周囲の雑草の匂いが鼻をつく午後である。眼下の渡し場には、舟が着いて10人ほどが下りてくるところだった。
.gif)
筑後川の旧渡し場付近
「俺は、おっちゃんのことば何も知らん」
「そんなことはどうでもよろし。わては、大きなあきんどを志す若もんに興味を持っただけやさかい。わての国の商いの話なんぞ、おまんに聞いてもらおう思うてな」
相手は、喜次郎が古くからの知り合いででもあるように気安く話しかける。
「おっちゃんの国の商いは、久留米とどう違うと」
「大違いや。何せ近江あきんどの始まりは、徳川の世のもっと以前からやさかいな」
「何が違うとですか、久留米と近江では」
「近江の家には、どこにでも家訓いうものがありましてな。そこにはあきんどがけっして忘れてはいかんことが書かれてますのや。商いはすべて、売り手良し・買い手良し、世間もまた良しの精神でいかなあかん、とな。加えてわては、店の主人から金持ちになるにはどうしたらええかまで教わりましたんやで」
「・・・・・・」
「あきんどが金持ちになるには、贅沢(ぜいたく)をせんで、ひたすら長生き(健康)と始末(節約)を心がけなきゃあかんとな。それが5万とか10万両を貯める第一歩になるんやと。喜次郎はん、ここを間違えてはいけまへんで。今言うた始末ちいうのは、ケチとは違う」
傍に座っている増吉が、初めて会った他国の人とは思えなくなってきた。そこで、近江商人のことを、もっと深く知りたい欲望にかられる。
「おっちゃんは、鍋屋さんでっしょ。売りもんの鍋は持っとらんのですか」
「そんな重いもん、よう持って歩けまへんわ。持ってるもんは、みいんなお品書きや。そやったら軽うおますやろ」
「そんなら、売りもんは・・・」
喜次郎は、これまでに聞いたことも見たこともない世界に、引きずり込まれていく気分であった。
.gif)
行商中の近江商人(五個荘外村邸展示)
「品物は、近江の本店から船なんぞに載せて運びますのや。それを全国いたるところに設けとる支店の倉庫に納めて、買い手があれば倉庫から荷車なんぞで届けます。運ぶのは別の人間やけどな」
増吉は、目を遠くの背振山脈に向けたままで話し続けた。
「そんなら聞きますばってん。金物屋のおっちゃんが何で魚屋の俺なんかに・・・」
「わてらが商う品もんはな、いつの間にか鍋釜から木綿・履物・海産物にまで関わってくるようになりましたんや。そんなわけで、これから木綿屋を目指そういうひよこはんと知り合いになっておくのも悪うない思いましてな」
近江商人は、日本国中はおろか、海を渡って安南(ベトナム)やシャム(タイ)にまで商売の範囲を広げているとも語った。増吉は、川面に映った雲の流れを、細い目を更に細くして追いかけた。
「もう一つだけ聞いてもよかですか」
「ええで、いくらでも」
「俺のような田舎もんでも、もっと広か世界で商いがでくるでっしょか」
増吉は、横に座っている喜次郎の手を手繰(たぐ)り寄せて、力いっぱい握りしめた。
「あほやな。でけもせんことを話しますかいな。ええか、目の前を流れとる大川は、栄養分たっぷりの泥を山から運んできますやろ。お陰で、米も綿も桑の木も藍草も、みんなすぐに大きゅうなる。そやから、筑後平野には宝物が仰山埋まってますのや。世の中が変われば、その宝物を掘り起こし、船で運び出して売りますのや。なにせ、筑後川は世界中の海に繋(つな)がっとるさかいな」
喜次郎は、更に近江商人の素顔も知りたくなった。
「おっちゃんには、奥さんや子供さんはおらんとですか」
「先ほども言いましたやろ。うちの店は江戸にも博多にも出店を持っとるって。日本中のあちこちに足場が設けられておるさかい、大概のもんは出先に2番目とか3番目の嫁さんがおりますのや。こんなこと、近江におる嫁さんに聞こえたらえらいこっちゃ」
増吉が、細い目とは対照的に、大口を広げて笑い飛ばした。
お宝拝受

井上傳手織り絣と肖像
国武合名会社秘蔵品
国武喜次郎がかすり屋になることを決意したのは、かすりが久留米藩の特定産品に格上げされ、「久留米絣(くるめがすり)」と漢字で表示されるようになった時期(元治元年=1864年)と重なる。明治維新から4年前で、20歳の頃である。
転業を勧めた本村庄兵衛は、喜次郎を久留米絣の創始者である井上傳に引き合わせた。
「こん若っかもん(若者)がっさい、魚屋ばやめてかすり売りば始むるとげな。そげなわけで、まずはお傳さんに引き合わせとかにゃち思うて」
庄兵衛に紹介してもらう間、喜次郎は正座したままである。
「庄兵衛さんも、世話好きじゃね。それで、あたいに何ばしろち」
「こん若っかもんに、織りもんのイロハば教えてやってもらえんじゃろか」
庄兵衛は、用事を済ますとさっさと帰っていった。一人残された喜次郎は、目の前の老女に、どう向き合ったらよいか迷った。
「喜次郎ち言うたない、お前の名は」
最初に口をきいたのは傳の方である。
「魚屋も立派な商売ち思うがない。それが、どうしてかすり屋になろうち思うたと。そこんとこば、あたいにわかるごと教えてくれんか」
傳の語り口は穏やかだが、目はしっかりと、喜次郎に向いている。一瞬答えをためらったが、思い切って話した。
「久留米から外に出て、働きたかとです」
「ほほう、久留米ば出てない。お侍さんじゃあるまいし。簡単には出られんち思うが」
傳にしても、藩の外に出ると言い出す若者の真意を測りかねている。
「近江の人が言うとらしたです。時代が変われば、あきんども国(藩)の外に出て商売がでくるごとなるち」
喜次郎が話している間、傳は聞いているのか眠っているのか、うつむいたままである。
「お前の生い立ちと、魚屋ばやめてかすり屋になるわけはわかった。それで・・・、久留米絣のことばどんくらいわかっとるか」
早速、かすり屋になるための知識の程度を試された。
「ようわかりまっせんばってん・・・。生地が強かこつと、いつまっでん(いつまでも)着崩れせんち聞いたこつがあります。それに、柄が上品かとも」
話をしていて、目の前に座っている老女が、久留米絣の創始者であることが不思議な気持ちになる。
「だいたい分かっとるごたるね。そんなら、久留米絣ば最初に考えついたのは、誰か知っとるね」
改めて質(ただ)されると、老女の意図が掴めなくなってしまう。
「そりゃ、あなたでっしょもん」
喜次郎の声が、小さくなった。
「そうたい、あたいが木綿織りに掠(かす)れ模様ばつけるこつば思いついたとたい。ばってん、何でんかんでん(どれもこれも)あたいが考えたわけじゃなか。津福村(つぶくむら)の大塚太蔵(たぞう)さんが、難しか絵柄の織りもんば作りなさったし、国武村(現八女市)の牛島ノシしゃんは、細(こま)か図柄のかすり織り(小がすり)ば考えた。それにあたいの娘のイトも、夜も寝らんで考えて、あげんきれいかかすりば織れるごつなった」
傳は、久留米絣の奥深さを、改めてかすり売りの卵に教え込もうとしている。
「久留米でかすり織りに関(かか)わっとる人(家)は星の数ほどおるとばい。その中で、新入りのお前がどげんして一人前のかすり屋になれるち思うか」
転業を決意したばかりの喜次郎に、木綿の売り方まで頭が働いているわけではない。
「日本中が俺の売り場ち思うて、走り回って、久留米絣ば売りまくります」
「大きく出なさったね、お兄(あに)いさん。気にいったばい」
言うなり傳は、「よっこらしょ」の掛け声とともに立ち上がり、風呂敷に包んだ小物を持って戻ってきた。
「お前は、庄兵衛さんお墨付きのかすり売りの卵たい。門出の祝いによかもんば進呈しまっしょ」
傳は、風呂敷包から分厚い板木(いたぎ)をとりだした。喜次郎が覗(のぞ)き込むと、使い古した板面には「お傳かすり」の文字が彫刻されている。
「ばさらか大切なもんでっしょ、これは・・・」
喜次郎は、手のひらに載るほどの板きれの重さを実感した。
「そうたいね、命の次とまでは言わんばってん。あたいにとっては、掛け替えのなか版木(はんぎ)たい」
傳が、版木の表面を指先で撫でながら、喜次郎の膝の前に置いた。
「どげな時に使うとですか、これは」
「この版木で刷ったもん(証紙)ば貼りつけたかすりが、お傳さんの作業場で弟子たちが織ったちいう証拠たい。庄兵衛さんとよう相談ばして、この版木の使い道ば決めるとよか」
そこまで言われると、ますます怖気(おじけ)づく喜次郎である。

お傳かすりの商標
「びくびくせんでもよか。お前が、これから日本中に久留米のかすりば売って回る男と見込んであげるとじゃけん」
「ばってん、俺はまだ・・・」
傳の前で、自分が引っ込み思案に陥っていることが情けなく、頭を上げられなくなった。
「今から、そげな情けなか顔ばしてどげんするとか。よかね、これからあたいが言うこつばよう聞かんね。聞いたら忘れちゃでけんばい」
傳は、作業場から娘が運んできた茶をゆっくり啜(すす)ったあとにしゃべりだした。
「今の久留米じゃ、はた織りのこつば、貧乏人が飯を食うためだけにやっとるくらいにしかみておらん。実際はそげなもんじゃなか。はた織りは、人間にとって米ばつくるのと同じくらいに大切な仕事たい。これからのもん(人たち)に、久留米絣ばそげな風にみてもらうごと、お前に頑張ってもらわにゃならん。この版木はあたいからおまえに渡すお守りみたいなもんたい」
喜次郎が礼を言おうと座りなおしたとき、老女は既に作業場に向かって立ちあがった後だった。
喜次郎は後に、自社のパンフレット(明治44年発行)で、そのあたりのことを述べている。
「傳女は晩年にいたり、自ら使用していた『お傳がすり』と彫刻した唯一の版木を授け、傳女の子孫その他伝授の婦女子が製造したる絣であることを表示し販売することを国武喜次郎に委託された。・・・以って如何(いか)に絣と国武合名会社との関係が厚かったかを証明するに足るべし」と。続けて、「後年かすり業の発展に随(したが)い、お傳版木の表示に代るに傳女の肖像をもって商標として登録を受け、国武合名会社の製品にこれを使用するのは、一つには発明者の遺徳を伝え、一つにはこの縁故の繋がれる所以(ゆえん)を記念するためである」とも。
喜次郎は、井上傳から授かった「版木」を、力にしたり、ある時はそれが耐えがたい重しになったりすることを繰り返しながら、大機業家(きぎょうか)へと昇っていくことになる。

|

