|
ものを売るより顔を売れ
母ヒサが、藤山村(現久留米市藤山町)の実家から紡糸車(いとぐるま)を借りてきた。
「祖母(ばあ)ちゃんが生きとれば、上手に教えてくれるとばってん」
ヒサは娘時代の経験を思い出しながら、長女の美代と次女のツルに糸の紡ぎ方を伝授した。当時、筑後地方の農家では、いずこも綿の栽培が盛んで、採れた綿花から糸を紡ぐのは嫁や娘たちの仕事であった。
.gif)
糸車(地場産くるめ展示)
喜次郎は、魚の売り台が取り払われた土間に立って考えた。新しい商いをするにあたって必要な屋号を決めなければならない。先祖からの家業への恩義を忘れまいと、「魚」の字に自分の名前を重ねて「魚喜(うおき)」と決めた。紋章は井桁の中に片仮名で、喜次郎の「キ」の字を入れた。
木綿屋に転職した喜次郎は、妹が紡いだ糸を持って、南に3里離れた藤山村に出向いた。純白の花を咲かせた梨畑を見下ろしながら、幼い日に従兄の富郎や久次(ひさじ)兄弟と、梨の木の間を駆け回りながら、かくれんぼをして遊んだ日々を懐かしんだ。久次は、後に国武合名会社の番頭として喜次郎を助けることになる男である。遊び終わると、伯母が黒砂糖の入った団子を腹いっぱい食べさせてくれた。
「大丈夫たい、喜次郎には伯母(おば)ちゃんがついとるけん」
伯母のサヨは、喜次郎の新しい門出を精一杯励ました。
「新しか商いば始むるとじゃけん、大変なこつたい」
従兄の富郎が、しきりと同情している。
.gif)
魚喜の紋章
「まだまだ、わからんことだらけたい。ばってん、その内に俺は久留米で一番の金持ちになるけん」
「そげな細かこつば言わんで、日本一になるくらい言わんかい」
富郎も、茶化し気味に喜次郎を励ました。喜次郎と富朗の会話に、弟の久次が割り込んだ。
「きい兄(あん)しゃん、俺ば店で雇うてくれんね」
突然真面目な顔で言い寄る従弟(いとこ)に、喜次郎が戸惑った。
「まだまだ俺はよちよち歩きの商売人ばい。職人以外ば雇う力はなか」
喜次郎の正直な気持であった。伯母のサヨが中に入った。
「お手当は出せるごつなってからでよかとたい。この子は、百姓より商売人の方が向いとるけん」
伯母に頼まれれば、それ以上断る理由も見つからない。頃合いを見て、久次を店に呼ぶことにした。
「ところで・・・」
昼飯の後、改めて伯母に向き合った。
「何でも聞くばい。かすりば織るとなら任せとかんね。ここらへんにも、はた織り娘がばさらかおらすけん」
「ありがとう、伯母ちゃん」
「ばってん、喜次郎が持ってきた糸じゃ、売りもんのかすりは織れん。もうちょっと太さば揃えんと。それから芯も強うなからんとない」
織り手は揃っても、妹らが紡いだ糸に駄目を押されては、持ち帰る喜次郎の足も重くなる。伯母から「この糸なら」の声を聞くまでに3ヵ月を要した。持ち込んだ糸でかすりが織られる。喜次郎の次なる仕事は、出来上がった反物を売って金に換えることである。
大風呂敷に包んだ反物を一度に背負える量は限られる。伯母から引き取ると、その足で福島町(現八女市)から三潴郡(みずまぐん)まで売り歩いた。商家や農家が主な得意先である。これも、事前に伯母があたってくれていて、どこでも愛想よく応対してくれた。だが、愛想はよくても買ってくれるとは限らない。
「せっかくサヨさんが言うてくれたばってん、うちはこげん柄の悪か反物はいらんもんの」
造り酒屋のおかみさんに軽くあしらわれて、その日も売り上げはゼロだった。
「かすりどころじゃなかばい。うちは食うに困っとるとじゃけん」と、素っ気なく断られることもある。「がまん、がまん」を復唱しながら次の家に。
「今日は挨拶に来ただけですけん」と笑って引き下がることも。
「かすりば売る前に顔ば売れ」は、いつか庄兵衛が教えてくれたあきんどの心得であった。「商売は、10軒訪ねて1軒当たれば上等と思え」とも語ってくれた。だが、店を出るとき持って出たかすりが1反も売れずに帰るときは、さすがに荷の重さが肩に食い込み、情けなさで涙がこぼれ落ちた。
「これじゃ、糸を紡ぐ綿も買えん」と嘆いても、手を差し伸べてくれる者はどこにもいない。
維新前夜の大商い
「ものを売るより顔を売れ」の格言を自らに言い聞かせながら訪問する喜次郎を、在(田舎)の住民は重宝がった。遠く離れた親類へのことづけや、街からの買い物の依頼など、連絡便として便利だったからである。そんなこともあって、喜次郎の木綿布売りは、それなりに歩きだした。
そうなると、織り手は間に合っても、妹らが紡ぐ原料糸だけでは間に合わなくなる。そこですぐに役立つ綿打ち職人を雇った。魚屋を取り壊した土間にござを敷いて、雇い入れた職人を含めて5人が黙々と糸を紡ぐことに。後々喜次郎が大経営者になる、これが第一歩であった。
時代は安政から慶応に移り、世の中は勤皇(きんのう)か佐幕(さばく)かで騒然となってくる。周囲に海を持たない久留米藩までもが、外国との戦いに備えて軍艦を購入したり、大砲を造ったりする。そのため領民には、徹底した倹約を強いられた。
喜次郎の店では、糸を紡ぐ者、原料糸を農家に持ち込む者、かすりを売り歩く者と店員の分業も進んだ。
そんな折、松屋の丁稚が来て「大将が呼んどる」と告げた。庄兵衛からの呼び出しには、何をおいても駆けつけなければならない喜次郎である。裏庭にまわると、座敷には鍋屋の増吉と鶴屋の六左衛門が座っていた。鶴屋も、鍋屋と同じく近江国の行商人である。
「おお、喜次郎か。来てもろうたつはほかでもなか。お前にこん人たちの商いば手伝うてもらいたか」
庄兵衛が喜次郎を座敷に招きあげた。
「心配せんでもよか。お前はこん人たちの加勢ばするだけじゃけん」
「俺が何を・・・」
「鶴屋さんと鍋屋さんが売るかすりば、揃えてもらいたかとたい」
話しかける庄兵衛も、いささか興奮気味である。
「いったい、何反くらいのかすりが要るとですか」
六左衛門が、火鉢の縁で勢いよくキセルの首を叩いた。
「1万とか2万とか・・・」
喜次郎の頭がおかしくなった。自分が商うかすりの分量と比べて、あまりにも桁が違い過ぎる。
「1万反ちは、いったいどんくらいのもんか想像もつきまっせん。ばってん、そればどこで売るとですか」
「長崎とか長州(山口県)で・・・」
鶴屋の返事に、喜次郎が大きくため息を吐いた。
「よろしいか、喜次郎はん。いや、今日からはおまんのことを魚喜はんと呼ばせてもらいまひょ」
今度は鍋屋の増吉が喜次郎に向き合った。その目には、3年前に筑後川の土手で見せた優しさなどどこにもない。喜次郎を一人前の大人と見立てての真剣勝負の眼差しであった。
「喜次郎はん、おまんはこれから日本国中を売り場にして商いをするんと違いますのか。1万とか2万の数でびっくりしてどないしますのや。数さえ揃えてもらえれば、引き取りの手間やお国(藩)から外に運び出す仕事はわてらがやるさかい。魚喜はんにはそれ以上の面倒はおかけしまへんよって」
「そんな大そうな数のかすりが、ほんなこつ(本当に)売れるとですか」
増吉からどのように説明を受けても、なお信じられない喜次郎である。今度は、鶴屋が胸を張ってみせた。
「久留米のかすりは、生地が強うて軽い。その上柄もええさかいな、売れること請け合いや。これから先、戦争ということにでもなれば、藩兵さん方の戦闘着としてもうってつけやし。わてが見込んだ反物どっせ、当てが外れてたまりますかいな」
未だに疑問だらけの喜次郎が、鶴屋に質(ただ)した。
「戦(いくさ)が始まるとですか?」
「そりゃわかりまへん。わかりまへんけどな。300年近こうも続いた徳川さまの世でっせ。この先どないなことが起こっても不思議なことはおまへん」
鶴屋の六左衛門は、先の世を読む勘だけは外れたことがないのだと自慢した。
「ばってん、1万反のかすりば揃えろち言われても・・・」
未だに、その分量の大きさを測りかねている喜次郎に、再び鍋屋のだみ声が覆いかぶさった。
「魚喜はん。久留米藩が扱うてはるかすりの分量がどのくらいなもんかわかってますのんか」
突然話を向けられても、お上の扱い高など分かるわけがない。
「ざっと、4万反から5万反どっしゃろ。わてらは、その2割程度のかすりが欲しい言うとるだけどす」
お城が扱うかすりは、どこで誰が織っているのか、またどのようにしてお城に納められるのか、その仕組みすら知らない喜次郎である。鍋屋が喜次郎にたたみかけた。
「領内の織屋に向けて、大号令を発してもらいまひょ」
「織屋にですか。誰が・・・?」
「お城に決まってますやろ、号令できるのは。決まりの税は払いますよって。お城にしても、わてらが売ってあげるだけ手間が省けるのと違いますか。藩にとっても悪い話ではおまへん」
熱湯を浴びせられたような気分の喜次郎が、頭を冷やすために暫(しば)し目をつむった。
「鍋屋さんに、もう一つだけ聞いてもよかですか」
喜次郎が、未だに解せないことを質した。
「鍋屋さんは、鍋とか釜とか釣鐘(つりがね)とか、金物を売る商いだと聞いとりました。それがどうして・・・」
「木綿の商いをするかって。以前にも言いましたやろ。わてらは年中日本国中を歩き回ってます。近江の本店から持ち出したものだけじゃのうて、行き先々で珍しいものがあれば買い付けもします。買ったものは、儲けを加えて他に売りますのや。近江の商いとはそないなもんどすがな」
喜次郎は、早速井上傳の作業場に赴いた。かすりを大量に生産する織屋といえば、ほかには思いつかないからである。庄兵衛に引き合わせてもらって以来、これまでも暇を見ては通外町に老女を訪ねている。ここにきて、傳の老衰の進み方が早くなった。作業場に出れない傳の代わりに、娘のイトが喜次郎の相手をした。
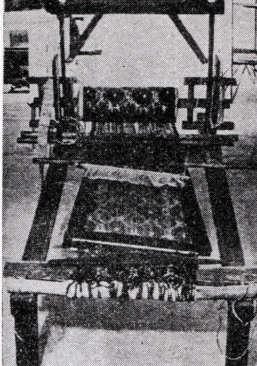
井上傳時代のいざり機
「うちのはたの数は、たったの30台ですもんの。1人の織り子が1日働き詰めでん、1反織るとに4~5日はかかりますもん。今までのお客さんもおらすけんで、そげん魚喜さんばっかりに回すわけにはいきまっせんもんの」
1万反という量は、お傳かすりを取り仕切るイトにとっても途方もない数字であった。
「そうたい、そうたい。うちのお弟子さんが、筑後中に何百人もおらすけん。そん人たちに頼んでみなっせ」
イトの娘のトモが、弟子の名前を記した帳面を持ってきた。今度は、田舎の織屋回りである。伯母のいる藤山村を皮切りに、八女郡から三潴郡(みずまぐん)へ、更に浮羽郡、三井郡へと久留米藩領内を歩いて、かすりの織り立てを頼み込んだ。
「ものを売るより顔を売れ」の精神でやってきたことが、ここにきて役にたつ。喜次郎は、1年かかって目標の1万反の仕入れに成功した。
長州路
慶応4(1868)年9月8日、260年間続いた江戸幕府が崩壊した。年号も慶応から明治に改められた。その日は、朝から日差しが強かった。武士はお城に上がり、町人は朝早くから働いている。いつもと変わらない久留米の町の光景であった。
「徳川さまが江戸城を去られた後、そこが天子さまのお住まいになるとげな。久留米のお城や有馬のお殿さまはどげんなるとじゃろうない」
城下の民の話題はそこにあった。明けて明治2(1869)年2月7日。藩主有馬頼咸(ありまよりしげ)が朝廷に版籍(ばんせき)を奉還した。「版籍(はんせき)奉還(ほうかん)」といわれるもので、藩主が版(土地)と籍(人民)を天皇に返上した改革のことをいう。これで、久留米というお国(藩)も消滅することになった。
夏も近づく同年4月(旧暦)。庄兵衛の店の小僧が駆け込んできた。
「魚喜さん、早よう、早よう。通外町に行って!」
通外町といえば、お傳の作業場のこと。とるものもとらずに駆けつけると、仏壇に向かって北向きの布団に寝せられた傳の顔には、白い布が被せられていた。
「半時前でしたもん。おっかしゃん(母)は旅立ちました」
イトが喜次郎に告げた。その夜、身内と庄兵衛ら親しかった者が集まって通夜が執り行われた。庄兵衛は、連れてきた養子の庄平に、池に咲いているショウブの花をとってくるよう言いつけた。
井上傳は、独特のかすり織りの技術を考案し、筑後一円にはた織りを普及させた女性である。彼女は、木綿屋に転職したばかりの喜次郎に、分身ともいえる「お傳かすり」の版木を与えた。それは「井上傳が心血を注いで織るかすり」を証明するための掛け替えのない宝物であった。その時傳は、「はた織りは、人間にとって米ば作るのと同じくらいに大切な仕事」だとも言った。
孫娘のトモが障子を開けて入ってきた時、生ぬるい風が喜次郎の首筋をなでた。
通町は、筑後一円から仕入れにやってくる小売業者と買い物客で、相変わらず賑わっている。喜次郎の店にも、八女や朝倉など周辺からの小売業者が、仕入れのために入ってくるようになった。そこで、店を改造し織工と販売員を増やした。藤山村の従弟の久次(ひさじ)を呼んで住みこませたのも、この時期である。
明治3(1870)年の夏。喜次郎は、生まれて初めて関門海峡を渡り、下関にやってきた。維新直前に鶴屋と鍋屋を介して送り込んだ久留米絣の評判を聞くためである。
「かすりの評判はよかですよ。何というても、鶴屋さんが太鼓判を押しなさったものですけん。それに・・・」
久留米絣が好評だと聞いて嬉しくなった喜次郎は、問屋の主人の次の言葉が待ち遠しかった。
「赤間関(あかまがせき)の太夫さんが、贔屓(ひいき)の男衆に配った手のごい(手拭(てぬぐい))が大そうな評判を呼びましてな」
「手のごいがですか?」
「久留米で、絵がすりを考えなすった男の人がおりまっしょうが。ほら、大塚(おおつか)太蔵(たぞう)とかいう。その方に、太夫さんの名入りのかすり織を注文なさったんですよ。粋でお洒落(しゃれ)でって。もらった旦那衆が自慢して回ること。つられて町の衆にも噂が広がってですね」
浮き浮き気分で店を出ようとすると、後から肩を叩かれた。鍋屋の増吉である。
「ひょんなとこでお会いしましたな、魚喜はん」
鍋屋は、喜次郎を海峡が見下ろせる料理屋に誘い込んだ。
「その節は、魚喜はんのお陰で、鶴屋はんもわても仰山(ぎょうさん)儲けさせてもらいました。改めて礼を言わしてもらいますよ。おまんの商いの方は、その後うまいこといっとりますやろか」
問いかけが逆であれば、増吉が「ボチボチですわ」と答えるところだろうが、喜次郎にはそんな便利な受け答え法が身についていない。「まだまだ、店ば繋いでいくとに精一杯ですけん」と返すのがやっとであった。
「わてが前に言うてましたやろ。徳川さまの世が終(しま)えたら、次はあきんどの天下がきやすって」
「何のことでしたか、鍋屋さん」
「かなんな、もう忘れはったんかいな。ほれ、大阪とか京都での商いのことでんがな。久留米の木綿は、藩が直々に取引をしとるという、あのこと」
明治維新を境に、それまでの「大坂」を「大阪」と書くようになった。先ずは近いところからと、九州各地の問屋回りをしているうちに、喜次郎は、上方でのことをすっかり後回しにしていたのである。
「日本中のあきんどが、動き出しましてんやで。木綿は何も、久留米だけの専売特許じゃおまへんよってな。1日遅れれば、取り返しのつかんことだっておます。ご維新(いっしん)を挟んで、それまでの10日が1日に相当するほどに、世の中の動きは早ようなってます」
「そげんに・・・、ですか」
言われてみて、海峡を通過する貨物船に積まれている荷物の中身が気になった。
.gif)
現在の関門海峡
「そうでんがな。これからのあきんどは、日本はおろか、海の向こうの外国とも商いをしていかなあきまへん。ここの海峡も、ますます船の行き来が激しゅうなりますやろ」
増吉と別れて久留米にとって返した喜次郎は、早速上方に向かう準備にかかった。
この年(明治4年)の7月。久留米の城下がなくなり、町の東側を「御井郡(みいぐん)」に、西側が「三潴郡(みずまぐん)」に組み入れられた。喜次郎の住む通町は、御井郡に属することになった。久留米藩と柳川藩は解体され、旧筑後藩領を久留米県、柳川県、三池県に分け、それまでの藩庁は県庁にと役所の名前も変った。
そんな折、佐田与平がやってきた。喜次郎が魚屋を廃業する際、店の道具等一式を引き取ってくれた幼馴染(おさななじみ)である。
「まじめにやっとるか」と喜次郎が挨拶すると、「お前こそ、悲鳴ばあげとりゃせんかと、心配になって寄ってみた」と、与平も減らず口で返した。
「魚喜の旦那も、早よう国武の苗字(みょうじ)ば表に出さんかい。商いは屋号で、暮らしには苗字ば使うとたい」
与平は、このほど明治政府が打ち出した政策「平民の苗字使用の自由」のことを言っている。
「別に、魚喜の喜次郎でも不自由はしとらんばってん。それより、『士族』ちいう身分になりなさったお武家さんの暮らし向きの方が心配たい」
特権的身分と役職にあぐらをかいてきた武士は、ここにきて生産や稼ぎの手段を持たない暮らしの厳しさに直面しているという。
「櫛原村(くしはらむら)(現久留米市櫛原町)では、お侍さんの食扶持(くいぶち)のためにち言うて、豚の飼育まで始めなさったげな」
久留米の事情に詳しい与平の口から、最近の武士の暮らしぶりがいっそう厳しさを増していると聞かされた。

|

