|
■ニーベルンゲンの歌-Das Nibelungenlied |
サイトTOP>2号館TOP>コンテンツTOP | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
++ドイツ語の地図サイトより。人にドイツ語聞きながら探してみた。++
旅の始まりは、やはりブルグント族の本拠地、ヴォルムスだろう。
「ヴォルムスへ行きたい、まずはハゲネに会ってみたい。」
ヴォルムスの川べりには、父なるラインに呪われた黄金を投げ込むハゲネの像があるという。
現代のニーベルンゲンの道は、そこから始まっている。
ドイツには多くの「街道」が存在する。70にも及ぶテーマ街道の中には、「ニーベルンゲン街道」、「ラインの黄金街道」の名前も見つかった。「ニーベルンゲン街道」の場合、ヴォルムスの対岸にある、古い修道院の町ロルシュから始まり、ジーフリトが殺害される森・オーデンワルトを30分ほどで抜けて、「オーデンワルトの心」と呼ばれる町ミヒェルシュタットに到着して終わるという。ずいぶん短いが、実際、物語に沿って3カ国を渡っていくような長旅をする旅人は、なかなか居ないだろうから、無理も無い話かもしれない。
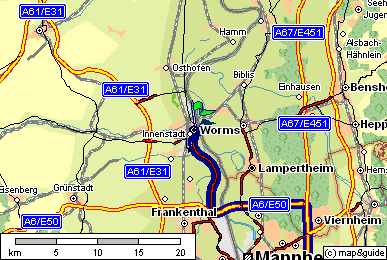 |
ニーベルンゲン街道を「ニーベルンゲンの歌」からではなく、ワーグナーの歌劇から知って辿る人も、多いという。だが、ワーグナーの脚本の和訳を読んでみると、その粗筋は、「ニーベルンゲンの歌」よりも、さらに古い北欧神話に近く、内容は、近代化された大衆写本のものに近いようだ。こちらのイメージを持って、北欧戦士の雄雄しさを宿したハゲネの像に出会うと、おそらく、びっくりするのではなかろうか。
リヒャルト・ワーグナーによって、戯曲「ニーベルングの指輪」が書かれたのは、一度忘れられた物語が再度脚光を浴びたのちの、19世紀のことだ。(他にもフリードリッヒ・ヘッベル、パウル・エルンストなど多くの芸術家たちによって、ニーベルンゲン伝説が取り上げられている。)
19世紀のニーベルンゲン伝説は、かつての力強い生命力と、多くの誇りを失っている。オーディンの成れの果てヴォータンは、諦めとしか取れない台詞とともに、自ら破滅を望む。定められた「運命」の前に敢然と立ちふさがり、大河の中を堂々と流れてゆくような精神は消えた。
断っておくと、私は、ワーグナーの描く世界を文字でしか見たことはない。だから、「ニーベルンゲンの歌」と「北欧神話」と「ニーベルングの指輪」を、同じく紙の上の世界として扱っている。
ワーグナーの作品に登場する「ニーベルンゲンの歌」の英雄たちは、かつての本質を失った、名前の役柄だけの存在である。ジーフリトは半神の英雄ではないし、ハゲネは己の信念のままに生きた武将ではない。クリエムヒルトやプリュンヒルトも、強く逞しく生きるゲルマンの女性たちではなく、美しさの半分を失った。
私は、そんなワーグナーの作品からではなく、古代のサガの世界から「ニーベルンゲンの歌」を見ている。
[ワーグナーの「ニーベルングの指輪」紹介ページへ]
古代北欧の武将然としたハゲネは、嫉妬や偽りの心ではなく、誇りと、義務と、自らの仕える王のためにジーフリトを殺害し、それゆえに胸を張り、己は正しいことをしたと自信を持って、自らの殺害した英雄の妻の前に立っただろう。
たとえ死が待つとしても、それが運命であるならば、堂々と戦い立派に死すことを望んだだろう。
人の運命は、指輪ひとつに縛られるほど軽くは無い。呪いを生み出すものは、神々でも妖精でも小人でもなく、それを受け入れる人間自身の心である。…
…そのように力強く語り、神も人も、運命を知りながらなおかつ最後の一瞬まで図太く生きるのが、「ニーベルンゲンの歌」にも受け継がれた、古代北欧の精神なのだと思う。
+++
前置きが長くなってしまったが、ここからは実際に、彼らの辿った道筋を語ることにする。
「ニーベルンゲンの歌」は、前編と後編に分かれている。
前編は、ブルグント族のクリエムヒルト姫と、ニーデルラントの王子ジーフリト(ジークフリート)との結婚、ブルグント族の王グンテルと、イースラントの女王プリュンヒルトとの結婚が描かれ、双方の王妃の不仲から、グンテル王とプリュンヒルトの結婚にまつわるごまかしが暴露され、ジーフリトが暗殺されるまでを描く。
続く後編は、クリエムヒルトがフン族の王エッツェルの再婚し、兄弟たちを招き、皆殺しにする復讐の惨劇を描く。
ハゲネ他、ブルグントの人々が旅をするのは、この、後編である。
クリエムヒルトの企みに気づいたハゲネは出立に反対するが、招致に応じないのは恥であるとして、主君らは聞き入れない。
かくて、はるかフン族の国への旅は始まり、ブルングント族の郎党、およそ1万は、一人残らず果てる破滅の旅へと出発することになる。
この、長い旅と後半の物語の始まりとなるブルグント族の王都は、ヴォルムスである。
これは、現在のドイツ南部、ラインラント・プファルツ州にある町、Wormsを指す。州都マンハイムから約50キロのところにあり、そのものズバリ、ニーベルンゲン伝説の町としても有名だ。
ジーフリト殺害現場となったのは、物語中では「ワスケンの森」と記されているが、この森に行くには、ヴォルムスから真っ直ぐに「ライン河を越えた」という、作品中の表記を信じるならば、ラインの対岸にある「オーデンの森」が現場となる。
この森の泉の側で、ハゲネはジーフリトを背後から襲って殺害する。この所業ゆえにハゲネを「卑怯者」呼ばわりする読者が後を立たないのだが、どっちが卑怯かと言うと、背後にしか弱点の無い、人間離れした人間であるジーフリトのほうが、卑怯である。貴婦人を欺いたことも、口にしてはならない秘密を漏らしたことも罪に値する。後世の大衆本ではジークフリートが名高いが、当時の愛読者であった宮廷の人々、および知識階級の人々にとっては、「英雄殺しの英雄」としての、ハゲネの存在のほうが大きかっただろうと推測する。
現在、オーデンの森には、「ジーフリトの泉」なるものが作られているらしいが、もちろん、当時からあったはずはない。このあたり、いかにも伝説を町おこしのために使おうとする商売根性が出ていて面白い。
そして、ライン河岸のハゲネの像とくらべると、かなり見劣りするらしいのも面白い。
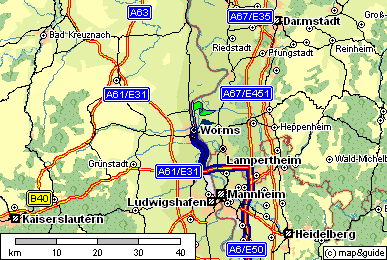 |
ちなみに、ヴォルムスの北にあるマインツは、印刷技術が開発された町として知られている。
印刷によって聖書の内容が一般に知られるようになり、宗教改革へと繋がっていくのは有名な話だが、印刷技術の発展は同時に、ニーベルンゲン伝説の広がりにも一役買った。16世紀以降、印刷により増産された大衆本によって、物語が一般に広く知られるようになった結果、伝説からは、かつての宮廷文学の荘厳な面影が消え、大衆の好む、単純な英雄伝説へと変貌していくのである。
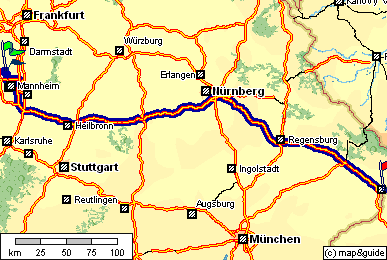 |
ヴォルムスをあとにして、ブルグントの一行は、一路エッツェルンブルクへと向かう。ヴォルムスは河の西岸にあるから、いったん河を渡って、東側に幕営してからの出発だ。
エッツェルンブルクは、ブルグントの王グンテルの妹姫にして殺害されたジーフリトの寡婦、クリエムヒルトが二度目の結婚のため嫁いでいく場所でもある。
エッツェルンブルクへの旅はクリエムヒルトの招致を受けた旅である。だが、それは、二度と生きて帰れぬ、災いの旅だった。
彼女は自らの受けた裏切りの屈辱を忘れておらず、夫殺しに加担した者を死の饗宴へ招き寄せようとする。
ハゲネは、そのクリエムヒルトの思惑を感じ取っていながら、なお、この宴に参加する。
何ゆえ? とは、問うまい。
主君がそこへ行くのに付いていかぬわけにはいかない。不確かな推測で宴に参加せぬことは、怖気づいたと思われて名誉に関わる。
よしんばクリエムヒルトが悪い企みを抱いていても、戦うことによって活路を開けばよい。剛毅な彼は、そう思っていたに違いないのだ。
そして、悲劇の運命を予感しつつ、一行は、東フランケンを通り、マイン川を経て、12日目にドナウ河へと到着する。マイン河は、ライン河の支流で全長524メートル。ヨーロッパの二大河川である、ドナウ河へむかって西から東へと流れている。この旅は、実は、行程のほぼすべてが川沿いを歩いている。いわば河から河への旅と言える。
ラインの名が男性名詞であるのに対し、ドナウは女性名詞だ、とは、よく言われる。その名のとおり、雰囲気も違うものだろうか。その気質は、果たして住む者にも影響するものかどうか。ラインから来た勇士たちは雄雄しいが、ドナウ河畔に住むエッツェル王の家臣たちは、のちにハゲネに「女々しい」と、揶揄されるはめになる。
一行は、メーリンゲンという場所で河を渡る。ここまでは河の北側を歩いて来たわけだが、ここからは南側に渡らねばならないのだ。
だが、河は増水しており、橋も見当たらず、迂闊に渡ることが出来ない。
そこでハゲネは、人々を渡してくれる渡し守を探して川沿いを歩き出す。彼が、川に住む水の乙女たちから不吉な予言を聞くのは、この時だった。
「王室の司祭ひとりを除き、あなたがたはブルグントに帰ることは出来ないでしょう。」
この予言を聞き、ハゲネは怒り心頭する。不吉な予言を聞かされたからではなく、自らが臨もうとする勝敗の行方を告げられたからである。
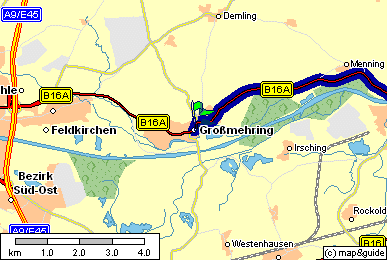 |
| ”メーリンゲン”=Griβmehring(有力説) |
クリエムヒルトが企みを抱いていることは先刻承知の上、その上でエッツェルンブルクへ向かうのだから、行けば戦いになることは当然、予想している。だから、彼らのすべてが死に絶え、帰路につくことは出来ない、ということは、すなわち、彼らが、エッツェル王の家臣たちに「敗北」することを意味している。負けるはずがないと思っているハゲネが、怒らないわけがない。
負ける、と分かっている戦いに挑むとは、どんなものか。それを簡単に運命だと受け入れられるのか。幾ら、華々しく立派に死ぬることに意味を持つ北欧民族の末裔といっても、そう簡単なことではないだろう。
ハゲネが純粋なキリスト教徒なら、そこで神に祈り、奇蹟を呼んだかもしれないが、彼はそうはしなかった。それ以後も決して、たとえ死ぬ間際でも、彼とその仲間たちの誰ひとり、神の名に縋ることはない。ハゲネは自らの裏切りをツミだとは考えず、神に懺悔することは無い。どんな困難に面しても、何者にも頼ることなく、己自身で立つ。その強さは何処から来るのだろうか。
ハゲネは、手に入れた船で河を渡るとき、増水した水の中に司祭を投げ込み、偽りを証明しようとする。だが、司祭は無事に岸に泳ぎ着き、命を永らえる。
予言は偽りではなかった、と知った彼が選んだ道は、水の乙女たちの勧めた「ここで旅をやめて戻ること」ではなく、「神に祈り、天に嘆く」というキリスト教的な行為でもなく、「自らを信じて運命に従い、突き進む」という、古代北欧の勇士の生き様であった。
この場所は、現在のGriβmehringという町で、インゴルシュタットとレーゲンスブルグの中間に位置する。
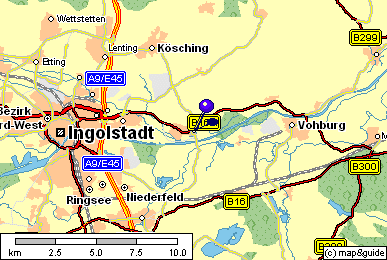 |
| メーリンゲンはインゴルシュタットの少し東 |
クリエムヒルトがエッツェル王のもとに嫁ぐ際に河を渡った地点も、ここからさほど遠くなく、少し西に行ったPforringという町である。
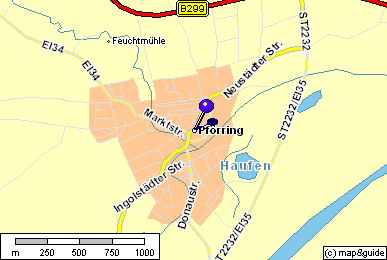 |
| 近辺地図 |
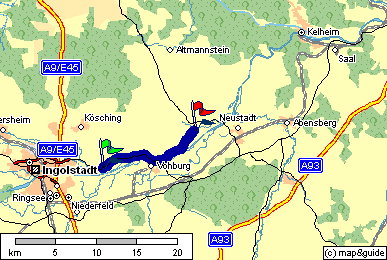 |
| 緑色の旗がメーリンゲン、 赤色の旗がフェルゲン。 |
物語の道とは直接関係無いが、この二つの町の少し北には、マイスター・ジンガー、ハンス・ザックスの出身地、ニュルンベルクがある。
ドイツは、職人の国だ。さきのワールドカップ決勝でのパスまわしの仕方なども、堅実実直な職人技を思わせた。
ニュルンベルクは、古くから手工業の町として知られ、職人たちが「ギルド」と呼ばれる寄り合いを作り、業を競い合った場所だ。
マイスター・ジンガーとは、そういったギルドに所属する職人でありながら、兼業として歌を作った詩人たちのことである。
14世紀から16世紀ごろは、かつての宮廷詩人やミンネゼンガーとは異なり、民衆のために、民衆出身の職人たちが、物語の語り手となった時代である。
印刷技術のうまれた町、マインツのあたりでも触れたが、民衆本としてニーベルンゲン伝説が姿を変える以前に、この、マイスター・ジンガーたちの手によって、既に、物語が一般むけに解体され、作り変えられる職人作業が始まっていたのである。
ハンス・ザックスによるニーベルンゲン伝説、悲劇「不死身のゾイフリート」の創作年は、1557年とされている。ハンスの本職は靴屋の親方で、彼は、本職に慣れた手つきで皮を継ぎ合わせて一足の靴を作り上げるように、「ニーベルンゲンの歌」や、大衆物語「不死身のザイフリート」など多くの作品をつなぎ合わせ、全7部の膨大な悲劇戯曲を書き上げた。
ハンスは、すべてを読んだ、と言われる。
「エッダ」の欠けた部分を補った「ヴォルスンガ・サガ」、13世紀半ばに書かれたとされる「シドレクス・サガ」、英雄叙事詩の集大成「ヘルデン・ブッフ」…伝説に関わる、ほぼすべてのモチーフを読み込んだ。そして、そのすべてを、一つの物語の中に、取り入れてしまったのである。
内容は膨大だが、そこには、英雄たちを戦わせ、派手な勝利と友情、メロドラマチックな英雄の死で物語を終える、単純な構造しかない。人気の高い英雄、ジークフリートの誕生と悲劇、彼の妻の復讐。読み手が誰を正義として読むかが、最初から決まっている。
もちろん、それはそれで面白く、当時の大衆は、複雑で高級な品物は、望まなかったのだろう。
人々の旅は、続く。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()