「ニーベルンゲンの歌」は、13世紀に書かれたドイツの英雄叙事詩である。
原題は「Dus Nibelngenlied」。liedは「歌」という意味だが、もっとも古いとされる写本では、「nôt」と、なっているようだ。
ノートとは災いの意味であるから、本来は「ニーベルンゲンの災い」と、いうタイトルだったことになる。
この物語にどうしてそのようなタイトルがつけられたのかを語る前に、まずは、ドイツ文学について調べた浅知恵を、披露してみたい。
ドイツ国のことを、英語ではGermany(the Federal Republic of Germany )と呼ぶが、ドイツ人自身はDeutschlandと呼ぶ。
German、ゲルマンという言葉が入っていることからも分かるように、ドイツはゲルマン民族が作った国だ。この「ゲルマン」は、民族の、という意味のgermanishを語源とする、ローマによって外部から与えられた名前だという。
対して、Deutschは、ドイツという国を作った人々が、自ら名乗り始めた名前だ。
地中海沿岸に住む国々の人々は、彼らをゲルマン民族、と一括りにしたが、ゲルマンと呼ばれた集団は、実態は、北欧を起原として多くの小さな部族から成り立つ集団であった。
言語や文化はよく似ていたが、血族意識が強く、他の部族とは基本的に相容れない。血族を重んじ、「だれだれの息子」を名乗り、封建社会に入ってからも、出身地を苗字代わりに「von 〜」と、つける。それは、サバンナに住むライオンの小集団のような、荒々しい野生の本能を感じさせる集団である。現在でも、ドイツには、ザクセン、シュヴァーベンなど地方ごとに多くの方言があるという。
ローマの人々は、そんな彼らを一括して異民族と認識していた。当然、その中の部族同士の細かな差異まで意識してはいなかっただろう。
1世紀末に書かれた、ローマの歴史家タキトゥスによる歴史書、「ゲルマーニア」からも、彼らの実際の生活と、ローマ側が認識していた生活の間には、解釈の点においていくばくかの違いがあっただろうことが、予想される。
傭兵として雇われた人々がいた。商人として取引した人々もいた。
侵略者、略奪者として、敵に回った人々もいた。
「ゲルマン人」と一括りにされていても、その中には、ローマと様々な付き合い方をした、幾つもの民族が存在したということは、留意しておくべきだろう。
さて…この、多くの小集団から成る「ゲルマン民族」と、ローマを含む地中海文化との交流の歴史は、紀元前150年ごろのゴート人の移住から始まったようだ。
移住者たちは、気候の悪化によって人口をまかないきれなくなったスカンディナアヴィア半島から、自分たちの文化を抱いて、交易、略奪、移住を繰り返しながら、地中海付近へと南下してきた。
長い年月の中で幾度もの殖民くり返され、ある者はブリテン島へ、またある者は小アジアへ向かい、さらにはアフリカ大陸へも足を延ばした。
そうした各地への遠征の結果、つくられた国のひとつが、バルト海からライン河、ドナウ河まで広がる広大なドイツである。
ドイツ人がDeutschを名乗り始めたのは、8世紀末だったとされる。
同じゲルマン民族から成るフランク王国のカール大帝が、ローマで帝冠を受け、世界の王となった時代だ。
これにより、移住者たちは、もはや「よそ者」ではなくなった。ゲルマン宗教はキリスト教と融合し、野蛮人の宗教とされてきた北欧神話が聖書の世界とまじりあい、新たな伝説を作り出していく。
Deutschの名は、そうした時代に生まれた。外から与えられた名でも無く、それまでの氏族名でもなく、内部から新たに掲げられた名前。元はバラバラだった民族が、一つに終結し、自分たちを「一つの国をつくる仲間だ」と、認識しあい、その仲間に新たな名をつけたのである。
この、新たに生まれたひとつの民族としての結束と、異文化との融合が、北欧神話世界の精神を母胎とした12−13世紀のドイツ文学を生み出した。かつて文字として物語を書き記すことを知らなかった人々の新たな伝承形態として、文学が花開いた時代のは、「ニーベルンゲンの歌」が書かれた、まさにこの時代である。
「ニーベルンゲンの歌」の中には、かつて口から口へ伝えられていたゲルマンの古い信仰・伝承と、新しいキリスト教の教えとが交じり合い、平行して存在する。伝説を伝え、育てて来た人々は、古代北欧人の末裔であるとともに、ローマのキリスト教文化の後継者でもあった。
しかしそれは、容易な融合ではなかっただろう。
現在でも、読む者はしばしば、物語の中に混在する二つの倫理観に惑わされる。
理性を重んじるキリスト教世界とは裏腹に、「ニーベルンゲンの歌」に交じる北欧神話とは、厳しい自然の中で生み出された、荒々しく、血なまぐさい神話である。
この神話の中で、世界は、神々による巨人殺しから始まって、天と地は殺され、解体された巨人の体から作られる。まず世界の始まりからして業を背負っている。
人々は、血族を重んじ、夫婦の絆よりも親戚・親子の関係を尊び、悲しみには復讐をもって対抗する。屈辱に対し報復せぬものは臆病者と呼ばれる。命には命、あるいは命と同等の黄金を、と、登場人物たちは叫ぶ。
人も神も、常に戦いながら己の命を削って生きねばならない。まこと、厳しい自然が育んだ神話に相応しい。
この精神の中で、最初のニーベルンゲン伝説は生まれた。
北欧神話の世界に息づくのは、避け難い「運命観」である。
古代北欧人にとって運命とは、決して変えることの出来ないものを指していた。神々さえも、運命を告げる女神ノルンたちの前に屈する。絶対的な運命を前にして、人々は、どのようによく生きられるかを考える。定められた死に対し、怯えたり、逃げ出したりしようとするのは臆病者の仕業である。勇敢なもの、立派なものは、決して逃げたりせず真正面から立ち向かう。
抗いがたい厳しい自然の中に暮らしていた人々は、「運命を享受する」態度をこそ、好ましいものと考えたのだろう。
「ニーベルンゲンの歌」の中にも、その考えはしっかりと根付いている。
竜の血を浴びて半神の身となったはずの英雄・ジーフリトの、定められた非業の死。この死によって、ニーベルンゲンの黄金を継承する、滅び行く定めのブルグント族の勇士たち。彼らはみな、その運命を知りながら、堂々として立ち向かっていく。運命を嘆いた者は生き残るが、受け入れた者たちは、みな、死に絶える。
これが「ニーベルンゲンの災い」である。
物語は災いを憂い、戦いによって皆果てる悲しみを歌うが、それは決して後悔の歌ではない。不可避の死を前にして、運命を受け入れながらいかよく生きるかが古代北欧人にとって重要なテーマであり、もしかすると、最大の関心だったかもしれない。
さりとて、物語の中の登場人物は、一部を除きすべてキリスト教徒である。
さきに述べた、ブルグント族の、随一の勇士ハゲネもまた、物語の上ではキリストの神に仕え、信仰していた。しかるに、古代北欧にあった「戦場において勇敢に死したる者の楽園」ヴァルハラも、戦死者を迎える美しき戦乙女も、彼の前には無かったことになる。
ならば、彼は、何を救いとして「物語の終焉の地」へと向かったのか。
異なる文化を継承しながら融合させるとは、過去のものを捨てさって新しいものを手に入れることではないだろう。古きものを抱きながら、新しいものを受け入れる。
しかし、新しいものを受け入れたとき、古きものを抱く人々の瞼に浮かぶものは、一体どちらの神だったのだろうか?
古代北欧の英雄からキリスト教徒に変わったブルグントの人々は、何を胸に抱いて運命づけられた悲劇へと向かって行ったのか。彼らが目指したものとは何だったのか。
私は、まだそれを知らない。
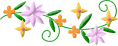
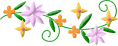
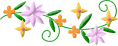
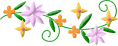
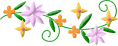
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()