|
■ニーベルンゲンの歌-Das Nibelungenlied |
サイトTOP>2号館TOP>コンテンツTOP | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
++ドイツ語の地図サイトより。人にドイツ語聞きながら探してみた。++
マイン河まではハゲネが「道筋をよく心得ている」と、書かれていたが、ここから先の道は、フォルケールが詳しい、と作品中にある。フォルケールは、ヴォルムスの西に位置するアルツァイの町の者とされているが、ここから、ドナウ河流域に行ったことがあるか、長期間滞在した経験がある、とうかがえる。
私は、この人物、作品中最も謎めいたフォルケールという人物にも、ひどく興味を抱かせられる。「フィーデルの名手、楽師」と呼ばれながら、旗手を任せられるほどの剣士でもある。その腕は、戦場においては妙なる赤い調べを奏でることも出来る。
フォルケールなる人物は、物語の中心であるハゲネの親友と呼ばれ、何度も重要な役目を課せられながら、「ニーベルンゲンの歌」以前の、いかなる物語にも登場しない。原型がどこにも見当たらないのである。
その人物像は、古代北欧の英雄から転化したものというよりは、「ニーベルンゲンの歌」の書かれた、13世紀頃の騎士を思わせる。この人物を、「ニーベルンゲンの歌」の作者の分身である、とみなす考えもある。
「ニーベルンゲンの歌」の作者とは、誰だったのか。
残念ながら名も素性も不明だが、かすかな痕跡からおそらく、パッサウの町に関わりがあっただろう、といわれている。
パッサウ(Passau)は、現在のドイツとオーストリアの国境にほど近い、小さな町で、観光名所としても人気の高い町である。
ここは、エッツェルの国へ嫁いで行くクリエムヒルトが叔父の司教ピルゲリーンに迎えられ、しばしの休息を取る町であり、何年かの後にブルグントの人々が辺境伯リュエデゲールの領地に向けて通過していく町でもある。
作品中には「インの流れがドナウに注ぐあたりのところ」に僧院が建っており、「司教ピルゲリーンが住んでいる」とあるが、まさにそのとおりになっている。
詩人は、ブルグント族の本拠地、ヴォルムスの記述では、オーデンの森とワスケンの森の位置を逆に書いたにも関わらず、ここの部分にだけは、実際の情景とぴったり一致する、生き生きとした言葉を当てたのである。
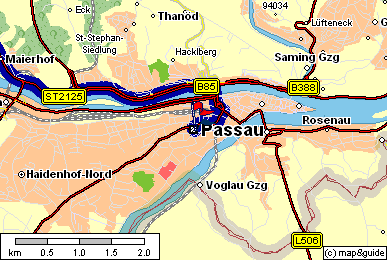 |
詩人は、おそらく、ヴォルムスを知らなかった。そこへは行ったことがなかった。そのかわり、執筆の紙の上で、ドナウ支流の流れるパッサウから、はるかラインの都を見、パッサウで待ちうけ、彼らが通過したあと、死へ向かうのを見守っていたのだ。
当時、「楽人騎士」という、パッサウとウィーンでしか栄えなかった職業があった。
剣をとりながら音楽にも通じたフォルケールは、この階級と符号する。また、パッサウには、物語に登場する司祭ピルゲリーンに相当する、ヴォルフゲルという実在の人物がいたことも確認されている。
パッサウは、クリエムヒルトの婚礼の一行と、武装したヴォルムスの人々の通過地点であると同時に、詩人の視点の中心地である。ふたつの川の交わる地点であるとともに、今から約800年前に、そこで物語を作った詩人と、現代に生きる私たちの、時が交わる場所なのだ。
現在、パッサウは、国境の町として交通の要所でもあるらしい。
パッサウを出た後…。
一行は、エッツェル王に仕える辺境伯、リュエデゲールの領地に入る。パッサウから、旅はドイツを出て、オーストリアへと国境を越えていく。
ベッヒラーレンは、現在ではPöchlarnと書く。町の観光案内サイトには、「ようこそ、ニーベルンゲン伝説の町へ」などと書かれていて、町にとって、ブルグント族の来訪は、かなり大きな意味を持つことがうかがえる。ここには、「ニーベルンゲン記念公園」というものもあり、主要人物の出身地の紋章が飾られているようなのだが、果たしてハゲネのものはいかなる紋章か。
ハゲネは、作品中「トロネゲのハゲネ」と呼ばれている。トロネゲはトロイア、ギリシア神話にも登場する、あのトロイアと同じ響きである。なぜ、そんな名前をつけたのか、また、トロイアとは何処のことだったのかについては諸説あるが、少なくとも、「ニーベルンゲンの歌」の原型となった物語では、彼は「トロネゲ出身の」とは、呼ばれていない。
と、なれば、彼にこの出身地を設定したのは、「ニーベルンゲンの歌」の作者か、あるいは、それに近い時代の誰か、であろう。
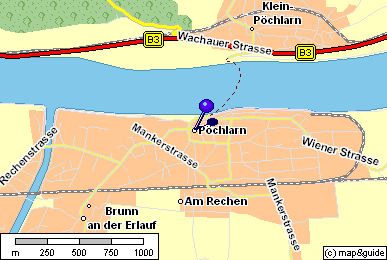 |
| ベッヒラーレン観光案内 |
ベッヒェラーレンを治める辺境伯リュエデゲールは、のちに重要な役割を果たす人物でもある。
この人物は、かつてエッツェル王の求婚の使者としてクリエムヒルトを訪れた時、彼女に忠誠を誓っている。と、同時に、ブルグント族の人々をもとなし、友好を結んでもいる。
クリエムヒルトからは、自分のために戦えと迫られるが、友情を持った人々とは戦いたくない、と、葛藤の中で揺れ動く。
「Swelhez ich lâze unt daz ander begân, sô hân
ich boeslîche und vil übele getan; …」
クリエムヒルトに誓った忠誠と、ブルグントの人々への友情との間で板ばさみになり、苦悩する様子が、切実に伝わってくる。
彼もまた、ブルグントの人々とともに、エッツェル王のもとへと向かう。
ベッヒラーレンには、また、ゴート族の英雄王、ディエトリーヒ(ディートリッヒ・フォン・ベルン)も、身を寄せていることになっている。
ディエトリーヒは、「シドレクス・サガ」では主人公として扱われ、その他にも登場叙事詩を多く持つ、かなり人気のあった英雄の一人だ。
ドイツ南東のバイエルン人にとっては、偉大なる祖先として、今なお畏敬の念を抱く存在であるらしい。
歴史上の人物テオドリクを原型とする英雄王についての伝説は、語ればとっても長い。それ専用のコンテンツがあるので、そちらをごらんいただきたい。
ここでの彼は、領地ベルンを追放され、エッツェル王のもとに身を寄せているところである。
ブルグントの人々に好意を持つディエトリーヒは、クリエムヒルトの企みを忠告し、のちにエッツェルンブルクで再会することとなるが、運命は皮肉にも、この王とブルグントの人々とを敵同士に変え、戦わざるを得ない場面へと持ち込んでしまうのである。
勇士たちの出会い、王と王とのすれ違い、新たに結ばれる友情と、破滅の予感。
ベッヒラーレンとは、ドイツの主要な英雄たちが出会い、一堂に会する場所である。
もてなしと友情。だが、その友情は、のちに彼らの意志とは裏腹に、互いの死をもって断絶される。この町には、クライマックスへと向かう、多くの予感が満ちている。
だが、その予感は単純な悲劇ではないし、また、誰かに踊らされた運命でもない。
彼らはそれぞれ、自分の守りたかったもの、誇りや、忠誠を、守っていた。それは、命をかけてでも守るべきものだった、だから戦ったのではないだろうか?
予言された結末が避けられなかったのは、人々が、みな己自身の運命に妥協しなかったからだ。
私は、そう思う。そして、それを信じたいと思っている。
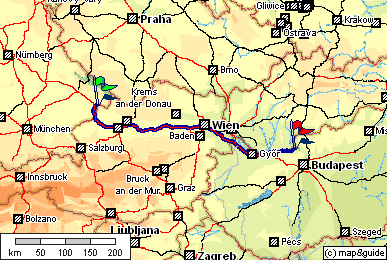 |
| 緑の旗=パッサウ 赤の旗=エステルゴム |
ベッヒラーレンの町を出ると、旅はハンガリーへと入って行く。エッツェル王の拠点、エステルゴムはスロバキア共和国との国境に近い。距離的にはかなりあるが、辺境伯の城からここまでは、何も語られることもなく、あっさり到着してしまっている。
ウィーン、ハイムブルク、ミゼンブルクと3箇所で観光し、優雅に船で下っていったと書かれているクリエムヒルトの輿入れとは対照的である。
もっとも、好意を抱かぬ者が待つ場所へ向かう彼らが、楽しみながら行くはずはないのだが。
ところで、エッツェル王の城のあるエッツェルンブルグの位置については、二つの説がある。
一つは、ハンガリーのかつての首都、エステルゴム(Esztergom、ハンガリーではGran)であるとする説。
もう一つは、岩波文庫の巻末に記されるように、ドナウ河を挟んでブダペストの対岸、オーフェンであるとする説である。
エステルゴムの別名は、グランである。詩節1497に「グランの城下」という地名が出てくることがこちらの説の根拠かと思う。ただし、物語の書かれた当時、この名前が存在したかどうかは分からない。
ブダペスト説については、ハンガリー最古の史書、自称アノニュムス Anonymus
著の「Gesta Hungarorum(ハンガリー人の事蹟)」(1200年頃)なるもの記述が関係しているらしい。
この中で、アトリが王都ブダ(現ハンガリー語でブダヴァル、ドイツ語でエキルブルク)と呼ばれる都を築いたと書かれており、この「ブダ」がブダペストのことと解釈されている、とのこと。しかし、この記録自体はかなり湾曲された部分が多いことが証明されてしまっている。
つまり、どちらの説が正しいかは、今の時点では分からない。少なくとも、私にはっきり言えるものではない。
そもそもエッツェルンブルクとは、Ezelen bourge、「エッツェルの要塞(または拠点)」と、いう意味である。固有名詞ではなく、単にエッツェルのいるところ、と指したもので、その場所の名前が「グラン」だったのだと考えられる。
だとすれば、実際にグランの名がついているエステルゴムのほうが相応しいのではないか。
こういう理由から、このサイトでは「エッツェルンブルクは、エステルゴムだ」と、いう説を採用して使っている。
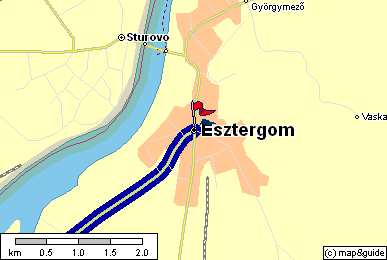 |
エステルゴムの町は、ハンガリーの初代王、聖イシュトヴァーンが生まれ、戴冠した、ハンガリー最初の都である。町には立派な、イシュトヴァーンを祀る大聖堂がある。写真でした見たとはないのだが、この壮麗な大聖堂と、その向こうに広がる町並みとドナウ河とが、何ともいえず、「ニーベルンゲンの歌」のクライマックスを思わせる。
ブルグント族とエッツェル王の家臣たち、さらには、ディエトリーヒの家臣であるアメルンゲン人(東ゴート族のことだ)をも巻き込んだ戦いは、物語上に出てくる数字を計算すると、15,000人以上に上る。
これほど多くの人々が死んでゆくのだから、物語のタイトルに「災い」がつけられても、当然と言えるだろう。
そして災いは、最後の一人の命までも求めた。
多くの人々の命を奪う戦いを引き起こし、恐ろしい復讐を成し遂げたクリエムヒルトは、その残虐性ゆえに、ディートリッヒの家臣ヒルデブラントによって誅殺されるのである。
人々はみな死に絶え、生き残った者の慟哭だけが聞こえる。
「ニーベルンゲンの歌」は、ほぼすべての主要人物が命を落としたあとに、人々の歎きを持って終わりを告げる。
だが、残された人々の人生というのは、それからのちも続いていく。
墓をつくり、また元の暮らしを取り戻すまでに、一体、どのくらいの労力と年月を擁したのか。
失われたものが大きければ大きいほど、取り戻すのは容易なことではないはずだ。
激しさと、その後に残る静けさ…大聖堂は、生き残った者の祈りが捧げられる場所になるのだろうか。
ここで、ドイツのヴォルムスからオーストリア、ハンガリーと3カ国を経てきたブルグント族の旅は、エッツェルンブルクにて終わりを告げる。引き返す道はなく、生きて帰った者はいない。
力の限り、己の信念を貫いた者たちは、悔いを持たずに死んだ。ハゲネとその一族郎党も、リュエデゲールも、クリエムヒルトさえ、憎しみを抱く相手を自ら手にした剣で貫けて、本望だったかもしれない。
だが、信念を持たなかったエッツェル王は生き残った。生き残って、ただひたすらに嘆く。
エッツェルの嘆きは、多くを失った悲しみとともに、自分に命を賭けられるものが無かったことを知った嘆きである。
この物語の中で語られる「愛」とは、北欧神話の世界観の中では「絆と使命」である。ゆえに家族も恋人たちは絆で結ばれ、復讐は、使命として行われる。
女は、うわついた愛の言葉よりも目に見える財産を、口だけの約束よりも血の誓いを示せる者をこそ、夫として迎えるべきである。誓いは何よりも重く、破ることは死を意味する。
その厳しいまでの愛は、古代北欧の世界観では悲劇でも残酷なことでもなく、当然のことだった。
戦いは、竜や怪物ではなく人間を相手として行うものである。人間ほど恐ろしい敵はいない。敵となり、味方ともなる。怪物には無い、神々の加護や信念や、彼自身の守るべきものや、多くのものを背負って襲い掛かってくる。
「ニーベルンゲンの歌」は、人と人との戦いの物語なのだ。
傷つくも、死ぬのも、すべて人間。しかも、それぞれの人間がそれぞれの信念や戦う理由を持ち、それを掲げてぶつかり合う。誰が正しく、誰が間違っているのでもなく、己の信じたものを譲らなかったために、皆果てる。
そこに面白さがあり、悲しさがある。人間という存在を強く感じさせる。
力強さもまた、人々の意志のぶつかり合う中から生まれてくるように思う。
信じるものの名を「愛」と呼んでも良い。だが、その「愛」のために、誰が本当に命を賭けられるだろうか。
+++
これは、古代北欧世界で小人アンドヴァリに呪われし黄金を手に入れた英雄たちが13世紀に歩んだ運命の道を、机の前に座ったまま、物語の通りになぞり歩く企画である。
物語の中では、マイン川からバイエルンの国までをハゲネ、バイエルンの国から辺境伯リュエデゲールの領地までフォルケール、ベッヒラーレンからエッツェルンブルクまでリュエデゲール…と、それぞれの国に先に立って案内してくれる人物がいる。この文章が、今からこの物語の深みに触れようとする誰かの案内役になれれば、と思う。
かつてその道を空想のままに辿り、物語を作り上げた詩人がいた。
そして今なお、多くの読者が、その道しるべのまま、過去の何時にも存在しなかった架空の歴史の中に、同じ道を辿り続ける。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()