|
第六章 部屋の中が真っ暗だった。 ベッドの横、小さな卓にろうそくが一本だけ立っていて、弱い光が揺らめいている。 窓と入り口の扉は閉められている。隙間から明かりが漏れてこない事で、尚志は夜になっている事を知った。 季迪老と子孟に話をした後、尚志は強制的に眠らされてしまった。子孟が尚志の腹をしたたかに叩いたのである。優男みたいな顔をしてるが、子孟は農家の跡取りだ。強烈な一撃で、尚志はノックダウンさせられてしまった。 おかげで、体はかなり楽になったようだ。痛みもなくはないが、転げ回るほどじゃない ベッドの上で体を起こそうとすると、背骨がボキボキと鳴った。 「いてててっ・・・あれ」 ベッドの枕元に西河がいる。粗末な椅子にちょこんと座り、尚志のベッドにうつ伏せになって眠っていた。 艶やかな小麦色の肌に、所々絆創膏が張られているのが痛々しい。泥に浸かった髪はきれいに洗われていた。小さな紅い唇が少しだけ開き、安らかな吐息をもらしている。 柔らかい灯火が、西河の寝顔を照らし出した。薄暗い中だと、いつもより大人びて見える。可愛いと言うより、美しい。 「寝てりゃ可愛いんだけど、な」 「誰が」 「げ」 西河の目が開いていた。 「げって何。起きてちゃ悪いの。・・・それより、体を隠しなさいよ! レディーの前でみっともないわねっ」 (どこにレディーがいるんだ・・・) 心中ぼやきながら、尚志は黄ばんだ掛け布を引っ張った。 「大丈夫なの」 語調はきついが、顔は怒っていない。 「生きてはいるな。この痛みがとれるなら、死んでもいいって気分だけど」 「・・・そんな」 「あン?」 「死ぬなんて、簡単に言わないでよ」 「はいはい」 「・・・・・・・・・・」 西河の様子がどうもおかしい。よくわからないが、いつもと違う。やりにくい。 「西河こそ大丈夫か。足はどうした」 「もうだいじょうぶ」
尚志が身を乗り出すと、若草色のズボンに隠された小さな足が見えた。そのまま視線を上に持っていくと、青のストライプが入ったワイシャツを着ている。肘までまくった袖から細い腕が出ていた。 「その服は」 「誰かさんが山に連れてってくれたおかげで、あたしのカバンがなくなっちゃったの。これは子孟さんのお母さんから借りたわ」 「・・・・・・・・・悪かったな」 「!」 西河は肩をすくめ、視線を逸らした。 「べ、別にいいけどね。大した物は入ってなかったし」 「そうか」 「うん」 やはり、おかしい。 「それより・・・あのね尚志」 「なんだ」 「あ、あの、あたし・・・」 西河はそこで言葉に詰まった。 (・・・・・・変だ) いつもの挑戦的な目付きでこっちを見ようとしない。傲慢なほど落ち着いた常の態度もない。そわそわして見える。 「なあ、西河」 「・・・なに?」 「お前、聞いたか」 「あ・・・愉さん家の事? 聞いた。大変みたいね・・・」 「いや、それも大変だけどそうじゃなくて」 「何よ」 「お前のことだよ」 「え、ええっ? あ、あた、あたし? 大変なの?」 尚志は溜め息を吐いた。 「違うって。だから・・・・便所の場所知ってるかって」 「便―」 「行きたいんだろ。一階の階段の下だぞ」 「・・・・・・・・・・・・・・・・」 ぴしっ。 尚志は空間に亀裂が入ったような錯覚を覚えた。 「・・・・・・・・・・・尚志」 「おう」 「バカバカッ!!」 客家の土楼に、痛快な破裂音が二回響いた。
作戦室から、昨夜持ち込まれた無線機が全て運び去られた。残っているのは作戦室に備え付けの無線機だけだ。省軍に作業を引き渡した部隊は撤収し、すでに全軍の三割が帰投済みだった。さらに半数が基地に向かっている。 司令員席に座る梁が、コップの水を飲み干した。口髭から滴が垂れる。 「作戦終了の実感が湧いてきました」 上官にハンカチを差し出しながら、俊卿が言った。 「そうだな。兵が戻ってくれたおかげで、今日は枕を高くして眠れる」 嘘だ、と俊卿は思った。南京司令部の命令を無視しておいて、平静でいられるわけがない。 実を言うと、俊卿のほうが一日中ビクついていた。いつ上海から問い合わせが来るか、叱責が飛び込むか。司令員の後に作戦室へ入った時は、俊卿の真っ青な顔に通信士官が絶句したくらいだ。 それに較べて梁は大したものだった。顔色はもちろん、口調から態度から、普段と一切変わりない。梁がいつもより多く水を飲み、いつもより多く便所に行った事に気付いたのは、事情を知っている俊卿だけだった。 (それにしても、どうされるつもりなのか・・・) 山の中の死体を探せなどという論外なものでも、命令は命令である。全軍の手本たるべき司令員だ。その地位にある者が命令を無視したとあっては、ただで済むはずがない。間違いなく一緒に処分される自分よりも、司令員のために俊卿は心配した。 人民解放軍では、人が死なないという事以外なら、どんな事でも起こりうるのだ。 副司令員が席を外した折に、俊卿は「どうするんですか」と司令員に聞いてみた。 「どうもせんよ」 「見せかけでも兵を動かしておけば、いざという時に言い訳がたちます」 「くだらん」 それが梁の答えだった。 「死んだお嬢ちゃんには可哀想だがな。死人のために疲れ切った兵士を鞭打てるか。論外だ」 「しかし司令員のお立場が・・・」 梁は耳元の俊卿の顔を見た。副官が真剣に梁を見つめている。かすかに笑って、梁は俊卿にささやいた。 「どちらにしろ、私は今期限りで退役させられるのだ」 「ええ!?」 思わず俊卿は大声を出し、作戦室の全員から注目を集めた。素早く司令員から離れ、平静を取り繕う。 (司令員が、退役?) にわかに信じられない話だ。梁はまだ五十代の前半。 解放軍には六十代の司令員がゾロゾロいる。退役にはあまりに早い。 再び近付いて俊卿がそれを指摘すると、梁が首を振った。 「私はどの派閥にも与しなかった。だから、これ以上の出世は望めん。野戦軍の司令員になれただけでも、我ながら大したものと考えておるよ。なあに、五十を超えれば恩給だってそこそこ貰える。後悔はない」 俊卿は何も言えなかった。 「それに」 悟りを開いたように、梁の相貌は穏やかだ。 「借りは返しておかんとな」 「借り、ですか?」 俊卿は梁の着任時から仕えてきたが、世話になった事こそあれ、梁が誰かに助けを求めた記憶はない。 「二年前の洪水、覚えているか?」 「もちろんです」 あの時も酷かった。 当時の野戦軍司令員はどうしようもない官僚主義者で、要請を受けてからでないと何もしようとしない。準備も用意もしていなかったから出動が遅れに遅れ、降水量は少なかったのにとんでもない被害が出てしまった。 「あの時、私は南平にいた」 南平は三つの河川が合流する町だ。交通の要所であると同時に、水害の町としても知られる。 「水に追いつめられた所を、南平の人々と省軍兵士に助けられてな。見も知らぬ私に良くしてくれた」 「そのお話、初めて聞きました」 梁はわざとらしく顎に手を当てた。表情をごまかす時の癖だ。 「誰にも話すな」 「承知しました」 自尊心の高い司令員らしい、と俊卿は思った。人助けは好きでも、助けられるのは恥ずかしいとは。 「借りは、返さねばならない」 ゆっくりと静かに梁は呟く。それから肩の力を抜いて椅子に沈み込んだ。 「これで借りは返した、と思う。心おきなく退役できようものだ」 敬愛のこもった声で俊卿は進言した。 「宿舎にお帰りになりますか? 後は自分どもが」 その時、通信士官が俊卿を呼んだ。 「愉中尉(ユィ・チュンウェイ)! 建陽(チェンヤン)から中尉に緊急連絡です」 俊卿が振り返ると、通信士官がヘッドセットを差し出している。 「自分に?」 通信士官は頷いた。
カタカタカタ・・・・ 三十一野戦軍の作戦室で、小刻みに机が鳴っていた。 それが自分の机の音と気付くまで、俊卿は一分かかった。足が震えていたのだ。 土楼が倒壊。 家族全員、泥の下。 弟は消息不明・・・ この三つだけが、頭の中をぐるぐると回っている。仕事柄、人の生き死には慣れているものの、自分の家族が全滅という時に冷静にはなれなかった。 「俊卿、足」 梁が小声で忠告した。気を抜くとすぐ足が震えてしまう。俊卿の顔は貧血症の白熊より白かった。 俊卿は武夷の客家だ。愛郷心と団結力が強い福建人の中でも、客家のそれは特に有名である。野戦軍の士官もみな福建人だから、俊卿の立場が痛いほどわかる。作戦室の全員が、俊卿を気の毒そうに見ていた。 「俊卿。お前、帰るか?」 梁が言うと、副司令員らも賛同した。 「・・・ありがとうございます。しかし救援活動が終了しておりませんので。お気持ちだけ頂きます」 梁が溜め息を吐いた。 もちろん俊卿とて、一刻も早く飛んでいきたかった。しかし家族が死ぬたびに兵士を帰郷させていたら、軍隊など成立しなくなってしまう。洪水で家族を亡くした兵士は、他にいくらでもいるはずだ。司令員の副官が悪しき例となるわけにはいかない。 梁は俊卿を見ながら、ボールペンで、薄い髪を梳いた。 (いい男だが、どうも真面目すぎていかん) 梁は部隊配置図を見ると、急にニタリと笑った。 「俊卿!」 「は? はっ」 慌てて立ち上がる副官を見ると、厳しい面もちで司令員は命令した。 「貴様弛んでおるぞ! 少し頭を冷やして来いっ」 作戦室の部下達は司令員の言い方に驚き、やがて非難の眼差しを向けた。 (そうだ。任務は任務。私事を任務に持ち込む事は許されない・・・) 俊卿がうなだれて部屋を出ていこうとすると、梁が副官の袖を掴んだ。 「どこへ行くのだ」 「はっ。顔を洗ってまいります!」 俊卿が空いた手で敬礼する。 「そんな事せんでいい」 「は?」 俊卿は上げた手を下ろした。 何を言っていのか。 「実はな。あれから考えて、やはり私もお前の薦めに従う事にした」 真面目な顔で梁が言うものの、俊卿には何の話だかわからない。 「・・・死体探し」 (あっ!) 梁が指摘して、ようやく思い出した。言われた通り、気が弛んでいる。 「作戦指揮の現場に立って、根性付け直してこい! 好きなだけ部隊を連れていい。全速力で武夷山脈に急行するのだ、いいな!!」 (閣下・・・) 「了解しましたっ」 再度敬礼する副官に司令員は素早く、しかし絶妙に眉を上げてみせた。 作戦室を飛び出した俊卿は、廊下を急ぎながら司令員の言葉を思い出した。 (借りは、返さねばならない・・・) 司令部の出入口で立ち止まる。満天に星々が輝いている。昨日、同じ空から大雨が降ったとはとても思えない。
拳を固めて空を見上げた。 (・・・そうとも) 借りは、返さねばならない。
腹が痛かった。 尚志が「死にそうだ」と言うと、傍らの西河も「あたしも、もうダメ」と応える。 二人は、阮家の晩飯から戻ったばかりだった。 晩餐では三十人の老若男女が勢揃いした。聞くとこれが家族で、皆この康成楼に住んでいるという。 阮家の土楼は円形だった。かなり広い。端から端まで四十メートルくらいあるだろうか八メートル四方の中庭に、井戸と小さな建物がある。その横を鶏が歩いていた。 核家族で育った尚志は、まず三十人の家族に度肝を抜かれた。子孟から、客家は一族集まって生活すると聞いていたが、まさかこれほどとは。尚志がそれを口にすると、季迪老は笑って「五十年前には百人住んでましたんじゃ」と言ったものである。聞けばもっと大きな土楼もあるという。ちょっとした団地だ。 着席すると、全員が自己紹介した。しかし多すぎて覚えきれない。尚志の横に座った西河は、五人目あたりから目を白黒させた。尚志は九人目まで頑張ったのだが、季迪老の姉の三男の妻の誰かに挨拶したあと、覚える努力を放棄した 食事は見た目荒っぽいが、味はなかなかのもの。しかも量がどっさりだ。西河は「あなたの分よ」と目の前に、丸々と太った鶏の塩蒸しを一匹ドカンと置かれ、思わず後ずさりした。尚志が手伝って何とか平らげたものの感想は一言。 「しばらく鶏はいらない」 料理の名前は聞き損ねたが、豚の煮物は最高に柔らかかった。スパイスが効いてて、食べるとじんわり旨味が広がってくる。子孟のお母さんに旨いと誉めたら、 「ありがとう。あの子もきっと喜んでくれるわ」 そのとき中庭で母豚が哭(な)いた。 格別にうまかったのは揚げ出し豆腐だ。最初は脱色した糞みたいで尻込みしたのだが、食べると味付けが抜群にいい。変な形なのは、日本のように型押しするのではなく、布巾に包んで作ったから。つまり豆腐も手作りなのだ。 尚志は最後に干物を渡され、「栄養がある」と言われて感謝しつつ食べてみた。やけに硬くて、飲み込むのが難しい。何かと聞いたら、誰かが教えてくれた。 「裏の山にいた長虫(チャンチョン)だよ」 「・・・・・・・・・・・・」 蛇だった。
「いくらなんでも食べすぎよ・・・」 ベッドに突っ伏したまま、西河が呻いた。 「そういう自分だって鶏一匹食ったくせに」 「鶏なんて言葉、聞かせないで」 尚志は立ち上がり、腹をさすった。この一時間で二周りは太ったと思うのは気のせいだろうか。 尚志の今の服装は、薄茶のシャツと、黒に近い藍色のズボンだ。 子孟の服を借りた(ちなみに代金を払おうとしたら怒られた。義理堅い一族だ)。 軽く肩を回し、膝を曲げてみる。痛みは残っていたが、歩けないほどじゃない。 (蒲城まで8キロ強・・・・行けるか) いや、行ける行けないは問題にならない。 「西河」 「んー」 くぐもった声が気だるげに応じる。 「足はもういいんだな?」 「いいよー」 「よし。行くぞ」
少女が動きを停めた。 「・・・・・・・・・・・え?」 「行くぞ、西河」 尚志に呼ばれて、ゆっくり顔を上げる。 「行くって、なに」 「ボケたか。期限まであと14時間しかないぞ」 「ええっ!」 西河は跳ね起きた。 「ホントに!?」 「やっぱりボケてたか・・・」 「そうじゃなくって!」 首をぶんぶん振って、尚志の顔を覗き込む。 「尚志のこと。大丈夫なの?」 「気持ちは嬉しいけどな、契約が最優先だ」 「そんな・・・無茶しないでよ」 「・・・・・・・・・・・・」 どの口でそんな事を言うか、と尚志は思った。 「全力を尽くすという契約だった。それに、俺の体がどうなろうと俺の責任だ・・・西河が気にする必要はない」 「気にするなって、尚志・・・」 「わかったら立ってくれ。一秒でも惜しい」 「ちょっと待って。あたしの話を聞いて」 「道中で話せばいいだろ」 「尚志!」 最後のは、ほとんど悲鳴だった。 「・・・・・・」 「・・・・・・・・・・・もういいの」 「何が」 「契約は、もういいから・・・・・・だから」 「何がいいんだ。家族に会うんじゃないのか」 「会いたいわよ! 約束だもん! でも、でもそうじゃない・・・・・今言いたいのはそんな事じゃないよ」 「西河・・・・?」 彼女は尚志を見ようとしない。寝台にかけた手で、シーツを握り締める。 「わかってる。最初からずっと、あたし、ワガママだったから。尚志が思ってることもわかる・・・・たぶん。 だけど・・・・やっぱり駄目だよ・・・あたしのワガママで尚志が痛くしなきゃいけないなんて、そんなの駄目。ぜったいダメだよ!」 「西河・・・・・・・・・・」 西河の膝に、ぽつっと雫が落ちた。 「・・・・・・・・ねぇ」 「ん」 「どうして?」 「・・・・・・・・何がだ」 「どうして、尚志はアタシのためにそんな一生懸命なの・・・?」 「・・・・・・・・・・それは」 尚志は西河から顔を逸らした。 「それは、お前のためじゃない」 「え?」 少女から視線を外したまま、低い声で話を続ける。 「俺は、ある子と約束した。二度と・・・仕事で手を抜かない。手を抜いて、誰かを不幸にはしない、と」 「ある子・・・?」 「もう、この世にいない」 自分のせいで― 「・・・・・・・・・・・・」 「・・・・・・・・・・・・」 尚志は心から噴き出る思いを戻すように、胸を押さえた。 「俺は、俺のために仕事をしている。だから西河も、自分の事だけ考えてればいいんだ」 西河が涙の浮かんだ目で尚志を見つめた。 「・・・・いいの?」 「ああ」 「ホントに?」 「ああ」 「あたし、ワガママだよ」 「慣れた」 「無茶言うし、すぐ叩くよ」 「それも慣れた」 「もうっ!」 西河は目を赤くしたまま、それでも笑って、尚志を叩くフリをした。 「そうだ、西河。訊いていいか」 「何」 尚志はベッドに腰掛けた。 「どうして広州に行かなくちゃいけないんだ。どうして時間に拘る。・・・・・ま、答えたくなきゃ別に答えなくてもいいが」 「知りたい?」 尚志は頷いた。 お金持ちの嬢ちゃんが、死ぬような目に遭ってまで行こうとする事だ。興味がないといったら嘘になる。 「あたしも尚志と同じ。約束があるの」 「聞いた」 「そうだっけ? それがね、一年前からママとパパ別居してるの。ママは広州にいて、あたしとパパが上海」 「・・・・・・・・・」 尚志の頭を『不幸な家庭の図』がよぎった。父親が浮気して母親が家を出る。そして子供が板挟みになるという例のヤツだ。 「あ、変な事考えてるでしょ? そんなんじゃないからね。パパがお仕事で上海に行かなきゃいけなかったんだけど、ママが広州を離れたがらなかったの。それだけよ」 尚志は苦笑した。 「でも、ずうっと会えないのも嫌でしょう? だからパパとママの誕生日に、みんなで会おうって約束したんだ。パパの誕生日には上海、ママの誕生日には広州の家でって」 ここで西河はきっと顔を上げた。 「それなのに! パパは誕生日に広州へ戻らないって言うのよ! 去年のパパの誕生日には、ママがちゃんと上海に来てくれたのにっ!」 いきなりの怒声に尚志は背筋を伸ばした。自分が怒られている気がする。 「パパったら、『仕事が忙しい』って。しょうがないからあたしだけ行く事にしてたの。そしたら直前になって、突然出発を取り消しちゃったのよ! ひどいと思わない!?」 「そ、そうか」 他に言いようがない。 「理由を聞いたら、『心配だから』だって! 馬鹿にしてるわよね! あたしみたいに一人前のレディーに対してっ」 尚志の脳裏を、泥道でバタつく西河の姿がかすめた。 「そりゃあ、迪斯科(クラブ)でお酒飲んだのは失敗だったわよ。でも騙されてんだからしょうがないじゃない。タクシーの運転手さんのおかげで何もなくて済んだしさ!」 どこかで聞いた話だった。 「納得できなかったから、ゼッタイ行くと決めたの。旅費はお小遣いがあったし、約束を破ったらママが可哀想だもん」 「可哀想、ね」 ・・・上海駅で一時間半も切符を探し続けて、やっと買ってきたら「硬座は嫌」 ・・・危ないし面倒だって警告して、さらに承諾を得てから山に入ったのに、「一生恨んでやる」 ・・・命がけで救ってやったら、再会して五分で平手打ち二連発。 母親への豊かな愛情を他人に分け与える余裕はないのか。 「ねっ、ひどい話でしょう!?」 「・・・・・・・・・そうだな」 (おかげで俺は死にそーになった) 尚志は大きく息を吸い上げ、海より深い溜め息を吐いた。 「ところで西河。お前、自分の小遣いから旅費を出したって言ったよな」 あの金額、小遣いにしては多すぎる。 「西河ん家はそんな大金持ちだったのか?」 「当たり前じゃない! あたしを見ればわかるでしょう」 (どうしようもなく自己中心的な所は金持ちらしいな) 「親父さんは何をやってるんだ?」 「知らない。色々だって言ってた」 「それじゃわからないって」 「知らないもん」 「お前、親の仕事くらい確かめとけ。学校で困るぞ」 「困らないもん。あたしが知らなくてもみんな知ってるから」 「何だって?」 尚志が詳しく聞こうとした時、轟音が土楼を覆った。 「うるさいな」 「飛行機じゃないの?」 見えるはずもないのに、西河は天井を見上げる。 「違う」 飛行機ならすぐに遠ざかるはずだ。それに、窓から風を切る甲高い音が流れてくる。 「これは・・・」 「尚志!」 扉を蹴破るようにして、子孟が部屋に駆け込む。 「びっくりですよ。こんなに早く着くなんて!」 尚志と西河は顔を見合わせた。 同時に尋ねる。 「誰が」 「来て下さい。小愉の命の恩人を紹介しないと!」 「おいおい?」 「ああっ、尚志に無理させないで!」 「大丈夫大丈夫」 何が大丈夫なのか、子孟は強引に尚志を引っ張りだした。 中庭を強風が渦巻いている。 雨上がりで良かった。さもなければ埃が空まで舞い上がっていただろう。 爆音に空気が震えていた。 中庭の真上で、こうこうとライトを輝かせたヘリコプターが滞空している。
子孟が叫んだ。 「愉俊卿です! 雲卿の兄の!!」
(続く) |
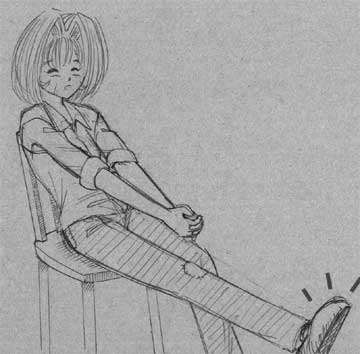 「もうだいじょうぶ」
「もうだいじょうぶ」 「!!!」
「!!!」 「満点の星」
「満点の星」 「よし。行くぞ」
「よし。行くぞ」 「軍用ヘリコプター」
「軍用ヘリコプター」