|
第五章
福建省に、曙光がさしこんだ。 豪雨は午前四時頃、蛇口をしめたようにピタリと止んでいる。黒雲は飛び散り、天に蒼空、地に泥水が残った。
中国の河川の特徴は、色にある。多量の沃土を含んだ黄色。それは上流の土が溶けてきたものだ。洪水の水も濁っていて、平野に氾濫した水は大地に黄土色の爪痕を残す。いま福建上空を飛べば、大地が、死人の顔さながらの土気色に見えるだろう。 この豪雨によって流された福建省内の橋は百八十脚。決壊した堤防は四千カ所を超えた。浸水による被害、暴風による破損を被った家屋は二十九万戸以上で、その四分の一は全壊状態だったという。 福建人の生活基盤を圧壊して、水禍は終結した。
水田の真ん中に築かれた土手道を、一人の青年が歩いていた。 履き古したズボンの裾を濡らして、冠水した稲の様子を見て回っている。くたっと寝転がった稲を水から引き揚げると、指先を添えて丹念に調べた。 「・・・・このたんぼも駄目か」 青年は稲穂を投げ捨てた。
肌が若々しく、眉がきりっと引き締まった好青年だ。笑えばいい顔になるのだろうが、今は暗い影に覆われている。 青年の名は阮子孟。農家の跡取りで、悪い知らせを家に持って帰る所だった。 ここは福建で一、二を争うド田舎。 昔からこの一帯には客家が住んでいる。客家は「お客さん」という意味で、大昔、華北から戦乱や飢餓を逃れてやってきた人々だ。良い土地に住めず、多くは山間の僻地に一族集まって住んでいる。かつては警戒心が強く、要塞化された土楼に拠って暮らしていた。現在でも土楼は残っていて、実際に人が住んでいる。 子孟も客家だ。 特に大きなその土楼から、地元の者ならずとも、阮家の康成楼(カンツンロゥ)、愉家の隗元楼(コェイヤンロゥ)は知っていた。隗元楼は阮家の隣家で、濃厚な血縁関係があって特に親しい間柄だ。 いや、間柄『だった』。 「爺ちゃんになんて言やいいんだ・・・」 ぼそりと子孟は嘆いた。 台風に洗われた空は限りなく青い。細い谷間に開かれた水田が、陽光でキラキラ光っている。台風一過のさわやかな朝だ。どんなに感性の鈍い者でも、この風景には心が躍るだろう。 しかし子孟は例外だった。 「・・・はあ」 谷に沿って道を曲がると、斜面を登る小道がある。この小道をずっと登っていくと、武夷山脈の山道に出るのだ。 「・・・ん?」 子孟は周囲を見渡した。赤ん坊の泣き声が聞こえる。 「気のせいか・・・」 気のせいじゃなかった。 小道から土手に上がる階段に、汚い男と少女が座り込んでいた。泣き声は二人の間から漏れているようだ。
少女が男にもたれ、男は土手に体をあずけている。二人とも目を瞑っていた。泣き声は、男の胸元から聞こえる。 男は疲れきった顔をしていた。穴だらけの雨ガッパから、泥の染み付いた作業着が覗ける。胸の部分がおかしな形で膨れていた。 少女のほうは黒いTシャツの上に、これまたボロボロの雨ガッパを着込んでいる。 二人とも、これ以上ないほど泥まみれだ。 子孟は、水を吸って緩んだ階段を用心して降りた。二人の前に屈みこみ、泣き声の正体を探る。 息を呑んだ。 「なんてこったい」 子孟は駆け出した。
副官は梁司令の大声に耳を疑った。 「今、この状況で全員撤収しろと言われるのか!! ありとあらゆる場所で人民が水に溺れかけているんだぞっ」 「全員撤収!?」 思わず言葉の漏れた口を、俊卿は慌てて塞いだ。 (撤収? たしかに防衛体制は不備だが、全員撤収とはどういう事だ?) 梁と俊卿は、仮眠を取るため司令員室に戻った所で無線通話を受けた。相手の言葉は丁寧だが、冷たい。それにかすれるほど低い。 『申し訳ありません』 全然申し訳なさそうに聞こえない。 『史(シー)閣下は貴軍の活躍を大変に評価しておいでです。しかし別命を優先するように、とも言っておられます』 「別命とは、何だ!」
梁の大声を気にしていないのか。それとも声が遠いのか。相手の口調は冷静なこと極まりない。 『シェ令媛の事はご存じですね。令媛はそちらの管轄区内に赴かれたようなのです。動員できる全ての兵力を用いて令媛を捜索救出せよ、との史閣下のご判断です』 「どこを探せというのだ! 福建は南京みたいにちっぽけな街じゃないんだぞ!」 そんないい加減な命令に従う阿呆がいるかと、梁は余計な一言を言いそうになった。 『重点調査位置を、さきほどそちらに電送しました。富屯渓(フーテンシー)より北のどこかに居られると予想されます』 富屯渓は福州の上流。武夷山脈を両断して流れる川だ。梁は壁面に張られた地図をさっと目で追った。 (これは死体を探せという事だな) あの雨の中で武夷の山にいたとは、不運なお嬢さんだ。まず命はないだろう。谷に落ちたか土砂崩れに巻き込まれたか、いずれにしろ生存の余地はない。 「了解した。しかし当方の限られた兵員では多大な時間を要すると思うぞ」 心の中で、見つける頃には骨になっとるかもしれんな、と付け加える。 『承知しております。ですから、省軍を自由に采配しろ、との史閣下のお言葉も頂いております』 「何いっ!!」 梁は完全に激発した。 「省軍こそが洪水対策の中心だろーが! 連中がいなくなったら誰が人民を救う!!」 『申し訳ありません』 実に見事な棒読みだった。 『しかし浙江や江西の部隊も動いております。貴軍が動かなければ、そちらの省長殿がこの先おおいに迷惑を被りましょう』 説明の次は脅迫か。 「・・・了解した(この人非人め!)」 『ありがとうございます。史閣下にそのようにお伝えいたします』 会話が終わった。 資先は心の中で数え始める。 一、二、三。 「ふざけるなーっ!!」 梁が怒号して受話器を壁にぶち当てた。受話器が粉々に砕け散り、コードに引っ張られて本体も床に落ちる。 「広州のシェ家が何だ! ガキの死体を見つけるために三千万の窮民を見捨てろというのか! 省軍を自由に采配しろだと!? 身内を見捨てろと言われて兵士が動くと思うのか!!」 野戦軍も省軍も、兵士は地元出身だ。梁は違うが俊卿だって福建人である。命令が絶対といっても、身内を放って山に行けと言われて、素直に従うはずがない。たとえ行ってくれたとしても、土砂崩れにでも巻き込まれて死体の数を増やすのがオチだ。 梁は白い壁をしばらく睨み付けていたが、やがて荒々しく椅子に座った。肩が激しく上下している。これほど激した司令員は初めてだった。 それにしても信じがたい命令だ。どう考えても正気ではない。 (それだけあの一族の影響が強いという事か・・・) シェ令媛を預かっていた偉いさんの面子もかかっているのだろう。 (死体一つを見つけるのに全兵員を投入しろとはな。やるだけはやりましたよ、とでも一族に言うつもりか?) ・・・おそらくそうだろう。 馬鹿馬鹿しい話だった。 「俊卿」 いつの間にか、梁は窓際に移動していた。外では、シュロの木から水滴が落ちている。一滴一滴が、太陽の光で輝いた。 「はっ。司令員閣下」 「・・・」 梁は振り向かなかった。俊卿の位置からは、梁の表情が読めない。 「お前は、たった今、部屋に入って来たんだな?」 「は?」 わけがわからない。 「俊卿は、電話の壊れる音を聞いて、部屋に入って来たんだろう?」 よくわからなかったが、とりあえず俊卿は「はい」と答えた。 「ふむ・・・」 梁がわざとらしく咳をする。 「俊卿、私は寝ぼけて電話を床に落としてしまった。すまないが替えの電話を持って来させてくれ」 「・・・はい」 沈黙。 「・・・・・・・・・・・・」 「・・・・・・・・・・・?」 先に静寂に耐えられなくなったのは、俊卿だった。 「あの、閣下・・・それだけ、ですか」 「他に何かあるのか」 梁は素気ない。 「はい。各地の兵員を集合させなければ・・・」 「俊卿!」 梁が怒鳴った。 「部屋にいなかったお前が命令の内容を知っているわけなかだろうが!」 「なっ」 (そういう事か!) 「さあ、今日も大変だぞ。まず兵士に交代で休息を取らせるよう、指示せねばならん。そういえば、連中は飯も食ってないだろう。兵站部に用意させねば。いやはや、忙しいものだな」 俊卿は黙って電話器を拾い上げると、司令員に敬礼して部屋から退出した。
気が付くと、誰かが尚志の顔を覗き込んでいた。 「・・・・・・・?」 焦点がぼやけてよくわからない。 「大丈夫かい」 少しずつ視界がはっきりしてくる。見知らぬ、若い男が尚志を見下ろしていた。 「ここは・・・」 尚志の声を聞き取って、若者は肩の力を抜き、にっこりした。抜群に笑顔が明るい。彼は顔を離して、近くの椅子に腰掛けた。 暗い部屋だった。床と天井は板張りで、黄色い壁は土壁のようだ。暗いのは扉と窓が小さいせいだった。窓は特に小さい。縦には長いが横幅が三十センチあるかないかなのだ。 尚志の横たわるベッドは土壁に押しつけられていた。乾燥したシーツと掛け布が体を覆っている。 身に付けているのは、腕時計とトランクスだけだった。 服を脱がして体を拭いてくれたらしい。 「目が覚めてよかったよ。訊きたい事がたくさんあってね。待ってたんだ」 若者がほっとして言った。 尚志は頷こうとした。 「ぐっ!?」 その瞬間、全身が痛みを訴え始めた。どこが痛いというのではなく、全身にまんべんなく激痛が走る。体中を針で刺されているようだ。耳たぶや髪の毛穴までが悲鳴をあげていた。 「う・・・・・・・ううっ」 尚志のうめき声に若者が眉をひそめる。しばらく我慢していると痛みにも慣れ、尚志はわずかだが声も出せるようになった。 尚志が名乗ると、若者も自分を指す。 「林尚志ね。僕は阮子孟。ここは蒲城(プーチョン)からちょっと離れた康成楼って所」 「康成楼・・・・・・」
若者の言葉には変な癖があった。公用語にのっとった語調なのに、ときどき福建なまりの単語が混じるのだ。尚志は土壁を見た。ゆるやかに曲がっている。窓枠からわかる壁の厚さは、三十センチを優に超えていた。 「客家の土楼・・・?」 「そうさ。僕が今朝、尚志たち三人を見つけた。みんなでここに運んで来たんだ」 「そうか、ありがとう・・・・・」 尚志はかっと目を開いた。 「みんなは!? 西河と小愉はどこだ!? 無事なのか!?」 急に動いたせいで、背筋を再び激痛が走る尚志は歯をくいしばり、呻きながら痛みをこらえた。 子孟は尚志が落ち着くまで辛抱強く待ち、再びしゃべり始めた。 「そんな一遍に訊かれても答えられないよ。大丈夫。二人とも生きてる」 尚志の全身から、安堵で力が抜けた。それを見て子孟が席を立つ。 「ちょっと待って」 二分ほど経っただろうか、尚志の部屋に腰の曲がった老人が入って来た。すっかり色落ちした人民服を着た、動作のゆったりした爺さんだ。右目の横にある黒子(ほくろ)が印象的だった。 「尚志。僕の祖父、阮季迪(ロァン・チーティ)。この康成楼の長で、阮家で一番怖い人!」 老人が渋面を浮かべると、子孟は対照的な笑顔を見せた。 尚志は再度名乗り、改めて礼を言う。尚志の名前を二、三度呟くと、季迪老人は子孟が座っていた椅子に腰を下ろした。 その時だ。 「あの汚い行き倒れ、生き返ったの!」 甲高い声と共に、ふいに小さな女の子が部屋に飛び込んできた。女の子を追うかのように、季迪と同じ年代のお婆さんが入ってくる。 「こら宣明(シャンミン)。お客さんに何ですか!」 そう言って女の子を捕まえると、尚志に軽く頭を下げて出ていった。 汚い行き倒れ、か。尚志は苦笑した。 子孟がクスクスと笑いながら、「祖母と妹だよ」と言う。子孟は部屋の隅から椅子をもう一つ持ってきて、それに座った。 「えっと、西河はどこに?」 「あ、女の子の名前、西河ちゃんていうんだ。二つ隣の部屋にいるよ。叔母が看てる」 「小愉は?」 「僕の母さんが看てる」 「そう、それだ」 いきなり季迪老が、しわがれた声を出した。 「どうしてお前さんが小愉を連れていたんだね」 「小愉を知ってるんですか!?」 いきなり愉家の知り合いに出会えるなんて・・・・・ 季迪は歯の欠けた口を開けて笑った。 「知らないわけがない。小愉は孫同然、儂は小愉の名付け親になるはずなんじゃぞ」 尚志は言葉がなかった。それを見て目を細めながら、季迪老はきりだした。 「それで? なぜお前さんが小愉を連れていた。雲卿たちはどうしたのだ」 そこで尚志は語った。雲卿と出会ってから今までの事を。 思い出す事は、体の痛みより何倍も辛く苦しかった。
「気にくわねえ」 資先が外を睨み付けた。 時間は昼飯時に近い午前十一時四十四分。 事務所の中は普段と同じ、前と変わらぬ忙しさだ。ひっきりなしに電話が鳴り、運び屋達が入れ替わり立ち替わり、書類や小荷物を持って外に飛び出していく。総経理は昨日のアクシデントを忘れようというのか、年甲斐もなくハッスルして事務員の涙と微苦笑を誘った。 いつもと違うのは二点だけ。つまり尚志と恵泉の不在だ。 尚志は年中外を走ってるから、それほど違和感はない。しかし恵泉がいない事務所は、皆にちょっとした喪失感を感じさせた。その恵泉は、今ごろ自分のアパートで熟睡しているだろう。 もっとも、資先が気にくわない理由はそんな事と関係ない。 葛の行動だ。 昨日一日やりたい放題やって、未練も見せず消え失せた、その態度が心に引っ掛かっている。 「気にくわねえ」 資先は心を決めた。 「総経理!」 呼びながらその机に歩み寄る。 「俺、ちょっと外出します」 総経理がいぶかしげに顔を上げる。資先は唇を歪めた。 「すぐ戻りますから。ほんの二、三日で」
尚志が話している間、季迪老と子孟は口を挟まず黙っていた。唯一の例外は雲卿が地滑りに呑まれた下りである。季迪はうめき声を上げ、長いあいだ黙とうし、子孟もそれに倣った。 西河と小愉を担いだまま山を下り、土手に辿り着いて意識が途絶えたところで締めくくる。 話が終わっても二人は黙っていた。 しばらくして子孟が喘ぐように漏らした。 「信じられない・・・」 「俺もそう思う」 「本当なの? 子供二人を負って山小屋からここまで歩き通したなんて」 「これ、失礼を言うでない」 「でも爺ちゃん。爺ちゃんだってあの道が何里あるか知ってるでしょう?」 尚志は首を振った。 「別にいい」 「え」 「別に信じなくていい。ただ、やらなきゃどっちかが死んでた。俺は」 尚志は生々しい掠り傷のついた掌を見た。転んだ時、小愉を守るために岩場でつけた傷だ。 「俺は・・・どっちも死なせたくなかった・・・」 子孟は口をつぐんだ。 「・・・・・・・・・・」 季迪も言葉がなかった。
武夷山脈の麓に生まれて七十余年。山なら裏庭も同然だ。雨が降るとどうなるかも、嫌になるほど知っている。山に消えた身内と知り合いの数は、両手両足を使ってもまだ足りない。 それをこの若者は・・・・・・ 「林先生(ラム・シンサン)・・・」 季迪老が絞り出すように言う。尚志がきょとんとしたのを見て、季迪は「林先生(リン・シェンション)」と言い直した。茫然自失のあまり福建語を使ってしまったらしい。 「あの、先生って一体」 『先生』は目上に用いる敬称だ。 「林先生。ありがとうございました」 季迪老は曲がった腰をさらに折った。 「え、えええっ? そんな、こっちが助けられたのに」 慌てる尚志に、季迪老はゆっくり首を振った。 「いや、助けられたのはこちらなんじゃ」 「そうですよ。先生」 子孟まで言葉が丁寧になっている。 「先生は一族の未来を救われたのです!」 尚志はぽかんと口を開けた。 (一族の未来、だって?) 話が妙に大きい。 「あの・・・」 尚志は感動している二人を問い質さずにはいられなかった。 「一族って、どういう意味ですか」 「・・・」 季迪老が黙り込んだ。子孟も顔をそむける。 嫌な予感がした。 季迪老は何かを切り捨てるように勢いよく首を持ち上げた。それでも言いにくそうに、何度か逡巡する。 尚志はじりじりしながら待ち続けた。 「・・・いないんですじゃ」 「・・・は?」 「昨日の雨で・・・」 子孟も辛そうだった。 「愉家の土楼が崩れてしまったんです」 「ハア!?」 尚志は、自分でも変な声を出しているとわかっていた。思わず振り返って康成楼の分厚い土壁を見上げる。とてつもなく頑丈そうだ。 (こんなモンがブッ壊れるのか!) 季迪老がまた首を振った。 「今、家の者を使って生き残りを捜しているのじゃが。土楼の土は重いしのう。あの豪雨で流されてしまった者もいるじゃろうし・・・」 子孟が言い足した。 「先生はご存じかどうか・・・客家は一族全員で生活しているんですよ」 「一族・・・全員」 尚志はぼうっとして天井を見上げた。 「あ、もちろん家を出た者や町に行ってる者もいますから、天涯孤独じゃありません」 子孟が尚志を安心させるように笑う。かなり無理のある笑顔だったが。 「僕の叔母も愉家の出身です」 「じゃあ、一族の未来なんて大袈裟な事をどうして」 季迪と子孟はため息を吐いた。 「男子が、いないんですじゃ」 季迪老が憎々しげに言うと、子孟が急いで付け足した。 「あ、いや一人だけ、いる事はいるんですけど。その人、子供を作れる体じゃないんです」 季迪が「あの馬鹿者が」と吐き捨てる。 尚志はようやく納得できた。 つまり一族の跡継ぎになる、そして跡継ぎを作れる男子が、小愉しかいないという事らしい。 「その生き残りの人に連絡を取ろうと思ってるんですが、昨日の雨で電話が切れちゃって。今、父が蒲城の町に行ってますけど、すぐ捕まるかどうか」 子孟が小さな窓から空を見た。 「蒲城にいるんじゃないの?」 尚志が尋ねると、子孟は即座に否定した。 「町は町でも、泉州にいるんです」 「・・・」 尚志はまたも嫌な予感がした。 「あの・・・俺、なるべく早く出発しなきゃいけないんだけど・・・」 「駄目です」 子孟はにべもなかった。 「自分の体を見て下さい、先生。山道を二人背負って一晩歩き続けたんでしょう。体中が悲鳴をあげてるはずですよ」 (悲鳴? そんな生易しく表現して欲しくないなぁ) 尚志は心の中で修正した。
「安心して下さい。小愉の命の恩人なら、阮家にとっても恩人です。食事も着る物も、何一つ不自由させません」 (ここに居なきゃいけないのが不自由なんだ) 季迪老が首を持ち上げた。 「それに愉家の大恩人を逃がしたりしたら、儂らがあの男に射殺されますわい」 「射殺ぅ!?」 子孟が祖父の言葉に苦笑した。尚志をなだめるように言う。 「解放軍の、兵隊なんです」 「そんな事より、いつまでここに居なきゃいけないのか・・・」 子孟は首を傾げた。 「さあ、それは向こう次第ですね。勤務中だからどこにいるやら。まず父が電話を見つけるのに時間がかかるでしょうし。電話が基地に通じても、はいそうですかと彼に繋げてくれるかどうか」 すがるような顔付きで尚志は訊いた。 「何日くらいかかるんだ・・・」 「早ければ明日、遅れれば一、二週間先、てな所ですね」 子孟がにこりとする。尚志には悪魔の微笑に見えた。 (明日の朝までに・・・広州・・・) 尚志は腕時計を持ち上げた。 七時八分。 「・・・いま何時?」 子孟が自分の時計を見る。 「午後二時ちょうどです」 壊れている。 (安物・・・) 季迪老が首を傾げた。 「時間が何か?」 「え、はい。ちょっと」 あと20時間しかない。 20時間で広州に行けるのか。 (蒲城から広州まで750キロ・・・・・あの西河を連れて・・・・・・) 気が遠くなりそうだった。
(続く) |
 「台風一過」
「台風一過」 「・・・・このたんぼも駄目か」
「・・・・このたんぼも駄目か」 「赤ん坊の泣き声が聞こえる」
「赤ん坊の泣き声が聞こえる」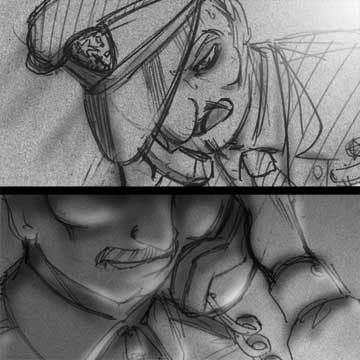 「史閣下は貴軍の活躍を大変に評価しておいでです。しかし...」
「史閣下は貴軍の活躍を大変に評価しておいでです。しかし...」 「僕は阮子孟」
「僕は阮子孟」 「死の山」
「死の山」 「体中が痛い」
「体中が痛い」