|
四章 『・・・始めに上海市の明日の天気をお知らせします。』 「後でいい」 資先が唸った。 『明日は雲一つなく晴れるでしょう』 「空見りゃわかる」 と葛。 『次に北京市の明日の天気です・・・』 「消しましょうよ。時間の無駄です」 これは恵泉。 総経理が立ち上がって、電源を切った。 「・・・・」 総経理が振り返ると、皆が見ている。 「「「なんで消す?」」」 三人同時に文句を言った。 総経理はため息をつくと、再び電源を入れる。その背中が「どうして私がこんな目に」と語っていた。 どうしてこんな事になったのか。 破時快梯が終業時間になると、希望者は帰宅してもよい事になった。賀や崔などは喜んで帰り、事務所には総経理と資先、それに恵泉と葛が残った。総経理は真っ先に帰りたがったが、責任者が帰れるわけがない。葛の部下は他の者と交代し、現在は三人だけ外の車に控えている。 時間は午後六時二十分。 テレビでは地方ごとの天気予報に変わっていた。 『・・・れるでしょう。次は江西省の天気です』 全員が耳をそばだてる。 『江西省東部では局地的な豪雨となっておりますが、明日の朝には晴れるでしょう。中央部では曇りのち晴れ。西部では晴れるでしょう。次は福建省の・・・』 今度は葛がテレビを消しに立ち上がる。 「消すな」 資先が語気鋭く言う。 葛は資先を見下ろすと、小声で何か呟いて椅子に戻った。 『・・・雨は一晩続くでしょう。明日の朝からは曇り空になるでしょう』 最後に資先が立ち上がり、乱暴に電源を切った。 「隊長さんよ、尚志は見つからないだろ」 「見つからん。玉山から南昌まで調べさせて、今は浙カン線沿いにもっと先までやっているんだが」 浙カン線の機関車運転士や駅員は、今ごろ怒髪天を衝いて列車運行を修正しているに違いない。解放軍の命令は絶対だし、調べるとなったらとことん徹底するからだ。 資先は鼻を鳴らした。 「徒労だな。尚志は浙カン線に乗ってない」 「何!」 「文句を言うなと言っといたはずだ。ま、俺も尚志が浙カン線に乗ると思ってたからな。デカい顔はできんが」
資先がどかっと椅子に座る。偉そうに足を組んだが、ズボンが短すぎて剛毛の密生するスネが出た。 「この時間になって見つからないなら、尚志は浙カン線のどこにも居るまいよ。」 恵泉が、首を傾げた。 「資先さんは、尚志が福建に入ったと思ってるんですか?」 ありえない事と聞かされたが。 「他に可能性はない」 「事故に巻き込まれたというのは?」 総経理が言うと、三人に一斉に睨み付けられた(特に恵泉の目付きは強烈だった)。 総経理は語尾を濁し、丸い体を縮めた。 「まったく信じられんなぁ。あの尚志が福建路を選ぶとは」 資先は頭を振った。恵泉がすかさず問いただす。 「あの尚志とはどういう意味ですか」 葛隊長はムキになる恵泉に苦笑し、何かに納得したように頷いた。 「資先、その尚志という日本人はどういう男だ? 危険な人物ではなかろうな」 「どんな意味の危険を言ってるか知らんが、しごく人畜無害な若僧だな」 「なぜ日本人が配達屋をしているんだ」 「隊長さんは、何で兵隊をしてるんだ?」 「・・・・・・・・・・お前の知った事ではない」 「そうだ」 「何?」 「知った事じゃねーんだよ。ここは上海だぜ。他人の事情なんて誰が気にするか」 言外に、「お前の田舎と一緒にすんな」と皮肉っている。 解放軍の隊長が唸った。 「し、資先さん! 福建に行った尚志は今、どこにいると思いますか?」 恵泉が殊更に明るく問いかけた。尚志を配達先から「拾って」来たのは資先だ。その資先が尚志を庇っているのだから、恵泉も協力するのが当然だった。 資先は口を開きかけ、少し口ごもった。 「福建か・・・んむ、こりゃ難しくなったぞ。恵泉、地図」 「はい」 恵泉が書棚に向かう。 「・・・・・・・・今度は外れまいなぁ?」 むっつり顔の葛が多分に嫌味を込めて言った。 「俺に言えるのは、一つだけだ。配達屋が生きてる限り、届かない荷物はない・・・・・遅れる事はあってもな」 「答えになっていないぞ」 「答えじゃない。忠告だ」 資先は腰を上げ、便所に入っていった。
夕闇と共に、泉州の三十一野戦軍にも出動要請が舞い込み始めた。 「司令員の嫌な予感って、どうして当たるんですか」 梁司令の副官、俊卿がぼやいた。 二人は士官用の食堂で晩飯を食べている。司令員なら自室で食べればと思うが、食堂で若い士官と話すのが好きだという。それで士官とのコミュニケーションが取れているから、好きというより司令員流の人心掌握術なのかもしれない。 せっかく食べ始めた二人だったが、食事中の所に続々と各地から出動要請が入ってくる。食卓の脇に伝令がずらりと並んでは、落ち着いて食べられるものではない。 「安渓(アンシー)の堤防警戒を・・・」 「福安(フーアン)で救出活動を・・・」 「将楽(チャンロー)の住民避難を・・・」 「・・・飯を食べさせてもらいたいですね」 八件目の要請で俊卿が舌打ちすると、梁司令は蒸した章魚(タコ)を摘みあげた。左に座った副官(俊卿は左耳がないので、司令員は右側に座る)に示す。 「人生はタコに似ておる。足の長い、優れたタコほど多くの災厄を吸い付けるものなのだ」
「幸運は吸い付けないんですか」 「吸い付ける前に、まず見つけんとなぁ」 妙にしみじみと語る上司の姿に、俊卿は苦笑した。タコを一切れ口に放り、噛みながら立ち上がる。 「司令員、お先に失礼します」 「もう行くのか」 まだ料理が半分以上残っている。 「出動する部隊の、割り当ての準備がありますので。司令員はごゆっくりどうぞ」 俊卿がそう言って略礼すると、梁も立ち上がった。 「私も行こう。満腹になると頭が働かなくなるからな」 俊卿が梁司令の食器を見ると、ほとんど手を付けていなかった。俊卿は気付かれないようにため息を吐いた。 部下が忙しい時に飯を食えるような性格ではないのだ、うちの司令員は。 二人は給仕に詫びると、早足で食堂から出た。今夜は眠る暇もないだろう。 副官の脳裏に、ふと弟の顔が浮かんだ。自分は基地に、弟は山に、それぞれこもりっきりで、去年の春節(旧正月)以来顔を見ていない。 (山の危うさは身に染みているはずだ。あいつ、ちゃんと家に逃げたろうな)
「死ぬかと思った・・・」 尚志がうめいた。 これから先どんな事があっても、今以上に実感がこもる事はないだろう。 ただし、言ったのは一回や二回じゃないし、尚志だけが言ったのでもない。尚志の記憶が正しければ最初に言ったのは雲卿で、場所は峠から十メートルほど下ったカーブ。峠を下りはじめてすぐだ。 停まらないのである。 雲卿が真っ青になってブレーキを踏みつけても、ズルズルと崖に向かって滑り落ちる。絶壁を目前にして停まった時、尚志は生まれてはじめて神に感謝した。全員冷や汗でびっしょり、平気だったのは小愉だけだ。 「だめだ。車は使えない」 雲卿が言うと全員が賛成した。 西河は歩いて下山する事に不安そうだったが、尚志が「落ちるぞ。この車」と言ったら真っ先に雨具を取り出した。
こうして徒歩で下り始めたのだが、まさに「死ぬかと思う」道行きだった。 有名なイロハ坂ほどではないが、ちょこまかと曲がりくねっている上に岩場が多い。柵なんて上等な物もなかった。危険な所にはペンキでドクロマークが書かれているそうだが、雨でドクロマークそのものが見えない。西河が急斜面ですっ転び、地面に突いた掌をどけたらドクロマークが現れた事もあった。 それに土砂降りの下り坂はきついわ、寒いわ、よく滑るわで、生きた心地もしない。尚志は坂の途中で滑り出し、土の壁にぶつかってやっと止まった。不運を呪ってそこから離れた途端、崖崩れが起きた。五秒遅ければ泥に埋もれていた所だ。尚志は声も出なかった。 そのあと崖の端で西河が躓いた時は、こっちの心臓まで止まりそうになった。慌てて尚志が抱きとめると西河は尚志にしがみつき、きっかり二分間離さなかった。彼女は尚志に張り付いたまま、「一生あんたを恨んでやる」と言い放ち、二度と口を開かなかった。 雲卿と季倫はもっと大変だった。小愉がいたからだ。季倫が雨ガッパの中に縛りつけていたが、たちまちバテて雲卿と交代。細身の雲卿もしばらくするとフラフラになって、見かねた尚志が小愉を奪うと、かえって感謝の目で見てくれた。小愉は寒いのとひもじいのとで泣き出したが、心を鬼にして尚志は無視した。 雲卿の話では、峠から家まで車で二十分。 今日は六時間かかった。
「家に着いた!」 尚志が前方を注視すると、暗がりの中に傾きかけた小屋が見えた。 「はあ・・・」 「やっとか」と言いたかったのだが声にならなかった。下り道の後半、ほとんど一人で小愉を抱いてきたのだ。がっくりうなだれた首に、紅い紐がかかっている。それが小愉の命綱だった。両手を使えない時に、それだけが尚志と小愉をつなぐのだ。この二時間、尚志は命綱だけで小愉を運んでいた。 後ろにいた季倫が尚志と並んだ。 「良かった。潰れてないわ」 季倫が胸をなで下ろす。 「さあ、家に入って何か暖かい物でも飲みましょう」 「賛成ー」 西河が歓声を上げる。二人とも急いで雲卿を追った。 「お・・・お・・・!」 意訳(お前ら、小愉を持っていけ! 自分達の子供じゃねーのか!) 尚志は呻いた。見知らぬ他人が見たら、きっと狂人と思っただろう。 一人でズルズル歩いていると、先に行ったはずの西河が戻ってきた。 なんと走っている! 尚志は急に疲れを覚えた。がくっとその場にへたりこむ。尻が泥水に浸かったが、全身ズブ濡れだから、もうどうでもいい。 (・・・このガキ、どこにそんな力を隠してた・・・) 尚志の胸中を知りもせず、西河は尚志の顔を覗いた。 「何一人で死んでるのよ。早く行きましょ」 「い・・・」 意訳(行けるモンならとっくに行っとるわ) 「ダメねえ。あたしや季倫さんより体力ないの」 「お・・・!」 意訳(お前は小愉を運んでなかったろーが!) 「ほら立ちなさいよ。背中を押してあげるから」 「そ・・・!」 意訳(その前にあすこの無責任夫婦を呼んでこい!) 「立てないの? まったく情けない男だわ。それで保護者だなんて大笑い」 「!!!」 意訳(放送禁止用語につき翻訳不可)
尚志は泣きたくなった。
中国の山は、不毛だ。土が痩せ山は丸坊主、岩盤の露出した荒涼たる地勢がどこまでも続く。 これが、四千年続いた文明の『成果』。 尚志たちが歩いてきた道に、大木など一本たりと生えていなかった。こういうハゲ山には保水力がない。土壌の枯渇がどんどん進む。風で表土が吹き飛ばされ、雨は沃土を洗い流す。地中に染み込んだ水は、表土と粘土層(もしくは岩盤)の間に蓄積され、表土は水の上に浮き上がっている。 そして台風が来る。 遊離した表土層は、嵐によって簡単に剥落してしまう。剥落した土は大量の水をともない、想像を絶する速度で斜面を駆け下りる。激流は凄まじい破壊力で岩石や枯れ木を巻き込み、時には谷一つを丸ごと押し潰す。これを中国人は山洪(シャンフォン)、日本人は山海瀟(やまつなみ)と呼んだ。 すなわち土石流である。
ゴロゴロ・・・ 西河が空を見上げた。 「雷」 「かみなり?」 ゴロゴロゴロ・・・・ 今度は尚志にも聞こえた。西河が顔をしかめる。 「嫌だ。早く愉さん家に入りましょ」 「怖いのか」 「ち、違うわよっ」 「そーかそーか。西河お嬢様は雷がお嫌いですか」 「もうっ。違うの!」 ご。 ごご。 ごごごご。 ごごごごごごごご。 「ずいぶん近いな・・・・・・あれ」 地面が揺れている。 小刻みにぶるぶると― まるで、震え怯えるように。 「雷の次は地震?」
次の瞬間、二人は闇に呑まれた。
「何か」が尚志たちを真横に跳ね飛ばした。 続いて聴力の限界を遥かに凌駕する爆音。同時に、耳目に吹き込む容赦ない塵埃。 泥だらけの地面に叩きつけられた尚志は、鼓膜に殺到する大音響に殺気すら感じた。反射的に叫び声を上げたが、固体と見紛う粉塵が、開いた口に飛び込んで来る。尚志は喉を押さえてのたうち回った。 西河は体重が軽いぶん、尚志より遠くまで飛ばされた。耳と鼻に泥砂が突っ込まれる。少女はすべての穴を塞ごうとしたが、結局どれも塞げない。埃に恐怖するなど初めてだ。『媽媽(ママ)ッ!』声にならない叫びを上げるが、尚志と同じく土煙を吸い込むだけだった。もうもうと立ちこめる煙に咳込みながら、西河は思いつく限りの名前を呼び続けた。 やがて、轟音が通り過ぎた。 地鳴りも鎮まっていく。 ただ天空の栓を抜いたような雨だけが、今までと同じように降り続ける。
「・・・・ベッ!」 尚志は小石を吐き出した。舌の裏がジャリジャリする。 「ひでぇよ・・・」 気が付くと、横向きに転がっていた。恐る恐る身体を仰向けにする。顔に当たる雨水を口に受けて、尚志は口をすすいだ。雨がついでに顔を洗ってくれる。 地面に擦ったのだろうか。右のこめかみが熱く、水が染みた。 「ひでえよ・・・」 五体は一応つながっているようだ。全身が火を噴くように痛かった。 「重い・・・」 胸の辺りが重い。 「・・・・・・って、小愉っ!!」 尚志は無理矢理起きあがった。所々穴の空いた雨ガッパをたくし上げ、胸に抱いていた産着をむく。 「・・・・・・・・おい」 信じられなかった。 「寝てやがる」 小愉はすうすうと寝息を立てていた。念のため耳を近づけたが、安らかな吐息だけが聞こえる。泣き疲れて眠ってしまったのかもしれないが、呑気な事このうえない。尚志は腹立ち紛れに手荒く産着をくるむと、雨ガッパを下ろした。 「どういう神経してやがんだ。このガキ」 泥のこびりついた顔で周囲を見回すと、埃がすっかり消えている。三メートルくらい離れた所だろうか、暗がりの中に白いものが目に入った。 西河の靴下だ。 「西河!」 尚志は急いで立ち上が・・・ろうとした。 立てない。 足は思うように動くから、骨折したわけではないだろう。腰が抜けたらしい。 「情けねー・・・」 尚志は嘆きながら、懐の小愉をかばいつつ西河の足元まで這った。 会社の連中に絶対見せられない格好だ。特に恵泉には。 「西河」 西河はうつ伏せに横たわっていた。泥に顔の左半分が埋まっている。 「西河、おい!」 窒息してしまう。尚志は西河を強引にひっくり返した。かなり手荒だったが、ピクリとも反応しない。 不安を感じて喉元に掌を当てると、弱いが着実な脈拍が感じられた。 「・・・生きてる」 安堵のあまり、全身の力が抜けそうになる。 「西河! こら西河、生きてるか!」 呼びながら尚志は西河の頬を叩いた。 無反応。 「西河!」 「うっさいわね。聞こえてるわよっ!」 「うわあ!」 西河がいきなり尚志を突き飛ばした。二、三度咳をすると、さっきの尚志と同じように、雨で喉をすすぐ。 「ホンットに失礼な男ね、尚志って。あたし・・・」 後はしゃがれて声にならない。尚志には理解できなかったが、口調から、命に別状なさそうなのはわかった。まだ何か言っている西河を放って、尚志は立ち上がった。 少しふらつく。 足元に注意しながら、尚志は闇に目を凝らした。大して移動したわけでもなさそうだ。暗闇でも、雲卿の小屋の場所は見当がついた。 「ああっ、靴がない! 右足のーっ」 雨音の向こうで西河が喚いている。あれくらい元気なら、骨の一本や二本折れてても大丈夫だろう (いったい何が起きたんだ・・・?) 尚志の記憶にあるのは『混乱』の二文字だけだった。気が付いたら地面に転がっていた、としかわからない。 「愉さん、大丈夫か!? 馬さん!」 歩きながら呼んだが、返事をするのは盛大な雨音だけだ。 「愉さん、馬さん! ・・・・・・おっ」 尚志は立ち止まった。足元が変に暗い。 片足で探ってみる。 ・・・・・・何もなかった。 「う」 思わず体が震える。 足元をのぞくと、暗い夜の闇の中、下はさらに暗い。そして雨音も届かない。
尚志は崖っぷちから飛び退った。 地滑りが起きたらしい。さっきまで地面があったはずなのに、何から何までさっぱり消え失せている。 危うく落ちるところだ。気付いて良かった。 「危ない危・・・・・・」 そこで、吐きかけた溜め息を呑み込む。 ・・・・・・・・地滑り? ぞくり。 悪寒が背筋を走り抜ける。 さっきまで、地面があった場所から、何もかもきれいに消え失せた。 消えてしまったのだ。 地面も。 木々も。
愉夫妻の小屋も―
バツ印が書き込まれた。 大判の福建省路線図に、無数のバツ印がついている。 さらにもう一つ、やや乱暴にバツ印を書いて、資先は赤ペンを放り出した。 「こんなもんだ」 「・・・・・・・・・・・・・」 「・・・・・・・・・・・・・」 「・・・・・・・・・・・・・」 資先以外の三人・・・総経理、恵泉、葛は、各々べつの理由で渋面を浮かべている。 「言ったろ。無茶苦茶ヤバいって」 資先は三人の顔を見て、ほとんど投げやりな口ぶりで言った。 「これで全部か?」 「目ぼしい所はな」 「他にもあるのか」 「ぜんぶ書くなら、赤ペンなんか使わん」 赤インクをぶちまけたほうが手っ取り早い、そう言って資先は椅子に体を預けた。 葛隊長は唸った。 福建路を示した資先に、危険の大きい要注意点を教えろと頼んだ。しかしこれでは参考にならない。 「多すぎる」 葛隊長が再び唸る。 「そうだ。そういう土地だからな」 資先の眉間に深い皺が刻まれている。 太い腕を伸ばし、葛は路線図を鷲掴みにした。 「これで失礼する。部下を一人残しておく。二人から連絡が入ったら必ず知らせろ」 そう言いおいて、巨漢の隊長は事務所から出て行った。 「・・・・・・・・・・・・何なんだあいつは」 「何でしょうね・・・・・・・・・・・・・・・・」 「あの、その地図は当社の備品なんですが・・・・」 総経理の小さな声は、閉ざされた扉に跳ね返された。
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」 うんざりだった。 雨、暗黒、山、湿気、空腹、胸元で安眠を貪る赤ん坊と瞼の裏にちらつく死神、その全部に、尚志はうんざいりしていた。しかし彼が嫌悪するモノと比べれば、それら全部をあわせたって大したものではなかった。 この、目の前の少女に較べれば。 「疫病神!!」 猫のような目がいっそう吊り上がっている。髪の毛に土が絡んでいるせいで、叫ぶ西河自身が鬼(ゆうれい)のようだった。 彼女は歩けなかった。突風で飛ばされた時に打ちつけたようだ。 怒りだしたのは、尚志が「助けを呼ばないと」と言ったからだ。 見捨てられると思ったらしい。 「あんたが全部悪いのよ! 列車は着かない、ご飯は不味いっ。雇い主に車を押させて、服は汚れるしズブ濡れになるし! 半殺しの目に遭わせてクタクタにさせといて、よくも保護者なんて名乗れたわねっあんたのせいで二人が死んじゃったのよっ。愉さんと馬さんが! こんな場所で一人っきりなんてあんまりよぉっ。もうすぐあたしは死ぬわ! 絶対死ぬ! 死んだらあんたに取り憑いてあんたも殺してやるっ。九泉(あの世)に行ったら一生いじめ抜いてやるから!。覚えときなさい、この人殺し!!」 「・・・あの世に『一生』はないぞ」 「うるさいっ、このワンバー!!」 少女が地面に寝ころんでワアワア泣き出す。腕をバタつかせ、手当たり次第に泥を投げつけてくる。すでに全身泥まみれだから何でもないが、もう手の付けようがない。 「アーーーーーーーーーーーーーーン!!」 「・・・助けてくれ・・・」 尚志は天を仰いだ。この状況を何とかしてくれるなら、悪魔でも鬼でも何でもいい。命でも魂でもプレゼントしてやる。尚志は本心からそう思った。 もちろん、助けはこない。尚志のもとに降り来るのは仏でも天使でもなく、げっそりするほどしつこい雨だけだ。 (・・・西河、お前だってじゅうぶん疫病神だぞ・・・) 「ワァーーーーーーーーーーーーーン!!」 「はあーーーーーーーーーーーーっ・・・」 尚志は駄々ッ子の前にしゃがんだ。 「あのな・・・勘違いするな」 「え?」 「俺は西河を見捨てたりしない。置き去りにもしない」 かんで含めるように話し掛けると、泥だらけの少女がきょとんとする。
「俺は配達屋だ。配達屋が生きている限り、届かない荷物はない。荷物を・・・・西河を捨てるわけないだろ」 西河の顔が少しだけ明るくなる。しかし靴のなくなった足に目が行くと、表情に翳りが増した。 「でも、でも、あたし・・・・歩けない・・・・」 「荷物は普通、自分から動かない」 尚志は西河の頭に手を乗せた。 「運ばれていくもんだ」
泉州の解放軍基地。
「松渓(スォンシー)の堤防、H点から出水しました!」 作戦室に持ち込まれた十台の無線の、七番担当士官が叫んだ。兵員配置図を前にした梁司令が直ちに指令する。 「堤防は放棄しろっ。下流の省軍と合流して人民の避難を最優先!」 三番無線機の士官がヘッドホンを外す。 「二師の徐(シュ)連隊長からですっ。古田(クティェン)、浸水多数、船舶の派遣を請う!」 「できればとっくに送っている。筏でも作って対応しろ、そう言え!」 梁司令はボールペンの尻を眉間に当て、「想像力のない奴め」と批評した。 次は五番と九番の担当士官だ。同時に報告してくる。 「三明(サンミン)の欧(オゥ)中隊長から! 沙縣(シャーシェン)で住民孤立、省軍に連絡をっ」 「金渓ダムの倪(ニ)連隊長から! 警戒水位を突破、十分後に放水開始との事です!」 「副司令、五番を見てくれ。九番! こっちに回線を回せっ」 俊卿がメモに各地の状態を走り書きしていると、隣で梁が一喝した。 「このバカタレ!! 三十分前に連絡してこんかっ」 司令員が叩きつけるように受話器を戻した。 とんでもない事になってきたな、と俊卿は思った。時が経てば経つほど、救援要請も増えていく。省軍は全兵員を投入して余力を喪失。三十一野戦軍の基地も、最低限の防衛戦力を除いてカラッポだった。 「今攻撃されたら危ないですね」 「かといって、目の前で溺れかけてる同胞を無視もできんだろう。南京の総司令部が後で何と言ってくるやら、考えたくもないわ」
梁は蒸しタオルで顔をぬぐった。渋面を部下に見せないための習慣だ。 「順昌(シュンチャン)の陸(ルー)はどうした? 南平(ナンピン)に奴の部下を割かせたはずだが」 俊卿はわずかに微笑んだ。 「泣いておられました」 「よし」 俊卿はコップに水を注いだ。 「いつまで続くとお考えですか?」 「さて・・・」 言いかけた所に、二番の士官が立ち上がる。 「第7大隊が抑えきれないとの事です! C点からH点まで決壊っ、K点も・・・うわっ!」 梁がボールペンを投げつけたのだ。 第7大隊が潰れては福建の省都が危ない。 「省軍に緊急連絡!。大隊長に『そこで死ね』と言えっ。それと、お前が死んだら福建も終わりだとな!!」 外の雨を消し飛ばす勢いで梁が怒鳴った。
1992年7月。 三日から降り出した雨は一昼夜続き、江山に次いで福建においても降水量百ミリ超を記録した。これは多雨の福建においてすら、雨期半月分の降水量に匹敵する。
後の調べによれば、埼玉県丸ごと一つ分の田畑が壊滅し、死者行方不明者は四百七十人にのぼった。死者の中には愉姓の者二十七人が含まれる。うち一名は福建省の林業局主任。 まだ若く、非常に有能な植林研究者だったという。
(続く)
|
 「徒労だな。尚志は浙カン線に乗ってない」
「徒労だな。尚志は浙カン線に乗ってない」 「人生はタコに似ておる」
「人生はタコに似ておる」 「落ちるぞ。この車」
「落ちるぞ。この車」 「!!!」
「!!!」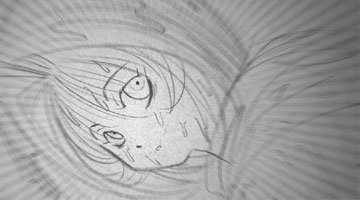 「!」
「!」 「・・・・・・何もなかった」
「・・・・・・何もなかった」 「俺は西河を見捨てたりしない」
「俺は西河を見捨てたりしない」 「作戦室」
「作戦室」 「とんでもないことに」
「とんでもないことに」 「降水量百ミリ超を記録した台風」
「降水量百ミリ超を記録した台風」