|
第三章 何処までも野原が続く武夷の山嶺を、細い茶色の線が貫いていた。かなり急な未舗装の山道を、黒煙を吐きながらワゴン車が登っている。 ポンコツ。 その一言で全て説明できよう。 太古の昔、純白だったであろう車体は、砂漠の戦車の如き塗装を施されていた。埃と泥による『天然カモフラージュ』だ。 やがてワゴンは、きつい坂の途中で歩みを止めてしまった 「まただよ。このオンボロ」 運転手の若者が後部座席に振り返った。 「OKOK、待ってな」 クネクネしたアラビア文字の書かれたドアが開き、後部座席からスーツ姿の青年が飛び降りる。 尚志だ。 後ろに西河が続く。 二人とも下半身が泥まみれだった。 「えいやっ!」 掛け声を揃えて後ろから車を押すと、ワゴンは真っ黒な煙を吐きながら坂を登りだした。足に泥が張り付く。ワゴンの中から、跳ねるような赤ん坊の笑い声が聞こえた。
「踏ん張る尚志の顔が面白いって・・・っ!」 西河が歯を食いしばりながら、憎まれ口を叩く。 「そーゆーそっちこそ、大した見せ物だぜっ」 飛んできた泥で、尚志も西河も顔まで汚れていた。 十メートルほどのろのろ進むと、坂が緩やかになった。運転手が左腕を突き出し、乗ってくれと叫ぶ。ぐったりした西河と元気な尚志が車に入り、ワゴンは再び走りだした。 「本当にありがとう」 助手席に座る、細面の美人が振り返った。 「なんだかこっちが助けられてるみたい」 今時珍しく人民服をきちんと身につけている。その女性は胸に子供を抱きながら、穏やかな笑みをうかべていた。 尚志は手を振った。 「大したことじゃない。俺達のほうが助けられたんだ」 食堂で二人の話を聞いていた運転手が、乗らないかと声をかけてくれたのだ。尚志は運賃を払うと言ったのだが、頑として受け取らなかった。 若者は愉雲卿(ユィ・ユィンチン)という。妻と息子を紹介したあと、このワゴンに乗せてくれた。助手席に座っている馬季倫(マー・チーリン)と赤子がその妻子だ。「お子さんの名前は?」と聞いたら、小愉(シャオユィ)と呼んでいるという。いずれ、しかるべき人物から正名をつけてもらうのだろう。 道すがら聞いた話では、知り合いを江山に送りに来て台風に捕まり、二日も宿屋に閉じこめられていたという。雲卿は植林労働者とかで、林に豪雨が与えた被害をしきりに気にしていた。
「愉さんのおかげで、車を探す時間を節約できたよ」 運転席の雲卿が人の良い笑顔を浮かべた。鼻の形が団子に似ている。 「気を使わないでくれ。こっちも家に帰るついでさ」 「ついでって、家は山の中でしょ。山向こうの麓まで連れてってくれるなんて、あたしは有り難いけど迷惑じゃない?」 顔についた泥をこすりながら西河が尋ねる。尚志にとってありがたい事に、西河は車を押すことにあまり文句を言わなかった(あくまで『あまり』だが)。 尚志は肘で西河を小突いた。 「その言葉使いをなんとかしろ。年上に失礼だろが」 「ちゃんと気は使ってるんだからいいじゃない。ねー、愉さん!」 「おう! 俺っちは気を使われて嬉しいぜ」 尚志が眉間に皺を寄せ、それ以外の全員が笑った。小愉も吊られてキャッキャと笑う。桃色の産着にくるまれた赤ん坊は、実によく笑い声をたてた。 山道の周囲に岩石が増えてくる同時に、天気が翳りだした。ガスで視界がどんどん悪くなる。 雲卿は口にピーナッツを放りながら、器用にハンドルを回した。 「家は山ン中って言っても、住むのは夏の間だけだよ。冬は親元に住んでるのさ。台風が通った後だから、親に顔見せせにゃならん」 夫の言葉を季倫が引き継いだ。 「だからホントについでなの。運賃がどうとか、もう言わない事」 夫婦二人から言われると、尚志には何も言えなかった。かわりに頭を下げる。 ぺしん。 下げた尚志の頭を小愉が叩いたのである。 再びワゴンに笑いがはじけた。 笑いすぎて目に涙を浮かべながら、季倫が後部座席の二人を交互に見た。 「さっきから聞こうと思ってたんだけど、あなた達どういう関係なの? 夫婦にしては若いし、林さんが西河ちゃんをさん付けで呼んでるし。でもカップルみたいに気が合ってるし」 雲卿も頷いた。 「俺も知りてーな」 「気が合ってる?」 尚志は心底驚いた。 「俺とコイ―痛っ! ・・・西河さんが?」 西河も同意見だったらしい。 「あたしと尚志のドコがカップルに見えるってゆーの!?」 「お似合いの二人に見えるけど。違うの?」 季倫の言葉に尚志と西河は身を乗り出し、二人同時に宣言した。 尚志いわく、「ワガママ娘とその保護者」 西河いわく、「雇い主とそのお供」 次の瞬間そろって怒りだす。 「なんで俺様がお供なんだよ!」 「そっちこそ! ワガママ娘なんてどういう事!?」 「ワガママだからワガママなんだよっ。飛行機は駄目だの硬座は嫌だの言ったのは誰だ?」 「経費は全部こっち持ちなんだから、それくらい当然でしょ! 保護者を名乗るんだったら相応しい仕事をしたらどうなのよっ。あんたなんかお供で充分よ、お供で」 「なーにが雇い主だ。自分の金じゃないくせに、偉そうな口叩くな!」 「そんなのアンタに関係ないじゃない!」 「人として納得できないんだよ!」 「・・・・・・・・・・・」 勢いに呑まれた夫婦はしばらく二人を見ていたが、どちらともなくクスクス笑い始め、最後には車を停めて笑い出した。 「・・・やっぱりお似合いよ、あなた達」 二人が叫ぶ。 「絶対に違ーう!!」 コンマ一秒のずれもない合唱だった。
台風が去った上海― 破時快梯の事務所は、建物の中も台風一過だった。兵士がひっくり返した机や書棚を、職員が手分けして片付けている。一分に一回ため息が聞こえ、総経理は泣きながら書類を集めていた。恵泉はそれを見て、「総経理は一生、解放軍を許さないだろうな」と思った。 葛は事務所の真ん中にでかい図体を曝し、職員に邪魔者扱いされながら携帯電話に怒鳴っている。 「五峰、聞こえんぞ! もっと大きな声で言え!」 雑音が激しいようだ。 『はい・。令媛・・尚・・・江・に・ない事が確認さ・ましたっ。子連れ・婦と・緒にワ・ン車に乗・て、どこ・・・えてしまったそ・です!』 「全然わからん! おい、どういう状況なんだ。声が遠くなる一方だぞ」 『です・ら先程申し・・たとお・・異・・豪雨・襲・れ・いる・・す! 電・も切・・しまっ・・我々・・・』
「おい五峰、どうした! もしもしっ。もしもし!!」 ツーッ。 ツーッ。 「・・・・・・・・・・」 葛は携帯電話を握りしめて窓の外を見た。 「雨・・・?」 ビルの谷間に太陽が顔を出し、道路から水蒸気がたち昇っている。路面がキラキラ反射してまぶしかった。 「豪雨、だと?」
台風は、たしかに去っていった。 しかしそれで終わりではなかった。 1992年のこの台風は、双子台風だったのだ。しかも、第二弾は一つ目に倍する勢力を誇っていた。 華南地方の住民の多くは、その事実を知らされなかった。最初の台風によって地域の電波塔が倒され、交通路も遮断されてしまったからだ。人々は束の間の陽光を見て、台風通過を確信した。そして身内や田畑の安否を確認しようと駆け出した。 かくして悲劇は準備された。
江山を含む山嶺地域を強烈な暴風雨が襲ったのは、爽やかな日の出から、わずか数時間後の事だった。 豪雨は電線を切り電話ケーブルを引きちぎり、脆くなった橋梁をたやすく川に蹴落とした。水田は泥に埋まり樹木が倒される。低地の民家は濁流に侵され、住民は屋根の上に追い立てられた。高台に位置する江山公安局は、避難してくる住民と助けを求める声で混乱を極めた。泣き叫ぶ子供や狼狽する大人を前に、職員は唸った。 「台風は行っちまったんじゃないのか!!」 彼の言葉は全住民共通の思いだ。 三日間で十五億元もの損害を生み出した、九十二大水災(チウシーアル・ターショイツァイ)・・・ それはまだ、始まったばかりだった。
服の汚れなど気にする余裕はなかった。 尚志も西河も雲卿も、全身ズブ濡れ泥人形と化している。西河は車を降りるたびに、尚志を殴る回数を心の中で数えていたが、三十回を超えたあたりでどうでもよくなった。それどころではなくなったのだ。 豪雨なんて生やさしいものじゃない。 バケツをひっくり返したみたいに水が脳天に叩きつけられる。空全体が滝になったようなものだ。地響きと聞き間違うような雨音だった。山道は水が流れ込んで川同然。ワゴンはエンジンをフル回転させながら後ずさりし、隣にいる者の声も聞きとれない。水煙が頭までたちのぼって、もちろん視界はゼロ状態。
今、車は西河を挟んで尚志と雲卿が押していて、季倫がハンドルを握っている。尚志は、西河が息切れを起こしているのを見て叫んだ。 「西河! お前、車に入れ!」 いつの間にか呼び捨てにしている。西河も当人も全然気付いていなかったが(というより聞こえないのだろう)。雲卿が背中を押すと、西河は素直にワゴンに乗り込む。 「愉さんっ。もう峠に着くんでしょう!」 「ここが峠だよっ! この坂を越したら下り道! もうすぐもうすぐ!」 もうすぐと言うが、先が見えない、距離がわからない。ワゴンのエンジンが、瀕死の羊みたいに啼いている。 「愉さんさあっ。あんた運はいいほうか!?」 肩で車を押しながら尚志が叫ぶ。雲卿は息も絶え絶えに答えた。 「当たり前だ! でなきゃ季倫が嫁に来るわけねーだろっ。」 こんな所でノロけるなと言い返したが、雲卿には聞こえなかったようだ。 尚志は乾いた喉に雨を流し込んだ。そして窒息しそうになってむせ返った。 (するってーと、悪運のモトはやっぱり俺と西河かよ) 旅の経過を見るかぎり、西河もあまり幸運とは言えない。その西河は車の中で、ナップザックからタオルを取り出して髪を拭っている。 (どーせすぐ濡れるのに) 尚志はワゴンを押す腕に力を込めた。 「愉さんさあっ。この坂どこまで続くんだ!」 「もうすぐもうすぐ!」 「本当だろーなっ!?」 「もうすぐもうすぐ!」 雲卿の『もうすぐ』は、それから二時間続いた。
「まいった・・・」 「ああ・・・」 倒れ込むように後部座席に腰を下ろすと、尚志と雲卿はしばらく口もきけなかった。ひきつったあえぎ声だけが車内に響く。運転席の季倫は心配そうに夫の顔をのぞき込んだ。 雲卿によれば峠に着いたらしいが、尚志と西河にはよくわからない。周囲360度が水のカーテンに覆われているのだ。雲卿に頼るしかなかった。 朝は整っていた雲卿の髪は、頭頂から柳のように垂れていた。尚志は思わず自分の髪を確かめた。 (この雨でハゲたりしなかったろーな) 「どうしたの、尚志。カツラが心配?」 「誰がカツラだ」 「大丈夫。ちゃんと乗ってるよ」 「違うっつの」 西河はいつの間にかシャツとズボンを着替えていた。今は助手席で小愉を抱いている。 「あなた、服を脱いで。風邪ひくから」 季倫が夫にタオルを渡す。 「雲卿」 「・・・ん、ん」 かろうじて雲卿は唸り、のろのろと人民服を脱ぎだした。尚志は馬のように息をしながら、自分のジャケットで髪をごしごしと擦った。どうせ安物だし、タオルもないから仕方ない。 「林さんは着替えないの?」 尚志が首を振ると、季倫は雲卿の荷物の中から、埃っぽいシャツとズボンを取り出した。カーキ色の上下揃いで、所々に繕いが施してある。作業服らしい。 「家で洗おうと思ってたから、汚いけど。そんな服よりいいでしょう」 尚志は好意に礼を言い、雲卿と並んで着替え始めた。ふと顔を上げると、バックミラーの中の西河と目があう。 「見るなよ」 「見たくもないわよっ!」 小愉がまた笑った。
「悪くない」 解放軍の隊長、葛はプラスチックのタッパーから飯をかきこんだ。 白米の上に、甘辛く味付けした豚肉の角切りが乗っている。酢豚に似ているが、肉は蒸してある。 「そーだろ。けっこう人気あるんだぜ、この盒飯屋(べんとうや)」 資先が満足そうに胸を反らした。 日本と同じように、中国にも弁当がある。盒飯(ホーファン)と言って、駅でよく売られている。値段はそこそこだが、味と中身は作る者によって千差万別。上海では近郊、無錫(ウーシー)の盒飯が有名だ。 「おい恵泉。食べないのか」 恵泉は首を振った。せっかくの弁当にほとんど手をつけず、ため息混じりに俯いている。 午前中いっぱいと午後二時間。それだけかかってようやく事務所の片づけが一段落した ほっとした職員だが、悶着がすぐ発生した兵士が昼飯を買いに行かせてくれないのだ。結局、スーツ姿の事務員と解放軍兵士という、世にも珍妙な二人連れで弁当を買ってくることになった。 葛は図々しくも破時快梯の職員に混じって、いるのが当然という態度で箸を動かしている 「資先さん、気が付かなかったんですか? 朝からずっとこうですよ」 女子事務員の賀が言った。 「朝から? なんで」 賀は資先の鈍さに呆れた。 ずっと一緒に仕事してるのに、これじゃあ鈍すぎる。 (道理で、お嫁さんも逃げるわけね) 「なんでって、資先さんは尚志が心配じゃないんですか。孤立無援の江山で、行方不明なんですよ!」 賀の攻撃も暖簾に腕押し。資先は無感動な顔でお気に入りの緑茶(リュィチァ)をすすった。 「心配なんてするか」 「!」 恵泉は弁当を机に置き、早足で給湯室に行ってしまった。 「冷たい人ですね・・・・資先さんって。だいたい無神経ですよ。恵泉の目の前であんな言い方しなくても」 賀は資先を睨みつけた。 「なんで恵泉の前で言うと冷たいんだ」 これには一同、頭を抱えた。だがその後に資先が続けた言葉は、予想外のものだった。 「勘違いすんな。俺は心配する必要なしと言ってるんだ」 「はい?」 「少しは自分の同僚を信じたらどうだ」 皆がぽかんと口を開けた。 ただ一人、葛だけが興味深そうに資先を観察している。 「あいつだってガキじゃねぇんだから、放っといても仕事するだろ」 今まで沈黙していた総経理が口を開いた。 「しかし資先、日ごろから尚志は駄目駄目だと言ってるのはお前だろう」 「俺様と比べりゃね。でも配達屋失格だと言ったのは、一度きりのはずですがね?」 「・・・・・なるほど」 葛がごみ箱に弁当箱を投げ込んだ。 「お宅は、尚志という男がどうにかできると思っているんだな」 資先は豚肉を噛み、唇の端を歪めた。 「俺の名前は戚資先だ。『お宅』じゃねぇ」 葛は呆気にとられたが、やがて資先そっくりに唇を歪めた。 「それで資先、尚志はどうすると思うんだ?」 「三通りあるね」 もぐもぐと飯を噛みながら話す。 「ところでこの弁当代、誰が払うんだ」 同僚はまた頭を抱えた。事もあろうに、資先は解放軍に昼飯代を払わせようとしているのだ。総経理が心配そうに葛の顔色をうかがう。 しかし葛は不愉快そうではなかった。それどころか、いかつい顔に楽しむような表情すらほの見える。
「いいだろう。お近づきのしるしとして俺がおごってやるよ。それで三通りとは?」 資先が満足そうにお茶を飲む。喉がごくりと鳴った。 「進むか、逃げるか、留まるか。それしかないだろう。進んだならしばらく捕まらんな。逃げたならここに連絡して来るはずだ。江山に留まったなら、とっくに見つかってるだろう」 葛は前屈みになって両手を組んだ。体重が前にかかり、椅子の前脚がミシリと鳴る。総経理は椅子が潰れないように祈った。臨時出費がこれ以上増えてはたまらない。 「つまり令媛と尚志は広州に向かうのを諦めていない。ならばどうしていると思う」 資先は手をヒラヒラさせた。 「小日本(シャオリーベン)の考え方など俺にはわからんよ」 「小日本?」 意表を突かれた葛は一瞬言葉に詰まり、ふいに大声を放った。 「林尚志(リン・シャンチ)というのは日本人だったのか!? 何故それを言わなかった!」 「訊いたか?」 訊いていない。 ぐっと葛が言葉に詰まる。 「馬鹿な奴なら駅でのんびり待ってるだろうよ。でもな、尚志は子連れの夫婦とどこかに行っちまった」 口をへの字に結んで、葛が肯定した。 「普通なら線路に沿って車を走らせて、次の駅から列車に乗るだろ。なあ夢阮(モンユァン)?」 崔夢阮が同意する。 「要は川と橋だ。信江さえ渡っちまえば、次の駅から鉄路が動いている。十中八九、尚志は浙カン線沿いのどこかにいるだろ。遅けりゃ上饒(シャンラオ)、さっさと動いてれば今頃は貴渓(コイシー)に着いてるはずだ」 上饒は江山の西90キロ、貴渓はさらに西にある。 「もっとも手際の悪い尚志のことだ。玉山(ユィシャン)でうろうろしてても、俺は驚かんね」 葛が感嘆の声をあげた。 「よく読めるな」 「言っとくが、俺ならそうするだろうってだけだ。見つからなくても文句を言うな」 「わかったわかった。・・・・フン、南昌と玉山から挟み込むように調べていけば、どこかで令媛が見つかるわけだ。これなら我が軍だけで何とかなる」 南昌付近の解放軍は、上海と同じ南京司令部の指揮下にある。ちなみに福建省の部隊もそうだ。 「そんな所だな。ただ・・・」 資先は今一つ断言できないようだ。葛はその迷いを見逃さなかった。 「ただ、なんだ?」 「南昌を通るコースだと、契約期限までに辿り着けないだろう。浙カン線は台風でズタズタだからな。安全に行ける事は間違いないが」 「契約期限・・・七月五日か」 「そうだ」 資先は額に皺を寄せて腕を組んだ。 「俺が期限までに行こうとするなら・・・・・フン」 「どうする」 葛の目が光る。 「福建に抜けて海に出るな。無茶苦茶ヤバいが」 「福建か!」 崔が手を打ち合わせた。 「そいつはいい手だ。どこがヤバいんだ?」 「江山から福建に入るには、まず山越えの車を見つけなきゃならん。あの辺の山道は狭くてな、整備もされてないし、ただ走るだけで一苦労も二苦労もさせられる。おまけに岩が多いくせに地盤が脆い。危ないったらありゃしない」 さすがに『活地図』と呼ばれる事はある。
「・・・まあ、今のは万が一の話だ。福建の道を使おうとするのは命知らずの阿呆か、俺みたいに危ない場所を知り尽くした奴だけだろーよ」 資先は緑茶の最後の一滴まで飲み干し、結論を下した。 「尚志は子供連れだ。そんな馬鹿なマネはせんだろう」
福建省南東部、泉州(チュァンチョウ)。 泉州は古くから、商港として栄えてきた。今は台湾に最も近い街として、五万の兵を擁する三十一野戦軍(サンシーイー・イェチェンチュィン)が常駐している。この野戦軍、本来は『集団軍』と呼ぶのだが、兵士は精悍さに満ちた野戦軍の呼び名を好んだ。
野戦軍はそれ自体で完結した戦力である。格下の福建省軍と違い、独立した軍団として歩兵、戦車、砲兵はもちろん、ヘリコプターや病院まで備えている。あらゆる局面に対応しうる実戦部隊なのだ。 その司令部。 打ち放しのコンクリートで立てられた司令部は、二階建ての小さな建物だった。壁や天井は分厚いが、役割を知らない者には日本の小学校のほうが立派に見えよう。未塗装のまま熱帯植物に囲まれている様は、安っぽいレジャー施設を思わせた。 中国では司令官の事を『司令員(スーリンヤン)』と呼ぶ。なんとなく、司令部で働く士官みたいに聞こえる。あまり威厳を感じさせないが、そうなってるんだから仕方ない。三十一野戦軍の『司令員室』は二階の中央部に位置していた。 「酷いのですか?」 受話器を戻した司令員に、副官が問いかけた。 副官はとてつもない美男子だったが、左耳を削ぎ落とされたように欠いている。切れ長の目やきりっとした眉が、耳の異様さで台無しだ。 一方の司令員は、町のどこにでもいそうな小男だった。胸の勲章で司令員とわかるものの、容姿では部下にかなり劣る。名は梁元瑞(リャン・ヤンレイ)。しわの目立つ風貌で、六十歳以上と取られる事が多いが、実際は五十を二つ出たばかりである。
「かなり酷い」 司令員の元瑞は、ただでさえ目立つ眉間の皺を、さらに深く寄せた。 「上饒から江山にかけては連絡が完全に途絶してしまった。公安局の無線も飛ばん。最後の連絡では、降雨量が百ミリを超えたと言ってきたそうだ」 「百ミリ!! 本当でしょうか」 耳のせいではなく疑念から、副官は聞き直した。信じられなかった。いくら何でも多すぎる。 百ミリというのは、東京で三月中に降る雨の総量だ。東京で三十日かけて降る雨が、武夷山脈周辺に半日足らずで降ってしまった計算になる。 「計測に間違いがあったのでは。それに連絡途絶と言っても、あの地域は孤立しやすい地勢です」 「そうかもしれん。だが豪雨なのはたしかだ。例によって出動要請が来るだろう・・・・・・嫌な予感がするぞ」 水害の多い福建では、罹災者の救出や復旧作業に解放軍が出張るのは日常茶飯事だ。 梁司令は窓際に立った。ここ泉州でも、確実に雨足は強まっている。 「それにしても遅いな。昼飯時を過ぎているというのに」 新聞の事だ。中国の新聞は配布遅れが実に多い。 「俊卿(チャンチン)。お前の知り合いに福州(フーチョウ)の人民日報支局に勤める者がいたろう。今度会ったら文句を言っておけ」 副官は黙礼した。
福建省、武夷山中―
尚志と西河の乗るワゴンは、まだ峠にいた。周囲はさっきと変わらぬ『滝降り』だ。疲れはてた尚志と雲卿は、後部座席で鼾をかいている。小愉も雲卿の横で昼寝の時間。西河と季倫は前の席に座って、小さな声でおしゃべりしていた。 「なるほどお。お父さんの代わりに、か。それで上海から広州までわざわざねェ」 「嫌々じゃないの。ずっと住んでた街だし、ママに会えるんだもん」 「でも西河ちゃんがいなくなったら、お父さん心配しないかしら?」 「あたしだってこんな事したくなかったもん・・・けど、約束は守らなきゃ」 「うんうん」 季倫はニコニコした。 「あなたいい子ねえ」 西河は俯いた。照れてるらしい。 「それより!」 西河は季倫に身を寄せた。 「どうして愉さんと結婚したの」 「あら、どうして?」 「だって馬さんていいトコの人っぽいし。愉さんも植林の仕事に向いてそうじゃないけど、言葉使いは庶民だから。なんか釣り合いが取れないってゆーか」 「まあ」 季倫は口元を押さえてクスクス笑った。 「女の子はこれだから・・・」 「ほら、そういう笑い方。とても山のおかみさんには見えないの」 季倫はまだ笑っている。 「雲卿はあれでも大学を卒業してるのよ」 「ええっ!」 西河は驚いて後ろを見た。雲卿の団子鼻から鼾が洩れている。 「とても学士様(エリート)に見えない・・・」 「静かにしてね。小愉が起きちゃうから。私と雲卿は同じ大学にいたの。勉強していた科目は違うけどね」 「どうやって知り合ったの?」 西河が体を乗り出した。黒い瞳が好奇心で輝いている。 「面白い話じゃないわよ。実家の裏にあったハゲ山が土砂崩れを起こしたの。大学に行ってた私だけ助かって、あとはみんな土の下」 「・・・・・・・・・・・・ごめんなさい」 「いいのよ。その後、再発防止のために植林する事になったんだけど、偶然その工事に雲卿が参加しててね。それでまあ、色々あって・・・ 同じ大学と知った時は、お互いにびっくりしたのよ」 「ん・・・」 「大学を卒業してから雲卿の実家に行って結婚したの。仕事はいちおう、福建省の職員になるのかしらね。お給料も省からもらってるし。でも、やってる事は植木屋さんよ。雲卿も工事現場で働いてるうちに、すっかり周りの言葉に染まっちゃって」 「楽しそうだね」 「そんな事ないわ。夏の家なんて堀っ建て小屋よ。水は崖下の川から汲み上げなきゃいけないし、ご飯は焚き火で炊かなきゃいけない。電気がないからテレビもないの。楽しみはラジオくらいかしらね・・・」 「うわ、大変そう。でも馬さん、幸せそうに見える」 西河が言うと、季倫は目を細めた。 ゆっくりと、噛みしめるように、呟く。 「幸せよ。今は家族がいるんですもの」 西河は季倫をまぶしそうに見つめた。 「・・・ふわぁ。おい、今何時だ!」 尚志が急に声をあげた。 「西河、おい」 西河はこめかみをひきつらせ、剣呑な顔で振り返った。 「自分の時計を見なさいよ。せっかく良い話を聞いてるのに、ぶちこわしじゃない」 「何だよ、時間くらい教えてくれてもいいじゃないか」 「自分で見なさいって言ったでしょ! それに『西河』って何? いつからあたしを呼び捨てにできるほど偉くなったの。『西河さん』と呼びなさい、『西河さん』と」 少女の柳眉が逆立った。 「はいはい、西河『様』」 尚志は起きあがって頭を掻いた。 「まったく、馬さんを少しは見習ったらどうかね。馬は馬でも悍馬みたいな性格しやがって」 西河が足元のナップザックをゆっくり持ち上げた。その時ちょうど、雲卿が目を覚ます。 「あ、愉さん起・・・ぐぶ!!」 ワゴンの中にくぐもった声が響き、季倫は困ったように微笑した。
(続く) |
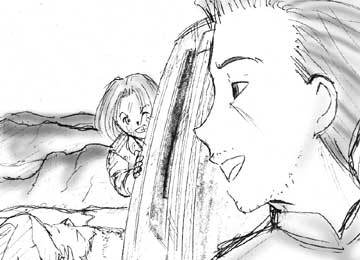 「えいやっ!」
「えいやっ!」 「なんだかこっちが助けられてるみたい」
「なんだかこっちが助けられてるみたい」 「異常な豪雨に襲われているんです!」
「異常な豪雨に襲われているんです!」 「豪雨なんて生やさしいものじゃない」
「豪雨なんて生やさしいものじゃない」 「人気の盒飯屋」
「人気の盒飯屋」 「この弁当代、誰が払うんだ」
「この弁当代、誰が払うんだ」 「無茶苦茶ヤバい福建の山」
「無茶苦茶ヤバい福建の山」 「三十一野戦軍」
「三十一野戦軍」 「酷いのですか?」
「酷いのですか?」 「止まない雨」
「止まない雨」