山内英郎さん<ハワイ イヒラニ宮殿ドーセント 日本語案内>
山内さんを知ったのは、ハワイに陳舜臣さんが病の後、療養をかねていかれる時ご一緒して
その時出あった方だ。
1930年生まれで関西学院大学から当時の出版社タイム社へ、リタイヤー後ハワイへ1992年に
移住された。
イオラニ宮殿でドーセントつまり日本語の案内役をボランテイアでされており、このドーセントになるには
イオラニ宮殿の歴史美術などを4ヶ月にわたりトレーニングを受けて更に試験を通らないとなれない。
山内さんは当時水,木、土曜日の午後2時半から日本語のツアーを受け持っていた。
この方の案内はイヒラニ宮殿の隠された本当の話をされるので<特に我々には>不思議発見みたいな
ものだった。
1997年にイオラニ宮殿のクイーン エマ サマーパレスの小雑誌を日本語に訳した事などの功績が
認められ当事のカエタノ知事からキロハナ賞を日本人では初めて受賞した。
彼の名刺にはIOLANI PALACE Volunteer Docent
H.BETO YAMANOUCHIと書かれてあった。
名前を呼ばれる時、やまのうちなのに、やまうちと言われると物凄く嫌がる人でした。
ハワイで会うとリーフホテルの海際のバーでビールを飲み、夕日を見ながら一人でコンドミニアムで
日本酒を飲むのが楽しいと話していました。
この方に後に自分の家のように過ごせるビーチウヲーク通りにあるブレーカーズホテルを教えられ
たのです。
教え方の一言は、こんなホテルがあるが、プールサイドの奥にバーがあり、そこのバーテンが
変わった人ですよという一言だった。
尋ねてみると確かに一風変わった海軍出身の男でトムといい、その発音がトムではなくタムに近い
発音でそうでないと機嫌が悪かったが根は優しい人だった。
山内さんハワイでの一人暮らしで、お酒の量が段々増えてきて、時には電話しても
ろれつが回らない時もあり心配していたら、日本で亡くなってしまった。
でもハワイの友人たちがワイキキの海にレイを流してドーセント山内さんの霊を慰めたという。
我々がイヒラニ宮殿を訪ねたときは、山内さんのお招きで、微々際にわたる忘れられない案内を受けた。
ハワイにはこのような方もいらしたのだ。
杉山義法さん<作家 脚本家>
2004年に亡くなった義法さん〈われらはギホウさんと呼んでいた>代表作は帝劇で公演した
弧愁の岸とあるがもう一つ忘れられない作品がある。
神社庁、永職会がプロデユースした、ミュージカル スサノオだ。
永職会の石清水八幡宮の田中宮司、生田神社の加藤宮司がミュージカルを作りたいと言ってきた時
一番に浮かんだのは作品を書いて頂く方それは義法さんしかいないと直感したのです。
丁度沖縄にいた義法さんに大阪に立ち寄りを願い、石清水八幡宮の田中宮司と大阪のホテルで
ミュージカル スサノオの話をして脚本をお願い、書きましょうということになった。
義法さんは朝のドラマ「風見鶏」で神戸のいろいろの人たちと懇意になり、しかもピアノ、ギター演奏の
上手な事、歌も上手く何処に言っても人気者でした。
この方,宝塚歌劇の花組にいた春野双子姉妹と親しく劇場に観劇にいったり、ご飯を食べたり結婚式には
後見人で出席すると言う関係でした。
バーに行くと良く飲んでよく歌いギター演奏でその腕前を披露、別名寅さんといわれていました。
ミュージカル スサノオは主役が3人いたので、その扱いに苦慮、3人のスサノオが最後には合体して
一つのスサノオを誕生させるという、素晴らしい舞台を考え出したのです。
公演は池袋のサンシャイン劇場でここには高円宮妃殿下も御出でいただき、舞台をご覧になり喜ばれました。
この後、名古屋の中日劇場、京都の南座で公演、神社庁、永職会の後々までの話題を生んだのです。
何事にも長けた方で、今日義法さんのような、繊細ながら太っ腹でアイデイア豊富な方が少なくなった事は
誠に淋しい限りといえます。
山本直純さん〈指揮者>
山本直純さん出会ったのは、大阪城ホールが出来た時、そこで一万人の第九コンサートをやろうという
企画が持ち上がった時だ。
初めは朝比奈隆さんに話を持ちかけると、この人でないとそれは出来ないといって直純さんを推薦してきた。
日経新聞で日本フルート協会会長の峰岸荘一さんが破天荒な指揮者と交遊録でかかれているが、正にそのとおり。
一万人のコーラスの指揮をするのだから指揮台の上で躍りあがって指揮棒を振っていた。
お酒の好きな直純さんは、大阪城ホールで一万人の第九コンサートが終わると関係者だけと中華料理の
テーブルを囲んでお酒が入ると駄洒落の連発でお色気交じりの話で出演者を喜ばせていた。
ある時、一万人の第九コンサートが終わりほど良くお酒がまわったころにホテル ニューオータニのロビーで
コーヒーをということに、そこにピアノがあるのに気がついて直純さん延々と演奏を始めた。
深夜のホテルのロビーで直純ピアノリサイタルの独占演奏会だった。
ミュージカル スサノオを公演するというと見に行くといい、ある日公演を見に劇場に姿を、
、どうでしたかと聞くと良かった!90点というので、直純さんそれ紙に書いてください、
楽屋に張り出すからというと、そのとおり書いて楽屋に張り出した事があった。
心の優しい方で、その夜は新宿のホテルで深夜まで初めて二人で飲み明かした。
そのとき直純さんは「人生即交響楽」という色紙を書いてくださった。
お酒が入ると駄洒落と発言が少々過ぎる時があるが、いずれも本音だったと思う事がある。
永遠に一万人の第九コンサートの指揮をするかと思っていたら、ある事情があって違う指揮者と
変わる事になった。
変わるときに、さよなら山本直純さん一万人の第九コンサートで花の道を飾れるかと思っていたが
その花道はなく、その後しばらくして直純さんは鬼籍の人となられた。
直純さんの人生は、何か皆責任を直純さんが背負ったみたいに感じて、心は本当に優しい方で
その指揮棒から出るパワーからは型破りの企画が生まれていたのです。
レンズの厚い眼鏡の奥からぎょろっと見つめる直純さんの目が今でも懐かしい限りです。
美吉左久子さん<宝塚歌劇団元生徒>
美吉さんを知ったのは、昭和51年頃だったと思う。
その頃はすでに現役生徒ではなく、宝塚歌劇団の演出家植田紳爾さんの公演の時、演技監督で
稽古場で生徒の芝居を見ていて、歩き方とか、日本物だったら刀のさしかた、抜き方など細かく
指導していた。
その若い頃のお顔を知らないが、多分に鼻筋が通った、きりりとした男役だったんだろうなあと、稽古場で
横顔を見ながら想像していた。
稽古場では、いつも私の横に来て座り、稽古を見ながら、あの生徒はどうとか意見を求められていた。
逆に、これという生徒に、こんな芝居をしたほうがいいと思うときは,美吉さんに伝えると、生徒を横に呼んで
そのまま話を伝えていた。
稽古場でいつも植田先生が私に声をかけてくれるので、うれしいと話していた。
それは図らずも元生徒として芝居は演じられないが、共に舞台に立っている気分に浸れたのだと思う。
日を追うごとに宝塚の生徒の雰囲気が変化していくので、昔を懐かしんでいた。
稽古場で最後に出あった頃は少し弱られたかなと思っていたが、その後お会いする機会もないままに
今日に至っていたが、2010年の秋にふと美吉左久子さんどうしてるかなと思い、
以前に演技監督になった時ニュースで取材したテープが出てきたので記念にとDVDにダビングして
お送りした。
2010年の年末に、春馬美智子さんが亡くなったというお知らせのはがきを受け取った。
春馬美智子さんとは美吉左久子さんのことだ。演技監督という役を設けたのも演出家植田紳爾さんの
アイデイアだった。
植田紳爾さん<元宝塚歌劇団理事長 演出家>
植田さんと懇意になったのは、まだ夕方のワイドニュースMBSナウがスタートした頃だった。
昭和51年、宝塚歌劇を取材始めた頃に知人の写真家の竹内広光さんが宝塚の演出家の写真が
撮りたいと言い出した。
白井鉄造さん、高木史郎さん、内海重典さんという方々がまだ元気の頃で、大阪の谷町のご自宅に
くつろいだ雰囲気の写真が撮りたいという竹内さんの希望で同行した。
植田さんのベルサイユのばらの人気真っ最中の頃で竹内さんも演出家皆さんの普段の顔、稽古場の顔を
撮影、演出家女の園の中でというタイトルで写真集を出した。
その本の表紙の写真も舞台で、風と共に去りぬの演出に当たる植田さんの写真だ。
その頃の植田さんは、トップスターが退団する時,いわゆるさよなら公演は必ず植田さんが作、演出に
当たっていた。
植田さんのサヨナラ公演の作品は一つの型があった。
それは未来があると感じた人の場合は旅立ち、そうでない人の時は最後が死ぬという物語だ。
発想的にその創り方には興味を持った。
稽古場での植田さんは大変に合理的でお昼前に稽古を始めて夕方6時頃には稽古は終了だ。
その為生徒も予定が立てやっすく、その頃の生徒たちは和気あいあいで、上級生の誰かが必ず
稽古のあとお鍋しよう、植田先生だから何処何処の店に6時半に集合という話がすぐにまとまる。
夕方6時を過ぎてまで稽古をすると言う事はほとんどなかった。
その代わり稽古中、遠慮して植田さんに直接台本の疑問点を聞きに行かない生徒は時間が長い場合
出番をカットされる時もあった。
それでも自分が担当する組の場合、事前にその組の公演をじっと客席から見ていて、その生徒に合う
台本を書くという、座付き作者の使命はちゃんと責任を持って果たしていた。
あるとき、折角良い生徒がいて役をつけても、次の公演の時その生徒が何もない役だと、折角の
盛り上げが無駄になると嘆く言葉を聞いた。
宝塚歌劇を取材していた間、植田さんはよく稽古場に見に来てと声をかけてきた。
初めて植田さんの作品に冠スポンサーがついたときは、やっと市民権を得たと喜んでいた。
今、宝塚歌劇の演出家はよくブロードウエイミュージカルなどを宝塚版と称して公演しているが
それは所詮ブロードウエイミュージカルなのだ。
植田さんの作り上げた作品,風と共に去りぬにしても誰が為に鐘は鳴るにしても、総てが宝塚調に
塗り替えられていたのだ。
只作品を舞台に上げるのではなく、宝塚調という基本を確実に守っていたところが素晴らしい。
舞台でも横で見ていて、ここはこう変えたほうがいいのではという意見を言うと、納得してれば素直に
意見を取り入れた。
たまたま後に星組のトップスターになった麻路さきの入団からトップなるまでの稽古場やオフの写真を
撮影していて、その話をすると、一言写真展したらと、宝塚の画廊で開催すると東京でもしたらと一言
有楽町の阪急デパートで開催、当事阪急関係者に一人の生徒の写真展なんか貴方でないとできませんよ
といわれた。
植田さんは、長年取材してきた事に対して、心で現したものだったと勝手に解釈した。
これも植田さんの一言で、念のため写真展を開く時、植田さんに一文を書いてもらった。
手形みたいなものだ。
その麻路さきが退団するときのサヨナラ作家は植田さんで歌劇団理事長でもあった。
作品は皇帝、暴君ネロの話だ。あるとき劇団の事務所にいると稽古場から出てきた植田さんが
稽古見た?マリコ<麻路さきの愛称>がいいからと一言。
当時は、宝塚歌劇団の演出家はみな、自分の稽古をしている稽古場に未見に来てと声をかけてきた。
和気藹々の雰囲気の中でわれわれも意見を良い、演出家もそうした助言を大切にしていた。
麻路さきの退団記者会見では、植田紳爾さんは宝塚の典型的男役風貌をもった人という表現を使った。
宝塚歌劇に燃えていた人だと感じた。
この植田さん、星組で鳳蘭が退団した後、瀬戸内美八がトップに、その稽古場で植田さんの横に座って
稽古を見ていたら、突然芝居している瀬戸内美八のそばに行き、一言つれちゃんそこ違うと。
鳳蘭が退団後初めての稽古だったので、まだ余韻が残っていたのかもしれない。
植田さんの頭の中には、通り過ぎていった生徒の面影がいつも漂っているのだろう。若き日の植田さんの
稽古場の姿が懐かしい。ええんちがう?ええやん!植田さんの口癖の言葉だ。
杉 良太郎さん<俳優>
杉 良太郎さん、東日本大震災の宮城県石巻市はじめとした避難所を訪れてカレーなどの炊き出しを
8500人分の食事を25人のスタッフで行った。
いかにも杉さんらしい、熱血漢振りを感じた。
この杉さんをはじめて知ったのは昭和50年初めの頃だ。
大阪の南にあった新歌舞伎座で年に二回杉さんの公演があった。
その頃、舞台から客席に降りてきて観客にサービスすると言うのが話題になり始めていた。
その頃夕方のワイドニュース「MBSナウ」というのが、始まったばかりで、早々に新歌舞伎座に
杉さんを取材にいった。
テレビ局が取材に来ない頃だ。
昭和53年1月演目は「明日の詩」ショウだ。
ロビーでカメラをセットして待ち受けると、杉さんが現れた。
「お尻から太ももの線が、そして、こんな目線が、お客様はいいとおっしゃるんですよ。
僕は別に意識してないけど、サービス精神ですよね。三階のお客様でも大切にしなくちゃ」
インタビューに杉さんはこう答えた。
杉さんのこの頃の着物の身巾は普通八寸のところが極端に狭くしたててあり、動くとさりげなく
素足が見えるようになっていた。
これも女性ファンの多い杉さんの舞台人としてのサービス精神だった。
それが杉さんの言うぬくもりかも。
それから公演ごとに取材に行くと、インタビューなのにロビーでは面白くないと、舞台の上に
稽古で役者さんたちが板付きになっている所でインタビューを。さすがに背後に偉い役者さんが
控えているので、恐れ入った。
楽屋を訪れると人なっこい顔でいらっしゃいと。楽屋に入るのはなかなか入れないと聞いていたが
杉さんはいつも気楽に暖かく迎えてくれた。
パイプを愛用していた頃なので、杉さんがパイプの葉は何をと聞くので、次に訪問した時オランダの
パイプ煙草の葉を差し上げると喜んでいたのが印象的だった。
周りの人へのしつけ?はなかなか厳しい様子と感じたこともあった。でもそれが自分の芸への
厳しさであったかもしれない
杉 良太郎芸能生活20周年記念のお祝いの会を開くとき、一言書いてほしいといわれて杉さんの事を
書いた。他にも縁の深い沢山の人が書いたが、それをまとめて「ぬくもり」という本にして、お祝いの席で
皆に配った。
ぬくもり、今回の東日本大震災で、石巻市で炊き出しをしたもの正に、ぬくもりの精神だ。
インタビューをしていたとき、杉さんがじっと見つめる目が、あまりにも燃えている目だったのが
今でも忘れられないし、杉ブームが加熱した頃に、他が騒ぐ前に取材に来てくれた事を喜んでいると
つぶやいた一言が今でも忘れない。
表面だけではわからないが、杉良太郎という人は、熱血とぬくもりを心の中に秘めている人だ。
今はない大阪難波にあった新歌舞伎座を思い出すと、そこには同時に杉良太郎さんがオーバーラップ
してくる。
※無断転載・使用禁止
 次のページへ
次のページへ  前のページへ
前のページへ 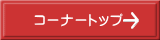 出会いそれは人生の道連れ
出会いそれは人生の道連れ
 次のページへ
次のページへ  前のページへ
前のページへ