アンジェリークは、強烈なスピードで仕事を覚え、こなしはじめた。
それはまるで砂に水が染み込むように、彼女は"秘書"の仕事を完璧に身に付けている。
その目に狂いはなかったと、アリオスは思う。
現に、彼女は、社の人間がけちをつけるところがないほど、彼のためによくしてくれている。
これが、個人的なことであったなら、と、彼は思わずにはいられなかった。
勿論、お昼休みになると、二人は公園に出かけ、アンジェリークの手弁当を食べ、ゆっくりと仕事を忘れて語り合う。
至福の時間が重ねられるほど、アリオスはアンジェリークのことを寄り深く思うようになっていた。
そして、アンジェリークも…。
共に時間を過ごせば、過ごすほど、二人の心の距離は縮まりつつあった。
だが実際の距離は、足踏み状態だった。
それは、アンジェリークが、アリオスを社長として捉え、引け目を感じていたからだ。
それを取り除くために、彼は気さくに彼女に接し、辛抱強く彼女を待っていた。
その様な日常が続く。
今日も、その様な一日がくれようとしている。
何の変哲のない日常が・・・。
午後5時。
仕事終了を知らせるブザーが、"アルヴィース”ビルに響き渡る。勿論、社長室も例外ではない。
「アンジェリーク」
「はい」
声をかけられて、資料をタイプ中だったアンジェリークは手を止めた。
「もう今日は帰っていい。カインが出張中で、おまえには連日残業で迷惑をかけたからな。週末ぐらいは、のんびりして、来週に備えろ。いいな?」
優しさの溢れる視線が彼女に降りてくる。いつも、仕事に向かうアリオスの目つきは厳しく、冷たい。だが、この一瞬に見せる彼の優しい笑顔こそが、アンジェリークを魅了して離さない。
だからこそ、彼の仕事が終わるまでは、傍にいたかった。
週末は、社長であるアリオスにとっては、目を通さなければならない書類の山と格闘しなければならない日である。
そんな日に帰る事なんて出来ない。
ましてや、彼の片腕カインが、海外に出張に言っていて、手伝うものがいない状態なのである。
「----社長、私も残ってはダメですか?」
凛とした強い光と優しさの混在した視線で、彼女は彼を見上げ、微笑む。
「----だが、おまえも疲れてるんじゃねえのか? あまり無理すんなよ?」
本当はその申し出が嬉しかった。
だが彼女の体を考えると無理をさせることが出来ない。
ただでさえ華奢な少女が、これ以上儚げにすることは出来ない。
「大丈夫です! ----けれど、社長が邪魔だと仰るなら…」
最初の勢いは良かったものの、徐々に自信を無くし、アンジェリークはすっかり元気を無くし、俯いてしまった。
そんな彼女が、可愛くて堪らないと、アリオスは思う。
彼は席から立ち上がると、静かに彼女の席の前へと進む。
「社長?」
「邪魔じゃない。残ってくれた方が助かる。だが、決して無理はするなよ? しんどくなったらいつでも帰っていいからな」
深く慈しみの在る眼差しを彼女に向けながら、そっとそのまろやかな頬に一瞬だけ触れる。
彼女の頬は一気に熱を帯びて、そこだけに総ての感覚が集中したように、感じる。
彼の指先は、彼女の熱を覆って止まない。
「あ…、有難うございます…」
思わず出た言葉だった。それがかえってアリオスの苦笑を誘う。
「クッ、それは逆だろ? ったく、俺がおまえに言うならともかく…」
「ご、ごめんなさい」
今度は別の意味で恥ずかしくなってしまい、アンジェリークは視線を僅かに下にする。
「サンキュ。アンジェリーク」
華奢な肩をポンと叩いて、彼は席に戻ると、再び書類に向かい始める。
その姿を、目を細めてゆっくりと見惚れながら、アンジェリークは幸せそうな微笑を浮かべる。
社長・・・。ううん…、アリオス…。私はあなたが大好き。ねえ…、好きって言っていいですか?
その熱い視線に気がついたように、アリオスは、一瞬、書類から顔を上げる。
からかうようなそれでいて少し可愛い笑顔を、彼は浮かべる。
もちろん、アンジェリークはその表情を捉えていて、余計に恥ずかしくなり、すぐにパソコンに視線を落す。
「わ…、私も仕事をしなきゃ…」
慌てて入力を始める彼女がおかしくて、アリオスは忍び笑いをしながら、仕事を続けていた。
いつか…、おまえを手に入れたい・・・。
心の中で、深く、願いながら----
----------------------------
二人は集中して仕事を続けた。
部屋に響くのは、パソコンのキーを叩く音と、書類がめくられる音だけ。
やがて、集中して仕事をしたのが幸いしたのか、アンジェリークの仕事が一段楽し、彼女は安堵の溜め息をつき、肩をポンポンと叩いた。
アリオスもその様子に、彼女の仕事が終了したことを感じ取る。
「終わったのか?」
「はい。一応」
彼女は柔らかな微笑を浮かべ、満足げに頷く。
「だったら、おまえは切り上げていいぞ? おまえのお蔭で仕事はかなり進んだ」
アリオスは相変らず書類の山に埋もれていたが、彼女に僅かに笑みを浮かべながら、帰るように促す。
銀色の髪をかきあげ、少し疲れた様子に見えた彼は、不謹慎だが、アンジェリークにとってはこの上なく艶やかだと思った。
こんな彼の傍にもう少しだけいたい----
彼女はそう願わずにはいられなかった。
時計をちらりと見る。
午後7時30分を軽くまわったところ。
ひとつの考えが、彼女の脳裏に浮かんだ。
「あ、あの、社長!!」
立ち上がった彼女から、突然、一生懸命な声が聴こえ、アリオスは、喉を鳴らして笑いつつも、魅惑的な光を宿す瞳を彼女に向ける。
「何だ? アンジェリーク」
「お、お腹、空きませんか!!」
唐突な質問がこれだとは、余りにも色気がない。
だがそこがこの少女らしいということを思い、アリオスは思わず笑顔が零れてしまう。
「そうだな・・・。いい時間だ。店屋物でも取るか…」
「私に、私に作らせていただけませんか? 下の階に行けば、パントリーもあるし…」
余りにも可愛い申し出。
アリオスの心は不思議と温かくなり、フッと優しい笑みをもらした。
「サンキュ。だが、キッチンはここにもあるんだ。それを使え。それに奥には玄関と、専用エレヴェーターも在るしな。良かったらそれを使え」
「え!?」
息を飲む間なんて、彼女にはなかった。
アリオスは引出しから電子キーを出すと、それを壁に向かってスイッチを押した。
すると、壁が左右に開き、その向こうには、立派な居住空間が広がっていた。
そこだけでも、十分に暮らしていけそうだ。
「俺が仕事で遅くなったときのための"家"だ。守衛室を通らずに済む一階まで直通のエレヴェーター、キッチン、バス、ベットルーム、客間とある。ここだけで住めるけれどな」
突然現れた部屋の豪華さに、アンジェリークは大きな目を見開いてみることしか出来ない。
「ほら」
アリオスは彼女に電子キーを投げる。
「そこを使っていいぜ? 全部の部屋のドアの、セキュリティを解くことが出来る鍵だ。夕食楽しみにしてるからな?」
甘く艶やかな微笑まれると、体の奥が熱くなるの絵尾彼女は感じる。
どうしようもないほど胸がどきどきして、切ない苦しさを覚える。
この微笑のために、一生懸命、美味しいものを作ろう…
「社長、がんばって、美味しいものを作りますね?」
ふふっと嬉しそうにはにかみながら笑う彼女が、彼の心の中を明るくする。
同時に誰よりも彼女が欲しいという感情が、彼の中に渦巻き、苦しめる。
アンジェリーク・・・。おまえが誰よりも欲しい・・・。
この気持ちを、俺は抑えることが出来るのか…?
「じゃあ、行って来ますね?」
それこそ嬉しそうに、楽しそうに、立ち上がると、別室へと入ってゆく。
「楽しみにしてるぜ?」
微笑みながらアリオスに答えると、彼女はドアをロックし、壁が閉じられた。
「おまえを"俺専用"にしてーよ、アンジェ…」
----------------------------
アリオスの別宅に踏み入れると、まさにそこは“ペントハウス”だった。
アンジェリークの脳裏に、一瞬、幸せそう、そこで暮らすアリオスと自分自身の姿が浮かび上がる。
それだけで、彼女は赤面してしまい、その空想を払うのに時間がかかった。
それが、現実になったらいいのに…
彼女はそう思いながら、キッチンへと向かう。
冷蔵庫の中身を確かめ、何もないことを確認する。
その後、キッチンから続く廊下を通り、玄関らしきものを見つけ、そこを開けてみた。すると、小さな廊下に出て、そこには、エレヴェーターと階段が備え付けてあった。
「これね、専用エレヴェーターは…」
部屋の鍵は、先ほどの電子キーと同じになっており、すぐに閉めることが出来た。
アンジェリークはエレヴェーターに乗り込むと、ボタンの“降りる”を押して、一階へと降りていった。
エレヴェーターを降りると、小さなホールに出た。
そこはセキュリティが完璧に施されている場所のようで、鉄の重い扉があり、電子キーで開けてからそこから外に出ると、社長専用の駐車場へと出た。
そこから彼女は歩いて入り口へと向かい、社員証でセキュリティを解いてから、外へと出る。 何もかもが完璧にされており、彼女は大きく羨望の溜め息を深く吐いていた。
スーパーで無事買い物を終えたアンジェリークは奥様さながらにキッチンへと立ち、アリオスのためにその腕を振るう。
今日のメニューは、手早く作れる物と言うことで、ミートソース味のパスタが選ばれた。
といっても、彼女が位置からミートソースを作るのである。
「社長、喜んでくれたらいいな」
アリオスの甘い笑顔を浮かべつつ、アンジェリークは料理の仕度を始めた。
アリオスは、彼女の笑顔のお蔭か、かなり集中して仕事をこなすことが出来、書類も総て目を通してしまった。
時計を見ると、まだ8時30分。
夕食食った後、アンジェリークを家に送ってやれるな…
彼は伸びをして立ち上がると、おくの彼だけの空間へと向かう。
勿論彼は、電子キーを余分に持っているために、中に入ることが出来るのだ。
キッチンからは、とてもいい匂いがしてきて、アリオスの食欲をそそる。
「アンジェリーク?」
キッチンにいる彼女は、その低くよく通る声に反応し振り返った。
勿論、太陽のような微笑を忘れてはいない。
「あ、社長、丁度良かった。今、呼びに行こうとしていたところなんです」
テーブルを見ると、既に二人分の食事の用意が出来ている。
「サンキュ」
アリオスの温かな微笑みに、アンジェリークは少し恥ずかしそうに微笑んで返した。
「さあ、腹減ったから、メシを食おうぜ?」
アリオスの声を合図に食事が始まり、穏やかに時間が流れ始める。
「アンジェ、おまえ、ホントに料理が上手いな?」
「有難うございます」
二人は他愛のないことを話しながら食事を楽しんだ。
食事の後の後片付けは、二人で一緒に行い、ようやく息を着いたのが、午後10時を過ぎていた。
二人とも、話に夢中になったのが
「あ、俺、仕事が済んだから、おまえを送っててやるよ?」
「はい、有難うございます」
急にかしこまる彼女を、アリオスは少し不満に思う。
彼女の態度がそうであればあるほど、彼にとっては二人の距離を感じてしまう。
「なあ、アンジェ」
「何でしょうか?」
「----仕事以外の時間は、俺のことは”アリオス”と呼んでくれねえか?」
何よりも嬉しい申し出だった。
彼女は僅かの頬をばら色に染め、彼を上目遣いに見つめると、コクリと頷いた。
目に見える進歩だと、アリオスは思う。
また二人の距離が縮まったかと思うと、彼は内心ほくそえむ。
「アンジェリーク…」
彼の低い声に導かれて彼女は顔を上げると、そのまま顎を持ち上げられて、深く、貪るようにその唇を奪われてしまった。
「あ、アリオス…」
思わず甘い吐息が彼女から漏れる。
「これが俺の気持ちだ。おまえはどうだ?」
艶やかに揺れる瞳に覗きこまれて、アンジェリークはうっとりと、夢見るように彼に見惚れる。「…同じ気持ちよ…、アリオス」
「そうか・・・。だったら、もっと深く俺の気持ちを教えてやりたい…、いやか?」
彼女は最早頷くことしかできない。
顔を赤らめる彼女を、彼は、愛しそうに見つめると、彼女を抱き上げ、寝室へと運ぶ。
彼女は彼の首に、同意の証として腕を巻きつける。
二人の情熱的なひと時が、今始まろうとしていた----
TO BE CONTINUED
JE TE VEUX
(Ⅳ)
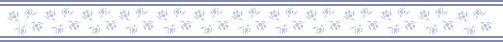
コメント
短期集中連載「実業家アリオスくん」まだおわりません(苦笑)
次回で完結しますが、このラスト私に「裏を書け」と誘っているような終わり方だにゃ。
どうするにゃ(笑)
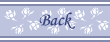
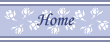
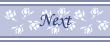
![]()
![]()
![]()
![]()