肌に唇を感じて、アンジェリークは目覚めた。
「----あ…」
瞳をゆっくりと開けると、そこには銀の髪をした愛しい人が素肌に唇を落している。
途端に昨夜の記憶が蘇り、全身が熱で火照ってしまう。
体の奥にある、気だるい甘い痺れが、それを事実だと物語っている。
彼女が目覚めたのに気が付き、アリオスはゆっくりと彼女の肩から唇を離し、穏やかに見つめた。
「おはよう、アンジェリーク」
「お、おはよう…、ございます…」
恥ずかしくなってしまい、顔を隠してしまった彼女がひどく可愛くて、彼は思わず喉を鳴らして笑う。
「アンジェリーク、顔を見せろよ」
「だって恥ずかしい…」
まるで幼子のようにいやだと何度か首を振り、栗色の髪がシーツの上を踊った。
「んなこと言うヤツはお仕置きだ」
「あ…、や・・・ん」
きつく首筋を唇で吸われ、アンジェリークの口からは甘い吐息が漏れる。
まだ聞き慣れない甘い声に、彼女は益々恥ずかしくなり、顔を覆う手に力を込めてしまう。
「ほら、おまえの顔が見てえんだよ。手をどけろよ」
何度も低い声で囁かれ、指に唇を受ける。それが余りにも甘美で、痺れるような感覚を、彼女の頭に残した。
何度か宥められて、彼女が彼に顔を見せたときには、既に紺碧の瞳は潤んでいた。
それは彼を魅了して離さない。
「アンジェ…」
優しく触れるだけの唇。
離された後、二人は互いを穏やかに見つめあう。
「もっとおまえが欲しい…、おまえを感じたい…」
低くくぐもった声が耳元で囁かれると、アンジェリークはもう何も考えられなくなる。
二人は何度も求め合う。
飽くこともなく、何度も、何度も・・・。
お互いの気持ちを伝え合うために。
お互いの情熱を分け合うために、何度も、何度も求め合った----
---------------------------------
ベッドサイドの電話が鳴り、眠りつづけるアンジェリークを抱きしめながら、アリオスは、彼女を起こさないようにそっと電話を取った。
「ああ。アリオスだ。----カインか・・・。どうだ、そっちは」
アンジェリークに囁く低く甘い声とは違い、怜悧で抜き身のような鋭い声だ。
「そうか。交渉成立か。ああ。俺も月曜にはそっちに飛ぶ。ご苦労だった」
電話を切りフッと息を吐くと、彼女を抱きしめる腕に力を込めた。
「あ…、アリオス…、今、何時?」
ようやく目覚めた彼の天使は、僅かに煙る蒼い瞳を彼に向ける。
「5時を回ったところだ。すっかり夕方だ」
「え、5時!!」
びっくりして、彼女は慌てて飛び起きる。
同時に起こるこの上ない羞恥の嵐が、彼女に降りかかる。
私ったら、何時間も…
「おい、今、すっげーいやらしいこと考えただろ?」
からかうように言われて、彼女は恥ずかしさの余り、今度は上掛けをすっぽり頭までかぶり、顔を隠してしまった。
「もう知らない!!」
すっかり拗ねてしまった彼女を、甘く笑い、上掛けごと抱きしめると、そっと顔を出させる。
「体、平気か?」
「え…」
一瞬意味が判らなかった。しかし、たっぷり数秒後に意味が判ると、彼女ははにかんで顔をまた隠そうとする。
「隠すなよ? おまえ…、初めてだったのに、無理させちまったんじゃねえかと思ってな」
隠そうとした彼女の顔を、彼は両手で覆い、そのまま上を向かせると、宥めるような優しいキスをした。
「マジで大丈夫か?」
「…ちょっと痺れてるけれど…、大丈夫だから」
「そうか…」
優しく微笑んだ後、アリオスは彼女の額にそっと自分の額をつけた。
「腹へらねえか? どっか連れっててやるよ。ついでに家まで送ってやる」
「…うん…」
彼女が頷くと、彼は体を離しベットから降りる。
「シャワー室と風呂があるから、おまえは風呂を使え。俺はシャワーを浴びるから」
「うん」
二人は、夕ご飯に行くために、ベットから降り、夫々の仕度を始めた----
--------------------------
アリオスがアンジェリークを連れて行ったのは、カジュアルなフレンチレストランだった。
そこで食事と話を堪能し、二人は互いに穏やかに何度も微笑み合った。
時間が止まってしまえばいいのに…
アンジェリークに小さな願いも、無常にも時間は聞き入れてはくれない。
食事が済み、アリオスは彼女を送っていった。
フレンチレストランから彼女のアパートまでは、車で10分ほどの距離だ。
その間も、過ぎる時間がアンジェリークには恨めしかった。
車はアパートに到着し、彼は彼女の部屋の前まで送ってくれた。
「アンジェ、楽しかったぜ?」
「私も…」
彼とほんのひと時でも別れたくなくて、彼女は切なくなり、おもわず俯いてしまう。
「明日から、俺は、急に海外に行かなくちゃならなくなった。金曜には帰ってくるから、その日は、ペントハウスで待っていてくれねえか?」
「え?」
すっと顔を上げ彼を見つめると、あの部屋の電子キーが差し出された。
「嫌か?」
間髪いれずに彼女は首を振ると、返事の代わりに彼の首に両腕を回した。
「待ってる。待ってるから、金曜日には、絶対に帰ってきてね…」
ふわりと甘い彼女の香りがする。
彼はそれを吸い込みながら、ほんの一瞬、彼女をぎゅっと強く抱きすくめた。
「ああ。その間、浮気すんなよ!?」
「するわけないわよ」
彼がゆっくりと体を離し、二人は見つめあい、微笑み合う。
「じゃあ、金曜日な?」
「うん」
手を上げて彼女に一瞥をすると、彼は階段を下りてゆく。
彼女は慌てて部屋の中に入ると、車が見える窓辺へ駆け寄り、開けて、彼が出てくるのを待った。
アパートから出てきたアリオスは彼女の視線を感じ振り返る。
アンジェリークが嬉しそうに手を振ってくれるのが見え、彼は手を上げて彼女に答え、車へと乗り込んだ。
幸せな気分の中、車を自宅へと静かに走らせる。
彼は途中あることに気がついた。
あいつを求めるのに夢中になりすぎて、愛してるって言ってやれなかったな…。
金曜日にはたっぷり聞かせてやるぜ? アンジェリーク。
----------------------------
僅か一週間のことだったのにもかかわらず、この期間が、アンジェリークにとっては、永遠のように感じられた。
そうしてようやく迎えた金曜日。
彼は5時30分着の飛行機で帰ってくるのだと言う。
この日のために、アンジェリークは前日からペントハウスに泊り込み、買い物などを済ませて、何時彼が帰ってきてもいいような状態にしておいた。
終礼のブザーが鳴り、アンジェリークはいち早く仕事を片付けると、そのままペントハウスに入った。
素早く料理がしやすいように着替え、寂しいからリヴィングのテレビを付けながら、彼のためだけに料理をしていた。
「えっと、後は…」
彼女の耳に、ふいにテレビのニュースが入ってきた。
「ニュース速報です。アルカディア空港に5時30分着のエア・ガイア航空の旅客機が消息を断ったというニュースが、今入ってきました…」
アンジェリークは一瞬耳を疑う。
5時30分到着のエア・ガイアの飛行機…!?
それは、アリオスから直接聞いた、彼が乗る便。
料理をする手を止めて、彼女はテレビへと飛びついた。
「まさか…」
全身の血がすっとひいてゆき、背筋に冷たいものが流れる。
足がガクガクと震えて立っていられなくなる。
「あ・・・あ・・・、どうしたら・・・、あ・・・あ・・・」
涙が止めどうもなく溢れる。
「アリオス!! アリオス!! まだ、“愛してる”って言ってもらってないのに、もっと、抱いて欲しいのに…!!!」
半狂乱になって彼女は泣き叫び、そこに立っていられなくなる。
アリオス…!!!
彼女はその場で意識を手放した。
彼女を発見したのは、一足先に昨日帰国をしたカインだった。
彼は、アリオスからの伝言を彼女に伝えるために、ペントハウスへと入ってきたのだ。
「アンジェリークいますか…、アンジェ!!」
リヴィングで倒れている彼女を見つけ、彼はすぐさま彼女を抱き起こす。
「アンジェリーク、アンジェリーク!! しっかりしなさい」
何度頬を叩いても、彼女は反応しない。
「いったいどうした…、あっ」
彼は、ずっとつけっぱなしだったテレビのニュースを見て、彼女が卒倒した理由をすぐに判断した。
「そんなに心配するなんて、社長、あなたは彼女に深く愛されてますよ…」
カインは、フッと優しい微笑みを浮かべると、アンジェリークをベットへと運び、寝かしつけた。
どれぐらい、眠っていただろうか。
彼女は誰かに抱きしめられているような気がして、そっと目を開けた。
一瞬、銀色の髪が彼女の視界を掠める。
え…、神様が私に夢を見せてくれているの…?
震える手でそっと手を伸ばしてみる。
確かに柔らかい髪の感触がある。
もう一度、ゆっくりと目を凝らしてみる。
そこにいるのは、確かに愛しい人。
翡翠の瞳が優しそうに揺れている。
「あ・・・」
彼女は涙で視界がよく見えない。
「----ただいま、アンジェ…」
甘く低い囁きは確かに彼のものだ。
アリオス…!!!!
「アリオス…、アリオスだ…」
涙声で、感極まった声で彼の名前を呼ぶ。
「ああ。俺はここにいる」
「アリオス!! アリオス!!」
感情の堰が切れたように彼の首に両手を巻きつけ、彼の名前を泣き叫ぶ。
「アンジェ、心配掛けた。偶然、飛行機に乗り遅れたんだ。それに、あの飛行機も墜落せずに、胴体着陸して、全員が助かったらしい…」
優しく、まるで子供をあやすように彼は囁き、彼女の亜麻色の髪を何度も撫でた。
「あのね、あのね、私…、どうしていいか…」
胸を引き攣らせながら、彼女は彼の胸に顔を埋めて、言う。
彼は思う。
誰よりも少女に愛されているのだと、今、全身全霊で感じることが出来る。
「もういい、何も言うな・・」
低い魅力的な声が彼女の心に落ちたかと思うと、そのまま顎を持ち上げられ、上向きにさせられる。
艶やかな翡翠の瞳が、今、彼女を捉えて、離さない。
「----愛してる…、狂おしいほどおまえだけを…」
深く唇を彼女に押し付け、彼は何度も何度も貪るように口づける。
「私も…、愛してる…」
激しい口づけの合間に、彼女もやっとのことで、彼にその愛を伝える。
その言葉を合図に、二人は愛の嵐に飲み込まれていった----
アリオスの逞しい腕に抱かれながら、アンジェリークは満足にうっとりと彼を見つめていた。
「さて、我が秘書殿」
「何かしら、我が社長」
「今日付けで、ミス・コレット、おまえはクビだ」
彼の意外な言葉に、アンジェリークは一瞬息を飲む。
その反応が可愛くて、彼は咽喉をクッと鳴らして笑う。
「俺、個人の専用になってもらうからな? 会社の業務はこれで終わり」
彼の言葉の意味が判らず、彼女は一瞬きょとんとしてしまう。
「ったく、これじゃあ判らねえのかよ」
彼は仕方ないとばかりに溜め息をつくと、ベットサイドにある蒼いヴェルヴェットの箱を手に取り、そこから指輪を取り出す。
「手を出せよ」
緊張の余り、アンジェリークは右手を出してしまう。
「違う、反対。左だ」
「あ、左…」
慌てて手を帰る彼女が、可愛くて堪らない。
「よし」
アリオスは、小さな彼女の手をそっと取ると、薬指にシンプルな指輪を填めた。
彼女の瞳と同じ宝石の付いた指輪を。
嬉しくて、何もいらないほど嬉しくて、涙を大きな瞳に浮かべながら、彼女は左手をかざしてみた。
「これ、選んでて、飛行機に乗り遅れた。これはお守りかもしれねえな」
「アリオス…」
彼は、今度は、優しく彼女をしっかりと抱きしめる。
「俺の専属は嫌か?」
「嬉しい。もちろん専属になる」
「明日、俺の家に連れて行くからな。そこが明日から、おまえの家だ…」
再び唇が重ねられ、二人は歓喜に飲み込まれていった。
今夜のこと、私は永久に忘れない…
翌日、夕方になって、ようやく二人は、アリオスの屋敷へと向かったと言う----
HAPPY END
JE TE VEUX
(Ⅴ)
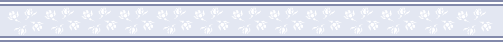
コメント
ようやく終わりました「実業家アリオス」さん。
幸せなシンデレラストーリーにしたかったのですがいかがでしたでしょうか?
この作品、実は未消化部分がありますよね〜。
書こうかな、ど〜しようかな。只今考え中です。
ですが、本編が終わって、少しホッとしています。
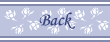
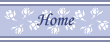
![]()
![]()
![]()