「驚いたか?」
艶やかに微笑み返すアリオスは、何時になく魅力的だった。
それもそのはずで、彼はディナージャケットに身を包み、一分の隙もない身のこなしだ。
「あの…、どうして…」
呆然と見つめるアンジェリークに、彼は優しい微笑をフッと浮かべた。
「ロザリア、ご苦労だった。」
言って、彼は彼女に一瞥を投げる。
そこには満足げな表情がある。
「かしこまりました」
ロザリアが優雅にそれを受け取り、社長室から出て行くと、そこにはもう二人しかいない。
「私ったら、あなたが社長だなんて思いもしなくて、失礼なことをしてしまって…」
震える彼女の声がやけに愛らしく、守ってあげたくなり、抱きしめて、甘く"違う”と囁いてやりたかった。
だが、そうするのは、少し早急のようにも思える。何とか、彼女を抱きしめようとする腕を抑えながら、ゆっくりと彼女に近寄る。
「そんなことはねえよ」
アリオスのきっぱりと言い切ったたった一言の言葉が、アンジェリークの心の枷を外した。
「有難うございます。じゃあ、どうして私なんかを秘書にしたんですか? 実力もないのに…」
戸惑いと力がない自分への悔しさが、彼女の肩を落させていた。
「それは、おまえが俺の秘書を務まると思ったからだ。俺が今まで秘書を置かなかったのは、適任者がいなかっただけだ。おまえなら出来る。そうじゃねえのか? アンジェリーク」
確信に満ちたアリオスの言葉と視線が、アンジェリークに降り注ぎ、彼女の心の中を明るく照らし出す。
アリオスさんに言われれば、出来るように思うから、不思議…
「判りました…、努力します」
そう云って顔を上げた彼女は、もう先ほどの戸惑いはなく、決心に満ち溢れた表情になり、どこかしら凛としていた。
「頼むぜ? アンジェリーク」
彼の妖艶な瞳に眩暈がするほど悩ましい笑みを滲み、彼女は甘やかな陶酔を胸に感じる。
コクリと頷く彼女の頬は、少し可愛らしく、うっすらと赤かった。
「じゃあ、早速、最初の仕事だ」
アリオスは、確認するかのように、着飾った彼女の全身を、ゆっくりと視線を這わせる。
その視線が、まるで甘い拷問のように、彼女の心を潤ませた。
「完璧だ。それだと、あのパーティでも遜色がないだろう…」
その視線から、彼女は逃れることなんて出来ない。
「行くぜ? 秘書さん?」
ポンと肩を叩かれ、彼に導かれて、彼女は部屋を出る。
それは、彼の秘書としての始めの一歩だった----
----------------------------
二人が駐車場へと着くと、車は、意外なことにアリオスの愛車だった。
たいそうなことを嫌う彼は、車の運転も自分で行う。
「乗れ」
促されて、最初、アンジェリークは後部座席へと座ろうとした。
「違う。おまえは前。俺の隣」
「はい」
言われるまま、頬を赤らめつつも、彼女は助手席へと座った。
恥ずかしそうにする彼女が、彼は可愛くて堪らない。
そこにいるだけで、アンジェリークは、否が応でもアリオスの艶やかさを肌で感じた。
彼女は胸に甘い疼きを感じる。
車は駐車場を出て、パーティ会場へと向かう。
運転する彼の整った横顔を見つめながら、彼女は胸の鼓動を速めた。
こんな、素敵な男性(ひと)の秘書が私なんかで、ホントにいいんだろうか…
うっとりと彼を見つめる彼女の緯線が、勿論彼を幸せな気分いさせたのは、言うまでもなかった----
パーティの会場は、ウォン財閥が所有する高級ホテル”クィーンズ・ロイアル”だった。
名前だけは知ってはいたが、こんな高級ホテルに足を踏み入れるのは、アンジェリークは初めてで、すっかり緊張してしまっている。
「ほら、行くぜ?」
「はい…」
さりげなくアリオスに腰を抱かれて、彼女は白い肌をほのかにばら色に染めながら、俯いたまま会場へと入って行く。
そんな彼女が可愛くて、アリオスは、溜め息が出るほどの艶めいた視線を彼女に送っていた。
アンジェリークが会場に現れるなり、男達の心奪われた視線が、彼女に向けられていたことなど、本人は全く持って気づいてはいなかった。
赤いドレスを身に纏う彼女が、清らかな美しさで、まるで天使のようだと、誰もが思っていたのだ。
会場のライトすら、彼女の羽根に見える。
「アリオスやん! ひさしぶりっ!」
アリオスとはまた違ったタイプだが、大人の魅力を醸し出した長身の青年がやってくる。
「よお、チャーリー」
アリオスも軽くてを上げ、彼に答える。
「あの方は?」
「ああ。チャーリー。ウォン財閥の総帥だ」
「え、あの方が!?」
青年の余りにもの若さに、アンジェリークは息を飲む。
ウォン財閥の総帥は、もっと年の言った男性だと、彼女は思っていたのだ。
「あれ~、可愛いコ連れてどうしたんや?」
チャーリーはうっとりとアンジェリークに溜め息を吐くと同時に、羨望の眼差しをアリオスに向ける。
あからさまなチャーリーの視線に、彼女は、恥ずかしくて堪らなくて、はにかむように俯いてしまった。
アリオスは、彼女が可愛いと思うと同時に、チャーリーの視線が気に入らず、それを阻止するために彼女の腰を抱く腕に力を込めた。
「俺の新しい秘書のアンジェリークだ」
アリオスはわざと"俺の”の部分を強い調子で言う。それは彼にとって、無意識の、所有の証でもあった。
「アンジェリークです」
「アンジェちゃんか~。かわいいな~。俺はチャーリー、宜しくな」
アリオスなど目に入らないといわんばかりの勢いで、彼女に精一杯近付いて、挨拶をする。
「宜しくお願いしますね、チャーリーさん」
それこそアンジェリークの太陽のような天使の微笑を向けられると、チャーリーは頬を緩ませて、それに答える。
「しっかし、おまえもとうとう秘書を置いたんか~。それもこんなエエコを」
「ああ。まだ、コイツを紹介しなきゃなんねえから、また後でな」
わざとチャーリーからアンジェリークを遠ざけ、他のパーティ参加者とも挨拶を交わしに行く。 挨拶をする人、する人、全員がアンジェリークの天使のような笑顔に魅了され、心奪われていった。
そのたびにアリオスの腰へ回された腕の力がどんどん強くなっていった。
「リラックスしろよ、アンジェリーク? 今日はおまえはお披露目だから、特に深刻に考える必要はないんだぜ?」
「はい…」
アリオスにそういわれたものの、やはり洗練された財界人に中に自分がいることが、彼女にはひどく場違いなことのように思われた。
「あら、アリオス、元気だった?」
艶やかで、大人な洗練された女性達が、アリオスに挨拶にやってくる。
どの瞳もアリオスをうっとりと見つめているのと同時に、彼の傍らにいるアンジェリークを疎ましく感じていることを、怜悧な彼女はすぐに察知した。
”恋”に関しては鈍い彼女だが、こういったことは、敏感に気がつく。
「ね、少しお話したいけれど、いいかしら」
女たちのリーダー格ともいえる、セクシーなドレスを着込んだ女性が、妖艶に彼を誘う。
「いや、こいつが…」
アリオスがそう言うと、激しい嫉妬の矢が彼女を遅い、その視線が痛かった。
「あ…、社長…、私はいいですから…、少し、行って来て下さい」
俯くアンジェリークはどこかしら元気がない。
「ね、アリオス、少しだけ」
余りにもせがまれていかないわけには行かず、アリオスは溜め息を吐きたくなった。
本当は、隣にいる、誰よりも美しい少女の傍らにいたいというのに。
「しょーがねーな。ちょっとだけだぜ?」
途端に女達からは明るい笑みがアリオスに向けられ、勝ち誇った笑みがアンジェリークへと向けられる。
「すまねえな」
「いいえ。社長、お気になさらないで下さい」
心とは裏腹な、少し能天気とも取れるような笑顔を彼女は彼に送り、送り出してやった。
アリオスが女達とテーブルに行き、楽しげに話す光景を目の当たりにしながら、アンジェリークは心が音を立ててきしんでゆくのを感じた。
胸の奥が苦しくなり、切なくて、寂しくて堪らなくなる。
私、ひょっとして、社長のことが----
大きな瞳から、これまた大粒の涙がとめどなく溢れそうになるのを必死で彼女は堪える。
隣にあり、自分だけの笑顔だった彼の笑顔が、今、あの艶やかな女性達に向けられている。
そう思うと苦しかった。
「どうしたんや、寂しそうな顔して?」
「チャーリーさん!!」
横にはチャーリーがいつのまにか立っていて、彼女の分のジュースを持ってきてくれた。
「はい、あんさんのジュースや」
「有難うございます…」
受け取った瞬間、今度は背後に人の気配がする。
「アンジェ、行くぜ?」
そこには、先ほどまで、女達と話していたはずのアリオスが立っており、まるで自分の所有物かのように、アンジェリークの腰を再び抱いた。
その行為が余りにも甘く、彼女の胸に深い陶酔を芽吹かせる。
「すまねえ、まだ、挨拶は終わってねえんだ、またな、チャーリー」
軽くウィンクをすると、アリオスはアンジェリークを連れて行ってしまった。
それが”嫉妬"という名の元で行われた好意だと知らないのは、会場には、アンジェリークしかいなかった。
---------------------------
結局、このパーティの間、アリオスはほとんどアンジェリークのそばを離れず、常に腰を抱いている状態だった。
誰もがアンジェリークに心を奪われながらも、アリオスという砦のために、臍を噛むことになった。
パーティもお開きとなり、アリオスはアンジェリークが一人暮らしをしているアパートに、彼女を送り届けた。
勿論彼女のナビゲーションの元である。
彼女のアパートの着くと、アリオスは、昼間買った彼女の荷物を、総て部屋へと運んでやった。
それがひどく恐縮してしまい、アンジェリークは終始、彼に気を使っていた。
「すみません、申し訳ありませんでした」
「いいぜ? また明日もお弁当を作ってくれたら?」
「え?」
嬉しい申し出に彼女の表情は一気に明るくなる。
「待ってるぜ」
そういうと、アリオスはほんの一瞬、アンジェリークの頬の羽のようなキスをした。
「…!!!」
余りにもの突然のことで、彼女はびっくりし、その後、羞恥で全身をばら色に染める。
その様子は、余りにも愛らしく、アリオスは思わず喉を鳴らして笑った。
「またな、アンジェリーク」
そう云って、アリオスは去ってゆく。
「アリオス社長…」
彼の残した甘く艶やかな笑顔は、アンジェリークの心を深く潤した----
JE TE VEUX
(Ⅲ)
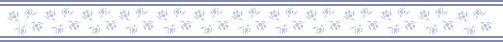
コメント
短期集中連載「実業家アリオス」の3回目。全く終わる気配なし(苦笑)。
tinkは特殊な仕事をしているので、OLさん、特に秘書の方がどのようにしていらっしゃるか判りません。
そのために少しリアリティがかきました。
まだ、続きますので、どうぞ宜しくお願いします。
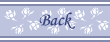
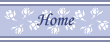
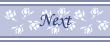
![]()
![]()
![]()
![]()