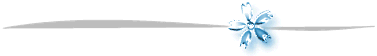
今のは・・・? アンジェリークは呆然と見ている。 大きな瞳を精一杯見開いて、ただ彼の姿を捕らえることしか出来なくて。 走りたかった。 アリオスの元に走っていきたかった。 だがそれも心を縛り付けている”鍵”がそうさせてくれなくて。 アリオスもまた、アンジェリークだけを見ていた。 今の彼にとっては、思いを伝えることが出来たことが嬉しい。 彼はゆっくりと立ち尽くすアンジェリークに近付くと、彼女を真摯な瞳で見つめた。 「----俺は本気だ、アンジェリーク」 低い声が温かさを帯びて、彼女の心の中に入り込んでいく。 アンジェリークは何とか頷くと、アリオスに泣き笑いの表情を浮かべた。 彼女の心が震えているのが確かであることを、アリオスは感じる。 そして、それだけでも第一歩だと、アリオスは思った。 「今度の休み、一緒にどこか出かけねえか? おまえさんをもっと知りたい」 アンジェリークはそれに頷くと、手を差し延べた。 それをアリオスは優しく包み込む。 今はこれでかまわねえ…。 きっとおまえを、振り向かせて見せる…。 互いの暖かさを感じながら、二人はじっと見つめ合う。 恋はゆるやかに進行していた---- マンションに戻ると、レイチェルが不思議そうな顔で、アンジェリークを見た。 「アンジェ、いいことでもあった?」 「えっ? 何で?」 ついつい顔がにやけてしまう自分にアンジェリークは真っ赤になってしまう。 「その顔が何よりの証拠!」 指摘されて益々茹で蛸のような顔色になる彼女が、レイチェルには可愛かった。 アンジェ、アナタが幸せだったらワタシは何も言わないヨ。 ただ、アナタが傷つくのを見たくないから・・・。 今度大きな傷を負ったら、アナタの心はきっと壊れてしまう・・・。 レイチェルは、繊細な心を持つ親友を、誰よりも心配していた。 入浴の後、アンジェリークは早速メールのチェックをした。 すると期待した通りに、アリオスからメールが来ていた。 後先構わず、アンジェリークは嬉しくなって、それを開いた。 ”今夜は楽しかった。明後日、公園にでも行かないか? 良かったら近くまで迎えに行く” メールを読みながら、アンジェリークの形相は変わっていく。 明るく可愛いものになる。 アンジェリークは、心を込めて、アリオスへの返事を打つ。 ”今夜は有り難うございました。私こそ楽しかったです。明後日の件、宜しくお願いします。” メールを打つだけで優しい気持ちになれる。 アンジェリークは送信ボタンを胸をときめかせながら押した。 約束の前の日の夜から、アンジェリークはいきいきとし、瞳は輝いていた。 こんなに綺麗なアンジェリークをレイチェルは今まで見たことはなかった。 服を選ぶのに悩む彼女に、レイチェルは微笑ましく思う。 「アンジェ、お洒落をしなくたって、今のアナタは十分に綺麗だよ」 頬を染め、首をかしげてアンジェリークは本当にと尋ねる。 「本当だってば! 自信を持ちなよ!」 強く言ってやると、アンジェリークはようやく恥ずかしそうに頷いた。 「明日、アリオス先生と会うんでしょ?」 一瞬、アンジェリークは体をぴくりとさせる。 「大丈夫、ワタシは止めないよ。アンジェ、頑張っておいでよ」 笑いながら肩をトンと叩いてくれた親友に、アンジェリークは本当に嬉しそうに頷いた。 ----------------------------- 翌日、約束の場所に、アンジェリークは立っていた。 薄いクリーム色のワンピースがいかにも彼女らしくて清楚に見える。 アリオスはアンジェリークの姿を見つけるなり、胸の奥が甘い感覚になる。 こんな狂おしい感覚はかつてなかった。 「アンジェ!」 目の前で車を止め、アリオスはその名を呼んで助手席のドアを開ける。 助手席を当然のごとく開ける彼は嬉しいのだが、何だかアンジェリークは気後れしてしまう。 「どうした…? 早く乗れ」 その問いに、アンジェリークはスケッチブックを取り出して、アリオスに書いて伝える。 『私がそこに座っていいの?』 「あたりまえだ、バカ。この場所はこれからはおまえ以外は乗せねえ」 さりげない愛の言葉が、アンジェリークの心の奥の鍵を、ゆっくりと溶かしてゆく。 彼女は唇の動きだけで"ありがとう"と伝えると、意気揚々と助手席へと乗り込んだ。 「行くぜ?」 彼の言葉にアンジェリークはしっかりと頷いて、嬉しそうに姿勢を正した。 車中、アンジェリークは彼に気を散らせまいと、何も特には話し掛けない。 手話で話し掛ければ、彼はきっとそちら集中してしまうだろうし、スケッチブックもまた同じような気がする。 話せなくても、運転する彼をじっと見ているだけでも、アンジェリークは幸せであった。 「どこに行くか興味はねえか?」 勿論とばかりにアンジェリークは頷く。 「だろ? 折角の俺たちの本格的なデートだしな?」 "本格的なデート” その言葉もまたアンジェリークの心を深く潤ませて、頬を紅潮させる。 「だけどヒミツな?」 途端に彼女は、わざと少しむくれた顔をした。 「やっぱり思い出のデートにしてえからな。おまえをびっくりさせてえし」 アリオスの楽しげな話に、アンジェリークの表情もいつしかほころんでいった。 アンジェリークは、"ありがとう”という思いを込めて、アリオスに頭を深く下げる。 「いいんだよ。遠慮するな?」 アンジェリークは何度も何度も頭を下げて、アリオスを見つめた。 「こら…、俺には遠慮するんじゃねえぞ? 二度とな?」 アリオスは小さな彼女の手を一瞬だけ握って、笑いかけてやる。 安心したように彼女も微笑み、頷いた。 温かな空気が車内に流れて、それに二人は漂っていた---- 車は、一時間ほど走った後、小さな自然公園の駐車場に止まった。 「降りるぞ?」 アリオスは自然とアンジェリークの手を引っ張ってゆく。 彼女も最初は少し恥ずかしかったが、だが嬉しかった。 彼の温もりを感じることが、その心を感じることのような気がして、とても嬉しかった。 ぎゅっと握り返すと、アリオスもそれに答えてくれてさらに強く握ってくれる。 アリオス…。 もっと強く握ってもいいのよ? アリオスはアンジェリークを無言で、目的の場所へと誘った。 そこを一目見るなり、アンジェリークは息を飲んだ。 そこはデイジーが可憐な色をつけて、野に一面に咲き誇っている。 爽やかな風が二人を包み込む。 「おまえだけにこの花を見せてやりたかった。 おまえこういうの好きだろ?」 目の前に見える光景を、アンジェリークは涙を日血筋だけ流して見つめる。 「アンジェ!?」 アンジェリークの涙に、アリオスは思わずドキリとした。 アンジェリークは首を何度も振って、否定をすると、慌てて鞄からいつものようにスケッチブックを出して書き始めた。 『凄く、嬉しいの。 こんなに綺麗な光景を見せてくれて有難う。 私の里も、秋になるととても綺麗に花を咲かせるのよ。コスモス畑があるの。そこをあなたにもいつか見せてあげたい…。 有難う・…』 「アンジェ…!!!」 アリオスは、もう彼女のことが愛しくて堪らなかった。 溢れる思いを停めることは出来ない。 「愛してる…」 アリオスはその華奢な身体を始めてかいなに抱く。 ぎゅっと強く、彼女を放さないように。 初めて抱かれる男性の腕のあた田坂、そして胸を騒がせる彼の香りに、アンジェリークは胸の奥が切なく痛むのを感じた。 自分が彼に釣り合わないことは判っている。 だが、求めずにはいられなかった。 彼に答えるように、彼女もぎゅっと身体を抱きしめてきた。 アリオスはあまりにもの感覚にアンジェリークをさらに抱きしめる。 「アンジェ…」 彼女を見つめる。 その潤んだ瞳には、明らかに艶やかな光があり、誰よりもアンジェリークが美しいとアリオスは思った。 彼は彼女の顎を持ち上げて、ゆっくりと唇を重ねる。 甘い口付け。 だが、彼のそれはとても深くて…。 彼女がびっくりしないように、最初は優しく、だが徐々に深さは色濃くなる。 舌で彼女の口腔内を愛しげに愛撫をし、力が抜けてゆく彼女をアリオスはぎゅっと支えてやって。 息が…できない・…。 アリオス…!! どうしてあなたのことがこんなに好きなんだろうか・… 唇が離された後、彼もまた艶やかな瞳で見つめてくる。 「アンジェ…」 あなたの名前がいいたい!! 呼びたい・…!!! その思いがやがて大きくなり、アンジェリークは一生懸命声を出そうとする。 「…ア…リ…オ・・・・」 か細い甘い声だった。 アリオスは驚愕してアンジェリークを見つめる。 彼の全身に感激の嵐が駆け抜ける。 「呼んで、くれたのか…?」 アンジェリークも、自分が声を出せたことに驚いて、頷くだけだ。 「アンジェ!!!!」 アリオスはそのままj心から彼女の名前を呼ぶと、もう一度しっかりと抱きすくめた。 俺は…、このときのアンジェリークの表情を一生忘れない…。 そして、あの天使のような声も…。 恋は、もう引き返せないところまできていた。 |
TO BE CONTINUED…
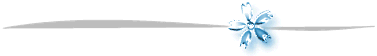
コメント
『愛の劇場』第四弾は、話すことが出来ないアンジェリークと、言葉を紡ぐことを
生業としているアリオスです。
アンジェリークのためなら心を入れ替えることが出来そうなアリオスさんです。
今回のラストシーンは、前半の山です。
これから二人は試練が待ち構えています。
アンジェちゃんを幸せにしてあげたいですね〜。
![]()
![]()
![]()