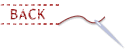コメント
「(I LONG TO BE)CLOSE TO YOU」6回目です。
最近、頑張って更新をしたせいか、かなりクライマックスに近付きました。
今回はクライマックスまでの中休み〜章です
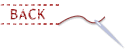


その夜、アンジェリークは何度となく鏡を見て、自分の顔が可笑しくないか確かめた。
「ねえ、お母さん、私の顔っていつも通り? ヘンじゃない?」
「さっきから何度も訊いて、どうしたのアンジェ? いつも通り、若い時のお母さんに似た別嬪さんです」
呆れたように彼女の母親は微笑み、真面目に取り合ってはくれない。
「もう〜真面目に答えてよ〜」
母の態度に、彼女は思わずその頬を不機嫌そうに膨らます。
「そんなに気になるんだったら、アリオスにでもお訊きなさい? 彼なら美容に携わってるから、すぐに返事をしてくれるわよ?」
アリオス----
その名を聞いた瞬間、アンジェリークは思わず唇に手を当て、真赤になった。
「どうしたのアンジェ?」
不思議そうに母に顔を覗かれて、彼女の顔は益々赤くなる。
「あ、私、部屋に帰るね!!」
慌てて二階に上がってゆく娘の姿を見つめながら、彼女は深い微笑を浮かべる。
アリオスと仲直りが出来たのかしら? アンジェ
もうお母さんも、あんなタイミングでアリオスの名前を出すことなんてないのに〜
部屋に駆け込み、上気した顔を、再び鏡で見つめる。
耳元に彼が力強く言ってくれた数々の言葉が蘇る。
『----おまえは”みっともなく”ない。むしろ、可愛い。自身をもて』
『今度のモデルの仕事はちゃんとやりぬけ。そこで、おまえが子供っぽくないことを教えてやる』
アリオスの言葉なら信じられると、アンジェリークは思う。
アリオス…。頑張るから、私、絶対に頑張るから、だから、わたしが"子供っぽくないこと”を教えて…
彼女は窓を開け、かつてはアリオスの部屋だった、向かいの部屋を見つめる。
今は誰もいない部屋----
そこを見つめながら、彼女は頑張ることを心に誓った----
---------------------------------------------------------------
撮影までの約一週間を、アンジェリークは肌と体調を整える時間に当てた。
レイチェルと相談しながら、誰にも頼らず、二人は一生懸命、美容についての勉強をした。
その間、彼女らがサロンに顔を出すことがなくなり、ほとんどのスタッフが寂しそうにしていたのは言うまでもない。
「とうとう明日か」
ロケの準備をしながら、アンジェリークは軽く溜め息を吐いた。
明日から2日に渡って、緑豊かな高原で撮影が行われるのだ。
かなりのパターンの撮影が行われるためと、場所が遠いために二日間が使われるのだ。
勿論その間、アリオスのサロンは営業をするが、縮小しての営業である。
それは、店長とチーフがいない以上、仕方のないことなのであった。
この一週間アリオスに勤めて逢いに行かなかった。
寂しかった・・・。
だけど、いっぱいいっぱい頑張ったって誉めてもらいたいから…。
私の存在を認めて欲しいから!!
彼女は、再び窓を開け、暗いアリオスの部屋を見つめる。
そうすると、何だか頑張れるような気がしてくるから不思議だ。
アリオス…、明日と明後日、頑張るからね?
彼女は潤んだ瞳で、頬杖をつきながら彼の部屋を真摯に見つめる。
アンジェリークのその姿を、アリオスが部屋の片隅で煙草をくゆらせながらじっと見ていた。
俺もずるいよな? おまえにばかりこんな想いをさせちまって・・・。
ついこの間までは、俺の後ばかり追いかけるガキだったのに、いつの間にか綺麗になっちまった。
時間は恐いな・・・。
あのチビが、今や俺の心の一番奥に住み着いてしまいやがった。
明日からの二日間で、俺はおまえに伝えてやりたいことがある…。
俺も同じ想いだということを----
だから待っててくれ、愛しいアンジェリーク・・・。
彼はフッと深い微笑を浮かべると、いつまでも彼女のシルエットに見惚れていた。
-----------------------------------------------------------------------
翌朝は早かった。
朝はどちらかといえば苦手なアンジェリークは、目覚ましを4つ仕掛けて、それでようやく起きれるというありさまだった。
どの目覚ましの音もかなり大きく設定してあり、正直言って、迷惑極まりない様相を呈していた。
勿論、昨日は実家に泊まったアリオスもその音に辟易した一人だ。
最も彼の場合は、それで起きれたということが大きいのだが。
「いってきま〜す!!」
「気をつけてね?」
母親に見送られて、アンジェリークが集合場所に向かったのは、まだ朝の5時30分だった。
彼女はチャーターのロケバスで、アリオスは愛車でロケ現場まで行くのだ。
荷物を持ちながら彼女が歩いていると、さりげなく、見覚えのあるシルヴァーメタリックのスポーツカーが、横にぴたりと止まった。
「アンジェ!」
声と同時に、アリオスがウィンドウを開けて顔を出す。
「アリオス」
「集合場所まで送ってやる、乗っていけ」
「有難う」
彼のさりげない気遣いが嬉しいけれども、ああいうことがあった後では、何だか照れくさくって、はにかんでしまう。
「おい、おまえが乗るのはこっちじゃねーだろ?」
そっと後部座席のドアを遠慮がちに開けようとして、アリオスに制止された。
「いいの?」
「いいも何も、いつも前に乗るだろう? 景色が良く見えるとか言ってよ?」
「うん・・!!」
いつものように溢れんばかりの笑顔----
この笑顔が眩しいと思いだしたのは、いったい何時からだっただろうか。余りに近くにいすぎて、余りに自然でずっと気がつかなかった。
彼女が助手席に乗り込み、シートベルトをすると、それを見計らって、彼はゆっくりと車を出す。
サングラスをかけ、車を運転するアリオスをアンジェリークはチラリと横目で見た。
ホント、アリオスって素敵なんだな。
幼馴染としては誇らしいけれども、ちょっと癪だな…
彼女の熱い視線にいち早く気付き、彼は、一瞬、優しい微笑を浮かべる。
「クッ、バーカ、何俺に見惚れてるんだよ?」
「見、見惚れてなんかないもん!」
「どーだか」
「ホントだって〜」
真赤になって怒る彼女が、アリオスは堪らなく愛しかった。
そして、今なら自分の気持ちに素直になれるかも知れないと思っていた。
車は静かに集合場所へと向かった。
「アンジェ〜!!」
車から降りると元気いっぱいのレイチェルが、手を振りながら駆け寄ってきた。
「レイチェル!!」
毎日逢っているのにもかかわらず、二人は手を取り合って、楽しそうに笑い合う。
「今日は頑張ろうね!」
「うん!!」
力強く返事をして、ふとアンジェリークの視線に親友の恋人が飛び込んできた。
「あれ、エルンストさん…」
「おはようございます、アンジェリーク」
レイチェルの恋人である堅物の大学講師エルンストが、礼儀正しそうに挨拶をしてくる。
その途端いつもは凛としているレイチェルが、頬を赤らめて上目遣いでアンジェリークを見る。
「あのサ・・・、進行スタッフに頭の切れる人がいるって聞いて、エルンストの話をしたら、是非にって…、オリヴィエさんが・・・」
「宜しくお願いします、アンジェリーク」
「こ、こちらこそ」
折り目正しく挨拶をされると、アンジェリークもそれにつられて頭を下げた。
「さあ、レイチェルもアンジェリークもバスに乗り込んでください」
エルンストに促され、彼女たちはバスに乗り込んだ----
主なスタッフ、アンジェリーク、レイチェル、そして機材の多いオスカーはロケバス、オリヴィエは愛車、セイランとアリオスの美容チームはアリオスの愛車にと、夫々が乗り込んだ。
ロケバスを先頭に、数台の車が連なって、目的地へと走り始める。
アンジェリークは、気を利かせて、レイチェルとエルンストを隣同士で座らせ、自分自身は一人で座ることにした。
バス、苦手だけれど、寝ていれば、何とかなるかな…
目を閉じようとしたときだった。
「お嬢ちゃん、ここいいかな?」
低い声に導かれて目を開けると、そこにはオスカーが立っていた。
「オスカーさん」
「いいか?」
一瞬、彼女は逡巡した。
脳裏にアリオスの顔が浮かんだからである。
アリオス…、誤解しちゃ嫌だな・・・
「お嬢ちゃん?」
怪訝そうに呼びかけられて、アンジェリークは思わずはっとした。
そうよね…、アリオスはそんな私に対してそこまで思っていないよね・・・
彼女は思い直して、少し引き攣った笑みを浮かべると、どうぞとオスカーに同意した。
「有難う、お嬢ちゃん」
オスカーが満足げに微笑むと、当然の如く隣に腰を降ろす。
「あの…、酔うかもしれないので、寝ていいですか?」
「ああ」
彼女は再び目を閉じる。
折角のシチュエーションを台無しにしてしまった少女の態度に、彼は少なからず苦笑いをした。
アンジェリークとオスカーが隣同士に座ったことを、アリオスは気がついていた。
アンジェ…!!
彼は不機嫌そうに眉を顰める。
アリオスの心が嫉妬で燃え尽くしていようとは、アンジェリークは知るすべもなかった----
-----------------------------------------------------------
最初のサービスエリアに入り、アンジェリークは真っ先に車を降りた。
自然の空気を吸うためである。
「あ〜、開放された気分〜」
駐車場で思い切り伸びをしていると、車から降りてくるアリオスを真っ先に見つけ、彼女は早速駆け寄った。
「アリオス〜!!」
もちろん、彼女は彼が嫉妬の炎を燃やしているとはついぞ知らない。
彼女が手を振っても、アリオスは目を逸らす。
「アリオス…!?」
それが彼女の心に大きな暗雲を齎し、急に元気が萎えてしまったように、立ち止まった。
「行くぜ? セイラン」
「いいのかい? アリオス、アンジェちゃん…」
逆にセイランが焦っている。
「いいんだ」
嫉妬に狂う余り彼は、大人気ない行動をとりつづける。
「あ〜あ」
思わず、セイランが呆れ気味い溜め息を吐いていた。
歩きつづけるアリオスを見つめながら、アンジェリークはがっくりと肩を落とし、茫然自失となる。
最近のアリオスはヘンだ…。
優しいかと思えば、今みたいにとっても冷たくなる…。
ねえ、私たちはもう元へは戻れないの!?
彼女はそのまま踵を返し、ゆっくりとバスへと戻っていった。
バスがサービスエリアを出て暫くして、アンジェリークは段々、乗り物酔いが辛くなってきていた。
先ほどまでは何とか気力で頑張っていたのだが、ショックが強かったのか、最早気力が使えないところまできていた。
「うッ…!!」
余りにも苦しそうなうめき声が彼女から漏れ、誰も彼女に注目する。
「アンジェ!!」
「お嬢ちゃん!!」
彼女の顔色はそれこそ紙のように白くて、今こそ崩れ落ちそうだ。
「ごめん!! ワタシがアナタの横に座ってあげればよかった!! バスに弱いのすっかり忘れてた…、ゴメン、アンジェ」
アンジェリークは弱々しく首を振る。
「とにかく、どこか近いサービスエリアで、車を停めよう!!」
オスカーはバスの最前列まで行き、運転手と協議をする。
その間、レイチェルがアンジェリークの隣に座って、背中を何度も撫でた。
「”ウリエル・リヴァー”が一番近いらしい、そこで停めよう。他の車にも連絡する」
連絡専用のトランシーバーを取り出すと、彼は簡潔に話し始めた。
「オスカーより各局へ。今、バスで急病人が出た」
「ねえ、急病人だって? 誰だろう?」
シーバーを聞きながら呟くセイランに、アリオスは一瞬、嫌な予感がする。
まさか…
『急病人はアンジェリークだ。かなりひどい乗り物酔いだ。とりあえず、"ウリエル・リヴァー”で停車する。』
アリオスは急にアクセルを踏み、車のスピードを上げる。
「どうしたんだ、アリオス!?」
「バスの先回りをする。そこからアンジェリークをこの車に乗せる」
「アリオス…」
迂闊だった。
アンジェが俺が運転する車以外はダメだってことを、すっかり忘れていた。
許してくれ----
アリオスは、夢中で車のスピードを上げた----
TO BE CONTINUED
![]()
コメント
「(I LONG TO BE)CLOSE TO YOU」6回目です。
最近、頑張って更新をしたせいか、かなりクライマックスに近付きました。
今回はクライマックスまでの中休み〜章です