| 第8章 望郷
転機
シゲが絣同業組合からの寄付帳を持ってきた。井上伝の没後30年を記念する顕彰石碑建設のためだと言う。井上伝が亡くなったのは、トクが久留米に着いた翌年であった。従って、「伝の没後」は、そのままトクの久留米在住期間と重なる。トクが60歳という区切りの年を迎えようとする頃である。
「あれから30年ですか、早いものですね。おシゲさんも私も年をとるわけだ」
トクの呟(つぶや)きを、頷(うなず)きながら聞いているシゲである。井上伝の記念石碑は、見上げるばかりの巨大なもので、両替町の久留米絣同業組合の中庭に建てられた。明治31年11月のこと。
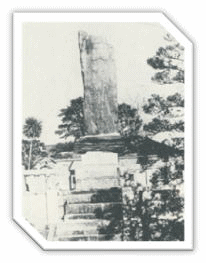
建立当時の井上伝記念碑
(両替町に建立、後五穀神社に移転)
料亭翠香園で催された落成祝宴にはトクも招かれた。
「あなたが久留米縞織りの小川トクさんですか。素晴らしい特産品を生み出されましたね」
目の前の来賓席から声をかけられて、トクは面食らった。立てられた名札には、「福岡県知事曽我部道夫殿」と記されている。
「もったいないお言葉でございます」
井上伝と自分が比較されること自体が恐れ多いことである。井上伝が創出したかすりは、その後弟子や職人らによって受け継がれ、国武や本村など商売人らが世に広げた。トクの縞織は、かすりの勢いに乗せてもらっただけのような気もしている。
縞織組合が、小川トクへの褒賞金として36円の一時金と毎月6円の生活費を贈ることを決めた。「生活費月6円」は、当時熟練の織り子が27日間働いて得る織賃分に相当する金額である。
「おシゲさんはどう思う? 組合からのお褒めを」
「もらっておきなさいよ。トクさんはそれだけのことばしてきなさったとですけん。これから生きていくのに、お金はいくらあっても邪魔にはならんと思いますよ」
悩んでいることが馬鹿らしいほどに、シゲの答えは明快であった。
先輩との対話
井上伝の没後30年を記念した行事がひと段落した頃、トクは寺町の徳雲寺を訪れ、伝の墓前にしゃがみこんでいた。
「伝さん、いろいろ行事が重なって、お疲れでしょう」
周囲の蝉時雨(せみしぐれ)がやかましくて、彼女の独り言もかき消されそう。
1.gif)
井上伝の墓(久留米徳雲寺)
「伝さんにとってめでたい時に、申し訳ないとは思うのですが・・・。しばらく、私の取るに足りない愚痴を聞いてくれませんか」
トクは、これからの生き方を、はた織りの大先輩の前で決断しようとやってきたのであった。小川トク、63歳になっている。物心ついてすぐにはた織りを始めた。江戸の上屋敷に奉公に上がった約10年間を除いて、1日も欠かさず織り機の前に座っていたような気がする。久留米に来て、伝が織るかすりを見て、もっと安くて丈夫で柄が美しい絹糸入りの縞を織ろうと心に決めた。伝に対して好敵手を買って出ている自分にハッとしたこともある。
久留米縞が世の評判を得ると、たくさんの婦女子がトクの門を叩(たた)いた。一人前になって巣立っていった彼女らは、トクのはた屋を助けてくれた。今では師匠を追い越す勢いの弟子も大勢いる。
トクは、はた屋のおかみさんになってからも、はた織りを止めることはなかった。「トンカラリン、トンカラリン」。杼(ひ)を投げた後、ヨコ糸を筬(おさ)で締め付ける音を聞きながら。
「私は、好きな時間に好きなだけ、いつまでも縞を織っていたいわ。でも、そんな悠長なことを世間が許してくれないのよ。こんなことなら、はた屋なんて始めるんじゃなかった、と悔やんでも後の祭りね」
「何を贅沢(ぜいたく)なことを言っているのよ、トクさん」
目の前の墓石が僅(わず)かばかり前にせり出して、中から女の声が聞こえたような気がした。
「伝さん、私ね、あなたが生きている間に、はた織りの真髄(しんずい)とやらを聞かせて欲しかったわ」
・・・・・・
「伝さんは、独特の美しいかすり模様を創りあげたわ。あなたが織った久留米絣は、日本中の男や女、それに子供やお年寄りまで、たくさんの人に好かれました。こうなることを、あなたは生きているうちに予想できたかしら?」
「そんなことわかるわけがないじゃないの。私だって、好きなことをやっていただけだよ。あんたと同じよ」
墓石からの言葉が現実味を帯びてくると、トクの語りかけも滑らかになった。
「はた織りは、人間が持つ感性が、手先や指先を通して生み出していくものだと思っていたわ。それが世間では、感覚も指先もそっちのけにして、機械ばかりに頼るようになって・・・」
「あんたの愚痴ってそういうこと? 私なんか、木綿布を織ることと織ったものを売る商売とは別物だと、とっくのむかしに考えていたよ。これからのあきんどは、もっと進んだ機械を考え出して、いっぺんに何百反ものかすりや縞を織るごとなるだろうからね」
「・・・・・・」
「でもね。あたしゃ、はた織り女だよ。今の時代に生きていたとして、やっぱりむかしながらのいざり機で、ヨッコイショ、ヨッコイショと、あの重たい杼を送り続けていると思うよ」
「伝さんは亡くなって30年も経つというのに、みなさんから慕われているわ。素晴らしい記念の碑まで建ててもらって、偉いわね」
「あんただって、同じだよ。遠い国からやって来て、独特の双子縞を創りだしたじゃないの。あたしのように久留米から外に出たことのない田舎者には、思いも及ばない技術や人の好みを取り入れてさ。それこそがトクさんの、何よりの功績だよ」
「・・・・・・」
「でもね」
「でも・・・、なに?」
「これから先どう生きていくかは、あんた自身が考えることだよ。私に聞かれても、それは無理なことだ」
「ここにいたんだ」
後からシゲの声が飛んできて、思わず立ち上がった。
「そうじゃないかと思って、追いかけて来たとこ」
シゲは、トクの瞑想(めいそう)などお構いなしに、そばにしゃがみこんだ。
「おシゲさん、もう一つのお墓にも付き合ってよ」
二人は寺町から人力車に乗って梅林寺に向かった。明治2(1869)年に東京で始まった人力車は、狭くて不規則な日本の道路事情ともあいまって、3年後には早くも久留米の街を走っていた。
トクは持参した生花を墓前に供えた後、浅乃に語りかけた。
「母さんは疲れたよ」
最初に出た言葉がそれであった。徳雲寺で聞いた井上伝の声。「でも、あたしゃはた織り女だよ。今の時代に生きていたとして、やっぱりむかしからのいざり機で、杼を送り続けていると思うよ」の言葉が脳裏に焼き付いている。
「母さんは生まれつきのはた織り女だもんね。だから、母さんにははた屋のおかみさんなんて似あわないからやめる。いいだろう、それで」
娘の了解を得なければ、今後のことも決められない自分がおかしかった。隣で聞いているシゲも、トクの決意に驚く風はなかった。
1.gif)
梅林寺(久留米市)
「そんなことだろうと思って、追いかけてきたとたい。トクさんも私も、とっくに還暦を過ぎてしまったしね」
反発しないシゲに、トクは拍子抜けを覚えた。
「これからの小川商店は、安男ちゃんに継いでもらいましょうね。大丈夫よ、後には倉蔵もいるし、平太郎だって・・・」
シゲの二男坊の安男が、成長して小川商店に入った。今では青木倉蔵とともにトクを助ける大きな存在になっている。
「本来なら、浅乃ちゃんが養子を貰って跡を継ぐところだったのにね。それでトクさんは、これからどげんすると?」
「そうね、近くに小さな家でも借りて、織り機を1台だけ据えて、往生するまで縞を織っていたいわ」
「トクさんがはた屋をやめれば、あたしだって遠慮はいらんね。これからは亭主と二人で静かに余生を送りますか」
両人の会話に湿っぽさはなかった。
日清戦争後の久留米地方における縞織物の生産は、伝統のかすりに急迫する勢いであった。明治32(1899)年、久留米市の縞織物の生産高は、23万5千反に及んだと記録されている。
ひとり住まい
トクは間もなく、水道町からほど近い鳥飼村の白山(現久留米市白山)でひとり住まいを始めた。明治35(1902)年である。
引っ越しを済ませると、シゲを誘って筑後川の土手に出た。蛇行している川を直線化して新しくできた人工河川を、土地の人は「放水路」と呼んでいる。江戸を発って初めて筑後川を渡るとき、「三途の川」に思えた渡し場近くである。土手には1200本ものさくらの苗木が植えられた。
「ここでお花見ができるようになるまで、あと何年かかるかしらね」
若木の列を見渡しながら、トクがため息をついた。
「そげん時間はかからんと思うよ。5年もすれば、ござば敷いて酒盛りができるごとなるよ。松屋のおじさんも時計屋の末吉さんも、それからウメさんもあちらの世界に逝ってしまったしね。その時は、トクさんと二人だけで、賑やかに宴会でも開きまっしょうか」

かつての筑後川放水路のさくら
トクが突っ込めばシゲが受ける。30年間のつきあいは、両人を肉親以上の間柄にしている。
そのシゲも、年を越せないままに他界してしまった。安男からの知らせで蛍川の家に駆けつけたとき、枕元には亀吉が無言で座っていた。
「私を残して一人で逝ってしまうなんて、ずるいよ、おシゲさん」
血の気のひいたシゲに向かって話しかけていて、不思議に涙も出てこなかった。葬式が済んで、浅乃のときと同じように放心状態が続いた。
このところ、白山の家を訪ねて来る人も少なくなった。たまに来る客といえば、顔も覚えていない「むかしの知り合い」が、金の無心に現われるくらいである。いちいち名前を確かめたりすることも面倒で、箪笥(たんす)の中の小銭を出してやった。借用書もとらないままで、誰にいくら貸したのやら、そのうちにわからなくなってしまった。
トクは、訪ねてきた新聞記者に、その間の事情を述べている。
「実は私もこんなに貧乏せいでもよろしかったのでありましたが、あちらこちらに金を借られまして、それが今日までとうとう取れずじまい。歳は老いるし、今日のありさまに立ち至りました」と。
気持ちが落ち込むと、織り機の前にいる。自分が着るものくらいは自分で織らなければと杼を投げるが、以前のように快い音は返ってこなかった。
隆盛を極めていたはずの縞織物業界にも、思わぬ落とし穴が待っていた。70歳を目前にして、めっきり白髪が増えたトクのもとに、安男がやってきた。明治41(1908)年の夏だった。
安男の話だと、東京から農商務省の役人が来て、『これまでの染料を、藍草から硫化染料に転換すべし』と助言したと言う。硫化染料といえば化学薬品である。
「お上の言うことには逆らえんとですよ、みんな」
安男も疲れているのか、口調に精彩がない。
「それで、あなたの考えはどうなの、その硫化染料とかいうもののこと」
「俺は絶対反対たい。むかしから久留米の縞は、藍草で染めたもん(正紺色)を看板にしてきたとじゃけん。それが化学染料に変わったと聞けば、客が離れていくのは目に見えとるけんですね」
「賛成という人たちの言い分は?」
「全国の競争相手に勝つためには、いつまでもむかしのことにとらわれとっちゃならんち・・・」
「平太郎さんや倉蔵さんはなんて」
「俺の考えと同じです」
それから間を置かずして、化学染料を導入しようとする派のはた屋が次々に組合から離れていった。そうなると、トクが受け取る手当ても6円が5円に下がり、最近ではそれすら滞るようになった。
孫の来訪
気がつくと、トクの身の周りから人がいなくなっていた。組合からの手当ても完全に止まり、その日暮らしの状態に陥った。時々顔を見せるのは野田マサヨくらい。マサヨは、姉のハツコを亡くした後も、しばらくは水道町の作業場で働いていた。だが、50歳を機にそれもやめて、家で孫の守りをしていると言う。
「いつの間にか、七十を過ぎたわ」
トクが立ち上がりざまに呟いた。
「先生、そろそろお里(生まれ故郷)が恋しゅうなったとじゃなかですか?」
マサヨがからかうように言って見上げた。言われてみれば、最近やたらと宮ヶ谷塔で過ごした頃の夢を見る。氷川神社で遊んだ子供の頃や、赤ん坊の栄三郎を背負って、綾瀬川のほとりを行き戻りしたこと。初恋の相手の清吉や彼の母親の郁枝など、時代も年齢もお構いなしに浮かんでは消えた。
「駄目ですよ、先生らしゅうもなか。まだまだ久留米の縞織りは、先生がおらんとでけんです」
マサヨは、ひとしきり日吉町での思い出話に花を咲かせた後、荒木の家に帰って行った。するとまた独りぼっちになる。
「ごめんください」
表戸が開いて若い男が入ってきた。「もう、人さまにお貸しする金なんて、びた一文ありませんからね」なんて、ブツブツ唱えながら立ち上がった。
「小川トクさんですか?」
青年の訛(なま)りは、遥かむかしに聞いた生まれ故郷のそれである。
「私がトクですけど・・・」
訛りは宮ヶ谷塔のものでも、目の前の来訪者にはまったく心当たりがない。
「おばあちゃん、はじめまして。あなたの孫の徳次郎です。栄三郎の息子です」
鳩が豆鉄砲を食らったとは、こんな時に使う言葉だろうか。頭の中が真っ白になった。
「確かに私は小川トクですけど。ふるさとの宮ヶ谷塔で産んだ子供に、栄三郎という男の子がいたことも確かです。でもね、もし息子が生きていたとして、私がこの場所にいることなど知るわけがないわ」
「どうしておばあちゃんの居場所がわかったかって? それはわかりますよ。だって、久留米縞を売り出した小川商店が小川トクの店だってことくらい、関東にいてもわかりますよ」
遥かに遠い武蔵国で、自分が始めた久留米縞の名が知られているとは、考えも及ばないことだった。国武商店や本村商店が、全国的に販売網を広げていることは聞いていても、現実問題として捉えることはできなかったからである。
「久留米縞はわかっても、小川商店の主が栄三郎の母親だってこと、どうしてわかるのかしら」
目の前の青年が、自分の孫だという実感がどうしても湧かない。
「親父が言っていたよ。久留米縞の商標に書いてある小川縞織商店は、俺のお袋の店だって。絶対にそうだって。血が繋がっていりゃわかるものだって」
しばらくたって落ち着きを取り戻したトクは、慌てて青年を座敷に上げた。
「それで、栄三郎さん、・・・あなたのお父さんは元気なの?」
「親父は元気だよ」
「あなたの外に、栄三郎の子供は?」
「妹と弟と2人いるよ」
「あの時赤ん坊だった栄三郎に、あんたを含めて孫が3人ね。あの子は、さぞこの母を恨んでいるだろうね」
トクは、台所に立ちながら、孫が発する次の言葉が怖くて振り向けなかった。
「親父が子供の頃には、おばあちゃんのことをずいぶん恨んだらしいよ。曾々祖父(じい)ちゃんが亡くなる頃、家には1反の田んぼも残っていなかったと言うし。親類の家に引き取られた親父は、大きくなったら必ずおばあちゃんに仕返しをするって決めていたらしいよ」
徳次郎は、父親を代弁するように、淡々と話した。
「栄三郎も苦労したんだね。みんなこのおばあちゃんがだらしないばっかりに」
卓袱台(ちゃぶだい)の上に湯飲みを置きながら、トクはようやく孫と向き合った。
「親父は、裸一貫から材木店を興したんだ。商売が軌道に乗り、失った田んぼを取り戻していくうちに、おばあちゃんに対する恨みも薄らいでいったんだって」
「そんな優しいことを言われると、あたしはどこに身を置いていいのかわからなくなるよ」
「本当だって、おばあちゃん。親父はもう五十だよ。歳をとるに従って、自分を産んでくれた母親に会いたくなった。同じ屋根の下で、他の人がしているように普通の親孝行がしてみたいって」
「でも、あんたを産んでくれたお母さんは、このおばあちゃんとは他人だよ」
.gif)
トクの生家跡
「そんなことはないって。九州に発つ前の晩にお袋が言ったよ。お前がお父さんの願いを叶(かな)えてあげなさいって。必ずおばあちゃんを連れて帰ってきなさいって」
話が進むに従って、トクの感情が高まり、頬を伝う涙が止まらなくなった。
「ところで、徳次郎さん」
「いやだなあ、僕はあなたの孫だよ。さん付けはおかしいよ。徳次郎と呼び捨てにしてよ」
「そうだね、あんたは私の孫だったね」
初めて祖母と孫が打ち解けて目を合わせた。
「こんなに遠いところまで会いにきてくれて、本当にありがとう。私は孫のあんたに会えただけでもう十分だ」
「ここから宮ヶ谷塔まで、おばあちゃんが思うほどに遠くないよ。汽車に乗っていれば、久留米から東京まで、あっと言う間さ」
「でも・・・、その間に海もあるだろう。九州と本州の間にさ」
「久留米の停車場を出れば、線路は海峡の渡し場まで真っすぐだよ。渡し船を降りたら、すぐそばに東京行きの汽車が待っているんだ」
「そうかい、そんなに便利になったかい」
.gif)
昭和4年当時の門司港駅(門司港駅展示)
孫に「武蔵は近いよ」と言われて、懐かしいふるさとの風景が目の前に躍り出た。20歳で宮ヶ谷塔を飛び出して江戸へ。江戸から久留米に来る途中、渡し船に乗って九州路へ。50日かけてようやくたどり着いた久留米の街を目の前にして、筑後川が立ちはだかった。その時、この川を渡ってしまえば、二度とふるさとの土を踏むこともできなくなるだろうと思ったものだ。
迎えに来た孫は、明日にでも久留米を発とうと誘った。
.gif)
関門連絡船(大正14年)下関歴史資料館
「待ってよ、徳次郎。確かにおばあちゃんは新しい縞織物を売り出したし、たくさんの弟子も育てたよ。はた屋稼業で一時は大金も手にしました。でもね、恥ずかしながら、今のおばあちゃんは、ふるさとまで帰る旅賃すら持ち合わせない貧乏人なんだ。どの顔下げて、捨てた息子のもとに手ぶらで帰れようか」
「それを言うなって。親父はおばあちゃんの消息をずっと以前から知っていたんだ。それでもこれまで迎えに来なかったわけがわかるかい?」
そう言われても返事のしようがなく、目をウロウロさせるばかりである。
「おばあちゃんの事業がうまくいっている間は、遠慮していたんだよ。だって、仕事が順調なときに、息子です、武蔵へ帰ろうなんて言われたら、おばあちゃんが困ったろう」
「・・・・・・」
「仕事仲間を通じて、おばあちゃんのことは調べていたのさ。はた屋をやめて、暮らしにも難儀をしていると聞いたから、僕に迎えに行くよう言いつけたのさ。おばあちゃんは、体一つで帰ってくれればいいんだよ」
そこまで聞いて、トクは堪えきれずに徳次郎の厚い胸板めがけて飛び込んだ。そんな祖母の背中を、孫が優しく撫でた。
第二の故郷
再度迎えに来ると約束して、徳次郎が久留米を去って後、栄三郎から郵便が届いた。
「母さんが久留米にいることを知りながら、これまで迎えに行かなかった不孝をお許しください。徳次郎から母さんがこちらに帰ってきてくれると聞き、嫁ともども喜んでいます。商売も順調だし、母さんが住んでいた頃より大きな家も建てました。大好きなはた織りを続けたければ、部屋も機械も材料も嫁が揃えるそうです。母さんを迎える準備は万端です。その日が来るのが待ち遠しくて、眠れない夜が続いています」
40年間住み慣れた久留米を後にする日が近づいた。再婚相手の徳三と娘の浅乃、姉妹以上に気持ちが通じ合えたシゲ、江戸の上屋敷以来の戸田覚左衛門の母摂子や隣人のウメ、それに、はた屋開業以来何かと支えてくれた本村商店の庄兵衛など、この間に身近な人が次々にこの世を去っていった。彼らが今生きていたら、自分を快く送り出してくれるだろうか。
.gif)
梅林寺の宗野末吉夫妻の墓(手前)
「それはなかばい、トクさん。これだけお世話になった久留米ば見捨てたら罰があたる」と言って、時計屋の末吉だったら目をむくかもしれない。
でも、宮ヶ谷塔に帰りたい欲望が、第二の故郷となった久留米への未練を飛び越えてしまう。孫の徳次郎が再び久留米にやってくる日が待ち遠しくて仕方がなかった。
見納めだと思いながら、久留米の賑やかな町中を歩いた。「槌屋足袋店」の看板が目に入った。西南の役で大損した倉田雲平は、「足袋作りこそ我が天職」の初心に戻って商売に精を出し、店を拡大している。今では4千坪もの土地に大きな工場を建てた大会社の社長さんである。
「相変わらずのご繁盛ですね」
トクは数少なくなった古い友人に、気安く声をかけた。
「時計屋の末吉さんもとっくに亡くなったし、これでトクさんまでいなくなりゃ、いよいよ久留米も寂しゅうなるな」
必ずしも世辞だけではないと、雲平の挨拶に感謝した。
「申し訳ないわね。大恩あるこの地に、何のお返しもしないままで去るなんて。むかし話にあるじゃないか、あの・・・」
「遠い月からやってきて、帰る術(すべ)を持たずに泣いてばかりだったお姫さまの話だろう」
「そうそう、かぐや姫だったね。私も人の子だねえ。懐かしい月の世界からお迎えが来れば、育ててくれたお爺さんやお婆さんへの大恩までも忘れてしまう」
「そんなことはなかよ、トクさん。誰でも年を重ねりゃ、生まれた場所が恋しくなるってもんさ」
雲平は、豪快に笑いながら、トクの掌に餞別袋を押しあてた。
|

