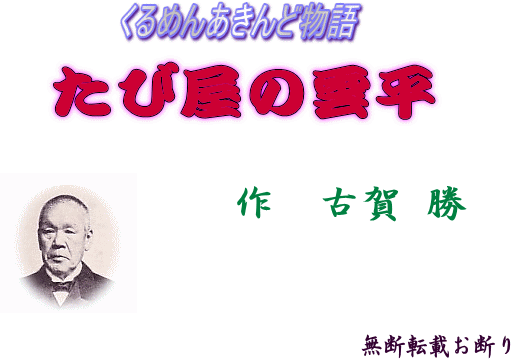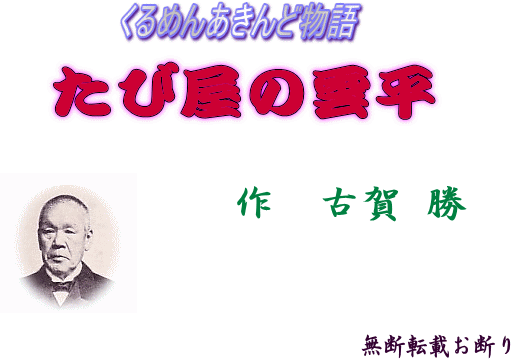|

長男と二男①
「またまた戦争が始まりましたね」
支配人の川上が雲平に、日露戦争勃発の新聞記事を説明している。
「大ごとにならなきゃよかばってん」
戦争は、商人にとって注文が殺到するよい機会でもある。だが、徴兵されて戦場に出向く親類の息子のことを考えると、単純に喜んでばかりもいられない。彼らに再び故国の土を踏める保証がないからだ。10年前の日清戦争では、久留米周辺だけでも1万3千人以上の戦死者をだした。今回の日露戦争は、北の強国ロシアとの戦いである。それ以上の犠牲を覚悟しなければなるまい。
そんな折(明治37年)、二男の泰蔵が久留米商業学校を卒業した。
「あいつには、事務方ばやらせるけん」
これまた、以前から考えていたことであった。
「金蔵は、長崎で良い成績を上げて自信を持ちましたからね」
長男重視の時代にあって、モトは泰蔵のことより金蔵が後継者としての実力をつけたことを大そう喜んでいる。雲平はというと、長男が職人修行にそれほど熱心でないことが気に食わない。
「金蔵は、職人というより商売人に向いておるんかな」
.gif) 写真:往年の倉田泰蔵(像) 写真:往年の倉田泰蔵(像)
「商いに向いているだけではありませんよ、金蔵のよいところは。内国博覧会に行った折に、その都度裁断機や便利な機械を見つけてきたじゃありませんか。工場の将来を見据えているところなんて、逞しいですよ」
モトの長男思いはとまりそうにない。
「その時は川上がついていたからたい。足袋が作れんもんには、足袋屋の跡取りの資格はなか。それに金蔵は、金ば使うことはできても、節約する道が分かっとらん。職人の気持ちとかそろばん勘定がわからんもんに、店の頭になる資格はなかちいうことたい」
「それは違いますよ。あなたさんが足袋屋を起こしなさったときと時代が違うのですから」
「どう違う?」
「あなたさんが店を起こしなさった時は、店にはあなたさん1人しかいませんでした。自分でやらなければ何も前に進まなかったのです。それが今では...」
「従業員の数が増えたち言いたかとじゃろ。ばってん、時代が変わっても、商いの本筋は変わらん。足袋屋の亭主は、足袋が作れるもんにしかできん」
「そんなことはありません。これからは分業の時代ですから。大勢の従業員をまとめていく能力を備えていればよいのです」
モトも、こと金蔵の将来のことになると、持論を曲げる気などさらさらない。
「人が増えて、売り上げも伸びました。それでも、むかしとちっとも変わらないのは、お金の苦労を私一人で背負っていることですよ。職人たちに払う毎月のお給金の心配も、私だけがしているんですからね」
夫との話が平行線に向かうと、次に飛び出すのは必ずモトの愚痴である。
複式簿記②
「先日、泰蔵が変なことを言いだしましてね」
「何て?」
「これからは、店の帳面を複式簿記に切り替えないといけないんですって」
「なんじゃ、それは?」
「今までのような帳面では駄目だというんですよ。だから、複式簿記にと」
話題が長男の将来から帳面のありように急展開した。
「フクシキ何とかちは、いったいどげなこつか」
「ずっとむかしから続いてきた大福帳とは、まったく違うものらしいですよ」
モトも、泰蔵の提案が商業学校上がりの思いつきのような気がして、本気には考えていない。それよりも、自分がこれまで向き合ってきた帳面(大福帳)までも否定されたようで、面白くないことこの上ないのである。
「呼んで来い、泰蔵ば」
我が意を得たりと、モトは小走りで自室に籠っている次男を呼びに行った。
「俺は、今までやってきた大福帳が、みんないかんちは言うとらん」
泰蔵は、いきなり父親に「母親が苦労してつけてきた帳面にケチばつけるのは百年早か」と怒鳴られて、小声で言い訳をした。
「それなら、どげなことか、父ちゃんにも分かるごと説明してみろ」
「日本の商人は、これまで大福帳ば頼りに商いばやってきたけん。店の取引高とか機械の数とかの規模が大きゅうなったら、大福帳ではやっていけんごとなるとたい。それじゃけん、複式簿記でなからんと・・・」
「そげん、商業学校の先生が言わしたとか。お母しゃんの大福帳がどこがいかんとか」
雲平は、息子の主張を聞きながら血相まで変えている。
大福帳とは、江戸時代から続いてきたもので、商家の取引を時系列的に記帳してきた帳面のことである。主に、取引先別売掛金と未払い金を記録していく。
一方、泰蔵が持ち出した「複式簿記」とは、すべての商取引と財産を、項目別に分類して記録する方式のこと。財産の項目は「資産・負債・資本」に分類され、取引状況は「費用・売上・利益」に大別される。これら、5つの項目は、取引ごとに「借方」と「貸方」を並行して記入(仕分け)し、最終的に「貸借対照表」と「損益計算書」にまとめられる。
「複式簿記ば採り入れたら、1度の帳面つけで、売り掛け・買い掛けはもちろん、会社にある財産の具合まで、1銭単位で正確に分かるとたい」
そう言われても、むかしから続く帳面しか知らない雲平とモトには、泰蔵の言い分を鵜呑みにはできない。その場に、商業学校卒業の先輩格である吉岡保が呼ばれた。
「学校では、商売の基本として、帳面ばいかに正確につけるかを教えられました。帳面ば正確につけておれば、1年間の儲け具合や、今店にある財産が一目でわかるようになるとです」
吉岡の説明でも、まだ納得いかない雲平である。
「1度にやり方を替えてしまうのは怖いですよ。でもね、せっかく泰蔵がやる気を起こしたのだし、吉岡もそう言うのですから、しばらくは大福帳と複式簿記とやらの両方をやってみましょうよ」
モトが、これ以上親子で言い争っていてもらちが明かないと言い出した。
「両方やることは、手間も2倍かかるちいうことじゃなかか」
雲平の大福帳固執は、少々のことでは変化しそうになかった。
「仕方ないですよ、これも新しい時代の会社に衣替えをしていくためですから」
「店」から「会社」へ③
「ここは、雲平しゃんが譲らにゃいかんじゃろない」
雲行きの悪さを悟った雲平が、青々館に駆け込んだ。だが、嘉助は雲平に助け舟を出そうとしない。
「ばってん...」
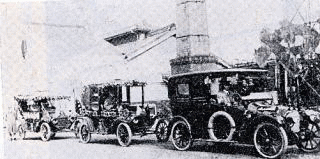 写真:つちやたびの宣伝カー 写真:つちやたびの宣伝カー
「ばってんも糞もなかばい、雲平しゃん。つちやたびば新しか時代に向いた会社に脱皮させるよか機会じゃなかか。そのために、泰蔵ば商業学校にやったとじゃろう」
嘉助の言う意味がよく飲み込めない雲平は、黙って出された茶を啜っている。
「どういうことか、もうちょっと詳しゅう...」
間をおいて雲平は、親友を促した。
「雲平しゃんが言う、天職の有り様も変わってきたちいうことかな」
「天職の有り様?」
「これまでの雲平しゃんは、足袋ば作り続けとりゃよかった。ばってん、今のごと工場に機械がばさらか(たくさん)入って、何百人もの人間ば雇うようになればない。雲平しゃんとモトちゃんだけでやっておった店と同じようにはいかんごとなってしまうとたい」
「・・・・・・」
「雲平しゃんに雇われたもんには、嫁さんもおれば子供もおろう。人によっては、親御さんや兄弟の面倒ばみとるもんもおるかもしれん。その人たちば皆んな、雲平しゃんが面倒みなきゃいかんとばい。自分は足袋作りの職人ば全うしておればよかちいうわけにはいかんたい」
「それはわかっとる。ばってん、それなら俺はどげんしたらよかと」
写真:つちやたび工場内部
 嘉助も、ここはいい加減な言いまわしは許されそうにないと思っている。 嘉助も、ここはいい加減な言いまわしは許されそうにないと思っている。
「金蔵が一人前になって、泰蔵も学校を出た。雲平しゃんもそろそろ作業場から卒業するときが来たということじゃなかか」
「卒業して、俺は何ばすればよかとか」
「これからの雲平しゃんは、大きゅうなった店が、行く先ば間違わんごと、正確に運転することたい。足袋作りの精神ば若い者に教えるとか」
「・・・・・・」
「金蔵も、今では人が嫌がる行商ば率先してやって、商売人の心が分かってきとるし、泰蔵も、大きゅうなった会社ば、どげんして持っていくか頭ば絞っとる」
いつになく熱弁をふるう嘉助である。
「雲平しゃんの工場も、また一つ、大きな転換期を迎えることになるじゃろない」
「どげなこつな、転換期ちは」
「いよいよつちやたびが、九州から日本国中に飛び出していく時が来たちいうことたい」
嘉助の見通しは的中している。それから間を置かずして、つちやたびは年産100万足を達成する。
明治38年、久留米の街を馬車鉄道が走るようになった。その頃、雲平は増産に次ぐ増産で工場の拡張と職工の補強に追いまくられた。金蔵らが勧業博覧会で見つけてきたドイツ製の靴底裁断機を、足袋の裁断機に応用して対応する。出来上がった機械は、1人で1日3千足分の裁断を可能にした。また、足袋底を縫う機械も実現した。つい何年か前までの生産ペースが、一挙に7倍にまで膨らんだ。
「足袋ば作るのに、材料を一々買うとったんでは、仕入先によって、材料が違う分だけ違う商品になるけんね。つちやたびは、どげな種類でも同じものでなきゃない。そのためには、自分で織って自分で染める、そげな工場が必要たい」
「職人」の実技を取り上げられた格好の雲平は、それまで気がつかなかった工場の隅々にまで目が届くようになっていた。
「それはその通りですが...」
モトが、言いにくそうに、言葉を選んだ。
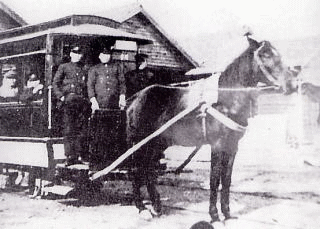 写真:久留米市内を走っていた馬車鉄道 写真:久留米市内を走っていた馬車鉄道
「よかけん、言うてみろ。俺の考えは間違いか?」
「そうじゃありませんよ。白糸(原料)を買いつけて、それをつちやの工場で織る。織ったものを製品に合わせて染色する。それがつちやたびとして世に出る。結構なことではありませんか。でも...」
「しぇからしかね(もどかしい)。言いたかこつがあるなら、どんどん言わんか」
「それなら言います。つちやで作る足袋の材料をつちやで賄うとなれば、今の工場では狭すぎます。それに、機械とその機械を操る人も少なすぎます」
モトの指摘は的を得ている。
「そのことならいま、川上が広か土地ば探しておる。機械も、全部買っておったら、金がいくらあっても足らんけん、機械に詳しか連中に研究ばさせるたい」
その後雲平は、原料を統一するために、つちや工場での織布機械を開発した。「織底機」を発想し、更なる研究の末に「倉田式吉野織機」も稼働させた。不足する人手の問題は、久留米市内に置かれている監獄内に織機を備え付け、囚人にも織らせた。
一貫生産④
モトの街中情報収集の鋭さは、未だ衰えることがない。
「嶋屋さんのことですが。店でお父さんのお手伝いをしてらっしゃる長男さん(重太郎)に次いで、来年には次男さん(正二郎)もお店に入られるそうですよ。うちもうかうかしておれませんね」
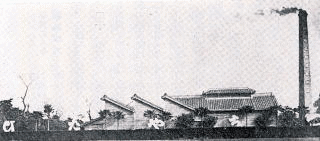 写真:完成なった白山本社工場 写真:完成なった白山本社工場
そうは言うものの、モトの口ぶりに慌てた様子は見えない。
「新参の足袋屋に負けてはおれんな」
雲平は、川上や吉岡などとの打ち合わせを重ねた。こんな席には、必ず金蔵と泰蔵も同席させている。
こうして得た結論は、モトが言う通り、大きな工場の建設を急ぐことだった。そこで見つけたのが、三潴郡鳥飼村白山(現久留米市白山・現在のムーンスター本社工場周辺)の土地であった。明治39年も師走に入ってからのことである。
敷地は4,025坪(13,283㎡)と、米屋町工場とは比べようもない広さである。そこには、足袋の材料となる綿布を織る工場を建てた。完成した工場には、半年かけて研修を重ねた技術班があたり、開発したばかりの織機を80台備え付けた。機械を動かすのは、蒸気発動機である。更に、織り上がった布を、商品別に染色するのも自前の技術で賄えるようになった。
「織布も染色も大事だち思いますばってん、足袋の製造工場も相当狭かですよ」
川上の進言に応えて、織布工場の隣りに400坪の足袋製造工場を建てた。そこには、蒸気による動力ミシン135台を備え、15キロワットの発電機もつけた。
時代は明治40年代へと進む。倉田雲平は57歳になり、人生も佳境期に入った。白山の新工場は順調に滑り出している。このときの職工数は1,523人。その内足袋製造に関わる男工240人、女工963人、織布男工190人、女工13人だったと記録されている。つちやたびは、久留米を代表する大企業に成長したのである。
ライバル始動⑤
雲平は、久しく顔を合わせていない石橋徳次郎に会いたくなった。モトの街中情報では、最近徳次郎が隠居生活に入ったとも聞いている。自分より10歳も若い者が隠居とは信じられないことだ。牛鍋屋の暖簾を潜ると、山田平四郎に呼び出された徳次郎が、奥まった座敷に収まっていた。
「隠居したち聞いたばってん。嘘やろう、その若さで隠居てん・・・」
話のきっかけを予想していたのか、徳次郎も落ち着いている。
「本当ですばい、隠居の話は。次男坊(正二郎)が、商業学校ば卒業したもんで」
「息子の卒業と徳次郎さんの隠居は、関係なかでしょうもん」
「わしはもともと体に自信がなかったし。それに、男の子が2人で商売ばやるのに、親爺がそばにおったらやり難かでしょうし」
徳次郎の話の端々に、澱みを感じる。
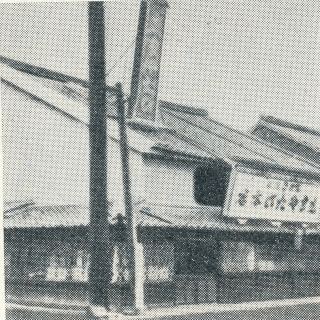 写真:明治期の志まやたび荘島工場 写真:明治期の志まやたび荘島工場
「今になって悔んどるんかい、息子に仕事場ば譲ったこと」
平四郎が、追加の料理を運んできて、そのまま座り込んだ。
「実は、そげんですよ。今の若か奴はとんでもなかことばしでかすからですよ。それも、わしには何の相談もせんで」
「どげなこつな、それは」
「これまで、弟子らと一緒に作ってきた印半纏とか脚絆とか。頼まれものの仕立物まで、みんなやめてしもうて」
平四郎と徳次郎の会話を、鍋をつつきながら聞くだけだった雲平が、顔をあげた。
「仕立物は嶋屋の看板じゃなかったかい。そればやめて、これから先何を」
「足袋だけにするち言うとです。それだけじゃありまっせん。店の屋号まで替えよって」
「嶋屋ばやめて、今度は何て」
「同じ『しまや』でも、看板の字ば『志まや』にするとげな」
雲平にとって、漢字の「槌屋足袋」を平仮名の「つちやたび」に改めたのは、徳次郎が「嶋屋足袋」の名前で売りだしたための避難措置であった。それだけに、「嶋屋足袋」が「志まやたび」に替ることは他人事ではない。
「これも、時代の流ればいのう」
平四郎が、雲平の気持ちも知らずに呟いて、キセルの雁首から刻みたばこをたたき落とした。
「冗談じゃなかですよ。せっかく嶋屋ばここまで大きゅうしてきたのに、一夜にしてどんでん返しされたとですけん。その上...」
「まだあるんかい」
雲平も、ライバルの変わりようを理解しようと懸命である。
「そうなんですよ。正二郎の奴、今度は雇っておる10人の弟子に、給金ば払うち言いだしましてね。その方が連中の働く意欲が湧くとか言いおって」
従業員の待遇改善は、川上らとの会話でもよく聞かされていることである。
「考えてもみて下さいよ。弟子には仕事ば教えてやって、その上にただで飯ば食わせる。その代わり、働いた分の報酬は無しというのが、徳川さま以来の決めごとでしょうが。それなのに、弟子たちに給金ば払うたりしたら、店の儲けはのうなってしまいますが。分かりますでしょう、つちやさん」
平四郎も雲平も、徳次郎の泣き言ともとれる打ち明け話に、応えようがなかった。
「話は変わるばってん」
山田平四郎が、一気に話題を転換した。
「町の中の馬車鉄道が、馬の代わりに、石油で動くごとなるげな。これでちょっとは糞の臭いから逃げられるかな」
噂には聞いていたが、山田が言えば本当のことだろう。この間に、息子のことで興奮気味だった徳次郎が、落ち着きを取り戻して、牛鍋に向かい直した。
「それだけじゃなかばい。今度は家の中まで電線が張られて、どこの家でん電灯がつくごとなるらしか」
久留米の人間にとって、待望のローソクから解放される時代が目前だというのだ。情報博士を自認する平四郎の話はその後も続いた。
大切な人⑥
明治も40年代に入ると、久留米の郵便局には電話交換台が設置された。居ながらにして、日本全国どことでも通話ができるようになったのである。もっと凄いことは、市内に電信柱が立ち並び、家庭や工場などへの送電が始まったことだ。つちやたびの白山工場にも電灯が灯り、染色・漂白の工程で、夜間も作業が出来るようになった。
米屋町の事務所で雲平が寛いでいるとき、年配の女が入ってきた。
「相変わらずの、ご繁盛ですね」
小川トクである。久しく会わない間に、頭に白いものが目立つようになっている。
「私も来年には古希を迎えますからね。歳はとりたくないわね、最近ではもの忘れがひどくて。それに、はた織りをしていても、細かいことがまったく出来なくなったわ」
小川トクは、40年前に遠い武蔵国からやってきたはた織り女である。雲平が足袋屋を開業した直後に、新廓町で機屋を始めた。トクを雲平に引き合わせたのは、時計屋の末吉であった。
.gif) 写真:小川トクの生前墓(久留米梅林寺) 写真:小川トクの生前墓(久留米梅林寺)
「末吉さんも、亡くなってしまったしね。それに...」
「何だい、トクさん」
「弟子たちが、こともあろうに、有馬さまの菩提寺(梅林寺)に墓まで建ててくれましてね」
「墓って、誰の?」
「私のですよ。何でも生きているうちに墓を持つと長生きするとかで。断ったんだけどね、半分強引に建てられちゃった」
彼女の流暢な江戸弁は、40年たっても健在である。
「俺に何か用があって来たんだろう、トクさん」
雲平が尋ねた。
「七十を目の前にしてね、里心がついてしまったのよ、私。だから...」
「まさか?」
「そうなの。実家に残してきた息子が、帰ってこいって。事業に成功して、大きな家も建てたからって。私が家を出るときには、まだ乳飲み子だったのにね。今さら母親でございなんて言えた義理じゃないんだけどさ。やっぱりね、死ぬ間際くらいは息子や孫に囲まれていたいじゃない」
雲平も、間もなく還暦を迎える身である。
「淋しかなあ。トクさんだけは、死ぬまで久留米におると思うておったのに」
小川トクが帰ってからすぐだった。事務所の電話が鳴り響いた。
「博多の達磨屋の番頭でございます」
甚兵衛の店からであった。
「甚兵衛さんが、どうかしたんかい」
不吉な予感が雲平の脳裏をかすめた。
「いえ、急ぐことじゃありませんがね。主人も近頃は寝ていることが多いもんで」
「それで...」
「雲平さんに会いたかち言うとるとです」
1年前だったか、店の近くに構える屋敷を訪ねたことがある。その時甚兵衛は、「もう八十ですばい」と言って苦笑いをしていた。
雲平は、胸騒ぎを抑えきれず、急ぎ博多行きの汽車に乗った。
「よう来たない」
甚兵衛は、床の上に起き上って雲平を迎えた。
「顔の色がよかですね」
番頭から「寝ていることが多い」と聞いて、正直もっと老けこんでいるのかと思っていた。
「そろそろ、鴨たちも北の国に帰る支度ば始めた」
甚兵衛は、庭の池で羽繕いを怠らない鴨のつがいを眺めたままでいる。周りの楓や柳が、今にも芽を吹き出しそう。
「わしはな、こう見えても鴨と話ができる名人なんじゃ。あいつらと話をしとると、その内の1羽が、どうしてか雲平に早変わりばするんじゃ。長崎に修行に出かけるときじゃったない、お前と初めて会うたのは」
庭を眺めながら、甚兵衛の気持ちは宙を泳いでいるように見える。
「そうでした、あの時甚兵衛さんに会うてなかったら、今の俺もなかったでしょうけん」
どうしてこんなことを喋っているのか、自分でも不思議な感覚であった。
やっぱり半物⑦
「ところで...」
甚兵衛は、改めて寝巻の襟を正した。
「わしがあの時、雲平という青年に興味を持ったのはなぜだか分かるか」
40年もむかしのことを、突然問われても答えようがない。
「それは、町の世話役さんから俺のことば頼まれたとか」
「それだけで、一度も会ったことのなか若造の面倒ばみるもんか」
「・・・・・・」
「それはな...。お前がわしに喋った『足袋作りは自分の天職ち思うとります』と言うた一言たい。あの時の雲平の目はキラキラ光っておった」
「それで、俺の面倒ばみてくれたとですか」
「それだけじゃなか。お前はあの時、俺は人がやりたがらん半物職人になるちも」
「そげなことば言いましたか」
そこに、茶を運んできた女中が、「寒くなりますけん」と、障子を閉めにかかった。
「待て、もう少し開けといてくれ。わしはどうも、鴨が見えとらんと、話がし辛うて」
座敷に入ってきた時より、池の鴨の数が増えている。彼らは、女中が投げ出す米粒を、順序よく食べに来る。一羽が食べ終わると、待っている次の鴨に席を譲って池に戻る。その繰り返しが面白くて、雲平もそちらに気をとられがちになる。
「ところで、雲平」
呼ばれて、雲平が甚兵衛に向かいあった。
「お前は、天職と思うて始めた足袋作りば、今もやり通しておるか」
「何度か、足ば踏み外しそうになりましたばってん。何とか堪えております」
「それで、これからも足袋作りは続けるのか」
「足袋作りは、人間の手から機械に代わってしまいました。ばってん、人が足袋ば履くうちは、ずっと作り続けようち思うとります」
「大きか工場ば建てて、人もいっぱい雇うとるそうじゃなかか」
「職工は2千人もおります。工場だけじゃのうて、町の奥さん方や田舎の母ちゃんたちにも、足袋底の縫いつけばやってもらよります。型紙づくりも売り込みも、金の計算も、みんな従業員がやるようになりました」
「それじゃ、雲平もモトちゃんも出る幕がのうなったちいうわけか」
「違うとです。店が大きゅうなった分、働いとる連中とその女房子供たちにも飯ば食わせにゃならんとです。俺が足袋作りば続けんと、皆んな飢え死にしなきゃならんけんですね。やっぱり、半物職人から足ば洗えんごとなっとります」
話しをしていて無性に喉が渇く。またしても、激しい羽音を残して、つがいの鴨が飛び立った。
「鴨たちは、寒かうちはここに来て、温うなったら北の国に帰る。毎年同じ苦労ば繰り返しながら歳ばとっていくとたいね。人間も同じだ。死ぬ間際まで、毎日毎日同じことば繰り返しておる」
甚兵衛が言おうとしていることが、雲平には少しずつ分かってきたような気がする。
「もう一度、雲平と一緒に長崎に行きたかな。長崎でしか話せんことや、雲平から聞きたかこつもある気がする」
別れ際の、甚兵衛の一言であった。
|