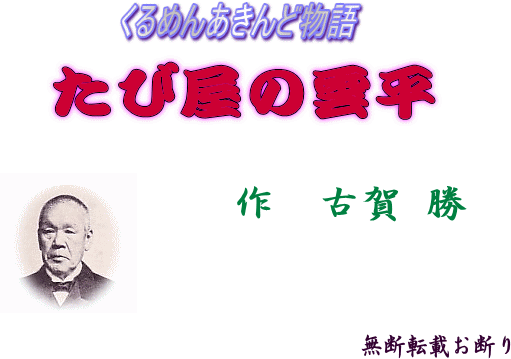
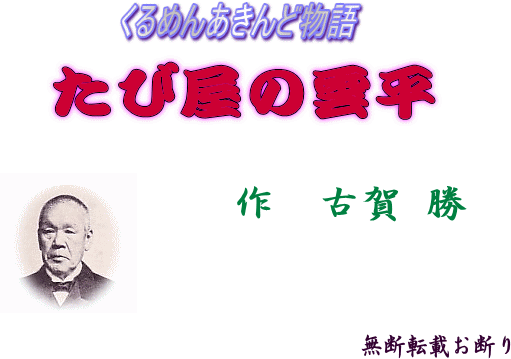
| 終章 長崎本線の旅 |
| 雲平とモトは、列車に乗りこんで長崎に向かっていた。汽車は佐賀駅を過ぎて、収穫には間がある佐賀平野を、黒煙を棚引かせながらのんびり走っている。明治43年(1910年)の初秋であった。 「あの時は、山坂越えて歩くしかなかったもんな」 雲平は、40年前に、足袋作りの修業に出た時のことを思い出していた。 「私だって、江戸から久留米に来る時は、歩くか駕籠に揺られるしかなかったですよ」 夫婦は、明治維新以後の人の暮らしの変化に、今さらながら驚いている。武雄駅を過ぎたところで、モトが風呂敷に包んだ弁当をとりだした。 「一度食べたかったんですよ、駅で売っている弁当を」 モトは、長崎本線に乗り換える際、鳥栖駅のホームの中央軒売店で弁当を買いこんだ。おにぎりに煮しめと沢庵が添えられているだけの簡単なもの。価格は15銭だった。 .gif) 写真:昔ながらの鳥栖駅ホーム 写真:昔ながらの鳥栖駅ホーム「おいしいですね」と、モトが悦にいっている。 早岐駅を過ぎてしばらく行くと、右手に大村湾が見えて来た。モトは、曇り空の下の海を見つめたままである。 博多と久留米間に鉄道が開通したのは明治21年だった。あれから20年が経過して、今では九州中に鉄道網が張り巡らされている。雲平夫婦が乗っている長崎本線の開通は明治31年(1898年)で、長崎での大勝負に出る4年前のことだった。この時分の長崎本線は、鳥栖を出て早岐で左折して大村湾沿いを走っていた。 「俺たちが、汗水たらして働いとる間に、世の中も変わってしもうたない」 雲平も、視線を大村湾に向けた。 「初めてですね、あなたさんと2人して家を開けるのは」 「そうだな。一度くらいは、こんなこともあってよかじゃろ。それに、長崎おくんちばぜひモトに見せたかったけん」 列車は各駅に停車しながらゆっくりと進んでいく。 「この分だと、長崎に着く頃には陽が落ちてしまうかもしれませんね」 「大丈夫だよ、むこうには稲益旅館がある」 妻の心細さを解消しようと、雲平が慰めた。 「あなたさんが、私を長崎に連れて行こうとおっしゃったときは、正直びっくりしましたよ。だって、一度だってそんなことなかったですから」 「機会がなかっただけたい」 「あなたさんも金蔵も、川上までもが長崎のことを話題にする時、私だけがのけ者にされてるようで淋しかったわ。それだけに、嬉しかったですよ、今回は」 .gif) 写真:大村湾沿いを走る大村線(当時の長崎本線) 写真:大村湾沿いを走る大村線(当時の長崎本線)長崎で大勝負をかけた時は、そばにいるモトの気持ちを察する余裕などなかった。 「あなたさんのところに嫁に来て、大方35年になりますね。先ほどは還暦を迎えて、子供たちに赤いちゃんちゃんこを着せてもらいました。金蔵には男の子が出来ましたしね。泰蔵の嫁も間もなくでしょうし」 「だから、何だ」 改めて、問い直されると、モトは次の言葉を発しない。 「博多の達磨屋さんも、あなたさんが見舞ったすぐ後に亡くなられました」 話があっちに飛んだりこっちに跳ねたり。2人の会話を聞いている人がいれば、おかしな夫婦に見えることだろう。 雲平が甚兵衛の死を知ったときは、全身から力が抜けてしまった。甚兵衛は見舞いを終えた帰り際に、「もう一度、長崎に行きたかな、雲平といっしょに。その時は、聞きたいこともあるし。俺の方から言いたかこともある」と言った。そのことがずっと雲平の頭から離れなくなっている。 「甚兵衛さんは長崎で、何を話したかったんじゃろうな」 雲が切れたのか、大村湾の水面の青さが眩しい。 「甚兵衛さん、雲平がもうすぐ長崎に着きますよ。勝手に遠くへ行かないで、待っていてくださいな」 モトが、海に向かって呟くように呼びかけた。そのとき雲平は、心地よさそうにいびきをかいていた。 「何か言ったか。せっかく眠っとるのに」 「何も言いませんよ。独り言ですよ」 汽車は諫早の駅に停車した。ホームでは、紺無地の半纏を着て、赤い鳥打帽を被った弁当売りが声を張り上げている。モトが窓を押し上げて、売り子を手招きした。 「お茶を2つ下さいな」 雲平は、停車中の車窓から宿場町の景色を見つめたままである。 「天職ちは、いったいどげなもんかのう」 夢でも見ていたのか、雲平が意味不明のことを言い出した。 「あなたさんの足袋作りのことですか」 「ああ、若い時に始めた半物作りのことたい。俺は全うしとるじゃろか。この頃、そげなことば考えとる」 「私はね...」 モトは、言いかけた言葉を、お茶といっしょに飲み込んだ。 「天がくれた仕事なら、俺はもうちょっとはしっかりした職人になっとるはずたい」 「違いますよ、あなたさん」 「何が?」 「あなたさんは、天から足袋職人の道をいただいたのではありませんよ。自分から出かけて行って手にしたのです」 「天まで出かけてかい」 「さあ」 モトは、夫が訊き直したことには答えないで、また目を窓の外に向けた。列車は町をぬけて、山が重なる地帯を走っている。トンネルに入る度に、機関車が吐き出す煙が客車内に充満して息苦しい。 「これだと信じて始めた仕事でも、うまくいかないことだってありますよ。でも、あなたさんは、失敗を重ねても挫けなかった。足袋を履いてくれる人が、より履きやすいように工夫を重ねなさった。その結果が、よい跡継ぎにも恵まれることに繋がったとは思いませんか」 「金蔵や泰蔵のことかい」 「あの子らも、一生懸命あなたさんの足袋作りの精神を受け継ごうとしています。でも、跡継ぎは子供だけじゃありませんよ。川上支配人だって吉村や慶之助だって、皆んな必死でつちやたびを盛りたててくれますから。後から入ってきた人たちも、あなたさんの仕事に役立つよう研さんを重ねているじゃありませんか」 「いやいや、あれもこれも、モトに背中を押されてやってきたようなもんだ」 「そんなことはありませんよ。私はただ、あなたさんのお仕事をお手伝いしたかっただけですから」 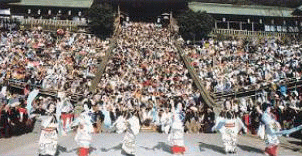 次の会話までに、しばらく間があった。 「そうか、人間か。モトが言う通り、家も会社も皆んな人で成り立っとるもんな。そう考えれば、俺の天職ちいうもんも、山あり河ありの人間臭いもんだったな」 夫婦しての含み笑いが、長い時間続いた。 「卯之助と嘉助には、長崎に行くち言わないで出てきたない」 雲平が慌て声を発した。 「大丈夫ですよ、私が伝えておきましたから」 「それはよかった。そろそろ、終点の長崎だ。忘れもんのなかごとない」 「分かっていますよ。それより、あちらに着いた後、私をおくんち見物に連れていくことを忘れないでくださいな」 完 |


