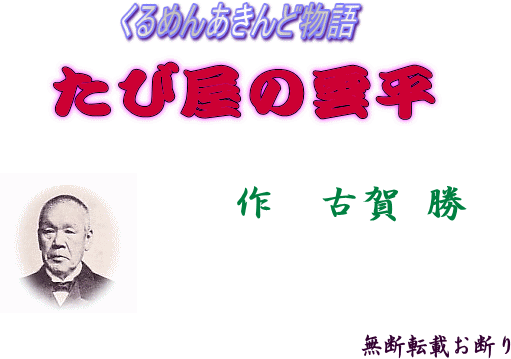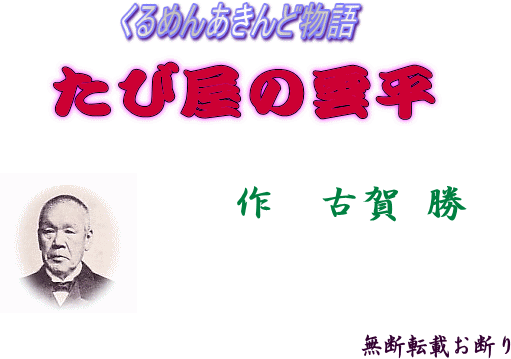|

変貌する城下町 (01)
2年半の修業を終えて久留米に帰ってきた倉田雲平。留守の間に、町はすっかり様変わりしていた。武士らしい人影は少なくなり、ねじり鉢巻きや前掛け姿の商人が目につく。お城の大手門が解放され、町民でもお堀の内から城下を見下ろすことができるようになった。点在していた広大な家老屋敷も、1軒また1軒と取り壊されている。
久留米藩が「久留米県」に替り、その後藩主の有馬頼咸は、家族ともども東京に移住した。
「商人になりたがっとるお侍さんも大勢おいでだ」
兄の清左衛門が、久留米の町の変わりようを教えてくれた。
「そうそう、この頃では、夜店で客呼びばしとるお侍さんもおらすげな」
母マチも、末っ子が帰郷するのを待っていて、久留米の変わりようを手ぶり身ぶりで話して聞かせた。
「ぐずぐずしとると、世の中に置いていかれそう」と、長崎で語った山田平四郎の言葉が現実味を帯びてくる。
修行を終えても、母と兄を頼るしかない自分が腹立たしかった。とりあえずは、修業前と同じように、実家の2階を間借りして、足袋の製造を始めることにした。
長崎に旅立つ前とは、倉田家の事情も一変している。姉のノブが嫁にいき、兄の清左衛門夫婦には長男が誕生した。そうなると、義姉(長兄の嫁)の立場は格段と強化された。寄る年波か、母マチには以前のような覇気が感じられない。
久留米に落ち着くと、すぐに嘉助を訪ねた。嘉助は、父親から「青々館」を任され、嫁ももらって、すっかり旅館の主人に収まっていた。
「よう頑張ったない」
嘉助は、嫁のミヨを紹介すると、すぐに雲平と2人だけの会話に戻った。変わることのない、無二の親友なのである。
「久留米も変わってしもうたない。びっくりした」
雲平が嘉助に向けた第一声である。
「ずっとここに居る者でも、びっくりするくらいじゃけん。ご維新とは、都から遠く離れたこげなところの暮らし様まで変えてしまう」
激しく移り行く我が町に、ついていくのも大変だと嘉助が嘆いてみせた。
「高良山の御井寺とか五穀神社の円通寺(神宮寺)さんも、とうとう姿ば消しなさった。坊さんは皆んな神主さんにならした」
2人は、ミヨに出された茶を啜りながら、感慨にふけっている。
「ところで、長崎はどげんじゃったね。赤毛の大男がうようよしとるち聞いたばってん。キリシタンへの取り締まりもあっとるじゃろ」
嘉助は、自分が久留米の変わり様を語るよりも、雲平からのみやげ話を聞きたがっている。
「むかしから、幕府はキリシタンば好かんじゃったけんな。新しか政府も、やっぱりキリスト教は好きじゃなかごたるない」
「なしてやろう?」
「日本が神さんの国じゃけんたい」
雲平は、嘉助を原古賀の牛鍋屋に誘った。長崎で知り合った山田平四郎のことを思い出したからである。町中を横切る池町川を越えて、新旧店舗が並ぶ三本松から苧扱川町(おこんがわまち)へ。その先の原古賀に牛鍋屋はあった。
前掛け姿の山田がでてきて、大袈裟過ぎる仕草で雲平の来店を歓迎した。
「隣で豚とか牛の肉ば売っとったろう。あれも俺の店たい。近かうちに、西洋料理店も始めるつもり」
 写真:現在の原古賀町 写真:現在の原古賀町
維新以後、失業武士対策に苦慮している新政府だが、山田は当局のお世話になる前に、既に商人の仲間入りを果たしていた。
「雲平しゃんが足袋屋ば始むるのはよかばってん、腕だけじゃ大変ばい」
鍋の匂いが最高潮に達する頃、嘉助が切りだした。
「どういうことか、腕だけじゃいかんちは」
親友の進言に、つい剥きになる雲平である。
「いくらよか足袋ば作っても、それが売れんことには商いにはならん。それに、足袋ば1足作るにも、材料から買わなきゃならんし」
「それなら心配なか。長崎の親方から貰うた餞別が、1円50銭は残っとるけん」
「それくらいじゃ、何足分の材料も買えん。それに、雲平しゃん自身も食うていかなきゃならんし」
「なあに、何とかなるたい」
「呑気なもんたいね、雲平しゃんは。俺もできるだけ加勢ばするけん」
嘉助は、牛鍋をつつきながら、商いの手始めとして、「まず試作品を作れ」と進言した。
試作品 (02)
牛鍋屋を出た嘉助は、雲平を青々館に誘い込み、女房のミヨと仲居のトミ子に雲平の商いを手伝うよう言いつけた。
早速雲平は、トミ子の足を計ることになった。長崎では来店した客の足を気軽に計っていたものだが、いざとなると、思考も手先も思うように動いてくれない。
「9文半(22.5㌢)でよかですかね?」
三十台半ばのトミ子は、着物の裾を整えながら首を大きく振った。.gif) 写真:往時の青々館(青々館ご子孫提供) 写真:往時の青々館(青々館ご子孫提供)
「そげん(そんなに)うちの足は大きゅうなかもんの。この前足袋屋で買うたときは、9文3分(22.0㌢)で丁度よかったもん」
計り直したが、やっぱり9文半と違わない。
「申し訳なかばってん、とりあえずこれで作らせてくれんですか。うまくでけたら、ただで進呈するけん」
近所の布屋から、表生地と裏生地、それに底生地用の材料を買ってきた。トミ子の足裏に合わせて型紙を作り、親方に貰った裁鋏で裁断する。生地の表・裏を確認しながら、甲の部分に鉤を縫いつけた。底生地と表生地を縫い合わせると後は仕上げ。長崎で修業してきた段取りを思い出しながら、1足の白足袋を作り上げた。
「ダブダブたい、こりゃ。ごげな足袋ば履いてお座敷に出らるるもんか」
トミ子の恨めしげな眼が、雲平の自尊心を打ち砕く。
「ここからが雲平しゃんの勝負どころたい」
友人が受けた衝撃を、他人事のように見ている嘉助である。作業場に戻ると、また一からのやり直し。青々館のトミ子だけではなく、母親と兄嫁にも試作台になってもらったが、結果は二人ともトミ子と同じく「ダブダブ」。計り方が間違いかと何度も確かめてみるが、結果は変わらなかった。
こんなところでぐずぐずしていたら、親方から貰った餞別金も底をついてしまう。何をどこで間違えているのか、雲平の長考が続いた。
「わかった!」
雲平の絶叫に驚いたマチが、階下から上がってきた。
「どげんしたと?」
母の問いかけには答えず、雲平は改めて自分の足裏を計ってみた。
「兄弟子から習うたことば忘れとった」
長崎の作業場では、深く考えることもなく言われるままに布を裁断していた。これからは、裁断から縫いつけまで、すべての工程を一人でこなさなければならない。張り切り過ぎて、親方や兄弟子からの大切な教えすら忘れてしまうところだった。
「親方は、寸法のことで何と?」
独り言をつぶやく息子が気になるマチである。
「計った文数より、一目盛り小そう裁断しなきゃならんかった」
「そげなもんかね」
「そげなもんたい。新品の布は目が詰まっとるけん、きつう感じるくらいが丁度よかち。履きよるうちにゆるうなってくると。母ちゃんの足裏は9文7分じゃったけん、9文半くらいで計算ばしとると丁度よか」
改めてマチの足裏に尺を当てる。
「これで、よかばい」
母親の次は青々館に。改めてトミ子の足裏を計るためである。
「そうじゃろ、うちの足は9文半もありますもんか。9文3分で丁度よかはずたい」
写真:当時つちやたびの見本
本人が言うとおり、「9文3分」で作り直すと、確かに爪先から踵まで、それに足甲の幅までぴったりである。それでもトミ子は納得した顔を見せない。
「うちの商売は、食事を座敷に運んだり、たまには三味線を弾いたりしてお客さんば喜ばせることですもんの。顔なんかどげんでもよかと。立ったり座ったり、目の前を歩いたりする時、お客さんの目はどうしてもうちの足元に向きまっしょうが。それにしては、この足袋は何ともしょぼくれとる(くたびれている)の。それに、寸法は合っとっても、何か気色(気持ち)の悪か」
どうだったらトミ子から合格がもらえるか、不安は増すばかりである。
「お座敷足袋は、全部縫い終わってからが本番たい」
長崎で、兄弟子の国松が言っていたことを思い出した。縫い終わって、更に木型に入れ込む、それから辛抱強く縫い目を叩く。そうすることで、縫い目や粗い布地が甲に食い込むのを和らげてくれる。
親方や兄弟子から指導を受ける際、深く考えてこなかったつけが、今ここに来てのしかかっていた。
頼母子講(03)
何度目かの試作で、ようやくトミ子から合格をもらった雲平。もう失敗は許されない。気がつけば、親方から貰った餞別金も半分近くがなくなっている。材料を買うにも心細さが先に立つようになった。
嘉助が資金援助を申し出たが、「やせ我慢たい」と言い訳をしながら断った。有り金を計算しながら生地布を買い、9文3分と9文半、それに9文7分(23.0㌢)の白足袋を製作して、青々館に持ち込んだ。トミ子が仲居仲間や出入りの芸者に売り込んでくれて、次の材料を仕入れることができた。作業時間も短縮し、次第に客の評判もよくなっていった。
青々館から戻ると、兄の清左衛門が待っていた。
「1日に3足とか4足くらいの足袋作りじゃ、男の商いちは言えん」
兄は、弟の堅過ぎる頭の構造を替えなければと思っている。
「ばってん俺は、親方に言われたことば守りたか。履く人が満足する足袋ば作るためには、そげん余計は作れん」
「それじゃ、先が思いやられるとたい。1日に50足とか、100足くらいは作って売らにゃない」
「夢のごたるこつば言わんでよ。その内に、10足くらいは作れるごとなるけん」
兄に対して口答えしながら、自分の言っていることの程度の低さに嫌気がさしている。
「よかことば教えるたい。頼母子講(たのもしこう)に入らんか」
突然「頼母子講」と言われても、雲平には何の事だかさっぱりわからない。
頼母子講とは、江戸時代から庶民の間で金銭を融通し合う仕組みのことである。発起人に金を預け、くじ引きで当たったものが受け取る。「伊勢講」などは、当選した者がお伊勢参りの費用に充てた。
「講に入るのはよかばってん、商いとどげな関係があると?」
「先日の講で、俺がくじば当てたとたい。50円入ったけん、それば雲平の商いの元手にしたらよか。そうすりゃ、5足とか10足とか、ケチなことば言わんでもよかろうが」
「ばってん、これ以上兄しゃんに迷惑ばかけるわけにはいかん」
「ただで金ばやるとじゃなか。貸すとたい」
清左衛門が言うには、頼母子講で当籤した50円を雲平に貸し付ける。その代わりに、雲平も講に加入して、毎月1円50銭の掛け金を払う。その内に雲平がくじを引き当てたとき、50円を清左衛門に返すということであった。
米1俵(60キロ)が2円の時代である。50円といえば、これまで手にしたことのない大金である。ある資料では、当時の1円が現在の7千円に相当するとか。その計算でいけば、兄から受けた50円は、現在の35万円程度か。
ここは遠慮せずに兄の申し出を受けることにした。大量生産のための材料と必要な道具が揃えば、あとは身体の限界まで働けばよい。
雲平は急ぎ旅支度を整え、空の荷車を牽いて博多に向かった。10里あまりの道のりだが、夕刻前には博多に着いた。甚兵衛が経営する達磨屋は、賑やかな櫛田神社の参道にあった。間口はそんなに広くないが、奥行きは相当ありそう。上がり縁に派手な女用の紋入り訪問着が飾られているだけの典型的な卸問屋であった。売り物の呉服から小物まで、所狭しと商品が積み上げられている。注文を受けた店員が、要領よく品物を見つけると、間をおかずに客の前に並べる。素人には見当もつかない暗号を駆使した取引が進んでいった。
「よう来たない。こんなに早う会えるとはな」
昨日長門から帰ったばかりだと言う甚兵衛が、雲平を歓迎した。長崎で分かれた後の修行の様子は、その都度小川源助から聞いていたらしく、「そろそろ現れる頃かと待っておった」と言って笑った。
「そうか、50円分の生地ば揃えろてか。鋏も親方がくれた一つだけじゃ、心細かない」
甚兵衛が、注文以上のことを勝手に並べるので、懐具合を考えて落ち着かなかった。
「金のことなら心配するな。雲平の門出の祝いだ。おっちゃんがくれてやる」
「そげんに甘えてばかりじゃ」
実は、小道具を揃えるのに、どのくらいの資金を要するものか、まったく分かっていなかったのである。
「材料とか資金とか、足りんごとなったらいつでも言ってきんしゃい」
独特の博多弁でまくしたてられ、力いっぱい両肩を叩かれた。3日間博多に滞留してる間に、品物は揃った。待つ間、街を見て回った。博多は、久留米と比べて通行人が多い。それに、祇園町から呉服町、更に千代町にかけて、各種専門の店先の賑やかなこと。大むかしからの、博多商人の底知れぬ商いの大きさを見せつけられる思いであった。
写真:戦前の櫛田神社界隈(博多ふるさと館展示)
生地や道具を荷車いっぱいに積んでいるが、久留米までの間まったく重さを感じなかった。
達磨屋から帰った雲平は、荷車に荷物を積んだまま、作業場で仰向けになった。目をつぶって思うことは、出来上がった足袋の山にほくそ笑んでいる自分であった。その先に、最も危険な落とし穴が待ちうけていようとは・・・。
落とし穴(04)
旅の疲れも重なって、雲平は深い眠りの中にいた。
「ウンペイ、ウンペイ」
背中から、母の呼ぶ声が聞こえる。
「ゆんべ遅かったけん、もうちょっと寝かしといて」
再び眠りこもうとするところを、顔面に母の平手が飛んだ。
「博多から帰ってきて、車力は何処に置いたと?」
「土間にあろうもん」
「それが、どこにもなかとたい」
マチの一言で、雲平の眠気が覚めた。博多から牽いてきたはずの車が土間にない。
「そげなはずはなか。暗うなって帰ってきて、車力は確かに家の中に入れた」
「玄関の突っ張り棒は、ちゃんとはめたね」
「あんまり眠かったもんで、...」
「それで、巾着は?」
「持っていった銭は達磨屋さんに払うてきたけん、いくらも残っとらん」
大風呂敷5枚に詰め込んだ木綿布と、甚兵衛が開店祝いにとくれた小道具が、車力ごと盗まれていた。
今さら、「材料の生地ば盗られました」と、甚兵衛に泣きつくわけにもいかない。無駄を承知で、世話役の傘屋に被害届を出した。
「番所の方には、わしの方から言っておくばってん。こげな世の中じゃけん、盗られたもんがまだ久留米にあるとも思えんし...」
達磨屋から買いつけた表生地用の木綿と裏生地に使うさらし、それに刺子を施す底生地がごっそり盗られてしまった。残ったのは、兄から借りた50円の借金のみである。
「とんだ落とし穴じゃったない。ばってん起こってしもうたことはしよんなか(仕方ない)。また一から出直すしか...」
肩を落とす雲平を、嘉助が慰めた。
「頼母子講のことはもう忘れろ。雲平しゃんは、やっぱり自分で稼いだ銭で材料ば買うやり方の方が似合うとる。長崎から帰った時と違うて、もう試し作りは必要なかけん。うちの旅館に出入りする芸者だけじゃのうて、よその料理屋のもんにも紹介するたい」
博多の甚兵衛には世話役を通じて事実を報告し、再び細工町の布屋から10足分の材料を仕入れた。今度も9文3分・9文半・9文7分の3種類のお座敷足袋から始めることにした。こんな非常事態においても、客には出来上がった品を試しに履いてもらって、ぴったり気に入った時だけ買ってもらう方式を貫いた。
屋号(05)
仕切り直しの足袋作りと販売は曲がりなりにも走りだした。「雲平さんの作る足袋は、ほんに履き(心地の)よかもんの」と、検番からまとめて注文がくるようになった。
「いつまでも雲平さんじゃおかしか」
突然の嘉助の話題変更に雲平が戸惑った。
「俺の名前は雲平じゃけん、雲平さんでよかろうもん」
「雲平はお前の名前たい。店には、それなりの屋号ばつけんといかん。うちの仲居も検番のおなご衆も、お前のことば雲平さんち言うじゃろう。それが当たり前になると、雲平さんが店の名前になってしまうが」
嘉助に言われるまで、考えたこともなかったことである。
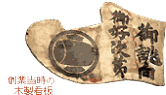
「それもそうじゃな。屋号ね。うちには先祖代々の屋号があるばってん。今母ちゃんがやっとる駄菓子屋も屋号は槌屋じゃけん」
先祖から続く倉田家の屋号である「槌屋」は、今も途絶えてはいない。
「俺の店に屋号をつけるなら、やっぱり『槌屋』しかなかない。『槌屋足袋店』でどげんかな」
「それでよかばい。雲平しゃんが作る足袋の名前は『槌屋足袋』ということにして」
帰るなり、母と兄に相談した。雲平が槌屋の屋号を使うことに異論はでなかった。
「3軒先の小間物屋さんが、店を畳みなさるげな」
マチが何を言おうとしていることを、清左衛門が繋いだ。
「あの店なら隣どうしじゃけん。何かと便利ばい」
「そう言われても、この前の泥棒騒ぎで、懐はすっからかんたい。やっと10足、20足の商いでは、家ば借りることなんぞ難しか」
現実離れした話にはついていけそうにないと、雲平は興味を示さなかった。清左衛門は、なんとか雲平に、自分の店を持たせようと考えている。
「家主さんは、敷金ば15円に負けとくち言いよらした。そこでこの前、定七と清兵衛にも相談したら、この際、兄弟で弟の商いば応援しようちいうことになったとたい。兄弟で出し合えば、15円くらいは何とかなるじゃろう」
何のことはない。話は本人が知らないところでどんどん進んでいたのだった。この調子だと、既に敷金も払い込まれているかもしれない。定七と清兵衛は、2番目と3番目の兄である。
大工が時計屋に(06 )
倉田雲平が長崎から帰ってきた明治5年も暮れようとしている。やがて来る明治6年は、雲平にとっても久留米の商人にとっても、歴史的に大変重要な年となる。
明治政府は、この年から、それまでの太陰暦(旧暦)を太陽暦(新暦)に替えることを定めた。つまり、明治5年(1873年)12月3日を明治6年1月1日として、新しい暦がスタートするのである。
嘉助と連れだって原古賀の牛鍋屋に出向いた。木々の紅葉もそろそろ落ち始めた頃である。
「ほら、向うに1人で鍋ばつついとる男がおるじゃろう。あいつも今度苧扱川筋に新しか店ば出すとげな」
同席している亭主の山田平四郎が囁いた。
「何の店ば出しなさると?」
雲平も、自分と同じ志を持って商いを開始しようとする男に興味が湧いた。
「西洋の時計ば売るらしか。こっちに座らせようかね」
間もなく現れた男は、雲平と同様、未練がましくちょんまげをいただいたままの町民である。歳の頃は雲平と変わらない。男は、「宗野末吉」と名乗った。末吉は、維新前までお城に出入りする大工の棟梁だったと言う。
「そんなに若うて棟梁かい」
嘉助が驚き顔で質した。
 写真:宗野末吉(宗野時計店提供) 写真:宗野末吉(宗野時計店提供)
「棟梁ちいうても、ご先祖さまから引き継いだもんで」
「その大工の棟梁が、どうして時計屋に?」
「いろいろあってな」
「いろいろって?」
宗野末吉への興味は、嘉助の方が雲平を上回っている。
「ある時、お殿さまに呼ばれて」
「へえ、お城におられるお殿さまに?」
「有馬の殿さまは、誰よりも新しかもんば好いとられるけん。維新前には西洋から渡ってきた時計ば手に入れられたりして」
「時計ね。西洋時計ちいうもんは見たこともなか」
「俺が、ちょっとばかり手先が器用かちいうことで、時計がうまいこと動かんとすぐ呼びだされるとたい。その内に、参勤交代にまで付きあわされて」
「江戸にも、行ったんかい」
「仕方なかもんない、お殿さまの言いつけじゃけん」
大工が時計屋に化ける経過が面白くて、嘉助も雲平も、身を乗り出して聞き入った。
末吉は、明治維新直前の慶応2年に、参勤交代の行列に加わっている。表向きの仕事は、江戸屋敷内の補修ということになっているが、実は殿さまの道楽の相手だった。
時は、徳川幕府の終焉を間近にした激動の中にあった。最後の将軍となる徳川慶喜の就任に合わせたかのように、倒幕を目的とした薩長連合が成立する。そして、ついに慶喜による大政奉還へとことは激変していった。(慶応3年10月14日)
末吉が江戸滞在中に、「江戸」が「東京」へと名前を替えた。この時期は、坂本竜馬と中岡慎太郎が暗殺されたこととも重なる。
久留米藩主の有馬頼咸は、江戸の屋敷に常駐する藩士とその家族に、久留米への帰還を命じた。屋敷内が右往左往する中で、藩主は宗野末吉にも「すぐに屋敷を去れ」と命じた。行き先は、横浜の時計屋だった。そこで西洋時計を修理する技術を磨いて、再び頼咸の元に戻ってくるよう約束させられた。
「それが、大工の棟梁から時計屋に変身するきっかけかい」
嘉助が、腕組みしたまま、しきりに感心している。
「腕ば磨いて、江戸屋敷の殿さまのところに戻ったのか」
「戻ったさ。ばってん、殿さまは国許(久留米)に向かわれた後じゃった。仕方のう俺も久留米に帰って来たわけよ。帰ってみたら、お城の中は上を下への大騒ぎたい。殿さまは、版籍奉還とやらで、領土と領民ば天皇さまに返上なさった。そうなると、有馬の殿さまは大名じゃのうなりなさった。俺だって、行き場を失ってしもうた」
「......」
「時代が変われば、お抱え大工も要らんごとなるわけ。そこで...」
「時計屋ば始めようち考えたわけ?」
今度は雲平が相槌を打った。
「そうたい。ご維新で、殿さまもおられんようになるし。暦の有りようも変わるし。時計屋ば開くなら今だち思うたわけよ。師走(明治5年)の3日が翌年(明治6年)の元日になるとじゃろ。何もかもが新しゅう生まれ変わるときが、俺も新しか仕事を始むるときと...」
「考えたわけか、末吉どんは」
雲平と嘉助が、同時に相槌を発して頷いた。
「俺が武士の身分に見切りばつけて牛鍋屋になろうと考えたのも、実は、この末吉どんの話を聞いたからよ」
平四郎もまた、大きく胸を反らせて高笑いした。
走り出すあきんど(07)
新しい暦(太陽暦)が始まった明治6年の1月末(1873年)。賑やかな苧扱川通りの一角に、宗野時計店が開業した。雲平は、お祝いを言うために出かけた。
「御時計師」と墨書された看板の下に人だかりができている。久留米の町民は、西洋時計の針が文字盤を這っている様子が珍しくて集まってきた。耳を澄ますと、「チックタック」の連続音が何とも心地よい。
「雲平しゃんじゃなかね。中に入らんね」
縞の着流しに前掛け姿から、末吉の前身(大工の棟梁)を連想することは難しい。
「久留米でこれだけの時計の種類ば集めるとはね」
お世辞ではなく、正直雲平は舌を巻いた。
「修行した横浜の時計屋の親方が紹介してくれて、品物ば揃えることができたと。それに、この八角時計は、有馬のお殿さまからいただいたものたい。こればっかりは俺の宝ものじゃけん、売ってくれち言われても売るわけにはいかん」
1日を24時間制とする新暦の始まりが、宗野末吉の前途をも祝福しているようである。この宗野時計店は、140年たった平成の今日もなお、久留米の中心街で繁盛している。
雲平が足袋店を開いた明治6年は、日本の産業や文化が劇的に向上した年でもあった。前年頃に始まった文明開化の風潮は、ますます燃え盛った。東京府下で始まった小学校の開設が、たったの3年で、久留米の隅々にまで及んだ。そして全国津々浦々の子供たちは、6年制の小学校に通い始めた。
 絵:開通当時の東京新橋駅 絵:開通当時の東京新橋駅
明治4年に東京と大阪間に開設された郵便制度は、翌年には列島全域に張り巡らされた。電気通信の普及も素早かった。当時は東京から横浜までの配線だったものが、4年後の明治6年には、長崎まで伸びた。更に明治10年には、九州から北海道まで切れ目がなくなる。
それまで自分の足で歩くしかなかった移動手段も、たちまち鉄道にとって代わられた。東京新橋から横浜までの29キロ間に敷かれた鉄道を、客を乗せた列車が所要時間53分で走りぬけた(明治4年)。速足の人間が休みなしで歩いても5時間はかかっていた距離をである。
商売人も役人も、そして何より日本で暮らす人々にとって、活動の範囲が飛躍的に広くなり、スピード化していったのである。
この時期、旧久留米城下の人口は、戸数3千920戸、人口は2万682人と記録されている。
倉田雲平は、隣の家を借りて、曲がりなりにも「槌屋足袋店」の看板を掲げることができた。これで、一国一城の主となった。明治6年の10月20日であった。
仕事への意気込みも重なって、少しずつではあるが売り上げも上がった。
城下町から商業都市への変革を遂げる久留米にあって、宗野末吉の時計店をはじめ、久留米つつじを世界に普及させた元庄屋の息子・赤司喜次郎がこの年に花卉業を起こした。更に、中村勝次の写真館、野村正助の鉛活字による活版印刷所など、技術の先端をなす店舗や工場が続々と名乗りを上げる。
同じ明治6年にもう1人。元武士の息子が、親戚の商家に商人見習いに入ったことも記しておかなければならない。後のブリヂストンタイヤを起こす石橋正二郎の父親徳次郎である。
舞い降りた織り姫(08)
雲平が槌屋足袋店を開業して、半年が経過した明治7年の春。雲平は、足袋職人を雇い入れた。嘉助から、「店を開けた以上、1日に10足とか20足とか、ちまちました商いでは話にならん」と、商い規模の拡大を進言されたからである。
長崎の師匠に頼んで、雲平より3歳若い卯之助を送りこんでもらった。案じるより産むがやすしである。卯之助は、いち早く雲平の足袋作りの心意気を吸収して、期待以上の仕事をこなした。
この頃では、時計屋の宗野末吉が、暇を見ては雲平の店を訪ねることが多くなった。彼は世間話が好きである。そんな末吉が、歳の頃なら三十(歳)台半ばの大柄な女を連れてきた。
 写真:小川トク 写真:小川トク
「江戸から来なさった小川トクさんたい。足袋作りば天職ち思うとる男がおる言うたら、ぜひ会いたいと」
久留米でも長崎でも、めったに見かけない垢ぬけした顔立ちの美人である。
「天職ち言われると、気恥ずかしか。それで、お江戸のお方がどうして...」
つい見とれてしまいそうな女性を前に、声が上ずっているのが自分でもわかる。そこは、末吉がうまく言葉を引き取った。
「トクさんとは、俺が江戸のお屋敷に上がっているときに知り合うたと。その後、江戸に詰めてなさったお武家さん方が、家族ぐるみで久留米に引き上げて来なさったもんで」
「それじゃ、あんたのご先祖さんは久留米の方かい」
「そうじゃないわ。私は武蔵国で生まれたのよ。たまたま、縁あって、お国のお屋敷(久留米藩江戸上屋敷)に女中奉公にあがったもので」
歯切れのよい江戸言葉に、そのまま聞き惚れてしまいそうになる雲平である。
小川トクは、天保10年(1839年)、武蔵国の春岡村宮ヶ谷塔(現さいたま市見沼区)で、農家の一人娘として生を受けた。幼い頃から、はた織りを仕込まれていて、娘盛りの頃には家計を助けるほどに腕をあげていたという。
「今の若い人が、天から授かった仕事を大切にして足袋を作るなんて、偉いと思うわ。私なんて、江戸から久留米に流れてきて、ただ食べていくために、子供の頃に覚えた縞織りを始めようと思っただけよ。それだって、天職と言えるような代物じゃないわ」
謙遜するトクを見兼ねて末吉が前に出た。
「トクさんは、久留米の縞織りは、技術的にも流行の面でも、世の中から遅れとるち言いなさる。生きていくためちいうより、子供の頃から身についたはた織りと、江戸で目に焼き付けた織物の感覚ば、お世話になる久留米の人たちに分けてあげたいと。そげなわけで機屋ば始めなさるとげな」
「分けてやるなんて、そんな」
歯にかむ姿は、未だ少女の雰囲気を残している。
「たまたまだったとしても、貴方と同時に商いを始めるのですから、よろしく頼みますよ」と言い置いて、小川トクは自宅のある新廓に戻っていった。
雲平はその夜、なかなか寝付けなかった。このあたりでは見かけぬ、艶めかしささえ漂わせる中年女に興奮したというだけではない。「久留米の織物が遅れをとっている」と言う話が、妙に気にかかるからだ。
江戸時代の封建制度は、久留米を江戸からも京都からも遠ざけてきたような気がする。久留米しか知らないものには、自分たちが作ったもの以上に優れたものはないと思い込みがちである。だが、広い世界から眺めてみれば、閉じ込められていた久留米で、何と時代遅れのものを自慢してきたことか。これでは、ふるさとで作る物や道具は、ますます時代から取り残されていってしまう。
これから足袋屋を生業とする自分にとって、もっともっと自らの頭を柔らかくして時代を先取りしなければならない。そうでなければ、せっかく神さまがくれた仕事を台無しにしてしまう、とも思う。
武家と商家(09)
母親マチと兄嫁のフデが、改まった顔をして入ってきた。嫁姑が揃って雲平に用事を持ち込むことなど滅多にないことである。
「雲平、お前もそろそろ身を固めなきゃない」
マチが切りだすと、フデが姑の言葉を奪うようにして畳みかけた。
「よかおなごがおらすとよ。大そう別嬪さんちいう話ばい」
雲平に口を挟む余地など与えてくれない。
「雲平しゃんのお嫁さんにち言うて、世話役さんが持ってこらしたと。相手は、お武家の娘さんげな」
母と義姉は、肝心の雲平が話を聞いていようがいまいがお構いなしである。
「ばってん、士族の娘と平民じゃ、釣合いがとれんめえもん」
雲平の正直な気持であった。維新以降、新政府は「四民平等」をうたって、それまでの士農工商による身分差別を取りやめた。町民が士族の娘と結婚しても、法的には何の不都合も生じないことにはなっている。
「何ば言いよるね、雲平しゃん。ご維新で世の中は変わってしもうたとばい。お相手がお公卿さまならいざ知らず・・・」
ここは、雲平が反対できるような雰囲気ではなかった。
.gif) 写真:実家のあった米屋町あたり 写真:実家のあった米屋町あたり
「そのお嬢さんちは、どこのどなたですな」
「ご維新まで江戸のお屋敷で勘定役をなさっておられた本村八郎兵衛というお方の娘さんげな。今は津福の江戸屋敷にお住まいで、名前をモトさんといいなさる」
雲平の結婚話は、町の世話役と兄夫婦の間で一方的に進められた。雲平は、生涯連れそうかもしれない女性について、あまりにも情報が少な過ぎることに不安を覚えている。江戸上屋敷といえば、先日会ったばかりの小川トクも住んだことがあると言っていた。
翌日、新廓に住む小川トクを尋ねた。そこも津福の江戸屋敷と同様、江戸から帰還する士族のために建てられた住居である。雲平はトクに、本村八郎兵衛の娘を知っているかと質した。
「江戸のお屋敷と言っても、上屋敷・中屋敷・下屋敷とありましてね。お尋ねの本村さまというお方に、私はお会いしたことがないわ」
トクは、雲平にとって大切な情報を伝えられないことを気の毒に思っている。
「私も、一度結婚に失敗している女だから、貴方の気持ちはよくわかるわ。納得いくまで相手のことを知った上で、お嫁さんにするかどうかを決めるといいわね」
数日後、雲平は坊津街道(国道209号)に面した江戸屋敷に出向いた。モトに会うためである。
「娘の縁談の件については、私ども夫婦も承知しております。こちらから挨拶をと考えていたのですが、丁度よかった」
正面で正座している八郎兵衛と妻の八重は、いかにも武士の夫婦らしく礼儀正しい。間もなく、茶を運んできた娘のモトを、八郎兵衛が紹介した。モトは、軽く会釈をしただけで、すぐに別室に去った。たち振る舞いも容姿も、武士の娘らしい品格を備えていると感じた。
雲平は、小川トクの進言通り、彼女の本心を聞くために、二人だけにさせて欲しいと頼んだ。夫婦が立ち上がるとすぐに、再びモトが現れた。
「一つだけ貴女にお尋ねしたいことがあります」
雲平は、ここは遠慮する場ではないと思っている。
「俺は、見てのとおりの職人です。職人といえば聞こえはよかばってん、毎日コツコツと足袋ば縫うて、それば売ってさるく貧乏の塊みたいなもんです。人並みの行儀作法も知らんとです。貴女のごたるお武家のお嬢さんが、こげな貧乏商人と夫婦になることを承知してもらえるとも思えんのですが」
言い過ぎたかと不安になって、そっと相手の表情を窺った。
「いいえ、このお話をお聞きしたとき、すぐにお受けしようと思いました。それは...」
次の言葉がなかなか返ってこないために、雲平は目の持って行き場を捜した。
「何でも言ってください。俺は、貴女が考えとることを知りたかだけですけん」
「父は、ご維新の折りに私に言いました。『これからの世は、武士とか商人とか、身分で人間の上下をつけることはなくなるだろう。例え維新前に武士であったとしても、自分の腕と才覚で生きていけないものは、世間から脱落するだけだ』と。私は、ずっと父の言葉の意味を考えていました。生まれて初めて江戸を離れたもので、筑後とか久留米のことを何にも知らないのです。なるべく早く、生涯を共にできるお方に巡り合って、この地にしっかり足をつけたいと思っております。できれば、私自身も旦那さまになるお方といっしょに、汗を流して働く嫁になりたいと考えています」
一気に話をして、頬がほんのり赤くなるモトを、雲平は見逃さなかった。
新婚時代(010)
雲平とモトの祝言は、世話役である傘屋の伊三郎夫妻の媒酌で執り行われた。宴会場は青々館の座敷である。式には、久し振りに兄弟全員が揃い、母マチも末席で満足そうに末息子の晴れ姿を見ていた。
親友の嘉助が、「高砂や」を謡い、青々館のトミ子が、三味線で囃したてた。
「あなたさん、お昼ですよ」
木型に入れた仕掛け品と格闘している雲平に、階下からモトが声をかけた。
「卯之助、昼飯だぞ」
祝言からひと月が経過するのに、モトに「あなたさん」と呼ばれるのが気恥ずかしくて仕方がない。そんな時、そばに卯之助がいてくれて助かる。
「奥さん、もう商家暮らしに慣れなさったかいの」
卯之助が冷やかすような口ぶりで問いかけた。
「まだまだですよ。この人の仕事ぶりを見ているだけで、あっと言う間に1日が過ぎてしまいますし」
「大将の仕事ば見ているだけでですか。ご馳走さんです」
モトと卯之助の会話の途中、雲平は黙ったまま口に食いものを運んでいるだけである。
「だんだん、おおきん(どうもありがとう=ご馳走さま)」
食事の最後は、卯之助の長崎弁で締めくくる。
「大将は奥さんとなかなか喋らんですね」
卯之助の方が、雲平の寡黙を心配している。
「男はベラベラ喋るもんじゃなか」
「ばってん、もうちょっとは優しゅうものば言ってやりなさったほうが...」
「そげなことば心配する暇があったら、さっさと仕事ば片付けんかい」
2人の会話はそれで終わり、再び縫い目を叩く木槌の音だけが部屋に籠った。
「とうとう、櫓もなくなりますね」
夕食の後、モトがしみじみ語りかけた。家から見える、堀の向うの櫓が取り壊されたことを言っている。
「大手門ものうなったし...」
時代の変化を、ただ成り行きのように見てきた雲平である。改めて新妻に「櫓がなくなる」と言われて、これまでの、お城と町民の間の壁の高さを思い知らされた。
「お江戸にある徳川さまのお城も、なくなったのでしょうか。私どもが住んでいた久留米藩のお屋敷は...」
雲平に初めて見せるモトの哀しい感情であった。
「淋しいのか、お城や櫓がのうなるのが」
「それは淋しいですよ。あなたさんといっしょになるまで、武家の社会でしか生きてこなかった女ですから」
「ばってん、モトは商人になりきると言ったじゃなかか」
雲平は、言うべきことではなかったと後悔したが、修正はできなかった。
「いいんですよ。どうせ私の気持ちなど、あなたさんにわかるわけはないのですから」
とうとう、下を向いて泣きだした。
日本中の武家社会にいた人たちが、モトと同じように淋しがっているのだろうかと、雲平は思う。
徳川時代の形あるものの一掃も激しかったが、その間に国や地方の行政の変化も著しかった。明治9年(1876年)には、それまでの三潴県が廃止され、福岡県に統合された。この時点で、筑後地区の政治的中心をなしてきた久留米の立ち位置が大きく後退して、福岡県下の一地方都市に格落ちすることになったのである。
明治9年の秋ともなると、雲平の商いは、小規模ながら安定してきた。1日100足の生産も順調だし、種類もお座敷足袋から職人が履くものまで、客層も広がった。店先には、白足袋・黒足袋を文数別に並べて、「槌屋足袋店」の形も出来上がった。
モトの生活にリズムが出てきたことを、雲平は何より喜んだ。所帯を持ってすぐ、モトには店の帳面と金銭を全面的に任せた。最初は「私にそんな大それたことは無理です」と、難色を示していた。だが、始めると彼女の1日は、人が変わったように躍動的になった。
今でいう「会計」全般のことだが、当時の帳簿は所謂「大福帳」をもっと単純化したものだった。最も重要な筆記事項は、「売掛金」である。客から、「ちょっと待って下さい」とか「給金が入ってからにして」と頼まれれば嫌とは言えない。だが、回収しそこなったらこちらが大損をする。
次に大切なことは、お金の出し入れ。雲平が「材料と道具を買ってくる」と言えば、言われるままに金庫の中の金を渡す。その先、何をどのように購入したかは、雲平任せということに。支出の面で絶対に粗末にできないことが、卯之助への給金の支払いだ。足袋を作る大事な働き手に、お金の面で不愉快な思いをさせては、槌屋足袋の屋台骨にも影響がでる。
後は、毎日金庫の中にいくら現金が残っているかを点検することだ。残高を確かめた後に、食材を調達したり店先の茶葉を購入したりする。
「大丈夫か、金庫の中は」
ときどき雲平が心配顔で覗きこむ。
「大丈夫ですよ。危なくなったら言いますから」
この手の夫婦の会話は、3日を置かずに交わされた。
そんな時、青々館のトミ子が忙しそうに表戸を開けて入ってきた。
「大将が、雲平しゃんば呼んどります。お客さんば引き合わせるけん、よかきもん(着物)ば着て来るごつち」
トミ子は、用事を済ますとさっさと出て行った。
「こげな昼間に、俺に会わせたか人ちは、誰かいの」
ブツブツ呟きながらも、不安な気持ちが頭の中を駆け巡った。その間も、モトは着替えの準備に余念がない。
内戦前夜(011)
260年間続いた徳川時代は、維新をもってすべて解決というわけにはいかなかった。
雲平が結婚した年(明治7年)の2月には、国の参議を降りて佐賀にあった江藤新平が首領となって、「佐賀の乱」が勃発した。戦いは、佐賀城周辺から福岡県との境にまで拡大し、久留米の町からも銃声が聞こえた。発足したばかりの明善小学校は休校となり、政府軍の負傷者が、校内に設けられた包帯所(病院)に次々と収容された。
新政府に逆らって士族が引き起こす反乱は、神風連の乱(明治9年10月・熊本)、秋月の乱(明治9年10月・福岡県)、萩の乱(明治9年10月・山口県)と、次々に勃発。
鹿児島で点火した西南の役は、日本国内における最大級の内戦へと発展した。この戦争は、雲平の運命をも左右することになる。
「久留米も、戦争に巻き込まれる」
つい先頃、嘉助が話していたことだ。鹿児島の西郷隆盛が決起すれば、政府は全力を傾注して鎮圧にあたるに違いないと。鹿児島から近い熊本か、或いは福岡が決戦の場になるだろう。そうなれば、久留米も戦場に巻き込まれる可能性が大である。
「いずれにしても、商人は命がけの決断ばしなけりゃならんときが来る」
嘉助は、この重大局面にいかに向き合うか、雲平に考えろと促していた。
青々館に出向くと、嘉助が今や遅しと待っていた。
「相手は、陸軍でも偉か人ぞ。何ば言われても、逆らっちゃならん」
雲平の性格を知り尽くしている嘉助は、階段を上る前に念を押した。2階の部屋には、見た目その辺の役所勤めの中年男が、1人で雲平の到着を待っていた。
「こちらは、この度の戦役で軍に必要な物資を調達なさる河野さまであられる。粗相のないように」
嘉助は、河野参謀を紹介すると、雲平の後方に下がった。
「吾輩は、この度の鹿児島の反乱軍を蹴散らすための、後方部隊に所属する。これまでに、兵隊の食いものや着るものを調達してきたが、少々の物資では持ち堪えられそうにない。そこでだ」
細い体型と小さな顔には似合わない大きくて真っ黒などじょう髭が、もの言う度にピクピク刎ねる。
「地元の商い仲間が、河野さまにご贔屓いただいていることは承知しております。ですが...」
「何か、吾輩に文句でもあるのか。まだ、何にも喋ってはおらんぞ」
先程嘉助が言った「何を言われても、逆らっちゃならん」は、この場面だと思った。
「とんでもございません、河野さまに文句など。何なりと言いつけて下さいませ。久留米商人の意地にかけて、薩摩軍との戦闘にお役にたちます」
雲平は、言い過ぎを自覚しながら、途中で止められなかった。
「それでは、申す。よいか、聞き洩らすでないぞ」
河野は、どじょう髭を片方ずつさすり終えると、一気に要件をぶちまけた。
「兵隊が履く草鞋掛け足袋を2万足、それにシャツとズボン下を各1万枚。それらを、向う20日の内に本営まで持参せよ」
河野の口調は、商談というより命令であった。
聞きながら、雲平の体中が硬直していく。「そんな無茶な」と言いたいところだが、後ろに控える嘉助からは、何の助太刀も来ない。
「分かりました。河野さまのお言いつけであれば、必ず期日までに納品させていただきます」
畳に額をこすりつけながら、承知することになった。河野参謀との商談を終えて階下に降りた雲平は、全身から力が抜けて、思わず嘉助の肩に崩れてしまった。
|