���̋{�Q��
�@���������̉��ŕ�炷�C�g�ƋV���v�w�ɂ́A���̎q���Q�l���܂ꂽ�܂܂ł���B�C�g�̎d���M�S�Ȃ̂͗ǂ��Ƃ��āA���������q�Â���ɂ��M�S�ł����ė~�����ƁA�`�͊���Ă���B
�@�O�����i1844�j�N�̏H�A�`�̂��Ƃɋg��э���ł����B��v�Ƃɗ{�q�ɓ����Ă��镺���Y�̉ł��A�j�̎q���Y�Ƃ����B57�ɂ��ď��߂ĕ�����j�̑��a���ł������B�u�O���v�Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ邪�A����Ɩ��Â���ꂽ�Ԃ�V�����������Ďd�����Ȃ��B����Z���đ�������Ƃ��A�����Ƃ����������Ă���ł̋C�����Ȃǖ������Ēʂ��������B
�u�������������������ˁB���x�͑c��(��)����A���炩�悩������i���炵���ǂ����ꒅ�j����Ă�邯��ˁv
�@����̋{�w��́A�܍��_�Ђłƌ��߂Ă���B�u���̂��{����Ȃ�A�_�傳�����(�˂�)�낾���A����̏����̌�������Ă���邩��v�Ƃ����̂��A�ł̃~�T�L��~�T�L�̐e��[��������E������ɂȂ����B
�@�����Ȃ�ƁA�{�Q��p�̐��ꒅ�̂��Ƃ������痣��Ȃ��Ȃ�B�����Ȃ�A�����ɉ����Ă������ƕ��̈Ă������Ԃ̂ɁA�����̑��̂��ƂƂȂ�ƁA�Ȃ��Ȃ����Ă�������ł��Ȃ������B
��Ə�ł͍��������������A��(�ق���)�Ɛl��������䖝���Ȃ���A�فX�Ɠ����Ă���B����҂́A��ɏo�Ď�����ɗ]�O���Ȃ��B
�@���̍��̓`�́A�R���ڂ̖{���ؖȏ��X�ɏo�����Ė��������w������@����������B������ɂ͓��肽�Ă̖��������āA���G���犇��A���߁A�D��A�����܂ł̊�b���������ނ̂ɂ������b�オ����B�����q����u����ς肨�`����łȂ���v�Ƃ�������������S�n�悳����`���āA�ʂ��������y�������B
�u�D�����C�g�����ɔC���āA�`����͒�q�{���ɐ�O������ǂ���ˁv
�@������킹�邽�тɁA�����q�͓`���͂��䂩�牺�낻���Ƃ���B
�u�Ȃ��ĂˁH�����͂܂��܂����������ɂ͕����Ă�����B�����A���̋{�Q��̂�����i�����j�̂��Ƃœ��������ς��ɂȂ邭�炢���Ⴏ��v
�@�Ƃ͌������̂́A���͂͂����Ă������A�������Ԃ̍�Ƃ͌��⍘�ɉ�����悤�ɂȂ����B�@����݂č�Ə�̈���C�g�ɏ��邱�Ƃ��l���Ă���B�����A���̂��Ƃ�N���ɘb���Ă��܂��A�r�[�ɐ�����ӗ~�܂Ŏ����Ă��܂������ŕ|�������B�u����̋{�Q�肪�ς祥��v�ƁA�g���̎��h�𖧂��ɑ_���Ă���Ƃ��낾������B
�u�C���]���ɁA�������傤�ق��̂��Ƃł����܂����v�ƌ����Ȃ�A���ۂ̂�����@�ɍ���Ȃ������B����̋{�Q��܂Ŏc�蔼�������Ȃ��B���̊O�͍��_�ɕ����Ă��ĈÂ��B�w�悪��������Ŏv�킸���̏��ɑ��𐁂��������B�t�������i�V���1�����{�j�ł���B
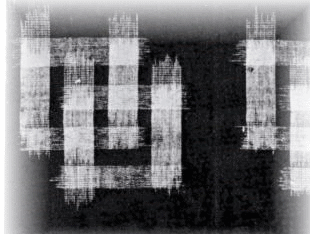
�������̎l���R
�i�v�����R�Z�p�ۑ���L�j
�u��ł����A�搶�v
�@�ׂ�ō�Ƃ��Ă��閺���m�点���B
�u�ق�Ȃ��i�{���j�A�ڂ���Ⴝ���ˁv
�@�����đ����J�����B������悤�Ȗk������Ə�ɗx�肱��ŗ����B
�u�������A���ꂵ���B�݂�ȕ��ׂЂ����v
�@���ɂ���C�g������Ă��đ���߂悤�Ƃ���B
�u�҂���́B���悩�Ƃ����Ⴏ��v
�@�C�g�̎���āA����O�ɏo�����B�D�F�̏�疳���̍��������~��Ă���B���悤�ɂ���Ă͐o(����)�Ƃ��Ƃ�邵�A�Ȗ�(�킽��)�̂悤�ɂ�������B�n�ʂɗ����Ă����ɗn������́A��̏��t�ɂƂ܂����܂c����̂��낢��ł���B
�u�����悩���A�߂Ă��v
�@���N�Ԃ肾�낤�A�Ⴊ�~��l���Ԃ��Ɋώ@�����̂́B�Ђ���Ƃ�����A���܂�ď��߂Ă����m��Ȃ��B
�u���������I�v
�@�`�̋��тɁA��Əꒆ�̖ڂ��W�������B�`�͍Q�ĂĂ͂��𗣂��ƁA�G��ƌ����������B��̍~��l�q��������n�ɍڂ������B12�̍��A�c��̖T��Ŏ��t���ꂽ�悤�ɌÒ��������A���ɂ�����(����)�̔��͗l(�܂�����悤)�ɖ���������(�����)�̍~��l��D��グ�����̎��̋������h�����B
�@�������ďo���オ�����̂��A���̔���ɒ�����{�Q��p�́u�l�ځv�͗l�ł������B
�u���ꂢ�����ꒅ���Ȃ������ł��ˁv
�@�܍��_�Ђ̐���n�낤�Ƃ���Ƃ���ŁA�m�荇���̎�w�ɐ���������ꂽ�B
�u�{���͂���������낵�イ�ĥ���v
�@����Ⴄ�s�x�A�Q�q�q����A�`�������Ă��鑷�ƁA���ɒ������l�ږ͗l�����݂Ɍ���ׂ�ꂽ�B

�܍��_�Ћ���
�@����ł́A9��ڗL�n����(���̂�)�̎��ŁA�ˎ�̍����L�n���i(���Ƃ�)�ւƈڂ����B���i�́A�`�����t�̐��b���������̖��N(��͂�����)�ł���B
�@�˂̍����́A��������̎؋���������Őg�����̂Ƃ�Ȃ���Ԃɂ������B�ӔN�̗������A����܂ł��ґ�(��������)�Ȃ����߂āA�܍��_�Ђɂ������\���������A�D���ȑ�������l�����肵���B�����A���̂��炢�̂��Ƃł͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��قǂ̍����߂ł������B
�@���i���ˎ�̍��ɏA��������ɁA�I�����_�D������ɓ��`���ē��{�̊J���𔗂����B���{�́A�S���̔ˎ�ɑ��ĉ��݂̌��d�x���𖽂����B
���̑r�������ʂ����̏o�����ɁA���i�͑傫�ȏՌ����A�̓��ɋً}�z�߂����B
�@�]�ˍΒ��̔ˎm�ɏq�ׂ��z�߂̎�|�͎��̂Ƃ���ł������B
�u�ٍ��D�̂��Ƃ͖����Ɏ���肩�łȂ����A���Ǝ���ɂ���ẮA����ǂ̂悤�ȏd�厖�ԂɎ���ʂƂ�����Ȃ��B�Ƃ��낪�A�䂪�˂̍�����Ԃł͏d�厖�ԂɑΏ������p���ǂ�����Ęd������悢���B�܂��ɔ˂������Đ^���ɍl���˂Ȃ�Ȃ����ł���v�ƁB
�@���đ����ɁA�ˎm����_���E�����A�_��E�m���Ɏ��邠����K�w�ɁA�V���Ȍ���߂�������ꂽ�B

11��v���Ĕˎ�E�L�n����
���������ߕ��ނ͂��ׂĖؖȕ���p���A��������ׂ��b���H�̕i�ȂǗp���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�܂��A�蓹��E�����ނ��A��������Ȃ��̂͗p���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
���Z�����ƍ앁���́A�J�R��Ƃ��Z�ނɂ���������ꍇ�̂ق��́A�s��Ȃ����ƁB
���������Ձ��q�������Ĕh��ɐU�镑�����Ƃ͂�߁A�ߐe�҂����Ŏ��f�ɍs�����ƁB
���|���Ƌ��s���O������x��ȂǗV�|�̌m�Â͈��߁A�ŋ��E���o�E�y�ƂȂǂ̋��s���֎~���邱�ƁB
������̔p�~������܂ő可���E���ʓ��y�ѕ����҂܂��͑�n��ɔF�߂��Ă����������p�̓����p�~����B
�@���i�́A�ˎ厩��͂��������߂ɁA�v�l�ƂƂ��Ɉߕ��̌����p����߂Ėؖȕ��ɂ����Ƃ����B�ᔽ�҂ɑ���E�����i�݁A�ݕ��i�c�Ɂj�̎�90�l�����i���p�̍߂ŏ������ꂽ�B
�@��������_���̓��퐶���Ɏ���܂ōׂ����K�������u�匐��߁v�́A���̌㕽���̍����܂ŁA�u�v���Ă̐l�Ԃ͌���^�v�Ƃ̑㖼�������������قǂɉe�����y�ڂ����B�u�v���Ă̋��鉺�ɂ͋��y�|�\�����Ȃ��v�ƌ�����̂́A���̎��̔ː��������炵�����̈�Y�Ȃ̂�������Ȃ��B
�ˎ�L�n���i�́A�����Č��ɑ������ŁA���m�ɂ͕��|�̒b�B���A�̖��ɂ͎Y�Ƃɗ�ނ悤�Ăт������B�܂��A�]�˂̉��~���ł͗m���̑�C�点�A�v���Ă̖����ɂ��H���݂��Ċe��̓S�C���������B
�@����ȗ��i(���Ƃ�)�̎�����A�ނ��}���������߂ɂR�N�ŏC������B����p������̗L�n����(��肵��)���A�v���Ĕ˂̍Ō�̑喼�ƂȂ�B�����A�ˎ�͑����Ă��A���i����̌���z�߂���������邱�Ƃ͂Ȃ������B
���j�̉H�D
�@����̋{�Q������ɂ��āA�`�̂͂��D�茻���͏I�������B�����ޏ����D�邩����́A�P���ɖ͗l����ׂ������̂��̂������B����ł��X�ł́A�u���~��̂��Ƃ���v�Ƃ��u��(�����)���~��p�Ɏ��Ƃ�v�Ƃ������Ă��Ă͂₳�ꂽ�B

���`����
�i�n��Y����ߓW���j
�@��ɁA��ˑ����⋍���m�V�������������Z�@�ɂ���āA����܂ŕs�\�Ƃ���Ă����G�͗l�⏬������͗l�����I�ɔ���̂ł���B
�u���v����A���ꂵ���B���`������͒N�ɂ���������͂���v
�@�C�g���A�ǂ������Ă����҂ɂ����낮����Ԃ߂��B�C�g�̒����g����13�ɐ������āA�͂��D����n�߂����ł���B���Ƃł́A���O��ŐD���ƋƂ��p�������̂��ƁA�����ۏ��Ă��ꂽ�B
�@�͂��D��̌�����ނ��Č�́A����ׂ̍�Ə�Ɩ{�������q�̋@�����������Ȃ���A���Ƃ̖������ւ̎w���ɐ�O���邱�Ƃ������Ȃ����B�`�������𗣂ꂽ���Ƃ�m�������Ă̋����q�������A������藧����育�@���f���ɂ���Ă���B���̓x�ɔ����u���̂������i�n���َq�j�������o���Ċ��}�����B�S���a�ނЂƎ��ł���B
�u���ւɂ��炩�������i�ƂĂ��傫�ȁj���q�������Ƃ��v
�@�ꉮ�ł��낢�ł���`���g�����Ăтɗ����B�o�Ă݂�ƁA�w�䂪�D�ɂU�ڂ͒��������Ȓj���Q�l�A�V����C�ɂ��Ȃ���A���������ɗ����Ă����B
�u�����ǂ�́A�����n�ɂ��ז����Ƃ鉡�j����(�ӂ�ǂ�)�����i�t���l�j�ł��킷�B���j���炨�`�a�ɐ܂�����Ă̗��݂����킷�䂦�A�����J�肦�܂����v

������O�Y�̋ъG
�@�������܍��_�Ў��ӂɑ告�o���s�̛�(�̂ڂ�)�������Ă��邱�Ƃɂ͋C�����Ă����B�Ŕ͎m�́A���j�̏�����O�Y�Ƒ�ւ̈ɒB�̊C(���Ă̂���)�ł���B�匟��߂̍Œ��ł��A�L�n�ˎ储�����̗͎m�Ƃ������Ƃ������āA�告�o�����͓��ʈ����ł������B
�@���l���̑��o�����ł͂��邪�A�`���ǂ��ɂ����Č����������Ǝv���Ă������̂��ƂŁA��j�̗��X�����}�����B�������̃C�g���ċ����̉�������K�˂�ƁA������삩�����A���j�̕����܂ňē������B
�u���`�a�̕]���́A���˂��ˍ]�˂ɂ��킷�a���畷���Ă���������B�v���ĂɎQ�������ŁA����Ƃ��H�D�n��D���Ă��炢�����v
�@���j�́A�莝���̐�q���L���ē`�̑O�ɒu�����B��ʂɂ́A�咹����ԗl��w�i�ɁA�u�����v�̗͎m�����{���Ă���B
�u���̊G��������D��ɂ��Ă͂��炦�܂����B�킵�炪�v���Ă�����܂łɥ���v
�@���̏����A���i�ΔȂ̑�Ð��܂�ŁA�����n�v���ďo�g�̏����ˏ��Ƃ͕ʐl�ł���B
�@��s���v���Ăɑ؍݂���̂͋͂��T���Ԃł������B�S�O(���イ����)����`�ɁA�ォ��C�g�����ł������B
�u�����͈�ԁA���`������̎��͂Ό����Ă��܂�����A���ꂵ���v
�@�C�g���l����悤�ɁA���`������̕]���𑼔˂ɂ܂ōL����܂��ƂȂ��@��ł���B���G��`�����Ƃ͂���Ȃɓ���͂Ȃ����A�����傫�߂���B�����̏ꍇ�A�ʏ�̕��͂P�ځi�~�ڂP�ځ�37.9�a�j�ł���B���̕����Q�����L���ĂP�ڂQ���i45.5�a�j�ɂ��Ȃ���A�����o����̒����Ƃ��Ă͎d���Ă��Ȃ��B����ȑ啝��D��D�@�ȂǓ`�̍�Ə�ɂ��낤�͂����Ȃ��B
�u��H�ΌĂ�ő��蒼�����܂�����A���ꂵ���v
�@�告�o��s�̑؍݊��ԂɎd�グ�邱�Ƃ��ł��邩�A�܂��������ԂƂ̐킢�ł������B��Ə�ɖ߂�����q�́A���̓�����Q���̍�Ƃɓ˓������B��Ă�����q�����Ƃɉ��G��`���͓̂`�̎d���A���̕҂ݏグ���犇��̓C�g�����Ȃ��B����オ���҂��āA�����̍����������̍�Ə�Ɏ����A�����B�����S�i1857�j�N�A���`�͊���70�ɓ��B���Ă����B
�@��s���v���Ă�������A�C�g���o���オ�����D����͂����B���j����̂͌����܂ł��Ȃ��B�y���݂ɂ��Ă����]�ˑ��o�̌����́A���̋@��܂ł��a���ƂȂ����B
�@���j����q�ŐD����������𒅂āA�����t�߂�舕�����p��z�����邾���ŁA�`�̖j�͎��R�ɊɂB
.gif)
�������̉ԉ�
�@�l�ԌÊ���߂���ƁA�̂̐����ƍ����ċC�͂����ނ���B����܂ł́A�����O�̋C���Ŏ�����������Ă������̂��A��������Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă����B�c��������Ƃ��ɉ߂����Ă��������̍������A�g�オ���q���瑷�Ɉڂ��āA�����ݗF�����Ƃ��ĕt���������x�ɂȂ��Ă���B
�����q�����́A���ς�炸���C�������B�u�l�\�A�\�͟���(�͂Ȃ�)�ꏬ�m�����v�ƈА��̂悢���t���āA�X�̂��̂��ە�����B�u���`����ɘV�����܂ꂽ��A�킵�����邯��v�ƁA�X�ɌĂт��Ă͐V�����}���̍l�Ă𑣂����B�{�����X�́A���ł͂��`����������Ɉ�������Ă����ɏ㓾�ӂƂȂ��Ă���B�Ⴆ���Y�ߏ�ł��A���X�o���������Ă��A�ق��Ĉ�������Ă����̂����當��̂��悤���Ȃ��B
�@�`���A�X��ŏ����q�Ɛ}�Ă��]�������Ă���Ƃ���ɁA�����^�Ő����Ȋ���̎�҂����ꂽ�B
�u�����A�쎟�Y���B�悩�Ƃ��ɗ����Ȃ��v
�@�����q�͐N���菵�����āA�`�Ɉ������킹���B��ˑ����̂Ƃ����������������A�����q�Ƃ������l�́A��قǐl�Ɛl���������킹��̂��D�݂̂悤�ł���B
�u����l�͂ȁA���`�������āA�������l���o�����l�����B����l�̂��A�ŁA�v���Ă�D���͂�����ɂȂ����v
�@�ő勉�̖J�ߌ��t�ŁA�`���Љ���B
.gif)
�����쎟�Y
�i�v���Ďs�j�j
�u�܂��܂��A�����q��������A�����������Ăĥ���B����͂悩���Ă�A������������͂��������ǂ��̂ǂȂ��ł��ȁH�v
�u���������ˁA���`����̂��Ƃ�肱����������̂��ƂΌ���ɂ�Ȃ��v
�@�����q�����ɂ́A���̎�ҁA�ʒ��T���ڂ̋����̑��q�ŁA�ŋ߂����蔄����n�߂�����̊쎟�Y���ƌ����B��҂̂��C���菕�����邱�Ƃɐ����b����������q���A�쎟�Y�ɏ����̃C���n�������Ă���Ƃ��낾�Ƃ��b�����B
�u�����́A�ǂ���t�������Ă��A���̋����ȏ�ɂ͂Ȃ��ł�����ˁB���́A�����q����̂�����A�悻�̍��i�ˁj�ɂ��o�����鏤���l�ɂȂ肽���Ƃł��v
�����ɂ��܂��A�����m��ʎ�҂��o�����Ă���B�����쎟�Y�A��Ɂu���̋@�Ɖ�(�����傤����)�v�Ƃ������A�S���ɖ���y����j�ł���B
�o������
�u�����ɂ��q������v
�@�ꉮ�ł��낢�ł���`���A�g�����Ăтɂ����B
�u�N����납�H�v
�u�������m���l�B���ł���쒬�̥���v
�u�����A���̂��l�����v
�@�v���������݂��������A�悭���É�̓X�ɗ�������Ă����A��쒬�i���v���Ďs��P�����j�̐��V���������B���V���͖���X���Ől�n�≮���c��ł��鏤�l�ł���B�l�n�≮�Ƃ́A�X���Ől���E�n�E�h���ĂȂǂ����T�[�r�X�Ƃ̂��ƁB
�u���ς����Ȃ�����v
�@���V���̓X�́A����̗��ԉƂⒷ���s���E���c�㊯���ȂǂӐ�ɂ��Ă��邾�������ĉH�Ԃ肪�悩�����B�ȑO�`�̐D���ɗ�����������V���́A�N�►�����̂��߂ɁA��������������ܔ����Ă��ꂽ�B�A��̓X���������Ԃɂ́A���ւ̂�������Ȃǂ��ς܂�Ă������Ƃ��v���o���B
�u���̎��̂�������ͥ���H�v
�u�������Ȃ��A���h�ȑ�l�ɂȂ�܂��ĂȁB���������A��������������̂́A���̑����̂��Ƃł��Ăˁv
.gif)
��P����ɉ˂���P��
�@���V���̑��Ƃ����A20���炢���B
�u�����ł��A���̑����ɂ͂��D��ΏK�킹�悤�Ǝv�������܂��āv
�u�Ȃ�ł܂��A������l�̂悤�ȑ�X(��������)�̂��삳�܂�����v
�u���ꂩ���A���オ�傫���ς��܂�����B���܂Ől�n�≮�Ƃ����ґ�(��������)�ȕ�炵���ł��邱�Ƃ��B���킢���������A�����ɂ킽���ĕ�炵�ɍ���߂ɁA�藧�Ă����͂��Ă����Ƃ����v���܂��āB�W�W�n���Ƃ����ł��傤���v
�@�͂��D��ɖ����ɂȂ��Ă���ԂɁA���̒��͑傫�������Ă����̂ł���B�v���Ĕ˂̕ی�̂��Ƃŏ��������Ă������V���ɂ��āA�߂������̉Ƒ��̕邵���l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ́B
�u����ť���v
�u�����A���`����̒�q�ɂ��ė~�����Ƃł��B�����ɏZ�ݍ��܂��ĥ���v
�u��X�̔����肨�삳��A�����Ȃނ����邵���Ƃ��ɂł����B����͂�����Ȃ�ł��ł��܂�����B����ɁA���͂����͂��D�����߂��Ƃł���v
�u����͎c�O���ȁB�����̂Ƃ�������Ƃ��Ȃ�܂��v
�@���V�����A���߂���Ȃ��ł���B
�u�悲�����܂��A����Ȃ玄����쒬�̂���܂ŏo�����܂�����v
�@�͂��D�����߂Ă���A�莝������(�Ă����Ԃ���)�ŋC�����������Ă����Ƃ������ɁA�`�̐S���������h�ꂽ�B
�u���v�ł����A�`����B���g�̂̕��́v
�u�������A�����͂��D�����킯���Ⴀ��܂���B�����ɂ��܂������ΘA��Ă����܂�����v
�@�{�l�̗������Ƃ�Ȃ��Ō��߂Ă��܂��Ƃ��낪�A�����ɂ��`�炵���B
�u����ɁA�����ł���A��P���́v
�u������Ȃ�ł��A�������炨��܂Ŗ����ʂ�����͂��܂���B�Ђƌ����炢�A���Ƃ�������ɂ���ɐQ���肳���Ă��낤�āB����ɥ���v
�u����ɁH�@������ł������Ă��������v
�u�͂��A����̂��ߏ��ł͂��D��ΏK������������������A�Ă�ł��������B���삳��Ƃ�������ɋ����܂�����v
�@���V�����A�`�̓Ƃ��߂͐��ԓI�ɕ������������Ǝv���Ă������ŁA�\���o�͓n��ɑD�������B
�@����ɂ킽�邩����D��̎菇���A�������̂P�����Ԃŋ����������Ƃ����̂�����A�`�ɂƂ��Ă������������ł������B���V���̑������܂߂�10�l�̖������́A�����ߖ��グ�Ȃ���Ō�܂ł��Ă����B
�u�悤���Ȃ������ł��ˁv
�@�v���Ԃ�ɒʊO���̎���ɖ߂����`���A���L�G���˂�������B�����������邤���ɁA�R�G��(��܂��܂ނ�)�i�����S�s�R�G�j�̏����Ɩ����l�����K�˂Ă����B
�u���ЁA�����̑��̖������ɂ������ė~�����Ƃł��B�����������m�ť���v�ƁA��(��)�������������B
�u�悲�����܂��B���̂͂��D����A�܂��}���̌������܂ł͍s���n���Ă���܂���v
��쒬�ł̂͂��D��m�̐����Ɏ��M��[�߂��Ƃ��ł��������̂ŁA�`�͂Ђƌ��̊����t���ŏ��m�����B������g���̓s�������āA�������ƈ����Ă��܂����B�R�G���ł�50�l�̖������ɋ������B
�@���炭����ƁA�}�㕽��ɒ��菄�炳�ꂽ�`�̒�q�����ɂ���āA���������̔_�Ƃ���͂��D��̉�����������悤�ɂȂ����B
���ɂ�����
�@���L�G���삯���ނ悤�ɂ��ē����Ă����B
�u�ǂ����ˁA������Q�Ăāv
�@�`���A�����������B
�u�悩�m�点�ł����B�����i�ˁj���Ⴑ�̓x�A������Γ��Y�i�ɂ��Ă悻�̍��ł����邲�Ƃ��Ȃ��邰�Ȃł���B���`����̂�������A���{�����ɂ����킽�邲�ƂȂ�Ƃł��v
�@���̒����Q�����Ȃ開���̌������i1864�j�N�B�B�Y���Ɛ���𐄂��i�߂�v���Ĕ˂́A�v�����R�i���̍����߂Ċ����́u�R�v�̕������m�F�ł���j���u���i�ˁj�Y�i�v�Ɏw�肵���B�P���ɂ��P��̗��ʐł��ۂ��ƂƂ��ɁA�ی����u���Đ��Y����ɏ��o�����̂ł���B���̎��Ɛ�I�≮�Ɏw�����ꂽ�̂��A���̕������ł������B�����ċv�����R�́A�������s��ɂ܂ő����邱�ƂɂȂ����B
�@���L�G�́A�`�̔���������Ă͂��Ⴂ���B���̂Ƃ���A�`�͈݂̋���v�킵���Ȃ��āA�Q����N��������J��Ԃ��Ă���B
�u���L�G�A���炢�̂��Ƃő����Ȃ���ȁB�l�Ԃ͐l����J�߂�ꂽ�肵���Ƃ����]���̎n�܂肿��������v
�u�����Ȃ���ł����ˁH�v
�@�`�̔����݂̓��ɁA���L�G�͂��������s�����ł���B
�u�����Ɠ����̂���ł��A����ƍ����Ȃ����Ƃ��������낤���B���������v���ƁA���\�i�j�ɂȂ��Ă������ƍ����L�тƂ�l�����炷�v
�u���`����̂��ˁv
�u�����ȂƂ��ő��ƂΑł���ł��悩�B�ǂ��ł��̍����o�邩�������ƁA������Ƃ�����̐S�̎����悤�����B����l�ł��A�В��蕅���Ăӂ�Ԃ��Ƃ����ɂ͕K�������������č����Ȃ���B���̔��ɁA��������獘�ΒႤ���Ƃ����́A���܂ł����͋Ȃ����v
�@�������P�b�����L�G�͉��x�������ꂽ���Ƃ��B�u���̘b�͂�������v�Ȃ�ĎՂ낤���̂Ȃ�A���̐��{���̘b���҂����܂��Ă��邱�Ƃ����m���Ă��邩��A�ق��ďI���܂ŕ��������Ȃ��B
�u���ꂪ�A���`����̐M�S�ł�����ˁv
�@�`���Â��ɂȂ鎞�́A�Δ��̒��̊D���Δ�(�Ђ�)�ł܂Ƃ߂āA�����ɐ������Q�{���ĂĂ���Ƃ��ł���B���̐������R���s����܂ŁA�u�Ȃ�܂v�̔O��������������B
�u�_����ł�������ł��A���{����₨������ɍs���ɂ�q�߂������Ƃ���Ȃ��B�����āA�S�̒��Ŕq��ǂ�A������Ɍ��̂Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��v
�@����܂��A80���ԋ߂ɂ��Ă̓`�̌��Ȃł������B�͂��D��≺�G�`�������Ă������������ނ����ɂȂ��Ă��܂����ŋ߂ł́A�܍��_�Ђ̒������(����)�邱�Ƃ������Ȃ����B����n���Ĕq�a�Ɉ�炵����́A�ׂɌ��Ă��Ă���~�ʎ��i�_�{�����_�Ђɕt�����Ēu���ꂽ���@�j�̖{���ɏオ��ށB�Δ��̑O�̔O�������ł͕�����Ȃ��Ȃ������́A�`�̃p�^�[���ł���B
.gif)
�`�����铿�_��
�u�ǂ����A�C�g�̑̂���肭�������v
�@�肢���Ƃ͂��̈�_�ł������B�C�g�̍ŋ߂̑����l�ُ͈�ł���B�S�̑��i�S���j�������̂��A����Ƃ��x���B��҂ɐf�Ă��炦�ƌ����Ă��A�u�ǂ����Ȃ��v�ƌ����ď]�����Ƃ��Ȃ��B�������P�l�̖��ɁA�������̂��Ƃ���������ǂ�����悢�̂��A�l���邾���ŋC�����������ɂȂ�B
�@�`�ɂƂ��āA�������S�c��͓��e�̍s�����ł������B���얋�{�����i�c���S�N=1868�N�j�A���̒����傫���ς�낤�Ƃ��鍠�A�`�͉�(��)�����Ƃ������Ȃ����B�Q�Ԃɂ́A�����⏯���q���悭�������ɂ����B�����⏯���q�̓X�ʼn�����쎟�Y�����Ă���B
�u�����A�����̖��͒����͂Ȃ��B������Ȃ�����A�����̂���̂��Ƃ�낵�����݂܂��v
�@����q����q�ɓ����������B
�u���`����͕s���g�̐l�Ԃ��Ⴏ��B������ȒP��腖�(�����)�����ĂтȂ����v
�@�����q���܂��A����������J��Ԃ����B
�u���������A�����ɗ���Ƃ��A��Ə�Δ`(�̂�)���Ă��錩�m��ʂ��Ȃ����������B���ł��]�˂̂����~�ɏオ���Ă��������A���ېV�ŋv���Ăɂ���Ă����Ƃ��v
�@�����q���A�\�ł̏o������`�ɍ������B

�ӔN�̏���g�N
�u�ǂ��̂��l����납�H�v
�u���̐l�́A�������Ő��܂�Ȃ��������ȁB�v���Ăɗ������R(�킯)�͐u����������Ă�A���낤�A�͂��D�肪�D���炵���v
�@�����q���b�������Ƃ́A����g�N�̂��Ƃł������B�g�N�́A�܂�ň��`����͂��D��l���̃o�g������邽�߂̂悤�ɁA�v���Ă̏鉺�Ɍ��ꂽ���ł���B
|
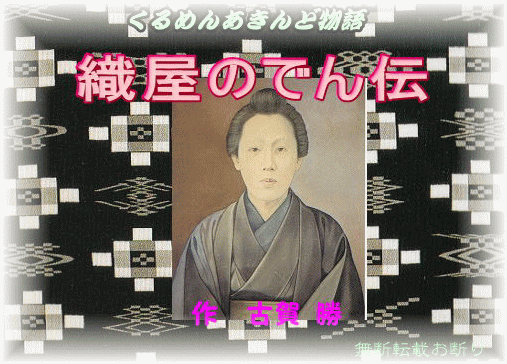
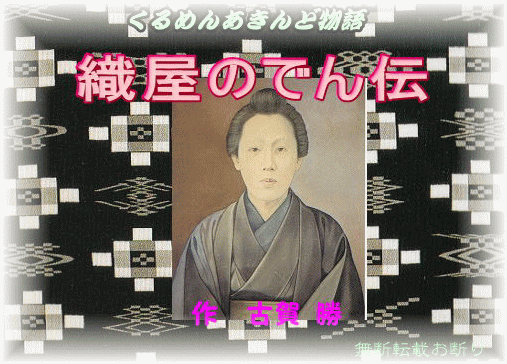
![]()
![]()
 �@�@
�@�@ �@
�@ �@�@
�@�@