お家の事情
井上伝が久留米絣を考案する5年前、7歳(数え年)に成長した頃である。
「もうすぐ御繁昌(ごはんじょう)たいね、待ち遠しか」
五穀神社(ごこくじんじゃ)境内を流れる筒川で遊ぶ子供たちの話題は、間もなくやってくる秋の大祭のことばかり。「御繁昌(ごはんじょう)」とは、町の繁栄と店の繁盛を願ってつけられた祭りの呼び名である。
「こげな雑魚(ざこ)ばっかり獲っておってもしょもなか(意味がない)」
川に浸かっていた1人が叫ぶと、他のものもいっせいに岸に上がって砂を掘り始めた。今度は砂に潜っているシジミが目当てである。
「これば持って帰りゃ、母ちゃんが喜ぶけんな」
シジミは朝餉の汁の具になる。だから家に帰るのが少々遅くなっても親から怒られることはない。幼児なりの知恵であった。
子供たちが話題にしていた御繁昌(ごはんじょう)の日がやってきた。城下の片原町から通町10丁目までの店先には作り花で飾られた行灯が飾られ、10丁目の構口(かまえぐち)から五穀神社の境内までは、これまた左右に掛け行灯(あんどん)や覆青傘(おおいあおかさ)が立ち並んでいて、祭りの雰囲気を盛り上げている。その間2キロにも及ぶ。
境内に入ると、芝居小屋や露店が立ち並び、大道芸人の居合い術・琵琶弾き・辻浄瑠璃などが入り乱れて客を呼び込んでいる。参拝客どうしは、「ごはんじょうで・・・」と挨拶を交わしながら雑踏の中に吸い込まれていった。
祭りを最高に満喫するのは、やはり子供たちだ。伝は、履物屋のキヌと示し合せて出かけた。時次郎ら男の子は、鬼の面を被りおもちゃの刀を持って、女の子を驚かせるための工夫を凝らす。その後は、そろってお化け屋敷に入り、キャーキャー悲鳴を上げるのが定番であった。
祭りが最高潮に達するのは、各町の屋台による出し物が始まってからである。能や狂言などを人形芝居に仕立てて、観客を泣かせたり笑わせたりする。町単位で稽古を重ねた成果を発表する場だけあって、「隣町にだけは負けられん」との競争意識がむき出しになる。それがまた、観客を興奮させる。
伝の生家は、代々米屋を生業(なりわい)にしてきた。屋号は「橋口屋」といった。家族は、父源蔵と母ミツ、それに祖母ヨシノと兄の敏造、弟の為吉を加えた6人である。
五穀神社の参道に面した店は、土間と板張りが半々で、米俵や枡などが雑然と置かれている。客が居場所を遠慮しなければならないほどに狭かった。源蔵は、働く割には稼ぎが悪いとぼやいてばかりいる。ミツはといえば、源蔵とともに店を切り盛りしながら結構忙しそう。だがこれまた、「米屋じゃ食うていけん」と愚痴の方が先にたつ。
つれ(祖父)に先立たれた祖母のヨシノは、裏の離れ間でいざり機にしがみついて、一日中木綿織りに忙しい。ヨシノが織って稼ぐ手間賃は、平山家の大切な生活資金になっていた。そんな貧乏世帯でも、長男の敏造にだけは無理をして寺子屋に通わせている。
.gif)
井上伝の生誕地付近(久留米市通外町)
父母の苦労も、未だ7歳になったばかりの伝には理解できない。「ちっとは店ば手伝わんかい」と母が怒ると、「キヌちゃんが待っとるけん」と反発して、裏口から五穀神社の境内に逃げ込んでしまう。
子供どうしの遊びがない時は、離れで祖母のはた織り歌を聞くのが楽しみだった。
♪ほうたい巻き巻きよ 巻き巻きよ
ほうたい巻き巻き 痛いかと問えば
何のチントンシャン 痛かろ 国のためよ サノ
ここでいう「国」とは、久留米藩のことである。ときどき「国のため」が「家のため」に変化することもある。「どげな意味の歌ね?」と祖母に訊いても、確かな返事をもらったことがない。
「うちも寺子屋に行きたか」
伝がヨシノに持ちかけた。
「そげん言うても、銭がなかけん」
予想したとおりの返事が返ってきた。
「祖母(ばあ)ちゃん、うちはそげん貧乏しとると?」
「何ば言いよると、突然に・・・」
不意打ちを食らって、ヨシノは杼(ひ)を送る手を止めた。
「お宮さんでみんなが言いよった。家が貧乏じゃけん、寺子屋にも行かせてもらえんとじゃろって」
「それもあるばってん。おなごは読み書きがでけんでもよかと。それに・・・」
「なに?」
「お城(久留米藩)からのお達しじゃ、町民もお百姓も、みんな贅沢(ぜいたく)はしちゃいかんち」
「寺子屋に行くのがそげん贅沢なことね、祖母ちゃん。それに、男が行くとはなして贅沢じゃなかと?」
言い出したら納得するまで諦めないのが伝の長所であり、また決定的な短所でもあった。
「男には、大人になって、頭と体を使うて、お国のためにうんと働いてもらわにゃならんし。おなごは、男ば助けて家ば守っておればそれでよかと」
祖母は、幼い伝にもわかるように語りかけている。伝も寺子屋の話題をいったん横に置くことにした。
「祖母ちゃん、この間キヌちゃんの母ちゃんが言っとった」
「何て?」
「よその国じゃ、絹ちいう布(きれ)で、きもん(着物)ば作るげな。絹のきもんちは、うちが着とるのとどげん違うと」
.gif)
木綿車(地場産くるめ展示)
幼い伝に絹布(けんぷ)のことをどのように説明したらよいものか、ヨシノも迷った。
「蚕(かいこ)ちいう虫の繭(まゆ)から紡いだ糸で織ったもんが絹たい。お伝が着ておるのは、綿毛ば紡いだ木綿じゃろう。絹の端布(はぎれ)がどっかにあったと思うがね」
ヨシノは箪笥の引き出しから、手拭ほどの布を持ってきた。
「わあ、ピカピカ光っとる。それに柔らかかね。こげな布(きれ)で縫うたきもんば着たら、どげん気持ちがよかろうか」
伝は、綿とは違う肌触りが嬉しくて手離そうとしない。
「お城のお殿さまは、あきんどやお百姓に、絹は贅沢(ぜいたく)もんじゃけん身につけちゃならん、木綿でなからにゃならんち、お達しば出されとる」
ヨシノは、申し訳なさそうに伝から絹布を取り上げた。
お城の事情
伝が産声を上げた頃(1788年・天明期)は、日本国中が「天明(てんめい)の飢饉(ききん)」の最中にあった。相次ぐ凶作と増税に苦しむ農民は、百姓一揆や打ちこわしに走り、世の中が騒然とした情勢にあった。日本における絶対的権力を掌握していたはずの徳川幕府にも、わずかにほころびが生じていた時代でもある。
当時権力の中枢にあった老中・田沼意次(たぬまおきつぐ)は、思い切った増収策に出た。それまでの年貢米収入だけの政策から、各地で発展していた特産物や商品生産、流通などが生みだす富を幕府の財源に取り入れようとしたのである。しかし、それらの政策は、ますます暮らしを苦しめることになる民衆を怒らせる結果に。それが、各地で頻発した一揆であり打ち壊しであった。
.gif)
久留米城跡
こうして、田沼意次の権力が行き詰まり、失脚することになる。田沼意次が失脚したあと、老中の座に就いたのが松平定信である。
定信は、幕府財政の危機を乗り切るために「寛政の改革」を断行した。幕内と各大名に対して、厳しい「倹約令」を命じた。
幕府の命を受けた久留米藩主の有馬頼貴(ありまよりたか)(第8代)は、藩内に「倹約」を徹底させた。「絹着用御法度(ごはっと)令」も、それら緊縮政策の一環であった。
藩主による倹約令は、何もその時始まったことではない。伝が生まれる100年前にも、「衣類の義、身の上相応の衣装これをすべしこと。分限に応ぜざる衣装着致すにおいては過料を出すべし。下々、絹布の類固くこれを禁止す」と。
この倹約令は、その後も綿々と引き継がれた。絹布の着用を禁止された農民や町民は、必定木綿の織物を求めることになる。
伝が、絹着用禁止令に関心を持ったその前後。久留米藩は、より付加価値の高い産物の開発奨励に着手していた。その結果・・・
生産物の独占的問屋を管轄する藩の印銭方役人岡野源次は、自ら甘藷(かんしょ)を用いて、黒砂糖及び白砂糖の藩内生産高を飛躍させた。
筑後地方の特産である「大川の家具」もまた、この時期に興されている。榎津町(大川市)の田上嘉作は、それまでの大川指物(おおかわさしもの)に改良を加えて、家具製作を軌道に乗せた。その後の筏(いかだ)流しによる木材の運搬方法などを考えると、彼もまた筑後平野と筑後川の自然環境を上手に取り込んだ先駆者であった。
竹野郡亀王村(現久留米市田主丸町)の大庄屋・竹下周直は、享保15(1730)年頃に櫨(はぜ)栽培を始めた。「竹下はぜ」と呼ばれるものがそれである。その後、宝暦年間(1700年代中頃)には、耳納山麓の松山で見つけた櫨を改良して「松山櫨」が栽培されるようになる。
更に御原郡小郡村(現小郡市)の内山伊吉は、蝋(ろう)の成分を多く含む「伊吉はぜ」の栽培に成功する。その後久留米藩領内のあちこちで櫨の植樹と生蝋(なまろう)の生産が興り、幕末には藩内の櫨の実生産高が960万斤(1斤=約600㌘)に達したと記録されている。キロの単位に直すと、約58トンということになろうか。現在、筑後地方の土堤や川岸などに散在する櫨の老木は、その頃からの名残りなのである。
.gif)
久留米柳坂の櫨並木
御井郡山川村(久留米市山川町)の富安忠四郎右衛門が酒造りを始めたのは、伝が生まれた翌年の寛政元(1789)年であった(富の寿)。酒どころ城島(久留米市城島町)での酒造りの始まりは、それから遅れること文政12(1829)年で、首藤重之進(有薫)らがしのぎを削った。
次から次に開発される付加価値の高い産物は、まるで「雨後のタケノコ」の呈をなしている。現代における久留米の商業は、ここから始まったといっても過言ではあるまい。
幼な子でも、お国(藩)や家の財政事情を聞かされると、早く大人になって、家や社会の役にたちたいと思うものか。 伝は7歳の頃から、はた織りを始めている。
師匠は、大好きな祖母のヨシノである。大きないざり機に座り込んで、杼を経糸(たていと)の隙間に潜らせる。更に大きな筬(おさ)で締め付けなければならない。大人の半分ほどしかない伝の体では、ひと通りの工程をこなすだけでも重労働であった。
それでも、伝は弱音をはかなかった。自分の手と足の動作で布面が広がっていくのが面白かったからである。
綿花から糸を紡ぐのも伝の仕事であった。町から原料を買ってきて、「サネクリ」と称する道具で綿の種を取り除いて紡いでいく。
1.gif)
井上伝愛用の筬(上)と杼(下)とメガネ・ハサミ
(地場産くるめ展示)
ときどき遊び仲間の時次郎やキヌが誘いにきた。でも、今の伝には、神社境内よりはた織りの方が楽しかった。
伝が10歳に成長した。背丈は並みだが、色白で痩せ型の体型を指して、祖母は孫の器量を褒めた。伝の上唇の左上には小豆大のほくろがある。ヨシノは、人知れず気にしている孫に言って聞かせた。
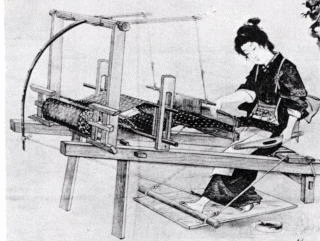
いざり機
(久留米市史)
「そこにほくろを持つもんは銭運がようて、一生涯食うに困らん」
祖母のさりげないいたわりが伝の気持ちを和らげ、更にはたを織る意欲を増加させた。ヨシノや伝が織っているのは、白木綿(しろもめん)や藍染めの無地木綿布である。たまには、縞織りをすることもある。
「面白うなかね」
仕事が進み過ぎたとき、伝の眉間に縦皺がよった。
「いつもんこつたいね、お伝の悪か癖ばい」
ヨシノは、新しく買った織機を伝に譲って、自分はあちこちの傷が目立つはたに座った。
伝が面白くないと言っているのは、何の変哲もない無地の布や、十年一日の如しの織り方に対する不満であった。藍汁で染めた布に美しい柄や模様を施したらどうだろう。そうするために、織る前の糸の段階で染め方をどうすればよいのか。伝はそんなことばかり考えていた。
|
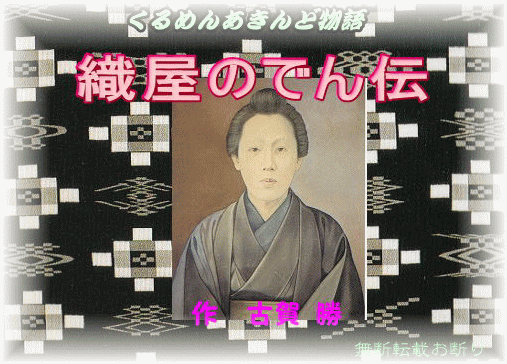
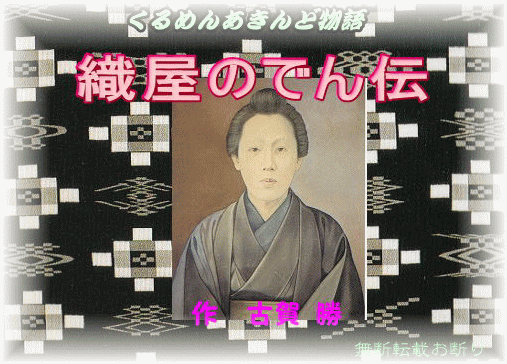
![]()



