興味津津
13歳に成長する頃の伝は、大人が顔負けするほどにかすり織りが上達していた。背丈が伸びた分、繋ぎ道具なしで踏み機まで足が届くようになり、杼(ひ)も片手で自由に動かせるようになった。はたが体の一部のようになっていることが嬉しかった。
織り上がった白木綿(しろもめん)や縞織(しまおり)を引き取りに来る福童屋(問屋)の丁稚(でっち)も、すこぶる機嫌がいい。受け取って帰れば必ず番頭さんに褒めてもらえるし、場合によっては褒美もくれる。丁稚が持って帰る分、新しい糸が置いていかれるわけで、伝にとって、文字通り遊ぶ暇はなかった。それくらいに伝の織り上げた木綿布は、売り物としての価値が高かったということになる。
商いがうまくいかない父親にとって、娘が得る手間賃への期待は膨らむ一方であった。
「困ったもんだね、お伝の父ちゃんは・・・」
祖母のヨシノは、いつものはた織り歌を口ずさみながら、未だ遊び盛りの孫娘に同情している。
「よかとよ、祖母ちゃん。うちははた織りが好きじゃけん」

綿花
現代風に言えば、かなりのおませ娘である。伝は、毎日繰り返す作業に少々物足りなさを感じている。織物に、自分なりの工夫を施して、もっとお金を稼げる織り子になりたかった。でも、織り上がった反物を買い取る福童屋は、そんなことを望んではいない。染め上がった糸を持ち込んだ分、上手に早く織ってくれればそれでいい。「お伝が織った木綿」というだけで、街の婦人たちが競って買い求めるのだから、それ以上の工夫など必要ないのである。もっとお金を稼ぎたい伝のジレンマは、そこにあった。
伝は着古した紺無地の普段着の裾を摘まんだまま、黙り込んでしまった。祖母が何ごとかと訊いても、着物の織り目を見つめたままである。
伝が見つめる先の普段着は、何度も水洗いを繰り返しているうちに、染料が剥げ落ちている。
「藍染めが、剥げきれんであっちこっちに白かぶつぶつが残っとるたいね。このブツブツばよう見ると、模様のごとあってほんに美しか。そげん思わんね、お祖母ちゃん?」
訊かれるヨシノの方が戸惑ってしまう。
「そうかね、染もんが剥げたとこが、お伝にはそげんきれいに見ゆるかね」
「ブツブツがきれいに見ゆるとはどうしてやろうか」
この調子だと、いい加減な返事では許してもらえそうにない。
「そげん染もんの剥げ残りが気になるなら、剥げとるところば解(ほど)いてみたらどげんね。解いた後の糸に、ぶつぶつがどげな風についとるか、自分の目でよう確かめるとよか」
「よかね? 解いても」
「よかくさ、自分の着もんじゃもん。後で繕っとけば済むことたい」
伝は、慌てて着ている普段着を脱いだ。祖母の傍らに座り込んでからは、布の織り目がばらばらにならないように気持ちを集中して、布地を分解し始めた。
「糸に戻してしまうと、経糸(たていと)と緯糸(ぬきいと)の青地のところどころが白うなっとる」
伝は、経糸と緯糸を別々に並べて置いてつぶやいた。解いた斑模様(まだらもよう)の古糸を参考にして、別の白糸を持ち出し、染めてはならないところを別の糸で括り始めた。経糸が終わると次は緯糸を同じ要領で括る。
「そうそう、縊(くび)ったところに藍汁が染み込まんごつ、きつう縛らにゃよ」
ヨシノには、孫娘が何を発見し、何を始めようとしているのか、大方の見当がついている。織物にしてわずかの布地分だが、糸を別の糸で括る作業も簡単ではない。
「それでは今度は染める番たい」

綿花
ヨシノは、括った糸を伝に持たせて、5丁目の紺屋(こうや)の暖簾(のれん)を潜った。迎えたのは、跡継ぎ修行中の佐助である。この時代、かすりを織るのに紺屋(こうや)(染物屋)の存在は不可欠であった。藍草から藍汁に至る行程では、専門的技術と設備が必要であり、一般の家庭では無理だったからだ。ヨシノは、佐助の店を常連にしている。
「試しですたい、この根性もんの・・・」
伝に代わって祖母が、ところどころ強く括った糸を染めて欲しいと頼んだ。
「また、ねえごつ(何事)か考えだしたばいね、お伝は」
佐助は、言われなくても、持ち込まれた糸の束を見て、かすりの新しい図柄を編み出そうとしている伝の考えを読み取っていた。糸の束を受け取ると、瓶いっぱいにはられた藍汁に浸けた。
「これまでに見たことのなかごたる、きれいか模様ができるとよかね」
染めた糸を藍汁から引き揚げて物干しに吊るしてもらったあと、伝はこの先の作業の結果を思い浮かべた。彼女が最高に気持ちを高ぶらせるときである。時に寛政12(1800)年の春先であった。
丸1日天日で乾かして自宅に持ち帰り、括った糸を解いてみると、古着の糸とは比べものにならない鮮やかなまだら模様が浮き出ている。こうして、いつものように杼(ひ)を経糸の間に潜らせる。筬(おさ)での締め付けにも、自然力が入った。
「きれいかね、お伝」
ある程度はた織りが進んだところで、覗き込んだヨシノが嬉しそうに話しかけた。
「そげんきれいに見ゆるね、お祖母ちゃん。藍汁で染めたところと縊(くび)っていて染まらないとこの境目がはっきりしておらん。縊(くび)り方が緩かったんじゃろうか」
確かに、白地を期待して括った部分に、薄く刷毛で掃いたような筋状ができている。
「祖母ちゃんは、その筋目がほんにきれいかち思うがね」
慰めのつもりで発したヨシノの声も聞こえないほどに、伝の織り上がった布地との睨めっこは続いた。
あられか、はたまた雪か
伝が考える藍と白のコントラストを強調する織物が少しずつ目標に近づいた。だが、売り物として通用するまでには、道は遥かに遠い。
織り上がりを見て喜んだヨシノとは対象的に、伝の表情はいつまでも冴えない。
「そげん初めから何でんかんでん(何でもかでも)うまくいくもんか。染めもんがはみ出て、かすれ具合に見ゆるところがほんに珍しかね。ここはここで大事にして、青と白の模様がくっきりすればよか。同じ青でも、濃いかとこと薄かところば自由自在に織れるごとなりゃ、お伝のかすりも一人前たい」
ヨシノは、伝の不満がむしろ上達への第一歩だと思っている。
「こげなふうにかすれた柄のことば、世の中ではかすりち言うとよ」
「なあんだ。それじゃ、こげな模様ば織ったのは、うちが初めてじゃなかと?」
「当たり前たい。大むかしから、数えきれんごと多くの人が、もっと美しか柄や織り方ができんもんかと工夫ば凝らしてきなさった。ばってん・・・」
「ばってん何ね? お祖母ちゃん」
有頂天になりかけたところに、一番身近な祖母から「あんたが最初じゃない」と言い放たれて、孫の自尊心が揺らぎかけている。
「お伝は、着古しのきもんば解いてみて、別の新しか糸で括って、藍色の中に白か色ば浮き立たせることば考えついた。このかすれた柄は、お伝が初めてたい」
それからも、伝とヨシノによる新しいかすり柄を編み出す作業が続いた。「これならいける」と思っても、なかなか縁が揃わない。藍の濃淡部分が不揃いになって、むしろ醜くなることもしばしばである。
孫と祖母が手を取り合って完成を祝いあったのは、それから数ヵ月後のことであった。それは、藍染めの中に無数に散らばる斑紋(はんもん)が、見事に浮き上がったときであった。
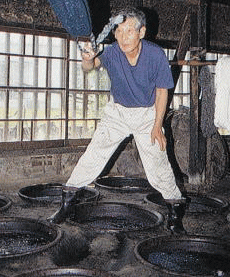
藍染め
はたの上に広げられた織物は、ヨシノがこれまでに見たことのない珍しい柄をなしていた。白い斑模様(まだらもよう)が星を散りばめたように綿布に浮かび上がっている。
これが、平成の今日もなお、被服の生地として重宝がられている、久留米絣の原点である。

井上伝18歳時作品と伝えられる「十八模様」(複製)
(久留米絣技術保存会所有)
噂を聞きつけてやってきた福童屋番頭の徳助、出来たての木綿布を睨みつけている。
「こりゃ、ほんにきれいかね。見本にするけん、すぐに1反織ってくれ」
番頭がヨシノに頭を下げた。狭い城下のこと、伝のかすりが評判を呼ぶのに時間はかからなかった。
「ほんに、空から雪が降ってくるごとあるね」
店先で品定めをしている婦人が、伝のかすりを手にとってため息をついた。
「白か雪にも見えますばってん、粒が大きゅうてはっきりしとるけん、霰(あられ)ち言うたほうがよかですよ」
「いいや、青かかつお菜に白か霜がかかっとるごつも見ゆるばい」
福童屋の店先には、宣伝用のかすりを見たさに、次から次に客が寄ってきた。
「名前ば『加寿利(かすり)』ちつけんね、お伝」
ヨシノが商品の名前を考えた。長年機屋と掛け合ってきて、彼女なりに商標に対する知恵は研ぎ澄まされている。
「うん、よかよ。ばってん、これだけ手間のかかる仕事ばい。これからどんどん売り出していくちいうわけにはいかんね。うちと祖母ちゃんだけじゃ、2人合わせてもしれたもん(大したことじゃない)じゃもんね」
「そうじゃね。福童屋さんに相談してみるか」
話も終らないうちに、ヨシノはもうよそ行き着物に着替えている。
実家の倒産
伝が織る加寿利は、問屋に持ち込む端(はな)から高値で売れた。彼女が15歳になる頃には、福童屋が自らの店の敷地内に作業場を用意した。ヨシノが福童屋の主人・半兵衛と相談して決めたことである。番頭の徳助は伝に、住み込みを条件で雇い入れた娘たちに、仕事を覚えさせるよう言いつけた。
「お伝しゃん、よか話ば聞かせてやるたい」
作業場に現れた徳助の機嫌がすこぶる良い。作業場での織り上がりが順調だからである。
「この頃、川向こうの北野村では、藍草(あいぐさ)が採るるごとなったげな。大庄屋さんが、いろいろ考えなさって、やっと売りものになったち言いよらした」
「それは初耳ですね。そうなると、もう阿波国(あわのくに)から買わんでも間に合うごとなるとですか?」
「そういうことになればよかばってん」
徳助と伝の会話を、聞いているのかそうでないのか、30人の弟子たちは黙々と杼を往復させている。
「大丈夫ね、お伝。自分で織らなきゃ腕が鈍ろうもん」
夜遅く家に帰ると、ヨシノが心配して声をかけた。その祖母もとっくに古希(70歳)を過ぎている。
「大丈夫だよ、お祖母ちゃん。人に教えればその分はっきり自分の頭に入るけん。よか勉強になっとるよ」
「教えるちいうても、相手はお伝と同じ年頃の娘さんじゃろ。素直に言うことば聞いてくれるかい?」
「みんな家の助けばするために来よるとじゃけん。中には福島(八女市)から来とるもんもおるとよ。早う一人前の織り子になって、家のもんのきもん(着物)ば織ったり、銭ば稼がにゃならんとたい。お伝の教えは聞けんなんてん言っておれんと」
「そうたいね、親ば助けとるのはお伝もいっしょじゃけんね」
祖母と孫娘の会話をそばで聞いている父の源蔵は、黙ったままである。母のミツもまた、夜鍋の針仕事を黙々とこなすばかり。すっかり商売も下火になって手持無沙汰の源蔵は、実年齢よりはるかに老けて見える。兄の敏造は相変わらず無口で、食事中もほとんど家族の会話に加わることはなかった。
文化3(1806)年。伝にとって悪夢のような出来事が相次いだ。正月早々、実家の橋口屋が倒産したのだ。店の前には連日借金取りが押しかけた。
「留守ち言うてくれ」
気の弱い源蔵は、奥に引きこもったまま動こうとしない。表での言い訳はミツに任せっきりである。
「お義母さん、こんな時、問屋さんは助けてくれんとですか。お義母さんもお伝も、いつも無理ば聞いてやっているのに」
ミツは、伝の加寿利を引き取ってくれる福童屋に、借金の肩代わりを頼めないかと相談した。
「それは無理だよ、ミツ。仮にだよ、貸してくれたとして、今の源蔵に利子ばつけて返す目途がたつかね? これ以上借金ば重ねたら、子供たちがかわいそうだよ。お前たち夫婦で、どこへなりと夜逃げすりゃよか」
「そんなあ、冷たかことば言わんでください」
ミツが大声を上げて泣きだした。伝にはこの場をどう繕ってよいものか、見当もつかない。
悪いことは重なるもの。頼りのヨシノまで寝込んでしまった。若い頃からの内臓疾患が、ここにきて老体を痛めつけているらしい。寝込んで3日目に意識がなくなり、10日目にはあの世に去ってしまった。あっと言う間の出来事であった。
「俺は貧乏は好かんけん、祖母ちゃんの葬式が済んだらこの家ば出ていく」
長男敏造の突然の申し出に、源蔵とミツの顔が青ざめた。
「こげな時に、何ば言い出すとか。家ば出てどこさん行くとか?」
源蔵の額に青筋がたっている。
「坊さんになるとたい。お寺とは話がついとるけん、あした京都に発とうち思うとる。こげなときじゃけん、路銀も見送りもいらん」
「・・・・・・」
ミツは、信じていた一人息子から突然の決別宣言を受け、俯いたままであった。
「長男にまで見限られたんじゃ、もうおしまいたいね」
源蔵は、ひと言呟いて奥に消えた。
祖母の葬式が終わると、すぐに敏造は旅立った。
葬儀から3日目のこと、福童屋の番頭徳助が顔を見せた。
番頭は、「お母さんにも聞いてもらおうち思うて」と前置きして、信じられないことを言い出した。
「お婆ちゃんが、亡くなるちょっと前に、店に来らしたとたい。旦那さんと直談判(じかだんぱん)ばしに」
「何の話?」
伝よりミツの方が話の先を急かせた。
「伝には、弟子への伝習ばやめさせるち。その後の3年間、弟子たちが織ったかすりば「お傳の加寿利」として、福童屋で売ってもかまわんち。もちろん、ただじゃなかですよ。源蔵さんが負っとる借金ば店で肩代わりするちいう条件でですね。お婆ちゃんも、死ぬ間際まで家のことば心配しとらしたとたいね」

実家のあった通外町
まったくの寝耳に水の話で、伝にはことの成行きをどう整理したらよいものかわからなくなってしまった。
「それで、はた織りができんごとなった伝は、これからどげんするとですか」
ミツも、家族の稼ぎ頭である娘の行く末が気になって仕方がない。
「伝にはしばらくはた織りば休ませてくれち。お婆ちゃんは言いよらした」
さすがに伝も、黙って聞いておれなくなった。
「うちからはた織りば取り上げて・・・、それで、うちはこれから何ばしたらよかとですか、番頭さん」
まさしく、喧嘩腰(けんかごし)である。
「それなんだがね。これもお婆ちゃんが言い出したことばってん。お伝には年季奉公(ねんきほうこう)に出てもらおうち。小さかときからはた織りばかりさせてきて、嫁入り後の作法も何も教えておらんけん。それで・・・」
「花嫁修業ばするために、奉公にやるち言うとですか、お伝ば」
一連の出来事で思考能力を著しく低下させているミツだが、ここは母親らしく、娘の将来を心配してみせた。
「丁度よか按配(あんばい)に、京ノ隈(現久留米市京町)のお侍さんのお屋敷で、女中さんば探しておりなさるけん。松田さまといわれるお方で、お城では馬廻組にお勤めたい。店でも何かとお世話になっておる関係もあって、まったく知らないところよりよかろうち思うて」
八方うまくいくことを考えての決断だったと、番頭は亡きヨシノの代弁にまわった。店が倒産した上に、最愛の祖母に逝かれたばかりの伝には、「はた織りができない奉公なんて嫌だ」なんて突っぱねることなど許されないことだと思った。
この年の重なる悪夢が、伝にとってその後の生き様を決めていくことになる。
|
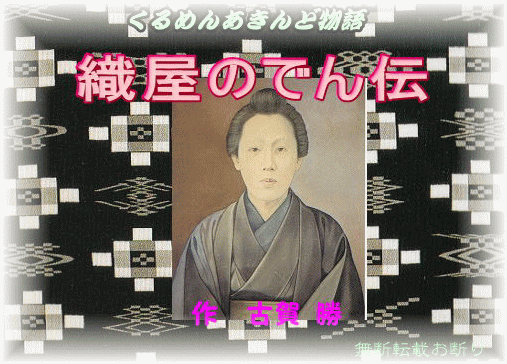
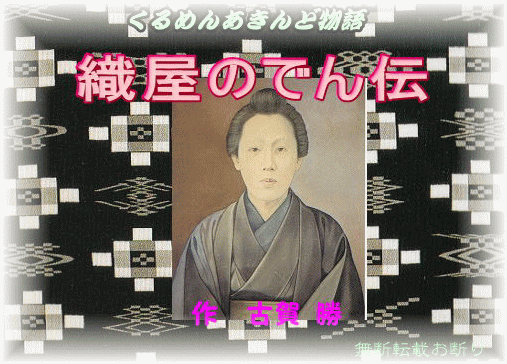
![]()
![]()



