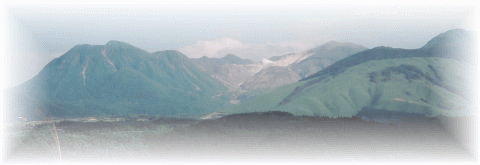豊次たちの住む木佐木村には、筑後平野の南部を流れる矢部川から、北部の筑後川に通じる中小河川が網の目のように張り巡らされている。その豊富な水の恵みを受けて藺草が育つ。農家が栽培する藺草を加工して編み込んだ花筵や畳表は、この地方の特産品である。
そんな時、「そちらを引き払って千町無田に来るように」との、父辰次郎からの手紙が豊次のもとに届いた。手紙には、「先発隊27人が共同でつくった畑で、トーキビや野菜が採れ、自給の目途がたった」とある。また、手分けして建てた家も出来上がり、いつでも家族を迎えられるとも添えてあった。
青木牛之助の指導で、一人(1戸)あたり3町歩の開墾予定地が割り当てられた。辰次郎に割り当てられた3町歩は、今は雑草と葦・茅に覆われた湿地であるが、家族が来て皆んなで開墾すれば、畑はどんどん広がっていくに違いない。先発隊に加わってみてそのことはよくわかった、とも記してあった。
父からの手紙が届いたのは、明治28年のやがて春を迎えようとする頃である。辰次郎など先発隊が久留米を発ってから丁度1年、あの忌まわしい洪水から既に6年が経過していた。
「今だ!」
豊次は、父からの手紙を握り締めた。
いよいよふるさとを後にする前日、豊次は2歳年下の妹ユキと、家から1里ほど離れた筑後川べりにいた。青木牛之助が住む鳥飼村からはずっと下流の、有明海に近くの大川市あたりである。
満ち潮で、大川の水の流れは下流から上流に逆流していた。川岸に繁る葦林は、半分以上が水に浸かっている。風向きのせいか、有明海からの塩の匂いが強烈であった。向こう岸には富津の貨物港が見える。大きな船が錨を下していて、多くの人夫が 忙しそうに働いていた。写真:大川市付近の筑後川
忙しそうに働いていた。写真:大川市付近の筑後川
豊次は、移住に備えて織物工場を退社したばかりのユキに誘われて、ここにやって来たのだった。
「あんちゃん、もう一生ここに戻って来ることはなかじゃろね」
ユキがうつむき加減のままで呟いた。
「そげなこつはなか。開拓が成功して金が貯まったら、いつでん帰って来られるくさ」
豊次は、精一杯妹に慰めを言った。
「この間、正夫がうちと別れとうなかけん、お前だけでん残れち言うた」
正夫はユキの同級生で、日頃から二人が友達以上に仲の良いことを知っている。
「正夫といっしょになるち言うとか」
豊次は驚き顔で妹を見返した。
「でけん(できない)めえもん、そげなこつ。わかっとる。じゃけん、断った」
そこまで言ってユキは、大川に向かって幼子のように大声で泣いた。
「辛かつは、皆んなも同じたい。誰でん我慢ばしとる」
兄弟思いの豊次は、自分も妹といっしょに泣きたかった。
「あんちゃん、千町無田ちゃ、この大川ばずうっと遡っていったところじゃな」
ユキは、頬の涙をぬぐいながら、話題を替えた。
「そうたい。ばってん、向こうは山ん中じゃけん、こことは違う」
「それでも、千町無田の川とこの川は繋がっとるとじゃろ」
「それはそうたい。ばってん、それが、どげんしたと?」
「千町無田の川に流れとる水は、いつかはここまで流れてくるとじゃろもん」
豊次は、ユキが言おうとしている意味をやっと理解した。そうなんだ、山の上での思いは、川の水が必ずここまで運んでくれるはずだ。
それからしばらく、豊次とユキは一言も発しないままで、川面を眺めていた。
旅立ち
旅立ちは早朝3時。春3月というのに、震えがとまらないほどに寒い。東の空では大きな星が瞬きを続けている。昨日までに、近所や親戚への挨拶は大方済ませた。氏神様にも別れを告げた。もう思い残すことはない。
不要な家財道具や衣類は売り払い、現金に換えた。伯父からの餞別金を含めて20円が手元に残っている。これが森山家の全財産である。その内の9円は、3町歩の開拓に参加するための分担金として行き先が決まっている。残りの金で新しく農機具を買ったり、家族全員が自給できるまでの生活を賄わなければならない。
ユキが、生い茂った金木犀の木の陰に人影を見つけて駆け寄った。正夫であった。正夫は、ユキに何かを手渡すとそのまま姿を消してしまった。
「正夫じやなかね」
豊次が小声で訊いた。
「お守りげな」
ユキは、恥ずかしそうに俯いたまま、正夫がくれたものを大事そうに懐にしまい込んだ。
「昨夜は耕吉がいつまでも泣きよったな」
ここを離れたくないと言って、5歳になる弟が愚図ったことを嘉市が言っている。
「さあ、出発!」
嘉市が合図した。森山家の家財道具一切を乗せた荷車が、暗闇の中を軋み音をたてて動き出した。この日、15里(60㌔)先の日田まで進まなければならない。いったん筑後川の土手に出て、それから田んぼ道を、東方に聳える高良山を目指した。
シマは、鳥居の前に座り込むと、頂上の神に向かって手を合わせた。嘉市と豊次もシマに倣った。幼いスエと耕吉だけは、荷車の上から、母たちの仕種を不思議そうに眺めていた。
一行は、久留米の街を離れて善導寺門前から、筑後川沿いに進んでいった。
向こう岸に原鶴温泉を見て、流れが急カーブする袋野(現うきは市浮羽町)にさしかかった。ここで筑後平野に別れを告げると、その先は豊後国である。先頭で荷車を牽く嘉市が、この地方に伝わる話を語り始めた。
「昔、このあたりに田代重栄ち大庄屋さんがおらしたげな。その人は、自分の財産ば投げ出して、水ば上流から田んぼにひくために、山に穴ば開けなさったそうじゃ。そのトンネルが丁度この真下に半里も繋がっとるげな。トンネルのお陰で、ここら辺の村じゃ米がばさらかとれるごつなった。村の百姓さんたちはみんな、田代さんのこつば神さんのごつ思うとるげなばい」
英彦山詣でで地理に詳しい嘉市は、得意気に説明している。一行は、渓谷そばに大庄屋を祀ってある田栄神社に手を合わせた。

袋野から虹峠に向かう坂道
国境越え
国境の虹峠を越えて、三隈川沿いに建つ木賃宿に着いた時、陽はすっかり山陰に隠れていた。大人1人12銭の宿賃であった。
翌日の行程は、日田から次の宿泊地である豊後中村まで。高塚地蔵尊の北側の山道を抜け、大太郎峠を越えて進む。筑後の道と違って道幅は極端に狭く、曲がりくねり、上り下りが急激に変化する。荷車を押したり牽いたりの力加減に神経を使った。前日まで筑後で見た景色が一変して、川を挟んだ向こう岸の山が、折り重なるように迫ってくる。
途中、幅100メートルもある弓型の滝(三日月の滝)を眺めながら、昨夜泊った宿が作ってくれたおにぎりを食べた。
「また山の姿が変わった」
嘉市が、不思議そうに遠くを見つめている。目まぐるしく変化する景色に、一同は夢見心地の心境にとらわれた。一つ一つの山が、まるで炬燵に布団を被せたようにさえ見える。

三日月の滝
「さあ、ぐずぐずしとると、陽が落ちるばの」
嘉市が、気を取り直して大声で叫んだ。一行はまた、荷車の前と後ろの配置に着いた。荷台の後方でスエと耕吉が、気持ちよさそうに眠っている。
日暮れ間近に豊後中村に着き、父に言われていた街道筋の豊前屋に泊ることになった。
「ここまで登って来ると、筑後川の川幅も随分狭くなるもんたい」
豊次は風呂からあがると、眼下の野上川の流れを見つめた。知らぬ間に、昨日別れを済ませたばかりの故郷を懐かしんでいる自分が恥ずかしかった。

豊後中村付近の野上川岸
疲れを癒す間もなく、翌朝も早立ち。宿の主人から、これからの山登りの厳しさを教えられ、不急の家財道具は預かってもらうことにした。
一行は豊前屋を後にすると、奥双石から鹿伏、猪牟田を通過し、赤池峠を越えて北方部落までの3里の山道に立ち向かった。宿の主人が言うとおり、道というより屏風を立てたと表現した方が適当なくらいに厳しい山道であった。前方を塞ぐ背の高い草や小枝を払いのけながら登らなければならない。
途中、スエが小石に躓いて泣きだした。スエの膝頭はすり傷に赤土がくっついて、痛々しい。
「かわいそうに」
長姉のユキが、首に巻いている手ぬぐいで拭いてやった。だが、幼子といえども必要以上にかまってやる余裕など誰にもなかった。
「母ちゃん、喉が渇いた」
山を登り切る手前で、今度は耕吉がむずかりだした。
「少し我慢ばすりゃ、川があるじゃろけん」
シマが諭すが、5歳の子供には聞き分けられない。母の困った顔を見て、豊次は何とかしてあげなければと思う。幸い、彼方に竹藪に囲まれた茅葺の家が見えた。豊次が飲み水を貰おうと中を覗いていると、嘉市がしきりに袖を引っ張った。
「人食い婆が出るかもしれんぞ」
嘉市は、以前田舎芝居で見た安達ヶ原の怖い話を思い出しているようであった。
「そげん言うても、耕吉が・・・」
嘉市の脅しに尻込みしながらも、豊次は弟のために一大決心をして家に入ろうとした。
「あんたたち、山を登って来んさったか。きつかったろう。ああ、、こんなにこまか子が、かわいそうに」
家の横手の畑から顔を出した老婆が、一行に優しく声をかけた。嘉市の脅しとは大違いの柔和な顔の老婆は、深く刻まれた額の皺をますます深くして弟たちに笑いかけた。
「あのう・・・」
豊次が、やっとのことで願い事を言いかけた。
「水じゃろう、わかっとる。好きなだけ飲んでよかよ。湧水じゃけん、冷たかよ」
老婆は、話しかけながら裏手の水瓶を指差した。毎度のことで、ここに登ってくる旅人の体の要求具合まで知り尽くしているようだ。
「さあ、もうひと踏ん張りぞ」
お化けの話をしてみんなを怖がらせた嘉市が、わざとらしい大声で荷車の牽き手を握った。
その時、今来た方角から大勢の話し声が聞こえた。10人ほどが2台の荷車を牽いて登ってくるところだった。親切な老婆は、豊次たちにしたと同じように、彼らにも冷たい湧水を振る舞った。
登ってきたのは二家族で、いずれも豊次たちと同じく、千町無田に向かうところだった。先を登ってきたのは、先発隊員の田川与吉の家族。与吉の妻のハルと長女のトヨエ、それに長男の為治と次男の好夫、次女のキミエ。それに、森山家と同じように、女と子供だけでは頼りないと、ハルの弟の良吉が着いている。
もう一つの家族は、たったの3人だけ。同じく先発隊で出かけた水田村(現筑後市)の井上寅五郎の家族であった。長男の平八、平八の嫁のトキコと少し腰の曲がった寅五郎の父親の定吉であった。寅五郎の妻は3年前に亡くなっていて、家のことは嫁のトキコが頼りの井上家だと平八がぼやいた。
「そうですか、お気の毒に。それでは家の中の女はトキコさんだけじゃね。うちには娘がこげん大勢おりますけん、不自由なこつがあったら何でも言うてな」
シマはトキコの手を握り締めて励ました。峠を降りる時、すっかり打ち解けた3家族の一行は、親切にしてくれたお婆さんに、振り返りながら姿が見えなくなるまで手を振った。この時の老婆、峠を越える旅人みんなが感謝してやまない、「赤池のばあちゃん」であることを、豊次は後になって知った。
火山群
一度に多くの友達ができて、子供たちは元気を取り戻し、列の先頭を歩くようになった。北方の集落を過ぎて小高い丘に出た。南ノ平(現在の朝日台)である。
「わあ、すごか!」
辰次郎の次女のミチヨが奇声を発した。眼前に、山の頂上が三つに割れたような三俣山がどっかと座っている。三俣山に従うように、いくつもの火山が折り重なり、中腹からは絶え 間なく白い煙が立ち上っていた。もちろん、そこにいる誰もが初めて目にする火山群の威容であった。写真:中央が硫黄山
間なく白い煙が立ち上っていた。もちろん、そこにいる誰もが初めて目にする火山群の威容であった。写真:中央が硫黄山
「あすこかいの、わしらの行くとこは」
井上平八の祖父定吉が、虚ろな目で指差した。老人の指の先に見えるのは、一面が茅と葦で覆われた盆地であった。その原野は、薄気味が悪いほど静かに横たわっている。
「こんなところを、どげんして開拓するんじゃ。これならまだ、今までん水田で傘ば貼っとった方がましじゃ」
放っておけば一人ででも後戻りしかねないほどに、思いつめた表情である。
「祖父ちゃんは、これまでずっと和傘ば作っておったとです。好きな傘作りば取り上げられた上に、見たこともなかこげな山ん中に連れてこられるこつに最後まで反対しとったとです」
嫁のトキコが、定吉の手を握ったままで説明した。
「今さら、祖父ちゃんだけば残しても行けんじゃろう」
平八がその場をとりなした。

千町無田全景
「好夫!」
その時、高台の下の方から低い大きな声が聞こえた。為治・好夫兄弟の父・田川与吉であった。与吉は大股で登ってくるなり、次男の好夫を抱きあげた。続いて為治やキミエの頭を強く撫でた。陽も傾きかけた午後3時であった。
森山豊次と井上平八の家族にも、先発隊として出かけていた家の大黒柱が出迎えに出ていて、賑やかに高台を降りて行った。
掘立小屋
「これが俺たちの家!」
耕吉が信じられないといったように頬を膨らませた。目の前にあるのは、3本の柱に竹と木を組み合わせ、屋根と壁は茅を被せて括りつけただけの掘立小屋である。両側の軒が地面まで下りていて、狭い潜り戸のすぐ脇の小さな四角い穴が唯一の窓である。人が住む場所というより、馬小屋のありさまであった。
次女のミチヨも末娘のスエも、こんな汚い小さな家に住むのは嫌だと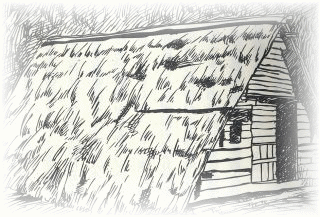 、母親の手を引っ張った。
、母親の手を引っ張った。
「こげな屋根なら、いん(犬)でん(でも)簡単に上れるばい」図:当時の開拓団の家(複製)
耕吉は、今からでも木佐木に帰ろうと言いたげに、豊次の表情をうかがった。
中に入ると薄暗く、枯れ草特有の臭いでむせかえりそう。土間に敷き詰めている藁の間から水がしみ出ていて、足元は凍りつくように冷たかった。
「それでも、父ちゃんたちが来て最初に建てた小屋に比べりゃ、住みやすうなったもんたい」
辰次郎は先回りをして弁解した。さすがに豊次はこの状態を予測していて、何の不満も漏らさなかった。
「便所はどこ?」
ミチヨが訊いた。
「そげなもんはなか。外でしろ」
辰次郎の返事はそっけない。
「そげなあ、恥ずかしか」
「何が恥ずかしかもんか。茅の陰に隠れりゃ、誰にも見えん」
思春期のミチヨは、今にも泣きだしそう。男ばかりの先発隊では、荒野のど真ん中に便所も必要がなかったのだろう。
耕吉やミチヨの気持ちを無視したようにシマが言った。
「やっと自分たちの家に住めるとばいね。ありがたかことです。これからは誰にも遠慮せんで暮らせるとじゃけんね」
義兄夫婦の屋敷内で過ごしたこれまでの辛さを考えれば、シマにはこの小屋が御殿にさえ思えたのかもしれない。
「耕吉もミチヨも、贅沢ば言うちゃいかん。おっちゃん(叔父さん)がこれから少しずつよか家にしちゃるけん」
すっかり家族の一員になっている嘉市が、甥の耕吉を膝に乗せて頭を撫でた。陽が湧蓋山に消えると、心細さで小屋の中は静まり返った。そんな時辰次郎は、外から松の枯れ枝を運んできて、黙々と囲炉裏の火中に投げ入れた。パチパチと樹脂がはじける音が、茅の壁に揺れる人影に伴奏しているようでもあった。
囲炉裏の火が燃え尽きるころ、豊次は小便がしたくて表に出た。3月の高原の空気は、身を切られるように冷たかった。見上げると、大小の星が空いっぱいに煌いている。南から北に伸びる天の川は、筑後の木佐木村から見るより遥かに明るくて、奥行きを感じる。やはりここは筑後川の源流であり、生れ故郷から遠く離れた山奥であった。
先発隊に加わらなかった家族のほとんども、続々入村してきた。合わせて40戸が九重の高原に第一歩を踏み出したのであった。
青木牛之助は、各家族に対して、割り当てた3町歩の開拓を急ぐよう指示した。加えて、各人が将来家を建築しようと思う予定地の周囲に、杉の苗を植えるよう指導した。杉は入植の記念であり、苦労して開拓した土地を、将来とも子孫が大事に守ってくれるようにとの願いを込めている。また杉の木が成長すれば、娘の嫁入り道具も作れるし、家を守る風避けにも役に立つ。そんな思いで牛之助が考え付いたものであった。
.gif)
集落に今も残る開拓記念の杉
年の神
翌日豊次と嘉市は、辰次郎の案内で、これから始まる開拓予定地を見て回った。辰次郎はまず、地元の人が「年の神さま」と言って崇める神社に連れていった。昨日南ノ平から下りてきた道筋の、低い丘の上に社は立っていた。
「本当にこれがお宮さん?」
豊次が驚くのも無理はない。社といっても、間口が1間足らずのこれまた掘立小屋である。太めの支柱に竹の骨組みが施され、屋根と壁の部分がすべて茅で覆われている。中に置かれた細長い板の上には、藁で包んだ餅とみかんが供えてあった。

年の神の社
「御神体は?」
嘉市が、首を傾げながら尋ねると、辰次郎は板の上の丸い石がそうだと教えた。
「年に1度の祭りが近付くと、北方の人たちが総出で、去年造った小屋ば崩して新しか茅で社ば飾るとたい」
「北方」とは、山を登ってくる途中にあった集落のことである。粗末に見える神社でも、住居の傍に心のよりどころが存在することに、豊次は安堵感を覚えた。
「ばってん、わしら他所もんには、祭りにもかてて(参加させて)もらえん」
不満そうな目を向ける豊次を、もうそれ以上は話したくないと言いたげに、辰次郎はさっさと次の場所に移動を始めた。以前から住む人といっしょに祭りを祝えない、それがどんな意味をもつものなのか。どうして父がこの話題を避けようとするのか、この時の豊次には理解ができなかった。
社の前から東方を望むと、葦と茅など雑草だけの千町無田の湿地帯が広がっていた。北側の山裾には、100㍍間隔で茅葺の掘立小屋が並んでいる。豊次には、そのどれが自分の住み家なのか見当もつかない。年の神神社から1番遠いところに畑らしい黒土が見えた。
「あそこは、俺たち先発隊が1年がかりで開墾した畑たい。共同でつくった畑じゃから、あそこは村の共有財産・・・」
「どうしてお宮さんがこげなとこに建っとると?」
それまであまり人が住まなかった高台に神社があることが不思議で、豊次が話をまた元に戻した。辰次郎は仕方なく、牛之助からの受け売りだと断って、年の神の由来である「朝日長者」について語った。
「ここは大昔に朝日と名乗る長者の屋敷があったところげな。長者はこの高台から、肥沃な田んぼで育った稲穂を眺め、何千人もの使用人に号令を発して悦にいっておった」
朝日長者は、小川の流れを強引に屋敷内に引き込んで、川を独り占めした。夜になると、引き込んだ川のせせらぎがうるさいと言っては使用人を怒鳴りつけ、黙らせたという。川の名前を音無川と呼ぶのはそのためだ、と辰次郎は説明した。
長者の驕り高ぶりはそれだけではおさまらない。神をも恐れぬ長者に、やがて報いが。それが、作物が全く育たなくなった今日の千町無田の姿だと言うのだ。
「そげな原野ば開拓して、ほんなこつ(本当に)作物の採れる畑になるとじゃろか?」
嘉市が呟いた。
「俺たちは、でけるち言いなさる青木先生ば信用するしかなか。今更後戻りなんちゃでけん」
辰次郎は、「もういいだろう」と言って、さっさと年の神神社の丘を下りていった。
近所付き合い
その頃シマは、ユキとミチヨを伴って、昨日赤池峠から同行した田川与吉の家を訪ねていた。これから長く付き合ってもらうための挨拶だった。
家の形や広さは自分のところとまったく同じで、家族が寝る場所もないくらいに狭い。与吉の妻のハルが、片づけものをしていた。片付けといっても家財道具らしいものは何もない。
「これでは、手間も省けます」
ハルが笑った。
「私のところも同じようなもんです」
シマもいっしょに笑う。ハルとシマは、二男坊の嫁という共通の立場にある。それだけに、同じ苦しみを持つ者どうしで、話は弾んだ。二人とも同じ筑後の女、これからはお互いに助け合っていこうと誓い合った。
田川与吉の家を出たシマとミチヨは、次に井上次八を訪ねた。昨日家族を迎えに出ていた寅五郎が、沼から刈り取ってきた鬼頭でせっせと縄をなっていた。農作業に必要な草鞋を作るためだという。南ノ平で虚ろな目をして千町無田の茅の林を眺めていた老人は、隅の方で居眠りをしていた。
「親父は水田の生まれで、4里先の久留米より遠かとこに行ったことがなかったとです。そんな年寄りにこげな山ん中で暮らせと言う方が無茶だちゅうこつはようわかっとります。ばってん、しようがなかですもん。毎年大水は出るし、地主への上納は厳しゅうなるばっかり。このままじゃと、家族みんなで首ば吊るしかなか」
寅五郎は、跡取りの長男に見捨てられた父親を、三男の自分が引き取ったのだと説明した。話す口元が微妙に震えているのをシマは見逃さなかった。その間も、たった一人の女手であるトキコは、、片づけものをしたり、シマたちに出す白湯を沸かすのに、忙しく動き回っていた。
湿原の開拓
青木牛之助は、入植者全員に「一戸当たり3町歩の原野を10年間で農作物がつくれる畑に変えること」を義務づけた。10年間は長いようだが、あっという間でもあると牛之助は説いた。 開拓する場所が必要以上に水分を含んでいるため、耕地に変えるには相当の時間を要するはずだと言うのだ。
森山家の作業は、入植の翌々日から始まった。豊次と嘉市は、辰次郎とともに、朝5時に起床してシマが準備してくれる朝食をすませる。食事といっても、粟飯に具の入らない味噌汁と漬物だけ。大人たちは、未だ夢の中にいる幼いスエと耕吉を残して外に出た。
高原の3月の冷気は肌身に堪える。澄み切った夜明け前の空には、ひときわ大きな星が冷たく光っていた。
「まず、雑草を刈る。刈った雑草は、堆肥にするため大事に積んでおけ」
1年間の経験を、辰次郎は豊次や嘉市に伝えた。草刈といっても筑後の平地でやるようにはいかない。前に降った雪が融けきらず、手袋をしていても痺れてくる。つま先には、藁沓を通して、泥濘の冷たさが伝わってくる。
膝まで沈み込む湿地に足を入れ、不安定な姿勢で鎌を使う。腰に堪える。刈り取った葦や茅は、乾燥するために高い場所に移した。運ぶのはシマとユキ、ミチヨの女手である。しばらくたって、スエと耕吉がやってきた。
「俺たちは、何ばすると?」
耕吉も、一人前の働き手になろうと張り切っている。
「お前たちは、母ちゃんたちが運び上げた草ば、積み上げろ」
耕吉とスエは、言いつけられた仕事が面白くて動き回った。だがすぐに飽きてしまい、その場に座り込んでしまう。
「おっちゃん(叔父さん)が良かこつば教えちゃるけん」
嘉市は子供が遊び感覚でやれる仕事として、小川の魚を獲らせた。重労働に耐えていくためには具のない味噌汁と漬物だけではもたない。川魚を家族の貴重な栄養源にしようというわけだ。
.gif)
三俣山の裾野を流れる筑後川の源流
耕吉が田川家の好夫を連れてきた。嘉市は耕吉と好夫に、枯れ草を運ぶためのしょうけ(竹製のざる)を川下に仕掛けさせ、寒くて草むらに眠っている魚を追い込むやりかたを教えた。鮒やどじょうのほかに、筑後ではお目にかかったことのない珍しい魚も獲れた。耕吉は、教える叔父の仕種が面白くて、自分たちでやるからと、しょうけを取り上げた。
陽が間もなく西の山に隠れようとする時刻、女3人と子供たちは、夕食の準備のために一足先に引き上げていった。くたくたに疲れて帰っても家には風呂がない。重労働で汗まみれの体を、シマが沸かした湯を使って拭いた。
「明日は、井戸ば掘るばい」
昼間耕吉が獲った小魚を頬張りながら、嘉市が言った。このあたり、地面を少し掘るだけで水はいくらでも湧き出る、と辰次郎が教えた。
翌日もまた日の出前に起きだして、家族総がかりの枯れ草刈りが続いた。昼前になり、豊次が食料の買い出しに出かけた。自前の畑を持たない今は、すべてを金を出して買うしかない。1里離れた筌ノ口まで出かけ、農家に頼んで野菜と当面の必要品を分けてもらった。
何日か経って、豊次と嘉市が荷車を曳いて山を下りていった。中村の豊前屋に預けていた家財道具を引き取るためである。帰りの荷車には、分厚くて直径80センチもある素焼きの鉢を乗せている。豊次と嘉市は、帰るなり裏手に大きな穴を掘り、運んできた鉢を埋めた。その上には簡単な屋根を被せ周囲を茅で囲った。ミチヨの悲願であった便所の完成である。

崩ノ平山麓に点在する農家
雨が降れば、男は藁を打っり編んだりして休む間がない。一方女は、たまっている繕い物や洗濯に忙しい。晴れれば、一時を惜しんで葦の刈り取りに精を出した。ある程度刈り取りが進むと、今度は排水溝造りに励む。沼地のようにジクジクの土から水分を抜く作業が延々と続いた。溝を掘り、底に笹を敷く。笹の上には杉の葉と粘土質の土を乗せて固めた。刈り取った葦や茅は、小さく刻んで乾いた土に混ぜた。子供たちは、竹や杉の葉を運ぶために山と湿地の往復を繰り返した。
水が抜け、土が乾いたところから、畝を築いて、入植する時運んできた野菜の種を蒔いた。4月に入ると、今度はジャガイモの種芋を植え付けた。もともと降り積もった火山灰に枯れ草などが積もっていて、土壌は肥えており、特別な肥料を施さなくても植物はよく育った。
野菜やトウモロコシの新芽を狙ってやってくる雉や鹿、それに野兎などを追い払うのは子供たちの役割であった。
豊次は叔父の嘉市とともに、ソバの種を手に入れるために筌ノ口の農家を訪ねるが、なかなか売ってくれない。他所者に対する面白くない感情と豊次たちのあまりにも汚い身形を薄気味悪がる地元民は、彼らが近付くだけで奥に引きこんでしまった。それではと、遠く湯ノ平あたりまで出かけることもあった。
牛之助は入植者に、なるべく米を食べないように指導した。手持ちの現金を節約させるためである。女たちが作る食卓は、トウモロコシを粉状にした団子や稗が主食であった。芽吹いたばかりの大根の葉を間引きして煮つけたものもご馳走であった。
真夜中の恐怖
まだ夜明けには間があるというのに、8歳のスエが起き上がって体中を震わせている。唇は真っ青で、何かに怯えているようだ。気配を察して、隣に寝ていた嘉市が起き上がった。
スエは言葉にならない声を発して、小屋の隅を指差した。そこには長さが70‐80センチもありそうな灰色の蛇が、天井からぶら下がったままでスエを睨んでいる。嘉市は、立ち上がるなり壁に立てかけてあった鍬を取り上げ、蛇めがけて叩きつけた。
「ぎゃーっ」
同時にスエが叫んだ。突然の大声で、深眠りの家族全員が飛び起きた。蛇は嘉市に叩きのめされて、外に放り捨てられた。
先日は、ユキが「何か光っている」と言って、戸の隙間を指差した。嘉市が戸を開け放つと、タヌキが2匹すっ飛んでいく「事件」があったばかりである。
「もういや!」
「母ちゃん、木佐木に帰ろう」
ミチヨとスエは、淋しさと怖ろしさにすっかり怯えてしまった。
「そげなこつば言うても、私らに帰る場所はなかとよ」
シマは、スエを抱きかかえたまま、泣きたいのは自分の方だと言いたげである。
子供たちが仕事を免除される日、耕吉は田川家の好夫とキミエ兄妹を誘って遠出した。スエもいっしょである。ところが運悪く、土地の子供たちと鉢合わせになってしまった。
「おまえら、無田の子じゃな」
「臭え、あっちに行け」
子供は、耕吉らをからかいながら騒いだ。
「無田のもんは米喰わねえ」
子供らは、周囲の大人たちが噂をしているのを聞いていたのだろう。
「なにっ」
好夫が、一番大きな子に掴みかかった。耕吉も好夫に続いた。キミエとスエが大声で泣き出した。相手は耕吉より一回り体が大きく、それに多勢に無勢である。殴られたうえに着物まで引き裂かれて散々な目にあった。

北方集落
着物が破れて泥だらけなのを、どうしたのかと母が訊いても、耕吉は泣きじゃくるだけで何も答えない。スエが代わりに一部始終を話した。
ご飯も十分に食べられない、風呂もない生活は、子供たちの心の中まで暗くさせるのか。そんな子供たちを見て、シマも長姉のユキも、何とかしてこの地獄から脱出しなければと思うのだった。
それから数日経って、突然耕吉が愚図りだした。
「母ちゃん、米のご飯ば食いたか」
他部落の子供に「無田のもんは米食わぬ」と言われた悔しさを引きずっている。
「贅沢ば言っちゃいかんよ」
シマが末息子をたしなめた。辰次郎が開拓団の寄り合いで出かけた日のことだった。
「よか、あんしゃん(兄ちゃん)が、あした米ば買うてくるけん」
木佐木村の家を出る時、不急の家財を処分して得た現金 も、農機具を買ったり、食糧費につぎ込んだりして底を尽きかけていた。それでも豊次は、約束通り出かけて行って5升の米を譲ってもらってきた。米1升が9銭だった。写真:手前が平治岳、向こうが三俣山
も、農機具を買ったり、食糧費につぎ込んだりして底を尽きかけていた。それでも豊次は、約束通り出かけて行って5升の米を譲ってもらってきた。米1升が9銭だった。写真:手前が平治岳、向こうが三俣山
開拓地を見下ろす平治岳が、キリシマツツジでピンク色に染まる5月末。子らの仕事がまた忙しくなった。鳥や兎は、せっかく蒔いた野菜や穀物の種をあさり、吹き出した芽を食いちぎってしまう。特に高原には雉が多い。夜になると、猪や鹿も出没して畑を荒らす。畑が荒らされると大人は、「お前どんがちゃんと見張りばせんけんたい」と言って叱った。
遊び盛りの耕吉たちも、欠かせない開拓家族の一員なのである。
台風襲来
入植から半年が過ぎた夏の盛り。高原とはいっても、昼間の暑さはさすがに厳しい。田川与吉の家では、5反ほど拓いた畑で、トウモロコシと野菜が順調に生育している。
「土間の石が湿っとるね」
ハルが呟いた。
「どうしたと?母ちゃん」
長女のトヨエが母の顔をうかがった。
「土間の石が湿る時は大雨が降るち、下荒木では昔から言われとったもん」
入植した当時は土間から浸み出る水が冷たくて、眠れない夜が幾晩も続いた。その後、開拓に加わっている良吉が、小屋の周囲に溝を掘ってたりして、最近では随分住み心地もよくなった。

飯田高原から見る湧蓋山
千町無田の南西方向に聳える湧蓋山(1499㍍)がどす黒い雲に覆われ、稲光と同時に雷鳴が掘立小屋を揺すった。雨風はますます激しさを増し、外は鉄砲水が音を立てて流れている。
家の周囲の溝も、この大雨では役に立たず、家の中まで流れ込んできた。強烈な横風は小屋を吹き飛ばしそうな勢いである。天井から落ちる雫は、やがて雨のようになって家の中を水浸しにしていった。
家の中では座ることもできず、小物を持ったままその場に立ちすくむしかなかった。台風襲来であった。気象情報など望めない時代である。こんな九重の山の中にまで台風が押し寄せるとは誰も考えていなかった。
与吉が血相を変えて外に飛び出した。
「あんた、危なか!」
ハルが、大声で呼び止めた。与吉は収穫間近の作物のことが気になっていたのである。与吉の後を良吉が追った。
間もなくして戻ってきた二人は、「外は真っ暗で、何も見えんじゃった」と言いながら、その場にへたり込んだ。小屋の中は水浸しで体を横にすることもできず、とうとう一睡もしないままに夜明けを迎えた。
台風一過、翌朝の高原は、雲一つない快晴となった。夜明けと同時に飛び出していった与吉が、肩を落として帰ってきた。
「畑の畝がみんな崩れて、トーキビもジャガイモも、何も残っとらん」
与吉は吐き出すように家族に告げた。秋の収穫を頼りにこの冬を乗り切ろうと考えていた矢先の台風襲来である。彼らにとって、命をも奪い去られるような衝撃であった。
台風の衝撃は田川家に限ったことではない。村全体が、秋の収穫を断たれて途方に暮れている。森山家では、筑後を出る時持ってきた金が底をつき、明日の生活の目途さえたたなくなった。
幼い耕吉やスエの着物を買ってやる余裕さえない。破れたところを繕って、もう原型がわからないほどになってしまった。子供たちの我慢も限界に達しているに違いない。弟思いの豊次は、木佐木村で迎えた正月の楽しさを妹や弟に味あわせたいと思い、嘉市を誘って山から松の枝を伐ってきた。
「あんしゃん(兄ちゃん)、その松ばどげんすると?」
耕吉が覗き込んだ。村の子供たちも集まってきた。
「門松ば作るとたい」
松や笹なら近くの山に入ればいくらでもある。梅の木も、野生のものが伐り放題だ。干した茅と青竹で根の周りを囲み、家の前に2基の松竹梅飾りを立てた。掘立小屋にも、正月を迎える雰囲気が漂った。
年が明けて明治29(1896)年、早朝から子供たちが騒いでいる。
「今日、うちのご飯には米が入っとった」
母シマが、せめて正月くらいはと、トウモロコシの中に米を混ぜたのだった。それがよほどおいしかったのだろう、耕吉が他所の子に自慢した。
「うちのご飯は、真っ白だったばい」
頬っぺたがリンゴのように赤い女の子も、負けずに自慢した。言い出しっぺの耕吉は、少し元気をなくした。
年頃のユキやミチヨには、正月といっても晴れ着すらない。故郷を出る時、売り払ってしまったからである。親の事情が理解できるユキは、愚痴一つこぼさなかった。そのことが兄の豊次には辛かった。
耕吉やスエは、正月が過ぎたばかりだというのに、「お盆はまだか」と言っている。
住み家炎上
正月気分も抜けて、一番寒い大寒の頃。夜鍋から解放されてやっと眠りに着いたばかりの深夜の出来事である。異様な臭いで嘉市が飛び起きた。
「大変ばい、家が燃えよる」
嘉市が叫ぶと、辰次郎もシマも豊次もいっせいに跳ね起きて外に出た。風上の西方で、炎が空高く舞いあがっている。
「井上さんとこじゃなかか」
嘉市が走り出した。辰次郎も豊次も続いた。井上寅五郎の家は、西に300メートル離れた場所に建っている。
嘉市が駆けつけた時、既に家は、原型を留めないほどに燃え尽きていた。茅を被せただけでは、全焼するのにいくらの時間もかからない。
寅五郎と長男の平八が、音無川からバケツに水を汲んできて、くすぶっているところにかけていた。平八の嫁のトキコは震えながら宙を見つめたままで、祖父の手を握りしめていた。
「これで、何でんかんでん(何もかも)無うなってしもうた」
寅五郎が、駆けつけた村の衆を前に頭を下げた。辰次郎の後を追ってきたシマは、持ってきた丹前を定吉の肩に着せた。
出火原因は、どうやらランプの灯が周囲の枯れ草に燃え移ったものらしい。最後まで起きていた定吉が、ランプの灯を消し忘れたためのことだった。
.gif)
千町無田の集落
寅五郎の家族は、その晩は開拓事務所に泊まることになった。
「一番恐れていたことが起こってしもうた」
牛之助が、寅五郎に付添っている利三郎に、ため息まじりに呟いた。入植して間もない頃で、消火装置などはない。助けを求めようにも、隣どうしが100メートルも離れていては、聞こえるはずもない。だからといって、氷点下の世界で火を使うなとも言えない。牛之助は、火事に無防備な開拓村の現状を嘆かずにはいられなかった。
翌日は朝から寅五郎の家の建て直しである。井上為吉や水田常吉など先発隊で小屋の建設にあたった“経験者”が、開墾を休んで骨組みに精を出した。豊次と嘉市は、音無川べりに生えている茅を刈り取った。屋根に被せるためだ。清水龍太郎と松尾露吉は、煮炊きに欠かせないくど(竈)作りのために、せっせと粘土をこねている。
寅五郎の新しい家は、1日足らずで完成した。鍋釜や寝具などは、各家から持ち寄った。
「心配せんでよかよ。私らがついとるけん」
シマは、毎日井上の家に通い、若い嫁のトキコを励ました。
「それより、お祖父ちゃんのことが心配で・・・」
定吉は、出火の原因を息子に責められたことが気になってか、その後言葉をなくしてしまったと言う。
「ところで、トキコさん。あなたひょっとして、おめでたじゃなかね?」
シマが遠慮がちに尋ねた。
「そうらしかですが・・・」
トキコは、うつむき加減に小声で答えた。こんな大変な時に子供を産むことが許されるわけがないと、考えているようだ。
「何ば言いよるね。こげん大変な時じゃけん、新しか命ば大事にせにゃならんとばい。大丈夫、私がついとるけん。早う平八さんに知らせんば」
トキコの妊娠は3カ月を過ぎていた。
その日は朝から雨。男たちは、雨天の日は体を休めることに決めている。だが、女たちには休みはない。朝はいつものように3時に起きて、叺を編んだ。日清戦争の勃発(明治27年7月)以後、噴煙を棚引かせている硫黄山の麓の工業所が活況を呈していた。そこに女たちが編んだ叺を持ちこむと、1枚3銭で買い取ってくれる。
夜鍋と早起きで3枚作れば、米を1升買えた。働き手や子供たちにひもじい思いをさせないために、シマやユキは、黙々と叺の折り目に針を突き立てた。
「青か鰯ば食べたか」
耕吉がまた無理なことを言いだした。耕吉は木佐木村を出る前の晩、家族全員の膳に「尾頭付き」の生鰯を載せて前途を祝ったことを覚えていたのだった。この山中では、新鮮な海魚など無い物ねだりである。このあたりで手に入るものといえば、塩をしっかりきかせた干し魚ぐらいしかなかった。
豊次が用事で山を下りた時、中村の町の店先を覗いていると、偶然そこに、生に近い鰯を見つけた。すぐに弟の顔が目に浮かんだ。店番をしていた 若い女が、豊次の汚い身形に顔をしかめた。すると奥から主人らしい初老の女性が出てきて、若い女をたしなめた。
.gif)
豊後中村の駅前通り
豊次から弟の話を聞いたおかみさんは、「安くしとくけん、好きなだけ持っていかんね」と語りかけてくれた。だが、中村から千町無田まで山道を3里も登っていかなければならない。急坂の野上道を、鰯を腐らさないでどうして運ぶか。
おかみさんは、豊次の心配を察して、鰯を厚紙で幾重にも包みこみ、氷をたくさん詰め込んでくれた。
日銭稼ぎ
明治28年に九重高原を襲った台風は、千町無田開拓団にとって計り知れない衝撃となって後々まで影響した。
その年の冬は特に雪の量が多くて、地面がまったく見えないほどに積もる日が続いた。森山辰次郎の家では、育てた農作物を売って現金収入をと考えていた矢先であり、家族は空腹と寒さで疲労が頂点に達している。
そんな寒い夜はありったけの衣類を身につけて、お互いの体を寄せ合いながら眠った。隙間風を防ぐために、壁面には藁や布切れを詰め込んだ。それでも凍てつく風がどこからか忍び込んできて襟元を襲う。北風が周囲の木々で高音を奏でると、降りしきる粉雪は容赦なく小屋の中で乱舞する。どんな防御策も通じなかった。
豊次が弟や妹に買ってやると約束した新しい着物も当面お預け。住む家も相変わらず掘立小屋のままである。未だに風呂も造れず、汚れたままの体で何日も過ごした。
父の辰次郎は、極貧の暮らしに疲れ気味で、寝込む日が多くなった。その分、長男の豊次の家族を守る責任の割合が膨らむ。豊次にとって今は、とにかく食べるため の金が欲しかった。
の金が欲しかった。
そんな家族の危機を救ったのが、皮肉にも明治27年に始まった日清戦争である。国にとって、硫黄山から採れる硫黄が、戦争を遂行するのに欠かせない燃料になっていたのである。鉱業所は、採取した硫黄を麓の町まで運び出す手段として、開拓団の若手労働力に目をつけた。
豊次のところにも馬の背に載せて運搬する仕事話が入ってきた。行程は硫黄山から雪深峠までの山道。峠は、千町無田を2里ほど下った湯ノ平の近くである。馬1頭に硫黄を2俵載せて運ぶと、1頭あたり25銭が貰える。
「馬を買おう」
豊次が父に相談した。
「そんな銭がどこにある。そんなことをしたら、肝心の開墾がでけんごつなるぞ」
辰次郎は、端から豊次の話に耳を傾けようとしなかった。
「ちょっとばかり借金すりゃ、駄馬なら買える。開墾の方は、硫黄運びから帰ってきてからやるけん」
それがどんなに困難なことか、豊次が一番よくわかっている。しかしこのままでは家族全員が、飢え死にしかねない。豊次は父の反対を押し切って駄馬を4頭買った。嘉市と2人で、2頭づつを牽いて、1日の稼ぎが1円である。米1升が10銭の時代、豊次にとって悪い話ではなかった。
豊次と嘉市の、硫黄運搬と開墾という「2足の草鞋」が始まった。今までより更に2時間早く起床する。起きたらすぐ馬に餌を与える。母のシマは、家族思いの豊次と嘉市の体を心配して、2人のご飯だけは特別に粟飯に米を半分混ぜた。
硫黄の採取場まで1里8合(約7㌔)。午前7時頃に着く。鉱業所に近づいただけで、強烈な臭いが鼻をつく。硫黄の入った叺を受け取ると、それを馬の背に載せる。重さは、1俵が約10貫目(37,5キロ)。

千町無田に残る硫黄運搬中継所跡
山を下って、吉部から家の近くの中継ぎ所を通り、雪深峠に到着するのが正午過ぎだった。馬に餌を与えた後、シマが持たせてくれた弁当を食べて一休み。
「しょうがなかよね、開墾がちょっとばかり遅れたっちゃ」
豊次は、父の反対を押し切ったことが気になっていて、荷を降ろした後に嘉市に同調を求めた。
家に着くのが午後4時を過ぎた。それから夕食の7時までが開墾の時間である。休む間もなく、草刈りや排水溝を造る。種まきも並行して行わなければならない。周囲が闇に包まれる時刻、豊次と嘉市の体はくたくたに疲れていた。
第四章 開墾につづく



![]()
![]()