|
長者原の白鳥伝説
牛之助は筑後川堤防の枯れ草に座り込んだ。旧正月を過ぎた頃である。あの時と同じ川なのに、どうして今日はこんなにも穏やかなのか。顔なじみが、すっぽり頭巾をかぶって黙々と釣り糸を垂れていた。土堤下の麦藁葺屋根の傍らでは、5歳くらいの女の子が若い母親に擦り寄って甘えている。
目を西に転じると、背振の山並みが。東に連なる耳納連山も、山肌をくっきり見せながら、筑後の里を見下ろしていた。ゆったりと流れる時の中でしばらく川面を見つめた後、屋敷に戻った。久留米西部の旧筑後川。後方は脊振山脈.gif)
留守中に麻生という男の人が訪ねてきたとツルが告げた。その客は梅林寺に泊まっているという。麻生と聞いてもすぐには思い出せなかったが、梅林寺と聞いてわかった。牛之助がまだ寺侍であった頃、訳ありげな浪人が梅林寺にやってきて、何日か匿ってやったことがある。浪人は、元豊後森の藩士だと言っていた。あの時二人は夜の更けるのも忘れて天下国家を論じ合ったものだ。
鳥飼の屋敷から筑後川岸の梅林寺までは20分とかからない。牛之助は着替えを済ませるとすぐに家を出た。
麻生幾次は、牛之助の到着を待ちかねたように、すぐに部屋へ案内した。
「久しぶりですなあ」
「その節は大変お世話になりました」
「なんの。それより貴殿は今どのようなご職業に?」
「未だ素浪人ですよ」
麻生は屈託なく笑った。牛之助が定職にも就けず、農民の苦しみを一人で背負っているような気負いの毎日に比べ、目の前の友人は「素浪人」を名乗ってはばかろうとしない。ありきたりの挨拶の後、麻生が続けた。
「私のふるさと豊後森は、1500㍍以上の高い山々を見上げる山里です。久留米など賑やかな街と違って静かなところですよ」
麻生は、まだ牛之助の知らない山間の生活を語った。話は尽きず、九重の山に伝わる伝説まで語ってくれた。
豊後の中村から山を登っていくと、標高900㍍のところに飯田高原がある。そこに昔、浅井長治と名乗る長者が住んでいた。長者には朝廷から「朝日」の称号が与えられていて、後千町・前千町の美田を幾千人もの使用人に耕させ、本人は贅沢三昧に耽っていた。長者の傲慢は、日を追うごとに激しさを増した。祝いの席で、こともあろうに鏡餅を的に仕立てて自ら矢を放つことまでしでかした。すると餅の的は白い鳥に変身し、何処かへ飛び去っていった。

朝日長者伝説のもとになった“鶴の墓碑”
「私の地方では、米は“福”と同意語でして、その福に矢を放ったのですから、長者のもとから福が去っていくのも当然のことです。それから間もなく、長者一族は大きな災難に遭って滅亡しました」
麻生は、話の後日談まで語った。長者の驕りの罰はそれだけでは済まず、あれだけ肥沃な土地が沼地と変わり、どんなに種を蒔いても作物が育たなくなってしまったという。
土地の人は、朝日長者が支配した高原一帯を「長者原」と名付け、荒地となった地域を「千町無田」と呼ぶようになった。白鳥が飛び去った場所には「白鳥神社」が祀られている。
「もう、千数百年も昔の話ですから・・・」
牛之助には、麻生の話しにでてくる「千町無田」という地名が妙に気にかかった。飯田高原といえば、いつも土堤から眺めている筑後川の源流である。水が湧き出る広い高原の土地に、米が一粒も稔らないとは不思議なことだ。牛之助は、友人の興醒めを覚悟で、昨年の洪水被害と被災者のハワイ移住計画のすべてを話した。
「そうですか。お気の毒に」
麻生は牛之助に同情しながら、言葉を継いだ。
「それで皆さん、どうなさいました。その後」
「どうにもなりません。ただ悔しがり、先行き不安に陥るばかりです」
牛之助の頭から、麻生が語った筑後川源流の話しがまだ離れない。
「青木さん、その人たち、千町無田を開拓する気はありませんか? お話ししましたように、そこは大そう厳しい環境ですが、国も官有地を解放して農地に変え、税収入を増やそうと考えているようですから」
牛之助の頭の中を見透かしたように、麻生が提案した。麻生が伝える情報とは、明治17年、農商務省が「興行意見、地方の部・大分県」を提起し、「原野を開墾し殖民を謀ること」を掲げ、具体的に10カ年計画を打ち立てることであった。
この夜の牛之助と麻生幾次の雑談は、これから始まる「千町無田開拓史」の、まさにプロローグであった。
移住の相談
麻生幾次が久留米を去って1ヶ月が過ぎた。牛之助は落ち着かなかった。そんな時、荒木村の川島利三郎や木室村の田中栄蔵を自宅に呼び出すのが習慣になっている。二人とも年齢が高くてハワイに移住できなかった者たちである。その後も連れ立って、牛之助の屋敷に来ては世間話を楽しんでいる。
今度は、栄蔵が木佐木村(現三潴郡大木町)の森山辰次郎を連れてきた。辰次郎はわずかばかりの借地を耕す傍ら、花筵の仲売り業をして家族を支えているという。
「兄貴の屋敷内に住んどるんですがね。かかあが、肩身が狭うて嫌だと言うんです」
辰次郎は、挨拶代わりに身の上話を始めた。
「18(歳)になる長男は、食い扶持減らしに兵隊にやりました。年頃の長女は久留米の織物工場に働きに出しとります」
昨年の洪水以来、自分が百姓のくせに食う米もないと愚痴った。
「先生、千町無田ちは、いったいどげなとこです?」
辰次郎が訊いた。
「そこでは、米はとれるとですか?」
続けて栄蔵が不安そうに質問した。
「俺も行ったこつもなかけん、はっきりしたことは言えん。だが、土地は肥えとると聞いたぞ」
突き放すように答える牛之助に、一同は悲しそうな顔をする。
「皆んな困っとるんだ。俺は明日にでも現地に行って、見てこようと思っとる」
妻のツルは、いともも簡単に行動に移そうとする夫を頼もしくも思うが、ハワイの一件もあり不安もそれ以上であった。
「今度はいつまで?」
ツルの問いにはまともに答えず、牛之助は旅支度を済ませると、もう歩き出した。栄蔵や辰次郎には、「行ったこともない千町無田のことなどわかるわけがない」と言ってしまったが、牛之助にはそれなりの予備的知識は持ち合わせていた。その後、麻生幾次から、何度か現地の様子を知らせる手紙を貰っていたからである。
手紙に書いてある内容は、10年前に現地の田野村役場が調べたものだという。写真:千町無田風景
「田野村の東方玖珠川の幹流を挟んで東西約8町(1.5キロ)、南北約19町(3.6キロ)、周囲54町(5.4キロ)、沼中ところどころに鬼頭、菅(カヤツリグサ科スゲ属の草木の総称、菅笠などの材料)等の草を生じ、鬼頭は藁の代用として縄となし、菅もまた藁の代用にして、筵・俵・叺等を作る。高地は低温のため藁の性が悪くて、これら雑草が貴重である」
続けて麻生は、千町無田の歴史的なことも付記していた。
「千町無田にこれまでまったく人が住まなかったというわけではない。記録によれば、正徳元(1711)年当時、入会の畑には、蕎麦・稗が花盛りであったそうな。当時は大豆・小豆・蕎麦・稗をつくり、三度の食事として稗飯・稗餅・蕎麦・そば団子汁を食していた」
その後も何度か開拓の試みがなされたようだが、いずれも成功しなかった。それほどまでに開拓が困難な場所だということだろう。
麻生幾次が親身になって知らせてくれる千町無田の情報が、牛之助をどれほど勇気づけたことか。
豊後路
鳥飼の屋敷を出立した牛之助は、筑後川に沿って、振り分け荷物を肩にかけ、豊後街道を颯爽と歩いていった。昨年の暮れに博多から久留米の対岸まで鉄道が開通したばかりで、大分方面への鉄道が完成するのはずっと後のことである。自分の足で歩くしかない時代であり、頼りは道案内人の筑後川だけであった。
当時久留米から大分までの街道は県道であり、それなりに整備されていた。現在の国道210号やJR久大線に沿ってはいるが、道幅は狭くカーブの連続であった。今その面影を探そうとしても困難である。
「俺は長旅には慣れている」
.gif)
うきは市吉井町 あたり
牛之助はそんなことを呟きながら、自らを励ました。ひと休みしようと座り込んだのは、浮羽の大石堰を見下ろすあたりだった。もう200年も昔、土地の庄屋たちが磔覚悟で久留米藩に嘆願し、筑後川から用水路をひき、一帯を水田に変えた話しを思い出した。その堰、改めて観察するとよくできている。大小の石を積み重ねて、流れが自然に取水口に向かうようになっている。石積みの堰の向こう側を、下流の自宅近くで眺めていたのと同じ4連筏がのんびりと下っていった。
この筏流し、天和年間(1681~84年)に日田の相良某が竹筏を組んで流したのが始まりだと、何かの書物で読んだことがある。筑後川の上流の山林で伐採された杉や桧など木材を急流に落とし込み、屈強の男が竹竿一本で舵をとりながら日田の集積所まで運ぶ。集積所に集まった木材を、長さ2間(3.6㍍)に揃え、蔓ででしっかり結びつけて4組連結する。連結された筏には、食料や寝具など家財道具を載せて、船頭が家具工場のある河口の大川まで運んでいくのである。

三隈川に集結した筏群(日田温泉あたり)
「おーい」
牛之助がありったけの声を張り上げて手を振った。声が聞こえたのか、船頭は持っていた長竿を思い切りこちらに向けて振り回した。
再び歩き出すと、間もなく急な上り坂にさしかかった。水が滝のように飛沫を上げて流れ落ちていた。眼下の急流を見て、登り道がきついはずだと納得する。現在の夜明ダム付近である。
筑後から豊後への入り口である虹峠を越えてしばらく行くと、四方から支流が合流する穏やかな岸辺に着いた。別名三隈川であった。
「ここが天領の日田か」
牛之助は日田でも一番賑やかな豆田の旅籠で草鞋を脱いだ。筑後では大分に通じる道を「豊後街道」と呼び、逆に豊後の人は、筑後への道を「筑後街道」と呼んでいた。

日田から玖珠町(戸畑)に通じる旧街道
翌日夜明け前に旅籠を出立すると、すぐに険しい山道にさしかかった。街道は、現在玖珠川の脇を走る国道210号線よりずっと北側の山伝いの、大分自動車道に沿っている県道あたりと思えばいい。道幅は狭く、曲がりくねっていて、急激な登り下りが交互にやってくる。
「高塚地蔵尊」の道標を見て、道中の安全を祈願する気になった。お参りした後、石仏の並ぶ本堂横の銀杏の巨木の下で遅い昼飯をとった。
急坂の参道をひっきりなしに参拝客が登ってきた。それら善男善女は、大銀杏の根元に、布切れで作った女性の乳房に似たものを置いて熱心に念仏を唱えている。
大昔、行脚中の僧・行基がこの霊木を発見したとされ、乳の出ない母親が拝むと乳が出るようになるとの言い伝えがあるからだ。高塚地蔵尊を後にすると、再び険しい上り坂が待っている。標高500㍍の大太郎峠にさしかかっていた。

高塚地蔵
峠を越えて、今度はなだらかな下り坂。そこから見える山並みは、鋭利な剣を逆立てたよう。少し進むと今度は優しい女性的な山に出会う。豊後の街道はけっこう旅人の目を楽しませてくれるものだ。
中村の旅籠・豊前屋についた時、もう周りの景色が見えないほどに暗くなっていた。
翌朝、宿に別れを告げて本格的な山登りとなった。雑木で覆われた山道は、旅には慣れているつもりの牛之助でも、少々心細い。筑後では見たことのない大きな鳥が、低くて野太い鳴き声をたてて飛び去った。果てしなく続く九十九折の道は、まさしく崖をよじ登る感じであった。
坂道と並行して流れる川の幅が極端に狭くなった。水の流れも、平野部とは比較にならないほど速い。その急流に幾筋もの小さな滝が落ちていて、日陰のところは凍りつき、青白く光っていた。氷の彫刻を見る思いである。木漏れ日が差し込む足元の苔の間から染み出る水滴が集まって小さな川をつくり、流れ下っている。
「これが筑後川の源流か」
そんなことを考えているうちに、牛之助は山登りの苦しさよりも、不思議な幻想の世界に紛れ込んでしまった。
.gif)
鳴子川沿いの渓谷に落ちる滝
やがて平坦な場所にでた。麻生幾次に描いてもらった地図によれば、そこから更にだらだらと登ったところが飯田高原である。目指す千町無田は、その飯田高原の東北部に位置する。
山道を登りきった牛之助は、筌ノ口の温泉宿で草鞋を脱いだ。部屋に入ると早速宿の主人を呼んで、千町無田を案内してくれるよう頼んだ。その夜は、鉄錆びを思わせる赤茶けた温めの湯に浸かり、すっかり旅の疲れがとれた気分になった。
千町無田踏査
「千町無田は、ここから更に1里はありますけ」
翌日、宿の主人は牛之助と肩を並べて東に向かって歩きながら、飯田高原周辺の説明を始めた。このあたり、明治22年までは田野村といい、最近いくつかの村が合併して飯田村となったところ。村役場は、現在の長者原のすぐ北の蕨原に設けられている。筌ノ口から真南に半里(2㌔)ほど離れたあたりである。
小さな集落を出るとすぐに一面の原野が広がった。
「昔、朝日長者という大変な金持ちがいまして・・・」

筌ノ口温泉
主人は、麻生幾次から聞いたことと同じ長者伝説を語り始めた。急ぐ旅でもないし、黙って聞くことにした。
「寒かでしょう?」
宿で借りたマントを羽織り、足は藁沓で防備しているが、氷点下の高原の冷気と風は自然と頬を強張らせる。
「ここが飯田高原です」
主人が立ち止まり、手を広げて範囲を示した。そこには、一面冬枯れのススキの原野が広がっており、高原を取り囲むようにいくつもの火山が連なっている。山々はいずれも真っ白い雪を被っていて、まるでよその国の景色である。しかも山の中腹からは絶えず白煙が上がっている。
長者伝説に出てくる「後千町・前千町」も、こうして現地に立ってみると真実味を帯びてくるから不思議である。
「千町無田は、この盆地です」
主人は、360度見渡せる高台に牛之助を案内し、ここでも両手を広げて、眼下に見える湿原地帯を示した。示された場所は、土がまったく見えない茅と葦だけの原野であった。自生する植物群は、人間の身の丈を遥かに超えている。
「この、葉にとげのある植物は何というんです?」
牛之助は高台を下りて、藺草に似た植物の名前を訊いた。
「この辺では、鬼頭といいますが・・・」
主人は、そんなことより目の前の客が本気でこの湿原を開拓しようと考えているのか、そちらの方が気がかりのようだった。悪いことは言わない、早めに諦めた方が身のためだと言いたげである。
「だめですか? ここを田んぼにしちゃあ」
牛之助が逆に質した。
「昔、朝日長者は、驕り昂ぶって、こともあろうに餅を矢の的にして罰があたったですよ。そのために、この土地はどげん開墾しようとしても作物が育たんようになってしもうた」
主人は、朝日長者の伝説を繰り返した。

長者原の湿原(開拓前の現地イメージ)
「この葦の下はどうなっていると思います?」
主人は葦の林を掻き分けて片足を下ろした。主人の足は、泡ぶくをたててたちまち股のあたりまで滑り込んだ。
「これが千町無田です。この広い草原の下は、みいんな沼のようになっています」
牛之助に手をとってもらい、乾いた場所に上がった主人が言った。
「伝説もじゃが、この水浸しの所をどうやって畑にするんです? 止めといた方がよかですよ」
なるほど、これは大変だ。筑後川の最源流域とはこのような湿地帯であったのか。火山灰が積もってできた土は、真っ黒くて粘っこい。いったん衣服についた泥は、少々のことでは落ちそうになかった。
「諦めますか?」
主人は、皮肉っぽい目で牛之助を見返した。
「いや、結論を出すにはまだ早い」
この湿地から水分を抜き取ったらどうなるのか、一面真っ黒の土で穀物は育たないのか。有り余るほどの雑草が役に立つことはないのか。
「寒かですよ、ここは。今日は晴れてちっとは温っかですが、ひどか時は雪が30センチも積もりますけ。気温も氷点下20度を下ることもあるけんですね」
牛之助は、主人の後ろ向きの話しに飽き飽きした。宿に戻ると、冷えきった体を時間をかけて温めた。湯船のすぐ脇を、鳴子川が名前のとおりの騒がしい音を立てて流れ下っていた。見上げると、満天の星が今にも地上に落ちてきそうで思わず首をすくめた。

筌ノ口温泉そばを流れる鳴子川
宿の主人は、「開拓は止めたほうが身の為」と言う。しかし、明日の暮らしもおぼつかない筑後の農民のことを考えると、主人の忠告に素直に従うわけにもいかない。
牛之助は、筌ノ口温泉を基地にして、1週間かけて千町無田の湿原を歩き回った。寒い高原の気温でも、日中は何とかなる。だが、陽が沈むと極端に寒くなる。温暖な筑後の平地でしか暮らしたことのない者には、想像を絶する寒さである。こんなに水が冷たかったら、苗代田もつくれまい。しかし、工夫すれば何とかなるかもしれない。湿地から水をぬけば野菜を作る畑にはなるだろう。地質は、火山灰の上に古代から堆積した枯れ草が、自然の肥料をなしているに違いない。水はあり余るほど。枯れ草は牧草にむいている。
問題は、筑後平野にしか住んだことのない連中が、故郷を離れて、我慢して永住できるかどうかだ。
湯から上がると、川島利三郎に宛てて手紙をしたためた。
「運輸の便、格別に険悪ではない。土は黒色、中央に川があり、腐植土だから窒素分は申し分なしとみる。周囲には草が多く生えていて牧牛にも適している」
牛之助が、湯船の中で移住・開拓を決意した内容であった。久留米を出て半月、海抜900㍍の飯田高原は、冬真っ只中であった。
分水嶺
矢は放たれた。利三郎に「開拓はいける」の手紙を書いたその時、牛之助はもう後戻りのきかないことを自覚した。ひとまず久留米に戻って休もうなんて心の余裕はない。牛之助は早朝、筌ノ口温泉を出て、山を下った。
登ってくる時には気がつかなかったが、眼前に豪快な滝が落ちている。名を「振動の滝」といい、落差は80㍍もあると、昨夜宿の主人に聞かされた。 滝の周囲は断崖絶壁をなし、黒松や樅・栂・楓・欅など大木が鬱そうと茂り、枝が地面すれすれまで垂れ下がっている。
.gif)
写真:振動の滝(雌滝)
滝は、雄滝・女滝と並んでいて、水飛沫を巻き上げながら、お互いに容姿を競っていた。雄滝はいかにも荒々しく滝壺を叩きつけ、女滝はしなやかに飛沫を衣の裾のように表現している。ひととき滝の美しさに見とれた牛之助は、思いなおしたように立ち上がると、森町(現玖珠町森)にある玖珠郡役場に急いだ。
役場は、旧久留島藩のお城の一角で、陣屋跡に茅と瓦の屋根が交互に連なった大きな建物であった。現在の三島公園で、童話の父として慕われた久留島武彦を顕彰する「わらべの館」や「童話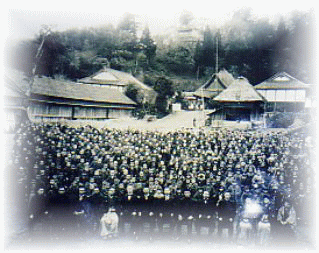 の碑」が建つあたりである。 の碑」が建つあたりである。
「駄目ですよ、あそこは」
千町無田を開拓したいという牛之助の下相談は、応対に出た役場の職員によって一蹴された。郡レベルでは埒が明かない。牛之助は役場を出ると、その足で大分県庁に向かった。玖珠郡役場から大分まで10里(40㌔)の険しい山道である。写真:玖珠郡役場(久留島記念館提供)
何度か上り下りを繰り返しながら峠を越えると、それまで西に流れていた川が、東に向きを替えている。筑後川ともここでお別れ。川上という集落を抜け、1583㍍の由布岳に向かって登っていった。
所々に農家らしい藁葺屋根が見え隠れするが、それもすぐに途切れて、あとは雑木と高山植物、それに野鳥たちの騒がしい鳴き声だけの世界となった。
由布岳を右に見ながら、半周する形で城島高原から湯の町別府に降りていった。そこから先は波静かな別府湾を左手に見て、旧大分城内にある(現大分市府内)県庁に急いだ。
県庁に着くなり、係官を通じて口頭で、千町無田の「開拓」を願い出た。応対に当たった係官は、しばらく待つようにと言ったきり、いつまで待っても戻ってこない。催促すると、給仕らしい若い職員が出てきて、「あれは受け付けられないそうです」と、間の抜けた小声で告げた。

写真:府内城跡
「そんな馬鹿な、さっきの係官は?」
「柴山さんなら帰られました」
応対する職員に、柴山三雄なる係官の住所を聞いて、彼の住む官舎に出向いた。玄関に現れた柴山は、迷惑そうな素振りをみせながらも、仕方なく応接間に招き入れた。
「郡が駄目と言えば県も駄目です」
「何故駄目なのか」「あんた、開拓にいくら資金が要ると思っているんだ。それに役所が関わらないで、農民をどのようにして統率するというんです?」
柴山は、同居する家族の手前か、役所内での横着な態度ではない。
しかし、口にする内容は、役所のときよりなお冷たかった。
「金は用意する。他に何が必要か。筑後では餓死する者も出ている」
「それは関係ない」
「関係ないとはどういうことか。それでもあんたは人間かっ」
引き下がれない牛之助は、もう帰ってくれと言いたげにそわそわする柴山を無視して訴え続けた。
「あんたは、私が大分の人間じゃないので、嫌っているんじゃないですか?」
「冗談じゃない。実は前にも、士族の仕事を確保するために勢場原というところで移住・開墾を計画したことがある。資金も土地も技術員まで県が提供したんだが、まったく成果を挙げないうちに頓挫してしまった。ましてや資金も技術もおぼつかないあんたたちが、あの広い湿地をどんなにして開拓しようというんです?」
柴山も、座りなおして剥きになった。柴山の話は、北海道の屯田兵や久留米藩士の安積開拓と共通するもので、原野の開拓は純然たる民間人の事業としては成り立たないのだと言いたいらしい。
「だからといって、計画書も見ないで無理だと決め付けるのは、やっぱり他県人への偏見としか思えない」
二人の議論は、すれ違ったまま夜更けに及んだ。翌日大分を出て久留米まで、帰る35里(140㌔)の道のりは遠かった。どうすればいいのだ。俺の説得に何が不足しているのか。
2日後に自宅に着いた牛之助は、妻のツルにも、いきさつを伝える気力を失っていた。
「千町無田の現地を見てくる」と言い残して家を飛び出してから、既に1ヶ月を経過していた。
遭難未遂
翌日牛之助は、柴山の言い分など無視して「開拓出願書」の作成にかかった。出願の趣旨は、千町無田を含む飯田村東部一帯の払い下げである。願主(申請人)は、藩時代の同僚武士や知り合いの商人などに名を連ねてもらった。また、奥書人(推薦人)は、水害の被害が大きかった上津荒木村の村長と、地元である鳥飼村の村長に引き受けてもらった。
大洪水から1年が経過しようとしている明治23年4月4日、出願書を大分県知事宛に送付した。だがその返事は日を置かずして「却下」の二文字で返されてきた。
牛之助は、間髪を入れずに2回目の出願書を送付した。今回は願主のほかに、移住希望者106名の署名捺印を添えた。奥書人も前の2人に加え、開拓現地の玖珠郡長と飯田村の村長にも加わってもらった。牛之助が、両名に粘り強く訴えた成果である。
だが、2回目の出願も、「聞き届け難し」との詰めたい返事であった。やはりあの柴山の嫌がらせかと思わずにはいられなかった。こうなれば、やれることをすべてやるしかない。
牛之助は、昨年開通したばかりの九州鉄道(現在のJR鹿児島本線)に乗って、福岡県庁に出向いた。当時久留米から博多までの所要時間は1時間20分であった。
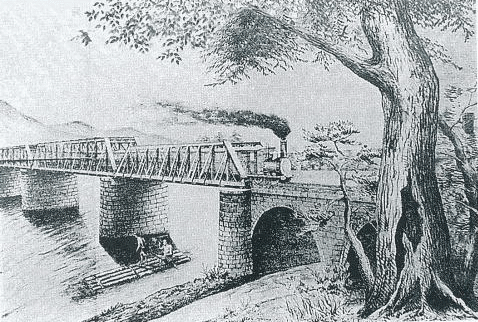
明治に筑後川を渡る蒸気機関車「クラウス号」 下には筏流しが見える
県庁ではまず、農商務課の係官に面会を申し出た。
「私ごとき士族の端くれが、大分県と直接交渉しても埒があきません。あの忌まわしい大水害から間もなく1年がたとうとしていて、農民の苦労も限界です」
何とか福岡県としてのご助力を、と薄くなりかけた頭を何度も下げた。大分と違い福岡県は身内である。係官は、知事から大分側に訊いてもらおう、と答えた。
筋を通すとはこういうことか、大分側から間もなく返事がきた。すぐに「願い主」である青木牛之助の身元調査を開始するという。
牛之助はまた福岡に出かけた。
「待っとったとこです。県としてもあなたたちの移住開墾の件について関心があります」

湯平温泉
係官は、農商務課の小笠原といい、牛之助といっしょに千町無田の現地を確かめたいと言った。
7月の暑い日、筌ノ口で待っていると、小笠原が玖珠郡役場の本田と名乗る役人と連れだって山を登ってきた。3人は千町無田開拓予定地の一応の調査を終えて、3里ほど離れた湯平温泉に出かけて酒を酌み交わした。その費用はすべて牛之助もちである。
酒肴のせいか、宴席では小笠原と本田が、牛之助の志を高く評価した。牛之助も褒められて悪い気はしない。これで願いが通じるだろうと楽観的気分に浸った。
12月に入って、久方ぶりに大分から呼び出し状が届いた。今回の大分通いが何回目になるのか、しかし今回は足が軽かった。牛之助はいつもの旅姿で、また筑後川を遡っていった。途中日田で一泊して歩き出すと雪が降り出した。夕方近く由布岳を登る頃には、横殴りの粉雪が激しく顔面を叩いた。視界はほとんどきかないし、峠を越えるのに最悪の天候となった。路面に積もった雪は膝まで埋り、前に進めない。だからといって、引き返しもままならない。
「俺の運命も、ここまでか」
寒さと強風で震えが止まらず、山陰に待避している間、牛之助は深刻に自分の一生を振り返った。少し風が収まったところで、また歩きだす。このあたりの雪はどのくらい積もっているのだろう。もう、路肩と並行して流れる川の区別すらできない。
地蔵橋付近まで来たとき、突然足元のバランスが崩れた。あっと言う間に40-50㍍下の谷底に落ちていき、そのまま気を失ってしまった。どのくらい時間が経ったか、自分がまだ息をしていることに気がつく。おそらく死神に、「こちらに来るにはまだ早い。やり残していることがあるだろう」と、追い返されたのかと、苦笑いした。
打ち身や擦り傷であちこち痛いのと、見る見る積もる雪のために一歩も動けない牛之助は、岩陰にうずくまりながら、若い頃から嗜んできた和歌をつくり、大声で詠みあげた。
豊国の 積もる雪をも尺八や 谷間に落つる鶯の声
陽が落ちて、あたりが暗くなり、寒さも倍加してわが身を締め付ける。力を振り絞り、指先とつま先に神経を集中して小枝を掴み、岩の安定度を確かめながら、谷底から這い上がった。持ってきた提灯は転落したときにバラバラに破れて役にたたない。わずかばかりの雪明りを頼りに、猛烈な横風を受けながら、一歩また一歩別府に向かう。
地獄に仏、遥か前方に薄明かりが見えた。灯は、いつも立ち寄る峠の茶屋からであった。
.gif)
写真:別府市に通じる鶴見岳付近の茶店(イメージ)
「爺さんっ」
重い引き戸を開けたとき、中からいつもの主人が現れた。
「どうしたんだ?こんな日に」
主人は、60歳を過ぎたくらいの柔和な顔を、心配そうに牛之助に向けた。
「無茶なことを・・・」
主人は話しを聞いて、牛之助の無謀を諌めた。そして、暖炉の火を精一杯強くして熱い湯を沸かしてくれた。その夜は、茶店に泊めてもらった。
翌日は雪もやみ、くっきりと稜線を見せる鶴見岳を目の前に置いて、また歩きだした。
難関の開拓申請
牛之助は、大分県庁に着くなり柴山に面会を求めた。柴山は、久留米から35里の山道を、大雪のなか悪戦苦闘してたどり着いた牛之助を労おうともしない。
「だいたいね、あんた、役所を何と思っとるのかね」
逆に、喧嘩腰で突っかかってきた。柴山の言っている意味がさっぱり理解できなかった。
「あんたが頼むと言うから親切にしてやっているのに、何かといえばすぐ福岡の方(県庁)に泣きつく。私らを信用していないのか」
柴山の怒りは治まりそうにない。そんな文句を聞かせるためにわざわざ大分まで呼び出したのか。こんな時牛之助は、相手をなだめて自分のペースに引き込む術を知らなかった。
「それは違う。大分側でちゃんと私の願いを聞いてくれるなら、わざわざ福岡まで出かける必要なんかない。百姓たちが飢え死にしかかってるのに・・・」
牛之助は剥きになって反論した。
「また、泣き落としか」
柴山は、「農民の困窮」話しになると、相変わらずのうんざり顔になる。これ以上柴山と口論していても空しさが増すばかりであった。
「申請書中、吉部地区には既に出願者がある。申請から吉部をはずすように」
柴山の口から予想だにしなかった言葉が飛び出した。牛之助が開拓予定地として考えていた 千町無田とは、見渡せる盆地一帯のつもりだった。もちろん、比較的土が乾いている吉部地区もその範囲内である。吉部地区を除けば、ほとんどが沼地同様であり、開拓可能な面積も極端に狭くなる。それでは移住希望者の120戸を全部収容することなど無理な話だ。ハイウェー脇の看板 千町無田とは、見渡せる盆地一帯のつもりだった。もちろん、比較的土が乾いている吉部地区もその範囲内である。吉部地区を除けば、ほとんどが沼地同様であり、開拓可能な面積も極端に狭くなる。それでは移住希望者の120戸を全部収容することなど無理な話だ。ハイウェー脇の看板
「どうすればいいんです?」
牛之助は切羽詰った表情で柴山に迫った。
「森町の北側の山に何ヶ所か官有地がある。あそこあたりを調べて願書を出し直したらどうだ」
柴山は、精一杯の助言だよ、と言った。
「吉部地区に私らより先に目をつけたのは誰です?」
牛之助の質問に、なるべくなら答えたくないという態度の柴山は、しばらく沈黙した後に重い口を開いた。
「・・・大分牧場」
大分牧場といえば、会社組織で、飯田高原一帯を牧場化しようと計画しているあれか。そういうことだったのか。牛之助は、出願する開拓予定の範囲すら正確に把握していなかった自分を恥じた。
「吉部地区」とは、現在のやまなみハイウェーのすぐ東側の草原である。そこは当時から比較的水分の少ない場所であった。
「株式会社大分牧場」は、東京の酪農家や地元万年村の大地主、それに熊本県人などが共同で願い出て国有地100町歩を借り受け、資本金1万2000円で設立したもの。東京の前田牧場の技術を取り入れたことを宣伝材料にしていると聞いている。
ずっと後の話しになるが、大分牧場は牧場建設と併行して60町歩の原野を開墾し、各地から入植者を招いて、新しい「吉部」を誕生させようとした。しかし、当時の牧場技術はまだ幼稚で、その後のさまざまな困難に耐え切れず、志半ばで撤退することになる。
大資本による牧場計画は失敗したが、大分牧場が開墾した国有地は、その後の村民の生活に多大の利益をもたらした。また、彼らの実験は、それまで「牛飼い」として蔑視されていた牧場経営者を、「畜産農家」に格上げさせる効果をももたらした。その点では、牧場経営としては失敗したが、功績は大きかった。
役所としては、同じ開拓を許可するなら、自らの痛みを伴わない大企業の方が無難なのであろう。筑後の貧乏百姓の手作業による開拓では、あまりにもリスクが大きすぎると考えているに違いない。
大分県庁を出た牛之助は、昨日大雪の中を歩いた疲れも重なって、足がなかなか先に進まなかった。ハワイ移住に漏れたあと、農民を救済する道はもう九重高原の開拓しか残されていないのだ。
ともすれば後ろ向きになりがちな気持ちに鞭打って、柴山が助言した森町の北方日出生台に向かった。そこで、福満山・黒灰・小麦が原・人見岳など官有地を一人で見て回った。
5ヶ月たって提出した3回目の出願書の「開拓予定地」には、柴山に言われたとおり吉部地区を外し、調べ上げた日出生台一帯を加えて提出した。

日出台の山岳地帯(大分県玖珠町)
大洪水の翌々年、明治24年の年明け早々、福岡県庁から呼び出し状が届いた。「大分県庁から返事が来ているので通達したい」という内容であった。牛之助はそれなりの期待を込めて九州鉄道に乗り込んだ。
「貴殿より出願の件、資本不足につき不許可」
係官から言い渡された大分県庁からの返事とは、情けないくらいに短く冷たい内容であった。牛之助はその場にへたり込みそうになるのを我慢して、福岡県庁舎を後にした。
何ということだ。俺は何のために久留米と大分の間を繰り返し往復してきたのか。牛之助は帰りの列車の中で、当局に対するというよりは自身の非力さに腹がたって仕方がなかった。こうなったら、役所が首を縦に振るまでとことん闘うしかない。「資本力不足」なら、金蔓を探せばよい。
かつて知り合いの、三潴郡三又村(現大川市)で酒造りをしていて羽振りのいい中村和三郎を訪ねた。中村は、いとも簡単に「金主」になる事を引き受けた。もちろん成功報酬の魅力に惹かれてのことである。だが数日たって、いったん引き受けた話しをご破算にして欲しいと言ってきた。どこからか横やりが入ったらしい。
仕方がない、別の金持ちを探すことにした。久留米の通町で呉服屋を営む青沼太平に頼んだ。青沼は古くから懇意にしていたこともあって、「金主」になることを承知した。
山岡鉄舟の尽力
金主は見つかっても、それだけで開拓が許可されるとは思えない。牛之助は、「大物」に根回しを頼む事を考え、その年の3月20日に東京へ向かった。ハワイ移住出願以来2年ぶりの上京である。
東京駅を降り立つと、今度も牛込の道林寺に向かった。東洲和尚は牛之助の再訪を喜んだ。
「あんたも立派じゃな。ハワイで不十分なら、今度は筑後 川の源流ですか」 川の源流ですか」
和尚は半分呆れ顔で牛之助の話を聞いた。翌日、和尚に書いてもらった紹介状を懐に、再び山岡鉄舟の部屋のドアを叩いた。写真:山岡鉄舟像
「諦めるんじゃないぞ。君がやろうとしていることは、政府でもなかなかできん立派なことじゃからのう」
門前払いも覚悟で出かけたこともあって、山岡鉄舟の激励がとても嬉しかった。
「わしが君の力になろう。だから、もう一度出願書を出しなおせ」
喜び勇んで帰郷した牛之助は、その足で大分県庁へ。
「何度来ても無駄だよ。一度出した不許可の決定がひっくり返ることはない」
応対に出た柴山は、薄ら笑いを浮かべながら牛之助を追い返そうとした。
「今に見ておれ」
そこでは山岡など大物の名前はいっさい出さず、出願文書を手渡すだけでさっさと県庁を後にした。
上京の成果はすぐに目に見えた。東京から農商務省の小林という技師が現地視察に出向くとの知らせを受けた。山岡にあった日から3ヵ月後のことである。ここをおいて再びチャンスは巡り来ないだろう。牛之助の人間業を逸した行動が開始されるのは、その直後からであった。彼が書き残した日記である。
明治24年7月11日 小林技師の現地調査に立ち会うため夜を徹して大分へ。
7月12日から3日間 同技師に随行して千町無田から日出生台周辺を検分。検分を終えると、金の工面をするため、夜中に久留米に引き返す。
7月16日夕刻 久留米を発って再び千町無田へ。
7月17日昼頃 到着すると、待っていた小林技師に会う。
7月18日と19日 終日雨で動けず。
20日 小林技師と連れ立って、森町の寺で役場が設定した地元農民との懇談会に出席。その日出席した者75人。他県の農民による開拓を地元がどう受け入れてくれるか、大いに議論を戦わせた。

城下町の面影が残る森町(玖珠町)
21日 交渉に必要な資金の算段のため、夜を徹して久留米に。
24日 小林の労苦を労うために湯の平温泉へ。そこで1泊。
25日 夜が明けると千町無田に取って返し、村民と話し合う。村民たちは、筌ノ口温泉の主人が何度も繰り返した、「長者伝説にあるとおり、千町無田の開拓は無理だ」を持ち出して、それでも開拓を強行するのかと迫った。牛之助は、「そんな迷信は信じるに値しない」と一蹴した。同席した小林技師は、「あんたの言うようであれば、世の中に不思議というものは存在しないことになる」と言って大笑い。
26日 湯ノ平で技師一行と別れる。牛之助は単身森町役場に出向き、検分の状況を報告。
27日 鳥飼の自宅に帰る。
28日 総代の西村常次郎と中村為吉が自宅に訪ねてきて進捗状況を訊いた。
29日 福岡県庁へ。現地調査に同道した小笠原に会い、農商務省技師との行動を報告。小笠原は、払い下げ許可に向けて着実な手応えを感じた模様。
30日から8月8日 10日間かけて、福岡県庁で詰めを怠らないための出願書の点検。
9日 久留米に帰る。
10日 急ぎ豊後へ。
12日 野上村(現九重町)役場で村長の奥書を貰う。前回までに鳥飼・上津荒木両村長、それに玖珠郡長と飯田村長(現九重町)の奥書は貰っている。念には念を、地元村長の推薦は多いに超したことはない。これも、福岡県庁の小笠原の知恵である。
14日 日出生村。
15日 小畑氏に面会。
16日 森町に戻る。
17日 大分へ。
18日と19日 大分県庁で野上村長などの奥書を提出し、柴山ら係官と交渉を重ねる。
21日 大分を出て森町へ。
22日 玖珠郡役場に県庁との交渉経過を報告。
24日 大分に引き返す。
25日 大分県庁の平田・行掘・岩崎氏を訪問して直談判。
27日 県庁に立ち寄った後久留米に向けて出発。
29日 ようやく久留米の自宅にたどり着く。2日間自宅で休養。
9月1日 汽車で福岡へ。小笠原氏の自宅を訪ねて大分での出願行動を報告。
2日-7日福岡県庁で、昼は書類の調査、夜は係官との話し合いを続ける。
8日 自宅で、西村など同盟者(総代)と協議。1日休んで豊後へ出立。
12日 到着早々玖珠郡役場へ。その後現地調査で馴染みになった本田・江頭氏らの自宅を訪問。
13日 大分県庁に出頭。
14日 1日かけて県の役人堀・平田・岩崎・安部氏宅を訪問して懇談。
16日 千町無田へ。橋爪氏の自宅に宿泊。
18日 森町の加藤氏の家に宿泊して懇談。
20日 久留米の自宅に帰る。
21日-22日 自宅で同盟者と打ち合わせ。
23日-26日 福岡に滞在。帰宅。
10月1日-7日 福岡滞在。
16日 金主の青沼太平に報告。
20日 大分着。
29日-11月11日 福岡県知事から大分県知事に事情を照会したことが判明。急ぎ大分県庁へ。大分県庁で堀・平田・安部・岩崎といった馴染みのメンバーに出願書について77ヶ所にわたって尋問を受ける。一つ一つ丁寧に答える。
11月13日 ようやく開放されて森町へ。
14日 玖珠郡役場。
15日 江頭氏。
16日 野上村役場でそれぞれ途中経過を報告。
18日 久留米の自宅に帰る。
21日-12月5日 福岡滞在。大分県庁での尋問事項について再検討。福岡県庁側と相談を重ねる。
12月10日 豊後へ向けて出発。
11日 玖珠郡役場。
.gif)
別府鉄輪温泉
14日 千町無田。
15日 日出生村を経て。
18日 別府の鉄輪温泉に泊まり疲れを癒す。
19日 大分県庁に出向くとまた尋問。
開拓許可所
明治24(1892)年も暮れようとする12月23日。久しぶりに鳥飼村の自宅で寛いでいると、大分県庁から電報が届いた。内容は、「出願書が受理された。次の指示があるまで待て」と。
行く手にかすかな灯が見えて、牛之助は率直に喜んだ。この時、払い下げ許可を受けたのは、千町無田と森町字黒灰・福万山・人見岳の原野で、総面積は1800余町歩であった。
明治22年の大洪水から2年半。長かった。自分も頑張ったが農民たちも耐えた。何故に、ここまでことがスムーズに運ばなかったのか。牛之助は考えた。出願書を受け取った役所は、柴山が言うように、何ヶ所にも分散した山岳地や沼地を、民間レベルで開拓するのは無理だと判断したのかもしれない。また、果たして現地の人間が、よそ者の開拓を気持ちよく受け入れるものか。そんなこんなで、役所自体が許可の判断を迷った結果が、こんなに時間を食ってしまったのだろう。
それより何より、役人は開拓予定地が農地として不向きであると断定していた向きもある。初めから、失敗が予想されるものに役所は協力しない。牛之助は、その役人の固い頭に真正面からぶつかった。開拓予定地近くの住民と徹底的に話し合ったのも、他県人への偏見を少しでも薄めようと考えての行動であった。
また、役人には、被災農民の現状を訴え続けることで、協力にまでいたらなくても、出願行動の邪魔をさせないことを心がけた。
石頭の役人も、片道35里(140㌔)の山道を、久留米から大分へと昼夜をかまわず通い続けて議論しているうちに情が通うようになった。今では相互に友情のようなものさえ芽生えている。
牛之助の多忙は、開拓の許可が下りてからが本番である。筑後での準備や資金の工面など。大分に行けば、県庁との間に書類の整備、現地住民との話し合いでひと時も休む間はなかった。
未だ手付かずの開拓予定地に立つこと何度目だろう。その都度、「この沼地が本当に水田に変わるのだろうか」と不安になる。引き返しのきかないところまで来ても、確信が揺らぐのである。
それから更に2年が経過。明治26年の暮れ、牛之助は正式に払い下げ(開拓)許可書を受け取った。筑後川大洪水から4年半が経過していた。
農民との契約
開拓許可が下りてからが、実は牛之助にとっての仕事の本番でもあった。
まず、洪水被災者が今なお移住を希望しているか、改めてその意思を確認しなければならない。また、個人単位の農業の経験しか持たない彼らが、集団生活を乱さずに開拓に参加できるか、その精神力も見極める必要がある。
大分県当局との「予約買い受け人」となる西村常次郎ら「総代」仲間と協議を重ねた。総代は、開拓希望の農民に、県から払い下げを受ける原野を又貸しする。その代金として1町歩(1㌶)あたり金3円を徴収することを決めた。貸与する土地は、1人(戸)最大3町歩まで。無事契約どおりに原野開拓が成就した時、土地は無償で分配される、という仕組みであった。
牛之助は、洪水直後に立った筑後川の土堤に、今日も上がってみた。大川は相変わらず穏やかである。夜を徹して豊後大分まで行き来すること37回、昨夜ツルがその回数と家から持ち出した金銭の額を教えてくれた。
千町無田や日出生台など調査に必要な枝道を加えて、4年間で大凡2800里(10,200キロ)を歩いた。これは、久留米から東京まで徒歩で5回も往復した計算になる。よくも歩いたものだと、我ながら感心する。
牛之助は、土堤下に生えている葦の葉を1本抜き取ると、さも大事な宝物を手にしたように帯にさし、瀬下の水天宮に向かった。移住する農民たちの心の支えになってくれるよう、神頼みであった。
大分県知事と総代との間に契約書を交し、実地の引渡しを受けたのは、大洪水から実に5年近くも経過した明治27(1894)年3月26日であった。
契約書には厳しい条件がつけられた。
「(契約日から10年後の)明治37年2月までに150町歩の開墾を必ず終了すること」
牛之助はまず先発隊を編成した。次に、総代と入植農民との約束事を決めた。途中でわがままは絶対に許されない。不要不急の財産は移住前にすべて処分して換金すること。共通の経費を確保するために、一定の拠出に応じることなど、牛之助が作った条文は26項目に及んだ。川島利三郎・田中栄蔵・石崎熊蔵の3人は、牛之助の手足になって入植の準備に駆け回った。
先発隊
選ばれた先発隊27人が、水天宮の境内に集合した。世の中に日清戦争の陰が漂う明治27年の早春であった。
現地に着いたら、何より先に住む場所を確保しなければならない。そのために必要な大工道具や寝具などを用意した。次に、開墾する鎌・鍬・作業着・食事に必要な炊事道具など。開墾が進めば、その時蒔く種など、当座の生活用具も加えて10台の車力に積み込んだ。
遠くは矢部川上流の黒木町や串毛村からも、女房や子.gif) 供たちが見送りのために水天宮に集まって来た。写真:久留米水天宮本殿 供たちが見送りのために水天宮に集まって来た。写真:久留米水天宮本殿
「向こうのこと、頼りば待っとるけんね」
「家のこつは心配せんでよかよ」
「早よう、迎えにきてね」
一家の大黒柱と家族のしばしの別れであった。当代でいう「単身赴任」する家族を見送る風景である。
先発隊全員が道中の無事を祈って本殿に額ずいた後、いよいよ青木牛之助を先頭に車力は動き出した。
「父ちゃん!」
車力部隊は、父親との別れが辛くて泣き出す幼な子らを振り切って、筑後川の上流を目指した。
日田と豊後中村に一泊した一行は、険しい野上道を汗びっしょりになりながら登っていった。途中北方の集落を通過する頃、「何じゃ、家があるじゃなかか。人一人住まん山ん中かち思うとったら」
下荒木の田川与吉がおどけてみせた。案外、彼の本音だったかもしれない。
鍬入れ
「ここば開墾するとですか」
千町無田に着いて、まず上津荒木村の木戸伝六が奇声を発した。見渡す限りの茅と葦と鬼頭の荒野である。眼前に聳える火山群のすべてが真っ白い雪の帽子を被っていた。高原は3月でも真冬並みに寒い。周辺の植物が芽吹くのはずっと先のようだ。
「文句ば言うな」
道中のまとめ役を努めた大善寺村の光山亀吉が伝六を諌めた。
「まず、今夜寝る場所ば作らにゃならん」
牛之助が、早速仕事の段取りを指示した。仮小屋を建てるには、なるべく湿気の少ない場所を探さなければならない。乾いた土地は開拓予定地から少し離れた北側の山(崩ノ平山)の斜面にしか見つからなかった。
小屋を建てるのに斜面を利用すると一方の壁造りが省略でき、強い北風を避けるのにも効果的である。近くの山から手ごろな木を切ってきて、とりあえず柱を立て屋根を組み立てた。屋根の上には枯れ草をのせ、近くに転がっている小石で、屋根が吹き飛ばないように固定した。
小屋の周りには幾筋もの溝を掘った。外から雨水が入り込まないための手当てである。立ち上がった家は、まさしく掘立小屋であった。
冷えきった土間には、枯れ草を幾重にも敷き詰めた。大工仕事の経験を持つ上広川村の井上為吉や水田常吉などが手際よく仮の小屋を3棟作り上げた。
牛之助が、手の空いている者数人を連れて出ていった。寒さを凌ぐために、燃料の調達である。役場の世話で、不要になった廃材を集めた。その間、食事班は夕食の準備にかかる。
夕日が山陰に落ちると、周囲が急速に暗くなった。同時に冷気が襲ってきて、外で働いていた連中が、出来立ての掘立小屋に駆け込んできた。持ってきたランプに菜種油を注ぐと、小屋の中がパッと明るくなった。中央の囲炉裏には、枯れた枝や草を思い切り放り込んだ。
入植第1日目の朝は、夜明けと同時に起床。川島利三郎の掛け声で、3棟の小屋から全員がはじき出された。空は真っ青に晴れ上がっている。火山群の間から昇る太陽に向かっていっせいに柏手を打った。その後小屋に入り、中央に仮祀りした水天宮に頭を垂れた。
「よかか。今日からは皆んな兄弟ぞ。喧嘩はご法度じゃ。知恵のある者、力持ち、足の強か者、それぞれ出し惜しみばせんで、仕事ばせにゃでけんぞ。俺たちには時間がなか。てきぱきとな」
牛之助は、ここに来て初めて訓辞を垂れた。先発隊が開墾する原野は、すべてが開拓団共有の土地になるとあらかじめ申し渡してある。

花牟礼山
木室村の田中為吉や豊岡村の水田常吉は、昨日に続いて、今度は長期滞在に耐えうる小屋の建設にかかった。小屋といっても柱を組み立てて木や竹を編み、その上に茅を載せるだけのもので、それを5棟造る計画であった。
小屋の骨組みには孟宗竹や木材が必要になる。山中の倒木を運ぶため、水尾鉄三郎と田中為吉ら5人が車力を牽いて出かけていった。孟宗竹を分けてもらおうと、清水龍太郎と松尾露吉が、途中で見かけた一軒家を尋ねたが、体よく断られた。何軒目かの家で庭仕事をしていた老人が、丈夫そうな竹を5本だけ分けてくれた。
「俺が住んどった大善寺じゃ、竹なら腐るごつあったばってんな」
龍太郎は、老人の親切に感謝しながらも、癖のブツブツが始まった。食事は、筑後を出るとき持ってきた食材で当座を凌ぐ。それでも足りないものを、1里離れた筌ノ口の農家に頼んで分けて貰った。
田中栄蔵らが小屋の建設に精を出している一方で、石崎熊蔵たち開墾班は、泥濘に足を膝まで沈めながら、茅や雑草を刈り取る作業にかかっていた。特に鬼頭は、縦に走った筋が硬くてなかなか切れない。凍てつくような泥水に足をとられながらの作業である。10メートル進むのに1時間を要した。気がつけば、陽が落ちる時間である。
刈り取った草は大事に積み上げた。堆肥にして土地改良に役立てるためである。枯れ草を刈り取ると、その下から真っ黒な泥が浮かび上がった。太古から降り注いできた火山灰である。
まず、泥土から水分を抜き取る。そのために、山側から下方に向けて2尺(60㌢)ほどの深さで溝を掘っていった。溝の底には笹竹を、その上に杉の葉、そして土を被せて固める。抜き取った水をスムーズに下流の音無川に流し込むためである。こうして、幾筋もの人口の小川ができあがった。

千町無田の中央を流れる音無川
気の遠くなるような仕事が続く。山手から水分が抜けていくと、今度は火山灰でできた真っ黒の土に、刈り取った茅などを小さく刻んで混ぜ合わせる。最も原始的な農業の手始めであった。
「ちっとは(少しは)種ば蒔けるじゃろ」
耕作班長の石崎熊蔵が、とりあえず雨露の心配がなくなった小屋で、暖炉を囲む食事の時間に報告した。
「畑はどのくらいできたかな」
牛之助が熊蔵に訊いた。
「3反くらいですかね」
「肥料は要らんな」
今度は田中栄蔵に顔を向けた。
「そりゃ、あれだけ土が黒かけん、大丈夫でっしょ」
「よし、それでは明日が鍬入れだ」
牛之助が宣告すると、27人全員が言葉にならない叫び声で応えた。
翌朝は春霞で、三俣山の稜線がはっきり見えなかった。
「まず、先生から・・・」
利三郎が、真新しい鍬を牛之助に手渡した。さすが年季の入った者たちが造った畝は、触るのも勿体ないほどに整地され、雑草1本残っていない。
牛之助は、鍬の刃先を出来立ての畝に向かって力いっぱい振り下ろした。執念で勝ち取った開拓地であり、利三郎らが家族の生活のすべてを賭けて乗り込んできた千町無田開墾の第一歩であった。
第三章 開墾につづく
|



![]()
![]()