ウァルターとヒルデグンドが誓いを交わしてから、7日後の夜のことだった。
彼は、国王アッティラやフン族の貴族たち、たくさんの家来たちのために宴をひらいた。戦うことのほかに何も知らぬ彼等は、ご馳走の山を片っ端から食べ尽くし、どしどし運ばれるぶどう酒を、浴びるように飲みつづけた。賑やかな饗宴が進むにつれ、大皿や空になった皿が、嵐に掻き乱されたように辺り一面に散らばっていく。半ば酔いつぶれた家臣たちは、胡乱な目で、そこかしこに横たわっていった。
それを見て、ウァルターは時が来たのを知った。彼は見事な彫刻を施した大盃を取り上げて、名のある美酒をなみなみと注ぎ入れると、アッティラ王に差し出した。上機嫌なアッティラは、その盃を一息にぐいと飲み干す。
「うむ、これは良い酒だ。なんとも美味い。みなのもの、どうだ。ひとくち味わってみるとよい」
盃は国王から貴族へ、貴族から家来たちへと回され、強い葡萄酒は人々をあっというまに酔いつぶれさせた。いつしか、賑やかであった饗宴も静かになり、酔いつぶれた人々がそこかしこで鼾をかいている。
辺りを見回したウァルターは、ヒルデグンドに向かってうなづき、ふたりして広間を抜け出した。
彼らは大急ぎで厩に向かった。そこには、「獅子号」という名の勇敢な馬が待っている。持ち出したアッティラ王の財宝を馬に積み、ヒルデグンドのうしろにウァルターが座って、手綱を取る。
少しばかりの食料と財宝、そして落ち人たちを乗せた馬は、力強く大地を蹴って、夜の中へと走り出した。揺れる馬の背中で、ヒルデグンドは大それた行為におののいていたが、決して後悔はしていなかった。
馬は走りつづけた。昼は、暗き森の中に潜み、夜は、闇に紛れて訪れる者のなき山の中を辿り。彼等の目指す先は、懐かしい故郷の国であった。
一方で、眠りから覚めたウァルターとヒルデグンドの姿が見えないことに気が付いていた。ウァルターの部屋には、冷たい風が吹き抜けているばかり。ヒルデグンドは、城の中のどこを探しても見当たらない。王妃は悲しみ、獅子のように恐ろしい一代の英雄王アッティラは、怒るどころか、豪胆な気質に似合わず口惜しさに食べ物も喉を通らなかった。
「誰か、あの恩知らずどもを連れ戻る者はいないのか。」
だが、誰も、そのような冒険を成すほどの者はいなかった。みな、王の燃える目に気おされて、子羊のようにおびえるばかりであったのだ。
こうした騒動の中、逃避行のふたりは、ただひたすら、故郷アクィタニアを目指してひた走っていた。
そのうちに、持って来た食料はなくなってしまった。ウァルターは小鳥や魚をとらえてはヒルデグンドに食べさせた。こうして辛い旅は10日を数え、ようやく薄暗い森を抜けると、彼等の目の前には、眩しく太陽に輝くライン川のさざなみが広がっていた。
川の向こうには、懐かしいウォルムスの塔が見えていた。ようやく、ここまで帰ってきたのだ。
喜びのあまり声を上げたふたりは、馬を降り、川べりに停まる渡し舟に乗り込んだ。ウァルターは船頭に、森で獲った魚を渡して、こう言った。
「これを差し上げるから、どうか私たちのことは誰にも言わないで欲しい。お願いだ」
こうして、ふたりは船で川を渡った。しかし、船頭は、このことを他に漏らしてしまうのである。
その日の夕方、ウォルムスの城では、城主の食事が始まろうとしていた。料理人たちは忙しく働き、出来上がったばかりの料理が城主の前に運ばれる。
と、城主は、運ばれてきたばかりの皿の上をじっと眺め、訝しそうな顔をした。
「こんな魚は見たことがない。この辺りで取れるものではないな。一体、どこから買い付けたものなのだ?」
問われた料理人は、答えた。
「渡し場の船頭から買って参りました。なんでも、珍しい鎧に身を固めた若い騎士と、美しい乙女とを渡してやったお礼だそうです。」
料理人から詳しく話を聞いたとき、王の傍らに控えていた従者が口を開いた。
「それはおそらく、フン族の国から抜け出してきたウァルターでしょう。」
それは紛れも無くあのハーゲン、そして、この城の城主とは、言うまでもなくグンテルであった。姿を消したハーゲンは、無事、国許に帰り着いていたのである。
ウァルターたちは、フン族の国から多くの宝を持ち出していた。そして、グンテルは、かつて父がフン族から受けた恥辱を忘れてはいなかった。
「これは神が、父ギビコの奪われた財宝を取り戻すようにと思し召してのことなのだ。こうしてはおられぬ。ハーゲン、奴を追うのだ」
食事もとらず慌しく立ち上がったグンテルのもとに、12人の勇士がはせ参じた。探索のため、馬に打ち乗った者たちが跡を追う。
…しかしウァルターは、このような追っ手のことなど、つゆ知らぬまま、間近に迫った故郷を目指していた。
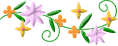
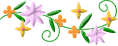
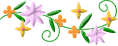
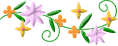
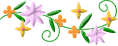
前のページへ TOPへ戻る 次のページへ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()