美しいライン川の岸辺を賭け抜けたウァルターの馬は、ほどなくフォスゲヌの森へと差し掛かっていた。相迫るように聳え立つ険しい山陰には、大きな岩がそそり立ち、緑の苔が分厚く生い茂っている。そこには、いかにも山賊の潜みそうな、暗く涼しい洞窟が出来ていた。
川を越えて、故郷が近づいていたことが、彼の気を緩ませたのだろう。フン族の国を抜け出してからほとんど眠っていなかったウァルターは、この洞窟で一休みしていこうと思い立った。
逞しい馬、「獅子号」の背を降りたふたりは、洞窟の奥に入り、ウァルターは久し振りに重い鎧を脱いだ。涼しい空気が体を包み、あまりの気持ちよさに、ウァルターは眠気に襲われる。
「すまないが、少し休ませてくれないか。もし足音が聞こえたら、起こして欲しい…」
ヒルデグンドにそういい残して、彼はあっというまに眠りに落ちてしまった。よほど疲れていたのだろう。
だが、このとき、執念深いグンテルは彼等のすぐ近くまで迫っていたのである。
「ウァルターは並ならぬ戦士です。そう容易く、宝を手放すことはいたしますまい。王よ、どうかご用心めされよ。そう迂闊に手を出すものではありません」
ハーゲンが耳打ちする。
草木を踏みにじる乱れた足音で、ウァルターに膝を貸していたヒルデグンドは、はっとして耳を澄ませた。誰かがやって来る。それも、ひとりふたりではない。
彼女は、フン族が追いかけて来たものと思い込んで、大急ぎでウァルターを揺さぶり起こした。彼はすぐさま鎧を身に付け、洞窟の入り口にぴたりと身をつける。
と、彼の口元に、わずかな微笑みが浮かんだ。
「フン族ではない。あれは、懐かしいハーゲンだな。…だが、どうやら我々の味方をするために来てくれたのではないらしい。」
ウァルターもヒルデグンドも、かつてハーゲンと兄弟のようにフン族の宮廷に過ごしていた仲だ。相手のことは、よく知っている。
意を決した彼は、洞窟から踊り出て、人々に向かってこう言った。
「随分とものものしい有様ではないか。さては、この俺が当然手にするべき宝を奪いに出てきたものと見える。」
大勢を前にしてびくともせぬ彼の眼光は、矢の様に人々を射った。そのさまは、昔と少しも変わっていない。
ハーゲンは、主君グンテルにそっと耳打ちをした。
「戦わぬほうが得策です。宝が欲しいのであれば、話し合いで解決してはいかがでしょう。」
これを受けて、12人の中からメッツの領主、カミロという男が静かにウァルターのもとへ近づいていった。
「情け深い我が主は、穏便な措置をお望みだ。軍馬と宝と、その美しい乙女とをこちらに寄越せば、命だけは助けてやろう。」
しかし、カミロの言葉を聞いて、ウァルターは高らかに笑った。彼にとって、ヒルデグンドを手放すことなど、とうてい考えつきもしないことだった。
「愚かしいことだ。グンテル王に伝えるがよい。それよりも、俺の邪魔さえしなければ、貴殿らは無事なまま、赤金づくりの腕輪の百を与えられるだろう。」
逆に、自分こそグンテルたちの命を助けてやってもいい、と言ったのである。これには、グンテルも腹をたてた。
「なんと無礼な。しかも思い上がったことに、自分ひとりでここにいる全員を相手にするという。」
「お待ちください、陛下。奴なら、本当にそれが出来るだけの力を持っています。…それに、私は昨夜、悪い夢を見ました。一匹の熊があなたに襲い掛かり、私が駆けつけたときには、片腕をもがれ、両の眼をえぐられたあなたが苦しみながら横たわっているのです。これはもしや、今日の日の暗示ではありますまいか。」
ハーゲンはなおも必死に王を止めようとした。しかしグンテルは、そのような言葉など聞き入れもしなかった。
「ふん、夢がどうしたというのだ。あのような者ごとき、ここにいる者たちでねじ伏せてくれるわ。」
「…では、お好きになさいませ。私は、ここで見守らせていただきます。」
忠告を聞き入れてもらえなかったハーゲンは、それだけ言って身をひいた。グンテルは、連れて来たつわものたちを率いて、見ておれとばかりにウァルター目指して押し寄せる。
※ここが、ニーベルンゲンの歌でヒルデブラント師匠の言う、「お前は盾の上に座って一族がやられるのを見ていたではないか。」の、シーン。
先陣を切って斬りこんだのは、ハーゲンの妹の息子、パタフリッドであった。だが彼は、一太刀のもとに切り捨てられる。ウァルターはあまりにも強く、フランク人たちは恐れをなして打ちかかることを忘れてしまった。
「ええい、何をしている。相手はひとりではないか。不甲斐ない!」
王に叱咤されて、勇士たちはウァルターに打ちかかろうとする。しかし、そこは狭い谷の一本道だった。みなで一斉に攻撃することは出来ず、ひとり、またひとりと傷つき、倒れ、とうとうグンテルひとりになってしまった。
味方をすべて失ったグンテルは、大慌てでハーゲンのもとへと逃げ帰った。
「なぜ手を貸さぬのだ。貴様は味方を見殺しにする気なのか。」
「…私は、忠告したはずですが。」
冷ややかな目で王を見つめたハーゲンはしかし、自分の甥、パタリフィッドまでが倒されたことを知ると、そのまま座っていることは出来なくなった。
「このままではらちが開きません。陛下、奴を広いところにおびき出すのが得策でしょう。」
智謀にも長けたハーゲンはそう言って、王とともに谷の出口に潜むことにした。
そのころ、攻撃の止んだのを知ったウァルターは、ほっとして、洞窟の中に戻って入り口を塞いでしまった。彼は仮の砦の中で今日一日の勝利を神に祈ると、再び眠りについた。
そうして、慌しく一晩が過ぎていった。
明け方になり、昨日倒したグンテルの家臣たちの馬を戦利品として繋ぎ合わせたウァルターは、それぞれに荷を分けてくくりつけ、一夜の宿をあとにした。彼は、待ち伏せがあることなど夢にも思わない。
ちょうど、一マイルほど進んだあたりだっただろうか。
ふと後ろを振り返ったヒルデグンドの目に、坂を駆け降りてくる二頭の馬が映った。
「敵だわ!」
ウァルターも、追って来る者たちの姿が目に入った。そこに、グンテルとハーゲンの姿を見出した彼は、このままでは逃げ切れぬということを悟った。
「すまぬが、俺は戦わねばならぬ。このまま逃げては、この名の恥となろう。あなたは、この馬と荷物とともに、早く森の中へお隠れなさい」
こう言って、彼は雄雄しくも駆け寄って来るふたりを迎えた。
彼は、久方ぶりに向かい合う幼馴染に向かって、まるで友人のように語り掛けた。
「久しいな、ハーゲン。お前が突然いなくなってから、どうしているかと随分心配したものだが。それにしても、こんな所で会うことになるとは、奇遇なものだ。どうだ? グンテルのような者の言うことを聞くより、昔のように俺と一緒に来ないか。」
しかし、ハーゲンは奥歯を噛み締め、低く答えた。
「…それは出来ない。お前は、我が同胞を殺めてしまったからな。」
「なるほど。残念だ」
言い終わるなり、ハーゲンは馬上から槍を投げつけた。ウァルターは鳥のように身を翻し、身構える。その足もとにもう一本の槍が届いた。グンテルの放ったものだ。
馬を飛び降りたハーゲンは、剣を抜いてウァルターと向かい合った。しかし、どちらも打ってかかろうとはしない。巌のようになった沈黙と静寂の時が過ぎていった。
その間、グンテルはイライラしながら成り行きを見守っていた。ウァルターの足元に落ちた槍を拾いたくて仕方がなかった。彼の武器は、それだけだったからである。
「斬り込め、ハーゲン! そいつを倒せ」
だが、ハーゲンは動こうとしない。静かに切っ先を見つめたまま、意識を研ぎ澄ましていた。
この状況に、先に痺れを切らしたのはウァルターのほうだった。
一声、気合いとともに足元に槍を踏みつけると、その持ち手は、今しもその槍を拾おうとしていたグンテルの腹にめり込む。王はそのまま、はっとする間も無く崩れ落ちる。とっさに滑り込むハーゲンの盾の上で、ウァルターの打ち下ろした穂先が激しく火花を散らして横に流れた。
「王! ご無事ですか」
グンテルは口元を歪めたまま、うんともすんとも返事をしなかった。
照りつける太陽の光が、焼きつくように暑かった。重い鎧を身に纏った彼らには、それは余計に重くのしかかる。
大粒の汗が流れ落ちていた。
今や猛るウァルターは、剣を抜き放ち、息つく暇も与えないほど激しくハーゲンに槍を打ち込んでいる。ハーゲンもそれを防ぎ流すが、反撃の糸口が掴めない。
そのとき、またもグンテルが手を出そうとした。1対2である。しかし、ウァルターにとって、グンテルはさほどの意味も持たぬ存在であったようだ。
一太刀のもとに、グンテルは足を付け根から切り落とされ、どうと倒れ落ちる。さらに、とどめを加えようと振り上げられる切っ先。だが、この鋭い太刀風の前に、またもハーゲンが立ちふさがった。
彼の剣は、ハーゲンの兜に当たって砕け散ってしまった。驚くウァルター。その一瞬の隙をついて、ハーゲンの太刀が横に一閃する。
ウァルターの右手は、空しく腕を離れて宙に飛んだ。
「これで…」
しかし、まだ終わりではなかったのである。
彼は、手を失った右手に盾を支えとどめを刺そうと振り上げたハーゲンの剣を防ぎつつ、いつの間にか左手で短刀を抜いて、ハーゲンの頭めがけて切りかかり、右目を抉った。
幾多の鮮血が流され、ようやく、彼等の動きが止まった。
荒い息遣いの中、すべての力を使いきった3人は草の上に座り込み、汗を拭った。
「もういいぞ、ヒルデグンド!」
ウァルターの声を聞いて、たちまち森の中からヒルデグンドが駆け出してきた。
彼女は、辺りに咲き乱れるような血の跡を目にし、血まみれで座り込んでいる3人を見ると、顔色を変えた。
すぐさま気付けの酒が持ち出され、手当てがなされる。側には、激しい戦いを物語るように、ウァルターの右手と、ハーゲンの右の眼とが落ちていた。グンテル王は片足を失っただけで済んだ。彼のかわりに、ハーゲンが片目を失ったのである。
戦いが終わったあと、ウァルターとハーゲンは、また昔のように仲良くなっていた。
「それにしても久し振りだな。お前と本気で戦ったのは、何年ぶりか。」
「お前も、腕が落ちていないようで安心したよ。いや、俺が切り落としたんだから、『落ち』たのか?」
「言うじゃないか。俺にはまだ左手がある。そういうお前は、城に帰れば、部下にやぶ睨みで号令をかけるんだろう?」
「いいさ。せいぜい、いいものを食べて新しい眼を育てにかかるさ。」
さも愉快そうに冗談をとばしあった彼等は、一休みしたあと、いちばんの重傷を負ったグンテル王を馬に乗せてやった。ハーゲンは、昔なじみに別れを告げると、王とともにウォルムスへ帰っていく。
その後姿を名残惜しそうに見送っていたウァルターとヒルデグンドは、勇を鼓しながら、再びアクゥタニアを目指して旅立ったのであった。
故郷に帰りついた彼等を、人々は熱狂して出迎えた。父王なきあとのアクィタニアには、美しいヒルデグンドを妻に迎えたウァルターが、その後、30年の永きに渡って君臨していたという。
おしまい。
ひとことツッコミ;「やっぱり情けないんじゃん、グンテル王」…。
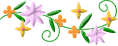
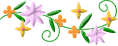
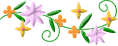
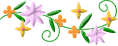
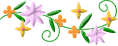
前のページへ TOPへ戻る
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()