それは、フン族の王国が出来てから、約一千年を経た時のことであった。
時の勇士として名高いフン族の王アッティラは、雲のような大軍を率いて嵐のごとくヨーロッパの只中へ押し寄せた。誰もこの大群に逆らうことは出来ず、多くの国々が飲み込まれた。
戦っても勝ち目はない。そのことを知っていたフランク族の王ギビコは、この大軍の迫る先がフランク王国に向いたとき、縮み上がり、すぐに貢物と人質を送ることを決めた。
しかし、王子グンテルはまだ幼く、狼のように飢えた敵の手に渡すことは出来なかった。そこでギヒコは、家臣たちの中から有力な貴族の息子、ハーゲンを、アッティラのもとに人質として送りつけた。
こうして、あっという間にフランク族の国を踏み越えたフン族は、次にブルガンディの国へ向かった。ここでも国王ヘリックは戦うことを諦め、美しい姫君、ヒルデグンドを差し出すことを決めた。恐れていたフランク人さえも降伏してしまったのに、どうして打ち勝つことが出来ようかと思ったのだ。
ヒルデグントと貢物を手にいれたフン族は、広野を伝う猛火のごとく、さらにアクィタニアにまで手を伸ばし、国王アルフェールは、ひとり息子のウァルターを人質として差し出すことを決意する。
かくして、はからずも、彼は許嫁の姫ヒルデグンドと敵地において再会することとなる。
フン族は、退くことを知らぬ、おそるべき剛勇の士であった。彼等はアッティラの率いるもと、絶えず戦いつづけ、多くの勝利を収めた。
だが王は、人質の子供たちに対しては本当の父親のように優しく接し、決して手荒な真似をしようとはしなかった。ヒルデグントは王妃に預けられ、男の子たちは武芸などの教育をほどこされ、申し分なく育てられた。
数年の時が過ぎた。
ウァルターやハーゲンは、フン族のどんな戦士と太刀打ちしてもひけは取らぬほど、立派な戦士となっていた。ヒルデグントは、フン族の戦利品の宝石で美しく着飾っていた。彼等にとって、アッティラの宮廷での日々は楽しく、決して、辛いものではなかったという。
しかしある時、アッティラ王のもとに、フランク族の王ギビコがこの世を去り、若いグンテルが王位に上がった、という知らせが届く。これを耳にしたハーゲンは、その夜、長く住み慣れたアッティラの宮殿を抜け出して、いずこへともなく姿を消してしまった。
彼を実の息子のように思っていたアッティラと王妃は悲しみ、もしやウァルターも、同じようにいなくなってしまいやしないかと心配した。ハーゲンもウァルターも、今やフン族の軍隊の一員として、先陣切って戦う身分にあった。戦力としても、失いたくはなかったのである。
彼を国に繋ぎとめるため、王妃は、しきりとフン族の乙女との結婚をウァルターに勧めた。しかし、既に胸に思う人のある彼は、決してその勧めには従わなかった。
「私には、そのような大それたことは出来ません。…あなたの軍隊での勤めほど、私の心を慰めてくれるものはないのですから。」
彼はその言葉のとおり、アッティラの軍を率いて見事に戦った。それでアッティラは説得を諦め、彼の言葉を信じることにした。―--結婚はさせなくとも、逃亡することはないだろう、と。
華々しく迎えられた凱旋の夜、ひそかにウァルターを迎えたのは、ヒルデグントだった。
むろん言うまでもなく、彼が結婚の勧めを拒んだのはこの姫君のためであり、いつかは、アッティラの城を抜け出すつもりであった。彼は言った、「幼き日の結婚の約束を果たしたい」と。彼女ひとりを、この宮廷に残していくことなど、到底出来ない…。
ヒルデグンドは、星のような瞳のきらめきをやどして彼の心に応じた。命を賭けて応えることを誓った。
彼女はアッティラ王の財宝を取り出してウァルターに与え、持ち出す財宝を箱に詰めた。
脱出は一週間のうちと決められ、ふたりは、意味のありげな視線を交わして頷きあい、それぞれの部屋に別れたのである。
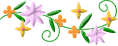
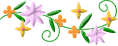
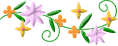
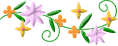
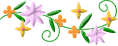
TOPへ戻る 次のページへ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()