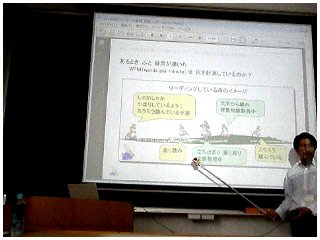presented by
presented by ミント音声教育研究所
ミント音声教育研究所
トップページ ミント アプリ
ミント アプリ
ケーションズ
ホームページ 映画で英会話
映画で英会話
動画シーン検索サイト
Seleaf ミント スクールズ
ミント スクールズ 動画で授業参観
動画で授業参観 英語で歌う
英語で歌う
マザーグースの
元気な声
7曲連続暗唱/Reciting 映画「オズの魔法使い」を使った動画辞典で
映画「オズの魔法使い」を使った動画辞典で
英語表現 「映画まるごとデータベース」を使った授業
「映画まるごとデータベース」を使った授業
映画で英会話 ベクターライブラリ
ベクターライブラリ 公開作品一覧
公開作品一覧- 英語作品
 朗読絵本
朗読絵本
ふしぎの国のアリス
第1巻 聞き取りドリル
聞き取りドリル
オバマ大統領 就任演説 聞き取りドリル
聞き取りドリル
オバマ ノーベル平和賞演説- 語学ソフト
 ミングル
ミングル
リーダビリティ計測ソフト ワーズピッカー
ワーズピッカー
英単語拾い2- ゲーム
 朗詠・百人一首
朗詠・百人一首
読み上げ&ゲーム 数独ナンプレゲーム
数独ナンプレゲーム
東海道五十三次
詰独 一人旅 数独ナンプレゲーム
数独ナンプレゲーム
富嶽36景 富士登山
詰独 次の一手- ユーティリティ
 書き起こしソフト
書き起こしソフト
ゆ〜ゆ バリュー 書き起こしソフト
書き起こしソフト
ゆ〜ゆ ライト 書き起こしソフト
書き起こしソフト
ゆ〜ゆ ビジネス 書き起こしソフト
書き起こしソフト
ゆ〜ゆ アカデミー ミント名作劇場
ミント名作劇場 日本の昔話
日本の昔話
朗読絵本
「竹取物語」 群馬の昔話
群馬の昔話
朗読絵本
「猿地蔵」」 日本の名作
日本の名作
朗読
芥川龍之介
「トロッコ」 英語朗読絵本
英語朗読絵本
マザーグース Mother Goose 映画
映画
オズの魔法使い
歌「オーバーザレインボー」 映画
映画
カサブランカ
シーン「君の瞳に乾杯」 英語で折り紙 Origami
英語で折り紙 Origami
折鶴 つる crane
2013年 6月 第130回 LET 関東支部研究大会(東京) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語教育メディア学会(LET)関東支部 第130回 研究大会(東京小金井)において、ミント音声教育研究所は2つの研究発表をおこなう
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ..[↑] 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
各種学会での活動のトップページへ Site:http://www5b.biglobe.ne.jp/~mint_hs/let/ ニュースのページへ Site:http://www5b.biglobe.ne.jp/~mint_hs/news/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||