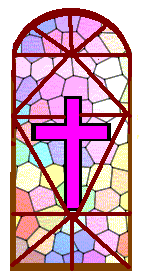
| ★聖書を元とすることわざ、習慣 | 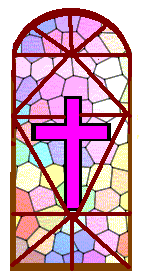 |
| ★祈り | |
| ★「三位一体」 | |
| ★聖書の常識のウソ | |
| ★イエスのたとえばなし | |

○ことわざ
『笛吹けど踊らず』(マタイ11−16〜17)
「この時代は何にたとえたらよいでしょうか。それは、子供たちが市場に座って、ほかの友達に呼び掛けて、こう言っているのに似ています。『私たちは、あなたがたのために笛を吹いてあげたのに、あなたがたは踊らなかった。私たちは弔いの歌を歌ってあげたのに、あなたがたは胸を打たなかった』。というのは、ヨハネが来て、食べもせず、飲みもしないと、人々は、『あれは悪霊につかれているのだ』と言い、わたしが来て、食べたり飲んだりすると、彼らは『ほら、大食いの大酒飲みで、取税人や罪人らの仲間だ』と言います。しかし、知恵の正しいことは、その行いが証明します」(現代訳)
『豚に真珠』(マタイ7-6〜7)
「聖なるものを犬にやるな。また真珠を豚に投げてやるな。おそらく彼らはそれらを足で踏みつけ、向きなおってあなたがたにかみついてくるであろう。(現代訳……神様のみ前に浄められたものは、たといそれがどのようなものであれ、天のお父様に故意に背を向けている者たちに与えてはなりません。彼らにはその価値がさっぱり分からないからです)。求めよ、そうすれば、与えられるであろう。捜せ、そうすれば、見いだすであろう。門をたたけ、そうすれば、あけてもらえるであろう」(日本聖書協会『口語訳 新約聖書』 マタイによる福音書7章6節〜7節)
『砂上の楼閣』(マタイ7−24〜27。ルカ6−46〜49)
「わたしが今まで話した言葉を聞いて、それを行う人は、ちょうど岩の上に家を建てた賢い人のようなものです。どんなに雨が降り、水かさが増し、洪水になっても、また、風が強く吹き付けても、倒れることはありません。それは、岩の上に建てられたからです。ところが、わたしが今まで話した言葉を開いても、それを行なわない人は、ちょうど砂の上に家を建てた愚かな人のようなものです。雨が降り、水かさが増し、洪水になり、風が強く吹き付けると、すぐに倒れてしまいます。しかも、それはひどい倒れ方でした」(現代訳)
『目からうろこが落ちる』(使徒行伝9−17〜18)
「そこでアナニヤは、出かけて行ってその家にはいり、手をサウロの上において言った。『兄弟サウロよ、あなたが来る途中で現れた主イエスは、あなたが再び見えるようになるため、そして聖霊に満たされるために、わたしをここにおつかわしになったのです』。するとたちどころに、サウロの目から、うろこのようなものが落ちて、元どおり見えるようになった。そこで彼は立ってバプテスマを受け、また食事をとって元気を取りもどした」(日本聖書協会『口語訳 新約聖書』 使徒行伝9章17節〜18節)
かつて、あるテレビの時代劇の登場人物が「目からうろこが落ちました」と台詞で言っていましたが、江戸時代の人がこの聖書にもとづくことわざを言う訳がないのです。
『学者叫ばず、石また叫ぶべし』(ルカ19−39〜40)
「ところが、群衆の中にいたパリサイ人たちがイエスに言った。『先生、あなたの弟子たちをおしかりください』。答えて言われた。『あなたがたに言うが、もしこの人たちが黙れば、石が叫ぶであろう』」(日本聖書協会『口語訳 新約聖書』 ルカによる福音書19章39節〜40節)
「その時、パリサイ派のある人たちが、群衆の中からイエスに向ってこう言った。『先生。あなたのお弟子たちは余りにも異常です。少し制止なさっては いかがですか』。すると、イエスは答えて言われた。『よく言っておきますが、この人たちが黙ってしまえば、石が叫びだし、石垣の石が音を立てて崩れる、神様の裁きが下るでしょう』」(現代訳)
○習慣
『日曜日』(マルコ16一卜2)
「さて、安息日が終ったので、マグラダのマリアとヤコブの母マリアとサロメとは、イエスの遺体に塗るために香料を買い求めた。そして、週の初めの日、つまり日曜日の早朝、日の出るころ墓に着いた」(現代訳)
ユダヤ教では、神が天地創造の7日目で休まれたことにより、週の7日目の土曜日が安息日になっています。(正確には、ユダヤの暦では日没より一日が始まるので、金曜の日没から土曜の日没までが安息日)。しかし、キリスト教では上記の引用のように「週の始めの日」にキリストが復活したので、ユダヤ教の土曜日に変わって日曜日を聖なる日として休みにしたのです。休日は英語で「holiday(聖なる日)」というように、教会でミサ(礼拝)をするために仕事が休みになるのであって、決して仕事の骨休めではないのです。日本では明治5年に西洋の曜日を輸入したとき、このような意味も知らずに形式だけ西洋のまねをして日曜を休みにしたのです。
『十字架』(ルカ14−27)
「自分の十字架を負うてわたしについて来るものでなければ、わたしの弟子になることはできない」(日本聖書協会『口語訳 新約聖書』 ルカによる福音書14章27節)
「新約聖書」のページでも紹介したように、十字架は反ローマ帝国の政治犯に対する見せしめの死刑の道具でした。それがキリスト教のシンボルになったのは、「旧約聖書」のページで説明したように、「神と人→縦、人と人→横」ということを表す、あるいは「火と水を十字に組む」という神様のみ働きを示すという意味からでしょう。その証拠に、上記の引用はイエスが十字架刑に処せられるよりも遥か以前の発言なのです。
ちなみに、初期キリスト教では、シンボルマークは十字架ではなく魚でした。それは西暦元年ころから20世紀までの2千年間が魚座の時代であることの象徴かもしれません。ちなみに21聖(世)紀からは水瓶座の時代だそうです。
※十字の切り方…「
(「聖父(ヤハエの神)」・「聖子(イエス・キリスト」・「聖霊」で三位一体。「三位一体」については後述)
『主の祈り(主祷文)』(マタイ6−9〜13)
《文語文》 | 《口語文》 |
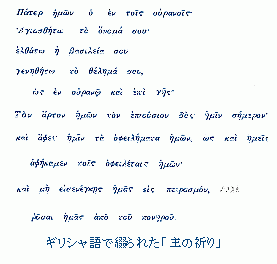
(副文)
慈しみ深い父よ。
すべての悪からわたしたちを救い、現代に平和をお与え下さい。
あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、
すべての困難に打ち勝つことができすように。
わたしたちの希望、
救い主イエズス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。
(頒唱)(歴代誌29−11)
国と力と栄光は、限りなくあなたのもの。
○「主の祈り」解説
「主の祈り」は教会で唱えられる祈りのうち、唯一イエス自身に教えられた祈りということになっています。この祈りはシュタイナーによると、イエスがユダヤ以外の異邦人の町で修行をしていた時に受けた御神示がもとになっているといいます。つまり、神より人類への警告として下された御神示の内容を、順序を逆にし、また逆さの内容にして祈りにしたのだということです。
イエスはヤハエの神を「父なる神」と位置づけました。これは単にユダヤ教という一宗教の神ではなく、全世界全人類の親神様という意味が込められています。
その「御名の尊まれんことを」願うのは、神の子としての人類の親神様に対する当然の責務であります。すなわち、「神の御名、弥栄えに栄えいかれますことを御祈念申し上げる」ということで、下から「神の御名」を上へ「フキ上げ」ていくことによって神の権限を万華させ、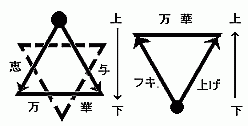 神の方からは人の方へ恵みを与えてくださる関係になります。これがモーセが用いダビデ王がその紋章としたカゴメの紋章で、それは天地創造の火と水を十字に組んだ神のみ働きを表しており、モーセもこの関係を知っていたと思われます。
神の方からは人の方へ恵みを与えてくださる関係になります。これがモーセが用いダビデ王がその紋章としたカゴメの紋章で、それは天地創造の火と水を十字に組んだ神のみ働きを表しており、モーセもこの関係を知っていたと思われます。
その神の「御国が来る」ということは、どういうことでしょうか? これは、そもそも神様は何の目的で人類をお創りになったのかということと関係してきます。神様は、この地上(三次元・現界)に、神の国(神界)の写し絵、地上天国を物質にって顕現されようとお考えになり、それを神の子である人類にさせようとされているのです。従って、この世に神の国を顕現させ、地上天国を実現させようという神様の御経綸(ご計画)実現を祈念し、それに参画させて頂くお許しを願い、またそのために精進努力する決意は人類にとって重責であり、それなくしては人類の存在意味もないということになります。
そこで「み旨の天に行わるるごとく、地にも行われんことを」となる訳です。神御経綸(ご計画)が神界・神霊界から現界にも移り、また神の置き手(掟・法則)がこの世を支配しますようにということです。つまり、神のみ意が一日も早くこの地上に成就しますようにという祈りで、人類が一丸となって御神意成就に邁進することが大切になってまいります。
そして「日用の糧」となる訳ですが、これは肉体を維持するための「食物」だけとは限りません。もちろんそれも含みますが、もっと大事なのは神の光とみ教え、神の御守護と御導きということです。イエスは『旧約聖書』「申命記」第8章の言葉を引用して、「人はパンだけで生きるのではない。神の口から出るすべての言葉によって生きる(マタイ4-4)(フランシスコ会訳)」と言っています。(申命記の記載……「人はパンさえあれば生きられるのではなく、神の御心でなければ決して神に祝福された、生きがいのある人生を送って、生きることはできないのだ」<申命記8-3>「現代訳」)
その次に、我われ人類の「罪」が問題となります。神に恵みを頂くその前に、人類としては太古に神に反逆したという人類共通の罪と、それぞれが再生転生中に包み積んできた個々抱くの罪をまず神のみ前に「悪うございました」と頭を下げて詫びる心が第一でしょう。(輪廻転生については現在のキリスト教の教義にはありませんが、イエスの教えの元になったエッセネの教義にはあったようです。4世紀ごろに、輪廻転生はキリスト教の教義から削除されたようです)。詫びる心があってはじめて罪は許されるものでしょうし、そのお詫びの証しを形として神様にお見せする必要があるのです。
その次は、文語では「試み」、つまり「試練」「神試し」を避けたいような言い方になっていましたが、「神試し」は「神鍛え」でもあり、積極的に「神鍛え」を頂いてこそ人は伸びていくものです。そこで、口語では「誘惑」となっています。つまり、「誘惑」に打ち勝つ勇気をお与え下さいという意味でしょう。
最後に「悪」ですが、悪の象徴として「悪魔(サタン)」が聖書には登場します。しかし、天地創造の折にすべてを「善し」とされた神様が、わざわざ悪魔をお創りになったのでしょうか? 神様は悪魔などお創りになっていないなら、悪魔は神に創られず自然発生したのでしょうか? 結論から申しますと、神様は「悪」はお創りになっておられませんが、一見「悪」に見られるような存在も人間に物質開発をさせるという点での必要上、一時方便としてお許しになってきたのです。従って、人知で善悪を判断することは、神の権限を犯すことになります。神様は奥の奥のそのまた奥の御存在で、そのみ仕組みも非常に奥深いものなのです。とても人間の人知で分かろうはずもありません。病気も不幸現象も神様はお創りになっておられず、それらはすべて神大愛のクリーニング現象なのです。神様は善一途のお方であります。病気も不幸現象も、人間が勝手に神から離れて勝手に積んできた罪や穢れから洗い浄めるための清浄化現象ですから、一切に「感謝」する要があるのです。それを、「つらい、苦しい」と言って不平不満ばかり言っておりますと、ますます長引いてしまいます。また、イエスが「悪魔憑き」の悪魔を追い払った記述が福音書にありますが、それらは厳密には悪魔ではなく、もともとは神の子として創られた人間の魂もしくは動物霊が、執着、恨み、妬み、嫉みなどで生きている人にとり憑いた憑依霊なのです。イエスはその憑依霊を神の光で離脱させた訳です。
(参考…キリストヘの神示) R・シュタイナー『第五福音書』より
「今世、汝らの心いよよ神を離れ行き、悪のみ栄えん世なれば、いささかの懸念ありて、ここに示しおくなり。汝らの自我の崩れゆかん様、また汝らの罪は、汝らの日用の糧の中に自ら体得すること大事なるも、今の世となりては天の意志、地上には全く行わるることなく、やがては神の国も遠ざかり行くならん。神の真の名さえ知らざるべし。神は天にまします父神よ」
ルドルフ・シュタイナー(1861〜1925)はドイツの思想家で、神智学協会ドイツ支部書記長。形態学に深い解釈を加え、人間観や宇宙観を霊性のヒエラルヒー、輪廻転生、存在界の三区分(物質界、生命界、霊界)、死後の世界の存在などの観点から論じた。シュタイナーによると、イエスがパレスチナ以外の土地の異教徒の祭祀の町で幽体離脱し、この神示を受けたという。この神示の内容を裏返したのが「主の祈り」だということである。
『天使祝詞』(前半・ルカ1−28、後半は中世にフランシスコ会が創作)
《文語文》 | 《口語文》 |
『栄唱』
(文語)願わくは、聖父と聖子と聖霊とに栄えあらんことを、
はじめにありしごとく、今もいつも世々に至るまで、アーメン
(口語)栄光は父と子と聖霊に。
初めのように今もいつも世々に。 アーメン。
○「アーメン」とは
キリスト教の祈りの最後に、「アーメン」と言います。これは、ヘブライ語で「真(まこと)に」という意味の「○aaMeeN」で、ギリシャ語でもその「真に」という意味を意訳せず、そのまま音訳して「Amen」としました。イエスの言葉も最初がこの語で始まっているのが多いのですが、おそらくイエスの口癖だったのかもしれません。 よほど印象的だったのか、福音書ではその語をギリシャ語に訳さずに、ヘブライ語をそのままギリシャ語のアルファベットで書いたという訳です。その部分は、日本語訳では「真(まこと)に真(まこと)にあなた方に言う」とか、「よくよくあなた方に言っておく」などと訳されています。イエスは「真(まこと)」という言葉が好きだったようで、その説法はいつも開口一番「アーメン、アーメン(真に真に)」で始まったのでしょう。そのアーメンが後には祈りを結ぶ言葉として使われ、ラテン語でも英語でも日本語でもそのまま「Amen」です(ただし、英語の場合は発音が「エイメン」になる)。ただ、ラテン語の祈りの本などの「アーメン」を「しかあれかし」などと和訳しているものもありましたが、そのように唱える人はいません。ちなみに「アーメン」も言霊から解釈すると、「ア」は「天」で「縦」、「メ」は音韻学上「ミ」に変化し、「水」なので「横」となり、「ン」は完成を表して、「火(縦)と水(横)を十字に組んで完成させる」というみ働きになります。
よほど印象的だったのか、福音書ではその語をギリシャ語に訳さずに、ヘブライ語をそのままギリシャ語のアルファベットで書いたという訳です。その部分は、日本語訳では「真(まこと)に真(まこと)にあなた方に言う」とか、「よくよくあなた方に言っておく」などと訳されています。イエスは「真(まこと)」という言葉が好きだったようで、その説法はいつも開口一番「アーメン、アーメン(真に真に)」で始まったのでしょう。そのアーメンが後には祈りを結ぶ言葉として使われ、ラテン語でも英語でも日本語でもそのまま「Amen」です(ただし、英語の場合は発音が「エイメン」になる)。ただ、ラテン語の祈りの本などの「アーメン」を「しかあれかし」などと和訳しているものもありましたが、そのように唱える人はいません。ちなみに「アーメン」も言霊から解釈すると、「ア」は「天」で「縦」、「メ」は音韻学上「ミ」に変化し、「水」なので「横」となり、「ン」は完成を表して、「火(縦)と水(横)を十字に組んで完成させる」というみ働きになります。
ちなみにイスラム教での祈りの言葉は「アーミン」であり、ヒンズー教やチベット仏教では祈りのはじめに「オーム・マニ・ペメ・フーム」と唱えます。その冒頭の「オーム」は某狂信教団の名称にも使われたので日本人はいい印象を持っていないでしょうが、それが日本の真言宗などで唱える真言の最初の「おん」という部分(「おん あみりた ていせい からうん」や「おん まか きゃろにきゃ そわか」などの最初の「おん」)となっています。それら「アーメン」も「アーミン」も「オーム」も実は同じ語言から発しているもので、こうして見ると万教の元が一つであるということが分かると思います。
上の「祈り」の個所で十字の切り方を紹介しましたが、その十字を切る際には「聖父(ちち)と聖子(こ)と聖霊の御名によって」と唱えます。この「聖父と聖子と聖霊」を三位一体といって、キリスト教の根本教理の一つです。では、その「三位一体」とは何なのでしょう? それは、『旧約聖書』の主人公である天の神=ヤハエの神を「父」とし、イエス・キリストをその子と位置づけ、さらに聖霊を加え、その三者は同質で不可分とする説のことです。その聖父と聖子と聖霊を三つの「ペルソナ」といいますが、この言葉を始めて耳にした幼少のみぎりの私はそれが英語の「パーソナル」の語源であることは知るよしもなく、パラソルを連想して何か傘のようなものを思い浮かべていました。
それはさておき、そのペルソナには「仮面」という意味もありますが、ここでは「人格」という意味で、ただし相手は神なので人格ではなく「位格」となります。そして聖父と聖子と聖霊の三者は、位格 (ペルソナ) は異なっていても「実体」 (スプスタンツィア Substantia)は一つだという考え方が「三位一体」です。この考え方がはじめて提唱されたのは、3世紀のはじめごろだといわれています。その後、4世紀にはイエス・キリストが神か人間かで教会内で大論争が起こり、結局その論争に勝ったアナスタシウス派によってキリストは神格化され、キリストも被造物である人間だとするアリウス派は異端として退けられてしまったのです。
その、キリスト神格化にとって都合がよかったのが三位一体説でした。なぜならキリスト教の土台であるユダヤ教は当時のヘレニズム多神教の世界でかたくなに一神教を守ってきた教えで、その流れを汲むキリスト教も当然一神教でなければならなかったのです。ところが、ヤハエの神に対してイエス・キリストも「神」であるとすれば、神は一神ではなくなって多神教になってしまいます。そこでヤハエ(天の父)とイエス・キリストはともに同じ御一体の神のそれぞれの位格(ペルソナ)であって、本質は同じと考えたのです。こうして、この説はコンスタンティヌス大帝が召集したニケーア宗教会議で基礎が確立され、その後381年の第1回コンスタンティノープル宗教会議にて確定しました。
さて、突き詰めて考えてみますと、この「三」という数は何を表すのでしょうか。そして真の「三位一体」とは何なのでしょう?
『旧約聖書』のページで、「神」とは「火と水」という相反する二つの性質を合わせ持ったお方であることはすでに紹介しました。ここではさらに突っ込んで、「二つ」から「三つ」にして考えてみましょう。そこで出てくるのが、『旧約聖書』のページの同じ部分に書いた「神・幽・現」の三大霊界です。これを大千三千世界ともいいます(仏教で「三千大千世界」といっているのは誤り)。神・幽・現三界の大霊界の“大仕組み”は、相即相入・密実一体に連動し関係し合っている“妙智界(みょうちかい)”であります。「大千三千世界」の「大」は霊的には「天」であり「神」であり「日」であり、数霊(かぞだま)では「五」ということになります。また、「千」という言霊(ことだま)は「地」であり「霊」ということで、「大千」の本義は『大霊界』を意味しています。それゆえに、神・幽・現の大千三千世界は、天・空・地、日・月・地、火・水・土、霊・心・体の“三位”で構成されております。
これを、数霊(かぞたま)で示せば、五・六・七の“ミロク”と云う事になります。なぜこれが数霊で「五・六・七」となるのかということになりますが、「五」は日、火、陽、霊で縦に働き、「六」は水、陰で横の働きをし、「七」は土で、「成り生り鳴る」、すなわち物質化・現象化を表しますから、物質である土や地球、人間でいえば肉体ということになるのです。この「五・六・七」が「五」を主体にして順序正しく並んでこそ、はじめてそれは「ミロク」ということになるのです。
つまり、宇宙万象ことごとくが、三位一体で出来上がっているのです。
大千三千世界は、観念界や哲学界のものではありません。それは、実在界、実相界であって、しかも相互に連動し合っている世界であります。ちょうど万生と生命界や空気界が相連動しているのと同じような性質の世界です。そもそも人間の環境を成す物質の世界は、固体と液体と気体とがあります。その代表的なものが、国土と水と空気にほかなりません が増量すると気体となり(水蒸気)
が増量すると気体となり(水蒸気)![]() が増えると流体化して液体となり(水)、さらに水の
が増えると流体化して液体となり(水)、さらに水の![]() が増えると固体となります(氷)。ところがH2Oという水の本質は異なるものになったかというと
が増えると固体となります(氷)。ところがH2Oという水の本質は異なるものになったかというと
今日の唯物科学は第4次元界の門に立っているのですが、霊界という極微の世界を解明するに至ってはおりません。しかも、唯物論の世界では恐るべき物主心従霊属の倒錯した世界観に低迷しております。物主心従霊属の原理では生きた霊的世界をサトることはできず、人類は永久に幸福者となることはできません。
この実在神や実相界を看取することができたならば、人生観は180度転換するに違いありません。唯物主義から脱却し、唯霊・唯心・唯物の三位一体の実相界を観取して行く事が重要なのです。
『霊主心従体属の法則』を学ぶ事によって生死の真相を把握し、それによって人生最大の疑問を解決することが初めて可能となります。目に見える世界が総てと思っている“唯物論”が、実は幻想であることをサトッていかなくてはなりません。あまつさえ神の子人は、再生・転生を繰り返して何度も何度も地上に現れ、“神性化”していかなくてはならないのです。
そこで天地一切が「三位一体」で組成されている以上、日本の神社では二拍手でお参りをしますが本当は三拍手しなければ神様には通じない時代になっているのです。「三」は数霊では「実り・安定・成就」を表し、西洋でも「三は完全無欠を示す聖なる数字」と考えられ、神を表す音楽が三拍子で統一されるといった現象をも起こりました。
ところでそうなると、「イエス・キリストは神なのか、人間なのか」という3世紀の命題が再び浮上してくることになりますが、「イエスは神の子であり、神である」と考えるのはキリスト教徒だけで、現代でもユダヤ教徒は「イエスは人間であり、ウソつきのペテン師である」と考え、イスラム教徒はイエスを「神の使い」と考え、「神は男も女もなく超越した存在なので、子を持つはずがないからイエスは神の子ではない」というのです。モーセもイエスもマホメット自身も神の使いであって、神ではないとイスラム教は考えています。では、実相はどうなのでしょうか。それは、「モウシェも釈迦もイエスも人間であるが、人間であって人間ではなく、神である。神といっても、天地創造の大天津神ではない、使いの神である」ということです。つまり人間であって中身は神様であるが、神様といってもいろいろな神様があり、人間に化けやすい神、子神、神の使いであり、人間であるということで、「人間にて神にて、神にて人間にてはなくて人間にて神なり」で、結局何なんだ? ということになりますが、イエス・キリストも「人にて、主でもなく、天の父ででもない。人で、神で、大神ではなくて、神にて神にあらずして人間なり」と、つまりどれもが正しくてウソで正しいということなのです。
○イエスの誕生日は?
イエスは西暦元年12月25日の生まれではありません。イエスは少なくとも紀元前4年以前には生まれています。イエスの誕生の年を紀元元年として西暦が定められたわけですから、紀元前4年の生まれというのはおかしな話ですが、イエスの誕生の年として西暦元年と定められた年より4年前に、イエス誕生時に在位していたはずのヘロデ王が死んでいることが分かったため、イエスの誕生は当初思われていたより古く、紀元前4年よりも前ということになったのです。また、誕生日が12月25日生まれというのも、ゲルマン民族の冬至の祭りに合わせて4世紀ごろに決められたもののようです。
○イエスの出生地は?
イエスはガリラヤで誕生したようです。聖書ではベトレヘムにて誕生となっていますが、これは「旧約聖書」で「救世主はベトレヘムで生まれる」とある記載と符合させるための作為と思われ、信憑性に欠けます。また、イエスの家族の家も、エドガー・ケーシーのリーディングによればナザレではなくカペナウムであったとのことです。
○キリスト教(ユダヤ教)は本当に一神教か?
「創世記」1−26では、神は御自身のことを「我われ」と表現しています。教会はこの「我われ」を上で述べた「三位一体の神」という意味に解釈していますが、どうも説得力に欠けます。また、十戒で「私以外の神を祀るな」という意味の掟を神は下しておられますが、ほかに神がいない唯一神なら「いらぬ心配」になるのではないでしょうか? 要は、天地を創造された創造神はおひと方だが、その眷属の神々は大勢いて、キリスト教ではそれを「天使」と表現しているとも考えられます。つまり、真実は一神であり、多神であり、汎神でもあって、どれもが本当でうそで本当ということになります。
○イエスは革命家だったのか?
一部には、イエスは宗教家ではなく、ユダヤのローマからの自主独立を目論んでいた政治的革命家だったと考えている人もいますが、「マルコ伝」9−29〜30でペテロがイエスに「あなたは救世主です」と言うと、イエスはそのようなことを言うなとそれを戒めています。イエスがなぜペテロの信仰告白とも取れるこの言葉を戒めたのかは、「救世主(ヘブライ語:メシア、ギリシャ語:キリスト)」という言葉の現代のわれわれが受けるイメージとは違う特殊性が、当時のユダヤにはあったからです。つまり、当時「救世主」というのは、反ローマ革命分子を意味したのです。ペテロがそのようなことを言ったものだから、イエスは激しく戒めたわけで、「反ローマ革命分子」という意味での「救世主」であることをイエス自身がはっきりと否定したことになります。イエスが反ローマの政治犯に対する処刑法の十字架にかけられたのは、ピラトゥスの誤解だと考えられます。
○イエスを十字架にかけたのはユダヤ人か?
福音書ではイエスの十字架刑をユダヤ人たちが望み、ローマが派遣したユダヤ知事ポンティウス・ピラトゥス(福音書ではポンショ・ピラト)はそれを抑えきれずにしぶしぶ従ったという記載になっています。しかしそれは、福音書の著者が読者ターゲットとしてローマ人をも意識していたため、ローマの知事を悪者にするのは都合が悪いと考えてピラトの弁護をしたものと考えられます。宗教犯ならばユダヤ人の手で石打ちの刑にもできますが、政治犯を処刑する死刑法である十字架刑はローマの知事にしか判決権も執行権もなかったのです。こうなると、もうピラトの弁護はできません。しかし、ユダヤ人とてイエスを逮捕し、最高法院で裁判にかけているのですから「シロ」ではないでしょう。
これは、イエスを既成宗教にたてつく新興宗教の教祖で危険人物とみなし、特に神殿で大暴れしたことから神殿を冒涜し、安息日を破り、祭司や律法学者を批判したなどの宗教犯として逮捕したというのが表向きのとらえ方ですが、ユダヤ人という民族の性質を考えるともっと奥の深いものがあるようです。ユダヤ人は唯一神を崇める民族ではありますが、その後の歴史上で果たした役割、すなわち多くの政治家、エジソンなどの発明家やアインシュタインなどの科学者、マルクスのような経済学者などがすべてユダヤ人であることなどから見ても、ユダヤ民族の役割は物質開発にあるようで、物力を持つ民族です。そして物質文明による世界制覇と支配が彼らの理想で、唯物とは反対の神の道を説くイエスは相容れない存在だったのでしょう。
そこで、神様はなぜ釈尊(ゴータマ・シッダルダー)をインドに、イエスをほかのどの民族ではなくユダヤ人として生まれさせなさったのかということも、何か奥深い神様のご計画がうかがわれます。
なお、イエスを裏切ったユダですが、ユダはどうもイエスに政治的反ローマの独立運動を期待していたようです。そして最後までイエスを信じ、イエスが死刑になりそうな時に大奇跡が起こって助かったら、それでみんなはイエスを信じるはずだという大ばくちに出たという考え方もあります。
○イエスは本当に十字架で死に、そして復活したのか?
前ページで引用した資料の「コーラン」や「竹内文献」を参照して下さい。ちなみに、イエスの弟のうちヤコブとユダ(イスカリオテのユダとは別人)はイエスの使徒になっていますが、すぐ下の弟のヨシェは一度だけ名前が出てくるだけで、そのほかは全く福音書には登場しません。
○誤訳シリーズ
『らくだの穴』(マルコ10−25)
「富んでいるものが神の国にはいるよりは、らくだが針の穴を通る方がやさしい」(口語訳)
「皆さん。富に心を向けたままで、神の国に入ることは不可能ですよ」(現代訳)
この部分は本当は「らくだ」ではなく、綱(ロープ)のことだという説があります。そうなると「針の穴」とは「針で刺してあけた穴」ではなく、針に糸を通すあの「針の穴」となります。なぜこのような誤訳が生じたのかといいますと、もともとアラム語では「らくだ」も「綱」も「ガムラ」という同音異義語だったから福音書著者がイエスの言葉をギリシャ語で表記する際に間違えたのだという説と、ギリシャ語では綱は「kamilos」、らくだは「kamelos」とよく似ているので混同されたのだという説とがあります。
『地の塩』(マタイ5−13)
「あなたがたは地の塩です」
ここでいう「塩」とは、調味料の塩ではありません。「人間の世界の味付けをする訳」という意味ではないのです。日本では塩を、お葬式の後などで「浄めの塩」として使ったり、飲食店の入り口に塩を盛ったり、お相撲さんが土俵に塩をまくなど、塩は「浄めるもの」として使われます。そしてなんと「塩=浄めるもの」という考え方があるのは、世界広しといえども日本民族とユダヤ民族だけなのです。古代ユダヤ人は、ランプの煤の汚れを塩で磨きました。従って、ここでは「あなた方は人々の魂の曇りを取り除く研磨剤」「全人類魂霊浄めと毒![]() 消除の
消除の
『ひとつの目』(マタイ6−22)
「あなたの目が澄んでおれば、全身も明るいだろう」(口語訣)
(英訳)“If,then,your eye is sound,your whole body is in the light.”
ここは、肉体としての「目」ではありません。日本語には名詞の単数と複数の区別がありませんから誤解が生じやすいのですが、英語訳をご覧頂ければ分かるように「目」は「eyes」ではなく、単数の「eye」になっておりbe動詞も三人称・単数・現在の「is」が使われています。つまりここは肉体の二つの目ではなく「ひとつの目」、すなわち人間の「魂(霊魂)」をさします。次の解釈を参考にして下さい。
(参考…M・ドーリル『聖書の真義』)
「第22章の『あなたの目が澄んでいれば』のひとつの目とは、人間の頭脳の中心にある松果腺に位置する第三の眼、つまり、魂の目のことである」
つまり、眉間の奥約10センチの「松果体」と呼ばれるところに神の分けみ魂である主魂が宿っており、イエスはその魂のことを言っているのです。つまり、川上である魂が浄い人は川下である肉体も清いということで、あくまで「霊が主体で、心は従、肉体はそれに属しているのみ」という宇宙の法則を述べているのです。本来は水晶球のように透き通っていたはずの主魂が罪によって曇れば神の光は入らなくなり![]() 」は枯れていきます
」は枯れていきます![]() 枯れ)」の本義です。
枯れ)」の本義です。
引用した「聖書の真義」の著者のドーリル博士(1901〜1963・米)はブラザーフッド協会の創始者で
『10人の少女』(マタイ25−1〜13)
「そこで、天国は、自分たちのあかりを手に持って、花婿を出迎えに行った十人の娘たちにたとえることができます。そのうち、五人は愚かで、五人は賢い娘でした。愚かな娘たちは、ランフは持っていましたが、予備の油は持っていませんでした。しかし、賢い娘たちはランプと一緒に、予備の油を持って来ておりました。花婿が来るのが遅れたので、彼女たちは皆、うとうとと眠り始めてしまいました。夜中に、『さあ、花婿だ。出迎えに行きなさい』と叫ぶ声がしました。娘たちは皆起きて、自分のランプを用意しました。ところが、愚かな娘たちは、賢い娘たちに言いました。『あなたがたの油を、私たちに分けてください。私たちのランプの火がもう消えてしまいます』。すると、賢い娘たちはこう答えました。『二人分の油はありません。それよりも、店へ行って油を買ってきた方がよいでしょう』。彼女たちが油を買いに行っている間に、花婿は来てしまいました。用意の出来ていた娘たちは、花婿と一緒に婚宴場に入り、戸がしめられてしまいました。その後で、油を買いに行っていた娘たちもやって来て、『ご主人様、ご主人様。戸をあけてください』と言いました。しかし、主人は答えて、『よく言っておきますが、確かに、私はあなたがたのことなど、どうでもよいのです。どうして初めから分かっていたのに、用意をしていなかったのですか』と言いました。だから目を覚ましていなさい。(以上、『現代訳聖書』。以下、日本聖書協会『口語訳 新約聖書』 マタイによる福音書25章14節)その日その時があなたがたには分からないからである。
天意の転換による火の洗礼・大天変地異がいつ訪れてもいいように、油断なく、落ち着いて、着実に行動しなさいという教訓である。
『4種の耕地』(マルコ4−3〜8ほか)
「『よく聞きなさい.種を蒔く人が種蒔に出て行きました。種を蒔いているうちに、ある種は道端に落ちました。すると、鳥が来て、それを食べてしまいました。ほかの種は、たいして土のない石地に落ちました。そこには土が深くないので、すぐに芽を出しましたが、日が上ると、焼けてしまい、根がないので枯れてしまいました。ほかの種は、いばらの中に落ちました。すると、いばらが伸びて、ふさいでしまいました。そのため、実を結びませんでした。しかし、もうひとつの種は良い地に落ちました。すると、芽ばえ、育って、あるものは三十倍、あるものは六十倍、あるものは百倍の実を結びました』。そして、イエスは最後にこう言われた。『わたしの言っていることが何を意味しているのか、よく考えてみなさい』イエスがひとりだけになると、いつも一緒にいる弟子たちが、十二使徒と共に、これらのたとえのことを尋ねた。そこで、イエスは言われた。『あなたがた弟子たちは、神の国の奥義を知ることが許されていますが、ほかの人たちは許されていません。ですから、すべてたとえで言わなければならないのです」 (中略)そして、彼らに言われた。『このたとえが分からないのですか。そんなことで、どうしてほかのたとえが理解できるでしょう。種を蒔く人は、み言葉の種を蒔くのです。み言葉の種が道端に蒔かれるとは、こういう人たちのことです。――み言葉を聞くと、すぐ悪魔が来て、彼らの心に蒔かれたみ言葉を奪って行ってしまいます。同じように、石地に蒔かれるとは、こういう人たちのことです。 ――み言葉を聞くと、すぐに喜んで受け入れはしますが、根を張らないでいるため、ただしばらくの間、続くだけです。み言葉のために患難や迫害が起こってくると、すぐにつまずいてしまいます。もうひとつの、いばらの中に種が蒔かれるとは、こういう人たちのことです。――み言葉を聞くことは聞きますが、この世の思い煩いや、富の惑わしや、そのほかいろいろな欲望が入り込んで来て、み言葉をふさいでしまうと、実を結ばなくなってしまいます。ところが、よい地に蒔かれるとは、み言葉を聞いて受け入れ、三十倍、六十倍、百倍の実を結ぶ人たちのことです』」(『現代訳聖書』)
このたとえは一面からいうと「人によって法を説け」ということで、教えを伝える相手が頑固で天狗になっているとなかなか受け入れにくいのですが、知識、教養度が広く深い人は簡単に判断を下さないから受け入れ態勢がよく、大樹に育つということです。もうひとつの面では、自分たちの受け入れ態勢がどうであるかによって、同じ神の光と教えを頂いても、一年、二年たつうちには非常に個人差を生ずるということです。ですから、自分の受け入れ態勢はどんな常態かということをはっきりと認識してかからなければならないということです。「自分の心ではなく、魂の実相を反省すること」が大事です。
『良きサマリア人』(ルカ10−25〜37)
「その時、ある律法学者が現れて、イエスを試そうとして言った。『先生、救われるためには、どんなことをしたらよいのでしょうか』。彼は逆に彼に質問して言われた。『律法には、どう書いてありますか。あなたはどう理解していますか』。彼は答えて言った。『心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの主である神様を愛しなさい。また、あなたの隣人を、自分自身のように愛しなさいとあります』。イエスは言われた。「あなたの考えは、正統的です。ただ問題は、それを実行していないところにあります。それが実行できるものなら、それを実行してご覧なさい』。すると、彼はいかにそれを実行しているかを示そうとして、イエスに言った。『それでは、私の隣人とは、誰のことですか』。彼は、もしイエスが、『この人が隣人です』と言えば、「私はその人を愛しています』と言いたかったのである。そこでイエスはひとつのたとえを話された。『ある人がエルサレムからエリコヘ行く途中で、強盗に襲われました.強盗どもは、その人の服をはぎ取り、傷を負わせ、半殺しにしたまま、逃げて行ってしまいました。すると、たまたま、ひとりの祭司がその道を下ってきましたが、この人を見ると、見ぬふりをして、向う側を通って行ってしまいました。次に、祭司を助けて神殿で働いているレビ人がやって来ましたが、彼もこの人を見ると、向う側を通って行ってしまいました。その後、ひとりのサマリア人が、旅をしながらそこに来ますと、この人を見て、かわいそうに思い、近寄って来て、携帯用の救急箱から薬を取り出し、手当てをし、自分のろばにのせて、宿屋に連れて行き、介抱してやりました.一晩中介抱してやった上、翌日、快方に向かっているのを見届けてから、宿屋の主人に十分なお金を払い、この人の面倒を見てやって下さい。もっと余計に費用がかかりましたら、帰りに私が払いますからと言いました。この三人のうちで、誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか』。彼は言った。『その人にあわれみ深い行ないをした人です』。そこで、イエスは言われた。『あなたも、この人のように真実に隣人を愛してみようと思ってごらんなさい。それが自分の力だけでできるかどうか』」(『現代訳聖書』)
この話は「隣人愛」をといているとよく言われますが、それだけではありません。傷ついた者を助けなかった祭司やレビ人は神に仕える人です。決して心が冷たかったわけではなく、彼らには職務があり、傷ついた人を助けたりして血がつこうものなら血の穢れに触れ、神殿での職務が遂行できなくなり、神にご無礼になると考えたのです。イエスが、そのような伝統の上にあぐらをかく既成宗教家を痛烈に批判したのがこのたとえ話です。生きた救われが伴わないいわゆる宗教家は、まじめにやればやるほど神のお邪魔すらすることになりかねないということです。
 |  |  |