| ��U�́@����ȐD���X
�͂����J��
�@�����X�i1876�j�N�̏t�A���g���̈�p�Ɂu����ȐD���X�v���a�������B����قǍL���Ȃ��Ɖ��ɁA�D�@�P��𐘂��������̓X�܂ł���B
�@�g�N�����鋰��^�e�����Ă݂�B�͂`�����܂��Ԃ�����Ă���邩�s���ł������B
�@�T��H�̋��͂Ŋ��������u���쎮�ȐD�@�v�ŁA�P����D��������T�������������B�������A�ł�������͖�����̂��̂ɔ�ׂĂ������y�Ȃ��B���蕨�ɂȂ�܂łɂ͑����̎��Ԃ��o�債�Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B�d�������܂�����������ƁA�R�ɐ���������T���ɂ������Ă��āA��Ƃ𒆒f������B
�u�ł邱�Ƃ͂Ȃ���B�g�N�����ɂƂ��Ă̂͂��D��́A20�N�Ԃ�̂��Ƃ��Ⴏ��ȁB������芴�G���v���o���悩�v
�@�{�������q���Q���Ƌ��ɂ���ė����B
�u�������݂܂���B������������Z�����ł��傤�Ɂv
�@�g�N�̕����C���g�����B
.gif)
���݂̐V�f�i���g���j
�u�킵�͉B���̐g�����B�B�����X�̒��E���E�����Ƃ�ƁA���q�����邳���邯��ȁB�������ƌ����ĉƂɃS���S�����Ƃ�����A���������►�Ɍ����邵�B�����܂ŕ����Ă���ƁA���x�悩�^���ɂȂ邯��v
�@���ς�炸�����q�̐��͑傫���B
�u���炠�珼���̂��������A���������Ƃ炷���ˁv
�@�V�Q�������ƁA���₩�����{������B�V�Q�̌�ɂ͎Ⴂ���������Ă����B
�u���̖�(��)�́A�L��i�������S�L�쒬�j�ł�����D����Ƃ�m�荇���̖������B�g�N����Ƃ��̐D��q�ɂǂ��Ɓv
�u�D��q�͎��P�l�ŏ\����B�D��@���P�䂵���Ȃ����v
�@���f�C���̃g�N�̕Ԏ��ɁA�V�Q�̑吺����(����)�������B
�u�����Ȃ��Ƃ���A�͂����̂����݂���͋܂�܂�������B�͂��D��͐D��q�ɔC���āA�����݂���͍ޗ��̂��ƂƂ����肳���̂��Ƃl���Ȃ���B����ɥ���v
�u����ɁA����v
�u�����̂��Ƃ����B���Δ����āA����ΐ��߂ĐD��B�D�������͔̂���Ȃ���̍ޗ���������ł��傤���B�g�N����͂��̓X�̑叫���Ⴏ��A�����̂Ƃ���悤�l���Ă����Ɓv
�u����ȐD���X�v�̊Ŕ��f����1�������o�������A�ɂ킩�ɍ�Ə�̕\�����������Ȃ����B
�u������A���̐l���T�l�����āA���ɓ���Ă���낿�����Ƃ�܂����v
�@�V�Q���A��Ă����m���q���A�O�̗l�q��m�点���B�W�܂����������́A���@���������Č����ɂ����炵���B
�u�d���̎ז��ɂȂ�Ȃ�����܂�Ȃ����v
�@��Ə�ɓ����Ă����������́A�Ⴂ������q����w���������N�܂ł��܂��܂ł���B
�u�ǂ����痈���́H�v�ƕ����ƁA�����̎҂�����A�Q�������ꂽ�c�ɂ���킴�킴����ė����ƌ�����������B
�u����Ȃ�A����ł悩�ˁv
�@�ޏ���̑���ۂ͂���ł������B�u�����̐D��@�����āA�ǂ�����́H�v�ƁA�g�N���q�˂�ƁA�u�����œ������Ă��������v�ƌ����o���B
�@�����̌��w�҂́A�X�ɑ�����10�l�����B
�u������A�����̐l�̎q�����@�B�ɂɂԂ牺�������葖�������肵�āA�d���ɂȂ�܂�����v
�@�m���q���ߖ��グ���B
�u�悩�ˁA���̓ꂩ�璆�ɓ������Ⴂ�����v
�@�V�Q���A�D��@������������悤�ɓ�����B����ł����w�҂̐��͑��������ł������B
�u�g�N����A�@�B�Α��₵�܂�����B���߂ĂT�䂭�炢�ɂ́v
�u�ǂ����āH�@���w�҂���������H�v
�u��������Ȃ���B�����̔ԓ�����A�o���オ�����i���Α��������Ă��邲�ƌ���ꂽ�Ƃł���B����ɁA���삳��॥��B�D��@�P�䂶��A�ǂ���撣���Ă��Ԃɍ����v
�@�����Ƃ́A�{�������q�̓X�̉����ŁA����́A�����쎟�Y���X�̉����̂��ƁB
�u������A�Ԃɍ��������Łv
�u���ꂪ������Ƃł���B���������J�X�̂��j�V�ɂƒ������Ă������邨�q����܂ő��ɂ�����A���̂��߂ɋ�J���Ă͂����Ύn�߂����킩���ł����傤���v
�u������������ǁA���̉Ƃ��Ⴑ��ȏ�D��@�͒u���Ȃ����v
�u���v�A�����̒���ɍ�Ə�Ό��đ��������邯��B�@�B����}���ō�点�邽���v
�u��Ԓ��͂ǂ�����́H�v
�u�n�����ˁB���ꂾ�������������A���炢�̋��͂����ɏo�邭���v
�@�V�Q�Ɍ�����A�Ԃ����t��������Ȃ��B������ꂽ�`�ŋT��H�ɐD�@���S�䒍�������B����Ȃ��Ȃ����D��q�́A���w�҂̒�����̗p�����B
�u�悩�ˁA�������炠�����͉�����̒�q���Ⴏ��A�搶�ƌ����Ȃ����B�m���q���悩�ˁv
�@�V�����@�B������A�D��q���T�l�ɑ������Ƃ���ŁA�V�Q���O���������B
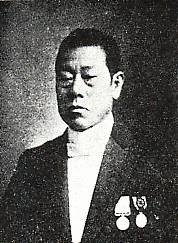
�{������
�@�g�N���A�͂����Ƃ��ď��߂Ĕ���o�����ȐD���̒l�i�́A�P��������80�K����85�K�ł������B������Ǝ�̂�������̂�1�~30�K����40�K�B�����v�����R���A���݂̂��̂łP�~50�K�������̂ɔ�ׂ�A�ȐD���͗y���Ɉ����ߗ��ł���B
�u�]�����悩�ł���A���쏤�X�̎Ȃ́v
�@���X��������鏯���q�̑��q�̏������A�����������ŖJ�߂��B
�u����ς�A�l�i����������ł��傤���v
�u�����������Ă�B�����ɂ��錺�l����i�������j�́A�u�i���悩�v�Ƃ�������炷�v
�@�g�N�̖₢�����ɁA�����́A������ɂ͂Ȃ��z�n�̕��̊��炩�������������B������̑o�������̌��ʂ������炵�Ă���̂��낤�Ƃ��t���������B
����푈�̌��Ɖe
�@�{��������̉����ŁA����ȐD���X�͏����Ɋ���o�����B��������͂����̔ԓ��i�ɔ[�܂��Ă���V�Q���A���ɂ̒������܂���ɂ܂���Ă���Ƃ��@���ł���B
�@�J�Ƃ��甼�N�o���������X�N�̕����߂����B�U���̂��ł��ƌ����Ȃ���A�����q�����ꂽ�B�����q�͂��̓��A��������s���ۂ������B
�u���q������������Δ���܂���Ƃ͂悩���Ă�B�D�鎅�������ǂ��Ȃ��v�ƁB
�u�����Ă�������A�D���͂�����ł�������Č���������Ȃ��ł����B���̕������ɁA�����a���ł�������炢���ł��傤�Ɂv
�u�S���̖���ł��a�����炢����A�Ԃɍ����Ƃ����v
�@�b�̓r���ŁA�����q�̘b�������ȕ����ɔ�B
�u�Ƃ���ŁA�܂���(������)���n�܂邰�ȁv
�@�������i�F���j�̕s���m���炪�A�V���{�ɑ��ĕ���������ƌ����B�s���m���Ƃ́A�����������t�Ƌ��F���̎Ⴂ�ˎm��̂��Ƃł���B
�@������m���̓������Ƃ݂Ȃ����{�́A�u���������\�k�����߁v���āA�ꋓ�ɒ@���ׂ��ɂ��������B�������ɔC����ꂽ�L�������m�e��(���肷���킽��ЂƂ���̂�)�́A�R��16���ɔ�������v���Ăɓ���A������̎t�͊w�Z�i�����P���Z�j�ɖ{�c��u�����B
�u���炭�A�}������ɂȂ邶��낤�Ȃ��v
�@�����q�́A�v���Ă̒�����Ȃ���悢���ƗJ�����B
�u����߂���ǂ̒��ł́A�푈�łЂƖׂ����悤�ƒ�����Ƃ�҂����邻���ł�������v
�@�V�Q���A���̉\�b�������q�Ɋm���߂��B
�u���������B����̊쎟�Y���Ɖ��̉_�����A�����Ă����̏����܂ł����A�ő��ɂȂ��҂������������Ē�����Ƃ�B���ɉ_���́A���R����傻���傫�������ΖႤ�����ȁB�쎟�Y���A�������̎d����ɑ��͂����Ƃ�v
�@���Ɍ����u����̖��i�푈�j�v�́A���ꂩ��Ԃ�u�������ĉ����B

����푈�����{�c�ƂȂ������P��
�@�퓬�̂����܂����͂W���i��32�`�j���ꂽ�v���Ă̒�������A�e�ՂɌ��ĂƂꂽ�B�R�c�a�@�Ɉߑւ������v���Ďt�͊w�Z�́A��ꂩ��^�э��܂�Ă��鎀�����ł������Ԃ����B�L�^�ł́A�펞��1300�l���̕��������S�����܂ꂽ�Ƃ���B

����푈�̐}
�@����������̍D�@�ƍl����q�c�_���̖�]�́A�Ԃ��Ȃ��ł��ӂ���邱�ƂɂȂ�B�J��ɂȂ�A�K�����R����������Ă����Ɠ���ő~���W�߂��R���������A���ׂē��ĊO��ɂȂ�������ł���B�q�c�_���́A�X���J�����Ƃ��̕n�R�X��ɋt�߂肵���B
�@�����쎟�Y�͂Ƃ����ƁA����푈�����܂���ɋt��ɂƂ��āA�������ɂ����B�푈�́A�쎟�Y�ɂƂ��č����l�ւƋ삯�オ���Ă������ݑ�ɂȂ����̂ł���B
�@����푈���I����āA�P�N�o���Ă��g�N�̊炪�Ⴆ�Ȃ��B����ȐD���X�͏����Ɋ���o�����Ƃ����̂ɁB
�u�쎟�Y����́A�����ׂ����ł�����������Ȃ���B�ł॥��v
�@��������Ȃɕs���Ȃ̂��A�g�N�̋C�������킩�鏯���q�́A��ɂ���ăL�Z���̎��@���ăL�U�~�����𗎂Ƃ��̂ɖZ�����B
�u�Q���l�߂��펀�҂������āA���ׂ����Ȃ������������Ƃ���낤�v
�u�����ł���B���ɂ͉_�������쎟�Y����̂悤�ȏ������킩��Ȃ���B����ɁA�v���Ă̐l�����́A���������̍w���ӗ~�Ɉ���肵�āA���̈�����������Ă�����Č������Ⴀ��܂��v
�@�g�N���Q���̂́A�v���ď��l���A�푈�A��̕������ɁA������̑e���i����Ă��邱�Ƃł������B�����ł���͂��̐����̑���ɁA�e���ȉ��w��i���g�p���Ă���Ƃ����B�����\�́A���ȗ��s��̂ƂȂ��ċv���ď��l�̐g�ɒ��˕Ԃ��Ă����B�u�푈�߂�ɋv���Ăł����������A�g�k(�ׂɂ���)���߂Ƃ͘I�m�炸�A�j�Ȃ�Ⴑ���x���ꂽ�v�ƁB
�@����푈�́A�v���ĂƎЉ�̏鉺�����珤�l�̒��ɕϖe�������ԗւ̖�����S�����ƂɂȂ����B�����A���Ԃ��̂��Ȃ����̈�Y���������ɔw�������ނ��ƂɂȂ����̂ł���B
�Ј���ꍆ
�@����푈���N�̖���11�i1878�j�N�B�_���̕�炵�͂܂��܂��������Ȃ��Ă����B�������}���Ɠ����n�͐�̔×��ŕĂ̎��n�̓[���ɓ������A�铦��������҂����₽�Ȃ��Ƃ����B�����āA�n��Ⓑ�j�̌������肪�����Ȃ�A��j�V�ȉ��̑��q�⏬��l�́A����̎������炵��Ȃ��Ă���Ƃ��B���́A�_��Ƃ̔�������Ԃ��Ȃ��A����Ƃ�]�V�Ȃ������B�_�Ƃ����ł͐H���Ă����Ȃ��҂́A��������܂ŏo�҂��ɏo���B
�@����Ȏ���̉āB
�u�g�N�����A���邩���v
�u��������̐��͂P���悩��ł��������܂���v
�@�{�������q���A���̓��͎�҂�A��Ă����B
�u�����͂ˁA�m�荇���̑��q�ő�Ε����Y�B��\��(�͂���)���ȁv
�u����ŁA������ɉ������p�ł��H�܂����A�D��q�u�]�ł��Ȃ��ł��傤�ˁv
�u�X�Ŏg���ė~�����ƁA���̒j�v
�@�����q�̌��t�ɁA�g�N�͌˘f�����B
�u�n���Ȃ��Ƃ�����Ȃ��ł��������B�͂��D��͏��̎d���ł��v
�@�����q�ƃg�N�����������Ă���ԁA�A��Ă���ꂽ�N�́A�ق����܂܊O�̌i�F�߂Ă���B�D��q�����͂Ƃ����ƁA��l�̉�b�ɂ͎����݂����A�فX�ƞ`�����E�ɓ����������������B
�u�����Y�ɂ͂��D������낿�͌����Ƃ��B�D��オ���������Δ��点��d�������B������͂킵�������邯��v
�@�����q�̐����A�ǂ�h����悤�ɑ傫���Ȃ����B
�u���̕����Y����Ƃ��̂������́A�N�������́H�v
�u�H���}�����炢�����ʼn҂������v
�u��������͋C�y�ł����ł��ˁB�ǂ�ǂ�D���Ăǂ�ǂ��A����ȂɊȒP�Ȃ��̂ł��傤���A�����Ƃ������̂́v
�u����ł��ǂ����Ĕ���̂��A�����Y�̎d������Ȃ����v
�@���l�̉�b�́A�̐S�̑�Ε����Y�����ɒu�����܂܁A���X�Ƒ������B
�u���������ɂ��̎�҂������t����A�{���̗��R(�킯)�����Ă��������v
�@���낻��g�N���A�����q�Ƃ̘b�Ɍ����������������B
�u�g�N����D��Ȃ́A���ꂩ����ǂ�ǂ��B�܂��A�g�N�����̐^�����ĐV���イ�͂�����������������Ă��邶��낤�B�����Ȃ�ƁA�܂��܂��M�p���ĂΏ��������ɂȂ��Ƃ������B�����Ȃ�ƁA��������̑g������ɂ�Ȃ��v
�u�������v
�u�����ł��A������Ɠ������ƁA�ȐD��̕��ɂ��L�\�Ȑl�ނΈ�ĂĂ����K�v������Ƃ����v
�u���̐l�ނ��A�����Y����H�v
�@�g�N�́A�����q���܂��܂��v���Ă̐D���ƊE�ɌN�Ղ��Ă��邱�Ƃ��Ċm�F������ꂽ�B�������āA�g�N�̂͂����ɎЈ���ꍆ���a�����邱�ƂɂȂ����B
�������Y����
�@�����������ɂ����������ŁA�g�N�̔Y�݂������邱�Ƃ͂Ȃ��B
�u�{���ɋC���d���̂�B�O�̂��Ƃ͕����Y������Ă����Ƃ��āA��Ə�̒��̂��ƂƂȂ�Ɓv
�u���Ό����Ƃ�́B�ڂ̑O�̂��V�Q���ᗊ��ɂȂ�����Ƃˁv
�@�V�Q�́A����̋T�g�ɐD�@�̉��ǂ𑣂��Ȃ���A�g�N�̎d����⏕���Ă������Ƃ��d���ɂ��Ă���B
�@����푈�̉e���ŕ����͍������A�_���̕�炵�͂܂��܂��ߎS���𑝂��Ă����B���̂��Ƃ��A����ɂ��A�ȐD�����ƂƂ���g�N�ɂ͍K�����Ă���B������͒l�������Ĕ����Ȃ��_�����A�����ď�v�ȏ���ȐD���X�̔������d������ł���B�ŋ߂ł͐D��q�̋x�ݎ��Ԃ��\���Ɋm�ۂł��Ȃ��قǂɑ��Z���ɂ߂Ă���B
�u���k������܂��v
�@�����Y�����܂��������Ńg�N�ɋ߂Â����B����Ȏ��̕����Y�́A�K���V�������Ƃ��Ă��Ă���B�ȒP�Ɂu�킩�����v�Ƃł����������̂Ȃ�A���ۂ̎d���͂��̉��{�ɂ��c���Œ��˕Ԃ邩����ł���B
�u�����̓X�́A���̂܂܂��Ⴂ����Ǝv���Ƃ�܂��v
�u�������v
�@�g�N�͕Ԏ��������ɁA���ނ����܂܂Ŏd���𑱂����B
�u���ꂩ��̔������́A�����l������₷�����ƁA�����Ες��ɂ�Ȃ�v���Ƃł��B����������ōl����Ƃ���̂��āA�����l�Ɍ��߂�����悩�ł��v
�u���Ȃ��������Ă��邱�Ƃ��đ�ςȂ��Ƃ�A�����Y����v
�@�������������l�̌����Ƃ���̕���D���Ă�����A����ꂽ���������̐}�ʂ�`���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��߂̐l����K�v�ɂȂ�B
�u����Ƃł���A�}����`��������Ȃ��Ȃ��r�̗����Ȃ����v
�@�����̒��A�����Y�͍r�ؑ��ɏZ�ޓ�\�㔼�̏�����A��Ă����B��̂悢���Ƃł́A�V�Q����������قǂ̒j�ł���B���̖��O�́A��c�n�c�R�Ƃ������B
�@����ȐD���X�̐D��q���W�l�ɖc�ꂽ�B�n�c�R�ƈꏏ�ɍ̗p���ꂽ���̃}�T���ƂƂ��ɁA��Əꂪ�₩���𑝂����B
�@�������Y�����������āA�����l�̏o����͂܂��܂��p�ɂɂȂ����B���鎞�ɂ́A�T�l���U�l���������Ɍ����ɍ��荞�ނ��Ƃ�����B
�u�����̂Ƃ���A���ǂ��ł́A�D����̂Ɍ��x������܂��āv
�@�g�N���ǂ�Ȃɒf���Ă������l�͋A�낤�Ƃ��Ȃ��B����ǂ��납�A���ɕ�T�~�Ƃ�10�~�̎�t��������ɒu���Ă����n���ł���B�����Ȃ�ƁA�������ߖ�ʂ�z���Đ⋩�������S���ɂ��Ȃ�B
�u����Ȃɒ�����f���Ă�����A���̂������q�����Ȃ��Ȃ�܂��v
�@�����Y���g�N�Ɉӌ������B
�u�ǂ���������Ǝv���H�@���ꂶ��A��������ɂ����삳��ɂ��s�`���̂�����������Ȃ��́v
�u���삳��Ə�������Ȃ���v�ł���B������ɂ́A�֓��Ƃ������炩����̒������E�����Ƃ邻���ł�����B�{���͎Ȃ�������Ƃ�ȂȂ��Ƃł��B�����襥��v
�@�����Y���܂������������Ƃ��邩��A�g�N�����R�ɐg�\�����B
�u�D��@�Α��₵�܂�����B���߂�15�䂭�炢�ɂ́v
�@�X�𗧂��グ�Ă���܂������̂ɁA�ꋓ�Ɋg�傷�邱�Ƃ��|�������B���̏o������̓V�Q�ɔC���Ă��邪�A�ʂ����Ă��������Ă���̂��ǂ��������悭�킩���Ă��Ȃ������B
�u���v�ł��B�X�͊m���ɂ��������Ƃ�܂��B�D��@�ƐD��q�Α��₹�A���̕���������グ�͏オ��܂�����v
�@�����Y�́A���̐S�z���Ȃ��ƌ����ď����B
�@
�@�g�N�̏��ɂ́A��q�u��҂����₽�Ȃ������B�������ɂ�10�l���̏�����Ə��苒���Ă��܂��B�V�Q����������̎d������������ɖ𗧂��Ȃ��B�ޏ���́A�Ƃ̎菕���̂��߂ɂ͂��D����o�������̂��ƌ����B���Ƀg�N�̒�q��20�l�ɖc��B
�@�����ɁA�V���ɂT��̐D�@�����������̂�����A��Ə�͑��̓��ݏ���Ȃ���ԂɂȂ����B�����ŋT�g�ɗ���ŁA�X�ɍ�Ə���p�����������B
�u�搶�A�����͂ǂ���D��悩�ł����v�ƕ������A�g�N�͌����炸�ɒ��J�Ɏw�������B�������Ă����������́A������͎����̎x���ɂȂ��Ă����͂��ł���B���̂��߂ɂ��A�d�����ł���҂ɂ͋������P�`��Ȃ����Ƃɂ����B���ꂪ�܂��A�u��q��]�v�̑����ɂ��q�����Ă���B
�@�����Ɋ���o�����͂��̂͂����ҋƂ��������A�����������܂������Ƃ͌���Ȃ��B�J�Ƃ���R�N���߂�������12�i1879�j�N�̉Ă��I�낤�Ƃ��鍠�B����ȂɌ�(�₩��)����������̐����u�W���W������W���v�ƁA��ꂽ�悤�ɏ������Ȃ����B
�@����Ȏ��A�d���M�S�������c�^�G���A�ˑR�u�d������߂����Ă��������v�ƌ����o�����B�c�^�G�́A���߂��������Ă������ł���B�ꏏ�Ɍ��ꂽ����͌��v���Ĕ˂̉������m�ŁA�ېV��͋߂��̐A�ؐE�l�̂��Ƃœ����Ă���ƌ����B
�u�����炩�瓭�����Ă��������Ƃ��肢���Ă����Ȃ���A���ӔC���Ɠ{���邱�Ƃ͂킩���Ă��܂��B�搶�ɂ͉��Ƃ��l�т������Ă悩���킩��܂���v
�@�c�^�G�́A���b���O�ɋ����o���Ă��܂����B
�u�ǂ������̂�B�����������́H�v
�u����̗F���́A�����������Ƃł��B�ǂ��̐A�؉�����Ɉڂ��Ă��A�Ђƌ��Ǝ�����̂ł�����B�����炩�炢���������������A���̐l�̂₯���̂��߂ɏ����Ă��܂��܂�������v
�u����ť���v
�u�X���Ώ��Ƃ�����������ɁA�Ƒ�����݂ł̊J��c�ɉ����Ȃ����ƗU��ꂽ�Ƃł��B�s����́A������ʂ�߂��āA�����Ɩk�ɍs������Â̈���(������)�Ƃ����Ƃ���ł��B�������͌����ƁA���͔����܂����B����Ȃ牴��l�ōs���ƌ�����ł��B�����ȍ����Ȃ��Έ�l�Ŋ������ɂ��킯�ɂ͂����܂�����B����ł��������͕v�w�ł�����B�S�@��]�A�����ŏo�������ƂɌ��߂܂����B�搶�ɂ͂����b�ɂȂ������ŐS�ꂵ���ł����A�����Ă��������v
�@�F���ƃc�^�G�v�w���������A���ϊJ��̂������͂������B

���ς̊J��n�ɍՂ�ꂽ���V�{
�@�����B�˂ł̖\���̎�d�҂�(������)�����Ƃ��āA�V���{���狌�v���Ĕˎm��Ɍ��������������������Ƃ�����B�����S�N�̂��Ƃ������B���̎��A���ˎm�̐X���Ώ����F�{�̌Y�����Ɍq���ꂽ�B�����ɐ���푈���u�����A�X�����Y�҂����R�ւ̎Q��������ɉ��ߕ����ꂽ�B�I���A�X����͓������̑�v�ۗ��ʂ���A���ςŎn�߂�m�����Y�̊J��ɎQ������悤������ꂽ�̂ł���B
�@�ېV����10�N�ȏ�������Ă���̂ɁA����Ƃ�������E�ɂ����ɖ����Ă��錳�ˎm�������A�X���̗U���ɏ�����B�F�������̒��̂P�l�ł���B�X����ɂƂ��Ĉ��ϊJ��ւ̎Q���́A���ˋv���ĂƂ̌��ʂ����Ӗ����Ă����B
�@�c�^�G�v�w���A���̉Ƒ��ƂƂ��Ɉ��ςɌ��������̂́A����13�i1880�j�N�������Ă����̊������������B�g�N�͂T�ɂȂ�����T���āA�����̓n����Ō��������B
�u�������Ȃ��Ȃ�����A���ł��v���Ăɖ߂��Ă�����Ⴂ�B���ꂩ�炱��A���Ȃ����ǥ���v
�@�g�N�͗F���ɋC�Â���Ȃ��悤�ɁA���K�̓���������݂��c�^�G�Ɉ��点���B�n���M���������݂ɒ����A��s���y����z���Č����Ȃ��Ȃ�܂ŁA�g�N�͐g��������Ȃ��Ō��߂Ă����B�F���ƃc�^�G�����̌�ǂ��Ȃ������A�g�N�ɒm�点�Ă����҂��Ȃ��A�܂����Ԃ��o�߂��Ă������B
.gif)
���{�n�̓n���t��
�@�c�^�G����Ə�������Ĕ��N���������̑����A��c�}�T�����삯����ł����B�o�̃n�c�R����ʂ̌���f���ē|�ꂽ�ƌ����B���������ŋ߂̔ޏ��̊�F�����������B�Z�����ɕ���āA�C���������Ƃ����Ȃ����������g�N���P�����B�������Y�̒S����ł���n�c�R�������Ɏ�͌v��m��Ȃ������B
�@���Ƃ������ė~�����Ƃ̃g�N�̊肢�����A�f������10���ڂɃn�c�R�͑��E�����B�g�N���͂���������Ă����̂ɗ��r�Ɨ��ށA�c�^�G�ƃn�c�R�̂Q�l���Ɏ������ƂɂȂ����B
|

