| ��T�́@��^�q�D�̋L��
���@�Ɠ����`
�@�g�N�́A���`�̍�Ə��`����������ɁA�{�������q�̓X��K�˂Ă���B�Ԍ��̍L���X�̒g��(�̂��)��������ƁA�����ɂ͎�X�̔������s�K���ɐςݏグ���Ă����B�����q�͒��q�����Ƃ���ɁA�����͏��k�Ɏg�����̉��ڎ��Ɉē������B
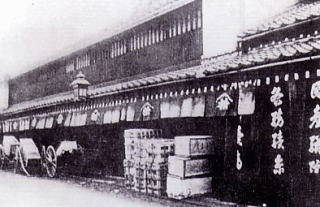
�ʒ��ɂ������{���ؖȐD�����X
�u�֓����痈���ƌ����Ƃ����Ȃ��B������́A�ނ�������ؖȐD�����������Ⴊ�A���܂ꂽ�Ƃ�������̂ւ��H�v
�@�����q�������Ȃ�D���̘b���n�߂��B
�u�������܂ꂽ�̂́A������(�ނ����̂���)�̋{���J�����Ƃ����Ƃ���ł��B����ɂ��Ă��ڂ����ł��ˁA��������́v
�u����͂��������B�������Ă��A�킵�͖ؖȂΔ��邠����ǂ��Ⴏ��v
�������Ȃ��痧���オ���������q���A�I���珤�i�̔��������o���Ă����B
�u���ꂢ�ł��ˁA�ǂ���B�ł॥��v
�u�ł��A���H�v
�u������͂��ꂢ�ł����A���̐D��@�ł��̐D����ł́A�P���ɂ�������D��Ȃ��ł��傤�ɁH�v
�@�g�N�́A���`�̍�Ə�Ō����A�������̋��������Ȏp���ł̂͂��D��̊��z���q�ׂ��B
�u�D���͂�����ł����邯��B�S���Ƃł́A��Ԓ��҂��ɉł���Ƃ������D���Ă����Ƃ����v
�u����ɥ���v
�u�����������Ƃ�����Ȃ�A�݂�Ȍ����Ă��܂���v
�@���̂悤�Ȏ��̏����q�̕Ȃ炵���A�L�U�~�^�o�R���L�Z���ɋl�ߍ��ޓ��삪���܂����B
�u�`(��)�ł���B���̂悤�ɑ傫���ďd�������̂�������A�����グ�邾���Ŕ��Ă��܂��܂��v
�u�������v
�@�܂��A��l�̊Ԃɒ��ق̊Ԃ��u���ꂽ�B���Ɍ��t�����̂��g�N�������B
�u����������Ɏg���Ă����D��@�Ɠ����`(�Ȃ���)���g���A������̂Q�{�͐D��܂���v
�u�قق��A�����̐D��@���͂����h�Ȃ����v
�u���A�������ĐD��܂�����A�����y�ɓ������܂��v
�u����ŁA�g�N����g���Ƃ��������`���́H�v
�u������̂��A�����Ƃ����Ə������Čy�����̂ł��B���ł��ȒP�ɑ���܂��v
�@�b���n�߂��g�N�́A��������10�N�O�̋L���������߂��Ă��鎩���ɋC�����āA�S�n�悳���o���Ă����B
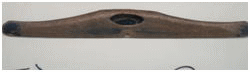 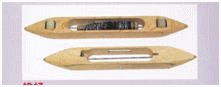 �@ �@
���`�����p�����`�i���j�ƌ���̓����`�i�E�j
�@�C�Â��ʂ����ɁA�����q�̃g�N�ɑ���Ăѕ����u���v����u�g�N�����v�ɕς���Ă���B
�u���ꂩ��̐D���́A�����Ƒ����݂̂Ȃ���Ɋ��ł��炦����̂łȂ��Ɓv
�@�g�N�̌����A�ӂ邳�Ƃł̎ȐD��ɘb���y�ԂƊ��炩�ɂȂ����B
�u�g�N��������A�݂�Ȃ���Ԕ������͂ǂ��Ȃ��ȁH�v
�����q���A�g�N�Ƃ̎ȐD��k�c�ɋ����������Ă����悤���B
�u����́A��������������Ȃ��A���S��������E�l����������܂��A�݂Ȃ����i���Ƃ��Ĉ��������Ă鐶�n��D�邱�Ƃł��B���̐l��������̂́A�����Ə�i�Ɏd�グ�Ȃ���v
�@�b���Ȃ���g�N�̔]���ł́A�{���J���ł̍��@(������)��D��オ��ȕ��͗l�̋L�����������Ă���B
�u�]�˂̕��ł́A�����Ɠ���(���炢��)�i�m�����A���Ȏ��j�Ύg������^�q��(�ӂ�������)�����������s(�͂�)���Ƃ邻������Ȃ����v
�@�g�N�������̐��������ɂȂ����B
�u�Ƃ������A��^�q�Ȃ��ǂ������Ƃ��v
�u���A���̎Ȃ̒[��(�͂�)��������Ă��܂��v
�u�{�������A�ǂ����āH�@�킵���{���������������v
�@�g�N�́A���g�̕�e���炨������ɖ�����[��̂�������������B
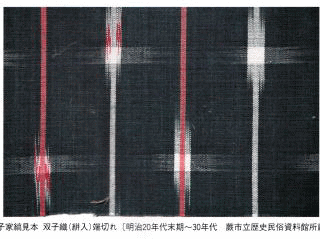
����20�N��̑o�q�D
�u�g�N�����A���܂�̋��Ŋo�����ȐD�����Ă݂�B��^�q�Ȃ��v���Ăł��D�ꂽ��A�悩�����ɂȂ邽���v
�@�ˑR�ȐD��������ɂ��Ă݂�ƌ����Ă��Ԏ��ɋ�����B
�u�ق�̓O�܂ŁA�D���Ƃ͂܂����������̍]�˂̂����~�ɂ�����ł���B����ɁA�������O�ɒ}����n���Ă�������́A�����̏��ł��B����Ȏ��ɁA10�N���̊ԐG�������Ƃ��Ȃ��������Ƃ����ƌ����Ă������ł��v
�u�����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B����10�N�O�̘b�����炷��Əo�Ƃ邶��Ȃ����v
�@�����ăg�N�́A���g�̊炪�Ώ�(�ق�)���Ă��邱�ƂɋC�����A�v�킸���ނ����B
�u��^�q�Ȃƌ����Ă��A���{�͓c�ɂ̂�����ɖ�����[�ꂪ�P�����邾���ł��B���ꂾ���ŁA�]�˂ŗ��s���Ă���ȐD���Č��ł���Ƃ��v���Ȃ����v
�@�����A�g�N�͖��H�ɓ��荞�C�����ł������B
�u�͂��D��������Ƃ����A�g�N�����́B�������̎ȐD���A�D��@��������Ώo���邭���B��^�q�D�ɕK�v�Ȍ������₪�ĉ��ւ���邶��낤���A�����i�A�����j��������T���ǂ����ɂ���͂������v
�u��^�q�ȂɎg���Ă��铂�����āA�ǂ̂��炢�̑���������v
�u�����Ȃ��Ƃ́A���ׂ�Ⴗ���킩�邱�Ƃ����v
�u�{���J���Ŏg���Ă����D��@�Ƃ����Ă��A���̒��ɂ��邾���ť���B�Ȃ̐}�������āA�`���ƌ����Ă��`���Ȃ�������v
�u�Q�Ă�ł��悩�B��������v���o���Ȃ���ł�v
�u�����D�������̂��A���l(�Ђ�)���܂����Ă���邩����H�v
�u���������g�N�����B���̏����q����Όy�����Ă�������።����B����ł��킵�́A�����Ƃ͖��̒m�ꂽ�����蔄�肶�Ⴏ��ȁv
�@�����q��������ǒ��Ԃ��畷������^�q�D�̍ޗ��́A�����i�A�����j��20�ԑO��̑����ł��邱�Ƃ����������B
������ǖ���
�@�g�N���v���Ăɗ��������āA�R�N���o�߂������B
�u��������܂����!�v
�@�����g���ʓ��̃g�N�̕����ɋ삯����ł����B�}�����~�ɏオ�������A�ێq�̗e�Ԃ͖���(�܂�)�������B
�u�������܂́A�܂��������Ȃ́H�v
�u�m�点�͏o���܂������Ă�v
�@�o���q�傪�č���������̂��Ȃ����A�����Ȑ��œ������B���Ȃ��͏��Ƃ̏o�Ȃ���A���Ƃɓ�������ƌ����ł���B�P�Ƃ��i�Q���ԁj���肵�Ċo���q�傪�A���Ă����B
�u���A�������肵�Ă��������v
�@���q�ɕ�����Ă��A�ێq�ɉ��̔������Ȃ��B�E�����A��Ă�����҂��A�͂Ȃ�������ɐU�����B
�u���ꂩ��A���ɍF�s���������Ǝv���Ă����̂Ɂv
�@�o���q��́A�₽���Ȃ肩������̎�����肵�߂��܂ܐ���U��i�����B�T�ɐ������������g�́A�u��������܁A��������܁v�Ƌ������Ԃ���B���̎��A�Ƃ̊O�ɂ��V�f�̏Z�������������āA�]�ˈȗ��̕t�������������ێq�ɕʂ���������B
�u�����܂ɂ́A����������Ȃ����ɁA��������̂��Ƃ������Ă��������܂����B���ꂵ�����Ƃ̐��������������������܂́A���ꂩ�炪�{���̍K�����Ɗ���Ă���ꂽ�̂ɥ���v
�@�m�������o���I���ċA������A�g�N�͕��Ɍ�肩����悤�ə�(�Ԃ�)�����B���̊Ԃ��A���Ȃ��́A�䏊�ƍ��~���s�������ċq�̂��ĂȂ��ɑ�Z���ł���B
�@�����S�i1871�j�N�V���̔p�˒u���ŁA�v���Ĕ˂͋v���Č��ɕς��A�X�ɂS�������11���ɂ́A�O�k��(�݂��܂���)�ɉ��߂�ꂽ�B
�u�]�˂̏㉮�~���A���{�ɏ����グ���邱�ƂɂȂ����v
���������Ă���g�N�ɁA�o���q�傪�����������B
�u���a���܂₨�Z��(���܂�)���܁i�ˎ�v�l�j�́A���ꂩ��ǂ��Ȃ���̂�����v
�@��\�i�j��̂قƂ�ǂ��]�˂̏㉮�~�ʼn߂������g�N�ł���B���~�̎�ł������ˎ�v�Ȃ̍s�����C�ɂȂ�B
�u���{�́A����܂ł̍]�˂̉��~�������グ�����ɁA�ԍ�̖�(�₰��)�ɂ����~���������邻�����B���a���܂͊Ԃ��Ȃ��A���Z�����܂Ƃ��ꏏ�ɂ����Ɉڂ��邾�낤�v
�@�ˎ�̐����̕ϖe�ƂƂ��ɁA�v���Ă̒��̗l�����}�ς���B�������T�N�ɂ́A�v���Ĕ˂̏ے������������E(�₮��)�����X�ɉꂽ�B�����ɓ_�݂����ƘV�̉��~����蕥���A�鉺�ƍ�(����)�̋����Ȃ����ԏ��i��j���p���������B���̍��ɂȂ�ƁA���v�̂��ߖ�X�Ő������炵�ċq���Ăэ��ތ��ˎm�̎p�����邱�Ƃ������Ȃ����B
.gif)
2000�N��̓��g��
�@�����ېV�Ȍ�V���{�́A�u�S����V�v�Ƃ��u�����Ŕj�v�������ċߑ㉻����𐄂��i�߁A���Ă̐V�������x��m����ϋɓI�Ɏ����ꂽ�B�������āA�����J���̕��������{�����ɐZ�����Ă����B
�@��������l�Ɏg�p�����A�A��瑾�z��ɕς����̂����̍��ł���B�����T�N12���R�����u�����U�N�P���P���v�ɉ��߂āA�u�V��v���X�^�[�g�����B���̖����U�N�́A�n���s�s�v���ĂɂƂ��Ă��A���j�I�ȑ�ϖe�̔N�ƂȂ�B
�@�g�߂ȂƂ���ł́A�Z�݊��ꂽ�V�f(�����)�������H(���ނ炢���傤��)�̏\�ԉ��~(���������₵��)�ƍ������āu���g���v�Ɩ��O�����߂��B�_���_�Ђ̂������������R���Ђ��Ж�����g�_�Ђƕς������߁A�V���������̖��ɏ������킯�ł���
�@�{�������q�ɂ͂����J�Ƃ����߂��Ĉȗ��A�₪�ĂU�N���o�̂ɁA�����̉����Ă��Ȃ��B�Ⴆ�X���n�߂�ɂ��Ă��A�����������Ă悢���̂�猩�������Ȃ��ł���B
�@�g�N�͋C���炵�ɊX�ɏo���B�v���Ăň�ԓ��₩�ȂƂ���Ƃ����A�O�{�������猴�É�(�͂��)�ɂ����Ă̓��ł���B�O�{���ł́A���̗�������C�O�̂悢�q�Ăт̐����������Ă����B�������̒�����(������)�����l���B
�@�X��ɒu���ꂽ�W�p�`�̎��v�ɐl�����肪�o���Ă���B���v�́A�召�̐j���ꎞ���x�ނ��ƂȂ��A�u�`�b�N�^�b�N�v�Ǝ�������ł����B
�u�������́A�ߌ�̂R��15�������v
�a���ɐ��m���̖X�q�������a�m���A�ׂ̏����Ɏ��v���w�����Ȃ��狳�����B�X�̌���ɂ́u�䎞�v�t�v�̊Ŕ��B
�u�Ђ���Ƃ��āA�g�N����Ȃ��ˁv
�@�ˑR�X�̒�����}�����j�̐����������B���̓y�n�ŁA����Ȃɐe�������������Ă����l�Ȃǂ���͂����Ȃ��̂ɁB
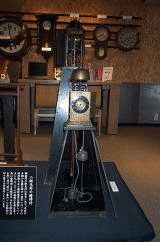
�����̘a���v
�u�]�˂̂����~�ʼn���A�ق�A��H�̖��g�����v
�@�O�|���p�ő�����˂������ĕ\�ɏo�Ă����j�̊�����āA�v���o�����B
�u�����A���V�{����ł�������A���̎��̥���v
�u���������A���̎��̏@�얖�g�����v
�u��H���A�Ȃ�ł܂�����v
�@���������āA�g�N�͎v���o�����B���̎����g�́A���m���v�ɋ��������a���܂����ω������Ă���ƌ����Ă����B�Q�Ό��̂��������č]�˂ɏオ�����̂��A���v�D���̓a���܂Ɍ��������Ă̂��Ƃ��Ƃ��B
�u�g�N����ƕʂꂽ�㉡�l�ɍs���āA���m�l�̎��v�t�ɒ�q���肵���Ɓv
���g�ƃg�N�������b�����Ă���Ƃ���ɁA�X�̒����珗���o�Ă����B
�u���ł������b�����Ȃ����ł����v
�@���[�̃}�c�q���Ɩ��g���Љ���B
�u���̎��v�́A�A�����J���̂U�C���`�i��15�a�j�����v
���g���A�W�p���v����ɂƂ��āA�������ɐ��������B
�u��H�̓��������v������ɂȂ�̂��āA��ς������ł��傤�H�v
�@�g�N�́A���g�̌��f�������@�����������B
�u����قǂł��Ȃ���B�^�ǂ��ƌ������a���܂ɓ{������Ă�B���オ�ς���Ă�������H���v��ƂȂ�������B���N�̕��ɁA����܂ł̗�ς�����낤�B�G�߂��ς��x�ɐj�Β��߂�����{���̎��v����A�l�W�����Ƃ�ςސ��m���v�ɑւ��������A���v���ɂȂ�悩�@��v���������B���a���܂̂��A�ŁA���l�ŏK�����Z�p�����ɗ��v
�@���g�̌��t�ɓb(���)�݂͂Ȃ��B�������肵�āA�V�����������������ƍl�������g�̌��f�ɂ͋���������ł������B
�u����ς�j�̐l�͈̂��ˁv
�u���ꂩ��́A���������̂ɁA�j�����Ȃ����Ȃ����B������A�g�N�����A�Ȃ��ċv���Ăɂ���ƁH�v
�u�ǂ����Ă���Ȃɉ����Ƃ���܂ł���ė��������āH�@����܂����R(�킯)�����Ă��v
�@�]�˂���300�������ꂽ��B�ł̍ĉ�ł���B�c���(�����ȂȂ���)�̂悤�ȋC�����āA�g�N�͂��̌�̂��Ƃ�b�����B
�u�g�N����́A�͂��D�肪�D���Ƃ邿����������ˁv
�u�����Ȃ́B�ʒ��̏����̂������������Ă������Č����Ă���邩��A������x�ȐD����n�߂邱�Ƃɂ�����v
�u����Ȃ�g�N����ɁA�悩�j�Έ������킹�邽���v
�@���g�́A����̕Ԏ����������ɗ����オ�����B���g�ƃg�N�́A��قǒʂ����O�{���̓��₩�ȏꏊ�ɖ߂��Ă����B
�u�������Ɍ����傫�����������r�r����B�O�{���ł���Ԃ̘V�܂��v
����ȌÂ��X�ɍ������āA�̍����Y���o�����Ă̓X���ڗ��B���g�ɘA��čs���ꂽ�Ƃ���́A�O�{�������班���������ĉ����̏����ȓX�������B�\�̊Ŕɂ́u�Ɖ�(����)���ܓX(���тĂ�)�v�Ƃ���A���܂�����Ĕ���X���Ƃ����킩�����B
�u�_������A���邩���v
�@���g���C��������������ƁA�O�|���p�̒j���o�Ă����B�����Ƃ��떖�g���T�`�U�ΔN���̂悤���B
�u����l�͑q�c�_���������āA���܍��ΓV�E���v���Ƃ�j�����B���ېV�O�ɂ͂���ɏオ���čٖD�t(�����ق���)���Ƃ������ȁB�Ȃ��Ȃ�������邵�A���Ƃ����Ă��悤�����v
�u����قǂł��Ȃ��ł���v
�@���g�ɏЉ�ꂽ�_�����A�����ݒ��q����ɍ����o�����B
�u�ٖD�t���Ȃ�ő��܍��𥥥�v
�j��l�̒��Ɋ��荞�݂����āA�g�N���_���ɐq�˂��B
�@�_���́A�����Ɍ������d���������ɒ���܂ōs���ďC�Ƃ�ς݁A�V�N�������Ă悤�₭���܉��̊J�Ƃɂ��������̂��ƌ����B

�n�Ɠ����̒Ɖ��̊Ŕ�
�u�̂���ˁB�q���̍����炢���Ȃ��Ƃ��l������A�d�������肵�Ă����̂ˁB���̎��ɂ͂ƂĂ��^���ł��Ȃ���v
�u�܂������B�g�N����̈����Ȃ��B���ꂩ��̐��́A�j�����Ȃ����Ȃ����A��قnj��������肶��낤���v
�@���g�������オ��Ȃ���A�g�N�̌��t����(����)�߂��B
�u�܂����ז����Ă�����������B�����Ƃ��Ȃ��̘b������������v
�@�������ł͂Ȃ��A�g�N�͖ڂ̑O�̎�҂Ȃ�A�����l�ɂȂ邽�߂̐S�\���������Ă����悤�ȋC�����Ă����B
�����a��
�@�V�Q���g�N�ɍč��b�������Ă����B����͋g�J���O�ŁA����̓��Ǝ҂��ƌ����B��l�̊o���q�傪�č��������Ƃ�A���ꂩ��̕�炵�̂��Ƃ��l����ƁA�����炪�˓c�ƂƋ�����u���悢�@��ƍl����g�N�́A�����b���邱�Ƃɂ����B
�@����������A�g�N�v�w�͌˓c�Ƃ���ڂƕ@�̐�̗��ʂ�ɉƂ���ĐV�������n�߂��B����Ƃŏ��������Ă����E�����O�サ�Č������A����܂��g�N�ׂ̗̉ƂɈ����z���Ă����B
�@�P�N���ƁA�g�N�ɏ��̎q�����܂ꂽ�B�u��T(������)�v�Ɩ��t�����B���O���������������������A�����̑�����݂���(�킴�킢)���āA�Ԃ��Ȃ����E����B
�u�悭�悭�������ɂ͒j�^���Ȃ��ˁv
���O�̎l�\������߂������A���ߑ�������Ƀg�N���E���Ɍ�������Ƃł���B
�u�g�N����A���ꂩ�炪�l���̖{�Ԃ���v
�@�E�������ɂȂ�����傫�������B
�u���ɂ͐�T������邶��Ȃ��́B�U�߂͂��Ȃ��Ă��A���̌`��������Ώ\������v

���݂̓��g���E�G
�@���ł́A�E���͂��������̂Ȃ��אl�ł������B
�u�������ˁA���ɂ͐�T���������ˁB����ɥ���v
�u����ɁH�v
�u�ނ���������n��(���˂Â�)�ƌ�������Ȃ��B�ȐD��̖ړr(�߂�)�������������Ă������v
�g�N�́A������������Č������̎������B�����B
�u���ꂿ���͊撣�邩��ˁB���O�����悤�傫�イ�Ȃ��āA���ꂿ���̂���`�������Ăˁv
�@�Ќ���������ׂ�Ȃ����Ɍ������Č����܂߂��B�{�������q�Ɋ��߂�ꂽ�͂����J�ƂO�ɂ������ł���B
�@�g�N�́A���̂Ƃ���{�������q�̓X��K�˂邱�Ƃ����������B�J�ƂɌ����āA�����̎�͂�������邽�߂ł���B�o�����鎞�͂�����T��w�����Ă���B
�u�����̓z�A�����蔄��Ɏ��M������āB����(��炶)�ɋr�J(����͂�)�Əƍ~�P(�Ă�ӂꂪ��)�Ύ����Ă������B��B����l���A�������ʂ܂ł�����Ƃ�B���x�͋��s�Ƃ����ɂ���荞�ނ��ȁv
�@�����q���{�q���q�̘b�����鎞�́A�z�ɉ��{�����(����)���Ċ��������B�g�N�́A�X�̂��߂ɏ���������g�������鏯���q�e�q���A�܂��������B
�u�Ɖ��̉_��������āA���ꂩ��ǂ�ȑ��܉�����ɂȂ�̂�����B����ɁA���v���̖��g����॥��v
�u���̓�l�ˁB����̊쎟�Y�Ƃ����̏����������āA���ꂩ��̋v���ĂΔw�����Ă���������ǂ����B�g�N�����������A�����ƌ��߂��炷�����s�Ɉڂ��ɂ�B��̂��ƂΐS�z���Ƃ����牽���ł���v
�u�ł��ˁA�d�������܂�����������ƁA�������̎q�������肾���̂�B����ς菗���d�������邱�Ƃ��Ė����Ȃ��Ƃł����ˁv
�@���v���̖��g����������{��ꂻ���Ȍ��t���܂��f���Ă��܂����B

�@�쎞�v�X�̂������ꏊ�i�{���j
�u���̂����A��T����d���Ύ�`���悤�ɂȂ邭���B�Ԃ�V�̂������C�͂����J�ƂɌ����������̈���v���悩�v
�����q���A�Ԃ�V�Ƃ̓�l�O�r�ōs���悤�ɂƗ�܂����B
�u���ېV��A�v���Ă̒��ɂ́A���삳�܂̐��ł͍l�����y�����X���ǂ�ǂ�ł����B���̐l�����́A���s������ǂ��悤�Ȃ�čl����ɂ��Ȃ����v����v
�@�����q�������悤�ɁA�����T�N����U�N�ɂ����Ă̋v���Ă̒��ɂ́A�V��������̕��������܂������B�����J���̔g���A��������y�����ꂽ��B�̋v���Ăɂ��m���ɋy��ł���B
�@���É�ɋ����X��m�����̓X���J�ƁB�����̑��q�Ԏi�쎟�Y�͐A�؉��u�L�y���v���J�Ƃ��A�v���Ă��𐢊E�Ɍ����ĕ��y�����Ă�����b��z�����B�������ł͒����������ʐ^�ق��A�쑺�����͒���Ɏ����ŋ�B�łQ�Ԗڂ̊��ň�������J�݂����B����܂ŏo�Ԃ��M(������)���Ă���������ǂ̐�(�Ђ�)���q�������A��Ăɔ�яo���������ł���B
�u�����Ƃ���̎��オ�I���āA������ǂ̐��̒����������������Ƃ����v
�����q�́A�E��̎w��܂�Ȃ���V�����X�̈��𐔂��A�ԐړI�Ƀg�N�̑O�i�𑣂����B
����H�̋T����
�@�v���Ă̂�����ǂ����́A������̔̔������B�S�悩��S���ւƊg�債�Ă������B�ނ炪�̘H���L�������A�D���ɕs���Ȍ������s������B
�u�ȐD��}���ɂ�Ȃ��v
�@���̎����A�v���ĂŌ�������̕z���p�������ꂽ�����Ƃ��d�Ȃ��Ă���B�����q�́A�g�N���D�낤�Ƃ����^�q�Ȃ��A�ؖȂ̑��Ɍ����Ⓜ���i�A�����j���g�����Ƃɒ��ڂ��Ă���B�ؖȎ������g��Ȃ�������̐��Y�����v�ɒǂ����Ȃ��Ȃ����������A�g�N�̏o�Ԃ��ƍl���邩�炾�B
.gif)
�v���Ēn���̍��@�i�n��Y����ߓW���j
�@���̂�����@�ł́A�D���̔�J�����ł͂Ȃ��A�Ў�œ�����`���g���Ȃ��B�{���J������̐D��@���ǂ�Ȃ��̂��������B���̒��ɂ͕����Ԃ̂����A��������ɏo���ĒN���ɘb�����Ƃ��ł��Ȃ��B�����q�̑O�ł͈̂����Ȃ��Ƃ����������̂́A������Ɏg���Ă������̍��@(������)�̎d�g�݂��ǂ����Ă��v���o���Ȃ��ł���B
�@�g�N�̃C���C���͕�����ł������B
�u���́H�v
�@���~�̗z���܂�ōl������ł��鎞�A�����ꂽ�̂��A�V�Q�����ɍ����Ă����B
�u���E������Ɍ��Ă�����Ă����v
�@�g�N�̌����A�V�Q���h�������B
�u�͂��D��@�B�̂��ƂŔY��ǂ�Ƃ��ˁB����Ȃ̈�l�ōl������ł����悤���Ȃ��B�����ɔC���Ƃ���ˁv
�@�V�Q�̓g�N���u��i�����U�i1873�j�N�Ɂu�S�C���H�v���璬���ύX�j�Ɍ�����~�n���́A����̍�Ə�ɘA��čs�����B����̖��O�͋T�g�B�u�T��H�v�̒ʏ̂Œm���Ă����H�ł���B
�T�g�́A���O�ɉ�����������Ă��Ȃ��炵���A�̍�������Ȋp�ނɍ������낵���B���������Ƀg�N�̘b���Ղ����B
�u����́A�����牽�ł��������B������̓��̒��ɂ���}�ʂǂ���ɕ�����킯���Ȃ��v
�@�����ŁA�V�Q�̊�ʂ��������Ȃ����B
�u�����̒��傪�������Ȃ��j����m������B�b���낭�ɕ�����ŏ��߂��瓦���o�����́A��H�̕���ɂ��u����j���v
�@�V�Q�̑吺�ɁA�w���̐Ԃ�V��������o�^�o�^�����ċ����o�����B
�u�ق���ˁA�q���ł�A�������Ȃ��e��(���₶)�Ɉ��z�ΐs�����ċ����������낤���v
�@�V�Q�̂Ƃ���́A���X�̂��Ƃł͎��܂肻���ɂȂ��B
�u���̂��A�D��@�̕��ͥ���v
�g�N�͑҂����ꂸ�ɁA�T�g�Ɍ������B
�u���܂�B�����ȃo�o�ł�A�o�čs���ꂿ�።�����ŁB���悤���Ȃ��B����ŁA���ɉ��ǂ��ȕ��ɍ���ė~�����ƁH�v
�u�������Ȃ���v
�@�T�g���܂��ƁA�V�Q�͉������Ȃ������悤�ɕꉮ�ɏ������B���ꂩ��Ƃ������́A�g�N�͐�T���E���ɗa�����܂܁A�T�g�̎d����ɒʂ��������B
�u�����A�����͈Ⴄ�v�̘A���ɁA���������̖؍ނ�䖳���ɂ��Ă��܂��T�g�������B
�u���ق��Ă����ˁB���ɂ͉�����̒����͓���v
�@�T�g���㉹��f���ƁA�V�Q�����ł����ɂ݂���B10���Ԃ̎��s����ŁA���@(������)�̎���i���o���オ�����B
�����Ƃ̋ߍ]����
�@�T��H�ɍ�点�����@���ꉞ�̊������݂����̂́A��͂܂������B���ɂ́A�����ĕs�����̎�a��(�Ăт�����)���ǂɊ������ĔP(�Ђ�)�铹��K�v�ƂȂ�B�v���Ă̎s�������n���Ă��Q�l�ɂȂ���̂͂ǂ��ɂ�������Ȃ������B
�u���ΔP��@�B�������Ă॥��v
�@�T�g�̊炪�A�Ăт䂪�B
�u�a��������̎��ł͑�������炾���A�D��@�ɂ����Ă������ɐ�Ă��܂���B��������P���Đ������������ɂ��Ă���łȂ��ƁA���@�ɂ͂������Ȃ��́v
�u�����Ȃ��Ό����Ă��A���͔����Ƃ���Ȃ����v
�@�����ł܂��V�Q���T�g�Ɋ��݂����B
�u���̑�H�Ȃ炢���m�炸�A�o���Ƃł��邲�Ƃ���̂��T��H����Ȃ����B���̔]�Ȃ��v
�@���[�ɂ����܂ł������낳��Ă͋T�g�̊��E�܂����E�炵���A�����Ă������Ƃ�U��グ���B
�u������Ƒ҂Ă�B������10���ڂ̋ߍ]����ɑ��k���Ă݂邩�v

���N�̓c���v�d�v��
�@�U��グ�����Ƃ�[�߂Ȃ���A�T�g���g�N�̊�F���f�����B�u10���ڂ̋ߍ]����v�Ƃ́A�ʒ��Ő��������c�ޓc���v�d�̂��Ƃł���B�c�����V�E�q��Ƃ����A�ʒ�10���ڂׂ̂��b�H���̑��q�������u���炭��V�E�q��v�̂��ƁB
�@�ނ́A�\��̍��Ɉ��`�̊G������͗l��n�肾���A���ߋ@�B���l�Ă������Ƃł��m���Ă���B���̌��₩�狞�s�ɏo�āA���N���v�△�s���Ȃǐ��X�̔������Ȃ��A�u���{���̍H�t�v�Ə̂��ꂽ�B���삩��́u�c���ߍ]�v�d�v�Ƃ������h�Ȗ��O�܂ł����������B���̌�ɏ����ꂽ����˂ł́A���C�D�����萸�I�ȑ�C�i�A�[���X�g�����O�C�j���n(������)�����B�c���v�d�́A����g�N�̂͂��D��@��ɋ��͂�����A�Ăѓ����ɏo�Đ��쏊�������A���݂̓��ł̊�b��z�����B
�@�g�N�́A�T�g�ɘA����ēc����������K�˂��B���̎��A�v�d�̔N��͊���70���߂��Ă����B
�u�P(�Ђ�)��Ȃ��玅��a���@�B������ė~�����̂ł�������v
�@����(��イ���傤)�Ȋ֓��ق��C�ɓ������炵���A�v�d�͑������ʂ����o���āA�g�N�̒����������Ƃ߂Ă������B
�u�T��H�̌������Ƃ�������f��˂��ȁv
�@�v�d�́A��������Ƃ��炭�l�������ɁA�g�N�̓��̒��̍\�z���Ɛ}�ʂɂ����B�����ďo���オ�����@�B�ͥ���B
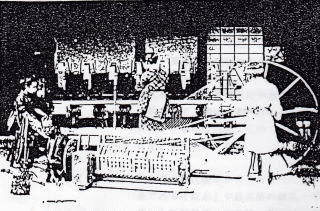
��ʂ̔����Q���@
�@�W�{�̊ǂɊ����ꂽ�����A���ꂼ��ɕ�����Ğy(�킭)�i�������������B�j�Ɋ������A�y��100��܂��ƁA�u�`�[���v�Ə�����B�X��100��ŁA�������̗g���͂����ł�������m�点�Ă����B�g�N���l���Ă������z�ɋ߂��@�B���o���オ�����B�v�d�́A������u�g���͂��@�B�v�Ɩ��Â����B��ʂŋL�����Ă���u�����Q���@(�͂����傤�˂�)�v�ɋ��ʂ���@�B�ł���B
�@�v�d�̓g�N�ɁA�R�~�̎�Ԓ��𐿋������B������܂��������̂Ȃ��g�N�ɂƂ��āA�R�~�͍����ȓ����ł���B�ĂP�i10�l��180���b�g���j�̒l�i���R�~64�K�̎���ł������B
�@�����傪�c�������͉̂����Ȃ����A��������Œ����������̒~�������ł͑��肻���ɂȂ��B�����Ŋo���q��ɑ��k�����B
�u�g�N�ɘb������v
�@�o���q��́A�g�N�������̑��k���������̓��ɁA�v�������Ȃ����Ƃ������������B��ێq���S���Ȃ����̂��@�ɁA���̔ˎ傪�Z�ޓ����ɏZ�����ڂ��ƌ����B�������A�Ƒ�����݂̈ړ��ł���B
�@�]�ˏ㉮�~�ȗ��\���N�ԁA��炵�����ɂ��Ă����o���q��₨���g�Ƃ̕ʂ�ł������B�����g�͕�e���R�Ɉ�ĂĂ��ꂽ�g�N�Ƃ̕ʂ���A�܂𗬂��Ď₵�������B
�u�g�N�ɂ́A���t�ł͐s�����Ȃ��قǂɐ��b�������Ă��܂����B���߂Ă��̕ƌ����Ă͉������A���̍ۋߍ]����ւ̎�Ԓ��킹�Ă��炤�v
�@�Ԃ��Ȃ��A�o���q��v�w�Ƃ����g�́A�V�f�̉��~����ɂ����B�g�N�Ȃǎv���o�����L����Ƒ����A�����̓n����܂ő����Ă������B
�@�c���v�d�̋��͂ŁA�g���͂��@�B���o���オ������A�g�N�͂Ȃ��Ȃ��Q�t���Ȃ������B���x���N�������ẮA�@�B�̂�����߂��肱�����G�����肵���B
�@�B�������A���͎Ȃ�D�邽�߂̎����K�v�ɂȂ�B���ɁA�ȖؖȂ�D�邽�߂̌��̒n���́A�����v���Ăł͎�ɓ��肻���ɂȂ������B
�u�C���Ƃ���ˁv
�@�����ł��V�Q�̃J�I�����ɗ����ƂɁB�ʒ��P���ڂŌÎ艮�i�Ò����j���c�ޒ������ɘA��čs���ꂽ�B��l�̒����������́A�n���ȓX�\���Ƃ͗����ɁA���݂ł����������Ђ̎В��ł������B
�u�킵���˂̌R�͂Ύ�āA���{�S���ɋv���Ă̂�����Δ����Ă܂����������ǂ����B�v���Ăœ��Y�i�ΎY�ݏo���K�v�́A�N�����킩���Ƃ����v
�������́A���ە���h����Ȃ���A���ݖf�Ղ̖ʔ��b���I���Ȃ���A��ォ�猦��������Ă��ꂽ�B
�u�����l���Ƃ��a��(�Ă���)����A�傫�߂��Ă��܂�������Ǝv����v�ƌ����A�����i�A�������a�ю��̂��Ɓj��32�Ԃ�22�Ԃ͑�ォ����Ă��ꂽ�B
�@�D��@�ƌ����̎����������Ƃ���ŁA�܂�����g�N�̎v�l���s���l�����B
�u����������ɒ��B���Ă�����������ɁA�Q����|����Ԃ��v��̂�v
�@���k���ꂽ�V�Q���A���߂ĕ������̂Ō��������Ȃ��B
�u�C���Ƃ���ˁA�ƌ��������Ƃ����Ă�v
�ƕԎ���ۗ����ďo�Ă������B
�u��������A�g�N�������Q(��)��|(��)���ԂƂ������v
�������A�v���Ă�m��s�����Ă���Ǝ�������V�Q�ł���B�����g�N���A���͂���̖쒆�i���j�̈ꌬ�ƂɈē������B�������̂́A�ŋߐe�ދ𗊂��ċ��s����ڂ�Z��ł����Ƃ��������ƕv�l�ł������B
�u���ɂ͗p�̂Ȃ����̂ł�����v�ƍ����o���ꂽ��a��(���Ƃ����)�́A��͂�g�N�̋L���Ɏc����̂ɋ߂������B
�u���̂܂܂ł͎g���Ȃ���ˁv
�@�g�N�͋T��H�ɁA�W�{�̎����Q(��)��Ȃ���ǂɊ������Ă����悤�w�����āA�u���Q(���Ƃ�)��ԁv�����グ���B
|

