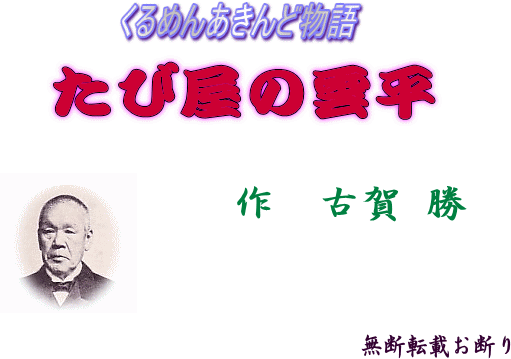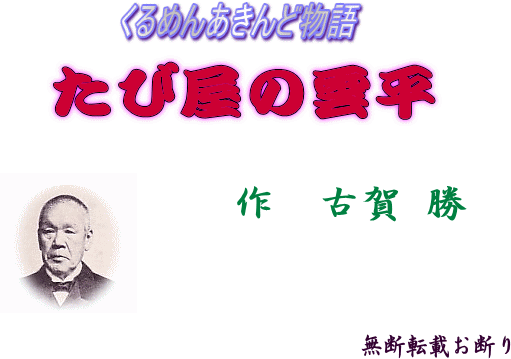|

跡取り教育①
この日も朝から、雲平とモトが口論している。
「あなたさん、金蔵は私ら夫婦にとって大切な跡取り息子ですよ。以前のように、食べるのに困っているというのなら話は別ですけれど」
「だから言っとるじゃろ。あの子には、つちやたびば継いでもらわなきゃならんち。そのためにも、職人としての腕ば確かなもんにしとかんと」
モトは、長男に一つでも上の教育を受けさせたいと考えている。一方雲平は、教育よりも腕に技術を持たせることが先決だと言う。夫婦ともに鉾を納める気配はない。
その場を収めたのは、卯之助であった。
「雇われの身で生意気なことば言いますばってん。金ちゃんには、なるべく早うから店の一員になってもろうた方がよかち思うとです」
「それはまた、どうして?」
常に自分の味方だと思っている卯之助の意外な発言に、モトは動揺を隠せない。
「これからの金ちゃんには、作業場の隅々まで目を配ってもらわなきゃならんからです」
モトも、少々のことでは引きさがらない。
「金蔵は、主人の後を継ぐ子供ですよ。ますます高等教育が必要じゃありませんか。せめて、中等教育までは」
 写真:明治期のつちや足袋店先風景 写真:明治期のつちや足袋店先風景
「大将が言われる『一人前の足袋職人に』の意味は、職工や町の奥さん方に仕事ば言いつけるときでも、言いつける側が素人では話にならんからです。上に立つ者は、誰よりも仕事がわかってなきゃならんとです」
卯之助がモトに対して持論を披瀝している間、雲平は一言も発しなかった。
「嘉助さんも信義さんも、これからの店には、高等教育が必要だと言いましたよね。このことは、あなたさんも卯之助さんも、忘れてはいないですよね」
雲平は、モトからの問いかけに頷くだけ。
「金ちゃんには、職人を目指しながらでも高等教育以上の学問ば受けられます。周りにはよか先生もおるし」
「誰?」
「川上ですよ。あいつなら、必ず金ちゃんば一人前の店の大将に育ててくれます」
「それでは、あまりにも金蔵がかわいそう。だって、早く職人になるための修業をするんでしょう。その上に、学校に行く以上の勉強をさせるのですか。未だ子供の金蔵に、遊ぶ時間も上げないのですか」
モトが普通の母親の顔を覗かせる一瞬である。さすがの卯之助も、それ以上の熱弁は振るえなかった。
すったもんだの末に、モトの方が折れた。雲平は、卒業式の日に、金蔵を母屋から丁稚の部屋に移した。商人見習いとして採用した清水慶之助も一緒である。「そこまでしなくても」と涙ぐむモトを尻目に、雲平は両人に心得を言い渡した。
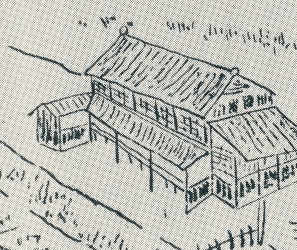 写真:明治12年の京洗小学校校舎 写真:明治12年の京洗小学校校舎
「金蔵も慶之助も、店の中では丁稚と同じぞ。誰よりも早う起きて、誰よりも遅う寝る。先輩の職人に生意気を言うんじゃない。作業場や店の周りの掃除もさぼったら許さん。その上で、卯之助おっちゃんからよう仕事ば習うて、早う一人前の足袋職人になれ」
卯之助に足袋作りのイロハを教えてもらう。合間を縫って、川上は2人に高等教育並みの猛特訓を始めた。
勧業博覧会②
雲平は、支配人の川上義信に京都行きを言いつけた。開催中の内国勧業博覧会を見学させるためである。
川上は教育中の金蔵を連れて行きたいと願い出た。金蔵に生きた教育を施したかったからである。明治28年の4月であった。
内国勧業博覧会とは、明治政府が殖産興業を目的として、明治10年(1887年)に東京上野で開催したのが始まりである。あたかも、西南戦争の最中であった。その後も2回、同じ東京上野で開催されたが、明治28年の第4回になって初めて地方での開催となったもの。
川上らが降り立った京都。都を東京に移される以前の賑わいを取り戻そうと、関係者の博覧会にかける意気込みは大変なものであったという。折しも平安遷都千百年の節目と重なったこともあり、官民こぞって博覧会開催に燃えた。
今日に残る様々な施設(例:平安神宮建設・日本で2番目の動物園・琵琶湖疏水・路面電車等)やイベント(例:時代祭り等)は、博覧会を機に始まったものである。
「すごかね」
京都の停車場に降り立つなり、金蔵は歓声の上げっ放しである。
「あんまり大っか声ば出すな、見っともなかぞ」
川上が金蔵をたしなめた。
「兄しゃん、道の真ん中ば電気車が走っとる!」
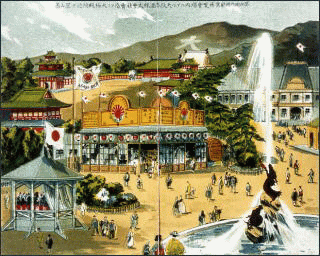 写真:博覧会会場になった平安神宮の会場=HPアサヒビールより 写真:博覧会会場になった平安神宮の会場=HPアサヒビールより
博覧会に合わせて開業した日本最初の路面電車のことである。七条停車駅(現在の京都駅付近)から南禅寺までの約7キロを、時速10キロの速さで走る電車は、金蔵にとって夢の中の世界であった。
川上は、展示場を周りながら、手に持った帳面に記録することを怠らない。金蔵はというと、各県ごとに並ぶ売店や食堂の方が気になって仕方がない。
「うんっ」
川上の目を惹いたのは、埼玉県から出展されている「行田の足袋」であった。展示品を、手に取りながら見つめる。
「兄しゃん、何がそげん珍しかと」
金蔵には、いつも見慣れている足袋と行田の足袋の違いは分からない。
「いらっしゃい。ご熱心だね」
店にいる中年の女性から声をかけられた。
「九州の久留米から来たもんです。珍しかですね」
「何が?」
「足袋の種類の多かことがです。いったい行田ではどのくらい足袋ば作るとですか」
「そうね。行田全体では、1年に100万足くらいと聞いとるよ」
川上は、目の前の女性なら何でも気軽に話してくれそうで、つい座り込んでしまった。
「行田の足袋の特徴ば教えてくれんでしょうか」
「そうね。足袋底が強いところかね。徳川さまの時代から、外で作業する職人さんによく履かれてきたもんでね。それに、町のすぐそばを中山道が通ってるから、旅人さんがたくさん買ってくれるんだよ。そんなわけで、足袋底の刺子なんぞは、よそでは真似の出来ない技を持っているんだ」
女は、お国自慢を聞いてくれる若者が気に入ったらしく、次から次へと展示品を見せながら説明した。
みやげ話③
半月ぶりに久留米に戻ってきた川上義信と金蔵。興奮が覚めやらない川上は、工場内の誰彼かまわずにみやげ話をしている。一方金蔵はというと、黙って話を聞いてくれる卯之助の前に座り込み、相手に仕事をさせようとしない。
「道中だけで1ヵ月くらいはかかるち思うとったばってん、汽車は早かね。久留米の停車場ば出て、すぐに門司港じゃもん。渡し船ば降りて、下関から京都までも早かった。東京から出とる店の、うなぎのかば焼きのうまかったこと」
金蔵の話は、乗り物か食いものに限られる。川上はというと、さすがに足袋の話しが主流である。
「大将へのみやげは裁断機です。裁断機は近かうちに現物ば送ってきます」
「そげん大そうなものか、博覧会で見つけた裁断機ちは」
「きっと大将にも気にいってもらえると思うとります。手回し式皮革用裁断機ちいうもんで、生地の上に足袋の刃型ば置いて一気に打ち抜くとです。いっぺんに何十枚もの布ば裁断することがでくるとです」
それまでのつちやたびでの裁断といえば、1足分の生地の上に足袋の型を乗せて、丸包丁で型に沿って裁っていくというものだった。すべてが人の手による作業である。
「裁断機のお陰で手間が省けた分、余った職工ば外に回せます。それに、機械で裁断すれば、規格も同じになるけんですね、後の作業もやりやすうなるとです」
さすが自分が見込んだ男だと、雲平は納得した。
裁断機の到着と同時に、皮革部門の技術者に、底生地を重ね裁断する機械に改造するよう言いつけた。間もなく出来上がった裁断機は、雲平の予想を超える切れ味と能率の良さを発揮した。
川上の出張報告は続いた。
「日本中から集まってきた機械や工芸品ば見て回りました。まだまだうちの足袋は遅れておることがようわかりました」
雲平は、川上の意外な自己評価に、我が耳を疑った。
「これから先、うちの店が足袋の生産ばどげんしていったらよかか、帰りの汽車の中で金蔵君と話ばしてきたとです」
雲平は、川上の真剣な様子に、自然と聞き入ることになる。
「もう一つ、大将におみやげがあります。博覧会で金蔵君が見つけたミシンです。金蔵君は、展示品ば見て、これで足袋ば縫えんもんかと言いだしました。言われてみて、僕もそう思いました。つちやたびの工場にミシンば入れてはどげんかと」
隣にいる金蔵も得意気に、「これからの足袋作りはミシンばい」と言う。いつの間にか、モトも卯之助も、川上のそばに集まってきた。
「洋服ば機械で縫うことなら聞いたことがあるばってん」
雲平は、足袋は職人が1足ずつ手で作り上げていくものだと思い込んでいる。
「これまでと同じことをしておっては、行田のごと大量生産ばすることは夢のまた夢です。金蔵君が見つけたのは、ドイツ製の青貝印ちいうものでした。説明ばしておる人の話だと、素縫い(刺繍)用として手で回すのと、洋服ば縫うのと同じごと足踏み式の両方があるとです」
「それで、そのミシンは、すぐに手に入るのかしら」
作業の能率化には特に熱心なモトは、話を聞き終わる前から既に購入する気になっている。
「販売する店の連絡先ば、聞いてきましたけん」
日清戦争が始まって、このところの足袋の需要はうなぎ上りである。つちやたびでも、人手が足りなくてお手上げの状態だった。人間の代わりを機械が果たしてくれるならこんなにいいことはないとモトは考えている。
「ミシンば入れて、生産がどのくらい上がるもんか」
モトに比べてもう一つ慎重な雲平は、腕組みをしたままで川上に質した。
「そのことなら、俺から話すばい。人が縫う何十倍かは早うなるち、展示場の人が言いよらした」
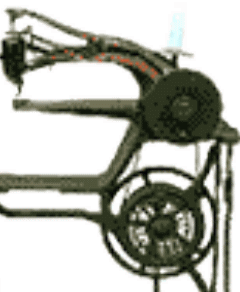 博覧会でのことを自慢したくて仕方のない金蔵が、帳面に描いてきたミシンの絵を見せながら説明した。モトは、我が子が工場の機械化のことまで考えていたことが嬉しくてたまらない。 博覧会でのことを自慢したくて仕方のない金蔵が、帳面に描いてきたミシンの絵を見せながら説明した。モトは、我が子が工場の機械化のことまで考えていたことが嬉しくてたまらない。
「高いんじゃろう、そのミシン。皮革部門も含めてたったの30人の工場では、勿体なかことはなかか」
雲平はなお導入に慎重である。
写真:つちや第1号ミシン
「そげなことはなかよ、父ちゃん」
間もなくつちやたびでは、素縫い用に手回し式を2台、甲縫い用に足踏み式を3台と合わせて、分厚い足底用を縫うドイツ製網代(あじろ)縫いミシン1台を購入した。
次なる戦略④
雲平は川上を連れて山田平四郎の西洋料理店に入った。嘉助も一緒である。
「肉も海老も好いとりますばってん。どうもこの、ナイフとフォークが馴染めんとです」
さすがの川上も、卯之助同様西洋料理の作法には溶け込めないでいる。
「これからの日本人は、ナイフとフォークと英語が出来んと役に立たん」
相変わらず、雲平と川上に対する嘉助の 注文は厳しい。
「先日、雲平しゃんの店の裏の方で大っか(大きな)音がしとったが」
「ああ、あれね。川上が京都の博覧会で見つけてきた裁断機たい。これまで、1枚1枚裁断しとった足袋の底生地ば、あの器械なら20枚とか30枚とかいっぺんに切れるごつなった」
嘉助は、出された料理の車海老を頬ばりながら、雲平の自慢話を聞いている。
「そげんよか器械なら、人の目につく場所に置けばよかとに。来るお客さんにも自慢すればよか」
嘉助と雲平の会話は、どうも噛み合わない。
「俺の足袋作りは、1足1足に魂を入れていくやり方たい。生地選びから裁断・縫製まで、どれ一つ手ば抜けん。便利じゃからいうてどんどん機械ば入れておったら、雲平の足袋が雲平の足袋じゃのうなる。うちの足袋は,機械で縫いよりますてんなんてん、言わるるもんか」
「それは違うばい、雲平しゃん。機械で作ったからいうて、雲平しゃんの足袋の値打ちが下がることはなか。要は、お客さんに満足してもらえるかどうかたい。足袋は、飾りもんじゃのうて、暮らしに必要なもんじゃけんな」
話はそこでいったん打ち切り、3人とも肉料理との格闘に集中した。
「裁断機の次はミシンたいね。モトさんが言いよらしたごと、つちやたびもいよいよ大量生産の時代に突入じゃね」
嘉助が、再び雲平のやる気を引き出そうとする。そこでやっと、川上義信の入り込む場所が出来た。
「ミシンとか裁断機とか、これからは、機械が人間の代わりばする時代になるとです。博覧会に来とらす人たちがそげん言いよりました」
雲平は、川上の発想が、自分よりずっと先を走って行きそうで不安が募った。
「ばってん、例え1日に1万足の足袋が作れたちいうても、それだけの足袋ば買うてくれるお人がおらんことにはない」
嘉助の不安はそこにある。
「そのことなら、俺にも考えがあるたい」
雲平の頭には、店を大きくするための次なる戦略が膨らんでいるようだった。
資金の効率⑤
裁断機とミシンの音が工場中に充満している。作業員どうしの会話も通じないほどだ。そのため、店主である雲平とモトには、工場の隅に仕切られた部屋が設けられた。
「大将、相談があります」
最近では、モトへの身構えが減った分、川上からの相談が気になる。
「言い難かことですばってん」
帳面をつけながら、モトの耳は川上の言葉に集中している。川上はというと、ここにきて言うべきか言わざるべきかで迷っているようだ。
 写真:つちや足袋のポスター(明治後期) 写真:つちや足袋のポスター(明治後期)
「何な、言いたかこつがあったらみんな吐き出したらどげんな」
店主の前で引っ込みがつかなくなった川上が、恐る恐る口を開いた。
「革靴と馬具の生産ばやめたらどげんかと・・・」
「何だと、お前!」
立ち上がった雲平の口元が小刻みに震えている。
「待って下さいよ。言いたいことがあったら吐き出せと言ったのはあなたさんですよ」
帳面を伏せたモトが、いつになくきつい調子で雲平の袖を引いた。
「すみません。出過ぎたことば言いまして。僕が言うたことは忘れて下さい」
神妙に頭を下げる川上に、今度はモトが噛みついた。
「男は、いったん口に出したことを途中でひっこめたりするものじゃありません。革靴と馬具は、主人がこれからの時代を見越して始めた商いですよ。それなりに、儲かってもいるのに」
「そうだぞ。足袋1足の儲けと革靴1足の儲けば比べて見ろ。足袋はやっぱり足袋でしかなか。苦労する割には報われん」
冷静さを取り戻した雲平は、川上が考えていることも聞いてみたくなっている。モトが言うように、確かに革靴も馬具も、足袋に比べて利益が大きい。儲かっている商売をやめると言う理屈を理解せよと言う方が無理かもしれない。
「僕が言いたかことは、資金の流動率の問題です。確かに足袋の方の利益は薄かです。ばってん、靴1足を売る間に足袋は100足も売れます。しかも、足袋はほとんどが現金商売ですけん。売って手にした金で、すぐに次の材料ば買うことができるとです。反対に、革靴の方は売値が高か分、材料の仕入れ値も高かです。それに、作って売れるまでに、足袋の何倍もの時間がかかります。その間、大切なお金が眠ったままになってしまうとです。この店ば大きゅうするためには、今は足袋と革靴と馬具の3本立ては多過ぎると思います」
もともと革靴生産に消極的だったモトは、川上の進言を心中喜んでいる。雲平はというと、先ほどまでの怒り心頭の表情は消えて、俯いたままで考え込んでしまった。そばにいる金蔵と卯之助は、その後の成り行きが心配で仕方がない。
「あなたさん、神さまですよ」
突然モトの口から「神さま」が飛び出した。呆気にとられたのは言い出しっぺの川上である。雲平には、モトが次に何を言おうとしているか分かっている。
「神さまが倉田雲平に危険信号を送っていなさるんですよ。19歳の時の雲平が、『足袋作りこそ我が天職』と神に誓ったのに、その辺のところを少し忘れかかっておらんかと」
「父ちゃんが足袋職人になるのに、そげなわけがあったと?」
初めて知る父親の「天職」話に、金蔵も目をぱちくりさせている。
「考えておく」
言い残して、雲平は外に出ていった。
こんな場合の雲平の行き先は決まっている。
「何ごとな、雲平しゃん。...そげな憂鬱な顔ばして」
雲平は、皮革部門の整理のことをかいつまんで話した。
「革靴ばやめろち言われたら、それは面白うなかろうない」
嘉助は、火鉢の炭をいじくるだけで、雲平の話に賛同している風には見えない。
「どげん思うね、嘉助は」
「雲平しゃんは、よか若者ば雇うたない」
問われて嘉助が一言。雲平の方は、ますます面白くない。
「モトの奴、俺の言うことは聞かんで、川上の言い分にばかり耳ば貸しよる」
「歳甲斐ものう、やきもちば焼くとか」
「そげなことじゃなか。馬具はまだよかとして、革靴までやめることはなかち思うとたい。これからの花形商品になるとじゃけん」
「雲平しゃんの言うことも一理はあるない。ばってん、つちやたびは、まだまだ家族が中心の個人商店たい。今は、欲張らん方がよかち、俺も思うがない」
「つちやの革靴なら言うて、贔屓にしてくれる小売店もできたとに」
未練たらたらの雲平である。嘉助に引導を渡された格好の雲平は、間もなく皮革部門に必要な設備と道具、それに得意先まで、久留米市内の米穀商に譲渡した。革靴と馬具の製造に関わった人員は、すべて足袋製造に振り向けた。
雲平、西南戦争で味わった痛い失敗以来の「天職」回帰である。
若者の登用⑥
明治27年(1894年)から28年にかけて勃発した日清戦争は、日本の圧倒的な勝利で終わった。
この時期には、全国的に実業学校が誕生する。明治29年、久留米簡易商業学校(現久留米商業高校の前身)が開校した。後につちやたびの経営を担う次男の倉田泰蔵や、ブリヂストンタイヤを創設する石橋正二郎などが学んだ久留米商業学校の前身である。
このところのモトは、以前にも増して機嫌がよい。雲平が革靴と馬具の製造販売をやめて、足袋の増産に力を注ぐようになったためである。夫には、自ら決めた天職の道を、もっと先に進めてもらいたかった。一度に数十枚もの布を処理する裁断機と、あっと言う間に縫い合わせてしまうミシンを導入してからというもの、足袋の生産量は年間10万足にも迫った。大飛躍である。
雲平は、暇を見つけては町の中を歩くことにしている。古くなりかけた自分の頭を洗濯するには、進んで世間を知ることが大切だと痛感しているからだ。明治維新から30年が経過して、気がついたら四十路も中間を通り越した。
写真:明治後期の久留米停車場
久留米が市制を布いてからやがて10年になる。この頃では、徳川の時代はおろか、西南戦争の面影さえ窺うことが難しくなった。新生久留米市誕生と同時に営業を開始した九州鉄道は、熊本から門司まで切れ目なく走るようになっている。1日1往復する貨物列車には、綿布・紡績糸・鮮魚・藍玉・綿などを満載して往復を繰り返している。
鉄道に合わせて、街の中も活気づいた。苧扱川町には、電信局と郵便局が開店し、居ながらにして全国に向けて通信が可能になった。
通町から米屋町、更に三本松から苧扱川町、柳川街道へと続く大通りには、新旧入り混じって、商店が軒を連ねている。その中を人力車が走りまわる。
更に大きな変化は、国分町に陸軍歩兵四八連隊が出来たことである。このとき以来、久留米の町は、軍隊と共存する商業都市として生まれ変わった。
目標100万足⑦
雲平が支配人の川上を呼んだ。たまたま、嘉助が立ち寄っている時だった。
「こうなったら、モトが言うごと、量産態勢に突っ込もうと思うとる。とりあえずは1年間に100万足くらいはと」
嘉助が、手に持った湯呑み茶碗を取り落としそうになった。つちやたびの年間生産量は、未だ10万足に到達したばかりだったからだ。
「正気か、雲平しゃんは」
「あくまで頭の中の計算たい。そのためにも、川上支配人には死に物狂いで働いてもらわなきゃならん」
「もちろん、働くことに文句はなかです。ばってん、俺が何ばすればよかとですか」
突然「100万足」と聞かされて、川上の頭もおかしくなりかけている。
「お前どんがびっくりするような大量生産ば成し遂げるには、工場も職工の数も、資金も、今のままでよかとは思うとらん」
雲平は、自分への指示を待っている川上を無視したまま、途方もない構想を打ち上げっ放しである。
「雲平しゃん、どこから100万足ちいう数字が出てきたか、俺にはさっぱりわからんが」
大量生産をけしかけてきた嘉助の方が怖気づいている。どうしても、西南戦争時の雲平の失敗が頭の隅を過ぎるからである。
「俺も四十七ばい。若い時のごと無茶はできん。売れる見込みがたったときにしか、設備に大っか銭ばかけたりはせん。よかか、義信。九州中で足袋ば履く人間がどのくらいおるか、そこから調べろ」
「それは、人口ば調べればよかでしょう。人間誰でも寒ければ足袋ば履きますけん」
「そげなことはわかっとる。ざっと見て、その数は百万とか2百万じゃすまんじゃろう。足袋の種類もいろいろある。これまで、家で履くもんは女房や娘が夜鍋して作っておった。そのもんたちも、値段が安けりゃ、工場でできたものば買うごとなるじゃろうし」
呆気にとられた格好で、嘉助も川上も聞き入った。
「実はな、モトが量産、量産ち言うもんじゃけん、九州中の人間ば皆んなうちの客にしたらどげなことになるか考えてみたわけよ」
しばらく沈黙していた嘉助が、重い口を開いた。
「九州中の足袋屋から、客ば皆んな取り上げるち言うとか、雲平しゃんは」
「そうじゃなか。九州の人間が履く足袋ば、岡山とか四国とか、大阪とかの足袋屋だけに任せておくわけにはいかんということたい。九州の人間が履く分くらいは九州の足袋屋で賄わんとない」
川上も、雲平が言おうとしている本音が少しずつ分かってきた。
市場調査⑧
「それで大将は、俺に...」
ここにきて、雲平も少々苛立った。
「今俺が言うたことば、ちゃんと調べろ。九州中の人間が1年間で何足くらい新しか足袋ば必要としとるか。それも、寒さ凌ぎの黒足袋とか、お座敷で履く白足袋とか、作業中の職人が履くもんは区別して調べにゃならん。それから九州には足袋屋が何軒あるか。もっとも大事なことは、今本州とか四国からどのくらいの足袋が九州に持ち込まれておるか」
川上は、雲平の言う意味をようやく理解した。今でいう市場調査のことであった。
「任せて下さい。学校の先輩で、大学校でそげな研究ばしとる人がおりますけん、協力してもらいます」
雲平が大きく頷くと、嘉助のため息も安堵に変った。
川上は、店主の命じる調査を始めるにあたって、金蔵と事務方にいる吉岡保を助手につけたいと願いでた。吉岡は、南方の矢部川沿いで育った若者で、久留米簡易商業学校を出たばかりである。計算に長けているだけではなく、世の中を流れる金にも興味を持っている。
この時期に足袋の生産が盛んだったのは、埼玉をはじめとして岡山・大阪・広島・和歌山・徳島などであった。店別にみても、埼玉県の行田では、既に年間の生産量が100万足に達している店がある。岡山県にも70万足。そのほか、30万足から40万足を作る店はざらにあることが分かった。
雲平がため息をつくように、九州中を合計しても、総生産量は86万足に過ぎない。大よそ1,600万足が、関門海峡を渡って九州に移入されていることも分かった。
「先ごろ大阪の堺にでけた『福助足袋』が、博多でも大々的に宣伝ばやっとるそうです」
川上は、先輩から受けた情報を雲平に告げた。
「宣伝か。どげんよかもんば作っても、履くもんがつちやたびば知らんことには、どもならんけんな。これから、九州中に名前ば売り込むためには、どげな宣伝ばしたらよかもんか」
倉田雲平には、次にぶち上げる狼煙の心づもりも済んでいるようである。
|