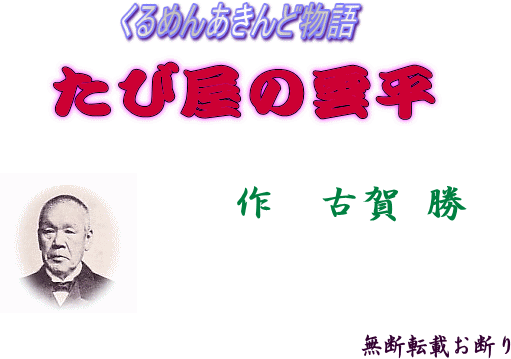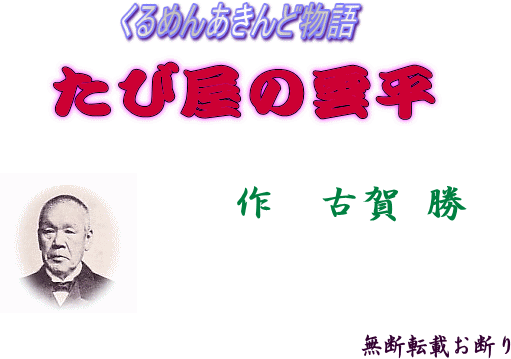|

勝負は本場で①
時は20世紀に入って2年目の明治35年(1903年)へと進む。日清戦争で日本が勝利した後、ロシア・フランス・ドイツの3国が、日本の遼東半島領有に干渉したこと(三国干渉)から、次なる日露戦争へと突き進もうとする時代である。
雲平が「年産100万足」を宣言した後も、モトの疑問は解けなかった。
「あなたさんにお尋ねしたいのですが・・・。例えわたしどもの工場で100万足を作れたとして、それを売る手立てはお決まりでしょうか」
雲平には、モトの疑問が最大限の皮肉に聞こえた。
「売れるか売れんか、やってみないとわかるもんか。まずは、売り物ば揃える方が先たい」
「それだけの足袋を売るのは大変ですよ。いったいどうするんです?」
「大仕掛けの売り込み作戦だ」
「売り込み作戦ですか。場所は久留米ですか、それとも博多?」
「いいや、長崎で...」
突然わけのわからないことを言い出す夫に、モトの方が戸惑ってしまう。
「長崎が、あなたさんにとって、足袋作りの出発点だということは何度も聞いてわかっています。ですが、久留米の足袋屋が、どうして長崎なのですか。そこまで長崎にこだわるわけを、少し詳しく聞かせてください」
父母の問答に息子の金蔵が割り込んだ。
「お母しゃん。父ちゃんは、長崎なら、むかしの知り合いが助けてくれるち思うとらすとじゃなか?」
息子の勝手な推測に、雲平が怒った。
「馬鹿なことを言うな。俺はそこまで落ちぶれてはおらん」
「そんなら、教えてくれんね。長崎でなけりゃならんわけば」
金蔵の挑発に乗った形の雲平は、重い口を開き始めた。
雲平は、一息入れた後切りだした。次男の泰蔵も金蔵の隣りに陣取っている。明治20年生まれの泰蔵はこのとき13歳で、中等学校の下等科に通っていた。将来は、金蔵とともに父親の仕事を手伝うよう言い渡してあり、そのために中等学校の次は久留米商業学校に進むことも決めている。
「長崎は、徳川さまの時代から、足袋作りが盛んな所じゃった」
「そのことなら、何度も聞いとるばい」
金蔵が、面倒くさそうに口を出した。
「黙って最後まで聞け!」
いつにない雲平の苛立ちに、座が静まった。
「長崎で作る足袋は『長崎足袋』ちいうて、日本でも一二ば争うごとよか足袋たい。ばってん・・・」
「・・・・・・」
「長崎の足袋は、どれも値段が高かか。うちが長崎の店より安か値段で売ったならどげんなるか。それでも、長崎の人たちは、長崎の足袋しか履かんち言うじゃろか」
「ばってん、父ちゃんが長崎ば離れてから30年も経つとじゃろ。そこのところがもうちょっとわからん」
「俺も、修業時代をぼけっと過ごしとったたわけじゃなか。お座敷で足袋ば履くおなご衆や祭りのときの男衆、植木屋とか大工が作業場でどげな足袋ば履いておるか、毎日見ておった」
雲平の話が、熱を帯びてきた。
「あの町には、むかしから日本中の人間が集まってきた。いいや、世界中から来ておった。日本が鎖国政策ばとったときでも、長崎だけは例外じゃった」
雲平が喋っている間、同じ師匠の下で修行した卯之助は、黙りこんだままである。川上が、雲平の話を遮った。
.gif) 写真:現在の長崎港 写真:現在の長崎港
「大将から見て、うちの足袋が長崎に負けておるのはどこらへんですか」
さすが支配人である。質問も核心をついてくる。
「長崎の足袋のよかとこは、何たって長持ちすることたい.。それに品がよか。そのことは、おかみさんから何百回も聞かされた」
川上の質問は続いた。
「うちが作った足袋じゃ、どげんしても叶わんとですか」
「お座敷足袋だけなら、そげん負けちゃおらん。ばってん、作業用の足袋となると...」
「どのへんが長崎足袋に叶わんのですか」
「作業用じゃけん、底生地が強うて軽うなけりゃならん。まだまだうちは遅れとる」
金蔵が不安げに、席を立とうとする。
「待て、最後まで黙って聞かんか」
しぶしぶ、金蔵が座りなおした。
「父ちゃんが、もう一度修業時代のことば思い出すたい。幸いなことに、そばには卯之助おっちゃんもおるけんな。若かもんが、長崎で商いばしやすかごと、よか足袋ば作ってみせる」
モトはというと、長崎足袋との競争より、採算の方が気がかりのようだ。
「売っただけ損をしているようでは、つちやたびは潰れます」
不安げなモトに、川上が応えた。
「奥さん、心配はいらんですよ。大将が考えていなさることは違うてはおらんと思います。今は、何よりも、大勢の人につちやの足袋ば知ってもらう方が先ですけん。その先に、本当の商いが待っておると思うとです。僕が大将より一足先に、金蔵君といっしょに長崎に行ってきます」
このとき金蔵は17歳であった。
販売拠点②
川上は、金蔵と市場調査に尽力した吉岡保を従えて長崎にやってきた。泊る宿は稲益旅館。雲平が、修業時代に関わりのあった宿屋である。主人の寅之助は今年古希を迎えたとかで、既に隠居生活に入っていた。代わりに、息子が後を継いで切り盛りしている。
「父雲平の名代として参りました。こちらさまには、父が若い頃に一方ならぬお世話になりましたそうで」
金蔵は、旅の途中で繰返し稽古して覚えた口上を何とかこなした。
「そうかい、あの雲平どんの息子さんかい。親父さんはいくつになられたかな」
「はい、五十二になると聞いております」
金蔵の話す一言一言に寅之助は大きく頷いた。
「ところで、この度のあんたらの長崎入りは、物見遊山とは違うようじゃな。わしと雲平どんとは、腐れ縁とまでは言わんが、頼まれれば一肌脱がんわけにもいかん仲じゃけん」
寅之助は、川上が切り出そうとする要件を、先取りして納得している。
「ありがとうございます。お言葉に甘えて、お願いがあります」
写真:現在の西古川町付近
.gif) 川上は、金蔵と座を入れ替わって商談を進めた。 川上は、金蔵と座を入れ替わって商談を進めた。
「足袋の本場で、罰あたりめがとお咎めでしょうが。雲平は、お世話になった長崎の人たちに、自分が作った足袋ば履いてもらいたかとです」
「なして長崎でなきゃならんのじゃ」
「長崎が足袋の本場じゃけんです。ここでの商いが、我が店の跳躍台になるとも思うております」
「それなら、長崎で商いばした後はどうなさるのかな」
寅之助と川上のやりとりが続く。
「はい。主人が申しますには...。九州の人が履く足袋は、九州の職人で賄わなきゃと」
「いま、雲平どんのところでは、どのくらい作っておる?」
「年間で10万足くらいかと」
「どのくらい作れば、九州人にいき渡るのかの」
「とりあえず、100万足を賄いたかとです。それでも、九州中の人に行きわたるには程遠かですが」
「おい、おい。そげん雲平どんだけで商売ばやられたら、外の足袋屋が皆んな干上がってしまう(潰れる)がな」
そこでようやく寅之助の表情が和らいだ。
「雲平どんが、本場の長崎で足袋を売りたかという気持ちはようわかった。それで、お前さんたちが、わしに頼みごととは」
「はい、お店の一部を貸して欲しかとです。私らとこれから乗り込んで来る従業員が泊りこむために」
「うちは宿屋じゃけん、お客さんに部屋を貸すのに何の文句もなか」
「借料は言われるままに払います」
「それは当たり前のこと」
「それから、お店の玄関先に看板ば掲げさせて欲しかとです。『つちやたび 長崎取次店』ということで」
「何のために、うちが」
「稲益屋さんは長崎でも名のある旅館だからです。ご当地の小売屋と私どもの店の繋ぎ目になってもらうには、これ以上の条件はなかと思うとります」
川上の説得に、寅之助の感情が高ぶってきた。
「わしは、この長崎で宿屋ばやっとる人間ばい。稲益旅館の客は、旅人だけじゃのうて、地元の商人や役人が、宴会もやってくれとる。客の中には、足袋の製造や販売をする者も多か。そげんお世話になっとるお客ば、敵に回せち言うとか」
寅之助の声が大きくなった。川上は、結論を先延ばしすることにした。
旧知と再会③
金蔵らから遅れること1週間経って、雲平が店員10人を引き連れてやってきた。雲平にとって、久方ぶりの長崎上陸である。師匠の小川源助夫妻は既に他界していて、一番弟子だった幸六が老舗の長崎屋足袋所を継いでいる。
「親方が死んだ後、雲平の面倒を見ておった国松も六太郎も、皆んな故郷に帰って足袋屋ば始めておる。俺だけだ、あの頃から変わらずの長崎暮らしは」
幸六は、店主の苦労は想像以上だったと述懐した。雲平も、眼鏡橋の袂の店で兄弟子に向き合うと、30年前と少しも変わらないことを実感する。
「俺もとっくに五十ば超えました。うちにおる卯之助も、間ものう五十です。あいつも、遅まきながら、よか嫁さんば貰うて子供もでけて...」
2人の思い出話は尽きることがない。
「ところで、長崎でつちやの足袋ば売るちいう話は本当か」
「稲益旅館さんに、力ば貸してもらうことにしました」
雲平は、長崎に着いて真っ先に稲益旅館を訪ねている。寅之助は、協力はしたいが、町の商人との間で板挟みになるのが心配だと打ち明けた。
「稲益屋さんの気持ちもわかるな。長崎は古い町じゃけん、何よりも同業者や町内への義理を大事にせにゃならん。ばってん...」
言いかけて、幸六の口が重くなった。
「何でも聞きますけん、言ってください」
しばらく俯いたままだった幸六が口を開いた。
「雲平も、寅之助さんや俺と同じくらいに長崎には思い入れが強かもんな。どうしても、自分が作った足袋ば長崎の人に履いてもらいたかとじゃろう。それなら、値段ば下げろ。思い切って、本家の長崎屋足袋所より」
兄弟子は、長崎で勝負したけりゃ、長崎の足袋より強うて上品な品物を、しかも格安で売れと進言した。
「それは分かっとります。大恩ある長崎の人たちに、俺が作った足袋ば履いてもらうとです。この地の方なら、俺の足袋が良いか悪いかをはっきり言うてくれるはずですけん。長崎で商いばするのに、そろばんはいらんち思うとります」
そこで雲平が示したのが、1足あたりの売値を、地場相場より3銭から4銭安くすることであった。まさしく、儲けを度外視した金額である。更に雲平は、取次店を引き受けてくれる稲益旅館にも、特別な手数料を払うと言いきった。
大恩なる親方との真剣勝負に挑む覚悟を持てと、幸六は弟弟子に檄を飛ばした。
たばこの宣伝④
稲益旅館の玄関先に、木目も真新しい『つちやたび 長崎取次店』の看板が掲げられた。寅之助や幸六などが事前に働きかけてくれたこともあって、同業者からの苦情は出なかった。
雲平が久留米に帰っていった後、川上は残留する連中と次なる行動計画を練った。
「お客さんは、待つもんじゃなか。こっちから迎えにいくもんたい」
川上が、持論を説く。
「どげんして、お客さんば迎えに行くと?」
金蔵には、次なる行動のイメージが湧かない。
「隣の部屋の人と風呂場で話したばってん。その人は、東京からたばこの宣伝に来た人げな」
新参者の今村博敏が、思いがけないことを言いだした。
「ほほう、たばこの宣伝ばする人ちな。その東京の人が何ば言いよらしたか」
吉岡保が、東京からの旅人と聞いて興味を示した。
「その人が言うには、近頃の東京でのものの売り方も、ばさらか変わってきたち」
そこで、今村が言う男の話を皆んなで聴くことになった。宴会室に招き入れられたのは、東京銀座に店を構える、岩谷商会の磯崎忠男。
「諸君は、たばこってものを知っているかい」
突然、「たばこを知っているか」と問われたら、田舎者が都会人に馬鹿にされたような気持ちになる。
「それは、刻んだたばこの葉ばキセルに詰めて...」
一番前に陣取っている金蔵が、父親がたばこを吸っている情景を思い出して答えた。すると磯崎は、掌を横に3度振った。
 写真:天狗煙草のポスター(JTたばこワールドHPより) 写真:天狗煙草のポスター(JTたばこワールドHPより)
「それも確かにたばこではあるが、我が岩谷商会が商っておるのは、『口付たばこ』といって、キセルは使わん」
聴いている若者には、キセルを使わないたばこのイメージが湧かない。
「これが実物である。こうして吸う」
磯崎は、かばんの中から取り出した紙巻きたばこに火をつけた。吐き出された煙が、低い天井を這うようにして広がり、聴衆の頭上に降りてきた。
「京都の村井兄弟商会は、同じようなものを『両切りたばこ』と銘打って、我らと激しく競争しておる」
「岩谷さんと村井さんは、どげな風にして競争ばしとらすとですか」
磯崎を紹介した今村が、たばこ屋どうしの「競争」に興味を示した。
「よくぞ訊いてくれた」とばかりに、磯崎の口もますます滑らかになる。
「我が岩谷商会の社長の名は岩谷松平と申す。まずはその岩谷社長だが、主力商品に『天狗煙草』というど派手な名前を付けた。次に、岩谷商会を東京都民に広く知ってもらうため、銀座3丁目の店の壁を真っ赤に染めた。それだけではまだ満足しない社長、自分が着る洋服の色も真っ赤な色にしたのさ。会社で持っている馬車も皆んな真っ赤にな。更にだ。会社が打ち出す広告では、自分のことを『広告の親玉』とか『東洋の煙草大王』と称してはばからない。すべては、世の中の耳目を岩谷商会に引きつけるための、社長の作戦だったのさ」
今度は川上が念を押した。
「それで、効果は上がったですか」
「当り前さ。目立つことが好きな人間が住む町だよ、東京は」
「すごかですね。ついでに、村井商会の宣伝のやり方も訊いてよかですか」
気軽に応えてくれる磯崎に親しみを覚えた川上が、競争相手のことまで訊き出そうとする。
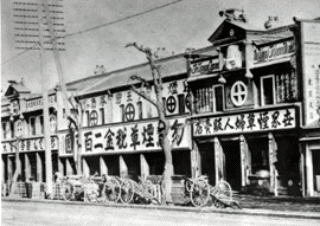 写真:岩谷商会の本社 写真:岩谷商会の本社
「ああ、いいとも。競争というからには、相手のことも言わなきゃなるまい。岩谷社長は鹿児島出身故、彼が鹿児島産の葉煙草にこだわるのは当たり前。対して村井の方は、アメリカやヨーロッパの葉たばこに執着したのさ。うちが『口づけ煙草』で売り出せば、相手は『両切り煙草』と銘打った。『天狗煙草』には『ヒーロー』とか横文字をぶっつけてくる。我が社の赤い馬車に対しては、これまたど派手に日章旗で飾りまくった。お互いに派手さを勝負の決め手にしたのさ」
「それで、軍配はどっちに上がったとですか」
金蔵は、東西でのたばこの売り込み合戦の様子が面白くて、勝敗の行方が気にかかる。
「簡単に勝ち負けなど決まるものか。競争してみてわかったことは、我が岩谷も京都の村井も、お互いに大儲けしたということだよ。わっはは」
笑い飛ばすところは、いかにも時代を先取りしようとする東京商人である。
「それだけではないぞ、東京の宣伝は。銀座では、サンドイッチマンも出現した」
「サンドイッチマンちは、どげなもんですじゃろか」
金蔵の質問も止まらない。
「おしろいを塗って口髭をはやしたおかしな男が、体の前と後ろに看板をぶら下げて、人の集まるところをウロウロしておるわけさ。これもまた、会社や商品を宣伝する手段だがね。その外最近では、新橋駅前に三井呉服店(後に三越)が等身大の美人の絵を描いた看板を揚げたりして。そうなりゃ、助べえ男どもが立ち止まって、よだれ垂らして見上げるわけよ」
磯崎の話を聞き終わって、一同次の行動にかかるまでに間を置かなければならないほどの興奮具合である。
言われてみれば、長崎の町でも、赤い鉄板に書かれたたばこの広告をよく見かける。磯崎が言うように、岩谷商会と村井商会の激しい宣伝合戦によって、紙巻きたばこは売れまくった。だがそうなると、お上が黙ってはいない。政府は後に、税収確保のためといって、たばこを専売制に移行させたのである。(明治37年=1904年)
謎解き看板⑤
磯崎の話を聴いた翌日のミーティングで、まず吉岡が手を挙げた。
「謎解きばやったらどげんでっしょうか」
「何な、謎解きちは?」
金蔵が、目を丸くした。
「たばこの宣伝に見習うて、長崎中につちやたびの看板ば貼りまくるとです」
「看板はよかばってん、謎解きちは?」
「看板を見た人に、看板と睨めっこばしてもらうためです」
「じゃけん、その謎ちは、どげなもんな」
川上は、吉岡の謎解き看板を採用することにした。早速吉岡を伴って近くの看板屋に出かけた。人のよさそうな親爺だが、なかなか注文の中身を理解してくれない。言われるままに作った薄い鉄製の看板とは、幅5寸(15.2㌢)、丈(高さ)1尺5寸(45.5㌢)という縦長で、背景柄として青ペンキを塗りつぶしている。
宣伝文句はというと、青地に白ペンキ塗りの5文字だけ。
にかぎり升
「わしも子供のころからこの商売ばやっとるばってん、こげんわけのわからん看板ば作ったとは初めて」
川上から宣伝のからくりを事前に知らされていた親爺でも、出来上がった100枚の看板を前に、大きくため息を吐く。
若者たちは、2人1組に分かれて、稲益旅館の取次店を出発した。車力には、出来たての看板と商品の足袋が積んである。
蛍茶屋方面を担当した今村博敏と田代公吉が、港を見下ろす斜面に建てられた百姓家に入った。
「お宅の小屋の壁に、この看板ば貼らせてもらえんでっしょか」
謎解きの看板を見せながら、還暦を過ぎたくらいの女に語りかけた。
「これ、何ですな?」
女は、怪訝な顔をして今村の顔と看板を交互に見比べている。
給金を貰う田代らにとって、最初の大仕事である。出かける前に川上や吉岡から厳しく要領を教えられていた。
「1ヵ月経ったら、必ずもう1度伺いますけん。その時まで看板の意味はわからんままにしておいて下さい。奥さんと子供さん用に、つちやの足袋ば置いていきますけん」
「つちや何とかとは、いったいどげなことですな」
今村博敏が答えた。
.gif) 写真:風頭公園から港町風景 写真:風頭公園から港町風景
「これは、筑後の久留米で作った足袋のことです。つちやいうのは、うちの店の名前ですけん」
「いらん、こげなもんは」
老女は、いったん手にした足袋を、土間に投げ捨てた。
「どうしてですか、私らの足袋のどこが気に入らんとですか」
血の気の多い今村が、思わず声を張り上げた。そのとき、先輩格の田代が今村の頬を力いっぱい叩いた。
「お客さんに向かうて生意気ば言うな。土下座して謝れ」
大声で怒鳴られて、今村がしぶしぶ土間に膝をついた。
「すんまっせん、俺が悪かったです」
老女も、息巻いた気持ちの持って行き場に困っていて、いったん投げ捨てた足袋を拾い上げた。
「最初に言わなきゃいけんかったんですが、この足袋は、西古川町の足袋所で修行した俺たちの主人が作ったもんです。もちろん、看板ば揚げさせてもらうとですけん、この足袋はお礼です。もし、履き心地が悪かったなら、勝手に看板ば外してもろうてもよかです」
今村と田代は、相手の目を見据えて語りかけた。
「ひと月経ったら、必ず来にゃならんばい。そん時まで、看板が掛っておればよかばってん」
初めての交渉に、2時間を要した。だが、ここで得た経験を、次の客に活かすことを繰り返して行くうちに、1軒あたりの時間は少しずつ短くなった。
つちやたび
にかぎり升
吉岡保が発案した「○○にかぎり升」の看板は、たちまち長崎人の注目を集めることになる。民家の軒先や屋根上に看板を打ち付けていく若者たちは、体で商売のイロハを覚えていった。
「あと200枚ばかり、追加しようかね。それから、青鉄板に貼りつける『答え』も、そろそろ注文しておかんとない」
「1ヵ月前にお邪魔した、つちやたびのもんです」
今村博敏と田代公吉が、いつぞやの百姓家を訪ねた。看板は、あの日のまま軒先に掲げられていた。
「貰うた足袋ば履いてみたばってん、長崎足袋と変わらんくらいによかね。孫のも、どげん走りまわっても破れんかった」
今村と田代が、思わず顔を見合わせた。
「ところで、『にかぎり升』ちは、どげなこつですな」
老婆は、外のことはどうでもよいと言いたげに、看板の謎解きを迫った。
「そげん難しかことではなかとです。これば、あの看板の上に貼らせてもらいますけん」
今村が、車力の荷台から持ちだしたもう1枚の薄板を、空白部分に貼りつけた。
「あれ、まあ」
老婆は、曲がりかけた腰を前後に揺すって笑いこけた。
要は、今日でいうイメージ広告のこと。商品の内容や代金のことより、製造した企業や商品の名前を売り込むことで、消費者に安心感を与える手法である。貼りめぐらされた看板は、日を置かずして長崎中の話題を浚うことになる。
股旅行商⑥
「さあ、これからどうするかだ」
川上は、金蔵の顔色を窺いながら、集まった若者たちに質した。
「俺の考えば言うてよかな」
真っ先に金蔵が手を挙げた。
「せっかく長崎の人がうちの看板ば見てくれたとじゃけん、今度は実際につちやの足袋ば買うてもらわにゃならん」
「......」
川上と吉岡の目が、金蔵の口元に集中する。
「力ずくで買わせるわけにもいかんし...」とは、昨日蛍茶屋付近の百姓家で、老女の説得に成功したばかりの今村である。
「無理やりとは言っとらん。ばってん、こっちから出かけて行って、『これば買うてください』ち言うことはでくる」
「行商のことじゃな、富山の薬売りとか近江の商人がむかしからやってきた」
川上が、金蔵の発言に相槌を打った。
.gif) 写真:近江商人行商姿=五個荘外村宇兵衛家資料 写真:近江商人行商姿=五個荘外村宇兵衛家資料
「...それも、磯崎さんが言うていたたばこの宣伝隊のごと、車力に幟ばたてて。そうすりゃ、否応なしに長崎の人はつちやの足袋ば履いてみようかちいうことにならんかな」
これには一同、沈黙してしまった。
「論ずるより実行を」と、今度も2人1組の行商隊が出来上がった。言い出しっぺの金蔵も、木下直吉と組んで出かけた。
この時代になっても、行商人の姿は、映画の時代劇で見る旅人の繕いとそんなには違わない。照れ降れ両用の編笠と革の合羽、簡単な手甲と脚絆に草鞋を履いた姿が一般的である。金蔵らも、いつ何時風雨に遭っても慌てないでいいように、身繕いをして出かけた。車力には、大中小、種類別に商品の足袋を積んでいる。
荷台の四隅には「つちやたび」の幟を括りつけた。例の「つちやたび にかぎり升」の看板も必需品。行く先々で、軒下の看板貼りを願い出る。行商班は、足袋の売り込みより、予め調べていた長崎周辺の小売店を1軒1軒回ることに重点を置いた。
稲益旅館内に設けた事務所では、川上と吉岡が地元の新聞社を呼んで、広告の打ち合わせ中。連日の新聞広告に、長崎市民が関心を示さないわけがなかった。
「これまでより、裾から見える白足袋が目立つね。お陰で踊りが引き立つ」
色町の芸者衆が、舞台で履く座敷足袋に満足した。
「何たって、値段が安いのが魅力」とは、商家のおかみさんや女中衆。「長持ちする」の声は、足元に神経を集中するとび職や大工たちの評判であった。
たばこの赤看板と並んで貼られた青看板は、長崎市民のつちやたびへの関心を高める一方となった。
こうして、雲平と川上が仕掛けた長崎におけるキャンペーンは大成功を収めることになる。
九州制覇⑦
雲平が、嘉助を誘って牛鍋屋に居座った。
「長崎での宣伝が効いて、1ヵ月間で1万足も売れたけんね」
雲平が自慢そうに胸を張ると、嘉助も親友の話を歓迎する。いつまでも変わらぬ友情である。
「雲平しゃんは、長崎の足袋に追い付け追い越せで、寝る時間も惜しんで作ったけんな。そこで、本場に追いついたのじゃから、さぞかし嬉しかろう」
嘉助の雲平に対する注文は、なお厳しい。
「九州の次は、日本一たい」
「嘉助が言うごとなるには、あと何十年かかることか」
そこでひと息、嘉助が念を押した。
「足袋作りば天職にする職人に終わりなんてかあるもんか。日本人が、足袋を暮らしの中で必要と思うておるうちはない」 従業員総出で、九州一円への行商作戦が始まった。22歳に成長した金蔵が計画を立てて、2人1組の班に分かれる。
この時代、九州鉄道の路線は、門司港から八代、鳥栖から長崎まで、そしてほぼ九州全域に張り巡らされていた。ミシンや裁断機などを操縦する訓練を受けた職工らがフル回転して製造した商品は、主要駅止めにして送り出された。編笠と革の合羽、手甲・脚絆・草鞋履きの行商隊は、砂埃を全身に被りながら、山を越え川を渡って、村々に点在する小売店を訪ね歩いた。その時々に、駅の貨物扱い所に立ち寄り、商品を受け取って車力に積み込む。
行商隊の仕事は、小売店に品物を下ろすだけではすまない。立ち寄る店や民家の軒先に、「つちやたび」の看板を掲げさせてもらうことも重要だ。
.gif) 写真:明治30年代に九州鉄道を走っていたドイツ製のクラウス号(大分県宇佐神宮境内に展示) 写真:明治30年代に九州鉄道を走っていたドイツ製のクラウス号(大分県宇佐神宮境内に展示)
近代化された生産手段と宣伝媒体の活用が功を奏して、売り上げは飛躍的に伸びていった。雲平が嘉助と、牛鍋屋で語り合った明治35年当時、つちやの生産高は10万足だった。それが日露戦争が終結する2年後の明治37年には、一気に78万足にまで伸びた。九州人が履く足袋はつちやが賄うと大見栄を切った目標の100万足まで手の届く距離である。
そんな勢いのつちやの行商作戦は、当時の新聞記事にも取り上げられている。
「夫(そ)れ苟(いやしく)も国権の普(あまね)き所、如何なる山地僻地も、店頭庇下(ひか)『たばこ』の赤札を横に吊るしたるを見ざるはないが、是と共に復(また)必ずや『つちやたび』の青札を認めざる所はあるまい」
長崎から帰った後の雲平は、工場を拡充するための土地探しに奔走した。並行して、優秀な職工をどう確保して育てるか。更に、大掛かりな生産には、分業化が必須である。
裁断部・素縫部・先付部・イロ消し部・回縫部・網代部などに、職工を組み分けした。新規採用した20歳から30歳までの職工には、半年間の猛特訓を課した。
「急がば回ればい、雲平しゃん」
訓練期間中の青年には、毎月10円の日給を支給した。これにもモトと川上の知恵が働いている。
「これからの店の経営は、何というても人ばい。雇うた人間が、思うように働いてくれんかったら、工場や機械ばかり揃えても、よか足袋はできん」
川上は、優秀な職工には、相応の給金が必要だと説いた。
|