|
明治の終わり
喜次郎は、この頃筑後川の土手を歩くことが習慣になっている。その都度、渡し場を見下ろす場所に腰をおろして考える。明治44(1911)年の初夏を迎えて、耳納(みのう)の尾根が霞んで見えた。自らの年齢(とし)を振り返ると、還暦を過ぎて早や5年も経っている。
この場所で初めて鍋屋の増吉に声をかけられたのは、50年もむかしのことであった。初対面の二人は、渡し場を見下ろしながら語り合った。あの時、世の中は徳川幕府崩壊の寸前だった。
.gif)
久留米市宮の陣付近を流れる筑後川
16歳の少年が、初めて会う近江のベテラン行商人に質(ただ)した。
「俺のような田舎もんでも、もっと広か世界で商いがでくるでっしょか」
対して増吉は、喜次郎の手を握って答えた。
「あほやな。でけもせんことを話しますかいな。筑後平野には宝物が仰山埋まってますのや。世の中が変われば、その宝物を掘り起こして船に積み、よその国に運び出して商いもでけます。筑後川は、世界中の海と繋がっとるさかいな」
増吉の握りしめた手の感触と言葉で、喜次郎はかすり売りになる決心をつけた。増吉が75歳であの世に旅立ってから、早や3年が過ぎようとしている。転職を勧めてくれた本村庄兵衛も、増吉を追いかけるように鬼籍に入った。商売仲間の岡茂平や松井儀平の姿も同業者の寄合(よりあい)から消えた。代わりに出てくるのは息子たちである。喜次郎もとっくに還暦を過ぎ、業界では長老と呼ばれるようになった。
かつて、井上傳の曾孫(ひまご)の久吉に会った際、彼は、機屋を再建して先祖が築いたかすり織りを再開したいと告げた。その言葉がきっかけで、同業組合が寄付金を募って井上傳没後三十年祭を挙行した。祭の一環として、組合の中庭には井上傳顕彰石碑も完成した。現在通外町の五穀神社境内に建っている、あの巨大な石碑のことである。その日の夕に開かれた宴会には、福岡県知事も出席して大盛況だった。更に同業組合は、井上傳の子孫に織屋再建のための資金として金50円を贈った。
一方、喜次郎が経営する国武合名会社は、工場従業員が600人、自宅職工2000人を抱える大所帯に膨れ上がった。長男の金太郎は37歳になり、二代目の就任披露も済ませた。金太郎から9歳離れて生まれた次男の克己は、出来立ての久留米簡易商業学校(後の久留米商業高校)を卒業後、大きな夢を抱いて朝鮮半島に渡った。
「おっかしゃんや藤山の伯母しゃんが生きていてくれたらない」は、喜次郎が久次と想い出を語る時の定番文句である。

国武喜次郎家族
「ここにおったとですか」
筑後川を行き来する渡し舟を眺めながら、過去に思いを馳せている喜次郎に声をかけたのは久次だった。
「下の方で魚釣りばしとったら、大将の姿が見えたもんで・・・」
長年国武の店を盛りたててきた久次も、最近退職して、隠居生活を楽しんでいる。
「何ば考えとったですか。ぼうっとして」
久次に言われて、喜次郎は反射的に立ち上がった。
「金太郎君が一人前になりなさって、張り合いがのうなったですか」
言われて、苦笑いしながら川岸に下りていった。
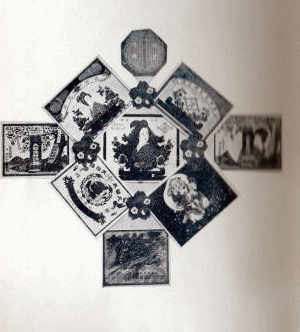
井上傳肖像を多用した国武専用商標
「久留米絣の生産も百万反に達して、大将もさぞ満足でっしょ。むかしからの夢でありなさったけん」
しばらく雨が降らなかったせいか、川底の岩の合間を泳ぎ回る小魚がよく見える。下流に架かる鉄橋を、黒い煙を噴きあげながら貨物列車が通過していった。
「工場に自動織機ば入れてから、かすりの生産高が一気に跳ね上がったもんない。これも、久次が金太郎ば支えてくれたお陰たい」
久次にとって、豊田式自動織機の導入は、上野での少年との出会いと合わせて、忘れられない大仕事であった。
「昨日、会社ば覗いた時、金太郎君が言いよりましたばい。松ヶ枝町の工場で働いとる太助が、えらい働きもんになっとるそうです。これからは、金太郎社長ば助けていくことになるとでっしょ」
久次が言い出した「働きもんの太助」とは、松ヶ枝町工場で責任者を務める岡本太助のこと。市内篠山町でかすり屋を営む岡本家の三男坊である。幼い頃から、商人見習いとして雇っていた青年だった。
「ほう、そげん働きもんになったか、太助の奴」
喜次郎も、自分と久次が第一線を退いた後の会社のことを心配していただけに、ひとまず安心であった。
時の流れは、喜次郎らが想定する以上に速いスピードで、目の前を通り過ぎていく。そして、くるめんあきんどらが大暴れした「明治」が後方に去り、次の嵐の時代が迫って来る。
大正~昭和のあきんど

井上傳像を使ったオカモト商店の商標
明治時代は、45(1912)年7月で幕を閉じ、時代は「大正」へと移る。この時国武喜次郎は数え年の66歳になっていた。日露戦争(1904~05年)勝利の余波もあって、商都久留米は更に賑やかさを増すことになる。石橋徳次郎の息子重太郎(二代目徳次郎)・正二郎兄弟による足袋生産が飛躍し、つちや足袋(槌屋足袋を改称)と合わせて、かすりの売上高を上回ったのが大正9年である。かすり業界も負けじと追走した。
岡本太助が国武合名会社の支配人に昇格したのはこの年である。彼は、喜次郎の期待に違わず、社長の金太郎を助けて、久留米絣の品質向上のために目覚ましい実績を残した。
国武喜次郎とともに木綿業界をリードしてきた本村庄平が、大正11(1922)年に71歳で没した。更に5年後の昭和2(1927)年には、国武喜次郎が81歳でこの世を去った。
国武金太郎が、父親喜次郎の悲願であった久留米公会堂を、久留米市に寄贈したのが昭和5年である。

戦前の久留米公会堂(久留米市両替町)
その年、久留米絣の生産量はピークに達し、年産220万反を記録した。その内の約40%を国武合名会社が占めたというから驚きである。
国武合名会社に大きな貢献を果たした野口太助は、昭和13(1938)年に退社している。その後時代は、かすり業界をも一変させる第二次世界大戦に突入。久留米の町と貴重な遺産が焼き尽くされて、昭和20(1945)年8月に終戦を迎える。
1.gif) 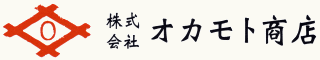
左:魚喜の紋章 右:オカモト商店の紋章
喜次郎の後を継いだ国武金太郎が昭和25(1950)年に死去した後、岡本太助がかすり問屋「オカモト商店」を立ち上げた。太助は会社の紋章に、井桁に岡本の頭文字「O」を挿入した。これが、現在久留米市日吉町に展開する久留米かすりの老舗「儀右ヱ門館」(株式会社オカモト商店)である。
魚喜の国武喜次郎が久留米絣を売りまくった時代、仕立てられた着衣は着物(和服)が主流であり、農婦や町娘の普段着として重宝がられた。戦後その様相は、「和服から洋装へ」と一変する。

久留米絣によるファッション
(オカモト商店提供)
オカモト商店会長の野口敏男氏(岡本太助の孫)は、地元新聞社の取材に対して、「うちは独自で良い商品を作り、適正価格で売っていく」と応えた。加えて、「人もかすりも一緒です。縦糸と横糸の支え合いですけん」と持論も展開した。彼もまた、近江商人や国武喜次郎の流れを汲む、くるめんあきんどの大切な継承者なのである。
本編の主人公・国武喜次郎は、現在久留米市内(寺町)の心光寺に眠っている。彼は、死後の激変する世の中をどのように見ているのだろう。
「後輩たちよ、久留米絣を守って、よく頑張っとるじゃなかか」とか、「近江商人は、筑後平野に宝物が仰山埋まっておると言ったが、今のくるめんあきんどは、その宝物を掘り起こして有効活用しとるじゃろうか」
なんて、ぶつぶつ唱えているかもしれないな。(完)
|

