|
士族授産の迷路
本村庄平は赤松社への関わりを少々負担に感じるようになっていた。社長の三谷有信はというと、繊細な図柄のかすり織りに成功したことで、いたって満足気である。 赤松社の商標である「山道形」は、「良質」と「信用」の代名詞ともなって、世間の評判を得た。その結果、生産高も明治23(1890)年には1万7800反を記録した。

赤松社絣商標
だが三谷の経営は、未だ武士の商法の域を脱出できないでいる。全士族を対象に始まった授産施設のはずだったものが、実際に工場で働く者の数は、対象者の2割にも達していない。これでは、設立目的である「士族授産会社」の実態には程遠い。経費ばかりがかさんで、赤松社の台所は火の車であった。
「いよいよだな、赤松社も・・・」
庄兵衛が座りなおして、キセルにきざみ煙草を詰め込んだ。本村商店の奥の間である。
「三谷さんの目指すもんがみんな間違っとるとは、俺も思わんですよ。あの人が言いだすまでは、あげな細か糸でかすりば織ることば、誰も言わんじゃったけんですね。赤松社の商標は上等かすりの印ち、あちこちから評判ば貰うとりますけん。ばってん・・・」
庄平は、悔しさを隠しきれないでいる。
「半年前の傘置き場の火事からこっちのことですよ。売りもんの傘がみんな焼けてしもうて。それからちいうもん、経営がおかしゅうなってしもうた」
庄平が奥歯を噛みしめた。
「三谷さんは、これから赤松社ばどげんするち言いよらすとか」
庄兵衛の表情には、笑みすら見える。しばらく間をおいて、やっと庄平が答えた。
「かすりと白皮表(雪駄)の生産はやめる、ち」
「それじゃ、赤松社で作るもんは、和傘(かさ)だけちいうことになるな。そうなりゃ、かすり工場で働いとったお侍さんや奥方たちはどげんなると?また客呼びに逆戻りか」
「そうじゃのうて、本村商店で引きとってくれろ、ち」
庄兵衛が、ほくそ笑んだ。
「やっぱり、そうきたか。ばってん、それじゃ資金ば出してくださったお殿さまが黙っておられんじゃろ」
「赤松社は、あくまでも、士族の皆さんのもんちいう建前は崩さんでいくち。そこで、俺に、かすり部門ば引き取れち。貸すちいう建前でですね」
庄兵衛の口元がますます緩む。
「どうしたと、親父さん。この話はそげん喜ぶことじゃなかろうが」
「何ば言いよるか。この日のために、お前ば赤松社に出したとじゃなかか。お殿さまがお金ば出しなさって、ご家来の絵描きさんが発案なさった立派な織物ば、今度は庄平が引き継ぐとたい。機械も足らんならこっちで増やせばよか。喜次郎のところに負けんくらいの規模にない。三谷さんには、喜んで引き受けますと言え」
明治25(1892)年7月、赤松社は臨時士族総代会を開いて、織物業に限って本村商店に引き継がせる(賃貸契約)ことを決議した。引き受けた庄平は、工場の名称を「赤松社絣織物工場」とし、織り上がるかすりの商標は、「赤松絣」をそのまま使用することにした。良質のかすりとして世間に名の通ったブランドを、最大限に活かすためである。
庄平はこの際、本村の店と工場を会社組織に変更した。明治29(1896)年10月24日、「絣織物工場」とは別に、「赤松社絣工場本村合資会社」を設立して庄平が社長に就いた。本村商店のかすりと縞の取扱高は、一挙に50万反に膨らみ、国武喜次郎を急追することになる。生産されたかすりの大半を東京・関西方面に送りだし、残りを九州圏内で販売した。
松屋VS魚喜
国武喜次郎が五十の坂を越える頃、明治30年代に入った久留米の町では、すっかり城下町の面影が消えていた。荘島町から松ヶ枝町にいたっては、倉田雲平の槌屋足袋店(現ムーンスター)や国武喜次郎と本村庄平のかすり・縞・白木綿(しらもめん)工場などがひしめき、一大工業地帯の様相を呈している。中でも、白山(しらやま)に建ち並ぶ国武合名会社の工場群は、その規模において群を抜いた。町民はそこを「国武丁(町)」と呼んだ。現在、西鉄バス停留所の「縄手(なわて)」あたりである。

国武第一工場
商業の中心をなす三本松や苧扱川(おこんがわ)(現本町)周辺も様変わりが激しい。加えてこの頃には、「集産場」なる店舗が目を引くようになった。集産場とは、明治10年代から全国的に始まった大型店舗のことで、現在でいう専門店を取り込んだスーパーマーケットみたいなもの。三本松町の集産場内には、呉服・洋品・雑貨・金物・小間物・下駄・陶磁器など30種類ほどの店が連なった。
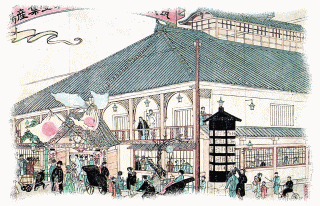
久留米市三本松の集産場
商都久留米を象徴する通町では、従来からの木綿問屋に加え、川崎峰次郎の籃(らん)胎(たい)漆器(しっき)や和傘商の豊後屋なども加わり、町内は一日中ごった返した。中でも三丁目の松屋(本村商店)と五丁目の魚喜(国武商店)では、筑後一円から仕入れにやって来る小売業者や一般客を呼び込む声が一日中響き渡り、賑やかな町をいっそう掻き立てた。
今では増吉を国武商店の客として扱う店員はいない。彼もまた慣れたもので、喜次郎の在宅を確かめると、さっさと棟続きの本宅に向かった。喜次郎が妻のたつえと向き合ったまま沈黙している。
「どうしたんや、喜次郎はんらしゅうもないな。どなかお葬式でもありましたんかいな」
「そげなこつじゃなかです。何でもありまっせん」
増吉の来訪で気を取り直した喜次郎が背中を伸ばした。
「何でもないことがおますかいな。わてはカネ以外の願いごとなら、愚痴でも何でもいくらでも聞きまっせ」
「ご維新以来走り放しだったもんで、ちょっとばかりくたびれてきたとですかね」
喜次郎が増吉に向かって話し出したところで、たつえが茶を入れに立ちあがった。
「何か一つ、身が入らんとですよ、商いに。かすりば売っておって、俺は心の底から買い手の立場を考えておるじゃろか、ち」
「近江あきんどの心得・三ヵ条のことですかいな。『売り手良し、買い手良し、世間もまた良し』という」
「売り手の方は、こげん儲けさせてもろうたとじゃけん、これ以上の贅沢は言えまっせん」
「買い手もよろしゅうおますやろ。紆余曲折はあっても、お客はんからの信用もとり戻して。だとすると・・・」
喜次郎の目が宙をさまようのを、増吉は見て見ぬふりをした。
「そげんです。俺は世間さまに対して、まともな商いばしてきたじゃろうかと」
「おまんは、誰にも負けんくらい税金を納めてますやろ。だとすると・・・」
たつえが戻ってきて茶を差し出すと、喜次郎が話題を替えた。
「ところで、増吉さんの金物屋の方はどげんですか」
「わての方は、ぼちぼち売れて食うていければ、それ以上何も欲しいもんはおまへんよって。店は武治に任せて、あっちこっち行ったり来たりですわ。昨日も高良山に登ってきましたで。拝殿の前から見下ろす景色はいつ見てもよろしいな。悠然と流れる筑後川には、久留米の街並みがよう似合うとります。水天宮はんもお城もな。やっぱり、久留米に落ち着いてよかったわ」
喜次郎に会うたびに、増吉は同じ言葉を繰り返している。
1.gif)
国武会社と自宅があった通町五丁目あたり
「そんなことより、どないしましたんや喜次郎はん。あきんどのお手本みたいなおまんが、ため息は似合いまへんで」
「五十(歳)の坂ば越えたとですよ、俺の年齢(とし)はもう」
「先ほどの、世間さまへのご奉仕のことでんな」
「そげんです。俺は世間さまに対してどのくらい役に立っておるかと」
増吉が、冷めかけた茶を啜(すす)ったところで、また二人の間に沈黙の間ができた。
「真面目なお人でんな、喜次郎はんは。おまんの売り物はかすりと縞織物ですやろ。久留米絣の技術を考えはったんは・・・」
増吉の言葉で、瞑(つぶ)りがちだった喜次郎の目が開いた。
お傳の残影
同業組合の事務所には、今日も本村庄平や松井儀平、秋山松次郎、湯浅易平ら面々が顔を揃えている。彼らが集まるとまず、日清戦争(1894~95年)後の景気のよい話が先行した。
「日本が戦争に勝ったお陰で、わがどん(自分たち)までが、朝鮮とか大陸(中国)で商いがでくるごつなったけんない。久留米絣と久留米縞は生産が追いつかんで困っとるたい。それに、白木綿(しろもめん)も・・・」
庄平の言うとおり、久留米絣・縞の生産高は順調に推移している。そんな時、長老格の喜次郎が小声で言葉を挟んだ。
「久留米のかすり屋も、このまんまじゃ先行きが危なかち思うとたい。下手するとまた、20年前の地獄ば見ることになるかもしれん」
喜次郎の一言で笑い声が消えた。20年前の地獄とは、西南戦争後の粗悪品の販売で、久留米商人の信用が地に落ちたあの一件のこと。
「ちょっとばかりかすりとか縞が売れるからちいうて、調子に乗っておったら、必ずその先に落とし穴がある・・・」
喜次郎の問いかけに、盛り上がりっ放しだった会話が急降下することに。
「ここで、お傳さんのこつば考えんとない」
突然喜次郎の口から飛び出した過去の話に、一同の表情が更に硬くなった。「お傳さん」とは、江戸末期に久留米絣の手法を考案した井上傳のことである。沈んだ雰囲気の中で、喜次郎が話を続けた。
「俺たちは売ることにばかり気を取られておって、久留米絣の本当の良さば世間さまに示さんままできてしもうた。時間だけ経つうちに、大恩人の傳さんの曾孫(ひまご)が食うに困っとることにも気がつかんじゃった」
「曾孫ちは?」
庄平も、未だ喜次郎が何を語ろうとしているのか図りかねている。
「川島猪之助さんとこで下働きばしとる久吉のことたい」
「久吉なら、俺も川島社で話ばしたこつがあるばい。母親のトモさん(傳の孫娘)が死になさって機屋ば畳んだげなない。ばってん、もう一度建て直したかち、久吉は言いよった」
「食うに困っとるだけじゃなかったのか、久吉は」
松井儀平が、腕組みをしたままで喜次郎に向いた。
「お傳さんだけじゃのうて、猪之助さんの祖父(じい)さん(大塚太蔵)や牛島さんの祖母(ばあ)さん(牛島ノシ)のこつも忘れちゃいかんとたい。二人とも、商売もんの絵がすりとか小がすりば創ってくれた大恩人じゃけんな」
事務員が運んできた茶を啜りながら、一同の沈黙がしばらく続いた。
「鍋屋の増吉さんに聞いたとばってん。近江のあきんどは、ご先祖さんの恩ば絶対に忘れんち。ご先祖さんは、うみ(琵琶湖)の周りにある泥とか草とかから売りもんばつくりだし、それば日本中に売って回った。商いの神さまみたいなもんじゃけな」
「ああ、麻布だとか畳表、薬草、それに釣鐘(つりがね)、屋根瓦(やねがわら)までもない」
松井儀平が相槌を打つ。
.gif)
井上傳銅像(久留米市寺町)
「魚喜さんの言う、久留米のかすり屋が忘れちゃいかんこつとは?」
問い質すのは易平である。
「先達の恩ば忘れたとき、商いの衰退が始まるち」
「・・・・・・」
「組合で、お傳さんの三十回祭ばやったらどげんかち思うて」
「三十回祭ばかい?」
「そうたい、三十回祭ばたい。それも、お傳さんの供養だけじゃのうて、この機会にもう一度久留米絣ちいうもんば、見直してみたらどげんかち思うて」
今や、日本でも指折りのかすり販売業者になった国武喜次郎からの提案である。庄平も、喜次郎の言うことに、素直にうなずいた。

|

