|
販路拡大
「待っとりました、田辺さん」
国武喜次郎は、長崎の外国人居留地近くに宿をとって、丸2日間田辺為三郎を待った。喜次郎、42歳である。

現在の長崎港桟橋
「いやいや、遅うなって申し訳ありまへん。岡山からここまでたどり着くのに、時間の計算を間違えてしまいまして」
田辺は玉島紡績所の支配人である。時は明治21(1888)年春、取締役の喜次郎と二人連れで、上海まで綿花の買い付けに出かけるところであった。
玉島紡績会社は新政府の保護のもとに設立されたもの。だが、後に設立された大阪紡績会社の方が、更に先を行くイギリス製紡績機を導入した。その規模は、玉島の10倍、1万錘にまで進化している。日本で初めて電灯による夜間操業を遂行することで、昼夜2交代のフル操業を成し遂げたのも大阪紡績だった。間もなく、摂津紡績(せっつぼうせき)や鐘淵紡績(かねがふちぼうせき)など大規模紡績会社も操業を開始する予定である。
田辺らにとっては、後進大規模工場に遅れを取らないための、原料(綿花)買い付けの旅であった。
「さすがにここは長崎ですな。赤毛の外国人が多いこと。我々も、ぐずぐずしておられまへん」
田辺は、宿まで歩いてくる間に、何人もの西洋人らしい大男と出会ったことを話した。
「支配人も西洋人なぞに負けてはおりまっせんばい。そげんハイカラなきもん(着物)ば着なさって」
「これは西洋人が着る服です。これから海を渡り、現地人や西洋人と商談しようというときに、革のカッパに三度笠でもおまへんやろ」
言われて喜次郎は、自分の身なりを振り返る。
「ばってん、俺はこれしか持っとらん」
「国武さん、ここをどこだと思うてますの。長崎ですよ。文明開化の震源地だよ。どこぞにテーラーくらいありますやろ」
上海行きの船が出る桟橋は、宿から目と鼻の先のところにあった。喜次郎は、新調の洋服と帽子、それに革の靴を履いて桟橋に向かった。
乗り込んだのは、日本郵船の定期上海航路である。喜次郎が上海渡航を決意したのは、田辺に誘われてのこともあるが、他に大きな目的を持っていた。これまで、日本国内でしか販売してこなかった久留米絣(くるめがすり)と久留米縞(くるめじま)を大陸にまで広げる魂胆(こんたん)である。
中国大陸、とりわけ世界中の商人や政府関係者が集う上海は、喜次郎にとっても憧(あこが)れの市場である。この時の旅行で、喜次郎は上海のほかに寧波(ニンポー=中国浙江省の沿海港湾都市。遣唐使の時代から日中交通の要地であった)や漢口(カンコウ=中国湖北省東部の都市)なども回って、更なる販路拡大を果たしている。そのことが、久留米絣の年間生産量を100万反の大台に押し上げる要因ともなった。

籃胎漆器
喜次郎が久留米絣の販路を中国大陸に求めた明治20年代。久留米の町では、新しい商いの芽が次々に吹き出ていた。西南戦争後の商いで失敗したことを教訓にして再出発した倉田雲平が、本業の足袋製造に加えて革靴と馬具の製造を開始したのもこの頃である。それは、生活様式の近代化を先取りする試行であった。
通町三丁目で漆器具店を営む川崎峰次郎は、自ら開発した籠細工塗(かございくぬり)(後に藍胎漆器(らんたいしっき)と命名)を売りだした(明治21年)。材料は、筑後地方に繁茂する真竹である。これを薄くて細長い籤(ひご)に割り、用途に応じて編み上げたものに漆を塗り重ねる。熱湯にも強く、酸やアルカリなどの薬品がかかっても塗料や材料を損なう心配はない。しかも使いこなすほどに光沢を増すというから、これ以上の実用的な工芸品はなかった。
久留米絣や藍胎漆器と並び称される「久留米つつじ」が世に知られたのもこの時代である。天保年間に、久留米藩士の趣味が高じて生まれた新種を、更に進化させたつつじの品種である。その後明治維新を経て、広又(現久留米市東町)の庄屋の息子・赤司喜次郎が品種改良を重ねて、大阪の市場で認められた。数百種の花弁と多彩な色合いが特徴で、今日では全国の公園や街路樹、家庭の花壇にまで植えられるようになっている。
近江商人根付く
明治22(1889)年は、大日本帝国憲法が公布され、総選挙など今日に繋(つな)がる国の重大な制度が大きく動いた年である。
久留米地方でも、忘れられない出来事が多かった。福岡と並んで全国で最初に市制が敷かれ、「久留米市」が誕生した年である。当時の人口は2万4000人であったと記録されている。
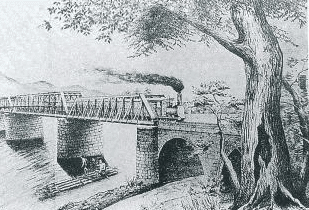
九州鉄道第1号車筑後川を渡るの図
鉄橋の下を筏が通過している
時を合わせるように、博多と久留米間に鉄道(九州鉄道)が開通した。博多まで片道わずか1時間20分で行けるようになった。明治22(1889)年を境にして、久留米はかすり産業を柱とした近代的地方都市の中核へと大きく舵を切ることになったのである。
更に、明治22年は、災害ということでも歴史に残る。降り続いた大雨で筑後川や矢部川などが氾濫し、流域の農民には、筆舌に尽くせない被害をもたらせた。
この時期喜次郎は、需要の急速な伸びに追いつくため、裏町(現松ヶ枝町)に新たな工場を建設するなど、規模の拡張も止まることはなかった。
「いま帰ったぞ」
喜次郎が玉島紡績の役員会から戻ると、奥から番頭の久次が飛び出してきた。
「待っとらしたですよ!」
久治の興奮した様子で、訪問者の見当がついた。
「どうしたとですか、突然に・・・」
鍋屋の増吉であった。
「突然ということもおまへんやろ、わては近江の行商人どっせ。いつ何時、どこに現れても、何の不思議もおまへん」
「そうでした。それで、この度の商いは・・・?」
「商いとは違いますねん、今回は。喜次郎はんに折り入って相談が・・・」
こちらから相談することはあっても、増吉の方からとは珍しいことである。
「わてもそろそろ還暦を迎えますやろ。天秤(てんびん)担いでの野越え山越えが少々きつうなりましてな」
こんな弱音を吐く増吉を、かつてみたことがなかった。
「増吉さんも、いよいよ近江の地に落ち着きなさるとですか」
「それが、そうもいきまへんのや。年中諸国を巡っているうちに、実は、己の死に場所すら分からなくなりましてな」
「・・・・・・?」
「行商人という奴は、年齢(とし)を重ねる度に侘(わび)しさが身に沁(し)みるもんどす。そこで、旅をしながら考えたことだが・・・」
「どこですか、決めなさった落ち着き場所とは?」
「実は・・・、次郎はんに誘われましてな」
「次郎さん?」
「そうどす。筑紫の次郎はんどす。ここに住め言うてくれましたんや」
増吉が言う「次郎はん」とは、筑後川の愛称である。
「筑後川のどこが?」と質そうとする前に、増吉が答えてしまった。
「筑後川には、温(ぬく)もりがおます」
「川に温(ぬく)もり・・・?」
「皆はんが、懸命に温めておいでやすさかいな。お殿さまからお武家はんまで。それからお百姓も、町民も。みんなして次郎はんを家族のように大切にしてきましたやろ。だから、わての死に場所も、皆はんに好かれた筑後川のほとりをお借りしよう思いましたんや。何と言うても、あの川は喜次郎はんと初めに会うたとこでもありますよって」
増吉の話しを聞くうちに、喜次郎の目が潤んできた。

高良山から見下ろす筑後川と久留米市街
「ばってん、増吉さんには奥さんも子供さんもおらすとでっしょ。久留米でよかとですか」
喜次郎が一番気になっていることだった。
「いつぞやそんなことも言いましたかいな。そうとでも言わなきゃ、自分が惨めやさかいな。わてみたいな風来坊に、女房とか子供なんぞおますかいな。立ち止まった先が住み家どす。袖振れ合うたおなごはんが女房どす。わてが久留米に居座ったからいうて、困るもんなぞどこにもおまへん」
鍋屋の増吉が、未だ一度も見せたことのない情けない表情である。
「増吉さん、そうと決まれば、ぜひ国武合名会社の相談役になってくれんですか。何年も前から言おう言おう思うとって、今まで言えんかったことですけん。まだまだ、俺一人では難しかこつが多過ぎて」
日頃、こんな日が来ることを夢見てきた喜次郎には、渡りに舟の心境であった。
「そりゃあきまへん。わてはこう見えても近江商人の端くれどす。腐っても鯛とまでは言わんけど、自尊心とかいう名の厄介な虫が、体の中に棲みついてますのや。幸い本店の大将から暖簾(のれん)分けを許してもらいましたよって。久留米の町の片隅でもお借りして、鍋屋の看板を揚げさせてもらおう思うてます」
会社の相談役にと考えてきた喜次郎は、見事に肩透かしを食った。
内国勧業博覧会
久留米の地に落ち着いた増吉は、三本松の賑やかな通りに「鍋屋」の看板を掲げた。売り物の金物が近江の本店から潤沢に運び込まれることもあって、開店以来そこそこの繁盛振りである。雇い入れた武治がよく働くため、増吉は2日と空けずに国武商店にやってこれる。
今日も国武の店に現れた増吉。
「黙って鍋とか釜を売っておればそれでええのに。身についた地獄耳はすぐには元に戻りまへんな」

昭和7年の久留米市街
笑いながら、今度は東京上野で開催される内国勧業博覧会の情報を持ってきた。内国勧業博覧会とは、新政府が明治10(1877)年から開催している、殖産興業のための博覧会である。
「今度は3度目やそうやけど、喜次郎はんも久留米のかすりを引っ提げて参加してきなはれ。そこで、日本中のあきんどの働きようを観察しますのや。それから、ついでに東京の問屋を回りはったらええ。魚喜はんが、日本中を売り場にしていく正念場やさかいな」
増吉のあきんど魂は、ここに来てもまったく衰えをみせていなかった。博覧会への出がけに、「これを」と言いながら何通もの手紙を持たせた。東京の知り合いの店に当てた紹介状であった。
時は明治23(1890)年の春。44歳の国武喜次郎が、岡茂平などかすり業界の主なメンバーを従えて、紋付袴姿で上野公園内の博覧会会場にいた。久次も一緒である。
13万2千平方メートルの会場いっぱいに、万国旗と提灯が張り巡らされ、建物も和洋折衷で賑やかなこと。陳列館は、農林館・水産館・機械館など。動物館や美術館など、現在まで継続している施設も数多くみられる。出品した人数7万7千人、出品点数16万点。入場者数は実に100万人に達したという。
中でも、喜次郎らが注目したのは、久留米絣に共通する織物と織機類の展示場であった。
「すごかない、東京の博覧会ちは」
会場をひと通り観て回った後、喜次郎や久次の感想は「驚嘆」の連続であった。
「俺たちは、久留米しか知らん井の中の蛙じゃな」
喜次郎は、己の知識の浅さを嘆いてみせた。
「織機も紡績糸も、年々便利なもんに変わっとる」
喜次郎にとって生まれてはじめて足を踏み入れた東京は、見るもの触るもの、ただ珍しさの連続であった。
その夜、会場近くの旅館に戻った喜次郎と久次は、興奮が醒めずなかなか寝付けなかった。
「あのう」
入り口の襖を少し開けて、覗き込んでいる者がいる。声の主に心当たりはなかった。
「見たところまだ子供のごたるが、どげんしたと」
喜次郎が部屋に招き入れて、事情を訊いた。
「博覧会ば見に、おとっさ(父親)と一緒にきんの(昨日)から来ております。おじさ(おじさん)たちの話がおもろうて、まぜてくりょう(加えてもらおう)思うて」
少年は、遠江国(とおとうみのくに)(現静岡県西部)から出てきたのだと言う。
「それで、お前のおとっちゃんはどげんしたと」
「そこらへんで酒飲んで来る言うて出ていきました。おらも、昼間の博覧会で見た外国や日本の機械のことが頭にこびりついて、眠れんのです。それに・・・」
「俺の声が喧(やかま)しいからか」
久次が少年の言葉を先取りして謝った。
「お前の年齢(とし)は十五か十六か。そげん若うして、どうして・・・」
喜次郎は、余りにも若い少年が、博覧会に興味を持ったことが不思議だった。
「おとっさ(父親)が大工なもんで。おら(俺)も道具とか機械とかいかいもん(大きい)から細けえもんまで、せせくったり(いじったり)、こさえ(作る)たりするのが面白うて。そのうち、布(きれ)ば織る機械ば造ろう思うとります」
喜次郎も久次も、まじめくさって話す少年の本気度を測るのに苦労した。
「若いお前が、どうしてまたはた織り機械てん・・・」
「おっかさ(母親)が、たったの1反織るのに4日も5日もかかって、おとましい(辛い)そうじゃもん。だで(だから)、織る時間がはんぺた(半分)以下でできんもんかと。そしたら、他のことをしがつら(しながら)はた織りがでくるようになるじゃろう思うて」
喜次郎と久次は、少年の田舎訛りがきつ過ぎて、何度も聞き直しながら納得した。
「親孝行たいね、お前は」
「おっかさのことだけじゃのうて、うちん村はみいんなひんしょって(貧乏しとって)。もっとおあし(お金)ば稼ぐ機械さ作って、村のためにならにゃち」
「へえ、若っかもんに似合わず、村のこつまで・・・」
久次がしきりに感心している。
「これは、おとっさから、おんし(お前)はそうしろち教えてもろうたことじゃ。そんで、はだって(わざわざ)はんまつ(浜松)から博覧会に連れてきて、うらっぽ(先端)の技ば見せてもろうたわけじゃ」
久次がおどけたような調子で、少年に念を押した。
「俺は、お前が作った木綿ば織る機械ば早う見たか」
「でくるもんかどうかはわからんが、おらは次の勧業博覧会に出そう(展示)思うとる。そん時は、見てくれ」
少年は、照れくさそうな笑みを残して、自分の部屋に戻っていった。
東京市場
博覧会での久留米かすりは、予想を超えた評判だった。気を良くした喜次郎は、久次を伴って上野からほど近い日本橋に出向いた。道行く人を掻きわけながら進んだ先に、目指す越後屋(現三越)があった。遥か西方に富士の霊峰が霞んで見える。
越後屋では広い店先を丁稚(でっち)が走り回り、手代が上品そうな女の客を相手に商談中。
「店のもんは、男ばっかりですね」
店内のざわめきに圧倒されている喜次郎に、久次が話しかけた。
「そう言われれば・・・」
その時、目の前に三十半ばの前掛け姿の男が立った。男はこの店の番頭だった。
「・・・気がつきなさったか。この店には女は一人もいません。男ばかり500人ほどが働いとるのです」
出遅れた気持ちの喜次郎が、慌てて立ちあがった。番頭は、二人を愛想よく奥の応接室に案内した。
「近江の鶴屋さんからも、魚喜さんのことをよろしゅうと、郵便で言ってきましたよ」
増吉が鶴屋に連絡したのだろう。
「呉服屋さんと聞いたもんで、絹織物だけのお店かち思うとりましたら・・・」
喜次郎が、遠慮がちに質した。
「そんなことはないですよ。徳川さまの時代から、うちでは儲かるものなら何でも売っております。200年前に先祖が伊勢から江戸に出てきて以来、それが私どもの商いのありようでして」
横山光太郎と名乗る番頭は、苦笑しながら喜次郎らに説明した。
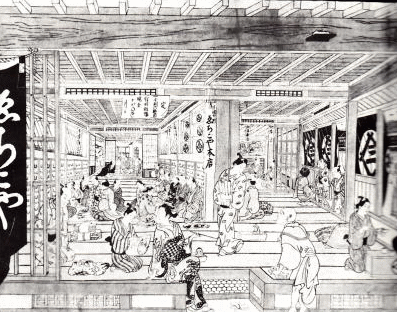
駿河町越後屋の店内
「博覧会では、久留米絣が大そう評判を呼んでいるそうですな。私も一度見物に行こうと思うとるんですが、まだ・・・」
「お陰さんで、久留米のかすりも、少しは世間さまに認めてもらえるごつなりました。ばってん、まだまだしれたもん(大したことではない)ですけん」
あらゆる面で東京の規模の大きさに圧倒されている喜次郎は、久留米商人の底の浅さを見抜かれているような気がして、落ち着かなかった。

小川トク
「かすりもいいですがね、東京のお客さんには、縞織物が喜ばれるんですよ。特にね、維新以前から流行ってます弁慶縞や子持縞なんぞには、ご婦人方が大そうご執心ですわ」
言われて喜次郎は、小川トクのことを思い出した。
「久留米でも縞織りが盛んになっとります。久留米藩の江戸屋敷に奉公していた女が、百姓の嫁や娘たちに教えたのが始まりで・・・」
「ほほう、江戸にいらしたご婦人がね。どんなお方です?」
「小川トクさんちいいます。武蔵国の宮ヶ谷塔(みやがやとう)ちいう所の出らしかです。こまか時(幼い時)からはた織りが好きで、江戸では、縞柄の流行(はや)り具合ば観察しておったそうです」
「宮ヶ谷塔なら、ここから10里足らずのところですよ。むかしから縞織りが盛んな場所です。江戸にいらして、更に久留米で腕を磨きなさったのなら、さぞ立派な物ができておりますでしょう」
横山は、すぐにでも見本を送るよう注文をつけた。
「ところで・・・」
喜次郎が、本題のかすりの商談に戻ろうとすると、横山が素早く話を引き取った。
「わかっていますよ、魚喜さん。久留米のかすりをうちの店で扱ってほしいんでしょ。鶴屋さんからの手紙にもそう書いてありましたから。私ども越後屋の先祖は、江戸幕府ができてすぐに、ここで呉服屋を開いた老舗中の老舗です。越後屋を知らない者なんぞ、この広い東京にはただの一人もいませんから。鶴屋さんが後ろ盾なら、久留米絣をしっかり売らしてもらいます。ですが・・・」
「はあ?」
「私どもの店では、ずっと以前から掛け売りはいっさいせず、固い商いを通しています。従って、扱う売り物にも大そう神経を使うとるんです。現金でお売りした品物にもしも不具合でもあったら、培ってきた店の信用が台無しになりますからね。魚喜さんの持ち込まれるものだから、万一にも間違いはないでしょうが」
「それはもう・・・」
胸を張ってはみたものの、西南戦争後の久留米商人の信用失墜を目の前の番頭が知らないはずはないし、腋(わき)の下に冷や汗が染み出す思いだった。
「言葉だけで、はいそうですかというわけにはいかないのが、私らの商いのやりようでしてね、魚喜さん」
言葉つきは丁寧でも、商談の際の番頭の言葉は歯切れがよく、田舎者の商売人には一分の隙(すき)も見せてくれない。
「そげなこつならようわかっとるつもりです。久留米んかすりば越後屋さんで扱うてもらうだけで本望ですけん。儲けは二の次、三の次です」
喜次郎の方から、売れた分だけを後から送金してもらう「委託販売」を提案した。もちろん、「商品に不都合があれば、無条件で引き取らせてもらいます」といった1反ごとに保証をつけることも合わせて申し入れた。「それなら」ということで、商談が成立した。
久次を促して立ち上がろうとするとき、横山が呼びとめた。
「魚喜さん、先ほどの縞織物の話ですがね」
番頭にとって、かすりのことより縞織物の方によほどの関心があるらしい。
「川越や岩槻なんぞの生産だけでは、この広い東京では間に合わんのです。よろしく頼みますよ、縞織物の方も」
喜次郎と久次は越後屋を後にして、次なる問屋を訪ねた。綿布とか麻布を扱う神田の播磨屋(はりまや)である。ここでも、鍋屋の紹介状が効いて、主人勘左衛門の丁寧な応対を受けることになった。
「よござんす、私も男だ。魚喜さんのためにひと肌脱ぎましょう」
勘左衛門は、久留米絣の大量仕入れと、未開の販路である奥州(東北)や北海道の問屋に宛てた紹介状を書いてくれた。
奥州-北海道
「久次、これからがお前の出番たい」
昨夜と同じ不忍池近くの旅館に落ち着いた喜次郎は、久次に大きな仕事を与えた。播磨屋に紹介された、奥州と北海道への販路拡大の任務を言い渡したのである。一瞬不安げな表情を見せる久次を、喜次郎が睨みつけた。
「俺は、久次が大そうなあきんどになる男と見込んどるけん」
「そげなこつはなかですよ、大将。自分は肝っ玉の細か男です」
突然振られた大仕事に、久次の頭が判断能力を失いかけている。
「なんば言いよるか、久次。西南の役のとき、南ノ関の寺で、兵隊たちにかすりと国武の店ば売り込んどったお前ば忘れんぞ。今の国武があるのも、文句ひとつ言わんで店ば守ってくれた久次のお陰たい。今度の仕事ばやり切れたら、ひょっとしたらお前は、俺を追いこすあきんどになっとるかもしれん」
このときの久次への激励は、喜次郎の本音であった。喜次郎らが九州に向けて帰路に就いたその時、久次は草鞋(わらじ)の紐(ひも)を締めなおして北に向かっていた。福島から仙台~青森へと、青森からは青函航路に乗って函館へ。札幌-小樽を経て、千島(サハリン)に渡るおおよそ半年間の長旅であった。行き先々で久留米のかすりを売りこみ、やっと久留米にたどり着いたのは、その年の秋も深まろうとする時期であった。
奥州から北海道を回って帰ってきた久次は、更に忙しくなった。東京・奥州などでの商売が急速に膨らみ、喜次郎が動けない分、久次が補うことになるからである。小川トクと縞織の図柄を相談したり、従業員に遠方への荷の積み出しを指示したりで休む暇もない。更に、東京の越後屋や播磨屋にも年に2~3度は顔を出して、先方の意見や苦情を聞かなければならない。
東京から帰ってきた久次が、喜次郎に旅の報告を追加した。
「帰り道、勧業博覧会の時のあの小僧に会うたとです。浜名湖近くの家に寄ってですね。もう、立派な大人になっとらしたですよ」
「上野の旅館で突然部屋に入ってきた、あの・・・」
「あん時、みんながびっくりするごたる織り機ば作ってみせるち大口叩いたあの・・・」
「あのガキが、新しか織り機ば作ったか」
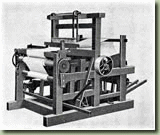
豊田式木鉄混製動力織機
聞いている喜次郎が、身を乗り出している。
「ほんなこつ、びっくりする発明ですよ」
「へえ、あいつがね。それで・・・」
「上野の旅館で言っておったことが、まんざらホラじゃなかったとです。人間の手の代わりばする機械ば作るち。未完成の機械ば見せてもらいました」
「そりゃいったい、どげな・・・」
「筬框(おさわく)ば、片手で前と後に動かすだけで、杼ば飛ばすのと緯糸ば締め付けるのがいっぺんにでくる機械ですよ。あん人が言うには、完成すれば、今までと比べて4~5割方能率が上がるじゃろうち」
喜次郎の目が、久次の口元から離れなくなった。
「『木製人力織機』ち名前ばつけて、来年の博覧会に出すげなです」
「わざわざ『木製』ちつけんでも・・・」
「『木製』ち言うことで、次は金属ですよと皆んなに期待ば持たせるためらしかですよ。早う金属製にせんと、機械そのものが強うならんち。それから、機械ば全部自動で動かさなきゃいかんちも」
「自動にない。紡績機械のごつ蒸気で織り機ば動かして、綿布ば織るちか」
「そうです。あの人は、次の次の博覧会までには、その機械ば発明してみせるち張りきっとりました」
明治23年の内国勧業博覧会は、国武合名会社とくるめんあきんどに、有形無形の大きな財産を提供してくれたのであった。

|

