|
殿の士族授産
庄平が、いつもながらに、養父の庄兵衛と口論を繰り返している。
「親父さん、店がこげん難儀しとる時に、ちっとは(少しは)心配してくれてもよかでっしょもん」
庄平が愚痴(ぐち)るように、最近の庄兵衛は、店のことになるとまるで他人事(ひとごと)である。朝起きればすぐ庭に出て盆栽いじり。元藩士やあきんど仲間でつつじの交配が流行(はや)っているとかで、すっかりはまり込んでいる。いつどこから出て行くのか、昼間に家にいることは滅多にない。あれほど庄平の商いに注文をつけていたものが、ここのところ見て見ぬ振りばかりである。一々口を出されるのも煩(わずら)わしいが、まったく無頓着(むとんちゃく)なのもおもしろくない庄平である。
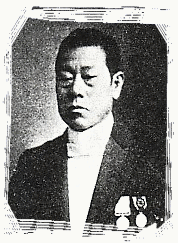
本村庄平
「何ば言いよるか、歳の三十にもなって、いつまでも親に甘ゆるもんじゃなか」
言われてみれば、庄平も来年は30歳を迎える。25歳で正式に伯父庄兵衛の婿養子に組み込まれてから、店の采配をすべて任されるようになった。二男一女にも恵まれて申し分はない。今も、これからのかすり販売について相談しようとしている矢先だが、養父は「一人前の大人なら、そんくらい自分で考えろ」と素っ気ない。
「魚喜(喜次郎の屋号)の扱い高は桁外れに大きゅうなったのに、親方格のうち(本村商店)は伸び悩んだままたい」
幼い頃から養父の店で商人修業を積んできた庄平には、魚喜の景気の良さばかりが目について、イライラも積もるばかりである。
「喜次郎さんは、親父さんの口添えで、お傳さんから版木(はんぎ)ば貰うたち聞いたばってん。本来なら、松屋(本村商店)が持つべき版木が魚喜に行ったお陰で、お傳さんの久留米絣も向うにいってしもうた。取り返せんもんかね」
「そげな情けなかこつば言うもんじゃなか」
養子の泣き言を叱っている庄兵衛だが、庄平の言うことも分からないではない。
「親父さんも知っとろうばってん、上方の問屋が魚喜のことば、『関西の機業王(きぎょうおう)』ち言いよるげなばい」
機業王とは、織物を生産する事業主の中でも特別な存在のこと。
「ほう、機業王ない。あいつも偉うなったもんたいね」
「いくら喜次郎さんが弟子同然ちゅうても、褒めすぎじゃなかね」
庄平の養父への不満は根深いものだと、庄兵衛は苦笑する。頃合いを見て、養子に話しかけた。
「話は変わるばってん、庄平。この頃東京におられるお殿さま(有馬頼咸(ありまよりしげ))が、ご家老の織部(おりべ)さまに手紙ば寄こしなさったことは知っとるね」
有馬織部(ありまおりべ)といえば、藩政時代には有馬主膳に次ぐ重鎮家老だった人物。
「話ばはぐらかさんでよ、親父さん」
「馬鹿たれ、関係あるから言うとるとたい」
「お殿さまとうちの商売と、どげな関係があるとですか。お殿さまがご家老さまに、何ば言いなさったか知らんばってん」
「そげなこつも知らんで、よう久留米であきんど面ができとるな」
口を開けば、息子への嫌みを忘れない。そこを我慢するのも養子の務めと考える庄平は、決まって口を閉ざすことに。
「お殿さまは、ご維新(いっしん)後の家臣にちいうて、2万5000円もの大金ば出しなさるげな」
「どうして、また」
「士族授産のための基金げな。確かに、この頃のお侍さん方は貧乏ばしとらすもんない」
維新後の士族は、家禄の代わりに金禄公債を受けたが、それもこのところの物価の値上がりで紙切れ同然になっている。士族授産とは、武士の資格をはく奪されて暮らしに困っている士族に、仕事を与えて援けることをいう。

十一代藩主有馬頼咸
旧久留米藩主の有馬頼咸(ありまよりしげ)は、基金を出すにあたって、「その事業は、地方産業の振興にも貢献できること。また、基金の使途を短命に終らせてはならない」等の注文をつけた。
手紙を貰った旧重臣たちは、連日連夜協議を重ねるが、なかなか殿の意を満たす案が浮かばない。結果、男は和傘の組み立て、女にはかすりを織らせることで落ちついた。
「そこでだ、庄平」
養父に改めて顔を向けられると、今でも全身に緊張が走る。
「何ごとですな、親父さん」
「実は株仲間から頼まれたとばってん、その授産施設のことでお武家さんの相談相手になってくれ」
今は平民との身分的差が縮まったとはいえ、明治維新までは、まったく異なった世界にいた武士群である。相談相手になれと言われても困惑の方が先にたつ。
「俺に、何ばしろち・・・」
「武家の奥方がかすり織りばなさるのに、機械や道具ば揃えてやったり、織り方ば教えたり・・・」
「そげなこつなら、他のもんでもよかろうもん」
息子の反応に、憮然とする庄兵衛。
「わからん奴じゃな。お前が、魚喜の喜次郎に差ばつけられとるのが悔しかち言うけん、腕試しに大仕事ばやらしてみようち思うたとに」
「腕試し」と聞かされたが、庄平が養父の本意を理解するまでには、しばらくの時間を要することになる。
絵師の下心
庄平は、外堀の向こうの旧武家屋敷に出向いた。現在裁判所などが建ち並ぶあたりである。そこは空き家で、留守番らしい爺さんが裏庭に案内した。しばらくして現れたのは、歳の頃なら五十がらみの色白の優男(やさおとこ)。
「お待たせしましたな、松屋さん」
その男、丁寧の頭に「バカ」がつくほどの声色(こわいろ)で話しかけてきた。身形(みなり)や仕種(しぐさ)からだけでは、町人なのか武士なのかさえ判断が難しい。
「維新まではお城の中にいましてね。襖(ふすま)や掛け軸の絵を描いていましたよ」
三谷有信と名乗る男は、聞きもしないのに維新前の身分まで明かした。三谷家は、江戸時代初期から続く久留米藩お抱えの絵師だったと言う。
「このお屋敷は、どなたの・・・」
「去年まで、名のあるご家来が住んでおられました。屋敷の広さは、800坪ですよ。お隣の屋敷も、またその向こうの空き地も、広さはだいたいそんなものです」

三谷有信
これまた、訊きもしない屋敷の広さを説明する三谷の意図が、もう一つわからない。
「ここ3軒の屋敷を壊して、一つにするのですよ」
「何のために?」
「作業場を建てるのです。お聞きでしょ、お殿さまからいただくお金で、貧乏な士族の暮らしを救おうとする計画のこと」
「そのことで、うちの親父(おやじ)から手伝えと言われとります」
「私はご家老の織部さまに、今度出来る施設の社長になれと言われているのです。施設では、和傘(かさ)を作ったりかすりを織って、それを商いにするのです。あなたには、かすりの方でいろいろ教えて欲しいのですよ。何しろ、私を含めて、皆さん商いや織物にはずぶの素人ばかりですからね、ホホホ」
言葉使いは丁寧でも、そこは永年武士の世界に生きてきただけあって、目は鋭く、あきんどごときに拒絶はさせないといった威圧を感じる。
「一つだけ訊いてもよかですか」
「一つと言わず、何なりとどうぞ」
「あなたは、どうしてこげな大変な仕事ば引き受けなさったとですか」
大量の人を雇って物を作らせ、それを売る。売り上げた金を管理し、働いた者に分配する。そんな仕事が、襖に向かって鳥獣や山水ばかりを描いてきた人間に、果たしてできるものなのか。
1.gif)
赤松社があった現検察庁あたり
「おかしいですか、絵描きが士族授産の仕事に関わることが」
「おかしかことはありまっせん。ばってん、よかならその理由(わけ)ば聞かせてください」
「絵描きだからやりたくなったのですよ、かすり織りの仕事を。かすりとは、藍草で糸を染めて、いろいろな絵柄や模様の織物を創り出すのでございましょう。見ていて飽きがこないじゃありませんか。こう見えても、私は絵柄を描く職人ですからね」
三谷が自分のことを「職人」と言ったことには、庄平も正直驚いた。
「でもですよ。生地も図柄も、もっと微妙なものがあってもいいと思うのですよ、私は」
三谷が突然話題を飛躍させた。
「はあ? かすりちはあげなもんと違いますか」
「もっともっと繊細な図柄が表せたら、幅広い人々の共感を呼ぶのじゃありませんか」
「どげんするとですか、そげな繊細な図柄の出し方ちは?」
「今使っているものより、もっともっと細い糸を使えませんかね。そこのところを、あなたに考えて欲しいのですよ」
とんでもない仕事が回ってきたものだ。親父さんは、三谷の真意をわかった上で、息子の自分に相談相手を命じたのだろうか。
「それはよかばってんですよ、三谷さま。言われるような細か糸で、かすりが織れるもんでっしょか。最近うちの工場に入れた織り機でも、そげな細か糸ば張ったらすぐに切れてしまいます」
「いませんかね、細糸を操れる職人さんは・・・。例えば、むかし微妙な図柄の絵がすりを織っていた大塚太蔵(おおつかたぞう)さんのような。武家の奥方に教える人さえいれば、細糸が通用する機械は私の方で何とか・・・」
「どこにあるとですか、そげな便利な機械が」
「先日県の勧業課を訪ねたのでございますよ。そこで小山改蔵とかおっしゃる課長さんから面白い話を聞きましてね」
「勧業課のですか。面白か話ちは?」
「その課長さん、東京に出張しての帰り道に名古屋の織物工場にお寄りになったそうでございますよ。そこで見た織機が、私が言う細い糸で木綿を織っておったと」
「ほう、それはすごかです」
庄平は、まだまだ知らない世界がこの世の中にあるもんだと感心した。
絵がすり創始者の孫
庄平が店に戻ると、養父の庄兵衛が来店中の青年と談笑中だった。
「こん人は川島社の大将ぞ」
どこかで会ったことがあるのだが思い出せない。
「津福村(現久留米市津福本町)で織屋ばしよらす川島猪之助しゃんたい。猪之助しゃんのかすり織りの腕は大したもんばい」
庄兵衛に持ち上げられて、猪之助は右の掌(てのひら)を左右に振った。
「そげなこつはなかです。何年たっても、祖父(じい)さんの腕には追いつけまっせん」
まんざら謙遜ばかりでもなさそうである。
「あんたとは、どっかで会うたような気がするばってん?」
思い出せないままだと気持ちが悪くて尋ねた。
「はい、小川トクさんのお店で」
「そうでした。トクさんの作業場で、熱心に高機(たかばた)ば見よらしたあん時の・・・」
トクの作業場で、高機の仕組みを食い入るように見ていた男だった。
.gif)
代表的な絵がすり(地場産くるめ)
「庄平も知っとろうばってん、こん人の祖父(じい)さんが織りなさった絵がすりは、大そうな評判ば呼んだもんたい。かれこれ50年もむかしのことになるばってん」
庄兵衛がまだ二十代(歳)の頃のことである。
「お傳さんのかすり織りがなかったら、うちの祖父(じい)さんの絵がすりもなかったろうち、父がよう言うとりました」
先ほどの三谷の言葉、「むかし微妙な図柄の絵がすりを織った大塚太蔵さんという人・・・」を思い出した。その大塚太蔵の孫が、奇(く)しくも目の前にいる。
「猪之助しゃんに相談があるとばってん」
突然相談と言われて、猪之助も慌てた。
「今までよりずっと細か糸ば使うて、複雑で目の覚(さ)むるごたるかすりば織ってみなさらんですか」
「どげなこつですな、細か糸ば使うてちは?」
「太か糸より細か糸ば使うて織った方が、柄はもっと複雑で上品なもんができるでっしょうもん? そげな細か糸で織る機械が、名古屋にあるげなですよ。今度篠山にでくる授産施設の社長さんが、その細か糸ば使うて織れる職人ば探しとらすとたい。名古屋に行って、そん機械ば見てきなさらんですか」
「見てきて、どげんするとですな」
「あんたにも、その授産工場ば手伝うてもらいたかとです。新しか機械で、もっと細か糸でかすりの織り方ば教えてほしかとです。お武家の奥方に」
「何で、わたしが?」
「大塚太蔵さんのお孫さんだからですよ。お祖父さんを超えるごたる絵がすりば織って、貧乏しとらす士族の奥さま方ば助けてやってくれんですか」
祖父の血筋だというだけで、強引に承知させられた猪之助は、急きょ名古屋に向かうことになった。
新生赤松社
庄平は猪之助の留守中も三谷に会って、その後の段取りを聞かされた。
「会社の名前は赤松社(あかまつしゃ)と決まりましたよ。あの屋敷跡に、間もなく工場もできますでしょう。はた織り機械はとりあえず30台くらいにして・・・。それから先のことは、川島さんがお帰りになってからということにしましょう。それまでにほかのことを準備しておかなければ・・・。松屋さん、よろしゅう頼みますよ」
「それはよかばってん、三谷さん」
「はい・・・?」
「肝心の、働き手のお武家さん方は、やる気があるとですか」
「そこなんでございますよ。お金を出してくださるお殿さまのご意向は、すべての士族の皆さんが何らかの形で赤松社の経営にご参加くださることです。でも実際問題となりますと、気位(きぐらい)の高いお方ばかりで。金を稼ぐために工場で働くなんて、そんな下賎(げせん)なことはできませんと・・・。お話しするのにも苦労しました」
「ばってん。お侍さんたちは、屋台で客呼びしたり、醤油ば売ったりしとらすじゃなかですか」
「それはそうですがね。身分を隠して一人で行動するのとはわけが違うらしいのですよ。工場で職女とか職工とか呼ばれて働くということは」
「そげなもんですかね、三谷さん。それでどうなりました?」
「仕方ないですからね。一軒一軒屋敷を回って、一人一人を口説いたんでございますよ。殿さまからの厳しい言いつけだと申しましてね。和傘(かさ)作りとかすり織りを合わせて、大方300人の皆さんが工場に出てくださることになりました。後は、川島さんの教育がうまくいけばと思っております。でもですよ」
三谷には、まだ話し足りないことがあるらしい。
「傘とかすりだけでは、売り物の種類が少ないんでございますよ。そこで役員の皆さんと相談しましたらね。白皮表(しらかわおもて)も作ろうと」
「白皮表?」
「つまりは、南部表のことですな」

白皮表で作った雪駄
白皮表とは、奥矢部(現八女市星野村)で採れる変異した真竹の白い皮を履物の表に施して、履き心地をよくする工芸品のことである。「南部」とは、岩手県の南部のことで、「南部鉄」などで有名。平成の今日でも、星野村から栃木県や群馬県、それに神奈川県や東京などに「皮白竹(かしろたけ)」と銘打って送られ、それぞれの地域の工芸品として重宝がられているという。
南部表は、その皮白竹(かしろたけ)を利用して、当時久留米藩とは親戚関係にあった南部藩が、足軽の内職として雪駄表(せったおもて)を作ったのが始まりだと伝えられる。赤松社の売上高では、かすりや和傘つくりには遠く及ばなかったが、原価が安い分それなりの貢献を果たした。皮白竹の雪駄は、今日では1足2万円以上もする贅沢な履物として販売されているとか。
川島猪之助が名古屋から帰郷して造り上げた織機は、三谷のメガネに叶(かな)うものとなった。これまでの半分ほどの太さの糸で、かすりの織立てが可能になった。従来の機械と比べて杼(ひ)の滑りもよく、1反織るのに1日から1日半も時間を短縮することができた。
三谷が意図した細糸によるかすり織りは、何処も真似ができない、赤松社の独壇場(どくだんじょう)となった。働き手は、士族とその家族に限られるということもあって、奥方らの勤労意欲も高まり、次第に成果を挙げていった。明治16(1883)年の頃である。
赤松社創業から1年が経過して、秋も深まった頃だった。
「忙しかごとあるない」
養父の庄兵衛が庄平に話しかけた。
「この頃、赤松社のかすりが、ばさらか(大変)よか賞ば貰うたげなない」
これも、株仲間から仕入れてきた情報らしい。庄平の方は、養父ほどに喜んでいない。庄兵衛が言う「賞」とは、先ごろ鹿児島で開催された九州沖縄八県連合の共進会で、赤松社制作の久留米絣が一等賞を受けたことを指している。共進会とは、明治政府が産業振興のため、各地で開いた見本市のこと。
「賞を取れば、売れ行きもようなろうもん。それがなして面白うなかとか」
動き出していくらもたたないのに、もう一等賞とは、確かに出来過ぎの観はある。
「三谷さんが熱心かとはよかばってん・・・」
「どげんしたと、庄平」
「あの人は、もともとが絵描きさんじゃけん、どうしても見栄(みば)えのよかかすりばっかりに気がいきなさる」
「見栄えも大事ばい、かすりには」
「見栄えの代わりに、採算はそっちのけにしてよかちいうことにはならんけん」
せっかく赤松社を軌道に乗せようとする矢先、社長の三谷は、売り物を作るより作品としての価値ばかりを追求するというのである。
それでも、赤松社の販路は次第に広がっていった。創業当時には年間1700反だった生産高が、やがて1万反を超えるところまできている。
「それならよかじゃなかか、庄平。はなから(最初から)何でんかんでん(何でもかでも)うまくいく方がおかしかたい」
庄兵衛は、生産量が伸びていることを評価した。
「そうはいかんばい、親父さん。見栄えのよか織立てに懲り過ぎると、作業が遅うなるばかりか、銭(生産コスト)も余計かかる」
原価が売上高を超えていくことを、庄平は心配している。だが、庄兵衛の興味は別のところに飛んでいた。
「お前はどうしても儲けの方が頭から離れんばいね。ばってん、三谷さんは絵心を大事になさる。あのお方は、お前たちができんこつばやってくれる。人は三谷さんのようなやり方ば『武士の商法』ち言うて冷やかすばってん。わしは、それもありがたかこつち思うとる」
武士の商法をありがたがる養父の考えを読めない庄平である。

|

