|
上方の豪商
喜次郎が上方への旅支度にかかっている最中に、藤山村の伯母がやってきた。明治5(1872)年1月末のこと。
「大ごとじゃったばい、昨夜(ゆんべ)は。柳川のお城が丸焼けになってしもうたげな。ようわからんばってん、誰かが火ばつけたらしか」
ニュースは、柳川から4里(16㌔)も離れた藤山村にまで、間を置かずして届いたことになる。
1.gif)
久留米城跡
「久留米のお城が無事じゃったけん、何よりたい」
母が義姉に相槌を打っている。伯母には、挨拶しあっているうちに肝心の用件を忘れてしまう悪い癖がある。喜次郎が出ていって声をかけた。
「伯母ちゃん、元気にしとらすばいね。可愛か久次(ひさじ)に会わんでもよかですか」
底抜けに明るい伯母の顔を見ていると、すべての悩みが馬鹿らしく思えることだってある。喜次郎を見て、伯母も用事を思い出した。
「久次には用はなか。それより喜次郎、伯母ちゃんがくさい、お前によかお嫁さんの話ば持ってきたとたい」
喜次郎も、時が来れば所帯を持つのはあきんどとしての必要条件だと考えている。
「どげなおなごな、俺の嫁ごになるとは」
「その娘さんな、田んぼば何十枚も持っとらす百姓さんの長女で、ばさらか働きもんげなよ。どげんね、喜次郎」
母のヒサは一応本人の意向を確かめるが、この時代親が気に入った縁談は決まったも同然である。「任せるけん」と息子が答えたところで、後は伯母と仲人との間で段取りを進めることになった。
明治5(1872)年には、220年間続いた身分差別的「庶民の絹着用禁止令」が撤廃された。時を合わせるように、かすりの統制も解かれた。
「よかか、喜次郎。お傳さんが言わっしゃった、お前が久留米絣ば日本中に広める、これが第一歩ばい」
上方への旅立ちを前に、庄兵衛からの激励であった。
喜次郎は、山陽道を経て大阪に入った。久留米を出てから半月を要する長旅であった。大阪に着くと、堂島川に架かる橋を渡って中之島に出た。そこでは、ねじり鉢巻きの男衆が荷車を引きまわして忙しそう。前掛け姿の番頭風が、急ぎ足で荷車とすれ違う。物見遊山の人間など一人もいない。

大坂中之島の賑わい(肥後橋欄干モニュメント)
再び玉江橋を渡って、橋のたもとの旅籠(はたご)で草鞋(わらじ)を脱いだ。
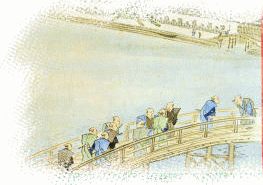
久留米藩蔵屋敷(玉江橋から)
「あれが蛸(たこ)の松だす」
堂島川に面した部屋に通されると、茶を運んできた女中が対岸の松の木を指差した。それは久留米藩蔵屋敷(くらやしき)の目印になる土手の松の木のことであった。川を上ってきた荷船が、屋敷に通じる門を潜って行くのが見えた。

久留米藩蔵屋敷に立つ蛸の松
中之島を挟んで向こう側の土佐堀川岸にも、各藩の蔵屋敷が軒を連ねている。その数50棟、中之島以外を含めると100軒を超しているという。これらの蔵は、江戸時代に各藩が自国領の年貢米を大坂に運び込んだ後(廻米)、売り捌(さば)くまでの一時保管所の役割を担っていた。再び蔵屋敷から運び出されると、堂島の米市場で取引され、換金されて藩の財政にあてられる。久留米藩の米も、筑後川河口付近の若津港(現大川市)で積み込まれた後、瀬戸内海を経由して大坂蔵屋敷に積み上げられた。
「待たせましたな」
大川端の景色に見とれているところに、足音を響かせながら増吉が入ってきた。
「明日、外村屋(とのむらや)の旦那はんが会うてくれるそうや。気ばって行きまひょな」
翌朝、増吉に連れられて船場(せんば)の太物問屋に出向いた。訪ねた外村屋は近江商家の出先にあたり、本家は金堂村(こんどうむら)(現東近江市五個荘(ごかしょう))にあると増吉が教えた。大阪でも一、二を競う大店(おおだな)だけあって、ごった返す中で誰が店の者なのか客なのか見分けがつかない。そこは慣れたもので、増吉が上がり縁にいる前掛け姿の男に来意を告げた。
「落ち着きなはれ、喜次郎はん」
商談室に通されてからも、目玉を左右に動かす喜次郎を増吉が諌(いさ)めた。
「わざわざ、九州からおいでなさったんかいな。ご苦労はんだすな」
主人の外村興左衛門である。恰幅(かっぷく)のいい、いかにも大店の旦那らしい中年男であった。
「久留米には大きな川が流れてまっしゃろ。何と言いましたかいな、その川の名前・・・」
「“ちっごがわ”ちいいます」
久留米訛りでしか話せない喜次郎の説明に、主人は小さく首を傾(かし)げた。
1.gif)
現在の大阪船場あたり
「筑後川どす。ここな若者は魚喜はん言いますねん。そりゃ真面目な若者どすせ。わてからもよろしゅうお頼(たの)申します」
増吉が、喜次郎に代わって深く頭を下げた。
「日頃何かと世話になっとる鍋屋さんの紹介やさかい、魚喜はんを粗末にはできまへんな。ところで、あんさんの売りもんの久留米かすりでんな。その良さをわてに説明してくれまへんか」
ここは初心に返って、久留米絣のことを話さなければならない。
「先年八十二(歳)で亡うなった傳さんちいうお人が、十二(歳)のときに考えだした平織もんです。その頃は、霰(あられ)模様(もよう)とか霜降り模様とか言うて大そう評判になったち聞いとります。俺はこの仕事ば始めたばっかりで、自分で旦那さんに久留米絣の良さば十分に話すことがでけまっせん。ばってん、亡うなる前に井上傳さんから聞いた話では、どこのかすりよりも肌触りがよかげなです」
「それだけかいな」
「いえ。傳さんが言わるるには、織った図柄がどこよりも新しかち。それから染めた藍がいつまっでん(いつまでも)剥(は)げんち。そして、何より生地が強かち聞いとります」
目を瞑(つむ)ったまま聞いていた興左衛門が、途中で「もうよろし」と話を遮った。
「あんさんも、正直なお人でんな。早う今話したことを自分の言葉で説明できるよう励みなはれ。これまでのお国(久留米藩)との取引では、こう言っちゃ何だが、おもろうなかったで。お侍さんとの商談ちいうんは、固うて固うて。それに比べ、あんさんとはうまくいけそうや。あとは店のもんとあんじょう話しといてや」
主人は、用が済むとさっさと部屋を出ていった。表に出た喜次郎は、体中汗びっしょりであった。
「さあ、明日は京都の辻忠郎兵衛はんとこどす。辻はんといえば日本一の太物問屋やさかいな」
外村屋が扱う「太物」とは、綿とか麻を原料とした織りものの総称で、対して絹を原料とするものは「呉服」と称した。翌日の予定を言い渡すと、増吉は喜次郎とは反対の方向に去っていった。
翌朝夜明け前に女中に起こされ、慌てて宿を飛び出した。増吉に教わったとおり、西国(さいごく)街道(かいどう)を北上して、昼過ぎには京都の街中へ。東寺の五重塔が目の前に飛び込んできた。つい数年前まで、攘夷(じょうい)派と佐幕(さばく)派に分かれて、血生臭い闘争が繰り返されていた場所なのだが実感は湧(わ)かない。
.gif)
東寺の五重塔
室町の辻忠郎兵衛の店先で、鶴屋の六左衛門が待っていた。
「あちらに見ゆるお山の向こうが、近江国(おうみのくに)どす。そこには、アホほどいかいうみがありやしてな」
六左衛門が言う「いかいうみ」とは、大きな湖、つまりびわ湖のことを指している。店では、番頭の満七が喜次郎らに応対した。
「主人の先祖も、琵琶湖の東岸どす。そんな縁もあって、鶴屋はんとは昔から仲良うさせてもろうてますよって。しっかり引きとらせてもらいますよ」
満七もまた、この取引が鶴屋あってのことだと、喜次郎に念を押している。その場で番頭は2万反ものかすりの買い付けを約束した。

現在の京都鴨川
辻商店での商談を終えた後、鴨川が見渡せる飯屋で、六左衛門が満足そうにキセルをくわえた。
「わてらが長崎とか長州に売り込むかすりを注文したとき、素人同然のあんさんが、文句一つ言わんと、約束どおりに品物を揃えてくれましたな。その時の苦労は、松屋はんから詳しゅう聞いてます。そやさかい、今回は、あんさんが一人前のあきんどになるための手伝いをさせてもらおう思いましたんや」
「ありがとうさんです」
喜次郎は、六左衛門の話しを聞いていて、涙を堪(こら)えるのに苦労した。
手紡糸(ていと)の工面
久留米に帰り着いた喜次郎は、家族や店のものに旅先での話もしないまま眠りこけた。一昼夜が過ぎてやっと起き上がると、傍(そば)に久次(ひさじ)が座っている。
「おお、お前か。商いが辛うなって、藤山に帰りたいと言うんじゃなかろうな」
「そげなこつはなかです。大将が元気で帰りなさって安心しました」
しばらく会わない内に、久次の言葉遣いが、従弟(いとこ)の間柄から店の主従のそれに変っている。そこに、母のヒサが入ってきた。
「よか話しがあるとばい。美代にややこがでけたげな」
美代は、1年前に隣村の醤油屋に嫁に行った妹である。
「よかったない。これで母ちゃんも、いよいよばばしゃんになるとたいね」
「孫はでけても、うちゃばばしゃんにはならん」
強がりを言いながら、ヒサの笑う目尻は下がりっぱなしである。
「大将、大阪の外村商店さんから郵便が届いとります」
久次が紙切れを持ってきた。番頭からの手紙であった。久留米に帰ってから何日もたたぬ間に、郵便物が追いかけてくる。不思議な気持ちのまま開封すると、「久留米絣5千反」の注文書であった。
昨年(明治4年)東京-大阪に郵便制度ができて、翌年(明治5年)にはそれが九州まで伸びた。久留米の原古賀(はらんこが)に「三潴県(みずまけん)下郵便取扱所」が開設されることは聞いていたが、こんなに早く現実のものになるとは考えられなかった。翌6(1873)年には、日本中に郵便網が完成し、全国均一料金もできあがった。
「これからは、一々飛脚に頼まんでも、原古賀まで持っていけば済むこったい」
木綿卸売業にとって、こんな便利なことはないと喜次郎は喜んだ。それにしても、外村と辻商店を合わせて2万5千反ものかすりの大量注文にどう応えればよいものか。事態の急変に、将来の原料糸と人手不足が気になり、嬉しい悲鳴を通り越して怖ろしくもなった。
喜次郎が藤山村のたつえと結婚したのは、暦が大陰暦から太陽暦に変わった明治6年の、秋も深まった時期であった。使用人も増えて、そうでなくても手狭な家である。新婚らしい夫婦生活など求めても無理であった。
農業の経験しか持たないたつえに、ヒサが商家のしきたりを熱心に教えている。嫁もまた、黙って姑の教えを聞いた。喜次郎は、新婚の甘い雰囲気に浸る間もなく、次なる旅支度にかかった。これまでは自分で草鞋(わらじ)や脚絆(きゃはん)などを揃えなければならなかったが、予定さえ告げればすべて妻が整えてくれるようになった。
「東京じゃ、2本の線路の上ば、真っ黒か煙ば吐いて陸蒸気(おかじょうき)(明治期、蒸気船に対して陸上を走った汽車のこと)が走っとるげな。新橋から横浜まで10里もあるとに、たったの1時間で行くとたい」
鍋屋の増吉から聞いた話をたつえに伝えた。
「あんたの話しば聞きよると、私も陸蒸気(おかじょうき)に乗ってみとうなりました」
茶目っ気たっぷりに返されると、その素振りが可愛くて、つい見とれてしまう。
「あんたは、早よう手紡糸(ていと)の算段ばつけなさらんと、辻商店や外村商店さんに迷惑ばかけますが」
ひと月もいっしょに暮していると、嫁の立場も微妙に変化してくる。喜次郎は、3度目の関門海峡を渡った。鍋屋の増吉からの手紙には、中国地方の士族の嫁の手が空いていると書いてあった。手紙を頼りに、長州から防州の問屋を回り、手間賃を添えて紡ぎを依頼してくれるよう頼んだ。
「久留米のかすりは、大そう評判がよろしかですけん」とは、問屋の反応だった。
防州(周防国の別称=現山口県)から安芸国(現広島県)まで足を伸ばした喜次郎は、十分な手応えを感じて帰宅した。
いざり機(ばた)から高機(たかばた)へ
喜次郎が中国地方から戻った明治6(1873)年は、久留米が商業都市として、劇的に生まれ変わる年となった。
長崎での修業を終えた倉田雲平が、米屋町で槌屋足袋店を開業した。宗野末吉は、久留米の中心地で西洋時計店を開いた。赤司喜次郎は、久留米つつじを世に送り出す赤司広楽園の初代経営者に。赤司は代々庄屋の家柄であったが、明治維新後に、病床に飾った盆栽花に魅せられ、花卉(かき)の栽培と販売を手がけるようになった。改良と販売方法に工夫を重ねて、やがて久留米つつじを世界的なブランドに押し上げることに。
そのほか、呉服町に写真館を出店した中村勝次、白山で活版印刷所を開業した野村生助など、後々にその名を残すあきんどが久留米でその第一歩を踏み出した年が明治6年なのである。三本松や原古賀など町家が連なる通りは、彼らの熱気が乗り移ったように、終日活気に満ちていた。
.gif)
代表的な久留米つつじ
「とうとうお城の櫓(やぐら)が崩(くず)れたそうですよ」
たつえが客から聞いた情報を喜次郎に伝えた。関ヶ原合戦の前から、威厳を保ち続けてきた久留米城から櫓(やぐら)が消えた。朝な夕な城を見上げて暮してきた城下の町民は、やりきれない寂しさに襲われたのだった。

取り壊し前の久留米城本丸櫓
各藩の境界を示す建造物が取り払われ、代わりに日本全国に電信網が張り巡らされた。人々が、国境を気にせず、居ながらにして日本国中と連絡がとりあえる時代に突入したのである。明治維新から8年が経過していた。
秋も深まる頃、たつえが男の子を出産した。国武家にとって、大事な大事な跡取り息子の誕生である。金太郎と名付けた。
「よかったね。これからは、喜次郎も心置きなく木綿売りがでくるたいね」
孫の誕生に、ヒサは浮かれっぱなしである。
喜次郎は、日吉神社(山王社を改名)裏手の作業場に小川トクを訪ねた。蛍川の大工亀吉や、最近久留米に戻ってきた田中久重(別名からくり儀右衛門)の協力でできあがった店である。
高機(たかばた)が、1台だけ部屋の中に据えられていた。
「こりゃ、びっくりした。腰掛けてはた織りがでくるなら、きつうなか(疲れない)ない」
滅多なことでは驚かないつもりの喜次郎が、舐(な)めるように高機を見回した。
「これが投げ杼(び)ですよ。小さいでしょう」
「ほんなこつ、鰹節(かつおぶし)のごたるない。これなら、一つ一つ手で運ばんでも、右から左にほん投げ(放り投げ)りゃよかたいね」
トクが脇に置いてある糸撚(いとよ)り器を指差した。
「これは、糸を撚(よ)る機械なの。一度に8本もの糸を撚(よ)って、できあがった糸はひとりでに管に巻きつくわ。便利なこと」
.gif)
久留米地方の高機(地場産くるめ展示)
得意げに話すトクを横目に、喜次郎は別のことを考えていた。これから先は、売り物の木綿布を、今までの何十倍、何百倍も生産しなければならなくなる。そのためには、織り手が疲れず、機械でできるものは機械に任せて人の手を省く、そのことがますます重要になってくる。得意先を広げていくことは、それだけ相手からの要望が増えるわけである。それだけに、目の前の「縞織機械」は、喜次郎にとってまたとない宝物に見えた。
放っておけば、一日中でも機械や道具の話を止めそうにないトクを、喜次郎が遮った。
「それでおトクさん、肝心の縞織りの方は・・・」
喜次郎は、商品としての縞織物がどうなるのか気になっている。
「まだまだですよ」
「そげな頼りのなかこつば言わんでくださいよ」
喜次郎は、井上傳の久留米絣と、小川トクの縞織を独占的に扱うことを考えている。傳女史から貰った版木と、いまトクに約束した縞織の大量買いつけが、その第一歩になることを確信したからである。

久留米縞商標

|

