武家奉公
伝が年季奉公を承知するまでには、それなりの時間がかかっている。福童屋は、「お傳加寿利」の商標さえ自由に使えれば、源蔵の借金の肩代わりなど安いものだと考えた。だが、思わぬところに抵抗勢力が潜んでいたのだ。抵抗勢力とは、当の福童屋に雇われている娘たちであった。
彼女らは、連日通外町の伝の実家にやってきて、「女中奉公なんかやめて」と懇願した。娘たちにとって、伝は将来を決める掛け替えのない教師だったからである。
伝は、娘たちの願いを振り切って、3年間の年季奉公に向かった。風呂敷包み一つだけの、京ノ隈(現京町)武家屋敷への引っ越しだった。

京町の武家屋敷跡(旧坂本繁二郎生家)
奉公先の屋敷は、久留米城から南へ直線距離にして1キロ足らずの武家屋敷街にあった。藩主有馬家の菩提寺(梅林寺)は、目と鼻の先にある。
「はた織りが大そう上手だと聞いておる」
主人の松田平蔵に想定外の話題を持ち出されて、伝は戸惑った。主人の隣には、夫人の隆子が控えている。
「はた織りは身分の低いものがする卑しい仕事だと決め付けてはならん。殿(藩主)からも、『領民が揃って倹約を徹底するためには、武家であろうとも、木綿織りをやるべし』と言われておるくらいだからな。いずれ身内でも始めるやもしれぬ故、その節は教えてやってくれ」
これには、隆子夫人が不満顔を見せた。主人への接見が済んだところで、早速隆子に呼ばれた。
「伝はこの屋敷に女中奉公に上がったのです。そこのところを忘れないように」
隆子も、伝が創りだした加寿利が、久留米の市中で大変な評判を呼んでいることを知っている。それだけに、普通の女中とは少しばかり扱いが難しかろうとも考えているようだ。
「娘も5歳になって、これからのしつけが大切な年頃です。万事よろしく頼みます」
松田夫人が言いたいのは、例え加寿利を考えだした町の人気者であっても、女中の身分を忘れないようにとの戒めであった。
松田家は、主人の平蔵と夫人の隆子、それに8歳の長男直太郎と5歳になる長女のさと子の4人家族である。
雇われ人としては、離れの建物に中間(ちゅうげん)の卯之吉が住んでいた。

取り壊し前の久留米城本丸
奉公に上がる際、好きだったはた織りとは縁を切って出てきたつもりだった。従って織機は持ち込んでいない。もし奉公先にお願いしたとしても許してはくれなかったろう。時間の経過とともに、伝の心の中からはた織りに対する執着が薄れていくことが分かった。
3年間の年季を半分残した頃、松田家の通用門に娘が2人立った。伝が出てみると、福童屋でかすり織りを教えていたユキエとアキであった。
「伝さん、もう我慢がでけまっせん」
姉さん格のユキエが涙声で切り出した。
「何がそげんに悲しかと?」
「伝さんがおらんごとなって、福童屋では夜鍋ばっかりさせらるるとですよ。寝ることもでけんくらいに」
「それに、伝さんがおらんごとなって困るのは、うちら織り子の腕が一つも上がらんことです。何とか、伝さんが福童屋に戻ってこれんもんかと」
甲高い声で二人が交互にまくしたてる。当然、部屋にいる隆子にも聞こえているはずである。
「無理なことば言うちゃいかんよ。うちはこの屋敷で年季奉公中だよ。勝手にやめることのできんことくらいわかろうもん」
「それは、わかっとります。じゃけん、うちらがときどきこちらに出向いて、教えてもらうわけにはいかんじゃろか?」
彼女らも、切羽詰った様子で、容易に立ち去りそうになかった。
ユキエとアキが帰って行った後、隆子から呼び出しがかかった。お叱りを覚悟で居間に出向くと、意外にも隆子の表情は柔和であった。
「伝は、あの娘(こ)たちの先生だったのですね。あの娘たちがいて、今でも伝の加寿利が織られているのですか。大倹約令のなかですからね、伝が考えだした加寿利を私も着てみたいものです」
隆子は、町人の世界にも興味を持ったようだ。
「私が先生てんなんてん、とんでもなかです」
「そんなに謙遜しなくてもいいですよ。旦那さまも言っておられるように、間もなく武家屋敷でもはた織りが始まるでしょうし。いつまでもあれは賤しいもののやること、なんて言っておれなくなります。この家に織り機を持ち込むことは無理だとしても・・・」
隆子は、10日に1度くらい伝の方から福童屋に出向いて、娘たちに教えたらよかろうと言いだした。
「そんなことば、お店の旦那さんが許すわけはありまっせん」
とっさに主人の半兵衛や番頭の顔が思い浮かんだ。
「私が福童屋にそうしたいと申し出て、文句なぞ言わせるものですか。それで娘らの仕事がはかどり、もっとすばらしい加寿利ができるようになれば、あちらだって言うことはないでしょう」
隆子は、目の前の伝というより、市中で人気の「お傳加寿利」にはまり込んでいるようだ。
縁談話
年季奉公も残すところ半年となって、出前伝習中の伝が主人の半兵衛に呼ばれた。難題をもちかけられることを覚悟で奥の座敷に出向いた。必要以上の飾り物や置物がまばゆい座敷である。
「娘たちの面倒ばよう見てくれているそうじゃないか。お礼ば言うよ。ところで・・・」
伝は、自然と身構えた。永年いろいろなことがあって、半兵衛から切り出されるとそうなる習性ができている。
「そんなに硬うならんでもよか。お前の年季もあとわずかたい。奉公が明けた後のことは考えとるか?」
予想した方向とは違う話で、少しばかり拍子抜けを感じた。
「いえ、まだ」
「父ちゃんや母ちゃんのところに戻っても、どうしようもなかろう」
半兵衛に言われるまでもなく、今さら父母のいる実家に帰っても、身の置き場すらないに決まっている。
「お前も間もなく二十一(歳)たいね。嫁さんに行くのに早過ぎることはなか」
「うちにお嫁に行けと言われるとですか? 花嫁道具の一つもなかもんば、貰い手なんぞあるもんですか」
「何ば言いよるか。そのために、松田さまにみっちり仕込んでもろうたんじゃろ。相手は織屋だぞ。幸いなことに、間もなく福童屋が預かっとるお傳がすり商標の期限も切れることだし・・・」
さすが半兵衛である。相手の思惑を先取りすることには長けている。それにしても手回しのよいことには驚くばかりであった。
「嫁入り先で、またお伝の加寿利ば織ればよか。こげなよか話はなかち思うが」
嫌なら話は打ち切るぞという態度も、相手に対する威圧行為の一種だ。
「少し考えさせてください」
年季明け後の不安もさることながら、伝には結婚の相手が「織屋」だということ以外に何一つ知らされていない。
「わかっとる。嫁入りはお伝がその気になった時ということにして。それまで、こっちで段取りば考えとくけん」
半兵衛は、これ以上の長話は無用と考えたのか、さっさと座敷を出て行った。伝が、考えていた次の言葉を発する間も与えないでである。

現在の原古賀辺り
3年間の年季奉公が明けると、伝の縁談はとんとん拍子に進んだ。相手は原古賀(はらんこが)で織屋を営む井上次八で、年齢は伝より5歳上だと聞かされた。商売もそこそこに繁盛しているとのこと。
立場上半兵衛が表に出ることはなく、代わって番頭の徳助がすべてを仕切り、仲人まで引き受けた。井上家の狭い座敷で、花婿・花嫁と仲人夫婦が床の間を背に。参列者は源蔵とミツ、それに次八の母親ヤエノと城下に住んでいる叔父が座るだけのささやかな挙式であった。
「織屋」といっても借家住まいで、柳川街道筋に形ばかりの看板が架かっているだけの小さな店であった。
この時分、町の中心部から街道に沿って原古賀までが所謂繁華街で、店の前も結構人通りは多かった。客の大半は、荘島町に住む武家(下級武士)の夫人方であり、安物の普段着を買ってくれたり、ほころび直しの注文を受けたりが主であった。
嫁に来て、伝は自分の役割を探すのに苦労した。家事一切は、姑のヤエノが「次八の好みはあたしでないとわからんもんの」と言って譲ってくれそうにない。それなら店の番でもと思うが、客を待つ時間の方が長くてすぐに退屈してしまう。そんなことから、姑には何かと遠慮することが多かった。冬場の夜鍋で、「伝しゃん、寒かろうが。あたらんね」と火鉢を差し出されても、「あたしは寒かつには慣れとりますけん」と、強がりを言って押し返すほどだった。
夫の次八は、大手の織屋のおこぼれをいただいたり、客の繕いの注文に応えるのが精一杯の様子。そんなある日の昼下がり、店先にユキエが現れた。
「あら、どうしたと。番頭さんには断って出てきたと?」
「父ちゃんが重か病気にかかったもんで、福童屋さんは辞めました」
ユキエは、三潴郡草場村の小作の娘だと話していた。弟や妹の面倒も見なければならない立場だとも。
「それも、どうでもよかごとなったとです。父ちゃんはうちがお店(たな)ば辞めてすぐに死んでしもうたし・・・」
「弟さんや妹さんは?」
「2人とも、奉公に出しました。博多におるおっちゃん(叔父さん)にお願いして」
「それで、あんたはこれから・・・」
「伝さんといっしょに仕事ばしたかとです。食べられれば、お給金なんぞどうでもよかですけん」
自分ひとりの身の置き場にも困っている伝である。とんでもない客が舞い込んできたものである。
「ちょうどよかった。店ばもうちょっと大きゅうしようち思うとったけん」
次八はユキエの受け入れに乗り気である。何を考えてるんだか、伝には夫の気持ちが計れないで困った。
織屋のおでん
次八は、お城の中までも知れ渡っている嫁の評判を、活かさない手はないと考えていた。そのためにも、織り手が嫁の伝1人だけでは心もとない。福童屋で修業を積んできたユキエの出現は、渡りに船といったところだ。
「そうは簡単にいかないのが商売ですばい」と夫に言い返しながら、伝は売れるかすり作りのことを考えていた。
次八は、嫁の言い分も聞かないで、さっさと2台の織機を買い入れた。間もなく、いくつかの機屋(はたや)から注文が舞い込んだ。
「お伝さん、ここが勝負どころですばい。もう何人か織り子ば増やしまっしょ」
ユキエが自信ありげに進言した。これ以上の織機を何処に置けと言うのさと言いたくもなる。するとすかさず、次八が裏の空き家を借りた。それから1年を経ずして、次八の織屋は、織り子が5人に膨れあがった。
「久留米原古賀 織屋おでん 大極上御誂」商標付きのかすりは、織り上がる端(はな)から機屋に持ち込まれていった。文字通り猫の手も借りたい忙しさであった。商標に「筑後」の文字を刷り込んだのは、その内「お傳かすり」を、外の藩にまで売りこもうとする次八の魂胆であった。
5人の織り子がフル稼働して、商いも順調に伸びてきた頃、長男平太郎が生まれた。伝は、産み月に入っても仕事の手を緩めず、産後10日目にはもう店に出た。
よいことばかりではない。久留米の町ではついぞ耳にしたことのなかった泥棒が、こともあろうに、伝の店に出没するようになったのだ。 写真:おでんかすりの商標(久留米商工史)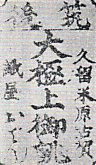 それも、金が狙われることはまずない。「織屋おでん 大極上御誂」の商標を縫い付けたかすりの反物に限った窃盗であった。番所に被害届けを出すのだが、泥棒が捕まったという知らせは来ない。盗まれた品物が、城下で売られているという噂も聞かない。 それも、金が狙われることはまずない。「織屋おでん 大極上御誂」の商標を縫い付けたかすりの反物に限った窃盗であった。番所に被害届けを出すのだが、泥棒が捕まったという知らせは来ない。盗まれた品物が、城下で売られているという噂も聞かない。
落胆する次八やユキエを慰めるのは、決まって伝であった。
「よかじゃなかね、命ば取られたわけじゃないし。盗まれたもんが久留米で見つからんということは、ずっと遠か国の誰かさんがこのお伝さんのかすりば着とらすとじゃろうけん。そうなりゃ、お伝さんのかすりも日本中の人気ば集めるかもしれんね」と笑い飛ばす。
「ばってん、悔しかですよ、先生」
雇われた織り子は、伝のことを「先生」と呼ぶ。その中のムツヨが、べそをかきながら悔しがった。
「まだわからんのかい、ムツヨ。泥棒はうちの仕事が何日かかっとるかよう知っとるとばい。じゃから、出来立ての反物ばっかり盗らるるとたい。向こうがそうなら、こっちは逆手ば取ってやろうじゃなかか。仕上げば1日早めりゃよかこつたい。これで泥棒も諦めるじゃろ」
窓の外で聞いている泥棒にでも聞かせるように、伝は啖呵(たんか)をきった。
長男の兵太郎に次いで、1年おきに二男の朝吉と長女のイトが生まれた。その時も、お産の前後を休むだけで、すぐに仕事場に戻った。その間、子守は姑のヤエノに押し付けっぱなしであった。
「お前たちの母ちゃんの名前は、男お伝たいね」
子守唄の代わりに、ヤエノは孫たちに節をつけて歌って聞かせた。
|
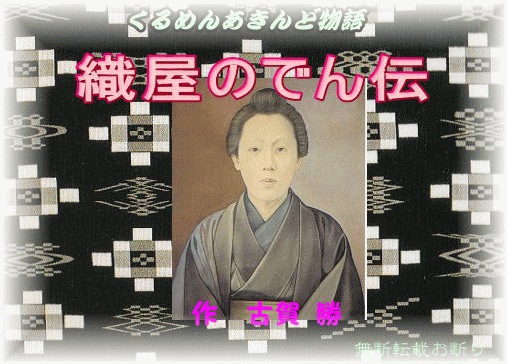
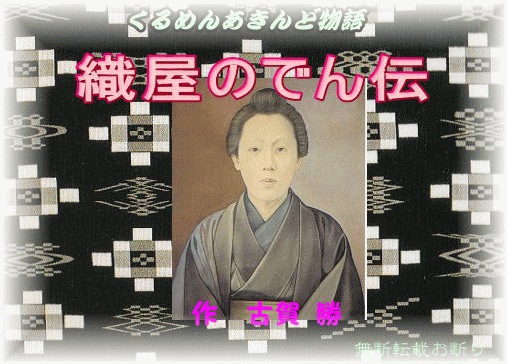
![]()
![]()



