紺屋の佐助
文化10(1813)年、伝は26歳になっていた。長男兵太郎から二男浅吉、そして長女のイトが生まれるまできれいに1年間隔であったため、子作りの期間は丸6年ということで区切りが良かった。
この間、原古賀での織屋が軌道に乗って、寝る間を惜しんでのはた織りが続いた。福童屋以来のユキエは別格として、残り4人の織り子も働きづめである。
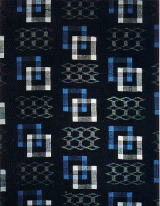
重ね枡
(久留米絣技術保存会所有)
この時分のかすりは、いわゆる「飛白(ひはく)」と呼ばれるもので、模様がすべて似たような柄だった。このままだと、伝のかすりに進歩が見出せない。柄が枡とか井桁模様だけでは頼りなく、何とかして花や鳥の図柄まで進みたかった。それができれば、武家や金持ちにも高く買ってもらえるし、収入も増える。しかしことはそんなに簡単ではない。木綿布に絵模様を描こうとすれば、その数だけ緯糸を通す杼が必要となる。ますます行程は複雑になり、織り上がる日数も計りしれない。紙に図柄を描くようなわけにはいかないのである。
「久しぶりに、御繁昌(ごはんじょう)でも観てきますか」
正直、伝は疲れていた。店の仕切りと外向けの手はずは夫に任せるとして、図柄の企画や娘たちへの伝習は彼女一人の身にかかる。その上、何とか絵模様のかすりをという欲も重なって、心身ともに参りかけていた。
秋も本番を迎えて、実家近くの五穀神社は大祭の季節であった。生後1年のイトを背負い、兵太郎と浅吉の手を引いて出かけた。子供の頃夢中になった御繁昌(ごはんじょう)(五穀神社の祭りの呼び名)は何年ぶりのことか。通町に出て順光寺を過ぎる頃、街は途端に華やかさを増した。造花をつけた飾り行灯や、大輪の牡丹花を飾った掛行灯、それに覆い青傘などで賑やかなこと。笛・太鼓の音があちらこちらから聞こえてきた。
「母ちゃんは、ここのお宮さんのそばで生まれたとよ」
生まれた時のままに残っている橋口屋を、子供たちに教えた。暖簾(のれん)を潜ると、弟為吉の女房ヒサコが形ばかりの挨拶を寄こした。お茶を飲んでいけとも言わない。父の源蔵と母ミツは、街中の料理屋に稼ぎに出ていて留守だと言う。
長居は無用と考えた伝は、子供たちの手を引っ張るようにして外に出た。祭り最中の神社境内は、相変わらずごった返していた。5歳になる兵太郎は、油断をすると伝の手を解いて露店の売り台にすがり付こうとする。浅吉ときたら、危うく迷子になりそうになった。長野村(現八女市)で切り出されたという重厚な石の太鼓橋を渡った先に、拝殿が建っている。その間、隙間がないほどに露店が並び、奥まった広場の見世物小屋(みせものごや)周辺では、客を呼ぶ大声が飛び交った。
.gif)
五穀神社の拝殿
拝殿近くの人垣は、町中が競って参加する屋台である。そこでは、能や狂言などが上演される。これまた、20年前の子供の頃と同じ風景であった。
10丁目が出す舞台では、とぼけた顔の人形が両手を振り振り動いていた。その仕草に観客がどよめく。舞台の袖のめくり板には、「雲切りからくり」と書いてある。
「お伝じゃなかか」
紺屋(こうや)の佐助であった。佐助は伝より2歳年上だから幼馴染のようなものだ。子供の頃から染物の技術を叩き込まれていて、業界でも名を知られるようになっていた。
「どうしたと、こげなとこで」
いつもは忙しそうにしている佐助が、祭り見物とは似合わない。
「そちらこそ、お忙しいお伝さんが・・・。ところで、あのからくり人形は誰が作ったか知っとるか?」

儀右衛門の、五穀神社祭礼からくり人形図(文政2年)
(久留米商工史)
「どうせ、どこかの商売人が持ちこんだもんでしょう」
「どっこい、そうじゃなかと。舞台の袖に小僧が立っておろうが。あいつが人形も舞台も1人で全部考えて作ったとたい」
「どこの子?」
「10丁目のべっ甲細工屋の息子たい。自分では、からくり儀右衛門ち名乗っとる」
「ああ、弥右衛門さんとこの・・・」
「そうたい。まだ十五(歳)ばってん。たいしたもんばい」
佐助は、一人で喋って勝手にうなずいた。
数日後、伝は5丁目の紺屋に向かった。べっ甲屋の息子のことをもっと知りたかったからである。
「たった十五の子が、どうしてあげな複雑なからくりば作れると?」
佐助が予期した通りの疑問が、伝から飛んできた。
「こまか(幼い)時からからくりのことばかり考えとったらしかけん。祭りで興行師がやっておったのを見て、病みつきになったらしか。舞台裏に回って、歯車じゃろ引っ張り糸じゃろ、目ば皿んごとして見つめとったげな。ある時には、一座について遠かとこまで行ったりして」
「そげなことしたら、父ちゃんに叱られろうもん」
「そりゃあもう。勘当寸前までいったらしか。ばってん、儀右衛門は、そんくらいのこつじゃへこたれん(まいったりしない)奴たい」
「ところで、あの人、人形のほかにも何か作っとるの?」
「他人には絶対に開けられん、鍵付きの硯箱とか・・・、」
「父ちゃんの仕事は、べっ甲細工師じゃろ」
「べっ甲は贅沢品(ぜいたくひん)ちいうことで、この頃では柘植(つげ)の木ばよう使うらしか」
伝の返事が急に気のないものに変化した。
「・・・ごめん。実は、今ちょっと別のことば考えとったもんで」
「そういうことじゃろうと思うておった。俺に何か相談があるんなら、早よう言わんかい」
幼馴染の気安さで、伝の口も次第に軽くなった。
「ばってん、紺屋のあさって(あてにならないこと)ちいう言葉もあるけんね」と憎まれ口を叩く。それでもすぐに、「実はね・・・」と続く。
儀右衛門の知恵で、かすりに多様な絵柄を入れられる器械ば考えられないか、と切り出してみた。
.gif)
代表的絵がすり「七福神」
(地場産くるめ所蔵)
「なんだ、そげなことか。この佐助お兄(あにい)さんに、ちょっとばかりときを貸しておくんなさい」
芝居口調でやり返したものだから、伝もつい噴き出してしまった。
10日もたって、佐助が原古賀の店にやってきた。
「おっしゃってくだされば、こちらから伺いますのに」
「御繁昌」以来すっかり打ち解けて話せるようになった伝は、佐助をわざとらしいよそ行き言葉で迎えた。佐助の答えがよいものであると感じての軽口であった。
「織物に絵模様をつけようというなら、まず下絵ば描くことたい。例えばこげな風に・・・」
佐助が、持参した巻紙を広げると、そこには墨の濃淡を生かした椿の花が2枚の葉っぱを添えて描かれてあった。そしてもう1枚の紙には、墨書で掠(かす)れを入れて、「紺屋佐助」の文字が。いずれも、店に出入りのご隠居さんに頼んで描いてもらったものだと言う。
「この下絵ば、そっくり糸に載せて、括(くく)っていけばよかはずたい。ここから先は、からくり儀右衛門さんの出番じゃけん」
からくり儀右衛門
からくり儀右衛門の父親が営むべっ甲細工屋は、10丁目の通りに面している。主人の弥右衛門は、工作用の眼鏡をかけたまま伝を迎えた。呼ばれて2階から降りてきた儀右衛門は、ぴょこんと頭を下げると草履を突っかけて外に出た。
体は大人並に大きいが、伝より12歳も年下の少年である。顔にはまだあどけなさが残り、吹き出ものが頬っぺたを赤く染めている。
五穀神社境内を流れる筒川の岸辺に座り込むと、子供の頃に魚をとったりシジミを探ったりした光景が蘇った。
「お城からの倹約令で、父ちゃんのべっ甲屋もうまくいかんげな。いつまで久留米におれるもんやらと、心配ばかりしとる」
初対面の伝に会うなり、儀右衛門が面白くない話を持ち出した。舞台の袖で天下をとったように得意顔だった、あの時の少年とはまるで違う。
「贅沢禁止令(ぜいたくきんしれい)さえなけりゃ、あたしだって今頃は絹を織ることに熱中していると思うよ。だって、かすりより肌触りはいいし、いろいろな柄も作れるし」
しばらく沈黙した後、慌てたように伝が話題を変えた。
「そうそう、その織物の柄織りについてだけどね」
「俺は、器械ばいじくるのは好いとるばってん、はた織りはご免ばい」
「違う、違う。それにしても、御繁昌の時のあのからくり人形は立派だったよ」
精いっぱいにお世辞を言ったつもりだったが、儀右衛門の方は面白くなさそう。
.gif)
八女の灯籠人形
「何で、あげなもん。人間に操られる人形が、ただ右に左に動くだけじゃろが。そういう俺も、興行しとるおっちゃんの真似ばしとるだけばってん」
「へえ。それで、あんたが考えとるほんなもん(本物)のからくりとは・・・」
儀右衛門は、我が意を得たりと目を輝かせた。
「人形の顔が、動きに合わせて泣いたり笑ったりせにゃ、ほんなもんじゃなか。それに動きも右と左だけじゃつまらん。前にも後にも自由に動かんことには。それに、2体以上の人形が舞台の上で絡みおうて芝居せんと面白うはなか」
「そうするために、どげな仕掛けば考えとると?」
「まだはっきりは言われんばってん。水の力ば使うて人形ば動かしたり、舞台装置ば早変わりさせることはできんもんかと。見といてくれんね、もうすぐ銭のとれる人形ば作って見せるけん」
儀右衛門の話しは、まんざらほら吹きとばかりも言えなかった。間もなく、世間をあっと言わせる「竹の輪水揚げからくり」と称する人形芝居を実現させたのだから。
「ねえ、儀右衛門さん。私の話も聞いてくれんね」
儀右衛門の話を打ち切って、伝はかすり織りに絵模様を加える技の相談をもちかけた。
「・・・絵の入ったかすり織りですか?」
考え込む仕草が何とも大人じみていて、10歳以上も年上の姉さんとしては、話のもっていきように苦労する。
「それで、成功した暁には、手間賃はいくら?」
開いた口が塞がらなくなった。15歳にしてこの商魂である。彼の考え出すからくりは、とっくに子供の遊びの域を飛び出している。
「いくらでもどうぞ、と言いたいところだけどね。こちらもしがない織屋の女房じゃけん。手間賃のほうは、できたもんば見てからにしてくれんね」
迂闊(うかつ)に太っ腹を見せれば、取り返しのつかないことになるような気がして、臆病風(おくびょうかぜ)が吹きまくった。
伝と別れた後の儀右衛門は、筆にたっぷり墨を含ませて、頭の中に渦巻くものを一気に下絵にした。次に、下絵を板面に彫刻し、その上に糸を張り、もう1枚の板で締めつけて染料に浸ける。すると、彫りこまれた凹部は染まり、凸部で押し付けられたところは染まらない。「板締め技法(いたじめぎほう)」の完成である。

儀右衛門生家跡(久留米通町)
伝は、儀右衛門に考えてもらった板締め技法で、「阿傳御誂」の文字を織ってみた。杼は今までどおり1本で済み、織る時間も前と変わらない。彼女は、目指す「絵がすり」に一歩近づいたことを実感した。
夫の死
からくり儀右衛門が考案した「板締め技法」により、伝の織屋は、絵がすり模様の織物生産へと店の質を変えることになる。注文が増えれば織機も織り子も不足する。
そんな時、姑のヤエノが寝込んでしまった。すべてが順調に回りだした矢先のことで、伝の脳裏も複雑に交錯した。仕事にかこつけて3人の子供の面倒をみてこなかった伝に、ツケが回ってきたのだと悔やんだ。だからといって押し寄せる注文を断ることは、彼女の性分としてできない。次善の策として、子守兼女中を雇うことにした。
間もなくヤエノは、あの世に旅立った。そうなると、次八のやる気も失せた。「やっぱり、母子だね」と感心する間もなく、次八もまた風邪をこじらせて、そのまま仏の世界に消えていった。
亭主の通夜と葬式を済ませた伝は、静寂に包まれた店に座り込んだまま動かなかった。
「父ちゃんは?」
3歳のイトが、父親を捜してべそをかいている。兵太郎と浅吉は、伝と口をきこうとしなくなった。7歳と5歳の子供にして母親を敬遠する姿に、伝は自らの身をどこに持っていきようもなかった。
初七日が過ぎても、伝に働く意欲は出てこない。地主からは、夫名義で借りていた母屋と裏の土地を返すよう迫られた。所詮は自分が井上家の嫁以上の何ものでもなかったことを思い知らされた。
「伝さん、しっかりしてくださいよ」
ユキエが心配顔で横に座った。
「伝さんにとって、兵太郎ちゃんたちのこと一番大事かことはわかるですよ。ばってん・・・」
真顔で話しかけられると、伝もユキエと向き合わないわけにはいかない。
「・・・・・・」
「伝さんの両腕には、他に5人もの雇われもんがぶら下がっとるとです。伝さんにしょげられたら、うちらみんな、行き場所を失うとです」
「まさか・・・」
「まさかじゃなかですよ。それに、伝さんのかすりができるとば待っとる人がどれだけおらすことか。一時も惚(ほう)けとる暇はなかですよ」
これほどきつく食いついてくるユキエを見たことがない。
「ねえ、ユキエ。あたしは、これから何ば目標にして生きていったらよかろうか?」
「冗談じゃなかですよ、うちらはあんたの弟子ですばい。弟子が師匠に生き方ば教えらるるもんですか。うちらにとってのお伝さんは、これからもかすりば織り続けるお師匠さんたい。それに、うちらだけじゃのうて、もっとたくさんの弟子に教えてもらわにゃならんとです」
「もっとたくさんの弟子・・・」と言ったユキエの言葉の意味が、伝にはこの時よく理解できなかった。
|
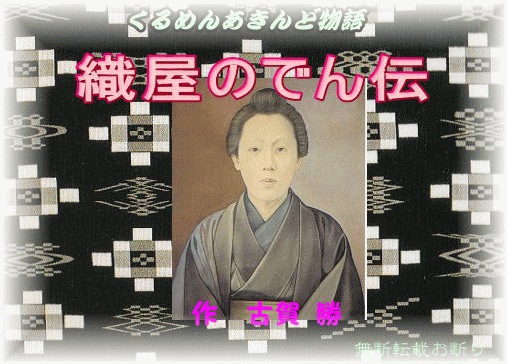
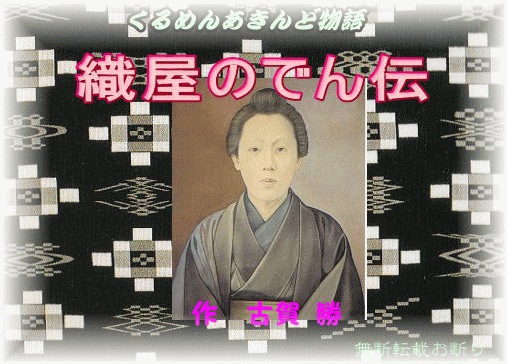
![]()
![]()



