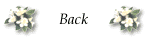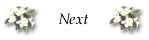TOUCH ME
WHEN WE'RE DANCING
前編
アリオスがダイニングに入ると、すでに部屋中に美味しそうな匂いが立ち込めていた。
「おはよう、アンジェ」
「あ、おはよう!! アリオス。今朝は早いのね」
明るく答えながらキッチンで作業をするアンジェリークに、アリオスは背後から強く抱きしめる。
「アリオス〜」
窘めてはいても、彼女の声はどこかしら華やいでいた。
「----今夜一日逢えないんだからな。これぐらいは許せよ?」
「だって…、学校の行事だから・・・、ん…!!」
アリオスの唇は、彼女の首筋を這い、思考能力を徐々に奪ってゆく。
「…首筋はやめ…て…」
「季節はずれの蚊に食われたとでもいえよ」
彼は、直も唇を這わすことを止めない。
「お願い…、ばれちゃうもん!!」
アンジェリークの懇願に、アリオスは舌打ちをして首筋から唇を離すと、腕の中で彼女をくるりと一回転させた。
「結婚してから一回も離れてねーのに、今夜は逢えないんだから、それなりのことはしてもらうぜ?」
ニヤリと彼独特のイタズラっぽい微笑を彼女に向け、探るように見る。
「で…、でも…、修学旅行とか、アリオスが帰ってこない日とか、今までもあったじゃない…」
その微笑に真っ赤になりながら、アンジェリークは必死になってその場を取り繕おうと、早口でまくし立てる。
そんな彼女が、心底可愛いと彼は思う。
「----あれは、結婚前で、お互いの気持ちを打ち明ける前だ。今と話が違う…」
「違うって…、…ん…!!」
深く唇を塞がれて、 アンジェリークは思わず切なげな吐息を漏らした。
口腔内を彼の舌で愛撫され、体の奥が痺れてゆく。
朝からにしてはかなり深く大胆な彼の唇を受けながら、暫し、アンジェリークは快楽の波に溺れた。
「ふう…」
『おはよう』のキスにしてはかなり大胆な口づけがようやく終わり、アンジェリークはうっとりと溜め息をついた。
彼女の蒼い瞳が欲望を映し出し、かすんでいる。その瞳の色は、彼を魅了して止まない。
「これ以上離さなかったら、そのままベットに連れ込んでしまいそうだからな」
苦笑して、アリオスは、名残を惜しむかのようにアンジェリークから体を離した。
「…バカ…」
アンジェリークは頬を赤らめて、とうとう俯いてしまった。
「ところで、いい匂いだが、何を作ってたんだ?」
「あなたの大好きな、ラム肉のシチュー。晩御飯に食べてね。アリオス、出来合いのものいやでしょ?」
「サンキュ」
彼に頬に軽いキスを受け、彼女の顔に自然と笑みが浮かぶ。
「ありがとう」
「何が?」
「今日のダンスパーティの準備合宿を許してくれて」
「バーカ、そんな可愛いこと言ってると襲っちまうぞ?」
彼に軽く頭を抱き寄せられて、アンジェリークは幸せそうにふふと笑った。
その表情は、とても幸福そうで、見ているだけでアリオスも幸せな気分になる。
本当に、合宿----といっても一泊二日だが----を許してやってよかったと思う。
まだ彼女は妊娠初期で、安定期に入っていないために、体の方は心配なのだが、レイチェルが面倒を見てくれる分は、大丈夫だろう。
「そろそろ、メシにするか?」
「うん」
二人は食卓につき、甘い朝の時間を愉しんだ。
朝食が済み、アンジェリークの登校時間になった。
いつもの荷物に加え、明日のダンスパーティに備えた合宿の為の荷物がそこに加えられる。
明日は、スモルニィ女学院の大講堂を使った、年に一度のダンスパーティがあり、生徒総出で準備に当たるのだ。
スモルニィのダンスパーティは、16歳以上であれば誰でも参加出来、そこでカップルになることも出来るし、もちろん予めパートナーと出席しても構わない。もちろん、今年のアンジェリークには、パートナーがいる。アリオスだ。
今や、クリスマス前の風物詩として、老若男女がその開催を待ちわびる、一大イヴェントだ。
そのイヴェントに花を添えるのがスモルニィの生徒たちによる、「FLOWER GIRLS」だ。彼女たちは、参加する人たちに講堂の前で、白い花を配るのがしきたりになっているのだ。
アンジェリークも、その「FLOWER GIRLS」に選ばれ、必要に駆られての合宿参加だった。
「明日、遅れないでね?」
「ああ」
アンジェリークは満面に太陽のような笑みを浮かべると、彼の唇に触れるだけの優しい口づけをした。
「いってきます!」
「明日の夜は、飢えた狼がどうなるか見せてやるぜ?」
「もうバカ!!」
「気ィつけてな」
アンジェリークが出かけた後、アリオスは、フッと幸せそうな笑みを浮かべた。
--------------------------------------------------------------------------------
以前なら駈けていた通学路を、今はゆっくりと歩いてゆく。
彼女のおなかに芽生えた命が愛しくて、なによりも彼との間の命だから大切に思う。
結婚するときも、妊娠したときも、いつもアリオスが守ってくれた。
名門女子高と誉れの高いスモルニィ女学院は、生徒の自主性を尊重させる学校で、アンジェリークの今回立て続けに起きた二つの出来事も、察して問題視されなかった。
それどころか、彼女を、今や全校上げて見守ってくれているのだ。
しかし、こうなったのも、影で努力をしてくれた、アリオスのおかげなのだ。
そう思うと彼には感謝しても仕切れない。とはいえ、彼女がせめて高校を出るまで待てなかった、彼にも若干の責任があるのだが。
猫の泣き声がして、アンジェリークは考え事を休止する。
「あ! 車道に子猫!!」
そう思ったのもつかの間。
子猫は、ヨチヨチと歩き車道を渡り、そこに車がやって来る。
いつもの彼女ならそこで助けていた。しかし今の彼女は、事情が違う。動きたくても、動けない。
「危ない…!!!」
アンジェリークが、悲鳴にも似た声を上げた、その瞬間----
「あっ!!」
紅い髪をした豊かな身長の男が、車道に飛び出し、飛ぶように子猫を抱き上げて、易々と救って見せたのだ。
「凄い!!」
大きな瞳をそれこそまあるくして、感心するかのように、アンジェリークは何度も頷き、ぱちぱちと手を叩いた。
その音の導かれて、赤毛の男は振り返った。
その振り返り方がとても印象的で、とても魅力のある男性(ひと)だとアンジェリークは思う。きっと、女性なら一度はその腕の中で溺れてみたいと思うだろう。
しかしその思いは、彼女にとっては冷静な分析力から来るものであって、決して恋焦がれる気持ちから来るものではなかった。
彼女の恋焦がれる気持ちは、たった一人の男性のためだけにある。
「誉めていただいてどうもありがとう」
ウインクをしながら、赤毛の男は艶やかな微笑をアンジェリークに送る。
普通の男なら厭味に写るが、この男はとてもすっきりとよく似合う。
伊達男ぶりが板についているといった感じだ。
「私も助けたかったんですけど、今はちょっとした事情で走れなくって」
少女の余り物穢れのない微笑が、男の心にまっすぐと光の矢のように入ってくる。
余りにも可愛らしく、新鮮で、一瞬にして彼を捉えて離さない。
「あ…、頬が汚れてますよ?」
先ほど子猫を救出するときに車の泥でもついたのだろう。
「ああ、すまん。なんともない」
その腕で拭おうとして、白いハンカチを持つ手がすっと伸びてきて、彼を制した。
「使ってください。今日は、たまたまいくつも持っているので」
笑顔と共に差し出されたレースのハンカチを、彼は、大事そうに受け取った。
彼女のその姿は、天使そのものだ。
「すまない」
「どういたしまして! じゃあ、私急ぎますから」
「待ってくれ!」
行きかけた彼女を引き止めるべく、彼は彼女の前に回る。
「お礼がしたい!」
「いいんです、そんなこと」
アンジェリークは、はにかんでいて、それでいて温かな笑顔を彼に向けた。
「じゃあ、せめて名前だけでも…。俺はオスカーだ」
「アンジェリークです」
突然、オスカーの言葉を遮るように、車のクラクションが激しく鳴らされた。
「アンジェリーク!!」
「アリオス!!」
シルヴァー・メタリックのジャガーの窓から、少し不機嫌な顔をしたアリオスが顔を出し、こちらの様子を覗っている。
「忘れ物だ…!!」
「あ…、ありがとう」
アンジェリークは、くるりとオスカーに向き直り二コリと微笑み、頭を下げると、そのままアリオスの待つ車へと急ぐ。
「じゃあ、さようなら!!」
「おい、ちょっと、お嬢ゃん」
オスカーの制止も何のその、アンジェリークは嬉しそうに愛する人に向かっていってしまった。
「ッたく…、まいったぜ・・・」
オスカーは、完敗とばかりにフッと微笑を浮かべると、車に一瞥した。
この俺のハートを一瞬で盗んでいくとは、たいしたお嬢ちゃんだ…。
またあおう、スモルニィの”天使”ちゃん
オスカーは、決して報われることのない”恋”だとは、このとき知らなかった----
----------------------------------------------------------------------------------
「…うん…!!」
少し走ったところで車はとめられ、アンジェリークはアリオスから、突然、奪うような激しい口づけを受けた。
彼の嫉妬にかられた口づけはとても荒々しく、彼女の唇を余すことなく犯してゆく。
彼の唇がやっとのことで離された時、アンジェリークの唇は所有の証のようにぷっくりと腫れ上がってしまっている。
「あの男は誰だ?」
「よく知らない」
「よく知らないって、おまえ」
「あ…、今、私、走れないでしょ? それで、車道に飛び出した子猫を、助けたくても助けられなくて、助けてくれたのが、あの赤毛の人。頬に泥をつけてたから、お礼がてらにハンカチを渡しただけよ」
アリオスの不思議な瞳を覗き込むと、嫉妬の炎がめらめらと揺らめいてるのがわかる。
それが何だか嬉しくて、アンジェリークはふふっと幸せそうに笑った。
「何だ?」
少しばつの悪そうなアリオスは、照れを隠すかのように再び車を発進させる。
「もう、アリオスが一番大好きよ!!」
アンジェリークは、甘えるように彼の肩に首を凭れさせる。
「俺も、愛してる…」
「ところで、忘れ物って?」
「大きな荷物を、身重のおまえに持たせるわけにはいかねーだろ?」
彼はいつもさりげない優しさで、気遣ってくれる。それがアンジェリークには堪らなく嬉しい。
「大好きよ…」
甘く囁かれて、アリオスの機嫌は表面的にはよくなった。
しかし、奥底は…。
アンジェリーク、あの男がおまえにちょっかいをかけなければいいがな・・・。
おまえは、おれだけのものだ!!
アリオスは、アンジェリークへの激しすぎる想いを持て余しながら、自嘲気味に笑った。
後編に続く。

コメント
アリオスお誕生日のスペシャルキリ番「1122」を踏んでいただいた、じゅん様のリクエストによる創作です。
「ORIGINAL ANGEL」で連載中の「WHERE DO WE GO FROM HERE」の叔父・アリオス、姪・アンジェの、結ばれた後の番外編で書いた、
「EVERY BREATH YOU TAKE」の設定での、「やきもちを焼くアリオス」がリクエストでした。
しゃれにならないと仰ったオスカーをあえて使ったというか、私がこの人好きだからつかったというか(笑)
実は、これ終わっておりません。嫉妬に震えるアリオスを次回描きますので、宜しくお願いします。
これは、あくまでさわりなのですが、じゅんさまいかがでしょうか。
「1122」がスペシャルだから、長くなったのではなく、私の蛇足シーンが長かったから、2回になってしまいました。
すぐに更新しますね!!