「ったく、昼休みぐらい息をつかせやがれって!! ったく、どいつもこいつも仕事、仕事、仕事ってよ!!」
会社で息が詰まり、気分転換と昼食を兼ねて、アリオスは公園に来ていた。
公園のスタンドでサンドウィッチとコーヒーを買い、食べる場所を探してうろうろとする。
陽射しが柔らかなそれから、徐々にきつくなり始め、木漏れ日が宝石のように輝く季節----
彼は、それを愛でるように眺めながら、あてもなく歩く。
生命の息吹にも似た陽射しが、彼の銀色の髪を宝石のように輝かせ、通り過ぎる者をうっとりと振り返らせていた。
肌にじんわりと汗が滲み、気温が上昇してきたことを彼に伝える。
スーツのジャケットを脱ぎ、ネクタイを緩めて、彼は、座る場所を探しつづけた。
時折、数々の女性が、憬れのような眼差しで彼に見惚れていたが、そんなことは彼にはどうでも良かった。
ようやく彼は開いてるベンチを見つけた。
そこは上手い具合に、木陰が出来ていて眩しくもなさそうで、眺めも噴水が見え、公園が一望できる、ベストポイントだった。
「歩き回ったかいがあるな」
アリオスは、僅かに口角を上げて微笑むと、どかりとそのベンチに腰を下ろした。
座れば、そこが、この公園で一番よい場所であることがわかる。
満足げに彼は、簡易お絞りで手を拭いてから、サンドウィッチを頬張ろうとした。
「あ、どなたか先客が…、きゃっ!!」
ふんわりと柔らかな声がしたと思うと、栗色の髪をした少女がアリオスの足に躓き、倒れそうになった。
「おっと」
彼がすぐさま抱きとめた栗色の髪の少女は、かなり華奢な体をしており、片手だけで充分に支えられた。
「ご、ごめんなさい…」
「どういたしまして」
ふと顔を上げた少女に、アリオスは小さく息を飲む。
彼を見上げる彼女の瞳は、紺碧の海の色のように澄んで輝き、彼の脳裏に大きく焼きつかせる。
彼は、無意識で、心のシャッターを押したのだ。
彼女の大きな紺碧の瞳は、彼の心の一番美しい場所に住み着いてしまった。
「あ…、あの…、もう大丈夫ですから、離していただけませんか?」
戸惑うような少女の声が彼に降りてきて、彼は慌てて彼女を離し、起こしてやる。
「有難うございます」
少しはにかんでいて、零れるような微笑を浮かべ、アリオスを見たとき、彼はその笑顔に酔いしれ、抱きしめて守ってやりたくなるような衝動に駆られた。
「隣、いいですか?」
「かまわねえよ」
うっとりと彼女の横顔に見惚れながら、彼は内心嬉しく思う。
「よかった。ここ、私のお気に入りなんです!!」
栗色の髪を揺らしながら、眩しいほどの笑顔を彼に向けると、少女はちょこんと彼の横に腰掛けた。
アリオスははっとする。
彼女が着ている制服は、彼の経営する会社のものだ。
「その制服は、”アルヴィース”のやつじゃねえのか?」
「良くご存知ですね!」
「まあ…、有名な会社だからな」
アリオスは言葉を濁しながら呟く。まさか自分の会社とは言えなかった。
「お見かけしないですけど、ここは初めてですか?」
「ああ」
飄々とした彼の答えに、彼女はふんわりと笑う。
本当に笑顔がよく似合う少女だと彼は思った。
「ここ、素敵でしょう? 雨の日意外はここでお昼休みは過ごすんです。ここに来れば、都会だって季節を感じることが出来るんですよ?」
「知らなかったな…、こんなに近くにいるのに…」
フッと切ない微笑を浮かべると、アリオスは空を見上げる。
少女は、初めて隣に座る青年の顔をまじまじと見つめ、胸の奥が痛くなるのを感じた。
何て、綺麗な人なんだろう…
彼の銀色の髪が光を弾いて七色に輝き、黄金と翡翠の瞳は憂いのある影が宿っている。
彼女は思わず見惚れていた。
「メシ食わねーか?」
突然彼の声が降ってきて、少女はどきまきしながら顔を赤らめる。
「あ…、ごはん、そうですね、ごはん、ごはん」
恥ずかしそうにしながらお弁当の包みを開ける彼女が可愛くて、アリオスは、彼には珍しい穏やかな笑顔を浮かべた。
あ…、この方はこんな風に笑うんだ…
少女もまたアリオスに捕らえられ、彼を見つめずに入られない。
再び彼の瞳が彼女を捉えたので、仕方なしにお弁当を食べ始めた。
「美味そうだな。おまえさんは、いつも家から持ってきてるのか?」
アリオスにお弁当を覗かれて、少し恥ずかしいと思いながらも、少女はコクリと頷いた。
「私、一人暮らしですから、お弁当を持ってこないと不経済なんです」
「普通逆なんじゃねーのか?」
「私の場合は、外食しないので、こっちの方が安いんです。冷凍使えば、食材も保存できるし」
この少女らしいと、アリオスは思った。
慎ましやかなところも、彼をすっかり虜にしている。
「俺も一人暮らしだが、外食専門だぜ? 最近、手作りもんなんて、何時食ったかも、思い出せねえぐらいだ」
「だったら、これどうぞ!」
少女は彼に手付かずのお弁当を、すっと差し出し、彼は目を丸くした。
「おい、いいのかよ?」
「その代わり、そのサンドウィッチ下さい。物々交換!!」
「いいぜ?」
少女の心遣いが嬉しくて、アリオスは甘やかな微笑を彼女だけに浮かべ、サンドウィッチを差し出した。
「有難うございます」
「俺こそ、サンキュ」
「では、頂きます」
少女に続いて、彼も無言で"頂きます”をした。
「美味い、おまえさん、ホントに料理が上手だな?」
お世辞を抜きにして、少女が作ったお弁当は、美味しかった。心からの賛辞を彼は、この小さな少女に向ける。
「有難うございます…」
彼の言葉がお世辞ではないことぐらいは、少女にもわかった。彼女は、それが嬉しくて、また恥ずかしくて、俯いてしまう。
そんな仕草も、また、アリオスの琴線へと触れる。
「おまえさん、新入社員か?」
「はい。何とかやってます。私の今いる部の部長さんがとっても良い方で、目をかけて下さっているので、働きやすいです」
少女が明るく答えている以上これは事実なのだろう。
もし、その彼女の"上司"とやらが邪な感情を持っていては困る、何とかしなければと、アリオスは内心思っていた。
二人は他愛のない話をしながら、昼食を済ませ、昼休みのぎりぎりの時間まで、ベンチを離れようとはしなかった。
しかし、過ごす時間が楽しければ、楽しいほど、過ぎるのは早い。
最初に立ち上がったのは少女だった。
「こんなに楽しかったお昼は初めてです。どうもありがとうございました」
「いいや。こちらこそ。おまえさんのお蔭で、いい昼を過ごさせてもらった。サンキュ」
二人は、視線を絡ませて微笑みあう。
そこには陽だまりのような温かさがあった。
「なあ、明日も来るか?」
「もちろん、来ます!!」
「だったら、俺もまた、来ていいか?」
途端に少女の顔に笑みが広がり、彼の心をすっかり捉えてしまう。
「もちろん!! じゃあ、明日は、私、お弁当を、あなたの分まで作ってきます!! ----あ、お名前、訊いてませんでしたよね?」
上目遣いで探るように言う彼女も、また愛くるしい。
「アリオス」
「アリオス…、いい名前ですね」
うっとりと呟く彼女に、彼は思わず苦笑する。
「おまえさんは?」
「アンジェリーク・コレット」
「アンジェリーク…、天使か…」
少女は自分には勿体いない名前だと小さく行ったが、アリオスは彼女こそふさわしい名前だと思った。
「あ…、私、行かなくっちゃ!! 明日、お弁当を作ってきますね!!!」
消去は時計を見ると、慌ててかけてゆく。
何度も、何度も彼に手を振りながら、彼女は会社へと戻ってゆく。
アリオスはそんな彼女を何時までも見つめていた----
--------------------------------
アリオスは会社に帰るなり、腹心の部下であるカインを社長室に呼びつけた。
「お呼びですか、アリオス様」
「----おい、"アンジェリーク・コレット”って社員を知ってるか?」
「ああ、彼女なら、私の部の新入社員です。いいこですが、それが何か?」
カインの部下であったことを、密かにアリオスは胸を撫で下ろす。
彼なら、決して手を出す心配がないからだ。
「----明日から彼女を、俺付の秘書にしろ。それだけだ」
「アリオス様。判りました、その様に手配いたします」
「頼んだ」
穏やかで怜悧なカインは、それが何を意味するか、すぐに察知する。
今まで秘書を置くことをいやがっていた彼が、こうもすんなり置くとは。
どう考えても、あれしかない・・・。
----------------------------------
翌日掲示板には、次のようなことが張り出されていた。
アンジェリーク・コレット。本日付で社長付秘書に任ずる
TO BE CONTINUED
JE TE VEUX
(Ⅰ)
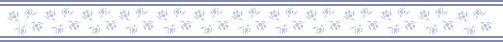
コメント
アンケートでナンバーワンだった「実業家アリオス」です。
すぐに完結する予定ですので、宜しくお願いします。
あるいてて急に思いついたネタです。
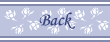
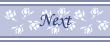
![]()
![]()
![]()