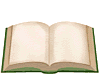
ヘンリ・J・M・ナーウェン、ウォルター・J・ガフニー
影山 由利 運営委員
〜図書室から〜
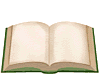
![]() 書評 『闇への道 光への道』 (こぐま社)
書評 『闇への道 光への道』 (こぐま社)
ヘンリ・J・M・ナーウェン、ウォルター・J・ガフニー
影山
由利 運営委員
|
「もっと早く・もっとたくさん・もっと快適に」−そのような現代社会にとって、「老い」とは何だろうか。もはや何の有用性もなく、肩書きや仕事、健康、やがては友人まで失ってゆくまったくの「闇」であって、私たちはそこから目をそらすことで自分だけは老いることがないという幻想に逃げこもうとしているのではないか。かくして老人とそうでない者とは弱者と強者として断絶する。結局、老いることを「闇」としているのは、肉体の衰えや喪失以上に、人間の価値を「どのような存在であるか」ではなく、「何を所有しどんな活動をしているか」によってはかろうとするこの文明なのだろう。
|