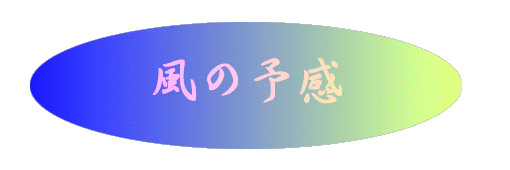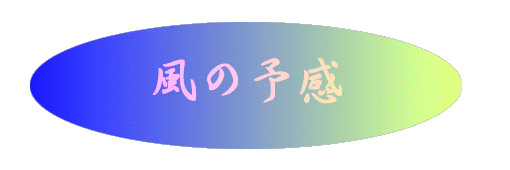
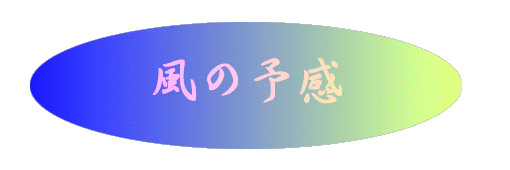
第1話 オフィス「風の予感」 =2=
|
チェックインの手続きはしたものの、まだ時間が早すぎて部屋に入ることは出来なかった。清花はセカンドバックの他にショルダーバックを抱えていて、それはフロントで預かってもらうことが出来た。「お荷物はこちらでお部屋に入れておきます」とのことだった。僕は着の身着のままで出てきているので預ける荷物もない。 僕はロビーで清花から若干の講釈を聞かされた。それは電車の中で教えられたことの復習だった。 「じゃあ、さっそく行動開始するよ」 仕事そのものにはそれなりの興味を持てた僕だが、実際の展開が全く読めない。期限も切られていることだし、思いつくことを早速やってみようと腰を浮かせる。 「あ、待って。もうすぐ資料が届くから」 清花は缶コーヒーを2本買い、テーブルの上に置いた。 そわそわしている僕に気が付いたのだろう、彼女は「落ち着いて」と言った。 「焦って飛び出しても得るものはなにもないわ。それなりの準備が必要よ」 清花は悠々と缶コーヒーを口にした。 ほどなく、1人の男がやってきた。 「あ、杉橋、こっちこっち」 清花が男を呼び寄せる。 その男は、なんというのだろう、目と口と鼻以外は全て髪の毛と髭でおおわれた、だるまのような風体をしていた。ヒゲダルマ、とはこういう男の事を言うに違いない。 背は低い。おそらく160センチはないだろう。そして、身体つきはがっしりとしている。年齢不詳。ネクタイとスーツをビシッと決めている。 「紹介するわ。こちら便利屋の杉橋貞治さん。そしてこちらが、新しい調査員の橘クン」 僕は「どうぞよろしく」と言った。 便利屋杉橋は、その姿からは想像がつかないほどかん高い声で、「こちらこそよろしくね」と言った。 「和宣、便利屋って、わかるよね」と、清花は僕の方を見た。 「うわさには聞くけれど、使ったことはないし、そういうことをやってる人に会うのも初めてだ」と、僕は言った。 「掃除洗濯料理家事全般から、引っ越し夜逃げ、大工仕事からアリ退治までこなす、よろず引き受けやさんなんだけど」 「うん」 「でもまあ、杉橋がまだ開業まもなくの頃、あんまり注文もなくてさ。それでたまたま私たちが連続して依頼したものだから、それ以来よろずのごたごたした細かいことを色々お願いしてるのよ」 「仕事の8割が『風の予感』さんからの注文ですね。おかげで飯は食えてますが、庶民の八百万に役に立ちたいっていう当初の目的とはほど遠いものになってしまいましたよ」 「あはは、特技がコンピューターのハッキング、なんていう便利屋さんは、庶民の役に立たなくても良いのよ」 清花は遠慮のないことをいう。それにしても、特技がコンピューターのハッキングとは。 「じゃあ、ひとつずつ確認して下さい」と、便利屋杉橋は言った。 「これが、ゼンリンの住宅地図。」 ゼンリンの住宅地図。出前などには無くてはならない代物だ。道路地図なんかと違い、どこに誰が住んでいるかまでこれで分かる。アパートやマンションも何階の何号室に誰が入居しているのか分かる。ただし欠点もある。がばっと地図帳を広げたとき、見開いたそのページに表示される部分が限られ、町全体を眺めることができない。だから土地勘のない者にとっては慣れるまでは遣いづらい。 「それから、この町の地図。両方を合わせてみれば、初めての町でも大丈夫です」 いたれりつくせりだ。 「それからこれが故人のデータ集。時間がなかったので、きちんとまとめられていないんですけど、住民票とか、預貯金額とか、取引銀行とか、親類家族がどうなっているとか、納税額がどうだったとか、まあコンピューターから簡単に引き出せるものは出しておきましたから。それからこれがお好み焼き屋の登記簿ね。」 ふうん、こういったモノが簡単にハッキングできてしまうのか。怖い世の中だ。 「で、このアタッシュケースとカメラ。これはそちらの会社の事務所から橘さんのために借りてきたものだから、使って下さい」 「ありがとう」 「で、報告書用の原稿用紙ですね。一応一冊。50枚綴りだから、充分でしょう」 「あはは、和宣の調査なんて、3枚もあれば事足りるよ」と、清花は笑う。 「それから、こちらが必要経費の30万円と、日当の領収書」 今度は清花が驚く番だった。 「そ、そんなものまで間に合ったの?」 「社長さんのケツを叩きました。わたしの報酬はこの中から払われるんですから」 「そうね。いい、和宣、ちょっと説明するわね。まず、さっきの5万円は返してね。アレは本来わたしの調査に対する仮払いだから。で、新たにあなたの調査に対する仮払い30万円を受け取るの。調査にかかる必要経費はこの中から使えばいいわ。でも領収書は必要よ。で、調査日数かける一万円の日当。それもこの中からもらって。もちろん自分で日当の領収書を書くのよ、いい?」 「それと、余計なことかも知れませんが、サングラスと伊達眼鏡を用意しておきました」 「そんなの、使うかなあ?」と、僕は言った。 「いいんですよ。とっといて。どうせ『風の予感』さんから出るお金、すなわち最終的には必要経費として依頼人が払うわけですから」 「商売熱心ですね」と、清花。 「なんだか、自分の懐が痛まなければ、何だっていいっていう感じがして、気が進まないけれど」と、僕。 「それは考え方の相違ですね。使えるものは使って、迅速に正しく処理をする。つまりその方が依頼者のためになるんです。そのために必要なものは当然依頼者が負担すべきです」 「まあ、そう言うことだから」 なるほど、それもひとつの考え方だ。 「あと、何か必要なモノやコトがあったら、こちらに電話して下さい」 便利屋杉橋は名刺を僕に差し出した。 「さて、で、これが今回の請求書なんですが」 「さっきの30万円の仮払いから、即金で払ってあげて」と、清花。 僕は請求書に書かれたとおりの金額を渡し、領収書を受け取った。 「これって、高いんだか安いんだか、さっぱりわからない」 「そうですね。ハッキングや情報屋の相場って、わたしも知りませんから、高いんだか安いんだか、わたしにもわかりません」 「じゃあ、どうやってこの料金を割り出したんだよ」 「労働時間ですね。月にこれくらいの収入が欲しいっていう希望額を月にこれくらいしか働きたくないっていう時間で割ると、単位時間あたりのわたしの人件費が出るでしょ? それに、2割をかけます。この2割で電気代とか家賃とか電話代とかをまかなおうってわけです。それに必要経費を足してあります。必要経費は全て『定価』で算出します。安く仕入れた場合は差額が収入になりますね。定価でしか仕入れられなかった場合は一銭にもなりません。こういう商売ですから、百円以下の単位は切り上げています。」 「その説明、もう3回聞いたわ」と、清花が笑った。 |
|
その日の調査を終え、僕は充足感で満たされていた。 これでバッチリ死者の気持ちをつかんだ、そう確信してホテルに戻った。僕はちょっとした興奮状態だった。行く先々で僕がどんな結果をつかんだか、それをはやく清花に話したいと思った。 けれどもホテルのフロントの話では、清花はまだ戻っていなかった。 清花がもうひとつ抱えているやっかいな案件。そう言えば、僕は自分のことに夢中で、そのやっかいな案件については何も知らない。訊かなかったし、清花も何も話そうとはしなかった。 ホテルの部屋に入り、バスタブにお湯がたまる間に、コンビニで買ってきた弁当を食べた。そして、缶ビールを飲んだ。食べ終えてバスを覗くと、お湯の状態は「あと少し」という感じだった。 服を脱いで、バスタブに身を沈める。 いったん目を閉じて、そして目を開けるとお湯の量はちょうどいいあんばいで、僕は蛇口を閉めた。天井は、強化プラスチックとでもいうのだろうか、何の感慨もないクリーム色に塗り込められていた。僕はもう一度目を閉じた。そして、今日の出来事を反芻する。 最初に訪れたのは、隣の文房具屋だった。 例のお好み焼き屋もその文房具屋も、駅から一直線に伸びる古びた商店街にある。駅を背にしてさらに進むと、国道との交わりの一角に、長距離バスのバスターミナルがある。そして、大きなスーパーマーケット、郊外型の大型書店、パチンコ屋があった。この町の住民とは全くかけ離れた感じでそれらは存在していた。なだらかな山の斜面に新興住宅地が広がっていた。駅からのびる商店街は旧市街、国道のバスターミナルなどを中心とした一角から新興住宅地にかけて広がるのが新市街、そんな印象を受けた。 文房具屋のおやじも結構な年齢のようだった。呼びかけると、よっこらしょっと言う感じで奥から顔を出す。しかし、顔色は良く、声も良く通った。 「なんであんたが山本さんのことを調べとるんだ? ええ? 孫に頼まれた。ばかばかしい。知りたければ自分で来いってんだ。よく聞かされたよ。息子も孫も顔を出さない。戦争を乗り越えたこの店もわたし一代で終わりだってね。アメリカの襲撃には耐えたが、身内に撃墜されたんだとさ。でも、本当は顔さえもっと出してくれていたら、店のことなんてどうだって良かったんじゃないかなあ。儂はそう思うがな」 この文房具屋は朝が早い。子供たちが文房具を買ってから登校しても間に合う時間に開けている。そのかわり、閉店も早い。下校してすぐに買い物に行かないと閉まってしまう。ちなみに、登下校の時間は小学校高学年が基準である。店を閉めたあとは隣のお好み焼き屋で、お好み焼きを注文するでもなく、桜さんと山本さんの3人で喋っていたそうだ。 僕は桜さんの住所を教えてもらった。訪ねてみようと思ったのだ。文房具屋を辞してから、僕は、桜さんの「桜」が苗字なのか名前なのか、果ては男なのか女なのか、確認していないことに気が付いた。教わった住所へ出かけると、全く違った表札が出ていた。 隣の家から人が出てきたので訪ねてみると、桜さんというのは苗字でも名前でもなく、桜の柄のエプロンをしているからそういうふうに呼ばれているのだと分かった。家を間違ったわけではなかったのだ。桜さんは山本さんや文房具屋さんと同年代ではなく、おそらく40後半か50になったばかりのおばさんだった。現役の主婦だ。 「ああ、あの人はね、店を閉めてからでも、ほとんど毎日掃除をしてたよ。閉めた店を掃除したって、疲れるだけじゃないの。そんな風にからかうとさ、『私が生きているうちはこの店も綺麗にしておきたい。そして私の死後は掃除する人もなく、私と共に朽ちて行くんだ。』なんて言ってたよ。 でも本心はどうだろう。息子さんも、お孫さんも、りっぱな勤め人になられて、いまさら店を継ぐなんてことは期待できないだろうけど、いつでも使えるようにしておきたかったんじゃないかな? どんな気持ちだったかって? 継いで欲しかったかどうかなんて私にはわかんないよ。強くそう願ってたわけでもなさそうだったけれどね。ただ、自分とともに店も終わる。それが寂しかったんじゃないかね。」 ふうん。そういうことか。 きちんとした勤め人になっている子供や孫に跡を継がせたいなどとあえては思わない。けれど、店がこれっきりで終わってしまうのは残念だ。そうだろうなあ。半生をこの店と共に生きてきた人だろうから。このまま店が消えて無くなってしまうのは惜しい。出来れば誰かが引き続きやって欲しい。誰かって、誰が? 大きな会社じゃない、個人商店なんだ。身内がやらなきゃ誰もこんな店、やらないよなあ。そこで、ぶつかる壁。息子も孫も立派な勤め人になっている。それを捨ててまで後を頼むなんて言えない。もちろん山本さんの血を引くのはこの二人だけではないが、便利屋杉橋が持ってきた資料によると、結婚して家庭を持つ者、自分で事業をはじめた者、まだ学生の者とまあ当然と言えば当然だけど、それぞれ自分の立場というのがある。 だから、おばあちゃんの夢を叶えるには、誰かが犠牲にならなくてはならない。 もちろんおばあちゃんは誰かに犠牲を強いるつもりなんかない。だから、近所の親しい友達やお客さんには心情を語っても、身内には何も言わなかったのだ。 でも、その本心は.... そう考えるとなんかやりきれなくなってしまった。だけど、もっとよく考えると、この程度のことは毎日あちらこちらで起こっていることでもあるだろう。 そうだ、お店の評判はどうだったのだろう? お店の評判など山本さんの気持ちとは直接は関係ないのかも知れないけれど、少し調べといた方がいいような気がした。もう店を閉めて3年になるというが、その理由は健康上の問題ということだった。体を壊したとかではなく、単に体力に限界を感じたらしかった。やむをえまい。お年がお年だから。そして、そういうやむを得ない理由で店を閉めるとき、このお好み焼き屋は惜しまれて店を畳んだのだろうか? 寿命がつきた電球のように、ふっと消えてしまったのだろうか? 気軽に話をしてくれそうな人を桜さんから2・3教えてもらった。 『とりたてて絶賛するような味ではなかったが、やはり素人が家庭で焼くお好み焼きとはひと味違った。おばあちゃんの人柄や店の醸し出す雰囲気がよかった。』というのが、最終的に出した僕の総合評価だ。 そうだ、お風呂から上がったら、これらをメモにまとめておこう。そして、明日にでもレポートを完成させよう。 さめはじた湯船から身を起こしたところで、呼び鈴が鳴った。ろくに身体も拭かず、ホテルの浴衣を羽織って出入り口のドアまで行き、「はい」と、返事する。 「あ、和宣? 帰ってたのね。いま、いい?」 清花だ。時計を見る。もう10時を回っていた。 僕はロックとドアチェーンを外した。 「どうぞ」 「うん」 「いま、終わったの?」 「そう。和宣はお風呂に入ってたのね。もしかしたら、まだ途中?」 「いや、いいんだ。どうぞ」 清花は「うん、ありがと」と言って僕の部屋に入ってきた。ちょっと疲れたかな、そんな足取りであり、表情だった。かってに冷蔵庫からビールを取りだし、ベッドの縁に軽く腰掛けて、リングプルを開けた。プシュワッという何とも気持ちのいい音がした。それを飲む清花のゴクッゴクッという音がはさらに気持ちよく、清花はとても美味しそうにビールを飲んだ。さらに美味しそうだった。 「結構疲れたみたいだね」と、僕は清花に声をかける。 「ん、まあ。覚悟はしてたんだけどね。そっちはどう?」 「順調」と、僕は答えた。 清花の方はあまり順調そうではなかったけれど、僕の答えを聞いてホッとしたのだろう。疲れた表情が和らいだ。 「それは良かったじゃない」 僕もビールを開け、今日の出来事をさやかに報告する。僕としては結構満足のいく仕事が出来たという気になっていたし、あとはひとつの報告書としてまとめるだけだと思っていた。 |
|
飲みながら僕は、問わず語りに今日の調査結果を喋っていた。 後はレポートにまとめるだけだ、全て順調だ。そう思っている僕だから、ちょっと自慢げに喋ったかも知れない。無意識のどこかで「よくやったね」と誉められようとしていたのかも知れない。だからだろうか、報告が進むにつれ、表情が硬くなっていく清花に、僕はものたらなさを覚えはじめていた。 文房具屋の件と桜おばさんの件を語り終えたとき、清花は「煙草、吸ってもいい?」と言った。 「あ、いいけど、吸えるんだ」 「本当は仕事中と人前では吸わないようにしているんだけど、いいかな?」 「どうぞ」 「ありがと」 清花はセカンドバックから煙草とライターを取りだし、一本を口にくわえて火を付けた。それから清花はいったん立ち上がってデスクの上の灰皿を持ち、そのまままたベッドの縁に腰掛けた。灰皿を持った左手を膝の上に置き、右手は缶ビールと煙草を持っている。親指と人差し指で缶ビールをつかみ、火のついた煙草は薬指と小指で挟んでいる。もちろんこのままの状態で缶ビールを飲むこともできるし、煙草を吸うこともできる。器用でちょっと憂いのあるポーズだった。 僕は続きを話す。それは店の評判についてだった。 僕が語り終えると清花は吸いかけだった何本めかの煙草を灰皿に押しつけて消しデスクの上に戻した。缶ビールはそっとゴミ箱の中に入れる。もう飲み終えていたのだ。僕もわずかに残ったビールを喉に流し込んでから、同じようにそっとゴミ箱の中に空き缶を入れた。 「で?」と、清花が言った。「今日のその調査を、どうするつもりなの?」 口調が少しとがっていた。目はにらむように僕を見据える。 及第点の調査をしたと思っている僕にとって、その所作の意味は計りかねた。 及第点と思っているのは僕の独りよがりで清花はそうは思っていない。それだけは理解できた。 「いや、だからこれを報告書にまとめれば、それで終わりだよ」と、僕は言った。 「その調査をそのまま報告書にまとめてどうすんのよ。言っておいたはずよ、私たちの調査は、死者のためにするのではなくて、生きている人のためのものなんだって」 「わかってるよ、そんなこと」 叱責もどきの清花の口調に僕もつい応戦してしまう。 「山本のおばあちゃんが自分の半生を費やしたお好み焼き屋に、どんな思い入れを持っていたか。子供や孫に跡を継いでくれとどうして言わなかったのか。この調査を報告書にまとめたら全ての気持ちが伝わるじゃないか。」 「だから、それじゃ、だめなのよ」 「何故?」 「そんな報告を受けても、遺族は『わかりました、では明日からお好み焼き屋を再開します』何てことが出来ると思うの?」 「それは、無理だろうけどさ」 「わかってるじゃないの。無理だと分かってて、そんな報告書を出すの?」 「そういう依頼だったじゃないか!」 気が付けば、清花の口調は落ち着きを取り戻していた。逆に僕は興奮していた。 「じゃあ、依頼の内容を無視して、遺族にとって都合のいい報告書を出せってコト?」 「....極論に走らないで」と、清花は言った。 しばらくの沈黙。 「銀行の預貯金や納税額のデータ、持っているよね。それを見れば分かるけれど、山本さんはご主人を亡くされてから、お好み焼き屋の経営で得てきたお金は多くはないわ。なんとか店を維持できる程度。そして実際には息子さんからの仕送りも受けている。つまり、現実的に儲かる商売じゃなかったってコト。家族を養っていくには簡単には転職することは出来ないじゃない。それに山本さんの死後、店は売りに出されていて、買い手も最近ついた。既に他人の手に渡ってしまった物件で商売することもできないわ。」 清花は淡々と語った。 「それはわかっているよ。山本のおばあちゃんはそれに、子供や孫たちの生活を奪ってまで、店を続けて欲しいなんて思ってなかった。」 「でも、自分とともに店が終焉を迎えることを残念には思っていた。そのことを聞かされて、遺族が平気な気持ちでいられると思う?」 「さあ、それはわからないけど」 「わからないなんてどうかしてる。こんな調査を依頼してくるほどの人が、平気なわけないじゃない。繊細な人なのよ、依頼主は。少なからず、心の平穏が奪われるのよ」 「そう、だね」 僕は清花が言わんとしていることが少し分かったような気がした。死者のためでなく、生者のための調査。 「それにね、あなたが調べたようなこと、とっくに遺族の人は分かっているのよ。わかってて調査依頼をしている。なぜかわかる?」 「え?」 「おばあちゃんにとって店が無くなることは無念だった。わかっているけれど、それに応える術がなかった。でも、本当にそうだったのか? もしかしたらおばあちゃんの本心はそうではなかったかも知れない。そう思うことで、救いを求めているの、依頼者は。」 「だからって、おばあちゃんは実は店が無くなることを何とも思っていなかった。まして跡を継いでくれる人がいればいいのになんてこれっぽっちも思っていませんでした、そんな報告書が書けるわけがない」 「そう、その通りよ。だから、こんな商売が成り立つんじゃない」 だから、こんな商売が成り立つんじゃない。 清花のその台詞が僕の頭の中を何度か行き来した。 だから、こんな商売が成り立つんじゃない。 「ねえ、和宣って、お墓参りしたことある?」 「それは、ある、けど」と、僕は答えた。答えたけれども、何故急に清花がそんな話題を持ち出したのか分からなかった。 「お墓参りをして、綺麗にお掃除をして、花を手向けて、線香に火を付けて、両手を合わせる。それは何のため」 「あ、そりゃ、先祖の霊を慰めて、ええと、それから」 「違うわ。そんな風に考えていたら、今回の依頼はこなせない」 「違うって?」 「死後、人間がどうなるかなんて、誰も知らない。でも、知らないけれど、先祖の霊を慰めるようなことをする。はたして先祖の霊は子孫が拝んでくれていることを理解しているのかしら。理解しているとして、それをありがたいと思っているかしら。 それに答えられる人はいないよね。けれど、お墓参りをするのは何故? 仏壇に手を合わせるのは何故? あるいは霊なんて存在そのものが否定されてしまったら? そうなったら人は先祖を拝むことをやめてしまうものなのかしら」 僕には分からなかった。 「先祖の霊がどうかなんて関係ないのよ。自分がお墓参りをしていることそのものが大切なの。先祖の霊は自分の心の中にあるの。だから、お墓参りなんて行動をするのよ。そして、心の中の霊を慰めることで、自分の心に平穏をもたらすの。元も子もない言い方をすれば『自己満足』よ。でもそれがかけがえのない平穏な気持ちにつながるの。」 はあ。僕は心の中でため息をついた。清花の説が正しいとか間違っているとか、理解できるとか出来ないとかではない。そんなことまで考えながら清花はこの仕事に取り組んでいたんだ、そう思うとため息が出るのだ。 「死者を悼む気持ち、それは、死者のためにあるのではなく、生きている人のためのものなの」 「うううう、ん」 唸るだけの僕。 「じゃあ、この調査の報告書、どう書けばいいんだろう」 「それはまだ分からないけど、調査不足であることは確かよね。でも、結論はある程度決まっているの」 「お好み屋の後を誰も継がなかったけれど、おばあちゃんはそれでもいいと思っていた。子供たちや孫たちは、自分たちの幸せのための努力をすればいい」 僕は朗読をするように声に出した。 「その通り。だけど、和宣の今日の調査からその結論を導き出すには無理がある。無理に結論づけたら嘘の報告をしたことになる。つまり、調査不足よ」 「そうだね、うん」 僕は調査を完遂したと思いこんでホテルに戻ってきたときの、気持ちの高揚なんかすっかり無くしていた。逆に、落ち込んですらいた。 「どうすればいいんだろう」 口に出すつもりはなかったけれど、声になった。清花の耳に入った。 「さあ、どうしようか。普通なら、和宣くらい聞き込んでたら、なんかその中にヒントがあるんだけどなあ。」 僕たちはもう一度おさらいすることにした。僕は自分の出した結論の根拠となることだけを清花に話したのであって、行く先々で何を見て、何を聞いたのかの全てをさやかに語ったのではなかったからだ。 「これじゃ、清花が自分で調査した方が早かったかもね」 「そんなことないわ。ホテルの一室に、居ながらにして色々なことを知ることが出来るんだもの。」 清花の言葉に僕は慰められる思いがするのだった。 |
|
普通なら、和宣くらい聞き込んでたら、なんかその中にヒントがあるんだけどなあ。 そうだろうか。 本当にそうだろうか。 確信はなかったけれど、僕はそう思いこむことにした。なぜなら、調査不足だからと言って、これから町に出たところで何ら得られるものがあるとは思えなかった。もう12時を回っている。今出来ることは、既に僕が聞き込んだ中に、何らかのヒントがあると信じることだ。 信じて、思い出すことだ。 信じて、思い出して、そして考えるのだ。 (信じるものは救われる) つまらないことを心の中でつぶやいていると、ふと。 思い出した。 そして、考えた。考えたら妙案が浮かんだ。 もしかしたら、使えるかも知れない。 しかし、実現できるだろうか? あの物件−お好み焼き屋−は既に不動産屋を通じて人手に渡っている。だとすれば、不可能に近い。 僕の表情が一喜一憂するのを、清花は見逃さなかった。 「なんか、思いついたね?」 「まあね。でも、むつかしいよ。不可能に限りなく近い」 「むつかしくてもいい。話してみて。不可能に限りなく近いってことは、可能かも知れないんでしょ?」 「いや、それは言葉のアヤで、実際には....」 「いいから話せ。業務命令!」 「そうまで言うんなら、話すけどさ」 どうせ実現できっこない、だから僕は渋々といった口調で話した。だが、清花は「出来るよ、それ。使える!」と言って、はしゃいだ。 「こうするのよ」と、清花は僕の耳元に唇を近づけてコソコソとその方法を説明した。僕たちの他に誰もいないから、内緒話なんてする必要はないのだけれど、確かにそれは人に聞かれるとヤバイ内容を含んでいた。 「犯罪だ!」と、僕は叫んだ。 「そうよ。だからわたしは警察とかにあまり関わりたくないの」 そう言えば、交通事故云々の時、清花はそんなことを言ったっけ。 「調査のためとはいえ、いつもそんなことをしているの?」 「まさか。そのための便利屋杉橋じゃないの。下請けに出すのよ。早速電話よ。」 今朝もらったばかりの名刺を取り出す。そこには「犯罪以外何でもやります、便利屋杉橋」と印刷されていたが、どうやら時と場合によっては犯罪でも請け負ってくれるらしい。 「ま、しょうがないですね。引き受けましょう。」 オッケーの返事をもらって、一筋の巧妙を見いだすことが出来た。 僕と清花は、さっきまで憂鬱に沈みながら考え込んでいたのが嘘のように、「やったー!」とか叫びながら狂喜した。 ノリで僕は清花に抱きついてしまった。 しまった、と思ったけれども、清花は別に僕を押しのけたり、頬をひっぱたいたりはしなかった。そのかわり、きっちりと注意された。それはまるで小学校の先生が「おいた」をした生徒を諭すような口調だった。 「仕事仲間と喜びを分かち合って抱き合うぐらいのことで、わたしはセクハラとか何とか言って、騒いだりはしない。けれどね、パンツぐらいはいてよね。はみ出してるよ」 「あ!」 そうだった。僕は清花に部屋の呼び鈴を押されて、裸の上に浴衣を羽織っただけで彼女を部屋に招き入れていたのだった。 「それから、『仕事仲間と喜びを分かち合っているだけ』なんだから、成長させないようにね。」 |