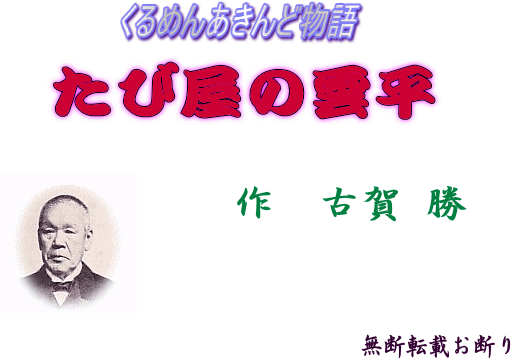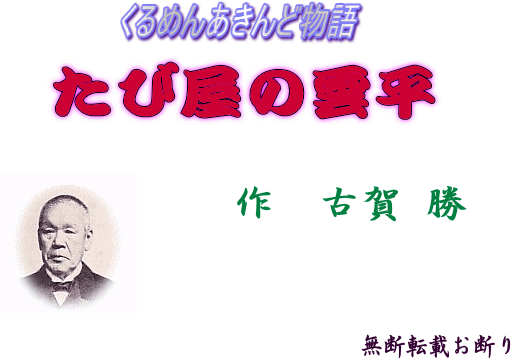|

逝く人、来る人①
雲平が命からがら久留米に帰りつく丁度その頃(明治10 年7月)、人吉(熊本県)を脱出した西郷隆盛らは、日向(宮崎県)から延岡へと移動中であった。しかし、いずこも政府軍による大包囲網の中にあり、彼らが安住できる場所はなかった。四方を敵軍に固められた西郷らは、九州山地の道なき道をただひたすら南に向かって歩き続けた。その間20日にも及んでいる。
.gif) 写真:西郷らが身を潜めていた城山の洞窟 写真:西郷らが身を潜めていた城山の洞窟
味方兵の戦死と投降を繰り返しながら、薩摩軍は鹿児島城下にたどり着いた。その時、残された兵の数は僅かに300。
手心を加えない政府軍は、薩摩軍が潜む城山に集中砲火を浴びせた。かつて西郷が設立した「私学校」に逃げ込んだ軍隊に向かって、雨あられとの如く砲弾が降り注ぐ。抵抗する薩摩兵士に対して、取り囲む政府軍の数は4万を超えていたとも記録されている。
西郷隆盛は、桐野利秋ら私学校時代の幹部に守られて城山裏手の洞窟に身を隠した。だが、諦めない政府軍は、一帯をしらみ潰しに捜索していく。洞窟も危ないと判断した一同は、5日間過ごした後急坂を降りて行った。
洞窟を出てすぐ、政府軍の流れ弾が西郷の腰に命中し、その先1歩も進めなくなった。「晋どん(別府晋介)、もうここらでよか。介錯ば頼むぜよ」と言い放ち、西郷は自らの腹に短刀を突き立てた。西郷を慕った兵士たちも次々に自刃し、或いは投降した。ここに、日本史上最大で最後の士族反乱となった西南戦争は終結した。開戦から7カ月後の明治10年9月24日であった。
雲平は戦場から帰還後、1足の足袋にも魂を込める職人であることを心がけた。 彼の頑固なまでの原点主義、悪く言えば要領の悪さは、家族と店の存続すら危うくしかねない。
「足袋屋のことを思えば、どげな仕事でも大したことはなか」
久留米の街では、雲平らの仕事ぶりをこのように揶揄するものもあった。着物や帯などを作る長物職人に比べて、足袋や脚絆のような半物を産み出す職人の価値は、それほどまでに低かった。作っただけ売れればまだよいほうで、一日中客が店に来ない日だってある。卯之助を含めて、歯を食いしばる日が続いた。
西南戦争から数年経っても、槌屋足袋の年間生産量は1万足にも達していない。単純に1日当たりで計算しても、30足にも達しない量である。しかも、1足あたりの売り上げは10銭にも満たない。
雲平夫婦が、食うものをも切り詰めて働いていた頃、久留米の町は好景気に沸いていた。戦争帰りの官軍兵士が、故郷に持ち帰るみやげ物を買い求めたからである。買いものの代表格はかすりだったが、他にも藍胎漆器だったり、竹細工の実用品やおもちゃなど、生産が間に合わないほどに売れた。
そんな折、兄嫁のフデが満面を紅潮させて作業場に飛び込んできた。
「雲平しゃん、大変なことが起こったばい」
フデの慌てぶりは尋常ではない。
「おめでたたい。赤ちゃんが出来たとよ」
それでも雲平は、何のことだか要領がつかめないでいる。
「しぇからしかね(いらいらするね)、雲平しゃん。モトちゃんのお腹に赤ちゃんが出来たと」
そこで初めて、雲平の体中に熱いものが走った。
「お母しゃんにも言わなきゃ」
自分でも、何を言っているのか分からないままに立ち上がっている。
「今、母屋でお母しゃんとうちが、モトちゃんから聞いたとこ」
「それで姉しゃん。赤ん坊はいつ生まれると。男ね、おなごね」
未だ平常心を取り戻せないでいる雲平。
「馬鹿ばいね、雲平しゃんは。そげなこつは、神さましか分かるもんか」
フデは、小躍りするようにしながら作業場を出ていった。入れ替わるように、うつむき加減のモトが戻ってきた。
モトが無事男の子を産み落としたのは、明治15年の4月6日。お城のさくらが満開の頃だった。
「お母しゃん、赤ん坊に名前ばつけて」
雲平が母マチに相談した。古希を迎えたばかりだというのに、マチの体は日に日に細くなっている。医者嫌いで、どこが悪いのか分からないままに、寝たり起きたりの繰返しであった。
「もう安心たい。雲平に子が出来たけん、わたしゃいつ死んでもよか」
この台詞、マチの口癖になっている。
お七夜の席で、長兄の清左衛門が、母親に代わって赤ん坊の名前を告げた。
「この子が倉田家に運をもたらせてくれるごと、名前は『金蔵』にした」と。
雲平夫婦に異論はない。一族のささやかな宴が夜遅くまで続いた。裏庭から手折ってきたさくらの枝が、床の間に飾ってある。その翌日の夕刻、マチは静かに息を引き取った。
文明開化②
雲平夫婦に後継ぎが誕生した明治15年。雲平、31歳になっていた。
世の中から西南戦争の話題も次第に消えていき、入れ替わるように、西洋文化の到来が人々を奮い立たせた。世に言う文明開化の時代到来である。
「東京あたりじゃ、ちょんまげ頭も少のうなったげな。町の中ば人力車が行ったり来たりして、それはもう、賑やかなこと」 図:文明開化の象徴的銀座煉瓦街 図:文明開化の象徴的銀座煉瓦街
雲平の店先である。相変わらず、世の中の動きを捉えるのに敏感な嘉助。感心しながら聞き入る雲平とモトだが、作業中の卯之助は、興味があるのかないのか反応を示さない。
新政府は断髪令を発しているが、人々はざん切り頭になかなか切り替えられないでいる。雲平もその一人で、維新から15年たった今でも長い髪を後ろで結んだまま。
「嘉助のハイカラ頭も捨てたもんじゃなかもんない。それに比べて俺は...」
「雲平しゃんの頭は、進んどるのか遅れとるのか、俺にもようわからん」
「何ごとな、それは」
嘉助は、筋が通らなくても、いつしか話題を別の方向に持っていこうとする。
「陸軍からの注文に尻込みするかち思えば、今度は走り過ぎる。足袋作りは天職ち言うて大威張りしたかち思えば、ラッキョウとか油紙まで売るけんない」
その話になると、モトはいつの間にか座をはずしている。
「それば言うなって。モトにしっかりお灸ばすえられて、今じゃこの店は足袋専門の店になっとる。お陰で...」
「貧乏ばしとると、言いたかわけ」
雲平の失敗談になると、両人の会話はなかなか噛み合わない。
「ところで...、東京とか大阪じゃ、着物が西洋風になっとるげな」
雲平は、西南戦争時の失敗談を反らすのに懸命である。
「それば言うなら、洋服じゃ。日本の着物に比べたら、動きやすかけん」
そこに、珍しい中年男が割り込んできた。博多の達磨屋甚兵衛である。見慣れている旅人姿ではなく、洋服を着て立っている。
「博多じゃ、とっくに洋服が当たり前になっとる。山高帽子ば被って、派手な洋服ば着て、革の靴ば履いて。足が悪か訳じゃないのに、杖ばついとる紳士が多うなった。ご婦人も、赤とか桃色とか派手な洋服ば着て。それに雨も降らんのに傘さして」
「それは、日傘のことでっしょ」
甚兵衛と嘉助の掛け合いが面白くて、いつの間にかモトと卯之助も話の輪の中に収まっている。一人、雲平だけが別のことを考えていた。
「革の靴ちは、西南の役のとき官軍のお偉いさんが履いておったあれですな、甚兵衛さん」
「そうたい。牛とか馬とか、動物の皮ばなめして、黒足袋と同じごと履くとたい。大むかしの足袋は、革でできとったちいうけん」
そこで嘉助が茶々を入れた。
「東京じゃ、西洋風の革靴のことば、窮屈袋とか西洋草履とか言うげな」
.gif) 写真:官軍幹部の服装(田原坂資料館) 写真:官軍幹部の服装(田原坂資料館)
これには、寡黙な卯之助まで、大口を広げて笑った。
「甚兵衛さん、博多までご一緒しまっしょ。革靴ば作っとる店に案内してくれんですか」
立ち上がりざま、今にも走りだしそうになる雲平を、嘉助がたしなめた。
「今言ったばかりじゃろ、雲平しゃん。お前の天職とする足袋と、甚兵衛さんから聞いた革の靴がどこで結びつくのか。走りだすのはそれがはっきりしてからでも遅うはなか」
モトも、嘉助に同調して大きくうなずいた。
量産態勢③
雲平は革靴の製造にこだわっている。この目で見た西南戦争時の官軍幹部の服装は、筒状の袖や股引風のズボンだった。足元は革製の長靴(ブーツ)で、下級兵士は足袋と草鞋を重ねて履いている。一方薩摩軍の士族兵は、幕藩時代そのままに、剣道着のような上着に袴姿。足元は、官軍兵士と同じく、足袋を履いた上に草鞋履き。これが、後に「右手(めて)に血刀、左手(ゆんて)に手綱(たづな)」と歌われた薩摩兵士(美少年)の姿だったのである。両軍兵士の服装を見比べただけでも、戦場での動きが容易に推察される。
雲平は、三本松の賑やかな通りで、洋服を着て闊歩する紳士を見かけた。牛鍋屋の山田平四郎である。革靴の色は黒。博多の靴屋に寸法を計って作らせたと言う。
「この頃では西洋料理屋も始めなさったそうで」
久しく会わないうちに、人は身なりまで変わってしまうものかと感心する。顧みて、自分は今でもかすりの着物に前掛け姿、足元は竹の皮で編んだ草履のままだ。
「そうたい。西洋料理ば久留米の名物にしようち思うてな」
西洋料理店は牛鍋屋と隣合せに新築されていた。元武士でも、時代の先端を行く商人になれることを彼は証明している。案内された2人掛けのテーブルには白い布がかけてあり、和服にエプロン姿の娘がグラスに入れた水を運んできた。
「雲平どんは、何ば食うかね」
平四郎が差し出した和紙には、10種類ほどの品が書き込まれていた。卵焼き(オムレツ)や肉料理などと合わせて、スープもついてくる。
雲平は、ナイフとフォークの使い方を習いながら、皿の上の料理を口に運んだ。食べている途中でも、正面に腰かけている平四郎の服装が気になって仕方がない。
「どうだった、うまかったろう」
食べ終わって、平四郎に料理の自慢をされた。だが、何を食ったか、味はどうだったか、ほとんど印象に残っていなかった。
「あなたさん、もう少し余計に足袋を作りましょう」
このところのモトは、二言目には増産のことを言う。
「ばってん、作り手が俺と卯之助だけじゃ、これ以上は・・・」
足袋の増産には消極的な雲平である。
「でもですよ。金蔵も大きくなってくるし、卯之助さんもいつまでも一人もんというわけにはいかないでしょう。もっと売上げを上げないことには、先が見えませんよ」
モトも、引き下がりそうにない。満1歳を過ぎた金蔵が、作業場を這いまわっている。当時、槌屋足袋の年間生産量は1万足未満。材料費や卯之助への給金を差し引くと、手元(利益)に残る金はない。
「売上げを、せめて今の10倍くらいにはしませんと」
「そんな無茶な」と言いかけて、雲平は口をつぐんだ。案の定、モトの口から、聞きたくない苦言がはね返ってきた。
「あなたさん、そうはおっしゃいますけど...」
足袋の増産に消極的な割には、雲平が未だに革靴作りを諦めていないことをモトは知っている。
「先日、県役所に行ったら、役人さんも洋服に革靴じゃった。今とりかからんと、他のもん(者)に先ば越されるが」
「そう言われますが、このところのあなたさんには、足袋一筋の精神が少しばかり薄れてきているような気がしてなりません」
モトは、夫の強引さが顔を出すとき、必ずと言っていいほど、西南戦争時の苦い経験を持ち出す。
「元手の銭も少なかつに、どげんして10倍もの足袋ば作れるか」
雲平が計算するに、自分と卯之助の2人では、生産量を2倍にするくらいが精いっぱいだ。
「私には、足袋の作り方はよう分かりませんが・・・」
モトは、今のままでも、生産高を10倍にすることは可能だと言い出した。
「仕事を分担するのですよ。あなたさんが何から何まで1人でやっていることをです。例えば、材料の仕入れはあなたさんのお仕事だとして、型紙づくりと生地の裁断、鉤つけ、縫い合わせ、仕上げという風にですよ。教えてもらえば私にだって、裁断くらいは出来るようになります。それに・・・」
「まだ、何かあるとか」
「はい、それでも人手は足りません。私には帳面つけやお客さんのお相手、それに子供の世話もありますし。たくさんの足袋を作ったら、誰かがそれを売りに行かなければなりませんね」
「だから、10倍てろ何てろは無茶じゃ言うとる」
雲平が勝ち誇ったようにして、立ちあがりかけた。
「違いますよ。本家の義姉さんだって、子育てが終わって暇だと言ってましたよ。また西南戦争のときのように、近所の奥さん方に手伝ってもらってもいいし。あの方々なら、そんなに高いお給金を出さなくて済みますから」
妙な夫婦で、ここは妥協案として、革靴も足袋の増産も両方取り入れることで、落ち着いた。そのために、革靴と馬具製造のための職工と、足袋製造の縫い子を両方雇い入れることになった。夫婦にとっては大冒険である。
それからというもの、雲平とモトの目の色が変わった。夜明け前に起きて、まずはお天道さまにご挨拶をする。モトに促されて雲平も、通りがかりの近所の年寄りや行商のおばさんに頭を下げる。すべては、将来を見据えて、お客さんを取り込むためである。
台所に戻ったモトは、新しく雇い入れた職人と卯之助の分を含めて、朝餉を用意しなければならない。食事の内容は、飯と味噌汁、それに漬物ともう一品を添える。夫婦が雇われ人と同じ席に着くことと、膳の内容も同じにすることで、職人らの食事に対する不満が出ないように配慮した。
朝食の間に、雲平から、昨日の反省と今日一日の仕事の内容を言い渡す。足袋や革靴の製造にあたって特に気をつけることは、「絶対に手を抜かないこと」だと言い含めた。これも、長崎の源助親方に仕込まれた職人の心構えであった。
新生久留米④
明治20年代ともなると、雲平の身の回りが忙しくなってきた。二男の泰蔵が誕生した頃である。
「賢いの、賢いの」
赤ん坊は、母マチの生まれ替りであると信じて疑わない雲平。
「あなたさん」
モトが話しかけると、雲平には自ずと身構える癖ができている。西南戦争時の商いで躓いて以来ずっとである。
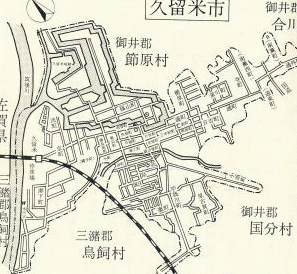 図:市制施行当時の久留米市図 図:市制施行当時の久留米市図
「先日嘉助さんがおっしゃっていたことだけど、久留米の町が生まれ変わるそうですね」
モトは、福岡と並んで新生久留米市が誕生することを言っている。
「お殿さまの名残りが、すべて消えてなくなるのですね」
城下も在方も、すべてが市・町・村のいずれかに組みこまれ、幕藩体制下の久留米の姿形がなくなってしまう。武家育ちのモトには、そのことが辛くて仕方がないのだと嘆く。
「これも、時代の流れたいね」
雲平は、徳川時代の遺物が消えることは、即ち、新しい商人の町に生まれ変わることだと思っている。新生久留米市の人口は大よそ2万4千人であった。
久留米市が誕生した明治22年、博多と久留米間に鉄道が開通した(九州鉄道)。列車は、大勢の客を乗せて、10里(40㌔)の道のりを、たったの1時間20分で走り抜けた。それまで自分の足で移動するしかなかった沿線住民にとって、夢のような話しである。
「甚兵衛さんのところへも、居眠りしながら行けるたいね」
鉄道の開通を、誰よりも喜んでいる雲平である。
「父ちゃん、俺も機関車の運転手になりたか」
金蔵は、黒い煙を吐きながら、びっくりするような大きな汽笛を鳴らして走る蒸気機関車に、興奮が収まらないでいる。鉄道の完成を追いかけるようにして、翌年(明治23年)には、久留米と熊本の間に国道も開通した。
かすり界の商人たちは、久留米絣を、東京・上野で開かれた内国勧業博覧会に出品して、一躍全国的な評判を得た。士族授産事業として新設された赤松社も、久留米絣や和傘などを生産して意気盛んである。
この日雲平は、珍しく卯之助を誘って原古賀に出向いた。西洋料理を食べさせようと連れ出したのだが、「箸がなけりゃ飯は食えん」と断られ、仕方なく隣の牛鍋屋に入った。
「嫁さんとは、うまいこといっとるかい」
「大丈夫ですよ、母ちゃんの方が俺に合わせてくれるけん」
卯之助は、3年前に嘉助が持ってきた話を受けて結婚した。それでも最初は35歳を過ぎて所帯を持つことに抵抗したが、雲平とモトが示し合わせて口説き落とした。それだけに、雲平は卯之助夫婦の行く末に責任を持たなければと思っている。
足袋の量産態勢は、一挙に年間6万足に飛躍した。労働力も、モトが提案したように、市内の女房や娘たちに働いてもらうことで間に合わせている。材料の仕入は雲平1人でこなし、卯之助は番頭格で店を仕切る。客の評判も、以前とは比較にならないほどに高くなった。
「大将が、日頃から、仕事に手ば抜くなと繰り返えすけん、職工たちの仕事も自然に念入りになっとるとですよ」
雲平も、長崎での師匠の教えが、槌屋足袋の評判の源になっているのだと思っている。
出会い⑤
そのとき、主人の山田が、歳の頃なら三十四か三十五の男の客を連れて近づいてきた。
「今度苧扱川(おこんがわ)で仕立物屋ば開く石橋徳次郎たい」
噂には聞いていたが、対面するのは初めてである。紹介されて徳次郎は、髪を短く刈った頭を丁寧に下げた。
 写真:初代石橋徳次郎 写真:初代石橋徳次郎
「うちの屋号は、嶋屋といいます。奉公先の主人から暖簾ば分けてもろうたとです」
自己紹介する姿勢が、商人とは違う雰囲気を醸し出している。
「父は洗町に住んどる久留米藩士でした」
雲平は、士族の息子が商人を志したわけを聞きたくなった。
「ご維新が、父の考えを替えさせたとです。これからの人間は、腕に技術を持つか商人になって金儲けをするか、いずれかを選ばなければ生きていけん言うとです。そこで、伯父さん(母の兄)に頼んで、商人の見習い奉公ばさせてもらいました」
「母方の伯父」とは、久留米の豪商として知られる緒方安平である。
15歳の石橋徳次郎が、商人見習いのため奉公に上がったのが、奇しくも雲平が米屋町で足袋屋を開業した明治6年であった。あれから15年が経過している。
山田平四郎が口を挟んだ。
「自慢するわけじゃなかが、俺も徳次郎も、武士を捨てて商人になった者どうしよ。先見の明があったというわけだ」
自分で喋ったことに納得して、豪快に笑い飛ばす。この男、長崎での初対面以来中身はまったく変わっていない。
「徳次郎は、仕立物屋の傍らで、半物も作って売るとげな」
「半物ばかい」
「仕立物だけじゃ、食うていくだけ稼ぐ自信がなかけんですね。印半纏の外に、職人の腹掛けとか、手甲、脚絆、そう股引も作ろうち思うとります」
歯切れよく、これから始める店のことを説明するこの男。後にアサヒコーポレーションやブリヂストンタイヤを起こした、二代目石橋徳次郎と正二郎兄弟の父親にあたる人物である。
「これからは、俺の競争相手になるとばいね。お手柔らかに頼みます」
雲平も、目の前の男が、子や孫の代まで続く槌屋のライバルになるとは、考えも及ばなかった。
作業場拡張⑥
石橋徳次郎と初めて対面した明治25年、雲平は43歳に達していた。この間に、開店時から続いた屋号の「槌屋」を、平仮名の「つちや」に変更している。これには、モトの強い意思が働いていた。
「あなたさん。苧扱川の石橋(徳次郎)さんが、お座敷足袋を作って売られるそうですよ」
雲平にとっては寝耳に水の情報である。徳次郎に初めて会った時、嶋屋が売り出す商品の列に足袋は入っていなかった。競争相手がいないことで、のんびり構えていた自分が情けなかった。
モトは、夫以上に平常心を失っている。
「嶋屋さんが売る足袋のは、嶋屋足袋というじゃありませんか。お客さんの方が、うちの槌屋足袋とごっちゃにならないか心配ですよ。あなたさんの足袋の方が、どんなに履き心地のよいものか、どっちが本物の職人技かを、世間さまにしっかり分かってもらわなければなりません」
モトは、新参の石橋徳次郎に、強烈な対抗心を燃やしている。そのためにも、相手が漢字の嶋屋足袋なら、こちらはひらがなで「つちやたび」にすると言いだしたのだ。
「あなたさん」
モトが口をとがらせて話しかけた。難題の飛来を予感して雲平が身構えた。
「昨日、お隣の吉塚さんの奥さまから話しかけられましたのよ。あちらさん、近いうちに田舎にお引っ越しなさるんですって。だから、家屋敷を売りたいって」
「うちに、その土地ば買ってくれち言うわけじゃなかろうな」
「そうなんです。せっかくなら気心の知れた倉田さんにお譲りしたいと」
「ばってん、家、土地ぐるみだと、半端な金では足りんじゃろう。それに、この家も借家のままだし」
「大丈夫ですよ。そんな時が来るだろうと思って、節約してきましたし。それに、仕事の量も増やしてきたじゃありませんか。革靴も馬具の儲けもほどほどにはあります。雇った職工と奥さん方にお手当を払っても、お金は残りますよ。お隣さんも、足りない分は、その内にいただければいいとまで言って下さいます」
一気に可能性をぶち上げられては、雲平にも抵抗のしようがなかった。購入した物件の内、建物はそのまま工場として活かすことにした。この家屋を第一工場と名付け、更に今使っている家屋の2階も改造して、職工の宿舎と作業場に当てることにした。
足袋の定価表⑦
「すごかもんたいね」
嘉助が、時計屋の宗野末吉を伴って雲平の店にやってきた。建て増しで店舗に余裕ができた分、客の出入りが容易になったと、嘉助もご満悦である。
嘉助と末吉は、こちらに来る前に「菊竹さんの店に寄ってきた」と告げた。菊竹さんとは、町内で書籍を売っている金文堂の主人の名である。店を改造していることは知っていたが、未だに中を覗いたことはない。
「これまで、客は履物を脱いで、畳の上に並べた書籍ば見るのが当たり前じゃったもんない。それが、土足のままで、土間に置いた陳列台の本ば品定め(立ち読み)ができるごとなった」
さすがの嘉助も、驚きが冷めないようだ。
.gif) 写真:現在も残る金文堂 写真:現在も残る金文堂
「俺たちも、菊竹さんの商いば見習わんとない」
金文堂の商法に感心しきりなのは末吉も同じである。
「ところで...、末吉さんの商売はどげんですな」
雲平が宗野末吉に話を向けた。これまた説明役には嘉助がしゃしゃり出る。
「末吉どんは、このほどばさらか(大そう)珍しかもんば作らした。今日は、それば雲平しゃんに自慢したかち言うて」
嘉助が、末吉を連れてきたわけを話した。
「風琴ちいうもんたい。西洋じゃ、オルガンちもいうそうじゃけど。音楽の道具のこと」
「そげなもんば作ってどげんすると」
「売るとたい。久留米のもんに」
末吉が、すまし顔で答えた。
「末吉どんの言うことにゃ、久留米の人間も、これからは西洋音楽に馴染んでもらわんといかんとげな」
いつの間にか、モトと卯之助も話の輪に加わっている。
「風琴のこともよかばってん、雲平さんの足袋作りはどげんなよるですか。ずいぶん職工ば増やしなさったそうですが」
末吉が、店の中を見渡しながら、しきりと感心している。それには、モトが答えた。
「職工だけは30人にもなりましたが、まだまだ十分なお給金を払うところまでは儲かっていません。お陰さんで、足袋の方は順調にいっております。足袋の定価表も作りまして。1足あたりの値段も大人もんで大よそ20銭台と安く売れるようになり、皆さまが自前の足袋をお家で縫わなくなった分、私どもに買いにきてくださるようになりました」
 写真:足袋の定価表 写真:足袋の定価表
モトは、足袋の生産と売れ行きの話になると目を輝かせる。今や番頭格として貫禄も備わってきた卯之助が、そばで大きくうなずいてモトの説明を補佐した。
「それは喜ばしかこつで。ところで、革靴とか馬具の方は」
話が足袋以外に向けられると、モトはいつの間にか立ち上がってしまう。
「評判はよかですよ。洋服の時代じゃけん、まだまだお客さんは増えるち思うとります」
ここは、雲平が一人で説明するしかなかった。
「つちやさんのこれからは、万々歳ですな」
末吉は、相手を喜ばせる話し方を心得ている
頭脳の吸入⑧
宗野末吉が帰っていった後、残った嘉助が真顔で雲平に向かいあった。
「雲平しゃん、ものは相談じゃが」
嘉助に真顔で迫られると、雲平も自然に背筋が伸びる。
「13歳の男の子供ば一人引き取ってくれんね」
嘉助に頼まれると、嫌だとは言い難い雲平である。
「うちには男の子が2人もおるし、それに、嫁の腹には3番目も入っとる」
「違う、養子のことじゃなか。その子ば店で雇って欲しかと。将来子供ば商人にしたかちいう、大事なお客さんに頼まれたもんで。雲平しゃんとこで修業ばさせてもらいたか」
いつの間にか、そばにモトが座っている。
「十三ですか、そのお子は。うちの金蔵と同じですね。それで、お名前は?」
「清水慶之助」
「お侍さんでしょうか、親御さんは」
「清水内蔵助さんちいう士族の旦那ですたい」
そこまで聞いて、モトの気持ちは固まった。慶之助という商人志望の少年が、長男金蔵に刺激を与えてくれそうな予感がする。そこで、夫の背中を押した。
間もなくして、雲平夫婦に3番めの子が誕生した。今回も男児であった。出産のため10日間ほど仕事を休んだモトは、子守りの娘を雇うとすぐに店に出た。
朝暗いうちに起き上るのは、商家の慣わしである。雲平夫婦は、数は増えても職工たちと同じ食卓について朝餉をとることに変化はない。食事の内容も彼らと一緒。最近では、おかずに焼き魚がつくようになった。
日清戦争のきな臭さが、久留米の町にも漂い始める頃である。
「新聞をとりましょう」
モトは、もっと世の中の動きを知らなければならないと言う。文字に強くない雲平は、モトほどに興味を示さない。
「大丈夫ですよ、私が読んで聞かせますから」
青々館では、泊り客向けに早くから新聞を配達させている。嘉助の情報通は、毎朝配られてくる新聞から得るところも多いと言う。雲平は、仕方なく福岡で印刷されている新聞をとることにした。
「雲平しゃん、これからのつちやたびには、頭のよか若者が必要たい」
嘉助は、経営者の良し悪しは頭の良さで決まると言いきった。
「ばってん、世の中の動きと足袋作りとでは関係なかろうもん」
生まれてこの方、寺子屋しか知らない雲平である。この手の話になると、知らずと、腰が引ける。
「それが、大いに関係があるとたい。これからのつちやたびは、高等教育ば受けた、頭のよか人間が引っ張っていかにゃならんごとなる」
「それじゃ、高等教育ば受けておらん俺の出番がなかじゃなかか。金蔵も、今は明善小学校(上等科)に行きよるばってん、ゆくゆくは一人前の足袋職人にしようち思うとるし」
「馬鹿だな、雲平しゃんは。雇いれた頭のよか若者は、みんな雲平しゃんと金蔵君の頭脳の一部になるとたい」
間を置かずして、嘉助は川上信義と名乗る青年を連れてきた。中等学校の上等科を卒業した19歳の若者である。「高等教育」を受けたエリート人材というわけである。
雲平は、川上に特別の役割を持たせた。新聞が配達されると、真っ先に声を出して読ませることだ。記事だけではなく、広告の欄まで隈なく紹介し、解説も加えさせる。
|