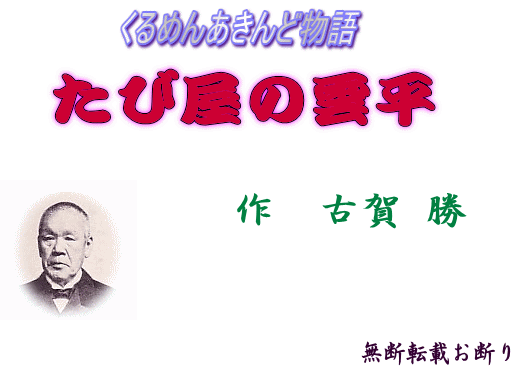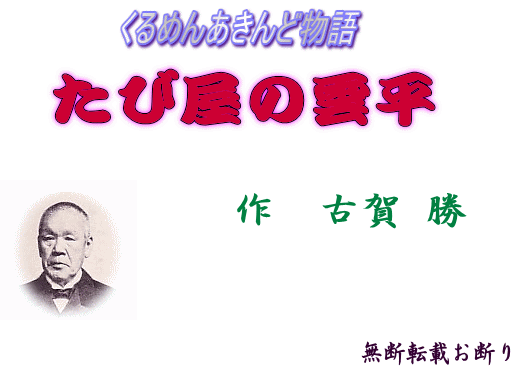| 長崎街道(01)
雲平は、明けガラスが鳴くとすぐに、水天宮そばの渡し場に向かった。見送ってきた姉のノブが桟橋から手を振っている。元号が明治に代わって1年半が過ぎた明治3年2月(旧暦)の初めであった。
人馬相乗りの渡し舟に乗りこむと、水面から吹き上げる風で身震いするほどに寒い。手綱を引いた髭面の男は、飼い牛の腹に顔を埋めるようにして寒風を避けている。
「しばらく、筑紫次郎ともお別れだ」
雲平は、波立つ川面を見つめながら、声にならない声を発した。筑紫次郎とは、筑後と肥前を隔てる筑後川の愛称である。雲平は、物心ついた頃から、よくこの川で遊んでいた。兄たちに連れられて来ることもあったし、仲良しの嘉助と川岸で相撲を取ったりもした。嘉助は道を挟んで向かいに建つ旅館(青々館)の息子である。
 写真:瀬ノ下の渡し場跡 写真:瀬ノ下の渡し場跡
舟を降り、土手を上がって振り返ると、見送ってくれた姉が土手の向うに消えるところであった。朝もやで、久留米の街もその向うの高良山もはっきり見えない。
倉田雲平、20歳を迎えたばかりの青年である。家を出るとき、「一人前になるまでは、ゼッタイに帰ってこんけんね」と母や兄たちに見栄を張った。だが、いかに強がってみても、生まれて初めて久留米を離れる不安は拭えない。
歩いていくうちに、西の方向に標高千メートル級の脊振の山並みが見えてきた。上空には、箒で掃いたような薄雲が覆っている。今宵の宿は、牛津(現佐賀県小城市)あたりか。長崎に着くまでに、いくつもの宿場と峠道を越えて行かなければならないと聞いている。
「死ぬつもりで、修行に励むけんね」
渡し場まで送ってくれた姉ノブの前でも息巻いた。
「そげん気張っとると、あとで引っ込みがつかんごとなるがね」
ノブは、弟の一人旅が心配でならない様子。
小道を横切って神埼の大通りに出た。小倉から長崎に通じる長崎街道である。道端の茶店に腰をおろしていた中年の男が、頃合いを見て立ち上がった。
前日からの緊張も重なってか、佐賀の城下町に入った途端に足が前に進まなくなった。こんな様では先が思いやられる。陽はまだ高かったが、仕方なく、佐嘉神社そばの宿屋で草鞋を脱いだ。
「兄ちゃん、そうとうくたびれとうな」
相部屋に案内されて、片隅に腰を下ろしたところで声をかけられた。神埼の茶店から後をつけてきた男である。
「あんまり知らんもんと親しくせん方がよか」とは、3日前にノブが助言してくれたことだった。すり寄ってくる旅人に、隙をみて金目のものを盗まれるとも聞かされた。
「心配せんでもよか。俺は怪しかもんじゃなかけん。博多で呉服屋ばやっとる甚兵衛ちいうもんたい。実はな…」
男は、意味ありげな笑みを浮かべながら、雲平の顔色をうかがった。
a.gif) 写真:佐賀市内の長崎街道 写真:佐賀市内の長崎街道
「おっちゃんは、ひょっとして、俺のことば知っとらすと?」
「そうくさ。米屋町の傘屋さんに頼まれた」
「ああ、世話役さんの…」
町の世話役をしている傘屋の伊三郎が、雲平の道中の相手を依頼したというのだ。男は、丁度仕事で長崎に行くついでだったので引き受けたと言う。
夕食を済ませると、すぐに甚兵衛の方から話しかけた。
「雲平と言うたな、兄ちゃんの名前。傘屋さんに聞いたとばってん、長崎まで足袋作りの修行に行きようとげなない」
耳慣れない博多弁が、次の答えをぎくしゃくさせる。寝る支度に入ったところでまた甚兵衛。
「兄ちゃんが弟子入りしようとする足袋屋のおやじの名前は、何ちいん(言う)しゃあと?」
「小川源助さんち聞いとります」
「長崎屋の源さんか」
「知っとるとですか、俺の師匠になる人のこつば」
「言うたろ、わしは博多の呉服屋じゃと。博多の祇園町で達磨屋ち言や、少しは名が売れとうとばい。うちの店じゃ、人間が身に着けるものなら何でも扱うとうけんな。それも日本中からよか品物ば仕入れてな。これから行く長崎にも、珍しかもんば探しに行きようとこたい。足袋も、うちの店じゃ貴重な売りもんじゃけな。長崎屋さんとも長い付き合いたい」
雲平はこのとき、小川源助の店の名前が「長崎屋足袋所」だということを初めて知った。
激動期の申し子(02)
雲平は甚兵衛に伴われるようにして、翌朝早く佐賀の宿を出た。
「どうやら、今日も天気はよさそうだ」
甚兵衛は、北方に横たわる脊振の山を見上げて、安堵した様子。
「どうして、今日は雨が降らんち分かるとですか」
雲平を従えるようにして歩く甚兵衛が、振り向き加減で答えた。
「何べんも同じ道を行ったり来たりしてりゃ、その日のお天道さまのご機嫌くらいはわかるくさ。ほら、あれが肥前で一番高か天山ちいう山たい。あげんして山が笑うとうときゃ、雨雲も寄りつかん」
山が笑うと聞かされて、雲平は思わず笑ってしまった。
やがて甚兵衛は、街道から外れて小さな農道に入りこんだ。
「近道だ、こっちの方が」
その後双方無口が続いたところで、雲平がたまらずに話しかけた。
「おっちゃん、教えてくれんね」
「ん?」
「これから俺のお師匠さんになるお方ちは、優しか人ね」
今度は甚兵衛が笑った。
「そげなことば訊いてどげんすうとか。恐い人か優しか人か、自分で当たってみなけりゃ分かるもんか。人と人が付き合うていくとには、相性ちいうもんがあるけんな。お前が、本気で仕事ば覚えようとすりゃ、そん時は、源さんも優しか人になるじゃろうたい」
一呼吸おいて、今度は甚兵衛が切りだした。
「雲平よ。はたちになったち言うとったない。ということは、嘉永生まれちいうことか」
甚兵衛の雲平に対する呼び方が、「兄ちゃん」から「雲平」に変わっている。
「そげんです。嘉永4年(1851年)の4月14日」
「お父っつあんとおっ母さんは?」
「父ちゃんは8歳のときに死んだ。母ちゃんが一人で、俺たち兄弟ば育てたとです」
「家の商いは?」
「もともとは『槌屋(つちや)』ちいうて、大きな呉服屋ばやっとったらしかです」
「へえ、槌屋ね。面白か屋号たいね。それにしても、ご先祖さんがわしと同じ呉服屋だったとはな」
「屋号の槌屋は、打出の小槌からとったらしかです。振るほどにお金が出てくる打出の小槌にあやかってですね」
.gif)
現在の米屋町
「そげな都合のよか道具があったら、おっちゃんも欲しかな。それで、兄弟は?」
「兄しゃんが4人おって、姉ちゃんが1人です。俺は6番目の末っ子」
「それで、先祖代々からの槌屋は、今どげんしとうと?」
「父ちゃんが死んだ後は、落ちぶれたとです」
「さすがの打出の小槌も、言うことば聞いてくれんかったばいね」
言いながら大口を開けて笑う甚兵衛を、雲平は憎らしく思った。母マチが、夫の死後子供らの食い扶持を1人で稼いだのだという。
マチは、10歳に満たない長女のノブに台所を任せて、店を切り盛りした。マチの気性は次第に激しさを増していき、客に対しても気に食わなと怒鳴りあげたりもした。子供たちは、優しさを失っていく母親を好きではなかった。
「そうか、お前たち兄弟も苦労したとたいね。それで、兄弟たちは今どうしとる」
「相変わらず母ちゃんは、駄菓子屋ば続けとります。兄しゃんは久留米の役所に勤めとります。兄しゃんには嫁さんもおらすとです。それから、ほかの3人の兄しゃんは、婿養子に行ったりよその店に奉公に出たりして家にはおりまっせん。渡し場まで送ってきた姉ちゃんだけが家に残っとりますが、来月には近くの道具屋さんに嫁に行くとです」
「それじゃ、お前も家では肩身が狭かない」
また、沈黙の道中が始まった。甚兵衛は、後ろから付いてくる雲平が気になるのか、時々振り返った。
「嘉永の4年か、雲平がこの世に顔ば出したんは。その2年あと(嘉永6年=1853年)には、アメリカのペリーが、どでかい軍艦ば4隻もつれて浦賀にやって来たとたいね。幕府に早う鎖国ばやめろち言うために」
その後もアメリカやロシヤなど欧米の大国が次々に日本にやってきて、幕府に開国と和親条約の締結を迫った。そんなこともあって、国内は開国論と鎖国強化論に二分し、京都周辺では小競り合いが激しくなっていった。
明治維新までは、江戸や京都から遠く離れた久留米までも、何かと騒がしい様子が聞こえてきた。
口減らし(03)
幕府は、全国の諸大名に対して、国の守りを厳命した。弱冠18歳で藩主に就いた有馬頼咸は、藩財政の緊迫の上に、度重なる出費を賄うために領民に対して徹底した節約を命じた。
やがて20歳になろうとする雲平の目には、激動する日本と久留米藩内の将来が少しずつ見えてきていた。
260年続いた徳川幕府が壊れる。その次に来る世の中が、果たしてどんなものなのか。雲平に聞こえてくるのは、都での日本人同士の殺し合いであったり、倒幕派に対する幕府の厳しい処罰であったり、斬ったはったの生臭い話ばかりで、先のことなど見当もつかなかった。
「母ちゃん、寺子屋に行きたか」
雲平は思い切って母マチに相談した。案の定、「そげな銭がどこにあるね」と一蹴された。「ばってん…」と、言いかけてやめた。もともと無理な相談とわかっていたからである。
ところがそれから何日も経たないうちに、マチの方から「寺子屋に行ってもよかよ」と言いだした。
 写真:久留米藩最後の藩主有馬頼咸 写真:久留米藩最後の藩主有馬頼咸
「これからの人間は、寺子屋くらい行っとかんとね」
死んだ父ちゃんが残してくれた金をはたけば、何とかなるだろうとも付け加えた。雲平をどこかに養子に出すにしても、読み・書き・そろばんのイロハくらいは身につけさせておく必要を感じたのかもしれない。
この時代どこの家でもそうであったように、男の子は、長男坊以外は成長と同時に外に出されるのが常であった。それは、商家への丁稚奉公であったり、男の子のいない家に養子に出されたりだった。女の子の場合は、一人っ子でもない限り、奉公に出るか他家に嫁がせた。早い話が、貧乏家庭の口減らしである。
生まれたその日から貧乏の中にあり、よその子は当たり前のように買ってもらえるおもちゃも、父親がいないというだけでそれもかなわない。早く大人になってお金を稼ぎたい。そして、母や兄弟たちを楽にさせてあげたい。雲平の頭の中ではそんな願望が巡るのだが、どうすればそれが実現するのか、具体論になるとまるで答えは出てこない。
そうこうするうちに、雲平自身の養子縁組の話が決まった。寺子屋を終了して、14歳になったばかりのときであった。行き先は、町の中で幅広くござの卸商を営む近江屋であった。
義父となる近江屋治助は、極端な倹約主義者であった。息子となる雲平に対しても、容赦はしない。「これも、将来店を継ぐものとしての修行だ」と言い聞かせながら、他の使用人と同じ時間に起床させ、一日中休む間も与えなかった。
使いに出たとき覗く実家は、相変わらず流行っている風には見えない。母親も、忙しそうにはしているが、客はどこにもいない。
誰よりも遅く風呂に入り、藺草の臭いを洗い落として床につく頃、身体はくたくたであった。それでも何故か、眠れない。他の奉公人と同じ部屋ということもあり、灯りが消えた布団の中ではいろいろなことを考えてしまう。
俺はこのまま近江屋の養子でいてよいのだろうか。養子の生活が1年たち、2年が過ぎていくうちに、雲平の気持ちは焦りのようなものに変化していった。
お城の内と外(04)
江戸時代の長崎街道は、長崎から江戸へ、西洋の文化や物資を運ぶための重要な道路であった。明治維新後も、しばらくはその役割が保持された。
「ところで、養子のことだが・・・。辛抱さえしておれば、お前も金持ちのござ屋の息子としてよか暮らしが待っておったろうに」
甚兵衛が、憐れむような眼で雲平を見返した。
「そうじゃなかですよ。例え後でよかめがあったとしても、ござ屋じゃ面白うなかです」
「何の商売でも、そげんに面白かことはなかよ」
「ばってん、俺は、自分の手で物ば作ってそれば売る、そげな商いがしたかったとです。それで・・・」
「ござ屋にさよならしたというわけか」
「養子ばなかったことにしてくださいち言うたら、近江屋の大将が怒らしたこと。面倒見甲斐のなかガキじゃち言うて。追い出さるるごつして母ちゃんのところに戻りました。そうしたら今度は、兄しゃんから、バカ・クソんごつ言われてですね。また兄しゃんのおる実家に居候ばするけんですね、兄しゃんには義姉さんへの遠慮もあるとですよ。気の強か母ちゃんも、さすがにこのときばっかりは参っておらした。兄しゃんに頭ば何べんも下げて、ちょっとの間だけここに置いてあげてくれろち頼んでくれたとです」
「それで・・・」
「しばらくは母ちゃんの駄菓子屋の手伝いばしとりました。焼けた菓子ば人通りの多か三本松の道端で売よりました。声ば枯らして客呼びばしてですね。青々館の嘉助も、ときどきやって来て客呼びば手伝うたりしてくれました。けっこう稼いだですよ。ばってん・・・」
「ばってん、まだ何か?」
「所詮はこれも、次の仕事が見つかるまでの繋ぎですけんね。そのうちに、兄しゃんから、お城の中の裁縫師さんの弟子になれち言われました。俺が、物ば作る職人になりたかち言うとったもんで、兄しゃんが世話役さんに頼んでくれたとです」
雲平が久留米藩の御用長物師の三谷松太郎に弟子入りしたのは、近江屋との養子縁組が破談になってから半年ほど経った頃だった。年齢は17歳になっていた。三谷が務める御用長物師とは、藩お抱えの衣服裁縫師のことである。上級武士や中級武士、ある時には大名とその家族の分まで注文を受けることがある。長物師の「長物」とは、着物や袴のような着衣のこと。長物に対して、足とか腕・手など身体の部分に着用するものを「半物」と呼んでいた。
「それで、弟子入りするためにお城にあがったのか」
甚兵衛は、自分では経験したことのないお城の中のことに興味を抱いたようだ。城中といっても、雲平の家からは、外堀を挟んで向こう側のことである。
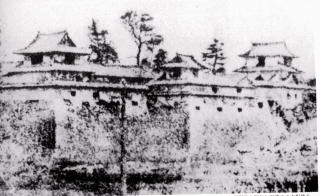 写真:取り壊し前の久留米城本丸 写真:取り壊し前の久留米城本丸
三谷の住み家兼仕事場は、外堀の中の武家屋敷街の一角にあった。師匠の三谷は、見るからにお城勤めがお似合いの、几帳面な顔立ちと物腰をしている。雲平が弟子入りすると、師匠からは兄弟子の義三の指図に従うよう指示された。新米の雲平に与えられた仕事は、家老や奉行などの武家屋敷を回ることであった。
屋敷の勝手口に回って、出てきた女中から注文を受ける。ある時は、出来上がった着物を届ける。着用する藩士の好みや細かいことは、師匠である三谷が直接承ることになっていた。
義三のほかに兄弟子は3人。雲平を含めて5人の内弟子は、武家屋敷への御用聞き以外の時間は、言いつけられた裁縫を黙々とこなすだけであった。

現在残る久留米城外堀の図
指南役の義三は、裁断から針の使い方、仕掛け品や完成品の畳み方まで事細かに教えてくれた。時々は師匠が作業場まで出てきて、お城の中での行儀作法や言葉遣いなどについて注意することもある。
「ござ屋と比べて、裁縫屋は面白かったろう?」
塚崎宿(武雄温泉)近くの茶店で一休みしたところで、甚兵衛が質した。あたり一面は麦畑で、5寸(約15㌢)ほどに伸びた芽が、やや強い北風にあおられて波打っている。
「米屋町におるときは、目の前のお堀ば越えることなんぞ考えもせんかったです。それが、現実にお堀の内側の屋敷で仕事ができるとじゃけん夢のごたる話です。教わった通りに布(きれ)ば裁断して針で縫うと、きもん(着物)になるけんですね、面白かわけですよ。もっともっと裁縫が上手になって、早う一人前の職人になりたかち思いました。お師匠さんからも、雲平の腕はよさそうだから、頑張ればものになるち言われたとです」
甚兵衛と雲平は、また麦畑の中を歩き出した。だんご状の山が目の前を遮った。街道は、その山を大きく迂回しなければならない。
裁縫師見習い(05)
「そげんに面白か裁縫の職人ばやめて、足袋の職人になったのは...」
「思うようにいかんとですよ、世の中ちゅうもんは」
「生意気ば言うて」
甚兵衛が噴き出すような仕草を見せながら言い放った。
「ほんなこつ、俺は裁縫の職人になりたかったとです。その時までは・・・」
「どうしたと。お師匠さんと喧嘩でもしたんか」
「そうじゃなかです。お師匠さんにお城から、江戸屋敷詰めば言い渡されたとです」
今でいう、地方から東京への転勤命令である。
「それは困ったな。それで?」
「お師匠さんからは、同業の長谷川先生の屋敷に行けと言われました。そげなことで、兄弟子たちともバラバラになりました。いろいろ教えてくれた義三さんとも」
そこまで話して、雲平の口が重くなった。道幅はますます狭くなり、登り坂が険しくなった。
「これから登るところが、長崎街道の中でも一番きつか俵坂峠たい。このくらいの坂でへこたれるようじゃ、一人前の職人にはなれんぞ」
甚兵衛は、ぐずぐずしていたら置いていくと言い残して、さっさと峠を目指した。
1.gif) 写真:関所跡が残る現在の俵坂峠付近 写真:関所跡が残る現在の俵坂峠付近
胸突き八丁にさしかかったところに、俵坂関所の建物がそのままで残っていた。峠が肥前鍋島藩領と大村藩領の国境となる(標高は190㍍)。現在でいう、佐賀県(嬉野町)と長崎県(東彼杵町)の県境のこと。
峠を越えて下り坂にかかると、雲平の足も信じられないくらいに軽くなった。
「それで、長谷川さんのところに宿替えすることに・・・」
お城の都合で、下々まで右往左往する様子が面白くて、甚兵衛が笑い声をあげた。
「笑いごとじゃなかですよ。こっちは、やっと仕事ば習い始めたばかりですけん。新しか師匠さんに、また一から裁縫のことば習う羽目になるとです。ばってん、それがかえってよかったとです。三谷先生のところでうっかり聞き漏らしていたこつば、長谷川先生のところで改めて習うことができて、より身についたけんですね」
「そこまで考えたんなら立派なもんだ。そろそろ海が見えてきたな」
急に話題をそらす甚兵衛は、大村湾の海岸に降り立って、腰にぶら下げている竹筒の水をぐい飲みした。
「長崎ちいうお国は幕府の直轄領じゃから、久留米のように殿さん(大名)はござらん。代わりに、幕府が仕向けなさったお奉行さまが仕切ってなさった。幕府は佐賀と大村の殿さんに長崎の港ば警備するよう命じなさった。
.gif) 写真:彼杵の荘そばの掲示 写真:彼杵の荘そばの掲示
日本国中が外国と付きあったらいかんという時にも、長崎にだけは、自由に外国人が出入りしておったからな。 お前がこれから行く古川町の近くにも、欧州のオランダあたりから来た商人が仰山おるぞ。そういうわけで、長崎には男には絶対必要な遊び場も揃うとる」
「遊び場なんぞ、修行の身には関係なかです」
「そうでもなかと思うがな。一人前の商人になるためには、遊び場やその土地の暮らしようもよく見ておかんとな」
たった2日前に知り合ったばかりの他人のおじさんが、若者の将来についてまで気を使っていることが、雲平には不思議に思えた。
大村の宿場町を過ぎると、街道はいったん海辺から遠ざかる。鈴田峠を越えて、道中最後の宿である永昌宿(現諫早市)に着いた。
「それで、どうなったのか、長谷川さんとこでは?」
甚兵衛の聞き取りは、寝るまで続いた。明日は目的の長崎に入る。
「三谷先生と違うて、長谷川先生は、直接手とり足とりで教えてくれたとです。着る人の身の丈に合わせて、生地や柄の選び方から、裁断、縫い合わせまでわかりやすうですね。これなら、案外早う一人立ちが出来るかもしれんなと、自分でも思うた矢先・・・」
次の言葉までに間を置いた。
「何か、うまくいかんことでもあったのか?」
「そげんですよ。三谷先生のときと同じごと、長谷川先生にも江戸詰の命令が下ったとです。先生は、次の師匠さんを世話もしてくれませんでした。ですが・・・」
雲平の口が急に軽くなった。
「これから先は自分で勉強しろち言われました。お餞別までいただいてお暇を貰い、やっとこさお堀の外側に出たとです。19歳になっとったですよ。今度も母ちゃんや跡取りの兄しゃんに無理ば言うて、実家の2階のひと隅ば貸してもらいました」
「修行の続きばやるために?」
「そうじゃなかです。俺には、2年間の修行で、もう一人前になったと思い込んでおったけんです。長谷川先生からいただいた餞別で裁縫に必要な道具ば揃えて、仕立屋ば始めました」
雲平には、その時世間の荒波がどんなものかもよくわからないままだった。
長物と半物(06)
茣蓙屋との養子縁組を解消して実家に戻った時から、御用長物師の三谷松太郎に弟子入りしている間、そして再び米屋町に戻った時期。日本の国は、徳川幕府が崩壊して新しい明治時代を迎える丁度その変わり目にあった。
開国か鎖国継続かで大揺れしていた幕末。開国派と鎖国派の論争は、血生臭い内戦の様相を漂わせながら、慶応4年(1868年)の明治維新へと突き進んでいく。
雲平が、お城を出て米屋町の実家に戻ったのが明治2(1869)年。中央での激動が九州の久留米市民にも、ようやく実感できる頃だった。
京都で始まった「戊辰戦争」には、久留米からも大挙して兵が送られ、多くの市民の命が奪われることになった。また、久留米藩中で幕藩体制を支持してきた若手藩士の今井栄など9人に、切腹の命が下された。新政府への忠誠を証明するために、藩主は市民への重い荷を背負わせることになったのである。その後、新政府によって久留米藩は召しあげられ、後には久留米県が発足した。(藩主は「知事」が)
母マチや兄清左衛門が暮らす町屋一帯にも、明治維新は現実問題としてのしかかった。新政府が打ち出した神仏分離令は、高良大社の神宮寺であった御井寺などを廃寺に追い込み、町民が心の支えにしてきた仏像も、大ぴらに拝むことができなくなった。久留米絣の井上伝が亡くなったのが明治2年4月28日(旧暦)、さくらが咲き始めた頃だった。久留米藩の消滅と時を同じくして、城下の象徴的存在でもあった伝女史の死は、時代の皮肉とでもいうのだろうか。
雲平は、その日も、青々館の嘉助と語り合っていた。実家に戻ってからの雲平は、嘉助から得る情報を大切に思っている。商売人の息子の世間を見る目は、自分では到底及ばないものがあったからだ。
「ばってん、悪かこつばっかりじゃなかよ」
口を開けば悲観的なことばかり口走る雲平を、嘉助が諌めた。
「何かよかこつがあると?」
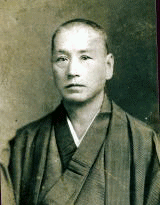 写真:青々館の安永嘉助(ご子孫提供) 写真:青々館の安永嘉助(ご子孫提供)
「親爺に聞いた話ばってん。この頃東京ではおかじょうき(蒸気機関車)が走るごつなったげな」
「そのオカなんとかちいうのは、いったいどげなもんな」
「海の上じゃのうて、陸ば走る蒸気船のごたるもんたい。列車にいっぱい人ば乗せて、船とは比べものにならんくらいに早う走るとげな。便利なもんはおか蒸気だけじゃなか。東京のあたりじゃ、ちょっとそこらまで行くにも、人力車ちいうて、人が引っ張る2輪車に乗って行くげな」
時代は、明治維新とともに、人々の想像を遥かに超える勢いで進んでいたのであった。
嘉助の話を聞いていると、自分一人が世の中から取り残されているような不安にかられる。長兄の家の片隅を借りて仕立物屋を始めたものの、雲平のもとに来る客はいなかった。来年には20歳を迎えようとする男が、自分の食い扶持すら思うようにならないなんて、あまりにも情けない。「長物師」といえば聞こえはいいが、雲平程度の腕では、世間はまともに相手にもしてくれなかったのである。
「雲平しゃんよ、こだわり過ぎとらんか」
突然、まじめな口調で嘉助が話題を切り替えた。
「なに?」
「長物師ちいう仕事にたい」
「何ば言いだすとか、嘉助は」
「きもん(着物)ば仕立てる店が何軒あるち思うとると、この久留米に」
「それが、どうしたと?」
「商売敵が多かちいうことは、それだけ雲平しゃんのところに来る客が少なかちいうことたい。同じ仕立物でん、長物とは違うもんば考えられんかな」
雲平には、嘉助の問いかける意味がなかなか解せなかった。
「雲平しゃんがお城で覚えた長物作りの技は、無駄じゃなか。ばってん・・・」
嘉助も、自分の言っていることを理解されないことがもどかしそう。
「長物とは違うもんば作れちいうことかい」
「そうたい。脚絆とか。足とか腕に付けるもんば作る店は、久留米には少なかろうが」
「ばってん、俺は長物作りの技しか習うておらん」
「馬鹿じゃな、雲平しゃんは。紋付とか袴とか、そう着流しでん、女の人の晴れ着でん。それば作るには鋏ば使うて裁つじゃろう。その次に、裁った布ば針で縫うとじゃなかか。足に履くもんも同じことじゃ」
嘉助の洞察力には、ただただ舌を巻く。
「ばってん...」
「まだ、何か気に食わんことがあると」
「半物ちいえば、長物に比べて、皆んながやりたがらん、げさっか(下品な)仕事じゃろが。俺にそげなこつは出来ん」
「贅沢ば言いよったら、今度こそ飯ば食われんごとなるがね。人がやらんことばやる。これからの商人はそげんでなけりゃならんとたい」
嘉助は、考え込む雲平を無視して立ち上がった。
「人がやらん仕事ばやる。これこそ、天が雲平しゃんに与えてくれる仕事ちは思わんか」
「天からいただく仕事ね。それで、俺はどんげな半物ば作りゃよかとじゃろ」
「それは、雲平しゃんが考えることたい」
このときの雲平は、嘉助の助け舟を十分に呑みこんではいなかった。母と兄に相談すると、「やってみろ」の一言で突き放された。
雲平が悩んでいる間に、町の世話役は長崎の足袋職人である小川源助への紹介状を認めてくれた。
「よかか、雲平。これが最後の仕事選びぞ。足袋職人になるということば、天職だち思え」
母マチは、貯めていたかねものだと言って、長崎までの旅費と支度に必要な金をくれた。
甚兵衛と雲平の、親子ほども違う男の二人旅は続く。
古賀宿を過ぎ、八郎川に沿って南下すると前方が大きく開けた。橘湾である。ここにも境界石が建っていた。つい何年か前までは、通行手形なしでは行き来することすらままならなかったかつての厳しい境界線である。
上り下りをくり返しながら、日見峠(標高200㍍)を越える。するとそこは、長崎までの残り距離を2里残すだけであった。久留米を発ってから40里(160㌔)の道程を3泊4日かけて辿りついた。
「天職、・・・か。羨ましかのう。わしは、もの心ついたときから、ずっと呉服屋の息子だ。自分の仕事を自分で選ぶなんぞ、考えたこともなかったぞ」
雲平の、長い話を聞き終えて、甚兵衛が大きく息を吐いた。
|